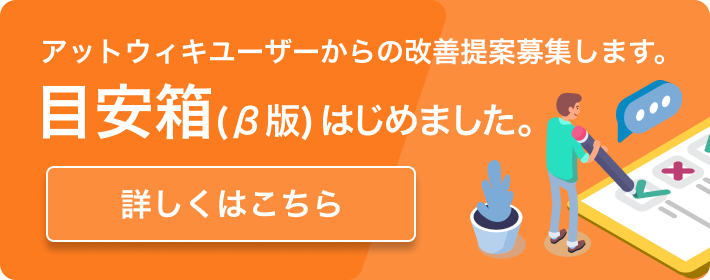オルタナティブとしての文学
─現代日本文学の現状
Seibun Satow
Aug, 31. 2001
「時代に没頭していては時代を批評することが出来ない。私の文学に求むるところは批評である」。
石川啄木『時代閉塞の現状』
今日の日本文学は停滞期に突入している。これまでに、何度か、文学の沈滞について語られたことはあったが、現在の状況は比較にならない。「失われた十年」は、経済だけでなく、文学にも適用されるだろう。出版市場でもOSの市場(the market of operating system)同様、正のフィードバックによるロックイン現象が生じている。IT社会ではすべてが自己組織的臨界状態にあるため、些細なことでなだれ現象が起きてしまう。浅田次郎の『鉄道員(ぽっぽや)』(一九九七)など少数の作品にセールスが集中し、他は絶望的な部数しか売れない。出版界でも、定常マルコフ連鎖(stationary Markov chain)は通用しない。従来、再価格販売維持法に保護されながら、不況に強いと見られてきた出版業界までも、デフレ・スパイラルに陥った日本経済の中、売り上げが落ち、深刻な出版不況に見舞われている。二〇〇〇年だけで、約千三百店もの本屋が国内から姿を消している。「文学作品も商品である以上、売れなければならない」と「文学作品は文化に属するのであって、必ずしも、売れる必要はない」という二つの主張が文学者の間で対立してきたが、日本文学は世界的にも稀有な出版産業の経済成長を基盤に発展してきたのであり、文学の停滞と出版産業の不況が直結している。世界的に見て、純文学は出版産業の盛衰に必ずしも左右されない。けれども、日本文学を考える場合、文学の政治経済学が必要になる。蓮実重彦と並び、一九八〇年代以降、最も影響力のある文芸批評家柄谷行人は、『飛躍と転向』(二〇〇一)の中で、「インテリや作家」は「赤字になっても、文化的プレステージを上げるから、とか言って」、「出版社を食い物」にしてきたと非難している。「インテリや作家」自身が文学の政治経済学を無視して、文学と出版産業の衰退に追いやっている。文学者は「文化的プレステージ」が低いとマスコミ批判を繰り返してきたものの、代替案を示したとは言いがたい。文学者は、マスメディアへの批判によって、存在意義を主張できる以上、それを既成事実として黙認する。今、マスメディアを脅かしているのは、文学ではなく、携帯電話であり、インターネットである。文学もマスコミと運命をともにしている。
その結果、出版産業は不況に陥るだけでなく、別の問題への早急な対応を迫られている。世界規模で最も深刻な問題として環境問題が上げられるが、今や商品は環境に配慮していなければならない。さまざまな素材が使われている出版物も厄介なゴミの一つである。戦後日本の政治・経済体制は、経済成長という目標の下、矛盾を承知しながら、機能し、文学は経済成長の矛盾を批判してきたが、既成事実に代替案を指し示さず、暗黙のうちにそれを支持している。と言うのも、文学は、出版産業の経済成長に基づいて、発展してきたからである。出版産業が経済成長すれば、排出するゴミも増える。文学は文化か商品かという二項対立ではなく、文学者が忌み嫌っていたゴミとしての姿を考慮しなければならなくなっている。
一九八〇年前後に生まれた文学傾向には、実は、今の状況の予兆がある。それを顕在化しても、厳密には、停滞の原因を解くことはできない。ただ、一九八〇年代から現在に至るまでの日本文学の流れを辿るとき、ある種のストレンジ・アトラクター(strange attractor)を描き出せる。それは今後の日本文学の流れを予測するものであり、日本文学の現状に対する一つの代替案、すなわち「オルタナティブ」である。近代という従来、文学は層流として考えられてきたが、今やオルタ米ティヴという乱流が文学である。オルタナティブとしての文学こそが八〇年代以降の最も重要な流れにほかならない。
一九八〇年前後に出現した文学傾向は「ポストモダン文学」と呼ばれている。ポストモダン文学の前段階に三人の小説家が登場し、ポストモダン文学に影響を与えている。一人目は中上健次、二人目は村上龍、そして最後に村上春樹である。ただし、ポストモダン文学の作家は、前者二人を好意的に、村上春樹を否定的に、それぞれ見ている。
東京オリンピックを境に、日本列島の風景が改造されていく。高度経済成長により農村を中心とした伝統的な生産手段・生産様式が衰退し、都市と農村の対立は終わり、日本中で都市化=均質化が始まる。風景に結びついている日本近代文学は、そのため、変容せざるをえない。中上健次は風景の変化を最も敏感に感受した作家である。『岬』(一九七五)により戦後生まれとして初の芥川賞を受賞しているように、中上健次には近代文学とポストモダン文学の二つの要素が同居している。日本近代文学の主流である自然主義文学から派生した私小説と物語の枠組みだけを残し、自分の修辞法で描くと、風景が一変し、多様な意味が創出される。こうした中上の文体は審美的ではなく、土木工事の荒々しさと緻密さが見受けられる。彼はウィリアム・フォークナーの影響を強く受け、ヨクナパトーファ郡を思い起こさせる熊野や紀州を舞台とした『岬』と『枯木灘』(一九七六-七七)から始まる物語群において、人物再登場法なども導入している。中上は被差別部落の出身であり、差別と文学が出会うその場所を「路地」と呼び、ローカルでありつつ、グローバルな文学空間を創出している。
一九七六年、村上龍は『限りなく透明に近いブル-』でデビューする。本名を村上龍之助というこの作家は、池田満寿夫の『エーゲ海に捧ぐ』とともに、これにより芥川龍之介の名を冠した文学賞を授与されるものの、選考委員の一人が結果に抗議して、辞任している。村上龍は若者文化や時事的な話題、風俗を掬い上げ、中上健次が行った破壊を通じた再生をパンク文学によって描いている。二〇〇一年から、かの文学賞の選考委員に就任している。
一九七九年には、村上春樹が『風の歌を聴け』を発表する。村上春樹は中上健次が無効にした修辞法を復活させ、それを新たな風景と物語との間に必然性ではなく、任意性によって結びつけている。バブル経済最中の一九八七年に発表した『ノルウェイの森』が空前のヒットとなり、以降、確実に部数を稼げる作家として、出版社から重宝されている。
日本文学は、八〇年代を迎えて、急速に変質している。日本は、自動車・家電産業を中心にして巨額の貿易黒字を築きあげ、世界第二位の経済大国に成長し、東京は、世界で、最もファッショナブルかつハイテク化された都市を自認するようになる。この豊かさを謳歌する社会的・時代的状況にふさわしい文学の登場が待ち望まれていたのである。
一九八〇年、一橋大学の学生だった田中康夫が『なんとなく、クリスタル』を発表する。ポストモダン文学は「一九八〇年東京」を描いたこの作品から始まる。全体は、モデルをしている女子大生由利を主人公にした私小説の本文、四四二に及ぶ註、人口問題審議会「出生力動向に関する特別委員会報告」と「五十四年度厚生行政年次報告書(五十五年度版厚生白書)」の三つの部分によって構成されている。本文で現代の若者の生活を描き、註で、ブランドやディスコなど登場してくるものを解説、若者に対する非難を批判すると同時に、若者にも苦言を呈し、さらに、最後の二つの表により、少子高齢化が急激に進み、次作で彼が命名した「ブリリアントな午後」にある日本社会もいずれ夕暮れが訪れると警告している。従来の文学と比べて、破格とも言える構成の作品は、出版されるやいなやミリオン・セラーとなり、「クリスタル族」という流行語まで生み出している。
田中康夫は、現代ではすべてが記号化し、等価の時代になっていると宣告する。価値はア・プリオリではなく、社会的・時代的背景の下、その都度、個人的な欲求・欲望に基づいて構成される。一切が無価値なのではない。ヒエラルキーが崩壊し、すべてが等価に置かれ、アナ-キーに、クロスオーバーしているのが「ぼくたちの時代」だと田中康夫は訴えたのである。
こうしたプラグマティズム的な主張は、江藤淳や野間宏、古井由吉などの少数を除く、既存の文学者・編集者・ジャーナリストから糾弾されたが、高度消費社会とポストモダニズムが融合した時代の中、次々に共鳴する作家がデビューする。一九八二年、高橋源一郎が『さようなら、ギャングたち』、翌年には、島田雅彦が『やさしいサヨクのための喜遊曲』、さらに、一九八四年、小林恭二が『電話男』を公表する。小説の他にも、一九八三年に浅田彰が『構造と力』、中沢新一が『チベットのモーツァルト』により登場している。特に、『構造と力』は思想書として類を見ない売り上げを記録する。浅田彰と中沢新一に代表される理論家は「ニュー・アカデミズム」と呼ばれている。
ポストモダン文学は、全般的に、理論志向が強く、新たな方法を携えて日本文学にやってきた越境者である。島田雅彦は現代ロシア小説、高橋源一郎は現代詩、小林恭二は現代俳句、ニュー・アカデミズムはポスト構造主義に強く影響されている。ポストモダン文学は、そのラディカルなアナーキズムによって、先行文学との非連続性が強調されるため、日本文学の後継への期待をこめて作家に与えられる芥川賞とは縁遠い状況になっている。
八〇年代の文学が近代文学と断絶していると判断されたのは、新中産階級の言文一致を行ったからである。ポストモダン文学の前の「内向の世代」も方法に意識的だったが、言文一致には踏み切れていない。一九八〇年前後、新中産階級の話し言葉を書き言葉と一致させる「新言文一致」が起きている。ポストモダン文学や村上龍、村上春樹の日本語は語り手と登場人物の台詞の間には差がなく、いずれも新中産階級に属している。それは近代日本の目標の一つである経済的豊かさが達成された初めての階級である。彼らの間では、女性の大学進学率は、急激に上昇し、女性の社会進出も進み、良妻賢母のイデオロギーは支配的ではない。新中産階級は物質的に豊かになったけれども、充たされない心を抱えている。ところが、既存の文学の書き言葉ではそれを表現できない。
新言文一致は、「昭和軽薄体」とも呼ばれ、小説にとどまらず、Walkmanが発売された一九七九年、「ま、とにかくその『眼ごたえ』があったナ、とわかったときのこちら側の気分というのは、じつにもう必然的緊縛大全的に自虐的にならざるを得ないのね」といったライト・ヴァ-スで綴られた椎名誠のエッセー『さらば国分寺書店のオババ』を皮切りに、エッセーにも波及し、かつてないほどのエッセー・ブームが起きている。他にも、橋本治が、『桃尻娘』(一九七八)の中で使った軽薄で、好色な女子高生の語り口調を「桃尻語」と命名し、清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』を桃尻語に翻訳している。「春って曙よ!だんだん白くなってく山の上の空が少し明るくなって、 紫っぽい雲が細くたなびいてんの! 」(『桃尻語訳枕草子 上』)。この流れは最も伝統的な文学である短歌にも波及する。一九八七年、俵万智が『サラダ記念日』を発表する。「『この味がいいね』と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」。「丸文字」と呼ばれる意識的に丸く記された「かわいい」文字が若い女性の間で流行していたが、この短歌はその文字がふさわしい。
新言文一致は女性的な言葉による言文一致である。近代文学を記してきた標準語は言文一致運動として成立しているが、それは国民の言葉であり、戦前の選挙権と徴兵制、高等教育が象徴しているように、国民は成人男性の均質化として形成されている。ポストモダン文学者は男性作家が多いが、シャルル・フーリエ的な両性具有によって、国民文学を解体する。
新中産階級の話し言葉は軽く、広告のコピーを思い起こさせる。一九八二年に『ルンルンを買っておうちに帰ろう』を発表して、話題になった林真理子がコピー・ライター出身であることは示唆的である。この年に糸井重里(いとい・しげさと)が考案した「おいしい生活。」というコピーが話題になる。この句読点の使い方は、当時はそれほど注目されなかったが、九〇年代後半に盛んに用いられるようになる。橋本治も、もともとは、一九六八年、東大駒場祭のポスター「とめてくれるな おっかさん 背中のいちょうが泣いている 男東大どこへ行く」を描いて有名になっている。ポストモダン文学は、ポップ・アートと同様、商品名やブランド名を記号として扱い、登場人物の名前も記号化し、過去の文学との断絶を強調する。ポストモダン文学の作家は、十九世紀的な「商品としての小説」ではなく、ノーマン・メーラーを思わせる二十世紀的な「商品としての小説家」を体現し、作品は「ぼく自身のための広告」である。登場人物の名前だけでなく、作家自身の名前や作品のタイトルにもその記号化を拡大化する。「吉本ばなな」という筆名は、松雄芭蕉の「芭蕉」がバナナの葉を意味しているとしても、こうした時代の流れをぬきに考えられない。その後、この流れは加速し、「田口ランディ」など非常に奇抜になっていく。瞬間的な奇抜さと無意味さがその選択基準であり、後に述べるように、それは無責任にすぎない。村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(一九八五)や『ねじまき鳥クロにカル』(一九九四-九五)は、キンクスのアルバム・タイトルのようなユーモアが感じられない。さすがにプリンスを真似て読めない記号を名前にするものはまだいない。
新言文一致を背景に、八〇年代から九〇年代に渡って、女性作家の活躍が隆盛を迎える。彼女たちはもう古典的な家族制度をテーマとはしない。小川洋子の『妊娠カレンダー』(一九九一)や荻野アンナの『背負い水』(一九九二)、川上弘美の『蛇を踏む』(一九九六)、柳美里の『家族シネマ』(一九九六)のように、妊娠や出産、恋愛、家族を扱っていても、主人公が破滅に向かうわけではなく、基盤が不安定なまま安定しており、古典的な枠組みから逸脱している。吉本ばななは、『キッチン』(一九八七)において、大切な人の死が自己を不確かにする状態を書いている。山本昌代は、『居酒屋ゆうれい』(一九九一)の中で、夫を慕って訪れる先妻の幽霊をグロテスクではなく、ノエル・カワ-ドの『フライト・スピリット』ばりに、あっさりと書いている。また、『ベッドタイムアイズ』(一九八五)の山田詠美や『ファザーファッカー』(一九九三)の内田春菊は奔放な性の描写を軽い文体で繰り返しているし、松浦理英子は、『親指Pの修業時代』(一九九三)において、自分の足の親指が男性性器になった両性具有の女性を中心に、さまざまなセクシャリティを描いている。言葉と自己との関係をテーマにする作家も登場している。生野頼子は、『タイムスリップ・コンビナート』(一九九五)の中で、言葉への違和感を小説化しているし、ハンブルクを中心に活動し、『犬婿入り』(一九九三)で知られる多和田葉子はドイツ語でも、日本語でも作品を書き、二つの言語間の溝を描いている。さらに、水村美苗は、後に言及するが、『私小説 from left to right』(一九九五)で、日本語と英語の溝を描くだけでなく、日本近代文学の記憶を遡行している。彼女たちの文学作品は従来の「女流文学」というカテゴリーにあてはまらない。そういう区別はもはや失効している。
ただ、すべてが新しいわけではない。過去の文学作品だけでなく、内田春菊がマンガ家でもあり、柳美里が劇団を主宰していた経緯があるにしても、映画やマンガ、音楽のパロディの意識を欠いた焼き直しである作品も少なくない点には注意が必要である。
現在、言文一致は、事実上、文学的な意義を失っている。九〇年代後半の十代の少女が中心のユース・カルチャーにとって最大の出来事は携帯電話の普及である。携帯電話の通話料は若者の生活費全体に占める割合が最も高く、他の消費が抑ええられている。携帯電話を通じたおしゃべりやEメールは彼女たちにとって最も重要な生活の一部であり、新たな言文一致は、文学を待つまでもなく、このメールで実践されている。彼女たちの早口で、隠語と省略に満ちた話し言葉は、メールでは、記号だらけの文章に変換されている。言文一致は日本近代文学の根幹であったが、この意味でも、近代文学は時代遅れになっている。
もともと近代文学の言文一致は二葉亭四迷の『浮雲』(一九八七-八九)に始まる。二葉亭は、第一編を書き上げてみて、江戸文学から完全に脱却できていないと感じ、その第二編をまずロシア語で書き、それを日本語に翻訳してから公表している。言文一致は翻訳から始まっているのであり、翻訳は異なる言語の間の交渉である以上、言文一致自体が古びてしまった今日、むしろ、文学者の交渉人としての立場はより鮮明になっている。二葉亭は、実際、エスペラント語の普及に取り組んでいる。それを最も理解しているのが柳瀬尚紀である。柳瀬尚紀は、過去の日本文学の文体だけでなく、童歌や落語といった民衆文化の語り口調を使い分け、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』や『フィネガンズ・ウェイク』を翻訳し、刊行し続けている。彼はその悦楽を、joyfulとJoyceをひっかけて、joycefulと呼んでいる。後に言及する清水義範も、『船が州を上へ行く』(一九九二)において、『フィネガンズ・ウェイク』のパロディを猿蟹合戦として書いていることを付記しておく。
言文一致運動の経緯からも、日本近代文学が越境の力学に従って発展してきたことは明白だろう。国民国家は領土化=国籍化を行うが、それには越境によって生じるエネルギーを力の源泉にできる認識が潜んでいる。越境は浸透圧(osmotic pressure)が可能にする。内部と外部は半透膜(semi permeable membrane)によって分けられ、溶液の濃度を一定にしようとするファントホッフの法則(πV=nRT)に基づいて浸透作用を始める。これは熱力学の領域に含まれる。産業革命が蒸気機関に象徴されるように、十九世紀は熱力学的世界である。この時代背景の下、国民国家の形成とともに成立した近代文学も熱力学的発想に従ってきたのである。
この越境の力学は、東西冷戦の崩壊という乱流によって、ほぼ機能しなくなっている。フランシス・フクヤマは、一九九二年、「歴史の終わり」を唱えたが、彼の意図とは別に、フクヤマが立脚する「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」(『法哲学』)、ならびに「世界史とは自由の意識の進歩を意味するのであって、その進歩を必然性において認識するのがわれわれの任務である」(『歴史哲学』)というヘーゲル的な歴史観が終わったことは間違いない。歴史は正しさを証明しないし、運動でもない。運動は力の方向性を意味するが、そうした線形的な歴史観は終焉を迎えている。歴史にはただ流れがあり、それは非線形である。そもそも日常的に見られる流れは層流ではなく、乱流である。世界史を考察するには、マルクス=エンゲルスが『ドイツ・イデオロギー』で「交通(traffic intercourse)」を提唱したように、運動ではなく、粉流体を含めた流体の科学の比喩で把握することが望ましい。
モダニズムやシュールレアリズムのような運動としての文学も終わっている。ポストモダニズムは運動ではなく、現象である。微積分ではなく、変分法(calculus of variation)を使って、文学現象を考察する時代が来ている。ジャン=フランソワ・リオタールが、ポストモダンを「大きな物語」の解体と述べた通り、ポストモダン以降、作品へのアプローチも、フェミニズム、カルチュラル・スタディーズ、ポストコロニアリズム、エコロジー、ポスト・マルクス主義、従属理論、サバルタン、クィアーなど多様化しているが、いずれも大きな理論とは言いがたい。歴史の終わりは大きな物語の対立から小さな物語の乱立を招いている。けれども、それら小さな理論の間に流体力学が働いている。この作品における「流体力学」は広義である。大きな理論は、線形的な運動の歴史観の下で、可能なのである。ポストモダン文学には大きな作家が存在しない。田中康夫は、デビュー時に、ポストモダン社会では、ドストエフスキーやトルストイのような壮大な小説を書けないと認めている。彼は決定論か確率論かという大きな二項対立ではなく、決定論的非周期性を追求する。ポストモダン文学は多くの小さな作家による集団的匿名である。歴史の終わりは組み合せの創造性を重要視させている。未知のものを新たに見つけ出すのではなく、ヨハン・フォン・ノイマン(von Neumann)がノイマン型コンピューターを考案したように、既知のものの反復を通じて、すなわち既知のものを組み合わせることによって、あるいは既知のものを置換することによって、未知のものを導き出す。大きな物語の終焉は、むしろ、小さな初期条件の差が大きな結果をもたらす社会を到来させている。この時代では、対決は有効ではない。交渉によって小さな差異の中で妥協する必要がある。
ポストモダン文学以降に登場する作家はポストモダン文学のジレンマに直面している。新たな方法を携えてセンセーショナルにデビューするものの、その時以上に評価を得ることは少ない。ポストモダン文学の反復であるが、ポストモダンが世界的な同時代性を意識していたのに対して、日本国内における共時性に基づいている。九〇年代において、パンク文学が隆盛を迎えるが、実際には、八〇年代のマンガや映画、音楽のリメイクである。辺見庸の『自動起床装置』(一九九二)、阿部和重の『インディヴィジュアル・プロジェクション』(一九九七)、藤沢周の『ブエノスアイレス午前零時』(一九九八)、町田康の『きれぎれ』(二〇〇〇)などが代表である。映像を意識した奇抜な発想と肉体的・精神的暴力、奔放な性への志向の強さが目立つ。自己と他者の関係の崩壊を表現するという点でも、彼らは先にあげた女性作家の多くと同じ流れにある。バブル経済が始まった一九八六年くらいから徐々に見られ、九〇年代半ばから顕著になっている。これは、バブル経済と失われた十年の中で、時代や社会に身を寄せようにも、それが遠く感じられるようになった作家の反応であろう。作家にとって方法はガルゲンフモール(the gallows humor)である。処刑の前に一度きりで発せられる。ところが、十九世紀がニヒリズムだったとすれば、二十世紀はニヒリズムでさえない。二十世紀は、クルト・ゲーデル(Kurut Goedel)が不完全性定理で結論づけた通り、決定不能の世紀である。仮想と現実、内部と外部、自己と他者の関係も決定不能である。ニーチェは、十九世紀、「神の死」を唱えたが、二十世紀では、神は、ウォルト・ディズニーのように、冷凍保存されている。神は死んでいるとも死んでいないとも言えない。二十世紀では、神の死と不死は決定不能の状態にある。ガルゲンフモールを口にした者は、死と不死の決定不能性を体現しなければならなくなる。
九〇年代に入り、治安が悪化するとともに事件が凶悪化し、『異邦人』のムルソーや『時計じかけのオレンジ』のアレックス、『冷血』のディック・ヒコック=ペリー・スミスを思い起こさせる事件が目立つ中、作家たちはよりいっそうの異様さやグロテスクさを追い求めている。大震災やオウム事件の中、あえて退屈な日常を抑揚のない文体で描く保坂和志の『この人の閾』(一九九五)のような代替案的な作品もあるものの、多くの作家は既成事実を追認する短絡的で、刺激的な作品を書く傾向にある。しかし、国内外を問わず、定住人口に比べて流動人口の比率が高まっているため、日本社会における暴力は表面的に見える以上に、さらに陰湿化し、invisibleさが強まっている。作家の方がそれに苛立ち、visibleな暴力を描くことにカタルシスを求めている。国際社会が流動化し、「日本文学」の手法では現象を記述することはできない。ニーチェの『ツァラトゥストゥラはかく語りき』における「精神の三段の変化」に従えば、八〇年代までの日本文学は「ラクダ」であり、八〇年代以降の文学は「ライオン」であって、日本の文学の現状は、「幼子」としてのポスト日本文学の登場を待ちわびているにもかかわらず、「幼子」からほど遠い。阿部和重や藤沢周もそうした作家に含まれるが、特に、柳美里はセンセーショナリズムを先鋭化させ、スキャンダルの具現を追及している。確かに、ブルジョアの社会では、スキャンダルは排除の機能を果たし、大衆社会では、逆に、セールス・ポイントであるけれども、すべてが等価である以上、スキャンダルの特権性は終わっている。
柳美里は、デビュー作『石に泳ぐ魚』(一九九四)の中でモデルにした女性から、プライバシーの侵害と名誉毀損があると名誉毀損で訴えられている。一九九九年、東京地裁は柳と新潮社に出版差し止めと損害賠償を命じ、二〇〇一年、高裁もこれを支持している。この判決に対して作家の間でもさまざまな反応があるが、プライバシー侵害ははなはだしく、「異様な生き物」や「顔に貼りついている不気味な悲劇の仮面」、「鳥肌が立つ」など問題になった悪口雑言は仰々しく、陳腐で、文学的表現と呼ぶことさえ不可能であることは確かである。他にも、『宇宙パトロール』に見られるてんかん患者への差別の記述に対するてんかん協会から抗議されたことに逆上した筒井康隆が、一九九三年、「断筆宣言」をし、九六年に「解除」している。筒井はマイノリティをスキャンダラスに扱い、差別を扇動して、カタルシスを感じる作家である。柳にしても、筒井にしても、彼らの表現者としての無能さと倒錯した権力意識を問うべきであり、これらを表現の自由として考えるべきではない。
日本における表現の自由という問題は天皇をめぐる記述だけに限定される。大江健三郎の『セヴンティーン』第二部と深沢七郎の『風流夢譚』は、天皇を描いたために、出版社から自粛され、全集にすら入っていない。『中央公論』一九六〇年十二月号に掲載された『風流無譚』は、カーニバルな革命の中、皇居に乱入した左翼の手で天皇一家が殺害される「夢」を中心にした小説であり、皇太子と皇太子妃の首が「スッテンコロコロ」と切り落とされるなど皇族を茶化した描写が数多くある。この作品に憤慨した右翼の十七歳の少年が中央公論嶋中社長宅を襲い、夫人に重症を負わせ、家政婦を殺害している。これは嶋中事件と呼ばれている。身の危険を感じた深沢は、サルマン・ラシュディさながら、身を隠し、各地を放浪している。さらに、勢いをつけた右翼は、翌年の『文学界』一、二月号に発表された『セヴンティーン』も問題視し始める。『セヴンティーン』は、一九六〇年十月十二日、社会党書記長浅沼稲次郎が右翼の十七歳の少年に刺殺された事件を扱っている。どちらのテロリストも大日本愛国党に籍を置く経験を持っている。これらの事件に関して多くの文学者や知識人の間で激しい論争が起きたものの、中央公論社も、文芸春秋社も、表現の自由の侵害に対する抗議記事ではなく、読者への「おわび」を掲載している。『セヴンティーン』は少年が右翼に共鳴してゆく過程を書いた第一部のみ出版されている。その後、天皇暗殺計画を描いた桐山襲の『パルチザン伝説』(『文芸』一九八三年十月号)も出版をめぐって問題化している。ほとんどの日本の作家は、昭和天皇の死の一年前に日本全国で自粛現象が起きたように、天皇をめぐる記述を自粛している。日本では認められているはずのことも禁止されているのである。
昭和から平成へと年号が変わり、バブル経済が破綻し、東西冷戦が終結した九〇年代、近代文学の伝統的諸問題が復活している。坪内逍遥の『当世書生気質』(一八八五)以来、日本近代文学は、定期的に、若者風俗に接近してきたが、『文芸』誌が渋谷や新宿といったよりストリート文化に根ざした若者の文学を「J文学」と命名し、意識的にとりあげている。また、純文学とエンターテインメントの境界が曖昧になり、よりクロスオーバーしていく。一九九八年上半期芥川賞受賞作家『ゲルマニウムの夜』の花村満月と直木賞受賞作家『赤目四十八瀧心中未遂』の車谷長吉は、それぞれ逆の範疇に属していると思われていたが、この受賞は、一九六二年下半期芥川賞受賞作の五味康佑の『喪神』とは違い、論争にもならない。と言うよりも、伝統的諸問題の復活が、論争を欠いたまま、受容されている。
古典的なテーマが復活してくるのは、社会や時代に代替案の提示を迫られたからである。文学者はかつて伝統的なテーマを批判として把握している。しかし、社会と時代の変化にともない、文学も既成事実に対する批判=対決ではなく、代替案の提示=交渉をする必要に迫られている。中でも顕著なのは政治と文学、すなわち文学者の社会参加への流れである。
一九九五年、一月十七日に、阪神・淡路大震災が発生し、三月二十日には、オウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしている。この二つの出来事は文学者に態度の変更を迫ることになる。忘れられていた「アンガ-ジュマン(commitment)」が蘇っている。
田中康夫は、地震直後に、神戸に救援物資とともに50CCのバイクで入り、ゲリラ的なボランティア活動を始めている。救援物資を住民一人一人に手渡ししつつ、「今、神戸では何が起きているのか」、すなわち現状はどうであり、誰がどこで何をし、何を必要としているのかをメディアを通じて、全国に発信している。田中康夫は、個々人のインディペンデントな連帯という持論に基づき、従来の組織的ボランティアやメディア主導のチャリティを転倒し、個人主体の活動を行い、一般の人々だけでなく、多くの文学者も彼を支援している。この活動は、翌年、田中康夫自身によって『神戸震災日記』として出版されている。その後、公共事業や選挙をめぐり、積極的に政治的発言・行動し、二〇〇〇年、長野県知事に当選している。
一連の田中康夫の行動に対して、浅田彰や島田雅彦を筆頭に十数人の文学者が支持を表明している。ポストモダン文学者は政治への関心は低いと先行文学者から見られていたが、ポストモダン文学の共鳴者坂本龍一が告げているように、全共闘世代の政治手法への違和感から、そうした態度を示したのであり、実際、一九九五年以降、政治への発言を特に強めていく。大きな物語の下で活動を始めたけれども、その時でも、ポスト八〇年代を見据えている。先行文学世代による一九八二年の反核アピールにしても、一九九一年の湾岸戦争反対アピールにしても、あくまでも既成事実への反対にすぎず、代替案の提示からは遠い。東西冷戦・高度経済成長という戦後の枠組みが崩れてしまった後、政治だけでなく、他の分野でも、批判するだけでなく、代替案を提案する勢力が求められるようになっている。田中康夫は、旧来の二項対立の一方の側につくのではなく、両者と交渉し、代替案を提出する。彼の社会参加は対決=怒りではなく、交渉=笑いである。田中康夫は、文学者だからこうした社会参加のあり方ができると強調している。ポストモダン文学者の社会参加は、文学者は批判者だけでは不十分であり、交渉人でなければならないという認識をもたらしている。
代替案を待っているのは現在ではない。むしろ、未来である。今日の重要課題は南北問題ではなく、世代間問題である。『なんとなく、クリスタル』は、ある点で、それを先取りしている。明日はまだ来ていない。そのため、現在が未来を代行している。現在は、交渉人として、未来に対して代替案を示さなければならない。現在は未来に説明結果責任を負っている。現在は未来の代理人として過去と交渉する必要がある。現在は未来との契約を尊重し、未来に不利にならないように、過去の負債と財産の両方を公開しなければならない。現在は越境の力学に従っている過去を流動化させる責任がある。世代間問題の中でも最大なものは環境問題であろう。かつての労働運動は現状に対する不満から湧き上がったが、現在の環境問題は未来への不安が根底にある。多国籍企業を非難すれば解消されるほど、その不安はvisibleではない。チェスに見られる勝敗が明確なゲームではなく、囲碁をするように、現実に臨む必要がある。未来はまったく未知であるわけではない。環境問題は気象という複雑系が支配する事象に左右されるため、バタフライ効果と大袈裟に呼ばれている通り、小さな初期変化が大きな結果の違いをもたらす。そもそも複雑系は、一九六一年、気象学者のエドワード・ローレンツのコンピューターへの入力ミスによって、偶然、発見されている。複雑系は初期値敏感性のある非線形であり、決定論的非周期性を持っている。微分方程式では解けないが、コンピューター・シミュレーションをすると、普通の帯とメビウスの帯を合わせたレスラーの帯と呼ばれる軌跡、もしくはストレンジ・アトラクターを辿る。複雑系には、カオス理論・自己組織化・生物モデルの三つの理論が含まれているが、いずれも本質や実体ではなく、現象を扱う。複雑系に左右される環境問題はたんに資源を枯渇させる現象ではない。倫理を枯渇させる。世代間問題は倫理の問題であり、文学は倫理の代替案を指し示さなければならない。二十一世紀は神が尊厳死を求めている時代になろう。国民国家を含め十九世紀以来続いている諸問題が尊厳死を願っている。国民国家の尊厳死は、EUが出発したように、実質的に、認められている。しかし、耐えがたい苦痛に悩まされ、日に日に衰弱し、治療法が残されておらず、神は安らかなる死を望んでいる。二十一世紀において、殺人や自殺と区別される尊厳死合法化のための交渉に文学も参画しなければならない。ゴミは死ぬに死ねない商品であり、その問題も尊厳死を認め、リサイクル、すなわち資源の永劫回帰によって解決される。
全共闘世代に属する村上春樹は、作家による社会参加への流れを認識しながらも、それを見せかけですまそうとしている。村上春樹は、「はじめに」の中で、ある女性誌の投書欄に寄せられた「地下鉄サリン事件のために職を失った夫を持つ、一人の女性によって書かれた」手紙が『アンダーグラウンド』執筆に至る動機としてあげている。ところが、この投書が実在しないことが明らかになっている。村上春樹はでっちあげた執筆動機にのっとって、この本を書きあげたというわけだ。『アンダーグラウンド』は、地下鉄サリン事件に遭遇した被害者と遺族、医師、精神科医、弁護士などからのインタビューを集め、「村上春樹が真相に迫るノンフィクション」として、一九九七年に出版されているが、ノンフィクションの前提が崩れたノンフィクション、フェイク・ノンフィクションである。だからと言って、村上春樹は、メニッポス的諷刺の作家である花田清輝(はなだ・きよてる)や寺山修司(てらやま・しゅうじ)のように、動機、すなわち起源をパロディ化しているわけでもない。こんな見せかけが村上春樹の倫理である。「顔のない多くの被害者の一人」ではなく「一人ひとりの人間の具体的な──交換不可能(困難)な──あり方」を浮き彫りにすると言いながら、証言者のプロフィールにおいて、「いかにも若々しい青年」や「いかにも思いやりがありそうだ」、「いかにも育ちのよい」といったように、村上春樹は「いかにも」を連発している。村上春樹は「具体的」どころか、ただイメージをなぞっているにすぎない。ソープ・オペラ的なイメージは解釈する必要がなく、受動的に接していても、即効的に、その意味を理解している錯覚に陥らせる。これは日本で「小説の神様」とかつて崇め奉られた志賀直哉の修辞法である。それでいて、「基本的に、自分が現在前にしているインタビュイーの一人ひとりを、個人的に感情的に好きになろうとつとめた」と告白する村上春樹の文学は施しの文学であると言わざるを得ない。
村上春樹のイメージへの依存はこの本に限らない。
ベストセラー小説『ノルウェイの森』の冒頭に、ドイツ人客室乗務員が登場するが、客室乗務員が次のような態度で機内の気分が悪そうな乗客に接することはない。
飛行機が着地を完了すると禁煙のサインが消え、天井のスピーカーから小さな音でBGMが流れはじめた。それはどこかのオーケストラが甘く演奏するビートルズの『ノルウェイの森』だった。そしてそのメロディはいつものように僕を混乱させた。いや、いつもとは比べものにならないくらい激しく僕を混乱させ揺り動かした。
僕は頭はりさけてしまわないように身をかがめて両手で顔を覆い、そのままじっとしていた。
やがてドイツ人のスチュワーデスがやってきて、気分が悪いのかと英語で訊いた。大丈夫、少しめまいがしただけだと僕は答えた。
「本当に大丈夫?」
「大丈夫です、ありがとう」と僕は言った。スチュワーデスはにっこり笑って行ってしまい、音楽はビリー・ジョエルの曲に変った。僕は顔を上げて北海の上空に浮かんだ暗い雲を眺め、自分がこれまでの人生の過程で失ってきた多くのものごとを考えた。失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い。
飛行機が完全にストップして、人々がシートベルトを外し、者入れの中からバッグやら上着やらをとりだし始めるまで、僕はずっとあの草原の中にいた。僕はずっとあの草原の中にいた。僕は草の匂いをかぎ、肌に風を感じ、鳥の声を聴いた。それは一九六九年の秋で、僕はもうすぐ二十歳になろうとしていた。
前と同じスチュワーデスがやってきて、僕の隣りに腰を下ろし、もう大丈夫かと訊ねた。
「大丈夫です、ありがとう。ちょっと哀しくなっただけだから(It’s all right now, thank you. I only felt lonely, you know)」と僕は言って微笑んだ。
われわれであれば、気をつかってくれた相手への感謝の気持ちから、たとえカタコトであったとしても、”Thank you for asking me, but I’m fine now. Don’t be afraid of me, please! It has made me a little nervous”と最低限は言うところだが、この主人公は” It’s all right now, thank you. I only felt lonely, you know”といささか失礼な物言いをしている。さらに、「失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い」は書かずに暗示させるべきである。しかし、これが村上春樹の本質を表わしている。着地してすぐの時間帯に機内を歩き、「身をかがめて両手で顔」を覆っている乗客に気分を訊くだけで何のアドヴァイスも言わず、「にっこり微笑んで行って」ならともかく、「にっこり笑って行って」しまう客室乗務員がいるとは信じがたい。また、客室乗務員は、客が座ることを求めない限り、乗客用の座席に座ることはない。客室乗務員は、航空会社のマニュアルと経験に照らし合わせて、そうした乗客に接する責務を負っている。ところが、村上春樹は一般の観光客が乗客に話しかけているように描く。機内で気分が悪そうにしている乗客を見かけた場合、客室乗務員と一般の観光客とでは認識・対応が違うのに、村上春樹はそうした決定論的非周期性をわかっていない。書く際に、トム・ハンクスが役を演じる前に収集するような、リサーチやプロファイリングをまったくしていないと言わざるを得ない。他にも、エアラインとしては常識はずれな点が多すぎるだけでなく、これ以降も、こうした不備が続く。否が応でも、存在が意識を決定してしまうことを村上春樹は無視している。は村上春樹は、『アンダーグラウンド』の中で、「私の机にあるマッキントッシュ6310にも、やはりねぎらいの言葉をかけるべきだろう」と言っているが、コンピューターのモニターに映し出された現象によって新たな数学が見出される時代において、CGのリアリティは決定論的非周期性に基づいている。それは、一九八七年にグレイグ・レイノルズによって局所的規則から大極的な行動パターンとして創発(emergence)されたバードイド(Birdoid)──略称ボイド(Boid)──が典型である。このボイド・リアリティはCGにおけるリアリティ、バーチャリティであって、村上春樹に見られるシミュレーションを欠くフェイク・リアリティと言うべきものとは根本的に異なっている。
ポストモダン文学の作家たちはアナロジーやメタファーとして作品を書いているが、その適用論理が倫理であり、倫理の不在につながる無批判的な使用は避け、イメージを素朴に受け入れることはしない。村上春樹はその倫理を無視する。ポストモダン文学者は中上健次と村上龍を評価しても、村上春樹を認めるわけにはいかない。
『1973年のピンボール』(一九八〇)において「一九七三年、そんな年が本当に存在するなんて考えたこともなかった」と書いた村上春樹は、『アンダーグラウンド』でも、地下鉄サリン事件に関する最大の疑問を「一九九五年三月二十日の朝、東京の地下では何が起こったのか?」だと述べている。「『こちら側』=一般市民の論理とシステムと『あちら側』=オウム真理教の論理とシステムとは、一種合わせ鏡的な像を共有していたのではないか」、すなわち「われわれが直面することを避け、意識的に、あるいは無意識的に現実というフェイズから排除し続けている、自分自身の影の部分(アンダーグラウンド)ではないか」と修辞疑問文を使って問う。修辞疑問文ではアイロニーによって問いが答えを強制する。村上春樹の自意識はまったく揺らぎもしない。村上春樹は、あの事件の前後で、本質的に、何も変わっていない。日本社会では、三十八度線のように、諸問題がvisibleではなく、invisibleである。光と対比される闇といった明確なinvisibleさではなく、明かりの中の光のごとく曖昧なinvisibleさである。『寂寥郊野』(一九九三)により芥川賞に輝いた吉目木晴彦は、東京郊外の分譲マンションを舞台にした『うわさ』(一九九三)において、穏やかな文体で、invisibleな社会の日常に潜んでいる陰湿さを綴っている。オウム真理教は、隠れるように、地下で活動していたわけではない。東京都に認可された宗教法人であり、国政選挙にも立候補者を立てた通り、彼らは闇の集団ではない。実際、オウム真理教徒は、奥行きを照らし出さない白い輝きの蛍光灯の光の下で、サリンをまいている。また、三月二十日以降、オウム真理教をめぐる話題で、ソープ・オペラ的なイメージを好むワイドショーを中心に、メディアの関心はほぼ独占され、神戸の地震は片隅に追いやられてしまっている。東京オリンピックまで、確かに、闇はあったが、以降、闇は消失している。闇は蒸気機関の時代において存在し得る。炭鉱に象徴される闇は光から排除された者が辿り着く場所である。しかし、石炭から石油へと生産手段・生産様式が転換していった高度経済成長は風景を次々に作り変えていき、闇も消されていく。
中上健次は差別を日本の闇とは描かない。八〇年代までの再開発事業によって「路地」は消えたが、差別がなくなったわけではない。むしろ、陰湿化し、invisibleになっている。そこで中上は、それを浮きあがらせるために、世界各地に差別と文学が出会うサバルタンの空間を散乱させようとしたが、その途上で、彼は亡くなっている。
村上春樹だけでなく、ボルヘスを模した室井光広の『おどるでく』(一九九四)が評価されてしまうように、中上や吉目木、田中康夫を代表とする例外を除けば、新旧を問わず、多くの日本の作家には文学的想像力をかきたてるvisibleな社会への羨望がある。しかし、それは想像力の欠落であり、ルサンチマンでしかない。日本文学における越境性は、概して、こうした旅行者や海外赴任者が抱くイメージに基づいている。もしvisibleな社会・時代の作品を模倣するなら、柳瀬尚紀のように、パロディとして描く必要があるだろう。生き難さを感じている人にとって、遠い世界の物語であるからこそ、リアリティを覚え、身を寄せて読むことができるとしても、それが流動化してゆく時代や社会への反動であるとすれば。硬直した自分自身へのナルシシズムにすぎない。流動には決定論的非周期性があり、決定論か確率論かという二項対立ではなく、柔軟な姿勢が要求される。柔軟さを持って、日本社会のinvisibleさを通じて想像力を発揮した文学作品の創造性をもっと理解すべきである。
なるほどアメリカ文学も越境を創造の源泉にしているけれども、アメリカの場合、実際に人が越境してくる。日本文学の越境は、後に触れるリービ英雄の登場までは、商社や旅行代理店のように、なされている。この点でも、村上春樹は典型的である。村上春樹は、影響された作家の一人として、翻訳までしている通り、レイモンド・カーヴァ-をあげる。しかし、カーヴァ-は小さな田舎町に住む貧しい白人労働者の抱く不安や無力感を描いている。彼らは繁栄するアメリカから取り残され、アメリカン・ドリ-ムに裏切られた階級である。他方、村上春樹は都市部に住む新中産階級を取り扱う。新中産階級は、自民党長期政権の下、年功序列と終身雇用に支えられた経済成長による経済的な豊かさを最も謳歌している。中上健次がフォークナーに惹かれたのと違い、村上春樹の選択には必然性がない。デビュー作から一貫して自己憐憫と自己嫌悪に溢れた作品を書き続けている点からも明らかだが、自意識の優位を確保するためにのみ村上春樹は越境させるものも選ぶ。
『アンダーグラウンド』の中で、「地下の世界は私にとって、一貫して重要な小説のモチーフであり、舞台であった。たとえば井戸や地下道、洞穴、地底の川、暗渠、地下鉄といったものは、いつも(小説家としての、あるいは個人としての)私の心を強くひきつけた」と告げ、最新刊『神の子供はみな踊る』(二〇〇〇)に至っても、依然として「地下の世界」を描いている通り、村上春樹が「地下の世界」を必要とするのは、ロマンスの作家だからである。村上春樹の作品は、ノースロップ・フライが『批評の解剖』の中で分析した「ロマンス」にあてはまる。フライによれば、ロマンスは、すべてが一つの意図に基づき、不純なものは排除され、始まりと終わりが同一の円環構造をとり、多層な世界によって構成されている。ロマンスは、神話的であるとともに、メロドラマ的であり、ヘーゲル的な自意識と歴史の運動が見られる通り、作者の願望充足を最もかなえる文学様式である。村上春樹は、「歴史の終わり」が到来しても、ロマンスを手放す気がない。
村上春樹の修辞法は、実は、近代文学の傾向と同じである。明治に入り、「文明開化」と呼ばれる近代化が始まり、鉄道に象徴される蒸気機関が日本全国の風景を作り変えてゆく。風流からかけ離れた風景を前に、明治の文学者は西洋の文学を導入し、文学の近代化を推し進める。言文一致運動は文学の近代化の象徴である。文学者は江戸までの意味に覆われた風景に対して、無視もしくは軽視された事物をアイロニカルにとりあげ、新たな風景を獲得し始め、日本近代文学が形成されていったのである。近代の文学者は、意味と無意味の二項対立の中で、意味に無意味を浸透させる。アイロニーはフェイントであるから、手法は進歩するものの、発想はさして違わない。デビュー作において「そんなわけで、彼女の死を知らされた時、僕は6922本の煙草を吸っていた」と書く村上春樹は、ロマンス構造の作品の中、この近代文学のアイロニーを多用する。
意味と無意味の対立において、村上春樹は必ず無意味を選択する。無意味さへの志向はその二項対立を可能にしている体制の黙認を意味する。二項対立は、魔女狩りがそうであったように、選択の問題ではなく、躊躇にすぎない。「閉鎖的、責任回避型の社会体質」は、こうした一つの選択肢しかないという感覚から、生じる。そこでは説明結果責任はない。
村上春樹とは逆に、意欲的な作家がそうした近代文学の記憶を辿ることを試みている。少女時代から大学院までアメリカで暮らした水村美苗は、夏目漱石の未完の小説『明暗』の続きをその文体を模倣して書いた『続明暗』(一九九〇)によって注目されている。この試みに刺激を受けて、『石の来歴』(一九九四)で戦争の記憶を扱った奥泉光が『「我輩は猫である」殺人事件』(一九九六)、皇太子にエイズを移しそこねた両性具有の顛末を『未確認尾行物体』(一九八七)に記した島田雅彦が『彼岸先生』(一九九五)を発表している。その後、帰国子女を主人公にした『私小説 from left to right』により有名になっている。この作品はすべて横書きで書かれ、ほぼ同じ比率で英語と日本語が使われている。私小説は近代文学における最も中心的なジャンルであると同時に、その閉鎖性・制度性を体現している。彼女は近代文学の起源を問い直し、その歴史性を明らかにしている。
『私は作中の人物である』(一九九二)を描いた清水義範は、過去に遡行するだけでなく、現在あるさまざまな言説をパロディとして書いている。一九八六年、名古屋に関する擬似比較文化論文『蕎麦ときしめん』を発表し、注目を浴びる。さらに、一九八八年には、日本教育をパロディ化した『国語入試問題必勝法』や『永遠のジャック&ベティ』を書いている。前者は問題を読まなくても、そこには長短除外の法則・正論除外の法則など数々の法則があり、選択肢を見ただけで答えがわかってしまうという作品であり、後者は中学生用の英語の教科書をモチーフに使った恋愛小説であるが、その語彙と文法上の制約から、二人の間でまったく愛が深まっていかない。言うまでもなく、自分自身とポストモダン文学の立脚点へのパスティシュも忘れない。締め切り間際の作家が何も書けないことへの弁明を綴った『深夜の弁明』(一九八七)、コピーライターに対するパロディ『三流コピーライター要請講座』(一九八八)がそれにあたる。清水義範は、現在に至るまで、日本国憲法や国語辞典、日本史、古典文学、方言、新聞、日本文学全集、世界文学全集、パソコン入門にとどまらず、ありとあらゆる領域に渡る娯楽性の強いパスティシュ作品を書き続けているが、不当に低い評価で扱われているが、最も重要な現代作家の一人である。
近代文学の記憶を辿りつつ、それが排除してきたものを顕在化させる試みも始まっている。沖縄出身の二人の作家、『豚の報い』(一九九六)の又吉栄喜と『水滴』(一九九七)の目取真俊がその代表である。彼らは沖縄の神話的な伝統から沖縄の現状を包括する。寓話的な作品は象徴的な近代文学によって排除されてきたが、それをとりあげることを通じて、現代社会の矛盾を批判する。沖縄は近代日本の矛盾を具現している地域であり、現代人の中にある古代人的な心情を描いた『スティル・ライフ』(一九八八)により芥川賞を受賞した池澤夏樹も、文学的刺激を求めて、沖縄に移住している。
さらに、九〇年代半ばから、リービ英雄の『天安門』(一九九六)やデビッド・ゾペティの『いちげんさん』(一九九七)、唐亜明の『翡翠露』(一九九九)、毛丹青の『にっぽん虫の眼紀行』(一九九八)、アーサー・ビナードの『吊り上げては』(二〇〇〇)のように、非ネイティヴ・スピーカーの手による小説や詩が認知され始めている。歴史的背景から日本で育ったコリアン・中国人による文学は「在日文学」と呼ばれ、日本文学を構成してきたが、この新しい流れの作家は日本語を個人的理由から選んでいる。日本の作家たちには、非ネイティヴ・スピーカーが日本語で文学を書けないという暗黙の信念がある。ピジン化、あるいはクレオール化した日本語を書いたため、「変な日本語」と誤解されたこともあったが、彼らはそれを打ち破り、「日本近代文学」という概念への代替案を提出している。「われわれが知っているものとしての文学(literature as we know it)」に対して、「ありえたものとしての文学(literature as it could be)」が交渉を申し出たのである。
こうした流れは二つのいまだに書かれていない「ありえたものとしての文学」を顕在化している。南の沖縄と違い、北海道を中心にアイヌという先住民族が住んでいるが、『魔の国アンヌビウカ』(一九九六)の久間十義などアイヌの伝統からアイデアを得た作家はいるものの、残念ながら、アイヌの現代文学はほとんど生まれていない、アイヌ語は日本語と違う言語に属している。アイヌを本格的に導入するには、アイヌ語を取り入れなければ成らない。国語としての日本語はアイヌ語を抑圧し続けている。アイヌは世界各地の少数民族と連携していく中で、むしろ、流体力学的に、現代文学を生み出していくことが期待されている。アイヌ語だけではない。手話は、明治になってから、聾唖者自身が、自然発生的に、創造した言語であり、文法が日本語とは異なっている。手話が日本語と違う言語である事実を知らない作家が多いせいか、最も身近な外国語の手話を使った文学作品も生まれていない。日本語を揺るがす越境に対しては過敏なまでに近代文学は反応する。書かれなかった文学は近代が言語の共同性を前提にしている点を明らかにしている。
村上春樹は「われわれが知っているものとしての文学」を強硬に守ろうとする。彼は、オウムの選挙キャンペーンを見たとき、目をそむけ、『アンダーグラウンド』の中で、「同じときに同じ光景に直面したら、世間の人々の八割か九割までは私と同じように感じ、同じように行動したのではないかと想像する。つまりおそらく見ないふりをして通り過ぎて、それ以上深くは考えずに、さっさと忘れてしまうのだ(あるいはワイマール時代のドイツ知識人も、ヒトラーを最初に見たときには同じ反応を見せたのかもしれない)」と書いてしまう。六〇年代後半のLOVE&PEACEのパフォーマンスを模したオウム真理教の選挙キャンペーンに対して、実際には、道行く大人たちは呆れ、子供たちが真似をしてからかい、彼らがまさか本気で当選できると信じていたとは思わずに、よくある泡沫候補の宣伝活動と見ている。ところが、自分自身の中で排除し続けた全共闘時代の記憶に拒否反応を示しただけなのに、村上春樹は自分と「世間の人々の八割か九割」を同じに見ているだけでなく、無批判的に、選挙で第一党となったナチスと惨敗したオウムを類似させ、「ワイマール時代のドイツ知識人」も同一視している。日本の「閉鎖的、責任回避型の社会体質」を可能にしているのが、こういう態度であり、村上春樹の作品が体現しているものにほかならない。
明治維新が偉業だったことは否定できない。近代日本の無責任は政治的思惑による曖昧さがもたらしている。明治憲法下、司法裁判所は民事や刑事の訴訟だけを扱い、行政訴訟は行政裁判所が担当することとなっている。しかも、行政訴訟の際、民衆にそれを認めた司法省達第四十六号を制定した江藤新平が失脚して以降、明治政府は裁判所に対して、事実上、行政側に有利になるように働きかけている。これは、明治維新が革命と言うより、クーデターだったため、封建制に慣れ親しんだ行政に責任を明確にすると、仕事が滞ってしまうことを憂慮したからだが、一度出された判決は判例として生き続ける。政府が不平等条約改正に向けて急速な近代法を導入したけれども、西洋と異なり、この近代法は伝統的な日本の法制度と断絶しているといった同情できる事情もある。多くの点で改善されたものの、戦後においても、シャルル=ルイ・スゴンダ・ド・モンテスキューが見たら卒倒するほど、三権分立が不十分であり、最高裁判所は行政や立法の決定を覆したり、違憲判断を示したりすることに極めて消極的である。大江健三郎は、一九九四年、ノーベル文学賞受賞を記念して、「曖昧な日本の私」という講演を行っている。曖昧さは意図的に施されている。曖昧さは政治的であり、近代日本の形成にともなう正統性の欠落を隠蔽する。近代化という目標を急いで達成するために、正統性を不問にした上で、為政者は既成事実を人々に突きつけ、泣き寝入りさせる手法をとり続けてきたのである。歴史的な起源を明らかにする批判では、代替案を提示できない以上、封殺されてしまう。その国を治める「万世一系」の天皇は現人神であるから、政治的失敗はしない。天皇制は王権神授説とよく似ている。王権神授説では、王は神から統治する権利を受けたものである以上、失政はないというわけだ。王権神授説から社会契約説が導き出されたのに対して、天皇制からは天皇機関説が考案されている。天皇機関説は、天皇も憲法の制限を受け、国家の一機関であるという憲法学説であり、明治末期から美濃部達吉によって説かれたものの、昭和に入って右派から非難され、圧殺されている。一神教は神との契約に基づいているが、天皇を現人神とする国家神道には契約概念がなく、それは見せかけの一神教にすぎない。ロラン・バルトは日本を「表象の帝国」と呼んだが、より正確には、それは「フェイクの帝国」である。急速に発展するために、このように指導者の責任を免除したのであり、支配される側も責任を回避するために、見て見ないふりを始める。この手法は、戦後も引き継がれている。明治維新がたんなる軍事クーデターであったにもかわらず、あたかも革命であるかのような幻想を作り出す。これこそが施しである。
最初、日本において仏教は、中華文明とともに知識階級によって受け入れられた(だが中華文明は仏教だけをもたらしたのか?)。続いて宗教の混淆(仏教─神道、儒教の諸要素)があった。一九世紀になって、国民宗教の名のもとに、「宗教混淆」への反動が現れ、それは一八六八年の近代日本お誕生とともに頂点に達した。「神道」が国家宗教となる。そして短期間ではあったが、仏教への迫害があった。一八七二年に仏教は公式に認められた……。しかし一八七五年、政府はふたたびその政策を転換し、神道と仏教の二つの宗教は区別され、「神道」は特別かつ唯一の地位を占めていくことになる。神道の地位は愛国的かつ国民的な機関へと上昇し、その宗教的性格を公的に放棄することで頂点に達することになった……。日本人は、いかなる宗教にも帰依することができるが、天皇の聖像の前では敬意を表さなければならない。こうして国家神道が諸宗教から切り離されることになったのである……。しかしながら、一般大衆の間にも、また教養人の間にも、宗教としての神道への意識と感情は脈打っている(このことは当然である.だが、私に否定できないように思われるのは、逆説的な形であれ、意識的であれ無意識的であれ、世俗意識の形成を目指す宗教改革の意義である。国家神道は宗教であるかどうかという論議は、日本文化問題のより重要なものだと私には思われる。だが、こうした論議は、キリスト教ではとても考えられない)。
(アントニオ・グラムシ『獄中ノート』)
文学者の説明結果責任は、他の国以上に、日本では極めて重要な意味を持っている。一九七五年十月三十一日、最初にして最後の公式記者会見の場で、戦争責任ついて尋ねられた際、昭和天皇は「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究していないので、よくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます」と答えている。説明結果責任は文学的な修辞法に属しているのであり、文学者でないものには答えられないとすれば、文学者が説明結果責任を負い、「曖昧な日本」への代替案を提供しなければならない。
ポストモダン文学者は、村上春樹や彼ら以降の多くの作家と違い、説明結果責任を果たし続けている。すべてを等価として扱う以上、意味と無意味の区別は無効になり、作家は選択対象に説明結果責任を負うことになる。無意味さを選択することによって、責任を回避できる状況にはない。村上春樹にとって、『風の歌を聴け』で双子の姉妹に208と209と命名しているように、差異は任意であり、無意味でなければならないが、こうしたデジタルな発想はブール代数と呼ばれる特殊な演算や情報理論に基づいており、必ずしも、無意味ではない。ブール代数は論理の数学的分析のためにジョージ・ブールにより考案された代数である。コンピューター・システムやネットワークはブール代数によって支配される世界であり、検索エンジンは最も目にしやすいブール代数の応用である。ブール代数を使うと、計算回路を設計できるだけでなく、計算速度も考慮できる。また、クロード・シャノンが創始した情報理論では、情報の保存・伝達をする際に、最適符号化(optimum coding)という観点が不可欠である。無意味さは残されていない。島田雅彦は、ロシア現代小説を選んだ理由として、東西冷戦の中、反アメリカの立場を表明するためだったと述懐している。ポストモダン文学の作家にとって、自意識も他のものと等価であり、いかなる場合でも優位ではない。
一切が等価であるという認識はすべてをファイル化できる発想と共鳴する。インターネットはまだなかったし、Echelonが当時は顕在化していなかったため、ネットワークへの認識は弱かったが、ポストモダン文学者はコンピューターに関心を寄せている。Windows95の発売をめぐる熱狂をきっかけに、作家もITをとりあげられるようになり、多くの作家がホームページを開設し、オンデマンド出版や電子出版に取り組み、より関心の高い作家は、ITを比喩として、作品に導入している。早くからITに注目していた村上龍は、『共生虫』(二〇〇〇)と『希望の国のエクソダス』(二〇〇〇)の二作において、現在のオブローモフ的な社会問題とITをからませながら、描いている。前者は、引きこもりの少年がネット上の噂を信じ、殺人を犯すという作品であり、後者は、不登校の子供たちが、共同して、ネット・ビジネスを起こして世界経済を混乱に陥れ、榎本武揚ばりに北海道に脱出し、独立国家を建設するというものである。田口ランディは『コンセント』(二〇〇〇)において自身の引きこもりの経験をITの比喩をちりばめて、描いている。また、中井拓志が、中学生がサイバー・スペースに国を作るという『quarter mo@n クォーター・ムーン』(一九九九)を発表している。ただし、こうした作品において、ITは口実にすぎず、ウィリアム・ギブソンの『ニューロマンサー』を超える作品はいまだにない。そもそも次の政治体制がLinux的ではなく、中井のように仮想空間であっても、国家であるという認識は不十分であろう。ネットを通じてすべてが流動化していく以上、流体力学が機能し始めなければならないのだが、彼らは越境の力学によって描いてしまう。彼らの独立国の子供は排他性が強く、文化大革命の紅衛兵やクメール・ルージュの監視役の子供を彷彿させる。また、機械語にしろ、プログラム言語にしろ、コンピューターにかかわる言語は論理的な記述ではなく、命令であるから、せめてコマンドとして文章を書くくらいのことは望まれるが、文体自体も、従来の小説と比べて、特に異なっているわけではない。内容はともかく、文学作品の制作自体がLinux的になっていることは確実である。パソコンや携帯電話を使ったネット句会やネット歌会、詩の連作が行われている。ネット社会では越境は有名無実である。ロック・ミュージシャンで、『海峡の光』(一九九七)により芥川賞を受賞した辻仁成は「文学を守りたい。ロックという世界から越境してきた者として、おそれるものは何もない」と話しているが、半透膜はすでに取り払われているのであり、こうした主張は文学にとって反動でしかない。越境ではなく、各サイトがLinkしている。村上春樹は、デビュー作の中で、自分の作品を「リスト」と呼んだが、今や作品はリンク集である。また、筒井康隆が、一九九二年、パソコン通信を通じて、『夜のガスパール』を読者参加型作品として制作している。サイバー・スペースは情報の発信者・受信者を選ばない。文学制作には編集者・校正者・装丁者の能力が必要になっている。ネット上の文学の状況は自己組織的臨界状態の砂山であり、発表され続ける作品はそこに降り注ぐ砂である。筒井の試みがより拡大され、インターネットによる不特定多数の集団的匿名としての作品制作が行われるだろう。そのin silicoの作品は執筆段階から公開されて、印税や著作権から離れ、アーカイブとして、トマス・レイが考案した人工生命ティエラ(Tierra)、あるいはコンピューター・ウィルスのように生成していく。ウィルスは、流体のように、種の定義をすり抜ける。今日の最も重要なテーマは共生であるが、実は、共生は寄生を認めることである。インターネットの普及は出版産業における編集・販売・流通形態を大きく変えている。ネットの書評情報をメールや掲示板で交換し、オンラインで本を購入する。そこでは新書と既刊書の区別もなくなっている。日本文学は、芥川賞や直木賞といったイベントによって、発展してきたが、イベントはマスコミや広告代理店が作り出した祝祭であり、冷たいメディアの時代にそぐわない。一切の文学賞の効力は失効しつつある。同時に、二十世紀文学にとって最も重要なメディアだった雑誌の役割も変化を迫られている。出版物では、権威ある第三者が作品に対して評価を下す。作品ではなく、雑誌への信頼感が文学を成立させてきたのだが、ネット上では、自分で判断しなければならない。それが駄作だけでなく、盗作の可能性もある。未完成やプレプリントの段階、あるいはアネクド-テのごとく作者不明のまま、原稿がネットワークを通じて流用し、レフェリーのいない世界で、評判になることさえありうる。それどころか、メールだけで評判になるサイバー・ヴォルテールが登場するかもしれない。つまり、ネット社会では、ポストモダン文学者の認識がより具現化され、新しさと古さ、個人と組織、無名と有名、完成と未完成も等価に置かれているのであり、ポスト日本文学はこうした状況から生まれてくるのである。それは「オルタナティブ文学」と呼ぶにふさわしい。
現在、自分史作製用のソフトが何種類か販売されている。ファイルを起動させて、画面の指示に従って項目に答えてゆくと、コンピューターが自分史を完成させてくれる。プログラムを書き、それによってコンピューターに文学作品を書かせることもいずれ可能になる。作家が文学版Deep Blueに敗北する日がこないとは言えない。しかし、かりにそうなったとしても、悲観する必要はない。なぜなら、勝負を競う対決の時代はすでに終わり、交渉によって共生していく時代を迎えているのだから。
かつてあったことは、これからもあり
かつて起こったことは、これからも起こる。
太陽の下、新しいものは何一つない。
見よ、これこそ新しい、と言ってみても
それもまた、永遠の昔からあり
この時代の前にもあった
昔のことに心を留めるものはない。
これから先にあることも
その後の世には誰も心に留めはしない。
(『コヘレトの言葉』一章九─一一節)
Quod fuit,
ipsum est, quod futurum est.
Quod factum est,
ipsum est, quod faciendum est:
nihil sub sole novum.
Si de quadam re dicitur: “ Ecce hoc novum est ”,
iam enim praecessit in saeculis, quae fuerunt ante nos.
Non est priorum memoria,
sed nec eorum quidem, qui postea futuri sunt,
erit recordatio apud eos,
qui futuri sunt in novissimo.
(“Liber Ecclesiastes” I: ix-xi)
〈了〉
参考文献
片桐薫編、『グラムシ・セレクション』、平凡社ライブラリー、二〇〇一年
椎名誠、『さらば国分寺書店のオババ』、新潮文庫、一九九六年
城塚登、『ヘーゲル』、講談社学術文庫、一九九七年
柄谷行人、『探究Ⅱ』、講談社学術文庫、一九九四年
柄谷行人、『日本近代文学の起源』、講談社文芸文庫、二〇〇九年
俵万智、『サラダ記念日』、河出文庫、一九八九年
橋本治、『桃尻語訳枕草子〈上〉』、河出文庫、一九九八年
村上春樹、『アンダーグラウンド』、講談社文庫、一九九九年
村上春樹、『ノルウェイの森〈上〉』、講談社文庫、二〇〇四年
柳美里、『石に泳ぐ魚』、新潮文庫、二〇〇五年
吉永良正、『「複雑系」とは何か』、講談社現代新書、一九九六年
渡部直巳、『不敬文学論序説』。ちくま学芸文庫、二〇〇六年
F・ニーチェ、『ニーチェ全集一〇』、吉沢伝三郎訳、ちくま学芸文庫、一九九三年
『文学界』二〇〇一年二月号、文藝春秋
佐藤清文、「気分と批評─田中康夫の『なんとなく、クリスタル』」、一九九〇年
http://hpcunknown.hp.infoseek.co.jp/unpublished/nc.html