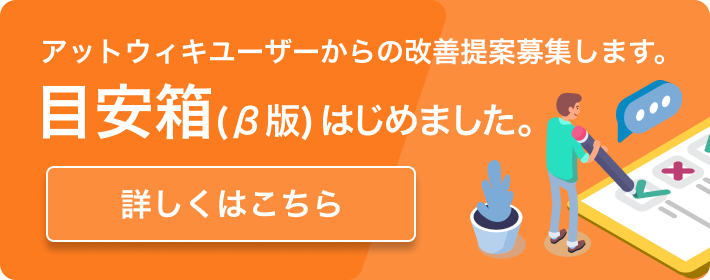戦争と社会階級
Seibun Satow
Mar, 24. 2010
「戦争が戦争を養う」。
フリードリヒ・シラー『ピッコロミーニ』
第1章 The War Dreamer
ブラックウォーターを始めとする民間軍事会社がアフガニスタンやイラクで深く関与していく中、『論座』2007年1月号に赤木智弘の「『丸山真男』をひっぱたきたい――31歳フリーター。希望は、戦争。」が掲載される。このタイトルは、「戦後民主主義なんぞクソッくらえ!」と考え、戦争のアウトソーシングに加わりたい31歳の男性の主張なのかという印象を読者に抱かせる。
しかし、軍務経験もなく、特殊技能も有していない31歳を雇う民間軍事会社はおそらくない。未経験者を一から育てる余裕などそこにはない。
そもそも、31歳では従軍するには年をとりすぎている。自衛隊を例にとってみよう。こうした経歴の31歳が自衛隊に志願するとしたら、道は非常に限られている。一般候補生・任期制自衛官の資格はいずれも18歳以上27歳未満のため、不適格である。予備自衛官補の一般公募であれば、受験資格が18歳以上34歳未満であるので、これならば可能である。ただ、この一般公募の予備自衛官補制度は、広報活動の意味合いが強い。事実、教育訓練期間は3年以内に50日、合計400時間で履修とされている。また、アメリカ軍の場合、公募の兵士の年齢制限は35歳未満であるが、30歳以上の志願者については基準が厳しく設定されている。志願制を採用している国の軍隊はほぼ同様である。一般兵士は過酷な状況でも戦闘できる身体能力を必要とするし、加えて、現代の兵器は高度にハイテク化しており、遅くとも20代半ばくらいから訓練を始めないと、使い物にならない。一民間人を一人前の兵士にするには、31歳はロートルだ。
もっとも、現代社会において戦争は国家間で起こる戦闘だけを指してはないない。この作品発表当時の米国のジョージ・W・ブッシュ政権は「テロとの戦い」を標榜しており、その過激派に参加すれば、戦争に行ける。彼らは年齢制限を設けず、未経験者も歓迎している。あるいは、メキシコやコロンビアなどで展開されている麻薬戦争に、シンジケートの一員として加わるという手もある、これらなら31歳のフリーターでも十分間に合う。
けれども、「『丸山真男』をひっぱたきたい――31歳フリーター。希望は、戦争。」の内容に目を通すと、自分が従軍したいという主張ではなく、格差・貧困問題の解決手段としての戦争の提案だということが明らかになる。
今日、貧富の格差が拡大・硬直化し、いくら働いても抜け出せない貧困状態に陥っていり人たちが少なからず生まれている。しかも、一般の人々は、彼らに対して、自分たちのせいだと言わんばかりで無関心である。この状況を流動化するには、革命では不可能であって、戦争しかない。その上、戦争は人々に平等に苦しみをもたらす。「『丸山真男』をひっぱたきたい」というタイトルは、戦時中の丸山真男のエピソードに由来している。1944年3月、30歳の丸山眞男に召集令状が届き、陸軍二等兵として平壌へと送られる。そこで丸山は中学にも進んでいない一等兵に執拗にいびられる。「社会に出た時期が人間の序列を決める擬似デモクラティックな社会の中で、一方的にイジメ抜かれる私たちにとっての戦争とは、現状をひっくり返して、『丸山眞男』の横っ面をひっぱたける立場にたてるかもしれないという、まさに希望の光なのだ」。
赤木も現段階で日本が戦争に突入することはないと見ており、この作品を問題提起のつもりで発表している。しかし、彼のイメージする戦争は現代ではなく、第二次世界大戦下の日本のある状況である。
第二次世界大戦中に参戦国で、平時であれば出会わなかった人たちの接触があり、それがある種の流動性をもたらしたことは確かである。
御厨貴東京大学教授は、『エリートと教育』において、戦時体制下での人材の「接触効果」が高度経済成長への道をサポートしたと次のように述べている。
戦時動員体制は、一九四三(昭和十八)年に主として中学校以上の勤労動員、そして大学生の学徒動員を決めた。かくて戦前の教育体系が予想もしなかった方向への人材の戦時強制動員が行われた結果、戦後へいくつかの人材育成面での遺産を残すこととなった。もちろん、戦争のため多くの有為な人材が失われたことは言うまでもない。しかし明治の教育体系が解体の危機に陥った時、軍隊や軍需工場の中で、これまでは絶対接することのなかった人間同士の接触がおこった。嫌な思い出もたくさんある反面、戦後すぐの教育への情熱、進学熱はこうした「接触効果」(小池和男)がもたらした。猪木武徳の指摘にある通り、戦後の新制高等学校の進学率の上昇、激しい学歴競争と企業内競争が、経済復興から高度成長へと進む戦後日本をサポートしたことは疑いえないであろう。
赤木の戦争を通じた社会における流動性の確保と痛みの共有は、この接触効果に論拠としている。けれども、接触効果は戦争一般ではなく、ここで指摘されている通り、特殊な状況で生じる。日本は満州事変から15年間も戦争を継続したが、それが起きたのは1943年の勤労動員や学徒出陣などが始まって以降である。明治に基本設計された教育システムが瀕死の状態に陥ったとき、戦時動員体制によって従来であれば出会わなかった人々が接触し、戦後の教育熱につながり、復興をサポートしている。徴兵制に基づく軍による総力戦も押し迫った段階でしか接触効果は期待できない。しかも、クラウゼヴィッツ流の消耗戦が否定された現在であれば、内戦を除けば、教育制度が解体に追いこまれる状態を迎える前に戦争は終結している。
第二次世界大戦は、日本にとって、総力戦である。それを遂行するためには、官僚機構が人・モノ・カネ・情報を総合的に管理統制する必要がある。開戦時の首相が統制派のリーダーの一人で、優秀な軍官僚の東条英機だったことは象徴的である。社会の流動性ではなく、国家全体を一体化させることがその目的である。接触効果は結果として起こっただけで、国家総動員の副産物にすぎない。接触効果による高度経済成長の後押しは確かであるが、社会の流動性の実現という点では、農地解放・財閥解体・公職追放などGHQの革新的な占領政策も忘れてはならない。
念のため、赤木の期待する戦争状態の可能性を内戦および国家間戦争から検討してみよう。主な内戦の原因は分離独立である。しかし、日本国内でこの動きは活発ではない。また、麻薬シンジケートと軍や警察の間の抗争が激化して、内戦状態に陥る場合もある。けれども、麻薬の製造でもしなければ暮らせないほどの貧困地域も日本国内にはない。
国家間戦争であれば、通常兵器だけで、その時点において、海上自衛隊が壊滅状態だという選定になる。これが可能なのは唯一アメリカ軍である。自衛隊はアメリカを仮想敵に想定していないが、現時点で日米開戦の至るシナリオを考えるとしたら、次のようになろう。扇情的な報道に溢れ、国内政治が混乱する中、思いつきと思いこみで判断する無責任で好戦的な政治家が国民の圧倒的な支持を背景に首相に就任し、国内外の反対に耳を貸さず、核武装計画を進める。IAEAの常駐査察官を追放し、アメリカを始めとする国際社会の外交圧力も無視する。とうとう合衆国はこの動きに対して日米安保条約を破棄、在日米軍は撤収する。日本は国際社会から経済制裁を受けるも、外需依存の産業編成と低い食料自給率も省みず、計画を放棄しない。日米の国交が断絶、アメリカを中心とする多国籍軍との間で開戦してしまう。
このようにして始まった戦争もいつかは終わる。しかし、赤木の意見には、戦争自体もそうだが、戦後のイメージが曖昧である。尊い多くの人命と財産が失われることは言うまでもない。少子高齢化の進展する日本が戦争に突入した場合、若年人口の大幅な減少が見込まれ、そのいびつな人口構成では、戦後復興はおぼつかない。戦争で心身に傷を負った人々のケアも欠かせない。現在の日本の債務残高はGDP比で150%を超え、先進国最悪である。戦費を調達する場合、政府は国内の豊かな預金量を当てこんで国債を発行すると考えられる。けれども、あまりに大量で預金が底をつき、吸収できなくなって長期金利が高騰、日本経済は耐えきれず、財政は破綻する。食料・生活必需品・燃料等が不足し、庶民の生活を強烈なインフレが直撃する。交通・生活インフラの復旧も最優先項目の一つであるが、一朝一夕でできるはずもない。また、戦時下では、国内に破壊被害が甚大でなかったとしても、災害・疾病・環境などへの対策が二の次にされる傾向があり、戦後、その影響による相当の被害も予想される。持続可能性のある社会の実現という国家的な目標の達成が著しく後退し、修復不可能な状態に陥る危険性もある。接触効果がこうした状況の飛躍的な改善につながっていくとは考えられないだろう。想像力を少し働かせただけでも、このくらいの光景が目に浮かぶ。
この作品が発表されると、各種のメディア上で賛成反対のいずれの意見が飛び交う。中でも、『論座』は4月号で、7人の識者による批判論文を掲載し、赤木がそれに対して、同誌6月号において、「けっきょく、『自己責任』ですか 続「『丸山眞男』を ひっぱたきたい」「応答」を読んで──」で反論する。「考える時間を得るためには、生活に対する精神的な余裕や、生活のためのお金がなによりも必要不可欠であり、それを十分に得られて初めて『考える』という行為をすることができる。そうした人間が、考えて活動するための『土台』を整備することこそ、私に反論する方々の『責任』ではないだろうか」。
しかし、環境的に余裕がない場合、体系的には難しいが、考えること自体は不可能ではない。マクロシンキングは無理でも、ミクロシンキングはできるはずだろう。この結語は、大戦終結後に戦争責任を免れるためにある種の人々が使った言い訳に似ている。吉本隆明が1956年にそれを批判したのだが、赤木はその前に舞い戻っている。
吉本隆明にとって許しがたかったのは、自分の無知です。(略)戦中世代の人たちは。われわれは知らなかった、教わらなかった、欺されていた、ということができました。しかし、吉本がとったのは、無知にも責任があるという態度です。では、無知に責任があるとするならば、どのように責任をとればよいのか。自分をふくむ世界を、徹底的に認識するほかないのです。
(柄谷行人『倫理21』)
31歳のフリーターが戦争を望んでいるというショッキングなタイトルが話題をふりまいたけれども、社会の流動性の確保と痛みの共有のために戦争を提案するのは暴論でしかない。流動性は時代の変わり目に生じる。19世紀の近代化=産業化というグローバル化は日本に石炭産業を勃興させたが、20世紀の石油によるエネルギー革命のグローバル化は国内の炭鉱に国際競争力を失わせ、閉山に追いこむ。グローバル化とイノベーションが流動性をもたらすとも言える。相対的貧困を絶対的貧困によって解消する問題のすり替えだろう。痛みの共有は、戦争を持ち出すまでもなく、災害時にしばしば見られる。災害直後、被災者の間で相互扶助の意識が芽生え、「困ったときはお互い様」とコミュニティが形成される。しかし、復興が進むにつれ、この精神は薄れていく。また、接触効果は生き残った人の間でのみ働くのであって、死者はそれを感じられない。沖縄では、決戦前に、第一次・第二次防衛召集で17歳から45歳までの男子2万人を二等兵として徴用、その後、中学生の一部も入隊、さらに、沖縄勤労動員礼が公布され、15歳から45歳までのほとんどの男女が動員されている。沖縄戦により、約10万人の県民が犠牲になる。出征した兵士も合わせれば、対戦中の沖縄の犠牲者数は15万人以上であるが、戦前の同県の人口は、最も多かった1937年で60万人弱である。それだけの損害を被りながら、失業率は国内最悪、一人当たりの県民所得も最低であり、しかも日本の領土の2%しかない沖縄に全日米軍の全基地75%も集中している。戦争の傷跡は非常に長く残る。この作品をめぐる議論は感情的なすれ違いも多く、結局、不毛に終わっている。
もっとも、赤木とは別に、デフレ傾向を脱却するには戦争特需しかないという意見も根強い。デフレは平和の時代の産物である。朝鮮特需の夢をもう一度とばかりに、戦争による大量生産・大量消費があれば、デフレを脱却できるというわけだ。しかし、時代が違いすぎる。現代の戦争はいたずらに長引く内戦が主流である。当初は国家間戦争であっても、内戦化するケースも少なくない。当該地域の政治的・経済的制度の基盤まで破壊し、流出した難民が周辺地域に負担となる。相互依存の進んでいる現代の国際社会では、局所的な戦争であっても、グリーバル規模で悪影響を及ぼしかねない。しかも、持続可能な発展という国際的な目標を最も阻害している原因の一つが戦争である。エコロジカルな戦争などありえない。大量生産・大量消費から循環型社会への転換を試行錯誤している最中であり、それを逆戻りさせることは有害である。今日、戦争か経済に好影響を与えるという主張は時代遅れでしかない。政治も経済もエコロジーを考慮しており、戦争では気候変動問題を始めとする環境問題を解決どころか。悪化させる。
こうした手合いに戦争の悲惨さを訴えたところで、聞く耳を持たない。戦争待望論は、結局、国内問題の打開策を外に見出そうとする発想である。しかし、これが夢想でしかないことは、1930年代の日本の歴史を見れば明らかだろう。こんな夢からとうの昔に目が覚めていてもいいころである。
第二章 The War Thinker
国際政治において、国防に翻訳して国家を把握する考え方がかつては優勢である。国家はお互いに潜在的に敵であり、友人などいない。国際協力を表面通り信じているとしたら、実におめでたい。敵の敵が今は味方だけのことであって、食うか食われるかだ。国際関係において諸国の利益はつねに衝突する。他国を排除しなければ、領土や権益といった国益を確保できない。その問題が世界に存在する以上、国際紛争は恒常的に起こるのであって、国家はそれに常に準備しなければ生き残れない。軍事力で優位さを維持するために、他国との相対的な関係から認識する必要がある。いくら国防費が前年の倍に増えたとしても、隣国がそれ以上であるなら、不十分である。国家は常に他国との戦争に備え、一旦始まったならば、それを優位に展開するようにしておかなければならない。このように、戦時から逆算して国家権力の構成要素を捉えるのが伝統的な国際関係論である。
藤原帰一東京大学教授の『国際政治』によると。それは次の六要素である。
|
1.地理 |
領土の大きさ・戦略的位置 |
|
2.人口 |
戦力としての人口 |
|
3.天然資源 |
戦争遂行のための自給能力 |
|
4.経済力 |
経済の規模・自給と持久・工業力 |
|
5.技術力 |
技術革新・兵器の性能・生産力 |
|
6.軍事力 |
規模・予算・破壊力・精密度 |
広大な領土や山岳地帯、密林、海洋などは他国にとって攻めにくく、自国にとって有利である。地理的条件と軍事戦略の関係は地政学としてよく知られている。
人口が多ければ、多くの兵士を戦場に投入でき、それを支える軍需を始めとする関連産業にも必要な人員を確保できる。大規模戦・長期戦になった場合、その差は歴然と現われる。ただし、実際には、人数といった定量条件だけでなく、士気や熟練度など定性条件も考慮しなければならない。
開戦すると、敵国のみならず、その友好国との貿易も停止される可能性がある。戦争を遂行するためには、国内に十分な天然資源を用意していなければならない。
戦争には莫大な戦費が必要である。豊かな国富があれば、それを賄うことができる。産業革命以来、国富の蓄積には工業力の発達は欠かせない。
兵器の性能やその生産力、技術革新力が戦争の結果を左右することは言うまでもない。
潤沢な国防費による大規模な軍隊はどのような戦争にも対応できる。機械化された兵器が主体の戦闘では、その破壊力と精密度が勝利を決定づける。
この六つの条件を総合的に判断して。その国家に最適な体勢を整えることが為政者の責務である。
しかし、現在、国際政治における国益は領土や権益だけではない。経済や環境も重要なである。前者は一方が得をすれば、他方が損をするというゼロサム状況である、それに対し、後者はみんなが得をすることもあれば、損をすることもあるノンゼロサム状況である。ゼロサム状況を絶対視して、国際関係を認識することはできない。経済を優先させるために、領土や権益の問題を一時的に凍結する動きさえある。インドと中国は、経済関係を良好にするように、国境線問題を棚上げにしている。両国の経済成長は目覚しく、そんなときに、ヒマラヤの山奥のことで争うなど無益である。
国防に翻訳する発想はゼロサム状況を前提にしている。先に触れた国防予算・編成・装備の考え方も同様である。他国よりも相対的に多く得る利得を「相対利得(Relative Gain)」と呼ぶ。一方、以前よりも増加させることを目的とした利得が「絶対利得(Absolute Gain)」である。前者は状況をゼロサムから判断し、後者はそれにとらわれない。かりに国防費をGNPの10%内にとどめると政府が決定していても、10%の経済成長があれば、黙っていても前年に比べて増額になる。経済成長に合わせて国防費が増すようにすれば、国家財政を圧迫することもない。戦後の日本の防衛費はこの絶対利得に立脚して組まれている。
戦時にとって有利な条件は、平時においては逆に負担となる。冷戦時代のソ連を例に解説してみよう。ソ連は多くの条件を満たしながら、解体に陥っている。広大な領土と寒冷な気候は、長い防衛線の維持やインフラ整備に困難が伴う。2億を超える人口は教育や医療、福祉など社会保障分野の予算を大きくする。戦時は人々に耐久生活を強いる。そうした不満を募らせないために、社会保障制度を手厚くしなければならない。豊富な天然資源があっても、それを加工できる技術がなければ、宝の持ち腐れである。ソ連の国営企業は資源を民生用にすることが十分にできない。国際的な競争にさらされ、技術革新とコス減に日々努力する西側企業の加工技術に遠く及ばない。軍需関連の重化学工業に傾斜し、民生品の技術革新がなおざりにされ、国際競争力のある製品を生産できず、東側の市場だけで流通するにとどまる。進んだ技術を持つ外資を呼び込もうにも、資本主義を敵視している体制には企業も及び腰となる。国内総生産はいつまで経っても増えず、外貨準備も不足し、思うように経済成長ができない。巨大な軍隊は維持するための巨額な国防費は、わびしい経済成長では、国家財政を圧迫する。結果、ソ連は崩壊する。
また、戦時であっても、これらが有利な条件として働くとは限らない。特に、個々の戦闘では反対の結果が出ることも少なくなく、あくまでこれは一般論である。第二次世界大戦の消耗戦の反省から、孫子が見直されている。クラウゼヴィッツ流の消耗戦がチェスの発想であるとすれば、孫子は囲碁である。少ない碁石で相手より多くの陣地をとれば勝ちとなる。
ノンゼロサム状況だとしても、そこにゼロサム状況を見出してしまうと、国際協力が瓦解する危険性がある。気候変動問題の改善は各国にとってノンゼロサム状況であるが、温室効果ガスの削減となると、経済への影響を考えて、他国よりも想定的に負担を減らしたいと望み、国際会議は常に紛糾する。また、経済状況が悪化すると、「奴らが俺たちの仕事を奪っている」と移民排斥が台頭するが、この論理もゼロサム状況に基づいている。付け加えると、中国が経済発展すると、日本が脅かされるという主張もそうである。国際関係では、ノンゼロサム状況を認識して理論構築をしていくことが世界的な利益につながる。しかし、こうした知的努力をしゃらくさいとゼロサム状況を扇動する独善主義が絶えず登場する。ゼロサム状況から出発する意見が社会で支配的になるとき、それは戦争の前兆である。
第三章 The War Believer
孫子は、戦争を浪費であると説いている。大量の物資・人命が失われ、戦費の重圧、物資・人員の徴発、国土の後輩によって国家経済を疲弊させる。為政者は合理的に考えれば、戦争を選択すべきではない。
しかし、これまで数えきれないほどの戦争が勃発し、今も続いている。
「帝国主義とは、国家の際限なく拡張を強行しようとする無目的な素質である」とするヨゼフ・A・シュンペーターは、『帝国主義と社会階級』において、戦争の原因について次のように述べている。
歴史上の事実を分析することによってわれわれは、第一に、何らはっきりした目標にしばられない「無目的的」な武力による拡張への傾向──すなわち戦争や制服を求める無合理的な非合理的な純粋に木能的な性向──が人間の歴史においてきわめて大きな役割を演ずる、という確かな事実をつきとめた。逆説的にきこえるかもしれないが、非常に多くの戦争──おそらくは大多数の戦争──が適当な「理由」(道徳的観点からというより、考えぬかれた尤もな利益の観点からの) なしに、強行されてきた。言いかえれば、諸国民の精根をつくしたような努力が実に無駄に流れたのである。われわれの分析は、第二に、この戦争を求める必要性ないしは意欲についての説明を与えており、その説明は、単に「衝動」や「本能」に言及するだけで終っているものではない。むしろわれわれは更に一歩進んで、民衆や階級が生きのこるためには武士にならざるをえなかったようなその客観的な生活上の要請の中にその説明を求め、また、遠い昔そのような環境の下で得られた心理的素質と社会的構造とが一度びそれとして確立されると──それの本来の意味と生命保存的機能とがなくなってしまったはるか後においても──いつまでもその力を持ちつづける、という事実の中に説明を求めるのである。われわれの分析は、第三に、このような性向ないし情造の存続を助長する第二次的諸要因が存在しているということを明らかにした。この種の諸要因は二つに分けて考えることができる。まず第一には、支配階級の国内政治上の利害関係が好戦的性向を助長したのであり、第二には、戦争政策によって経済的或いは社会的にそれぞれ個人として利益を受けるような人たちのもつ影響力が一つの役割を果している。これらいずれの要因も、大ていのばあい、政治的表現や心理的動機の上で、いろいろに異った飾りをつけてあらわれるのが常であった。それぞれの帝国主義は細かい点では相互にかなり異なるが、どの帝国主義も少なくとも右にのべたような諸特性だけは共通してもっているのであって、だからこそ第一章で述べたように、それは社会学上単一の現象として取扱われるのである。
経済において、個人的・階級的合理性の追求がしばしば社会的・国家的合理性と矛盾することが少なくない。シュンペーターは戦争の原因としてこの齟齬を見出す。戦争は、戦争は国家や社会にとって決して合理的な選択ではない。しかし、帝国主義国家は戦争を繰り返す。それ自体に合理的な目的はないにもかかわらず、戦争が頻発する理由は大きく二つある。一つは、支配階級が国内政治の失敗を外にそらすためである。もう一つは、戦争を始まると個人として報われる階級が増加しているからである。シュンペーターの独創性はこの第二の原因を導き出した点にある。戦争が厄介なのは、それでしか食っていけない階級を増加させ、次の戦争を誘発してしまうことである。
経済学者のマーク・ブローグは、『ケインズ以前の100大経済学者』の中で、『帝国主義と社会階級』を「現在でも読む価値のある作品」と賞賛している。残念ながら、日本では、『経済発展の理論』や『景気循環論』、『資本主義・民主主義・社会主義』、『経済分析の歴史』などは読まれているものの、この隠れた名作が振り返られることは稀である。しかし、シュンペペーターの政治学領域の考察は非常に示唆に富んでいる.
シュンペーターが「個人として」としている点に注意しなければならない。この社会階級は国防費ではなく、戦費にかかわっている。それは軍需産業の関係者ではない。彼らは自分たちが開発・製造している兵器が戦争を抑止していると軍から金を引き出したいと思っている。戦果を挙げると、瞬間的に受注を増えるだろうが、戦時になれば、経営・研究・開発に軍が干渉してくる危険性がある。差し迫った戦争の危機がなくなったおかげで、経済成長を遂げ、その余裕から装備の近代化を計画する新興国に自社製品を売却する方が実入りがいい。また、多くの軍人にしても、同様である。志願兵であれば、愛国心もあり、いざというときがきたなら、その覚悟もしている。けれども、そうなれば、自分や部下が死ぬ可能性は高くなる。それよりも、自分たちの存在が外的脅威から祖国を守っていると国内に認知させて誇りとした方がよい。軍人も家族がある。できれば、時期がきて、昇進し、給料も上がるなら、都合がいい。学費・資格のために、志願している若者も少なくない。いずれも軍隊で食っているのであって、戦争で食っているわけではない。
このシュンペーターの分析に当てはまる一例がフランス第4共和政である。大戦後、イギリスが次々に植民地を放棄していくのに対し、フランスは固執する。1947年から58年まで続いたこの共和国はつねに戦時下である。46年から54年までインドシナ戦争を行い、それが終わると、アルジェリア戦争に突入し、第5共和政が62年になってようやく終決させる。その間も、56年から57年にスエズ動乱を引き起こしている。同時代のヨーロッパでこれだけ戦争に明け暮れた国家はない。戦争でしか食っていけない人たちを多く生み出し、彼らが第5共和政成立前後に無数のテロ・クーデターを計画・実行する。
フレデリック・フォーサイスの『ジャッカルの日』は、この辺りの事情をよく描いている。これは、シャルル・ド・ゴール大統領のアルジェリア政策に反対する過激派組織OASがプロの殺し屋「ジャッカル」を雇い、彼の暗殺を企てるという傑作小説である。その作戦を立案したマルク・ロダン大佐の半生は、戦争でしか食えない人がどのようにして生まれるかをよく物語っている。
マルク・ロダンは貧しい靴職人の家に生まれたが、ハイティーンのときに、フランスがナチス・ドイツに占領されたため、漁船でドーバー海峡を渡り、「ロレーヌの十字架」に一兵卒として入隊する。北アフリカ戦線やノルマンジー上陸作戦、パリ解放作戦に参加し、彼の教育暦では困難な少尉にまで昇進している。大戦が終わり、民間に戻るか、それとも軍に残るかの選択を迫られた際、後者を選ぶ。10代後半から20代前半の時期に、教育や職業訓練を受ける機会が奪われた彼には、父から仕込まれた靴職人の技術しかなく、民生復帰には難しい。
ドイツと比べて、フランスの靴職人の地位は高くない。ドイツにおいて靴は実用性が重視され、早い時期から、リハビリなどとも結びついていたのに対し、フランスでは、ソフトなタイプが好まれているように、靴のデザイン性が重視されて、職人はそれを具現化することが求められる。今日でも、フランスは、そのコンセプトが強いため、ドイツを始めとする諸国と足の計測方法が異なっている。ちょっとした記述であっても、論理的に相対化することで本質が顕在化するものである。
軍に残ったものの、ロダンは叩き上げの将校の悲哀を味わうことになる。サン・シーリャンが彼を追い抜き、次々と昇進していく。サン・シール陸軍士官学校は幹部養成を目的としており、戦略や戦術、作戦を体系的に理論として学習させる。全体を知らなければならないので、工兵や砲兵など陸軍に必要な各技術を一通り教育する。現場上がりの少尉でも、陣地をどこに置くかくらいは判断できるが、大局的な観点から作戦を立てることはなかなかできない。ロダンの失意は怨念にまで成長する。残された道はただ一つしかない。戦場に戻ることである。
第一次世界大戦後、政党政治への不信感を抱き、強い指導者に率いられた全体主義体制を希求したのはアドルフ・ヒトラーを始めとした復員軍人である。軍隊は厳然とした階級組織である。上意下達で民主的ではない。幅員軍人の処遇は戦後社会における民主主義の浸透を左右する。
しかも、強固なヒエラルキーのため、軍人たちの間では昇進への願望が一般の公務員よりも強い。東西冷戦が終結した後も米軍が全世界に基地を持ち、展開しているのは、世界の警察を自認しているからではない。基地を閉鎖してしまえば、将校を含めた昇進を閉ざされた軍人の不満が蓄積し、現役武官だけではなく、在郷軍人会も政治への圧力を強め、政情を不安定化させる。アメリカは軍のリストラになかなか手をつけられない。米軍の基地問題は軍の官僚主義に要因の一つがある。外交問題ではない。政軍関係問題である。
1945年9月2日、ベトナム民主共和国が独立を宣言する。ところが、宗主国のフランスはそれを認めず、大戦以前の状態への復帰を画策する。46年12月、両者の間で戦争が勃発する。ロダンは、働きかけの甲斐あって、この植民地軍の空挺部隊に転属され、そこで居場所を見つける。「彼と同じことばをはなし、同じ考え方をする兵士たちがいた」。彼らは戦争でしか食っていけない。しかるべき時期に教育や職業訓練の機会を奪われ、しかも叩き上げであるため、戦闘で武勲を挙げない限り、軍でも昇進は望めない。シラーズは戦争がなくても、頃合があれば階級が上がっていくため、軍隊で食っていける。戦闘に次ぐ戦闘の8年間で、血と汗を流したロダンは、戦争が終結したとき、少佐になっている。
けれども、本国に戻ってからの一年間で、以前から心に巣食っていた怨念を憎悪に転化させる。ブルジョアが安穏とした生活をすごせるのは、遠く離れた戦地で兵士たち勝ちと汗を流しているからだと固く信じていたのに、そんなことに気をとめているものなどいない。それどころか、左翼知識人たちは、情報収集のためと捕虜に拷問をかけること非人道的であると軍を批難する有様である。本国政府と国民の支援が十分でさえあったら、わが軍はベトミンを蹴散らしていたのであって、インドシナの放棄は死んでいった兵士たちへの裏切りである。政治家と共産主義者に牛耳られた今のフランスを解放するには、軍人が決起するしかない。裏切り者と口舌の徒は軍にはいないからである。
日本にいると、労働者階級が共産主義者に乗っとられているというロダンの考えがわかりにくい。戦後の日本の議会勢力は複数政党制の参戦国の中で例外である。鍵になるのは共産党である。議会勢力として共産党が存在しているか否かで大きく分かれる。アメリカやイギリス、西ドイツなどでは共産党は議会勢力ではない。労働者階級を代表するのは社会民主主義的な政策をとり入れた政党である。一方、フランスやイタリアにおいては共産党は議会勢力として強力で、保守勢力と拮抗している。フランスの戦後初の総選挙で第一党となったのは共産党である。戦後長期に亘って、同党は有権者の20~25%の支持を受けている。労働者階級を代表するのは、言うまでもなく、共産党である。社会党は、第三党として、保守政党と共産党の挟み撃ちにされ、リベラルなホワイトカラーの支持をとりつけて一定勢力を保持し、連立政権に参加する。
ところが、日本では議会勢力として共産党が存在するものの、社会党の方が優勢で、なおかつ労働者階級の代表の座を両者が奪い合っている。地方レベルでは、京都のように、共産党の法が強い地域もあるが、これはあくまで国政レベルの話である。社会党は自民党と共産党に挟まれているけれども、総評をバックに当選してくる議員も多く、なまじ第二党であるため、市民政党への脱皮も難しい。しかも、自民党は、その複雑な形成過程に伴い、社会民主主義的な国内政策を採用しているので、社会党は違いを明確にしにくい。結果、社会党は護憲平和にそのアイデンティティを見出すほかない。このように、日本とフランスとでは、共産主義者と労働者階級をめぐる状況が違う。
戦後、フランスの知識人は左翼の立場をとり、「モスクワの長女(La fille aînée de Moscou-)」こと仏共産党に好意的である。しかし、彼らが鉄のカーテンの向こう側の実態を知らなかったわけではない。彼らにとって危険なのは共産主義以上にファシズムである。ヴィシー政権はナチスに協力したのに、戦後、東西冷戦の開始と共に、その責任追及がうやむやになっている。当時の政府は侵略軍に抵抗するどころか、それを利用して国内の自由主義や民主主義、共和主義の一掃を図り、労働運動・言論活動を弾圧している。社会党主流派を含む第三共和政の政治家たちは積極的・消極的にフィリップ・ペタン将軍を容認している。積極的に闘争を挑み続けたのが共産党である。解放後、その政権の要人や対独協力者は処罰されたり、追放されたりしたが、冷戦へのタイオウや経済復興のために、多くが復帰を許されている。知識人たちはそれを憂い共産党を支持する田市制を示している・この状況は日本も似ている。知識人にすれば、アメリカも信用できない。マッカーシズムは反共に名を借りたファシズムであるし、反共でありさえすれば、ワシントンはイベリア半島のファシスト体制を支援している。知識人にとって共産党は国内にうごめくファシズムの中和剤である。
1944年9月、パリ解放直後、シャルル・ド・ゴールを主席とする臨時政府が成立する。45年10月に発足した憲法制定国民会議でも将軍は引き続き首班に指名され、11月、共産党・人民共和派・社会党による反ファッショ連合政府は結成される。ところが、翌年の1月、ド・ゴールは、議会権限の強い憲法草案をめぐって他勢力とぶつかり、辞職する。
ド・ゴール将軍は政党政治に批判的で、超然主義の姿勢をとっている。しかし、それはいささか時代離れしている。確かに、19世紀、民主主義が衆愚政治と同義語として使われている。合衆国第4代大統領にして政治思想家のジェイムズ・マディソンは、政党政治を特定集団の利益を優先する多数派の横暴として厳しく斥けている。20世紀に入ると、一党独裁を絶対視する政治体制を別にすれば、政党政治は民主的な制度として広く認知される。もっとも、ド・ゴールも柔軟な政治家であり、政党政治に不満を抱きながらも、後に、新共和国連合(UNR)を結成している。
1947年1月、第4共和政がスタートするものの、先の三派の対立と小党乱立、冷戦の激化によって短命政権が続く。フランス共産党は何度か第一党になって政権に参加していたが、48年以降、下野する。人民共和派(MRP)はカトリック系の政党として出発したけれども、右傾化して党勢が衰退している。それに代わって、ゴーリストが進出していく。社会党は彼らの挟み撃ちにあいながら、勢力を維持しようと懸命に励む。戦争はこの不安定な国内政治の産物である。
ロダンの考えは手段と目的を入れ替えている。戦争は手段であって、目的ではない。戦争の勝敗は、戦闘の勝ち負けではなく、政治的に決定される。スエズ動乱がその典型例である。1956年、ガマル・アブデル・ナセル大統領がスエズ運河の国営化を発表すると、英仏とイスラエルが軍事攻撃し、エジプト軍は壊滅寸前に追いこまれる。しかし、米ソがこの三国を牽制し、国連も介入、連合軍は撤退する。エジプトは軍事的には完敗だったが、政治的には大勝利を手にする。他方、フランスは軍事的に勝ったけれども、この戦争を通じて人命を失い、金を無駄遣いし、国際的な威信を低下させるという政治的な大敗北を喫する。戦争の勝敗が政治的に決まるとすれば、遂行には民の支持が不可欠であって、それをなくしたとき、継続は不可能である。また、個々の戦闘自体が目的ではない、ある戦いで負けた場合、それをとり戻そうとすると深みにはまってしまうため、避けなければならない。
ロダンの遠近法的倒錯は自分のアイデンティティを戦場に見出していることから生じる。孫子は「百戦百勝は、善の膳なる者には非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは、善の膳なる者なり」と言っている。しかし、ロダンは戦争でしか食っていけない。孫子の教えは彼にとって存在の否定につながってしまう。彼にとって戦争の勝敗が政治的に決まるなどあってはならないことである。戦闘の勝敗が戦争のすべてである。
ロダンは、1956年春、アルジェリアへ向かう。彼はそこでFLNおよびALNと野戦や都市ゲリラとのとの戦いに明け暮れる。この強敵を打ち破るには本国からより多くの支援が絶対必要である。アルジェリアはフランスであり、そのためには、本国がいかなる犠牲を払うのも当然である。「過激派のほとんどがそうであるように、ロダンもまた、自己の信念がすべてで、現実を冷静にみつめる目を欠いていた。増大する戦費、その負担に耐えかねているフランス経済、兵士の士気の低下といった冷徹な事実も、彼の目から見れば些事にすぎなかった」。
一日約300万フランの戦費はフランスの経済・財政を破綻に追いこみ、社会危機を招く。1958年6月、国内の反戦気運に憤激した現地四将軍が中心となってアルジェリア駐留軍が反乱を起こし、コルシカ島を占拠、その鎮圧に向かった部隊まで同調、パリ進撃の構えまで見せる。瀕死の第4共和政は、その収拾のため、ド・ゴール将軍を政界に呼び戻し、国民議会は彼に6カ月間の全権委譲を承認、憲法改正を委ねる。ド・ゴール首相は、9月、大統領に強力な権限を与えた新憲法を起草、10月、国民投票で第5共和政を樹立する。12月、初代大統領に選ばれ、翌年1月8日に就任している。
それは、ロダンのような狂信者、すなわちとルー・ビリーバーにとって、待ちかねた瞬間である。軍人がフランスを統治する。すべての元凶である共産主義者は追放され、すぐに騒ぎ出す労働組合は屈服し、あの小うるさいジャン=ポール・サルトルは反逆罪に問われて銃殺刑に処せられる。アルジェリア同胞と駐留軍に対して祖国からの温かい支援の手が差し伸べられる。これで万事うまくいく。ベン・ベラに思い知らせてやるのだ。
「フランスのアルジェリア」と言ってエリゼ宮に入ったド・ゴールであったが、決して愚かな政治家ではない。したたかでしなやかなリアリストである。アルジェリア民族解放戦線と休戦交渉を進め、60年9月にアルジェリアの民族自決の支持を発表し、61年の国民投票の過半数もそれを支持する。62年3月エヴィアン協定によって戦争の終決とアルジェリアの独立が承認される。
しかし、右翼軍人たちはこれでは納まらない。アルジェリア各地で独立派へのテロを実行したのみならず、クーデターを計画する。中でも、最も過激な軍人や居留民、政治家たちは、1961年1月、マドリードで、「アルジェリアはフランス。これまでもこれからも」(L’Algérie est française et le restera)」を掲げて「秘密軍事組織(OAS: Organisation de l'armée secrète)」を結成する。ロダンも加わったこの極右組織は、彼らが「ユダ」と見なすフランスの最高権力者の暗殺を何度も試みる。しかし、度重なるフランス官憲の厳しく執拗な追求によって組織は先細っていく。ロダンの「ジャッカル」計画は、消滅間際のOASにとって、最後の賭けである。
マルク・ロダンはこうした社会的・時代的背景の下で戦争でしか生きられないウォー・ビリーバーになっている。しかし、彼のようなタイプは決して珍しくはない。アルカイダを始めとする過激派に参加した元アラブ・アフガンズもそうしたウォー・ビリーバーの一例である。
1979年、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻すると、イスラム教徒を共産主義者の脅威から守るという大儀を掲げてアラブ地域から義勇兵が参戦する。彼らは「アラブ・アフガンズ」あるいは「アフガン・アラブ」と総称される。オサマ・ビンラディンのような裕福で教育のある青年は珍しく、大部分は下層階級の出身である。失うものがあったら、いかに義憤にかられようと戦場には駆けつけられない。義勇兵は西側の提供する武器を手に、共産勢力と血みどろになって戦う。1989年、ソ連軍が完全に撤退し、彼らの大半も帰国する。「よくぞやってくれた!」と人々から熱烈な歓迎され、感涙に咽びながら、ねぎらいの言葉が発せられるだろうと期待して、故国の土を踏む。しかし、彼らが直面したのは無関心であり、ヒンズークシ山脈で戦闘に明け暮れていた間に、すっかり変わった社会である。子供たちはファミコンで遊び、若者はCDで音楽を楽しみ、CNNが世界のニュースを衛星を使って24時間放映している。一方で、政治腐敗と貧富の格差は相変わらず放置されたままである。
元々貧しい上に、20代の間に職業訓練も学問研究の機会を逃し、身につけたものといえば、戦闘の技術だけとあっては、民生復帰することは困難である。しかも、80年代はデジタル技術が徐々に社会に浸透しつつあった時期である。スティンガー・ミサイルを撃てるとしても、一般社会では特技に入らない。また、その経験を生かそうにも、これだけ特定のイデオロギーに染まった人物を国軍が受け入れることは難しい。近代において、軍は政治的中立の立場をとらなければならない。部隊内で若い兵士に自分の体験を交えつつ、過激な思想を吹きこまれたらたまったものではない。反乱やクーデター、革命といった軽挙妄動の種ともなりかねない。彼らには居場所がない。鬱屈とした怨念が心の中にたまっていく。
1990年、突如、イラクがクウェートに軍を進める。翌年、イラクに対して、多国籍軍が戦闘を開始して、湾岸戦争が勃発する。ソ連はこの件に関して安保理で拒否権を行使せず、アメリカに軍事的に対抗する立場を放棄している。このとき、事実上、冷戦が終結する。もはやアメリカと軍事的に対抗しようとする国家は存在しない。戦争は3ヶ月もしないうちに決着がつく。
しかし、戦争が終わっても、サウジアラビアの米軍駐留が続く。中東では、イスラエルを支援しているため、従前より反米感情が強いが、この継続は一般のサウジの国民の反発を招く。不満と不信に満ち溢れた元イスラム戦士には、共産主義者をアフガニスタンから追い払ったと思っていたら、今度は、こともあろうに、異教徒がメッカとメディナの聖地を抱えるサウジアラビアに居座り続けている。イスラムを守るために、奴らを追い出さなくてはならない。「アメリカに死を!」と立ち上がったとき、彼らは再び居場所を見つける。
ウォー・ビリーバーは戦争に対するアイロニーもシニシズムもない。そこはアイデンティティ確認の場である。ウォー・ドリーマーと違って、戦争は社会の流動性確保でも経済成長の手段ではない。戦争自体に自分の存在意義がある。正しいことをしていると信じている以上、なかなか彼らを止められない。
90年代、アラブ・アフガンズと各国で活動を続けてきたイスラム過激派が連携し、世界各地でのテロを実行する。貧しいものにとって、実は、テロ組織を創設することは難しい。先立つものがないからだ。むしろ、戦争に義勇兵として参加する方がたやすい。戦争は、概して、いずれの勢力にもバックアップしている国家がいるので、その辺の心配が要らない。食うや食わずでは継続してテロをしている余裕などない。比較的裕福で、高学歴のものたちが急進思想にかぶれて、テロ組織を結成することが多い。高い教育も受け、豊かであるなら、社会的な成功は十分可能である。けれども、社会変革は思っている以上に時間がかかり、待ちきれない。物事がそんなに簡単に割り切れるものではないのだが、とにかく答えが欲しい。オサマ・ビンラディンは過激派の幹部とアラブ・アフガンズの両面を兼ね備えている。彼が世界的なイスラム主義のテロ・ネットワークの中心人物となるのも必然的だったろう。
急進派たちは、世界各地を追われ、あるいは自ら進んで、アフガニスタンに集結する。国際社会の関心はもうそこに注がれていない。彼らとパキスタンに支援されたタリバンは、96年にカブールを制圧し、その後、短期間のうちに国土の9割以上を実効支配する。
タリバンの幹部は貧しい家庭の出身である。長引く戦争のため、満足に教育を受けられなかったり、何とか勉強を続けたいと学費が無料で食事も提供してくれる神学校に通っていたりするものがほとんどである。日本で言うと、統制派に対抗した皇道派の青年将校というところだ。リーダーのムハンマド・オマルは正規の教育経験は数年しかない。アフマド・シャー・マスードのような裕福で高い教育を受けた北部同盟の指導者とは違って、アラブ・アフガンズに近い。
2001年9月11日、同時多発テロが起きる、アメリカは、実行したとされるアルカイダのメンバーの引渡しを要求するが、タリバンは拒否する。10月、アメリカ軍を主体とする有志連合がアフガニスタンで戦闘を展開、12月、タリバン政権は崩壊する。2003年3月、調子に乗って、アメリカとその仲間たちはイラクにも侵攻、4月、バグダッドは歓楽する。しかし、その後、両国供には内戦状態と化し、国内各派だけでなく、国外からテロリストや義勇兵も流入する。そうしている内に、アフガニスタンではタリバンが息を吹き返し、支配地域を徐々に広げていく。バラク・オバマ米大統領は、治安の改善傾向が見えてきたイラクから2011年12月までに駐留軍を完全撤退すると表明しているが、アフガンに関しては出口戦略を明らかにしていない。それどころか、隣国のパキスタンにも戦線が拡大している。この間、新たなウォー・ビリーバーが続々と生まれている。
戦後復興の際に、元兵士の生活設計をどうするかは重要な課題である。軍や警察に入れない場合、学校教育・職業訓練などの支援が必要である。何も身につけさせず、社会に放り出しては、彼らは再び銃を手にする恐れがある。ソ連軍撤退後のアフガニスタンの混乱の一因は、元兵士の処遇をほとんど考慮していなかったことである。
ウォー・ビリーバーの生まれるメカニズムは、ワーキングプアのそれと似ている部分もある。バブル経済崩壊後、多くの企業が新卒採用の枠を絞り、大量の非正規雇用者が出現する。彼らは不安定で低賃金の仕事に追われ、専門的な技能や資格を習得する機会を奪われる。働いても、働いても、貧困から抜け出せない。彼らはロダンやアラブ・アフガンズと重なる。
しかし、戦争は別のタイプのウォー・ビリーバーも発生させる。ある程度の教育や職業技能を有しながら、戦争でしかアイデンティティを見出せなくなってしまう兵士も少なからずいる。自分が報われるのは戦場だけだと感じている。イラク戦争を舞台にした映画『ハート・ロッカー』のウィリアム・ジェームズ1等軍曹は、祖国での家庭生活になじめず、戦場に舞い戻っている。また、民間軍事会社の社員にもこうしたタイプが多い。彼らは戦争一般が正しいとは考えていない。ただ、自身がかかわっていることには意義があり、危険な戦場で任務を果たせるのは自分だけだという使命感を抱いている。戦場には彼らの居場所がある。
戦争はウォー・ビリーバーという社会階級をもたらし、固定化する危険性がある。ウォー・ビリーバーに関して、「階層(Strata)」ではなく、「階級(Class)」を用いるのは。彼らが「同じことばをはなし、同じ考え方をする」という所属意識を持っているからである。赤木のようなウォー・ドリーマーは、今の状況から何としても脱出したいために戦争を待望している。一方、ウォー・ビリーバーは戦争が終わって欲しいと思っていない。自分を生み出したその場を神聖視している。戦争にこそ自分自身がある。しかし、それによってまた新たなウォー・ビリーバーが生まれる。戦争はこうして自己増殖する。それを待望するよりも、真摯で建設的な議論をする方がはるかに有意義である。
現下の多様な危険要因に対応するためには、政策と制度をさらに強化し包括的なものとする必要がある。国家は安全保障に引き続き一義的な責任を有するが、安全保障の課題が一層複雑化し、多様な関係主体が新たな役割を担おうとする中で、われわれはそのパラダイムを再考する必要があろう。安全保障の焦点は国家から人々の安全保障へ、すなわち「人間の安全保障」へ拡大されなくてはならない。
(人間の安全保障委員会事務局『人間の安全保障委員会:最終報告書要旨』)
〈了〉
参考文献
赤木智弘、『若者を見殺しにする国―私を戦争に向かわせるものは何か』、双風舎、2007年
浅野裕一、『「孫子」を読む』、講談社現代新書、1993年
天川晃他、『日本政治史─20世紀の日本政治』、往相大学教育振興会、2003年
五百旗頭真、『米国の日本占領政策』、中央公論社、1985年
柄谷行人、『倫理21』、平凡社、2000年
高橋和夫、『改訂版国際政治─九月十一日後の世界』、放送大学教育振興会、2004年
長谷川慶太郎、『2010年 長谷川慶太郎の大局を読む』、フォレスト出版、2009年
藤原帰一、『国際政治』、放送大学教育振興会、2007年
シュンペーター、『帝国主義と社会階級』、都留重人訳、岩波書店、1956年
フレデリック・フォーサイス、『ジャッカルの日』、篠原慎一訳、角川文庫、1979年
マーク・ブローグ、『ケインズ以前の100大経済学者』、中矢俊博訳、同文館、1989年
ポール・ポースト、『戦争の経済学』、山形浩生訳、バジリコ、2007年
『世界の名著40』、中興バックス、1980年
DVD『エンカルタ総合大百科2009』、マイクロソフト社、2009年
人間の安全保障委員会
http://www.humansecurity-chs.org/japanese/index.html
防衛省・自衛隊
United States Department of Defense
佐藤清文、『経済と文学─戦後経済と日本文学』、2009年
http://hpcunknown.hp.infoseek.co.jp/unpublished/el.html