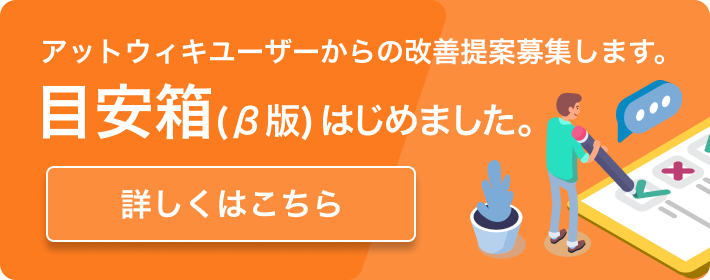ジャーナリストの文学
─ノンフィクション
Seibun Satow
Jul. 31. 2009
'Tis strange --but true; for truth is always strange; Stranger than fiction".
George Gordon, Lord Byron ”Don Juan”
1 雑誌とノンフィクション
20世紀を目前にした1890年代、アメリカの雑誌の世界に革命が起きる。それを担ったのは、後に「ノンフィクション(Non-fiction)」と呼ばれる散文ジャンルである。
従来、雑誌は論文や小説、詩などの投稿原稿が編集部の方針に沿って取捨選択され、誌面構成されている。そこには、ハリエット・ビーチャー・ストウ(Harriet Beecher Stowe)やラルフ・ウォルド・エマーソン(Ralph Waldo Emerson)、ヘンリー・ワーズワーズ・ロングフェロー(Henry Wadsworth Longfellow)などの味わい深い思索的な作品が並ぶ。東部の裕福な教養豊かな有望家・知識人による定期購読料を経営基盤としていたため、高額で、発行部数も少ない。『ハーパーズ・ニュー-マンスリー・マガジン(Harper's New Monthly Magazine)』、(1850年創刊)や『アトランティック・マンスリー(The Atlantic Monthly)』(1857年創刊)、『スクリブナーズ・マガジン(Scribner's Magazine)』(1887年創刊)などがその代表である。なお、『ハーパーズ・ニュー-マンスリー・マガジン』は『ハーパーズ・マガジン(Harper's Magazine)』、『アトランティック・マンスリー』は『アトランティック(The Atlantic)』に改称し、現在も発行されている。
ところが、1890年頃、権威ある高級誌を発行する出版社とは無関係のインディーズ誌が新たなビジネス・モデルを展開し始める。発行人たちは、シリアルや炭酸飲料など全国展開を視野に入れる企業から広告収入を集めて、価格を下げ、ニュース・スタンドで不特定多数の読者に販売するという方式を採用する。『マックリュアーズ・マガジン(McClure's Magazine)』(1893年創刊)や『レディーズ・ホーム・ジャーナル(Ladies' Home Journal)』(1883年創刊)、『サタデー・イブニング・ポスト(The Saturday Evening Post)』(1821年創刊)、『コスモポリタン(The Cosmopolitan)』(1886年創刊)などがこのニュー・タイプに含まれる。なお、『マックリュアーズ』以外は今も発行されている。中でも、サイラス・H・K・カーティスの創業した『レディーズ・ホーム・ジャーナル』は、19世紀としては驚異的な発行100万部を達成、1897年には『サタデー・イブニング・ポスト』を1000ドルで買収するなど雑誌がもはや金持ち相手の道楽産業ではないことを世間に知らしめる。
この三文雑誌の読者は学識の高い教養豊かなではエリート層ではない。一般庶民である。当時、急増する都市の人口を背景に、新聞や雑誌の出版ブームが起きている。教育がない人にも読めるように、語彙も少なく、やさしい文体で記され、内容も具体的で身近な実感できる話題でなければならない。その頃のアメリカでは、政府は企業活動に介入すべきではないという信念が強くあり、そのため、絶望的に貧富の格差は拡大し、全米中に不正が横行する。「このままでいいのか?」と全米各地で社会改良を訴える「進歩主義運動(Progressivism Movement)」が勃興する。雑誌の発行人たちは、渦巻く不正に対する憤りから社会改良の機運が高まっているのを感じとり、これを前面に出せば、売れると思いつく。
従前の雑誌は、知識人による読者への啓蒙という傾向がある。読者にあわせるのではなく、自分の考えを主張している。他方、新しいタイプでは、主体は読者の側にある。編集部は読者の求めていることを推測して記事にし、それを読み、怒りや憤りとして共感する。雑誌も市場経済の時代に突入したというわけだ。
それにあわせて、編集部の様相も大きく変わる。われわれの追いかける相手は巨大な組織だ。組織的な問題には組織で立ち向かう方が適切であり、チーム・ワークを活用すべきである。編集長の権限が大幅に強化され、彼の指揮の下、編集部は読者の関心を見越した企画を積極的に発案し、それを階層化・専門化された効率性の高い取材・編集体制で実現する。これほど手間暇をかければ金もかかるが、なあに、それ以上に売れれば問題はない。大儲けするには、ある程度の投資は不可欠だ。公的機関の発表だけに依存せず、独自の調査・取材を通じて、すなわち足と金を使い、事件や出来事の真相、政財界の実態、各種の社会問題を詳細に追求したレポートを誌上に発表する。これは後に「調査報道(Investigative Journalism)」と呼ばれ、ジャーナリストの真の仕事とさえ見られている。しかし、実は、それは極めて商業主義的な動機から生み出され、東部の教養人には、まったくもって低級にしか思われていない。
発行人の思惑とは別に、その雑誌で活動した作家やジャーナリストたちは世間で横行する不正や腐敗、強欲への義憤にかられ、ペンを通じて社会改良の必要性を真剣に訴えている。リンカーン・ステッフェンズ(Lincoln Steffens)は「都市の恥(Shame of the Cities)」(1904)で政界の腐敗を糾弾し、アイダ・M・ターベル(Ida M. Tarbell)は「スタンダード石油会社の歴史(The History of the Standard Oil Company)」(1904) で石油カルテルの不正を暴露、フランク・ノリス(Frank Norris)は「蛸(The Octopus)」(1904)で小麦農民による横暴な鉄道会社への抵抗を描き、エドウィン・マーカム(Edwin Markham)は「囚われの子供たち(Children in Bondage)」(1914)で児童労働の実態を暴く。もちろん、これだけではない。読者は、何てこった、アメリカにはこんな社会問題に溢れているのかと驚き、呆れ、怒る。
1906 年,セオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)合衆国大統領が政財界の腐敗を暴き立てる彼らを「マックレーカーズ(Muckrakers)」と揶揄する。それはジョン・バニヤン(John Bunyan)の寓意物語『天路歴程(The Pilgrim's Progress)』に登場する人物で,肥やしばかりを仰き続けて天上の神の恩寵に気づかぬ「肥やし熊手を持った男(The man with a muckrake)」に由来し、下ばかり見て、あら捜しをする連中という意味である。
ルーズベルトは社会改革に後ろ向きだったわけではない。むしろ、公共の利益のために政府は積極的に関与する「スクエア・ディール(The Square Deal)」とうスローガンの下、改良主義を唱え、有権者からの期待も極めて高い政治家である。ハーバード大卒のエリートで、史上最年少の42歳と322日で大統領に就任し、「テディ・ベア(Teddy Bear)」と親しまれている。「棍棒外交(Big Stick Diplomacy)」をモットーに、国益重視の好戦的な反面、自国とは直接的に利害が絡まない場合には、各国の調整に務めてもいる。1906年、日露戦争後のポーツマス条約に功績があったとしてノーベル平和賞を受賞している。彼は、アメリカの歴史において、初めて自動車に乗った大統領でもあり、初めて潜水艦に搭乗した大統領でもあり、初めてノーベル賞に輝いた大統領である。
実際、当初はこの第26代大統領もマックレーカーズに好意的だったが、次第に彼らに生地の改善を望むようになる。1906年、『コスモポリタン』2月号にデヴィッド・グラハム(David Graham)による「上院の裏切り(The Treason of the Senate)」なる記事を目にした大統領は、3月17日、ワシントンのナショナル・グリッドアイアン・クラブ(National Gridiron-Club )の夕食会で45分間ほどオフレコ講演をし、この手のジャーナリズムを激しく批判している。これが報道関係者の間で話題となったため、彼は、同年4月14日、連邦の下院のビル定礎式の記念講演として醜聞あばきを「マックレーカーズ」と厳しく批判し、翌日、『ニューヨーク・トリビューン(The New York Tribune)』他各紙がそれを大々的にとりあげ、その名称が世間に広まっている。
しかし、1906年、その偉大な大統領もショックを受けるマックレーカーズによる作品が発表される。それがアップトン・シンクレア(Upton Sinclair)の「ジャングル(The Jungle)」である。この小説は社会に衝撃を与え、アメリカの歴史を変える。
舞台はシカゴの食肉工場で、労働者の多くは後発移民のリトアニア人である。その労働環境たるや、反吐をもよおすほど不潔だ。労働者が肉を煮る大鍋に落ちたのに、そのまま処理され、人肉が市場に出回ってしまった、腐っているとクレームがついて回収されたハムやソーセージに薬品を注入して再出荷した、倉庫内の製品の上にネズミの糞が大量に溜まっていたなどの記述に溢れている。
これは、先に挙げた作品とは違い、ノンフィクションではないが、丹念な調査に基づいており、決して誇張やでまかせが書かれているわけではない。この攻撃的自然主義文学の代表作を通じて、シンクレアは、このような労働環境で働かざるを得ない移民に同情を寄せ、労働者の待遇改善を訴えている。彼とすれば、フリードリヒ・エンゲルス(Friedrich Engels)ばりの「アメリカにおける労働者階級の状態」を書いたという思いである。
「ジャングル」を読んだアメリカの人々は驚き、こんなものを食べさせられていたのかと怒りを爆発させ、食肉産業と当局へ抗議や非難が殺到する。1906年、怒り狂った大統領と世論に押された議会は、慌てて、食肉検査法と純粋薬品製造法を成立させる。前者は精肉業者への衛生規制ならびに精肉工場への連邦政府による検査の義務付けの法律であり、後者は粗悪および健康被害のある食品と薬品の製造・輸送・販売の禁止を定めている。これは「ジャングル」発表からわずか半年後の出来事である。
「ジャングル」はともかく、マックレーカーズの作品が最初の本格的なノンフィクションだと言ってよい。この新しい散文ジャンルは話題を呼び、雑誌は予想以上に売れ、発行人はホクホク顔、それを見て、新規参入も相次ぎ、出版産業は急速に成長する。売り上げが伸びれば、広告を募るのはさらに容易になる。ラジオが登場する1920年代まで、全国で販売される雑誌は最大の広告媒体である。新聞はすべてローカル紙であり、全米を網羅してはいない。一方、雑誌なら東海岸の人も西海岸の人も同じ誌面を見ることができる。企業はこぞって雑誌に広告を掲載し、その潤沢な収入によって雑誌は黄金時代を迎える。
こうした状況から生まれたのが、ノンフィクションの古典的名作「世界を揺るがした十日館(Ten Days that Shook the World)」(1919)である。1917年、ロシア革命が勃発した際に、アメリカの社会主義的雑誌『ザ・マッセズ(The Masses)』の特派員としてペトログラードに滞在していたジョン・リード(John Reed)は、周到な取材記録と膨大な資料を駆使し、自らの体験を交えて、ロシア革命の実像を浮き彫りにしようとする。彼の描き出すロシア革命に主人公はいないし、物語的統一感もない。ただただ雑然とし、猥雑でさえある。しかし、それこそが革命のリアリティを読者に実感させる。
広告媒体のチャンピオンの座は雑誌からラジオに移ったものの、20年代以降は完全にノンフィクションは独立した散文ジャンルとして社会的に認知され、定着している。ジョン・ガンサー(John Gunther)は、『ヨーロッパの内幕(Inside Europe)』(1936)で一般のアメリカ人に向けて、ヨーロッパを解説し、エドガー・スノー(Edgar Snow)が欧米人にとって噂話としてしか知らなかった中国共産党の姿を『中国の赤い星(Red Star Over China)』(1937)において伝え、ジョージ・オーウェル(George Orwell)は、スペイン内乱に身を投じ、人民戦線の四分五裂した内情を『カタロニア讃歌(Homage to Catalonia)』(1938)に著わしている。世界は、何かとてつもなく大きく変容しつつある。それを人々はノンフィクションから受けとる。
時が経っても、やはり雑誌とノンフィクションが特別の関係にあることには変わりはない。1946年8月31日、雑誌『ニューヨーカー(The New Yorker)』は次のセンテンスから始まるただ一作だけを掲載して発売される。
At exactly fifteen minutes past eight in the morning on August 6, 1945, Japanese time, at the moment when the atomic bomb flashed above Hiroshima, Miss Toshiko Sasaki, a clerk in the personnel department of the East Asia Tin Works, had just sat down at her place in the plant office and was turning her head to speak to the girl at the next desk.
日本時間1945年8月6日午前8時15分ちょうど、原子爆弾が広島上空でピカッと閃光を放ったその瞬間、東洋製罐の人事課で事務をとる佐々木とし子さんは課内の自分の机につき、隣の同僚に話しかけようと横を向いた。
この”Hiroshima”と題されたノンフィクションは、実に、3万1000語にも及ぶ。筆者の-ジョン・ハーシー(John Heresy)は従軍記者として、1946年5月、広島に入り、主に5人の原爆症患者に密着取材を試みている。多くの読者にとって、聞いたこともないこの東洋の地名は、原子爆弾がいかなる惨状をもたらすかという知識と共に、二度と忘れられない固有名詞となる。世界は、たった一作のノンフィクションによって、核兵器の恐ろしさを知るが、それには『ニューヨーカー』誌の英断も貢献している。
なお、現在刊行されている単行本の版では、筆者があのときから40年近くを経て再度広島を訪れた際の記述が最終章に付け加えられている。
1960年代に入ると、「ニュー・ジャーナリズム(New Journalism)」が新たなノンフィクションの運動として勃興する。それをサポートしたのも『エスククァイア(Esquire)』という雑誌である。この1933年にシカゴで創刊された男性誌は、60年代に、非常に物語性の強いニュー・ジャーナリズムを全面的にバック・アップし、次々と話題作を載せる。しかも、掲載については記事を署名入りにしている。これは雑誌ジャーナリズムの制度を変更させる。『タイム(Time)』や『ニューズウィーク(Newsweek)』などの大手の雑誌は、従来、記事を無署名にしてきたが、1971年までに署名入りに切り替えている。今では、アメリカの活字媒体では署名入りが常識となっているけれども、これにもノンフィクションがかかわっている。
以上のように、アメリカでは雑誌がノンフィクションを育てたが、日本の場合、ノンフィクションが本格的に独立したジャンルとして書かれるようになるのは、第2次世界大戦後のことである。アメリカの状況を参照するならば、ノンフィクションが発達しなかったことは不可解である。新聞は政財官界の不正・腐敗・醜聞を報道し、シーメンス事件の山本権兵衛内閣のように、内閣が総辞職に追いこまれる事態も起きている。また、関東大震災直後、空前の出版ブームが沸き起こり、『週刊朝日』や『サンデー毎日』といった週刊誌さえ発行されている。商業主義に対する抵抗感は、1905年1月から1940年9月までの『東京朝日新聞』の紙面を見る限り、今日より希薄である。この間、博報堂が第一面を買いとり、雑誌や書籍の出版広告で埋め尽くしたため、記事は一切ない。しかも、日本放送協会のラジオ放送は、民間企業が広告を受け付けず、全国をカバーする広告媒体としての雑誌の優位さは揺るがない。しかし、雑誌はマックレーカーズ登場以前のオピニオン・ジャーナリズムが中心で、ノンフィクションには欠かせない調査報道はあまり見られない。
言うまでもなく、戦前にも優れたノンフィクションは発表されている。横山源之助の『日本之下層社会』(1899)や細井和喜蔵の『女工哀史』(1925)がその代表であろう。横山源之助は、他にも、海外移民問題をとり上げた『海外活動之日本人』(1906)を著わすなど日本のノンフィクションの魁である。けれども、社会の実態を描く散文はノンフィクションではなく、取材や調査に基づきながらも、フィクショナルに加工した小説が主流である。この理由を検閲の厳しさに求めることはできない。確かに、多くのプロレタリア文学が当局から削除・発禁を命じられ、表現の自由も十分であったとは言いがたい。しかし、戦前のテキストをあたると、それが今日の先入観とは違う基準だったことを思い知らされる。農商務省による工場調査に嘱託として横山源之助が参加してまとめられた『職工事情』(1903)は、当時の労働現場が以下に暴力で支配されていたかを生々しく伝えている。
一例として、虐待・暴行された挙げ句、失明してしまった機織工女カノの証言を引用しよう。
縄を股の下に入れて、股から肩へ襷に縛って、それをまた腰の処で縛って、そうして高い敷居へ宙吊りに吊って打たれたんです。それは一時間ばかりで堪忍してもらったけど、またその翌日、腰だの何かが痛んで受取ができなかったもんだから、今度はまたブリキの銅壺(石油缶なり)をやっぱり股に挟んで、それで(残酷卑猥につき中略)といって来たんけど、そん時は友達が託ってよしたんです。
この報告書は戦前には復刻されなかったけれども、官製の文書でさえここまで記すことができている、これと比べると、プロレタリア文学は取材・調査が不足し、その代わりに、イデオロギー性が色濃い。小林多喜二の『蟹工船』(1929)を例にとると、蟹工船を舞台にしながら、蟹の捕獲や缶詰の生産工程、人員の具体的配置などに触れられていない。ノンフィクションは規範ではなく、実態を描く。それを書くには、ジャーナリストの技能が必要である。作者は自分の意見を語るのではない。扱っている対象から発せられる声を聞かなければならない。こういったジャーナリスティックな取材・調査の方法が志望も含めて作家の間に普及していない。何しろ、アメリカでは大学にジャーナリズム学科が設置され、そのリテラシーを体系的・総合的に教育している。ジャーナリストは、医師や弁護士と同様、専門職であり、体系的・総合的な教育が不可欠であって、組織的に再生産される必要がある。それに対し、日本においては現場で一から覚えるしかない現状とあっては、それもやむを得ない。
確かに、日本でも、1920年代の一時期、ジャーナリズムの専門教育が行われている。1910年代に新聞産業が拡大するにつれ、専門教育の必要性が議論されている。当時、取材記者は「探訪者」と呼ばれ、記事を書かず、ニュースを巷から集めることを専門にしていたが、とにかく評判が悪く、「羽織ゴロ」と毛嫌いされている。この状況に危機感や憂慮を覚える人たちは「新聞記者」を職能と位置づけようと制度設計に向かう。1923年9月1日に起きた関東大震災は新聞業界の地図を書き換えを促す。大阪の新聞社が東京に進出し、産業規模が拡大する。大卒も新聞社を希望するようになり、入社試験も実施され始める。と同時に、さまざまな養成機関が設立されている。さらに、欧米の動向も参考にしつつ、新聞記者の資格の制度化の検討も始まり、「新聞士」の認定も論議されている。しかし、激しい論争の後、1930年代には資格制度は斥けられ、ジャーナリスト養成も社内教育が中心になる。この辺の事情は、現在、研究課題として残り、まだ明らかではない。
篠田一士は、『ノンフィクションの言語』(1985)において、19世紀の近代文学は情報伝達の昨日も帯びていたが、急速に近代化した日本では、ロマン主義の受容に追われるあまり、それをノンフィクションに委ねざるを得なかったと論じている。しかし、ここには近代ジャーナリズムに基づく社会性という観点が欠落している。ノンフィクションは具体的な個別的事例を追求することで普遍性を見出すわけではない。それでは、チャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin)の『種の起源(On the Origin of Species)』(1959)もノンフィクションに含まれてしまう。そうではなく、ノンフィクションが浮かび上がらせるのは近代の社会性である。
「ありのままを書く」をモットーに、自然主義文学から派生した私小説が日本近代文学の中心的地位を占めている。しかし、これらは、著しく社会性に乏しく、ノンフィクションとは呼べない。ノンフィクションはリアリティショーではない。スポーツや芸術、芸能を舞台にしていようとも、ノンフィクションには「社会とは何か」という根本的な問いがあり、公共性・公益性への寄与においてその存在意義がある。読者は扱われている対象を通じて社会を改めて考える。
戦前にも私は匿名でしばしばものを書いた経験をもっているが、こんど単なる匿名評論ではなく、「猿取哲」なる新しい人間を創造して、陰からこれを入形のようにあやつる、というよりも、自分がこれになりきることだというふうに考えた。
「猿取哲」の特性は、まず第一に世間に通用している主義主張を決してもたないことである。厳正中立、不偏不党、徹底した是々非々主義で押し通すことである。書くのは大宅壮一であるが、書くことは大宅壮一から独立すべきで、大宅壮一個人にとってどんなに親しい人間をあげつらう場合にでも、絶対に私情には影響されないで、何でもいってのけられる立場に立とうというのである。そのころの日本はまだ“主義”という名のついた“思想”のレッテルが横行していて、生きた人間がいうよりはレッテルがものをいうことが多かった。そこで時と場合によっては「猿取哲」がその生みの親である大宅壮一をやっつけねばならぬこともあり、事実やっつけたこともあった。
世間はこれを文筆アクロバットと見た。だが、私は前にのべたような目的と信念をもって、一つの試みとして、計画的にやっていたのである。
(大宅壮一『「無思想人」宣言』)
傑出したノンフィクションが登場しても、後継者が生まれず、流れが形成されない。ノンフィクションの方法論が世代を超えて継承されていない。花が咲いても、種をつけない。戦後、こうした現状を変えるのに最も貢献したのがこの大宅壮一であろう。1957年、彼が中心となってノンフィクション・クラブを設立する。ノンフィクションに不可欠な方法を後進に指導し、ノンフィクションを独立したジャンルへと育成するのに努めている。ノンフィクションの執筆には、ジャーナリストのリテラシーが必要である。それは習得されるスキルであって、自然に身につくものではない。60年代後半から、その活動は実を結び始める。努力が実り始め、70年代には、独立したジャンルとして確立する。石牟礼道子の『苦海浄土─わが水俣病』(1969)や鎌田慧の『自動車絶望工場』(1973)はこの時期を代表する。
さらに、日本のノンフィクションにとって、歴史的な作品が発表される。1974年、『文藝春秋』11月号は「田中政権を問い直す」という特集を組み、立花隆の「田中角栄研究─その人脈と金脈」と児玉隆也の「淋しき越山会の女王」の二本の作品を掲載する。目次には、前者のリードとして「人は詳細を知らずに金権政治という。本誌は雑誌ジャーナリズム始まって以来の大調査に基づいて、その実態を今ここに明らかにする」、後者では「この人の存在自体が家政的国政の象徴である(。)いいわるいを超えてこれが自民党の体質だ!」と記されている。
田中角栄内閣総理大臣は、この雑誌記事、特に前者の内容をめぐって国会内外で激しく追及される。12月9日、絶えきれなくなった田中内閣は総辞職する。
この一件は、しばしば、一本のノンフィクションが首相を退陣に追いこんだと伝説的に語られる。しかし、立花隆のレポートが発表される前から、田中首相への世間の風当たりはすでに厳しい。1972年7月16日に、内閣総理大臣に就任したときの田中は「今太閤」ともてはやされ、各種の世論調査は70%前後の高い支持率を示している。ところが、1973年に、彼の日本列島改造計画が不動産価格と建設資材の高騰を招き、さらに、秋には第4次中東戦争に伴う第1次オイル・ショックが起こり、経済状態は急速に悪化する。その間に、田中の金権体質の噂に対して、当初はいぶかしく思っていた世間も次第に信じるようになり、失望感が広がっていく。とうとう74年7月に実施された参議院議員選挙で自民党は大敗を喫してしまう。角栄人気は今は昔という有様で、首相の交代は時間の問題と見られるようになる。読者が田中叩きの記事を待ち望んでいるときに、発表されたのが「田中角栄研究」である。それは辞職寸前の田中首相に最後の駄目押しをしたというのが正確なところだろう。
元々、この作品は立花隆自身の発案ではない。彼の『田中角栄研究 全記録』によれば、74年8月25日頃に、『文藝春秋』編集部から田中政権に関する企画のアイデアを求められ、それに対し、権政治の実態を世間に知らしめるために、集金手法を調べることを勧めている。当社、立花隆はそれを自分で手がけるつもりはなかったが、アシスタントを十分に用意するからと編集部に説得され承諾している。自身の立てた取材計画に沿って、アシスタントと共に作業を進め、最終的な原稿作成を行っている。
「田中角栄研究」は雑誌における日本初の本格的な調査報道であり、各方面に大きな衝撃を与える。調査報道の手法の有効性が確証され、積極的に採用されるようになっただけではない。月刊総合誌がそういったノンフィクションを発表する主要媒体となったことも大きい。月刊総合誌は、広津和郎の「松川裁判」が『中央公論』1954年4月号から4年半に亘って連載されるなど従来からノンフィクションを掲載していたが、自認しているかどうかは別にして、知識人が論文や評論、批評、エッセイを発表し、議論をするのがメインである。こういう雑誌を「論壇誌」や「オピニオン誌」とも呼ぶ場合もある。『文藝春秋』11月号でも、小田実の「国家はどのようにしてできるか」や橋本明の「征韓論を排す」、丸谷才一の「四国遍路はウドンで終る」、倉田保雄の「鎖につながれたアヒルの反骨」などが掲載されている。東西冷戦が始まり、各雑誌のイデオロギー傾向の強い論文を中心にすえることが常態化している。その状況がこのノンフィクションの成功によって変わる。1966年創刊の『月刊現代』が長編ノンフィクションを積極的に掲載するように、ホーム・グラウンドを獲得したノンフィクションは、日本でも、飛躍的に発展していく。
主張というのは、すごく難しいんですよね。主張することがマイナスになる場合がある。つまり説得力がない主張というのは、マイナスでしかないでしょう……。説得力がある主張というのは、あまり主張しない主張だと思うんです。その主張が通りだけの材料をあらかじめ与えておいて、あまり言葉は使わない。
(立花隆『ノンフィクションは、いま何をどう伝えるのか?』)
2 ノンフィクションとは何か
古来より同時代的な事件や出来事、人物、異文化を記録することは行われてきたが、ノンフィクションは実質的に20世紀から始まったと考えるべきだろう。トゥキディデアスの『歴史』やイブン・バトゥータの『三大陸周遊記』は、非常に興味深く、示唆に富んだ作品であるが、ノンフィクションとは呼べない。近代ジャーナリズムの方法論を踏まえていないからである。
近代ジャーナリズムを語る際に、しばしば正確性・客観性・中立性が問われるが、その基準は社会的に妥当であるかどうかから判断される。ジャーナリズムに法的トラブルはつきものである。最終的には、裁判になった場合でも、勝訴し得るだけの正確性・公正性・公共性があればよい。もちろん、ソクラテス裁判や松川裁判が示している通り、裁判所は無謬ではない。言論の自由に関して茶番のような裁判が行われている国や地域は世界中至るところに見られる。ジャーナリズムは、有形無形を問わず、圧力や嫌がらせ、暴力などの危険にさらされ、日本では「自粛」という”Terminate with extreme prejudice”が出版社から作品に少なからず発せられる。基準は会や時代に応じて変動し、なおかつある一定範囲の間で伸縮するものである。アグネス・スメドレー(Agnes Smedley)の『中国の歌ごえ(Battle Hymn Of China)』(1943)やフレデリック・フォーサイス(Frederick Forsyth)の『ビアフラ物語(The Biafra Story)』(1969)のように、明らかに特定の側に肩入れしている作品もあるが、それには、概して、社会の空気が一方的な方向に流れているという背景がある。
そもそも、近代ジャーナリズムを支える「出版の自由(Freedom of the Press)」は裁判を通じて確立されている。それは、植民地時代のアメリカにおけるドイツ系移民の新聞発行人ジョン・ピーター・ゼンガー(John Peter Zenger)の法廷闘争である。
当時の新聞は植民地総督の許可を受けて発行されており、当局に都合のいい内容だけで埋め尽くされている。1733年、ニューヨークで、ジョン・ピーター・ゼンガーが『ニューヨーク・ウィークリー・ジャーナル(The New-York Weekly Journal.)』紙を創刊する。彼は『ジャーナル』紙に、御用新聞とは一味違う記事を掲載する。その中には、ニューヨークの総督ウィリアム・コスビー(William Cosby)に対する批判も含まれ、1734年、御立腹の総督に代わって当局は、早速、彼を逮捕し、訴追する。しかも、ゼンガーは記事の真偽だけでなく、名誉毀損も問われる。18世紀前半のイギリスの法では、報道がたとえ事実であったとしても、名誉毀損罪が成立することになっている。この点でゼンガーは、正直言って、分が悪く、勝ち目はないというのが大方の見方である。にもかかわらず、公判の中で、ニュース・ソースを明らかにするように求められたのに対し、ゼンガーはそれを拒否し、新聞人が掲載した記事に対して全責任を負っており、情報の通告者を保護すべきであると主張している。
この法廷での彼の弁明は世間から広く同情が寄せられる。ベンジャミン・フランクリンの友人のアンドルー・ハミルトン(Andrew Hamilton)もその一人である。有能な弁護士と評判のあった彼はフィラデルフィアからニューヨークへ赴き、自らゼンガーの弁護をかって出ている。ハミルトンは巧みにゼンガーを弁護する。名誉革命の意義を踏まえ、専制的な権力に対抗して、真実を語ることは英国人としての当然の権利である以上、ゼンガーの記事が事実であるとしたら、彼は無罪となるべきだと訴えている。1735年8月、陪審員はこの弁論を支持し、ゼンガーは無罪となり、釈放される。
この公判の様子は他の植民地にも新聞を通じて伝わるが、それ以上に衝撃を受けたのはロンドンである。この判例により、政府や役人を批判することは、それが明白な虚偽ないし悪意であると証明されない限り、自由で、名誉毀損は適用されないことになったからである。加えて、植民地の同意がなければ、本国が法で植民地を縛ろうとするのが難しくなる。植民地の報道の自由は本国以上に拡大され、それに支えられた出版産業が発達し、後に、独立のイデオロギーを喚起・形成していくことになっていく。
1789年8月26日にフランスの憲法制定国民会議で採択された「人間と市民の権利の宣言(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)」は検閲の廃止を謳い、11条で出版の自由に言及されている。出版の自由はフランス人権宣言に先立ち、さらに近代体制そのものを実現化する一つの原動力として機能している。
さらに、ノンフィクションの登場には、出版の事由に保障された近代ジャーナリズムの発達だけでなく、写真という新たなメディアの衝撃による刺激を見逃すことはできない。
マックレーカーズの登場する直前に、ジェイコブ・リース(Jacob Riis)という写真ジャーナリストが活躍している。マックレーカーズは彼なくしてはありえない。1870年代後半から1890年代後半にかけて、『ニューヨーク・トリビューン(New York Tribune)』紙や『ニューヨーク・イブニング・サン(New York Evening Sun)』紙の記者としてニューヨーク社会にはびこる悪を撲滅すべく奮闘する。この1870年に海を渡ってきたデンマーク人は、中でも、移民労働者の劣悪な住・労働環境を取材・報道し、世間に改革を訴え、時には市当局に直談判している。その最大の武器こそ写真である。1888年頃から、フラッシュ装置を用いて撮影されたスラムの写真は、彼の主張を裏付け、社会改良の必要性を世論に納得させる効果を発揮する。当時の新聞の印刷技術では彼の写真を掲載できなかったため、1890年、『あと半分の生活(How the Other Half Lives)』という本にまとめる。そこには、酔っ払った母親に代わって子守をする幼い少女、16歳だと言い張って工場で針仕事をする12歳の少年、警察に問答無用で収容される女性たちが写っている。みんな暗く、すさんだ目をしている。今を生きるのに精一杯で、その先に出口など見当たらない。こんな生活を送るために、故郷を後にして、ここに来たわけじゃない。人々は、それを目の当たりにして、こんなことがあっていいのだろうかと憤り、彼の言う通り、社会には悪があると確信する。リースの写真の絶大な影響力がマックレーカーズとノンフィクションを生み出したとも言える。従来の文章表現はリースの写真の訴えには遠く及ばない。写真に迫るような文章表現を改革しなければならない。写真との緊張関係からノンフィクションは誕生する。
写真は、機械が媒介することもあって、非常に限られた方向に特化したメディアである。しかし、反面、それが強烈な印象をもたらす。
カメラを構え、レンズを片方の眼だけで覗きこむ。三次元が二次元になり、距離感が失われる。カメラは奥行きのある対象を正面から撮るのが難しい。構図を考える必要がある。
アナログ・カメラでは、被写体からの反射光がレンズを通ってフィルムの乳剤に感光する。写真に写っているのは物質、それも外形だけである。表情を写せても、その人が何を心の中で思っているかなど画像にできない。ある意味で、これは極めて近代を具現している。近代法では、内面の自由は保障される。しかし、だからこそ、その内部をうかがわせる写真は人を感動察せる。
写真には抽象性・一般性はない。写っているのは具体的・固有的な存在である。写真は、少女一般を扱うことはできない。そこにいるのは他とは取り替えることのできない固有な少女である。また、カメラは貧困という抽象性を直接的に写すこともできない。そうしたければ、何かに託してイメージさせなければならない。
写真の時制は現在完了形である。過去形でも現在形でも未来形でもない。写っている世界はすでに存在したものであり、それは現在において継続・経験・完了のいずれかである。また、レンズを通して見る視界はあまりにも狭い。写真は空間と時間のある一部分を切りよっているのであって、鑑賞者はその全体を想像力の中で回復させようとする。
しかも、写真は被写体のみならず、そこに写っていない撮影書も鑑賞者に伝える。撮影は、実は、その行為者の意思表明である。写真を見ると、サイズとアングルで撮影者の立ち位置がわかる。それにより、何かを主張しなくても、見る人もその同じ地点にいると感じ、撮影者の性格さえも認識できる。被写体との距離感にそれが一体なんなのか改めて考えさせられる。
ただ、モノクロ写真は、カラーと比べて、抽象度が高い。赤・青・黄が白と黒に単純に二分されるわけではない。真っ白から真っ黒まで白と黒の比率は数直線的であり、画面全体における暗部の占める比率も印象を大きく左右する。撮影にはカラー以上に明確な意図をもって臨む必要がある。このように抽象性があるため、モノクロ撮影では写真家は絵画の構図も参考にしなくてはならない。その意味で、アナログ・カメラでモノクロ撮影をする方が写真を本質的に学ぶことができる。
この写真が文章表現に与ええた衝撃は計り知れない。ノンフィクションは写真の特性を文章表現にとり入れる。小説や批評と比較してみると、それは明瞭になる。
言葉は抽象的・一般的なものを容易に示すことができる。そのため、写真が登場して、初めて、書き手は文章表現が具体性・固有性への意志が不徹底だったことに気づかされている。批評はノンフィクションより古く、18世紀欧州で諷刺の形式をとって全盛時代を迎えた散文ジャンルであり、「在野の文学」である。時事性だけでなく、アカデミズムも兼ね備えているため、抽象的な課題を直接的にとり扱うことができる。「ノンフィクション」というテーマを書く場合、ノンフィクション作品であれば、現場で活躍している作家や編集者などへのインタビューを通じて構成していかなければならないが、批評においては取材は必ずしも必要ではない。ノンフィクションは取材のできない対象を扱えない。事情を知る関係者がすべて亡くなっている以上、ユリウス・カエサルの暗殺事件の舞台裏や真相をノンフィクション化することは不可能である。ノンフィクションは、基本的に、同時代を対象とする。他方、抽象性を扱えるということは、批評はそこにないものも対象化できるので、未来や過去も語り得る。レイチェル・カーソン(Rachel Carson)の『沈黙の春(Silent Spring)』(1961)は冒頭で未来を寓話化しているが、あくまでも、今の社会に対する警告として描いている。文体や構成の展でもその実在性が反映する。ノンフィクションは、本当の社会の姿を描くために、すでに社会的に認知された文体や構成を用いる。それに対して、批評は、こうした因習には従わない。社会を風刺し、あるべき姿を語るため、文体や構成は非常に自由である。
近代小説は近代社会に登場した普通の人々を扱う「市民の文学」である。登場人物は等身大で、その性格・心理・志向は社会が表われたものである。社会的仮面、すなわちペルソナを被った本当の人間あるいは人間の真の姿を描写しようとすることから、しばしば因習的とならざるをえなくなる。しかし、反面、登場人物の心理に自由にかつ深く立ち入ることができ、それによって読者は平凡でどこにでもいそうな主人公に共感することも少なくない。等身大の人物をとり扱うことができるが、それ以外は不向きである。この短編形式は一般的には「スケッチ(Sketch)」と呼ばれている。
ノンフィクションは心理描写は行わない。写真のように、対象を外側から見る。作者が登場人物の私的領域である内面をあれこれ想像することはせず、公的領域の外発されたものだけを記す。その代わり、等身大に限定されることなく、いかなる人物も対象にできる。ノンフィクションは社会的文学であり、扱うべきは公的領域である。各種の証言を集めてその人物像の複雑さを提起する試みは重要であるが、アドルフ・ヒトラーの内面描写をして、よき家庭人だったと強調することでその公的行為を救うのがノンフィクションの仕事ではない。心理描写の禁止は、ノンフィクションの弱みや限界ではなく、強みであり、可能性である。
以降、ノンフィクションは新しく出現した映像メディアの衝撃に刺激を受け、その特性をとり入れ、自己変革していく。ノンフィクションはまさに「複製技術時代」(ヴァルター・ベンヤミン)の散文である。
ジョン・リードの前には、静止画である写真ではなく、動画の映画が登場している。画像と映像の間でも、異なった点がいくつかある。動きを獲得したため、映像の、時制は現在形である。写真は距離の遠近法だけが効果をもたらしていたが、動画では、それと同時に、時間の遠近法も作用する。アップになると、時間が速く、ロングになると、逆に遅く感じられる。そのため、映像を編集する際に注意しないと、日常的な感覚と逆転することがある。人はじっくりと対象を見ようとするとき、顔を近づける。しかし、映像ではアップのシーンは時間が速く感じられるので、せせこましくなる。映像のリテラシーを理解して撮影・編集しなければ、効果的な映像表現は難しい。
1910年代後半、D・W・グルフィスは映画を庶民の娯楽だけでなく、芸術にまでその可能性を拡張している。フェイドインやフェイドアウト、クローズアップ、クロス・カッティング、カットバック、ラスト・ミニッツ・レスキューを考案し、一つの作品に複数、最大で四つまでの筋を並行する方法も導入している。これはリードのロシア革命を描いたノンフィクションの手法そのものである。1925年、ソ連のセルゲイ・エイザンシュテインが『戦艦ポチョムキン』でモノクロ映画の可能性を極限まで追求して見せる。
1960年代に出現したニュー・ジャーナリズムのときには、テレビがお茶の間に入り込んでいる。先の特性は動画一般であり、主に映画を想定してきたが、テレビとなると、さらにいくつかの違いが出てくる。テレビにはテレビのリテラシーがある。テレビの時制は現在進行形である。映画はシーンの切り替えの際に、1秒24コマを基準に場面に応じて8コマや12コマといった具合に選択できる。テレビでは、生放送はもちろん、多くのスタジオ収録の番組は複数用意されたカメラの切り替えによってシーンが入れ替わる。このスピードは映画とは比較にならないくらい速い。フィルムのコマ数に換算して、3コマで切り替わることさえあるが、映画ではその倍は最低でも費やす。また、テレビは家庭で見られるため、ながら視聴を可能にする必要がある。それには、音声による情報量を増やし、聞いているだけで、話がわかるようにしてかなければならない。そうすると、ニュース原稿を読むキャスターでお馴染みの上半身だけ映すバスト・サイズのカットが多くなる。これらの特徴のため、ワン・ショットに入る情報量が少なく、それを速い切り替えと音声によって補う。俳優も、映画と比べて、日常性が透けて見える情報量の少ない顔のタイプがブレークする。
1962年、ゲイ・タリーズ(Gay Talese)は、『エスクァイア(Esquire)』誌6月号に、「ジョー・ルイス─中年男としての王様(Joe Louis: The King as a Middle-aged Man)」というノンフィクションを掲載したが、次のように書き出している。
「ただいま」とジョー・ルイスはロサンゼルス空港に出迎えていた妻を見つけて、声をかけた。
彼女は笑顔で近づいてくると、背伸びをしてキスしようとした─が、急にやめた。
「ジョー」と彼女は言った。「ネクタイはどうしたの?」
「なんだ」と彼は肩をすくめた。「ニューヨークで徹夜したんで、時間がなかったんだ」。
「徹夜したのね!」と彼女はさえぎった。「ここにいるときは、いつも眠ってばかりいるのに」。
「ね」とキョー・ルイスは疲れた笑みを見せた。「おれは年寄りなんだと」。
「そうね」と彼女は同意した。「でも、ニューヨークに行くと、また若返ろうとしてるわ」。
“Hi, sweetheart!” Joe Louis called to his wife, spotting her waiting for him at the Los Angeles airport.
She smiled, walked toward him, and was about to step up on her toes and kiss him – but suddenly stopped.
“Joe,” she said, “where’s your tie?”
“Aw, sweetie,” he said shrugging, “I stayed out all night in New York and didn’t have time…”
“All night!” she cut in. “When you’re out here all you do is sleep, sleep, sleep.”
“Sweetie,” Joe Louis said, with a tired grin, “I’m an ole man.”
“Yes,” she agreed, “but when you go to New York you try to be young again.”
日本の高校生でも苦もなく読めるほど平易で、ほとんどスケッチのようだ。しばしば映画的と評される先のハーシーの「ヒロシマ」と比べて、一つのセンテンスに収められた情報量は少なく、会話だけ読みつないでも、話が分かる。従来のノンフィクションに見られる説明的記述が抑えられている。ただし、このセリフは作者の創作ではなく、取材に基づいている。文体と構成を変えるだけで、ノンフィクションは読者にとって小説のように読みやすくなる。作者のタリーズはマンネリ化したノンフィクションの文体に不満を覚え、そのブレーク・スルーを目論み、ベータ版としてこの作品を書いている。
『エスクァイア』は1933年にシカゴで創刊された世界初の男性誌であるが、饒舌な文体の風俗記事を寄稿していたジャーナリストのトム・ウルフ(Tom Wolfe)はは「ジョー・ルイス」を目にして衝撃を受ける。彼はこの方法にジャーナリズムの新たな可能性を見出す。これこそ新しいジャーナリズム、すなわちニュー・ジャーナリズムというわけだ。ウルフは、『ニュー・ジャーナリズム(The New Journalism)』(1973)で、説明的記述を使わず、事実を脚色して小説の技法を加味し、主観を通じて真実に迫ることだと言っている。従前の客観セを追及するあまり没個性的な記事のスタイルではなく、徹底した取材に基づき、場面や会話を再現し、場合によっては、登場人物の心理にも立ち入るべきである。ウルフは、その方法論を実践し、宇宙計画を描いた『ライト・スタッフ(The Right Stuff)』(1979)などを発表している。
1960年代、こうした新たな手法を用いたノンフィクションが次々に登場する。中でも最も成功したのはトルーマン・カポーティの『冷血(In Cold Blood)』だろう。カポーティは、1959年にカンサス州ホルカムというスモール・タウンで起きた一家4人惨殺事件について、独自の取材・調査を重ね、『冷血』を書き上げ、65年、『ニューヨーカー』誌に掲載する。66年に出版されるや大ベストセラーとなったこの作品には「私」、すなわち作者は登場しない。すべて取材対象の証言として語られる。加害者を含む事件の関係者から集めたインタビューを巧みに構成することで、事件の発生から加害者の逮捕、死刑執行に至る過程を再現している。
タリーズは、「ジョー・ルイス」を所収した『名声と無名(Fame and Obscurity)』(1970)の序文において、ニュー・ジャーナリズムについて次のように述べている。
ニュー・ジャーナリズムは、しばしばフィクションのように読めるけれども、フィクションではない。それはもっとも信頼できるルポルタージュと同じく信頼できるし、またそうあるべきだ。もっとも、確実な事実のたんなる編集や会話文の使用、古い形の硬直した集団的スタイルに執着することによって現われる真実よりも、もっと大きな真実を捜し求める。
The new journalism, though often reading like fiction, is not fiction. It is, or should be, as reliable as the most reliable reportage, although it seeks a larger truth than is possible through the mere compilation of verifiable facts, the use of direct quotations, and adherence to the rigid organizational style of the older form.
タリーズは、一つの記事を何人もの目と手によってつくり上げる「コーポレイト・ジャーナリズム(Corporate Journalism)」を批判し、一人の書き手が練り上げる「ワン・マンズ・ジャーナリズム(One man’s Journalism)」や「パーソナル・ジャーナリズム(Personal Journalism)」を提唱する。ドワイト・マクドナルド(Dwight Macdonald)から1965年に「擬似ジャーナリズム(Parajournalism)」と揶揄されながらも、ニュー・ジャーナリズムは社会的に認知される。先に挙げた作家の他、デイヴィッド・ハルバースタム(David Halberstam)の『ベスト&ブライテスト(The Best and the Brightest)』(1972)やノーマン・メーラー(Norman Mailer)の『夜の軍隊(Armies of the Night)』(1968)らその代表である。
60年代のアメリカでは既存の権威や価値観が大きく揺らいでいる。公民権運動やベトナム戦争とそれへの抗議運動が激化し、68年頃にはアメリカは分裂寸前にまで混乱する。テレビはそうしたアメリカの姿だけでなく、ベトナムの戦場や月面までも全米中のお茶の間に伝える。活字ジャーナリズムがそんな世の中を報道するには新しい手法が必要だと考えても不思議ではない。事件を外側からではなく、内側から見よう。客観性が崩れているのだからとアイロニカルに主観を排除せずに表現するべきだ。この発想は生まれるべくして生まれたわけでが、非常に素朴である。
従来のジャーナリズムが官僚主義化していたことは確かであるし、説明的記述を使わず、取材を徹底化するという点で、ニュー・ジャーナリズムは非常に挑戦的であり、ノンフィクションを改革している。しかし、その方法の一部は古典的であって、ノンフィクションに後退をもたらしてさえいる。これは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したT・H・A・ドライサー(Theodore Herman Albert Dreiser)やスティーヴン・クレイン(Stephen Crane)等の自然主義文学に舞い戻っているだけである。事件を内部から見ようと心理描写をするのは、ジャーナリストの文章表現としては新鮮かもしれないが、文学的には、むしろ、因習的である。外部からの視線に徹する態度を文学者はなかなかとりえない。『冷血』が文学者の間でも評価されたのは、徹底的に「私」を作品世界に入りこまないようにした禁欲的姿勢である。映像メディアによって示されたリアリティを文章化すると共に、それではできない文章表現ならではの迫真性を追求しなければならない。映像メディアはノンフィクション文学を成長させている。そうした外部からの視線の新たな展開がノンフィクションの行き詰まりを打開するのであって、古臭い文学技法に依存するのは、あまりにも後ろ向きである。演劇人の平田オリザは、『演技と演出』(2004)にうおいて、演劇の観客は最もイメージの共有をしにくいものを見たいのであり、それこそが「人間の心の中」だと指摘している。役者が演技を通じて「人間の心の中」をいかに観客と共有するかを苦心スしている、ノンフィクションが安易に心理描写に頼ることは情けない。ノンフィクション作家には外側から内側を伺える社会的知性が必要となる。また、再現に専心しすぎると、リアリティショーに近づき、対象と社会とのつながりが見失われてしまう。社会的意義があるからとり上げたはずなのに、再現すればするほど、それ自体が目的化し、自己完結性が強くなり、社会性が見えなくなる。それがノンフィクションの「再現性の罠」とも言うべき危険な事態である。これに陥ったとき、その作品はノンフィクションでなく、私小説になる。
実際、1960年代、最も社会に影響を与えたノンフィクションは、ニュー・ジャーナリズムではない。ラルフ・ネーダー(Ralph Nader)が発表した『どんなスピードでも安全ではない(Unsafe at Any Speed)』(1965)である。59年、GMは初のコンパクト・カーであるシボレー・コルベアを発売する。ところが、ジャッキアップ現象によって転覆しやすいという構造的欠陥あがったにもかかわらず、GMはそれを知りつつ、隠し、販売を続ける。この事実に気がついたのがそのレバノン系アメリカ人である。たこの31歳の弁護士は、『どんなスピードでも安全ではない』の中でコルベアの構造的欠陥を告発する。これに対する世界最大の自動車メーカーは、彼の身辺調査を実施し始め、あらゆる手を使って評判を落とそうとする。しかし、ネーダーにそういった工作が発見されてしまい、逆にプライバシー侵害で訴えられ、莫大な損害賠償を払うことになる。コルベアも、結局、生産中止に追いこまれる。 その間、66年に全国交通自動車安全法が制定され、連邦政府は全国交通自動車安全局を設置している。
ノンフィクションはある生成過程を再現する。語りが一人称となるのは、取材活動の再現を通じて作品を執筆した場合である。ただし、作者の内省を排除し、インタビューと説明的記述を中心にすれば、使わなくてもすむ。他方、事件や出来事、人物を時系列で再現しようとすれば、語りは三人称となる。けれども、内省が増えれば、「私」こそ使っていないものの、事実上、一人称の作品である。
時系列に沿って作品を構成すると、物語性が強くなる。ノンフィクションは、立花隆の「田中角栄研究」のような物語性の弱い「レポート・スタイル」とニュー・ジャーナリズムに顕著な物語性の強い「ドラマ・スタイル」に分けることができる。物語化は対象の構造化を意味する。そこでは、登場人物を含めすべての要素が作者の導き出した結論を実現するために従事する。それにそぐわない要因は排除される。こうした作品が成功し、社会的に定着してしまうと、作者の用意したシナリオ以外はありえないかのような通説が広まってしまう。また、ドラマ・スタイルは、読者にとって読みやすくなる反面、特定の因果関係を主張するため、狭い世界には適しているが、錯綜し、混沌とした事象の再現には向かない。
人物から世界を再現しようとすると、物語性が強くなりやすい。多様性を浮き彫りにする場合は、それ以外に焦点を当て、その反射光として人物を登場させる。松本仁一の『アラシニコフ』(2004)がその好例である。これは、通称カラシニコフ、すなわちAK47とその改良型のアサルトライフルから現代世界を見るというノンフィクションである。世界で出回っている銃の半数が同ライフルだとされ、それは現代の国際社会の複雑さをよく照らし出す。『カラシニコフ』はノンフィクションは反射光を捉える散文であることを改めて思い出させる作品である。
日本でも、一時期、ニュー・ジャーナリズムの影響を受けたと思われる作品が相次いで発表されている。ジャーナリズムならびに対象に関する専門的知識・経験に乏しい作家に新鮮な切り口を求めたのだろうが、概して、自己完結性が強い。スポーツ・ジャーナリストの玉木正之は、『プロ野球大事典』の中で、大毎オリオンズの強打者だった榎本喜八をモデルにした沢木耕太郎の「さらば宝石」(『敗れざる者たち』所収)を「ノンフィクションとは言えない私小説」と批判している。沢木耕太郎を含めて、こうした種類の作品では、作者によって世界が還元され、すなわち「私」にとっての世界が展開されるだけで、社会性が抜け落ちている。ノンフィクションとして健康的ではない。岡崎満義の「榎本喜八」(『濠打列伝』所収)と「さらば宝石」を読み比べてみればよい。沢木耕太郎を読んでも、プロ野球ならではの魅力が何も伝わってこない。一方、岡崎満義は榎本本人にインタビューをし、資料を調べ、エピソードに触れ、他のプレーヤーたちと比較しながら、プロ野球の社会の一面を見事に描き出している。岡崎満義は日本プロ野球の本質を説く最良の作家の一人である。
尊敬できるライバルを持つことのできた幸福を、榎本は素直に語った。プロ野球は一発勝負のトーナメントではない。同じチームと一年に二十数回試合をする。同じ投手と何年にもわたって、何十回、何百回となく対戦する。相手の「技術」を見る。何よりも「人間」を見る。もちろん、自分も相手に見られる。長年にわたって「見る─見られる」関係の中からかもしだされる親愛感の中で、技を競い、人間を競うのがプロというものだ。親愛感をもてる相手をライバルにできる幸福こそ、プロそのものだ。
(岡崎満義「榎本喜八」)
自伝や回顧録、日記、書簡、事件・出来事の当事者・関係者による回想録などもノンフィクションにしばしば入れられている。しかし、それらは、散文フィクションの一ジャンルである「告白(Confession)」に分類すべきであって、ノンフィクションと見なすべきではない。
告白は「僧侶の文学」であり、「私」や「私というもの」を語る。古くは『ソクラテスの弁明』やアウグスティヌスの『告白』にまで遡るわけだが、これを散文「フィクション」に含めるのは、明確な形式を持っているからである。このジャンルを最も象徴するジャン=ジャック・ルソーの『告白』が示している通り、近代的な告白は「私とは誰か」というアイデンティティ探求の文学である。その最も壮大な作品は、7代に亘る自分の一家の系譜をたどったアレックス・ヘーリー(Alex Haley)の『ルーツ(Roots)』(1976)だろう。フランス革命の理念に基づくフィヒテ哲学は、文学的に突きつめれば、告白そのものであって、小説と別の面であるが、これは近代でも衰えることはない。告白は自伝や日記、書簡、伝道、紀行文なども含み、傾向は内向的・知的である。扱い方は主観的であるが、自己省察を続けながら、哲学や宗教、医学、政治、芸術、科学、法学、倫理などに言及され、ただなんとなくそうしたかったからではなく、告白するにたる理由がそれによって明らかにされる。時に、語り手は悩みを抱えていたり、病んだ心の持ち主だったり、神秘体験をしていたりする。また、文学的資質や修練に乏しい政治家や企業経営者、役人、芸術家などが優れた告白を記すことも稀ではない。突然50日も漂流することになったケネス・クック(Kenneth Cooke)のような一船員などというケースもある。もっとも、今ではそれも民主化されている。ブログやYou Tube、Twitterには冒険途上の報告に溢れている。その中には、メキシコから出航して南カリフォルニアをヨットで目指す17歳のザック・サンダーランド(Zac Sunderland)までいる。告白は、インターネット時代に、最も爆発的に急増した文学ジャンルである。そうれはともかく、精神性という点では、告白は非常に高い。「エッセイ(Essay)」は筋のない告白であり、その短編形式である。
一方、ノンフィクションは「ジャーナリストの文学」であり、社会性を踏まえ、調査・取材・体験によって、実在の人物や地域、集団、組織体、事件、出来事に関する散文ジャンルである。傾向は外向的・社会的、扱い方は客観的である。作者が登場するのは、取材・調査に言及する便宜上のためであって、彼らは、原則的に、公正な第三者である。それによって、外部からの徹底した認識を可能になり、客観性が保持できる。取材の性質上、体験を必要とする場合もある。ジョン・ハワード・グリフィン(John Howard Griffin)は、肌を黒くしてアメリカ南部に潜入し、人種差別の実態を『私のように黒い夜(Black Like Me)』(1961)で報告している。また、ギュンター ヴァルラフ(Guenter Wallraff)はトルコ人になりすましてドイツにおける労働現場での差別を『最底辺(Ganz Unten)』(1988)で暴露している。画期的なノンフィクションは切り口や文体よりも、その取材・調査方法が参考にされ、後継者を生み出す。散文の中で、最も社会的・具体的である。ただ、具体的であるため、それを自覚していないと、体系性や総合性をないがしろにして、ノンフィクションは物事の認識を断片化してしまう危険性がある。センセーショナルな犯罪が起こると、加害者の生い立ちから事件の背景を追い、現代社会をそこに投影するという報道やノンフィクションがしばしば見られる。しかし、これではその事例を犯罪全体から切り離し、断片的に伝えているだけである。それに加えて、全体の犯罪における位置付けを確認し、類型的事例との相違点を分析し、この事件の特性を丹念に読みとり、一般読者に報告する。これが望ましい。言語化することで救われようとする人たちを扱うことはできても、日常生活の繰り返しに新たな人生をつくっていこうとしている人たちをノンフィクションは登場させることは困難である。彼らは何らかのわだかまりを心の中に抱えている。そうしながらも、生きていかざるを得ない。こうした日常をとり戻した人は、取材に応じる必要もないので、ノンフィクションが描くのは難しい。ノンフィクションは限界があるが、それを認めながら、残念ながら口をつぐんでいる作品も見られるけれども、話を述べられるジャンルでもある。なお、20世紀に初めて登場した犯罪は子供を狙った営利誘拐である。1932年に生きた「リンドバーグ愛児誘拐事件(Lindbergh kidnapping)」がその発端である。この種類の犯罪を検討することは、確かに、大衆の世紀である20世紀の本質を考える一つのアプローチであろう。ノンフィクションの短編形式は「記事(Article)」である。
ノンフィクションに足る具体性への意志が一般の作家では不十分なことは、村上春樹の『アンダーグラウンド』(1997)がよく示している。これは、地下鉄サリン事件に遭遇した被害者と遺族、医師、精神科医、弁護士などからのインタビューを集め、「村上春樹が真相に迫るノンフィクション」として刊行されている。「顔のない多くの被害者の一人」ではなく「一人ひとりの人間の具体的な──交換不可能(困難)な──あり方」を浮き彫りにすると言いながら、証言者のプロフィールにおいて、「いかにも若々しい青年」や「いかにも思いやりがありそうだ」、「いかにも育ちのよい」といったように、村上春樹は「いかにも」を連発している。これは具体性から程遠い。通常の小説でも、村上春樹はとにかく具体性に乏しいが、ノンフィクションでも同様である。それでいて、「基本的に、自分が現在前にしているインタビュイーの一人ひとりを、個人的に感情的に好きになろうとつとめた」と付け加えている。なお、村上春樹は、「はじめに」の中で、ある女性誌の投書欄に寄せられた「地下鉄サリン事件のために職を失った夫を持つ、一人の女性によって書かれた」手紙が『アンダーグラウンド』執筆に至る動機としてあげているが、この投書は実在しない。2000年の前期に慶応大学で行われた特別講義で、田中康夫がそれを明らかにしている。
こうした定義は教条主義的情熱に促されてなされているわけではない。ノンフィクションならではの感動を明らかにするためである。このジャンルでなければできない文章表現が確かにあり、それはノンフィクションを読まないと味わえない。無数のノンフィクションが書かれながらも、「そもそもノンフィクションとは何か」という問いに答えようとしている考察は非常に少ない。その感動を新たにするために、ノンフィクションの基礎論を考える必要がある。
ノンフィクションは、戦争や革命、殺人事件、市民運動、スポーツといった舞台に従って分けられることが多いが、これでは際限がなくなってしまう。作品の目的という観点から考察すると、次の六つに分類できる。
(1)マックレーカーズ型
事件や出来事、組織、人物などのスキャンダルや不祥事、隠された実態を暴露する。
…鎌田慧『自動車絶望工場』(1973)
(2)内幕型
暴露型と違い、対象の内幕を伝えることに専念し、攻撃性が弱い。
…大泉実成『説得 エホバの証人と輸血拒否事件』(1989)
(3)提言型
専門的な調査に基づいて導き出された結論・仮説を示し、改善するための議論の必要性を暗に提言する。
…野田正彰『喪の途上にて 大事故遺族の悲哀の研究』(1992)
(4)発掘型
半ば忘れかけた、もしくはあまり知られていない事件や出来事、組織、地域、人物などにスポット・ライトを当てる。
…鈴木明『リリー・マルレーンを聴いたことがありますか』(1975)
(5)検証型
事件や出来事、組織、政策、制度などを資料やインタビューを通じて検証する。
…吉岡忍『墜落の夏 日航123便事故全記録』(1984)
(6)フィールド・ワーク型
緩やかで、いささか抽象的と思われるテーマについて取材・調査などを通じて具体的に報告する。
…野村進『コリアン世界の旅』(1996)
これはあくまでも作品の目的による分類であって、実際に社会的にいかに機能したかを考慮してはいない。ビクトル・ファリアス(Victor Farias)は、12年に亘ってマルティン・ハイデガーに関する膨大な資料を詳細に調査し、『ハイデガーとナチズム(Heidegger y el Nazismo)』(1987)において、彼の釈明以上にナチスにコミットしていたことを明らかにしている。この作品は暴露と言うよりも、検証に近かったが、世間はそうとらない。ハイデガーは、ポスト構造主義の潮流において、フリードリヒ・ニーチェに次いで影響力のあった哲学者である。それに批判的な勢力から、ハイデガーの過去は格好の口実として利用される。この動きに対し、ユダヤ系の哲学者ジャック・デリダは、ナチズムへの態度を論拠にハイデガーの思想をすべて捨てさるべきでないと反論している。むしろ、ナチズムを考えるためにも、ハイデガーを読む必要がある。ノンフィクションは社会性が強い散文ジャンルであり、フィクション以上に社会に難しい問題を提起することも少なくない。それもノンフィクションの重要な意義の一つである。
3 インターネット時代のノンフィクション
1970年代からアメリカでは総合雑誌の発行部数が低迷したが、その代わりに、『PLAYBOY』や『スポーツ・イラストレーテッド(Sports Illustrated)』、『TVガイド(TV Guide)』を始めとする読者層を絞った専門誌が売り上げを伸ばし、1990年に約2200万部にも上っている。日本の出版産業も、90年代に入ると、今まで経験したことのない不評に見舞われ、雑誌の売り上げが激減する。若者は月刊総合誌など見向きもせず、主な購読者層は高齢者では先細るだけと判断した出版社は相次いで休刊に踏み切る。一方で、『ロスジェネ』や『POSSE』など特定の問題に特化した雑誌が好調である(「ロスジェネ」と称される彼らだが、消耗し、精神分析学の防衛機制に追われているように見え、むしろ、「防衛機制世代(Defense Mechanism Generation: DMG)」が適切であろう)。1970年代のアメリカの雑誌業界を見ているようだ。
月刊総合誌の凋落は、ノンフィクションに試練を与えている。調査報道やそれに基づくノンフィクションは、潤沢な資金を背景に、人手と時間を費やしても、楽にペイする環境から生まれている。人・金・時を必要とするジャーナリズムであって、雑誌のビジネス・モデルが成り立たなくなれば、立ち行かなくなり、対応策が必要となる。
アメリカでは、インターネットの普及などにより、販売部数の低迷と広告収入の減少に伴い、新聞業界が苦境に陥る。04年くらいから、人員削減、身売り、経営破綻が相次いでいる。新聞社の中には、調査報道から手を引くところも少なくない。新聞や調査報道の行方がテレビで頻繁に討論されている。ディズニー映画の『おてんば探偵ナンシー・ドリュー(Nancy Drew)』(2002)の中でさえ、ジャーナリズムの黄金時代はすでに終わり、調査報道の行く末は厳しいと触れられているほどだ。PBSに至っては、2009年のピューリッツァー賞発表直後の4月20日に、『ニュース・アワー(News Hour)』で「メディア削減に見舞われる調査報道(Investigative Reporting Hard Hit by Media Cutbacks)」という特集座談会を組んでいる。
日本の場合、1942年に戦時体制の一環として内務省が指導した一県一紙制がほぼ戦後も存続したため、新聞社の経営規模がアメリカより大きい。販売部数の低下や広告収入の現象はあるとしても、全国各地で新聞社がばたばたと経営危機に陥る可能性は、現時点では、低い。しかし、調査報道を日本で主に担ってきたのは、新聞ではなく、雑誌である。アメリカの活字報道の新たな姿の模索は、日本のノンフィクションの今後を考える際に、参考となる。
新聞以上に雑誌が調査報道で成果を挙げた一因は記者クラブ制にある。雑誌はこの制度の外で活動する。言論統制は仕上げの段階に入る。1941年11月、政府は、すべての新聞社に「新聞統制会」への加盟や記者クラブの整理などを求める「新聞ノ戦時体制化ニ関スル件」を閣議決定する。記者クラブ自体はこれ以前にも存在する。1890年、第一回帝国議会の新聞記者取材禁止の方針に対して、『時事新報』の記者が在京各社の議会担当に呼びかけ、「議会出入記者団」を結成する。同年10月、これに全国の新聞社が合流し、「共同新聞記者倶楽部」と解消し、記者クラブ制が始まる。しかし、この統制のため、記者クラブの数は3分の1も減らされると同時に、自治も禁止されている。1941年12月、日米開戦後内閣情報局が「記事差し止め事項」を作成し、報道に対する管理統制を強め、政府は「新聞事業令」を公布し、新聞社を統合・削減し、「一県一紙」体制を確立させていく。戦後、記者クラブ制が復活する。これは政府や国会、行政機関、自治体、各種組織・団体などを担当する記者他とがお互いの親睦を高めるための自治会である。もちろん、これは建前であって、実態はそうではない。特定の報道機関のみが参加でき、ニュース・ソースとの接触をほぼ独占し、一見さんお断りの極めて閉鎖的な制度である。現在の記者クラブは、戦時下に内務省指導によって結成された「日本新聞会」とは別組織ということになっている。だが、現行の制度は、日本新聞会の傾向を受け継いでおり、それ以前の自主的な記者クラブとは異なっている。言論統制の前は、登録制がなく、クラブと言うよりもサロンであって、相当ゆるやかな集合体であり、そもそも複数の会が併存し、一元的ではない。戦後の記者クラブにはこうした風通しのよさはない。現行の制度の下でも、実際、地方紙も含めて、傑出した調査報道も見られる。何事も工夫次第だ。記者クラブ制度の帰省がかかりにくいテーマや切り口を選べばよい。けれども、特定の個人が可能だったからと言って、その制度存続の根拠にはならない。近代的制度は個人の資質に依存しない。
昨今、逆の対応も見られる。記者クラブが担当組織から事情を説明され、承知していながらも、世論の流れに抗うのが恐くて、それを口にせず、批判に回る。これは世論が感情的に過熱しているときに怒り、その組織の対応は二つに分かれる。多勢に無勢として反論せず、それを甘んじて受けるか、とりあえず、ほとんど無意味な形だけの態勢をとるかのいずれかである。これらは刑事司法や安全保障などあまり一般に知られず、むしろ、見せないようにしてきた領域でしばしば生じる。記憶に新しいところでは、記者クラブ所属のすべての報道機関がそうだったわけではないけれども、2009年4月に北朝鮮が実施した飛翔体発射実験の際の自衛隊による対応がそれに相当する。
調査報道がすたれれば、それを喜ぶ連中も少なくない。そこで、アメリカでは調査報道にとり組むNPOが登場し、成果を挙げ始めている。寄付によって運営し、ネットで記事を配信している。ニューヨークの「プロパブリカ(ProPublica)」やワシントンDCの「共性保全センター(The Center for Public Integrity)」などがその一例である。こうしたサイトでは分かりやく読みやすい記事ではなく、むしろ、読み応えがある入り組んだ長文の方に人気がある。いずれもプロのジャーナリストが記事を書き、法的トラブルにも対応できる専門家を用意している。正確性・公正性・公共性において、ブログよりもはるかに高い基準を設けている。長文を読むのに適したモニターやフォントの開発が進められているが、長年に亘って蓄積されてきた書籍のレイアウトには及ばない。また、電子書籍の端末もまだまだ高額である。しかし、技術革新がそれを解決するに違いない。もし成功すれば、調査報道の重要性が再認識されるだけでなく、それを可能にする新たなビジネス・モデル確立のきっかけとなるだろう。
プロパブリカのポール・スタイガー(Paul Steiger) 編集長は、同組織のホームページにおいて、「インターネット時代において、出版のプラットフォームの数と種類は爆発的に増加している。しかし、こうした新しいものので、オリジナルにあたる詳細な報道は皆無に等しい。要するに、意見の情報源は激増しているが、その意見の元になっている事実の情報源は縮小している(The number and variety of publishing platforms are exploding in the Internet age. But very few of these new entities are engaged in original, in-depth reporting. In short, sources of opinion are proliferating, but sources of facts on which those opinions are based are shrinking)」と言い、プロパブリカの必要性を説いている。ジャーナリストは専門職であり、そのリテラシーを体系的・総合的に習得していなければ、記事を書けるものではない。ウェブは、そのため、オピニオン・ジャーナリズムに舞い戻っている。
こうしたネットの現状に対して、調査報道に携わるジャーナリストのみならず、タブロイドからも憤りの声が伝わってくる。SBCが2009年6月30日の『ナイトライン(Nightline)』で特集したように、マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)の死に際して、アメリカの各ゴシップ誌は誌上にこだわらず、競ってウェブで最新情報を発信している。しかし、記者はいずれもアカデミズムでジャーナリズムの学位を得ている。対象がバラク・オバマ(Barack Obama)であるかブリトニー・スピアーズ(Britney Spears)であるかが違うだけで、手法に違いはない。持ちこまれる大量の情報を精査し、裏づけをとった上で、報道する。情報を垂れ流すことなどしないし、ジャーナリストとしてやってはいけない一線というものも心得ている。
確かに、インターネットは活字媒体のみならず、映像媒体の報道にも変化を促している。2009年に実施されたイランの大統領選挙では、投票結果の発表以降、当局は外国メディアの取材活動を厳しく規制し、報道はウェブ上に投稿された写真や動画に頼っている。報道ならびに分析の情報源はYou TubeやTwitterである。ハバナ訪問中に偶然革命に遭遇した写真家マリ・エレーヌ・カミュ(Marie Hélène Camus)の手記のようなノンフィクションはもはやありえない。
ジャーナリズムは発達するにつれ、煽動性の問題が大きくなってきたが、ネット社会はそれを頻繁にしている。送り手と受けて手の間で、感情の中でも「怒り」と「驚き」がイメージを共有しやすい。これらは情動と関係し、適応行動に直結する。この二つの感情は明確な対象によって引き起こされ、交感神経を強く刺激し、情報処理に割りこんだり、その資源を奪ったりして、思考力や判断力を低下させる。ある特定の刺戟に対する反応であるため、急激に精神状態の変化が自覚され、生理的喚起と表情表出が伴うが、一時的な感情に過ぎず、遺族性は弱い。世界的に評価を受けている日本の芸術家や作家、演劇人は、必ずと言っていいほど、作品に「驚き」を用いているが、それは受け手とイメージを共有する最も安易かつ確実な手口だからである。現在でも、具体的な例を挙げるまでもなく、マスメディアやインターネット上には怒りや驚きを引き起こす対象に溢れ、人々がそれにより衝動的・独善的な行動に走ることも少なくない。
言うまでもなく、活字媒体ならではの調査報道も厳然としてある。ウォーターゲート事件(Watergate Scandal)におけるボブ・ウッドワード(Bob Woodward)とカール・バーンスタイン(Carl Bernstein)の姿勢は、活字ジャーナリズムでしかありえない。情報提供者を「ディープ・スロート(Deep Throat)」のままで、その映像なしで報道し続けれるのはテレビでは難しい。まさかリンダ・ラヴレース(Linda Lovelace)の画像を放映し続けるわけにもいかないだろう。テレビは協力者に撮影を同意してくれないと、その説得力を十分に発揮できない。他方、活字では匿名ですむ。活字媒体による調査報道は依然として有効である。活字媒体の調査報道ならびにノンフィクションは、新たな映像メディアが登場すると、その特性を文章表現に生かしつつも、自らを見直す契機としている。
インターネットに直面したジャーナリズムはその意義をとり入れ、これがなければ、情報収集ができないために、書き得ない記事も生まれている。いわゆるカニングハム事件(Cunningham Scandal)をすっぱ抜き、06年のピューリッツァー賞(The Pulitzer Prize)に輝いたマーカス・スターン(Marcus Stern)のレポートがその一例である。一連の事情は、スターンなどがまとめた『ロング・スタッフ(The Wrong Stuff)』(2007)に詳しい。日本語では分かりにくいけれども、このタイトルは、もちろん、『ライト・スタッフ』のもじりである。
カリフォルニア州サンディエゴの新聞などに記事を配信している通信社コプレイ・ニュース・サービス(Copley News Service)のマーカス・スターンは、2005年5月8日、サンディエゴ選出の共和党下院議員ランディ・カニングハム(Randy "Duke" Cunningham)がサウジアラビアを旅行したという新聞記事を目にする。両者の結びつきがあまりにも意外だったため、ひっかかりを感じ、彼の住所をグーグルで検索し、その衛星画像もクリックしてみる。すると、彼と妻の収入だけではとても購入できるとは思えない豪華な邸宅がモニターに表示される。そこで、レクシスネクシス(lexisNexis)のサイトにアクセスし、不動産登記の売買記録を当事者の名前を入力して、議員の旧宅を調べてみると、「ニューハンプシャー・アベニュー1532番地(1523 New Hampshire Avenue)」という名称の企業に売却されていたことが判明する。そのふざけた名前の会社はそれを購入直後に売りに出し、8ヵ月後、70万ドルの損が生じるにもかかわらず、売却している。これは、事実上、議員への利益供与だ。ネバダ州で登記されたこの企業の社長ミッチェル・ウェイド(Mitchell Wade)はMZMのトップでもある。MZMのホームページによると、最近、国防総省との取引によって急激に業績を伸ばしている。しかも、議員は国防歳出小委員会のメンバーである。わずか半日、ネットで合法的に公開されたサイトを閲覧するだけで、下院議員と業者との汚職を疑われる親密な関係が見つかる。スターンはこのクサイ話の裏づけ取材を行い、05年6月12日、『サンディエゴ・ユニオントリビューン(The San Diego Union-Tribune) 』がこの贈収賄疑惑を一面トップで伝える。
この時点では、たんなるローカル・ニュースにすぎなかったが、TMPがこの記事をとり上げたことで一気に全米規模に拡大する。「トーキング・ポインツ・メモ(Talking Points Memo: TPM)」は2000年に開設された政治ブログで、「マックレーカー」を自認し、分析力が評判となり、読者数が急増、広告収入で記者を雇い、ニューヨークに事務所を構え、調査報道にも力を入れている。これをきっかけに、サンディエゴ地区の連邦検事キャロル・ラム(Carole Lam)が捜査に乗り出し、カニングハム下院議員とMZM社長を贈収賄容疑で起訴、さらに別の業者ADCSやCIAのナンバー3のカイル・フォゴ(Kyle "Dusty" Foggo)にも手が広がった途端、政府から彼女に圧力がかかる。07年1月12日、それを『サンディエゴ・ユニオントリビューン』とTPMが伝える。追い討ちをかけるように、同月16日、TPMは、少なくとも全米8地区で、連邦検事の突然の辞任・解任があったとスクープする。サンディエの記事を読んだ読者から、不自然な連邦検事の交代が地元紙で報じられているとメールが寄せられ、それを確認した上で、TPMがまとめ上げている。大手メディアが後追いし、07年9月、アルベルト・レイナルド・ゴンザレス(Alberto Reynaldo Gonzales)司法長官は辞任に追い込まれる。08年、TPMは、この件により、ジョージ・ポーク賞(The George Polk Awards)に輝いている。
こうした動向は日本のノンフィクションの今後を考える際にも参考となる。実際、日本でもネットの普及は「意見」を急増させたが、「事実」は恐ろしく貧弱である。ただし、マーカス・スターンのケースは非常に示唆的である。素人がネット・サーフィンに長けているとしても、こうした画期的な記事が書けるわけではない。ジャーナリストとしてのリテラシーを身につけ、現場で養ってきた勘やノウハウが必要である。一例を挙げると、ノンフィクション執筆には統計が必要となるケースが多々あり、そのリテラシーが不可欠である。統計に関する数学的知識だけではない。そのカテゴリーは、意図や目的に従って便宜上の条件によって分類される。平成20年版『犯罪白書』を見ると、「刑法犯の主要罪名別認知件数・発生率・検挙件数・検挙人員・検挙率」という表が掲載されている。「認知件数」である以上、カウントできていないケースもあることになる。また、その「殺人」の認知件数は1199であるが、これには「殺人未遂」や「殺人予備」も含まれている。作家は、問題に応じて、それに適合するデータを統計からを読みとれなければならない。活動の場が雑誌からネットに変わるとしても、読者をうならせるようなノンフィクションが登場するには、プロのジャーナリストの能力を持った人材を育成しなければならない。
これだけ「意見」と「事実」がアンバランスなる社会になると、必要とされているのはジャーナリストのリテラシーだけではない。今日あらゆる分野において細分化・専門化・高度化が進んでいる。欠陥製品ヤ偽装食品などが内部告発によって初めて発覚するケースが後を絶たないように、外部から眺めて、内部をうかがうことは不可能に近くなっている。ノンフィクションの読者には門外漢も少なくない。論文のように、専門家だけを相手にしているわけではない。これからのノンフィクション作家には、その内部で共通に認識し、継承されている固有のリテラシーに通じていることが求められる。従来、科学リテラシーに疎い作家が科学に関するノンフィクションを書いたり、映画のリテラシーを理解していないまま、映画をめぐる作品を執筆したりするケースが見られる。しかし、それらは科学や映画をわかったつもりにさせるだけで終わる。こうした現状である以上、ノンフィクションや記事を読者も鵜呑みにせず、自分で調べてみる必要がある。
インサイダーにとってリテラシーは暗黙知として身についている。けれども、アウトサイダーにはそれが分からない。暗黙知を明示化する必要がある。リテラシーから語ることは内部の心情を代弁することではない。佐藤学東京大学教授は、理解を「たんに自分が『できる』レベル」・「できたことが『説明できる』レベル」・「『教えられる』レベル」・「『相手の学びを支援できる』レベル」の四つに分類している。この中で、一番最後が最も高度である。自分とは違う考え方を理解しなければならない以上、この一番高いレベルを目標に設定する。これが学びあう関係をつくることであり、それは対等である。暗黙知を明示化でき、それを他者に納得させられるとき、人間関係は対等になる。近代の申し子であるノンフィクション執筆にも同様のことが言える。社会的他者にそれぞれの特有のリテラシーを理解しにくいであろうことを推測しつつ納得させられる。それを作品上で示すのがノンフィクションの将来像である。そうなれば、ニュー・ジャーナリズムのパーソナル・ジャーナリズムは困難であり、協同作業で記事や作品を作成する「協同ジャーナリズム」、すなわち「コラボレーティブ・ジャーナリズム(Collaborative Journalism)」が主流とならざるを得ないだろう。それは、かつてのコーポレイト・ジャーナリズムと違い、メンバーが水平的な関係にある。
日本の新聞を開くと、「『相手の学びを支援できる』レベル」を目指しているのかはなはだ疑問を抱かずにはいられない。具体的なケースを一つ一つ挙げることは差し控えるが、海外の事件や出来事に関する新聞記事を読むと、固有名詞に関する記述の不徹底さが目につく。この記事が伝える内容についてもっと詳しく知りたいとインタ-ネットで検索しようにも、固有名詞がろくに触れられず曖昧だったり、あってもスペルが記されていなかったりすることがざらである。その反面、統計的数字は正確なことが多い。そもそも、外国語には、カタカナ表記では判別しにくかったり、フランス語の”h“を始めとして発音されない文字もあったりするのだから、活字メディアはスペルを併記することは必須である。記事で言及されたアラビア語を読者が自分で調べようと思っても、記述が不十分で、工夫してキーワードを考えないと、肝心の情報にたどり着けない。統計的数字は固有名詞がわかれば、検索エンジンから簡単にリサーチできるのに、そちらの間違いは少ない。「相手の学びを支援できる」ことを念頭に入れているとはとても思えない。この事情は、正直、ノンフィクションでもしばしば見られる。
これは、日本語を外国人に教えることをイメージすると、わかりやすい。外国人に「こそあど言葉」の使いわけを尋ねられて、自分はネイティヴ・スピーカーだから、間違えない。しかし、その使い分けの論理的説明を求められると、答えに窮する。おまけに、彼らは、多くの場合、日本語と異なる言語学的特性の言語のネイティヴ・スピーカーであり、どのようにわかっていないのかということを推測できない。普段は情緒的な言動を繰り返しているとしても、いざ他者となると、人は論理主義者にはや代わりする。思いこみや思いつきの答えでは、矢継ぎ早に、質問が投げかけられ、すぐに矛盾が露呈し、不審の目で見られてしまう。日本語ができることと、それをわかっていることと、他者に教えられること、納得させられることとは違う。ちなみに、「これ」は話者のテリトリー内にあるもの、「それ」が相手のテリトリー内にあるもの、「あれ」はいずれのテリトリーにも属していないものを指す際に用いられる。
世界各地で日本語を教えた経験を持つ金田一秀穂杏林大学教授は、『「汚い」日本語講座』の中で、暗黙知と明示知の関係について次のように述べている。
その辺の日本人が、自分は日本語が出来るから日本語が教えられるんだ、と思ったら大間違いである。日本語を教室で習ったことがなく、相手の言語も分からない。何をどのようにしたら習ってもらえるのか、まったく分からない。
何より、日本語母語者は、自分の言葉をうまく説明できない。出来るのだけれど、間違えないのだけれど、それを言語化する、明示化することが出来ない。
不思議なことである。自分の頭脳が全て行っていることなのである。ただ、自分の中で働いているところを、自分が意識化出来ない。自分の頭の中に謎がある。探検すべきところ、調査すべきところは、自分の頭の中なのである。どこかへ行って調べるわけでもなく、何かの本を飛んで学ぶのでもない。常に自分と不即不難の状態にある頭の中のことが、うまく分からない。はっきりしない。
暗黙知というのは、そのようなものである。しかし、だからと言って、暗黙知よりも明示知が優れているというわけでもない。暗黙のうちに分かっていることは、そこに豊かな謎が控えているとも考えられる。まだ明示化されていないものの中に、驚くべき発見が隠されているかもしれないのである。少なくとも、直感的に、正しいか間違っているかの判断が出来る。
暗黙知で獲得された言語は、自分で直感的な判断が可能である。習った言葉は、正しいかどうかについて調べなければ分からない。文法書や辞書や語学教師ニラよらなければならない。母語については、自分だけで判断出来る。しかも、明示知によって学習された言語は、学習した範囲のことしか分からない。どうしても限界がある。獲得された言語は、人によって違いはあるけれど、その言語能力で表現出来る限界まで行くことが出来る。いつの間にか出来てしまう。暗黙知がいいか、明示知がいいか、どちらもどちらなのである。
私には、自分の中を探検することが面白い。本を読まなくても、どこかへ行かなくても出来る。しかも、分からなかったことが分かるようになる。その楽しさがあるので、こういう勉強をしているのである。
過去30年の間、日本のノンフィクションは自分のしていることについて暗黙知のままですごしてきたが、インターネットの普及や雑誌の退潮によって置かれた環境は激変し、自らを問い直す時期に来ている。ノンフィクションにおいて重要なのはリアリティであるけれども、それを再検討しなければならなくなっている。90年代に入ってイデオロギー対立の時代が終わり、自分の語る物語にのみリアリティを感じる風潮が目立つようになる。村上春樹の物語が世界的に受容されているのはその一端である。イデオロギーを通じてリアリティを覚えるのではなく、アイデンティティによって獲得する。それは著しく主観的であり、自意識がすべてに対して優位に立っている。しかし、自分の思いつきや思いこみに支配されているにすぎない。一言で言うと、社会性がない。イデオロギーが抽象的だとすれば、アイデンティティは恣意的である。むしろ、生のリアリティは、具体性を追求することで、立ち現われる。対象領域のリテラシーだけでなく、ノンフィクション自身のリテラシーも明らかにしつつ、作品が書かれる必要がある。この最も基本的なスタイルはたんに取材過程を再現するだけでなく、メディア・リテラシーを語りながら、報道することである。読者のリテラシーを高めないノンフィクションは自己完結してしまう。今、ノンフィクションをめぐる暗黙知を明示化して、新たなノンフィクションが生まれるために「相手の学びを支援できる」ことに向かう作家が待ち望まれている。
この頃の文学界は停滞してゐるとか、何かが待望されてゐるとかいふことが言はれる時、その背後には、古いものは駄目で新しいものがいいのだといふ考へが潜んでゐる。その古い所で、畳を換へるやうな話であるが、たださういふ気がするのでそんなことを思つて見るといふ種類のかうした態度を誰も疑はうとしない為に文学で実際に新しいものが無視される結果になる。
凡ては言葉の問題に戻つて来る。本当に沈滞といふものがあつて、それが長く続いた後に言葉らしい言葉に出会つたならば、その時に受ける印象が新しいといいふものであり、それが新しさの定義、或は尺度にもなる。そしてその新しさは失はれない筈である。(略)文学の世界では、新しくないものは文学ではないのである。
(吉田健一『新しいといふこと』)
〈了〉
参考文献
池内了、『似非科学入門』、岩波新書、2008年
石牟礼道子、『苦海浄土―わが水俣病』、講談社文庫、2004年
犬丸義一編、『職工事情』城中下、岩波文庫、1998年
井上一馬、『アメリカ映画の大教科書(上)』、新潮選書、1998年
宇佐美滋、『アメリカ大統領を読む事典』、講談社+α文庫、2000年
遠藤泰生、『アメリカの歴史と文化』、放送大学教育振興会、2008年
大泉実成、『説得―エホバの証人と輸血拒否事件』、講談社文庫、1992年
小栗康平、『映画を見る眼』、NHK出版、2005年
柏倉康夫他、『日本のマスメディア』、放送大学教育振興会、2007年
鎌田慧、『自動車絶望工場』、現代史出版会、1974年
河合幹雄、『日本の殺人』、ちくま新書、2009年
金田一秀穂、『「汚い」日本語講座』、新潮新書、2008年
小林多喜二、『蟹工船・党生活者』、新潮文庫、1954年
佐藤学、『習熟度別指導の何が問題か』、岩波書店、2004年
沢木耕太郎、『敗れざる者たち』。文春文庫、1979年
篠田一士、『ノンフィクションの言語』、集英社、1985年
鈴木明、『リリー・マルレーンを聴いたことがありますか 』、文藝春秋、1988年
スポーツグラフィック・ナンバー編、『濠打列伝』、文春文庫ビジュアル版、1986年
立花隆、『田中角栄研究─全記録』上下、講談社文庫、1982年
玉木正之編、『プロ野球大事典』、新潮文庫、1989年
常盤新平他編、『アメリカ情報コレクション』、講談社現代新書、1984年
野田正彰、『喪の途上にて―大事故遺族の悲哀の研究』、岩波書店、1992年
野村進、『コリアン世界の旅』、(講談社+α文庫、1999年
平田オリザ、『演技と演出』、講談社現代新書、2004年
廣津和郎、『新版 松川裁判』、木鶏社、2007年
福田収一、『デザイン工学』、放送大学教育振興会、2008年
細井和喜蔵、『女工哀史』、岩波文庫、1980年
松本仁一、『カラシニコフ』、朝日新聞社、2004年
村上春樹、『アンダーグラウンド』、講談社文庫、1999年
横山源之助、『日本の下層社会』、岩波文庫、1985年
吉岡忍、『墜落の夏―日航123便事故全記録』、新潮文庫、1989年
レイチェル・カーソン、『沈黙の春』、青樹簗一訳、/新潮文庫、1974年
ノースロップ・フライ、『批評の解剖』、海老根宏他訳、法政大学出版局、1980年
フレデリック・フォーサイス、『ビアフラ物語―飢えと血と死の淵から』、篠原慎訳、1982年
ギュンター・ヴァルラフ、『最底辺―トルコ人に変身して見た祖国・西ドイツ』、マサコ・シェーンエック訳、岩波書店、1987年
チャールズ・ダーウィン、『種の起原』上下、八杉龍一訳、岩波文庫、1990年
ヴィクトル・ファリアス、『ハイデガーとナチズム』、山本尤訳、名古屋大学出版会、1990年
アグネス・スメドレー、『中国の歌ごえ』上下、高杉一郎訳、ちくま文庫、1994年
ブルース・ポリング、『だからスキャンダルは面白い』、仙名紀訳、文春文庫、1997年
デイヴィッド・ハルバースタム、『ベスト&ブライテスト』上中下、浅野輔訳、朝日新聞社、 1999年
ジョン・ハワード・グリフィン、『私のように黒い夜―肌を焼き塗り黒人社会へ深く入った白人の物語』、平井イサク訳、ブルースインターアクションズ、2006年
『世界ノンフィクション ヴェリタ』全24巻、筑摩書房、1978年
『新書アメリカ合衆国史』全3巻、講談社現代新書、1988~89年
『吉田健一集成』2、新潮社、1993年
『世界の文学』35・50、朝日新聞社、2000年
『世界の歴史』21、中公文庫、2008年
DVD『エンカルタ総合大百科2008』、マイクロソフト社、2008年
『文藝春秋』1974年11月号、文藝春秋
『現代思想』1988年4月号、青土社
Capotem T. In Cold Blood. Vintage. 1994
Hersey, J. Hiroshima. Knopf. 1985
Gunther, J. Inside Europe. Rev. ill. ed. Hamish Hamilton. 1937
Nader, R. Unsafe at Any Speed. Grossman Publishers.1965
Price, S. Digging Up Dirt: The Muckrakers. Heinemann Library. 2008
Rutherfurd, L. John Peter Zenger: His Press, His Trial And a Bibliography of Zenger Imprints . Lawbook Exchange Ltd. 2006
Stern, M. Calbreath, D. Condon Jr. G. E. & Kammer, J. The Wrong Stuff: The Extraordinary Saga of Randy "Duke" Cunningham, the Most Corrupt Congressman Ever Caught. PublicAffairs. 2007
Talese, G. Fame and Obscurity. Laurel. 1986
Wolfe, T. The New Journalism. ed, Tom Wolfe and E. W. Johnson. Picador. 1975
Wolfe, T. The Right Stuff. Picador USA. 2008
佐藤清文、『日本型マスメディア万能時代の終焉』、2008年
http://www.geocities.jp/hpcriticism/oc/jmassmedia.html
佐藤清文、『持続可能社会とアナトミー─諷刺の復権』、2008年
http://hpcunknown.hp.infoseek.co.jp/unpublished/sustainable.html
佐藤清文、『経済と文学─戦後経済と日本文学』、2009年
http://hpcunknown.hp.infoseek.co.jp/unpublished/el.html
MacDonald, D. “Parajournalism, or Tom Wolfe & His Magic Writing Machine”. New York Review of Books. Volume 5, Number 2 · August 26, 1965
http://www.nybooks.com/articles/article-preview?article_id=12793
Jacob Riis Photographs
http://images.google.com/images?hl=en&q=jacob+riis&gbv=2
ABC.com
asahi.com
The Center for Public Integrity
http://www.publicintegrity.org/
The George Polk Awards in Journalism
http://www.brooklyn.liu.edu/polk/index.html
毎日jp
法務省
MSN産経ニュース
NHKオンライン
日本ペンクラブ電子文藝館
http://www.japanpen.or.jp/e-bungeikan/home.html
NIKKEI NET
PBS
ProPublica
The Pulitzer Prizes
http://www.pulitzer.org/index.html
Talking Points Memo
http://www.talkingpointsmemo.com/
YOMIURI ONLINE
47NEWS