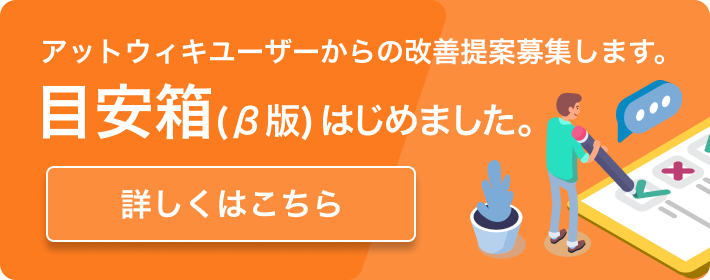PDF/EPUB 文学再入門 太宰治リンククリエイティブコモンズ版
喜劇の解読
─太宰治の『斜陽』
Seibun Satow
Oct, 31. 1992
「ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの」。
太宰治『女生徒』
「美しく生きることは、美しく死ぬことよりも難しい」。
アンドレ・ジッド
太宰治(一九〇九─四八)は、日本近代文学において、最も評価のわれる作家の一人である。あるものにとっては自らの代弁者であるが、逆に、別のものにとってはただ嫌悪の対象でしかない。こういう見解の相違は優れた書き手にはよくあるけれども、太宰の場合、いささか奇妙な事態を引き起こしている。と言うのも、そういうタイプの書き手は、肯定的であれ否定的であれ、文学史に何らかの影響を与えるものであるが、一方、太宰は文学史に何ものかを後世に残しているとは見受けられないからである。
こうした状況は太宰の作品の読まれ方に負うところが大きい。『思い出』(一九三三)から始まる自伝的色彩の強い小説に太宰の私生活に関する出来事を見出すことは可能であり、『人間失格』(一九四八)に至るまで何度となく言及されている家庭の事情や父親の社会的地位、兄弟との関係は、太宰にとって、重要であったことは認められる。彼は全体としての小説の出来以上に、作品に自画像を描くことに熱心になりすぎていることも少なからずあるくらいなのだ。彼の作品には自伝的要素が強いため、登場人物に対して感情移入する読み手にとって、太宰に親近感を抱くことが多々ある。フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーやジェームズ・ジョイスの作品の登場人物を鑑賞するのと違って、読み手は、表われてくる人物を通じて、太宰自身を発見し、それと一体化できたときに、感動を覚える。逆に、太宰の作品は親近感によって成立しているので、彼を見出せない中心的人物は読み手にとって極めてフラストレーションを残してしまう。つまり、読み手は太宰の作品を読むことによって、新たな何ものかを自らの経験に加えるのではなく、すでにある経験をただ追認するだけである。
このような太宰をめぐる受容の伝統は彼を神話的な書き手としている。太宰は、三島由紀夫とならんで、その死が最も神話化されている作家の一人である。太宰の命日には、特に女性を中心とした熱心なファンが、桜桃忌(桜桃祭)として三鷹にある禅林寺へ墓参りしている。これは、文学にとって、感情移入は文学的感染症である以上、健康的な事態ではない。文学における神話は精神的弱者から見られた世界解釈として機能しているにすぎない。神話作用は、確かに、われわれには不可避的であるけれども、太宰の神話の場合、それをあまりにも無批判的に受けいれすぎている。太宰の作品にある自伝的要素は否定できないし、それに焦点を合わせる読みは許されて然るべきとしても、その読解法は彼の可能性を限定しすぎている。それゆえ、太宰の作品における限界と可能性を指摘する必要がある。
伝記的事実をとりあえず括弧にいれて、太宰の作品を読んでみると、彼が非常に言語に関して繊細な書き手として顕在化してくる。
彼は、作品としては失敗作と見てよい『千代女』において、言葉の取捨選択について次のように書いている。
文章には描写が大切だ、描写ができていないと何を書いているのかわからない、等と、もっとも過ぎるようなことを、小さな手帖を見ながら、おっしゃって、たとえばこの雪の降るさまを形容する場合、と言って小さな手帖を胸のポケットにおさめ、窓の外で、こまかい雪が芝居のようにたくさん降っているさまを屹っと見て、雪がざあざあ降るといっては、いけない。雪の感じが出ない。どしどし降る、これも、いけない。それでは、ひらひら降る、これはどうか。まだ、足りない。さらさら、これは近い。だんだん、雪の感じに近くなってきた。これは、面白い、とひとりで首を振りながら感服なさって腕組みをし、しとしとは、どうか、それじゃ春雨の形容になってしまうか、やはり、さらさらに、とどめを刺すかな? そうだ、さらさらひらひら、と続けるのも一興だ。
これは少女にある男が文章を教えているシーンだが、太宰がセンシティヴに言語に接触していることがよく示されている。ここだけではなく、『人間失格』の「第三の手記」二において、葉蔵と堀木が「喜劇名詞、悲劇名詞の当てっこ」、そして「対義語の当てっこ」のゲームが描かれている。「たとえば、汽船と汽車はいずれも悲劇名詞で、市電とバスは、いずれも喜劇名詞、なぜそうなのか、それのわからぬものは芸術を談ずるに足らん、喜劇に一個でも悲劇名詞をさしはさんでいる劇作家は、すでにそれだけで落第、悲劇の場合もまた然り」。この言語との関係は、デリケートを通りすぎて、むしろ、強迫観念的である。もっとも太宰の悲劇と喜劇の区別は農村と都市、苦痛と快楽のそれに準じているにすぎないのだが。こういう記述がありながらも、『思い出』において、作家になろうとする動機はそこに自分と「同類」がいると思われたからだとして書かれているが、太宰の自伝的作品の中に作家になろうといかなることをしたのかという過程や創作行為が彼に何をもたらしているのかという内的充足度はほとんど描かれていない。つまり、彼にとって文学的行為とは制作と言うよりも、言葉に対する姿勢を意味している。短歌のほうがふさわしかったのではないか、なぜ小説という文学ジャンルを選択したのかという理由がわからなくなるほど、雲を見つめすぎて青空が見えないという姿勢が創作行為を台なしすることは、太宰には、少なからずある欠点は認められるとしても。
太宰治文学の可能性と限界を明らかにするために、数多い彼の作品の中から、代表的な作品である『斜陽』(一九四七)を中心に読解することを選択する試みに、もはや説明は不要であろう。
『斜陽』は次のような印象的な記述から始まっている。
朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、
「あ」
と幽かな叫び声をお挙げになった。
「髪の毛?」
スウプに何か、イヤなものでも入っていたのかしら、と思った。
「いいえ」
お母さまは、何事も無かったように、またひらりと一さじ、スウプを奥地に流し込み、すましてお顔を横に向け、お勝手の窓の、満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじ、スウプを小さなお唇のあいだに滑り込ませた。ヒラリ、という形容は、お母さまの場合、決して誇張では無い。婦人雑誌などに出ているお食事のいただき方などとは、てんでまるで、違っていらっしゃる。
ここで「ヒラリ」という言葉は太宰の言語に対するオブセッションを感じさせる。この世界は視覚的表現によって背景がとられているが、「ヒラリ」が聴覚をその世界に導入する。「ヒラリ」という一つの音だけがあるため、それが聴覚的な効果として読むものに残される。「ヒラリ」の出現は、聴覚に働きかけるのにとどまらず、さらに世界に対する視線を知覚作用から想像作用へと転換する。「ヒラリ」という音は具体的なものではなく、内的なものであり、朝日が徐々にあがり、光によって暗闇の世界に広がりを与えていくように、心的なものを平面から空間化する。こうした表現は抽象的・理論的な認識ではなく、直観的な認識によって構成されている。言葉の意味ではなく、その言葉がいかに機能するのかということに、太宰にとっては、関心がある、すなわち解釈学的な様式よりも、詩学的様式に集中している。つまり、『斜陽』では太宰の言語に関する繊細さがこのように冒頭から登場してくる。
『斜陽』は太田静子の書いた日記や彼女との関係、山崎富栄との交流をもとに、アントン・チェーホフの『桜の園』をモチーフとして書かれた作品である。太宰の作品は三つの時期にわけられている。初期は『晩年』や『二十世紀旗手』、『魚服記』など実験的な作品群の時期、中期は『津軽』や『走れメロス』、『富嶽百景』など私小説的な作品と古典を土台にした作品群の時期、後期は『冬の花火』や『トカトントン』、『人間失格』など現代を舞台にし、時代の雰囲気を反映させた作品群の時期である。それぞれ戦前・戦中・戦後に対応している。彼は、一九三三年から足かけ十五年の間、太宰治のペンネームを使って作家生活を送っていたわけだから、『斜陽』は晩年の作品にあたる。太宰は、確かに、戦争期にも『右大臣実朝』や『お伽草子』など優れた作品は書いているが、それらは彼を神話化させるには至っていない。太宰の神話作用は無頼派の一人として書いた『斜陽』のジャーナリスティックな成功が不可欠である。「太宰文学の集大成」(奥野健男)である『斜陽』を読解することが彼の文学の限界と可能性を明らかにする一歩にほかならない。
太宰に最も否定的な評価をくだしている作家の一人である三島由紀夫は、『私の遍歴時代』において、『斜陽』を次のように批判している。
私も早速目をとおしたが、第1章でつまづいてしまった。作中の貴族とはもちろん作者の寓意で、リアルな貴族でなくてもよいわけであるが、小説である以上、そこには多少の「まことらしさ」は必要なわけで、言葉づかいといい、生活習慣といい、私の見聞していた戦前の旧華族階級とこれほどちがった描写を見せられては、それだけでイヤ気がさしてしまった。貴族の娘が、台所を「お勝手」などという。「お母さまのお食事のいただき方」などという。これは当然「お母さまの食事の召上り方」でなければならぬ。その母親自身が、何でも敬語さえつければいいと思って、自分にも敬語をつけ、
「かず子や、お母さまがいま何をなさっているか、あててごらん」
などという。それがしかも、庭で立ち小便をしているのである。
この敬語の問題は『斜陽』の発表当時からかなり議論の的になっている。この奇妙な敬語が、印象的な食事のシーンから始まる『斜陽』の出来を損ねていることは、否定できない。「戦前の旧華族階級」をよく見聞してきた平岡公威こと三島由紀夫が言うように、『斜陽』において、確かに、尊敬語と謙譲語、丁寧語が混乱して用いられているし、また何でも「お」をつければ敬語になるものでもないのに、やたらと「お」を接頭している。ただし、「旧華族階級」ではなく、杉山画伯の娘と一緒に疎開していたある女性によれば、戦前の山の手の住人の中には、「ございます」言葉を用いたり、「お御飯」というように、何にでも「お」をつけたりする女性がいなかったわけではない。このことから津軽の大地主の子である津島修治こと太宰治が敬語を知らないと思われても仕方がないだろう。余談だが、われわれは「色気」よりも、「お色気」という言葉のほうが好きである。だが、逆に、あまりに稚拙すぎるにもかかわらず、このまま直すことなく発表させているのも解せないために、「テーブルスピーチの時に、あの野郎、ゴザイマスルという不可思議な言葉をつかったのには、げっとなった。気取るという事は、上品という事と、ぜんぜん無関係なあさましい虚勢だ」と登場人物に語らせていることから、作者は意図的に間違えたのではないかと推測させてしまうほどである。
一方、『斜陽』を太宰の「その死に近きころの作品」の中では「最もすぐれている」と評価しつつも、坂口安吾は、『不良少年とキリスト』において、その敬語に関して次のように述べている。
「斜陽」には、変な敬語が多すぎる。お弁当をお座敷に広げて御持参のウイスキーをお飲みになり、といったグアイに、そうかと思うと、和田叔父が汽車にのると上キゲンに謡をうなる、というように、いかにも貴族の月並みな紋切り型で、作者というものは、こんなところに文学のまことの問題はないのだから平気なはずなのに、実に、フツカヨイ的に最も赤面するのが、こういうところなのである。
まったく、こんな赤面は無意味で、文学にとって、とるにも足らぬことだ。
ところが、志賀直哉という人物が、これを採りあげて、やっつける。つまり、志賀直哉なる人物が、いかに文学者でないか、単なる文章家にすぎん、ということが、これによって明らかなのであるが、ところが、これがまた、フツカヨイ的に最も急所をついたもので、太宰を赤面混乱させ、逆上させたに相違ない。
もともと太宰は調子にのると、フツカヨイ的にすべってしまう男で、彼自身が、志賀直哉の「お殺し」という敬語が、体をなさんと言って、やっつける。
いったいに、こういうところには、太宰のいちばんかくしたい秘密があった、と私は思う。
彼の小説には、初期のものから始めて、自分が良家の出であることが、書かれすぎている。
そのくせ、彼は、亀井勝一郎が何かの中でみずから名門の子弟を名乗ったら、ゲッ、名門、笑わせるな、名門なんて、イヤな言葉、そう言ったが、なぜ、名門がおかしいのか、つまり太宰が、それにコダワッているのだ。名門のおかしさが、すぐ響くのだ。志賀直哉のお殺しも、それが彼に響く意味があったのだろう。
フロイドに「誤謬の訂正」ということがある。我々が、つい言葉を言いまちがえたりすると、それを訂正する意味で、無意識のうちに類似のマチガイをやって、合理化しようとするものだ。
フツカヨイ的な衰弱的な心理には、特にこれがひどくなり、赤面逆上的混乱苦痛とともに、誤謬の訂正的発狂状態が起こるものである。
太宰は、これを、文学の上でやった。
敬語の正否は文学の問題ではなく、作文や文法の問題であり、文学者たるものが論ずるべきではない。「文学にとって、とるにも足らぬこと」である敬語の問題にこだわる三島も、志賀直哉と同様、そのことによって「いかに文学者でないか、単なる文章家にすぎん、ということが、これによって明らかなのである」。実際、三島の作品にも、太宰の作品と同じように、「良家の出であることが、書かれすぎている」。三島の一連のパフォーマンスも──ボディ・ビルにしろ、楯の会にしろ、あの自決にしろ──「文学の上で」やられた──表面的には、太宰のそれとまったく逆であるとしても、構造上は同一の──「誤謬の訂正的発狂状態」にすぎない。自分のやろうとしたことをやられてしまったという口惜しさが三島の太宰嫌いの原因の一つになったと言ってさしつかえないだろう。三島自身も、『私の遍歴時代』において、「もちろん、私は氏の稀有の才能は認めるが、最初からこれほど私に生理的反応を感じさせた作家もめずらしいのは、あるいは愛蔵の法則によって、氏は私のもっとも隠したがっていた部分を故意に露出する型の作家であったためかもしれない」と告げている。
太宰は、自分自身が周囲のものとどれだけ異質であるかということを悟られないようにするために、躍起になる。彼の自己劇化は防衛手段である。彼はほんとうの自分は実はこうなのだと告白したい誘惑にかられることがあるけれども、結局、それに踏み切ることはない。彼には、カミング・アウトによって、傷ついてしまうことを何にもまして恐れるからである。太宰は、むしろ、最後まで素顔を隠し続けることを選ぶ。自己激化はもともとは彼の本質であったわけではないが、始めてしまうと、彼には欠くべからざる要素になってしまう。その仮面の身振りは周囲のものをいらつかせる。しかし、太宰は自己劇化をやめない。太宰にとって、仮面は素顔を隠すための演技である。一方、三島の仮面は作家になろうと思うものに何にでもなれる力を与えてくれるものだ。彼は太宰であれば、仮面の裏に隠そうとするものを押しつぶす。隠すものなど何もないと仮面の三島は言い放つ。三島は素顔そのものなどというものはなく、ただあるのは仮面だけであり、それこそが素顔なのだと考えている。素顔にとらわれすぎると、自分自身の可能性を限定してしまうことになる。三島にとっての仮面は素顔にするためのものである。つまり、太宰には仮面は盾であるのに対して、三島においての仮面は矛にほかならない。彼らは、それゆえ、矛盾した関係にある。
三島は後に天皇制賞賛と戦後民主主義批判へと向かうことになるわけだが、太宰は三島が彼を嫌悪していた時点にすでにそのことを書いている。
天皇の悪口を言うものが激増して来た。しかし、そうなって見ると私は、これまでどんなに深く天皇を愛して来たのかを知った。私は、保守派を友人たちに宣言した。
(『苦悩の年鑑』)
日本に於いて今さら昨日の軍閥官僚を攻撃したって、それはもう自由思想ではない。便乗思想である。真の自由思想かなら、今こそ何を措いても叫ばなければならぬ事がある。……天皇陛下万歳! この叫びだ。昨日までは古かった。しかし今日に於いては最も新しい自由思想だ。
(『パンドラの匣』)
一、十年一日の如き不変の政治思想などは迷夢にすぎない。二十年目にシャバに出て、この新現実に号令しようたって、そりゃ無理だ。(略)
いまのジャーナリズム、大醜態なり、新型便乗というものなり。(略)
一、戦時の苦労を全部否定するな。
一、いま叫ばれている何々主義、何々主義は、すべて一時の間に合せものなるゆえを以て、次にまったく新しい思潮の擡頭を待望せよ。
一、保守派になれ。保守は反動に非ず、現実派なり。チェホフを思え。「桜の園」を思い出せ。
一、若し文献があったら、アナキズムの研究をはじめよ。(略)
一、天皇は倫理の儀表として之を支持せよ。恋いしたう対象なければ、倫理は宙に迷うおそれあり。
(『一九四六年一月二十五日堤重久宛書簡』)
これらはいわゆる「太宰の天皇万歳発言」と呼ばれているが、太宰は時代通念に異議を唱えているのではなく、社会の共同性への同調に対する違和感を訴えている。これらの主張は錯綜し、それどころか、目茶苦茶でさえある。これは政治的アピールと言うよりも、美学的イデオロギーである。太宰にとって「自由思想」はそうした違和感を投影するヴィジョンを意味している。その感覚は、自らの存在の持続性を外界が危うくするものとして、太宰には感じられるわけだが、彼は一貫性・連属性が損なわれることに対して憤りを覚える。つまり、太宰は自分自身における持続性を天皇制に求めている。太宰において天皇制は政治思想などの情勢的・理論的問題ではまったくない。三島もそうである。特に、天皇を「倫理の儀表として」支持するという太宰の考えは、三島の『文化防衛論』における「文化の全体性」を代表する「究極の価値自体」としての天皇を想起させる。作品に登場する男性にこそ違いが見られるが、女性は極めて似ている太宰と三島も表裏一体の関係にあって、三島の太宰嫌いはむしろ近親憎悪である。
三島による評価はさておき、『斜陽』は太宰の作品の中で、タイトルだけでなく内容に関しても最も有名なものの一つであると同時に、最も優れた作品の一つと評価されている。確かに、あなどりがたい魅力はあるものの、安吾が『斜陽』を「ほぼ、M・Cだけれども、どうしてもM・Cになりきれなかったんだね」と言っているように、「誤謬の訂正的発狂状態」によって、「とるに足らない」敬語の問題以上に、決定的に、『斜陽』の出来を損ねている問題があるように思われる。
太宰の作品を「饒舌の文学」と批判し、彼に対する今日まで最良の批判者である寺山修司は、「肉体」(『幸福論-裏町人生版-』所収)において、『走れメロス』を例にとって太宰の作品について次のように述べている。
シラーの書いたもっとも美しい「友情論」の叙事詩「走れ、メロス」が、太宰治の手にかかって、たちまち書斎型の心情につくりかえられてしまった。死刑囚のメロスが、遠い故郷から、自分の死刑執行に間にあうように全力で野を越え、山を越えて走ってくる。それは自分の死刑のためではなく、身替りに牢に入っている石工のセリヌンティウスの信頼のためである。
メロスは、セリヌンティウスの命をかけた友情に応えようとして、力のかぎり刑場へかけこみ、あわや身替りの断頭台にのせられようとしているセリヌンティウスの、死刑執行の前に帰ってくることができる。
そこでシラーの叙事詩では、二人は顔を見あわせて、微笑しあって終っている。「微笑」のうちにかみしめられる、幸福といったものは、とても文字になるものではないし、言葉にしたとたんに、情念の「解説」に堕してしまうことが、シラーにはわかっていたのである。
ところが太宰治は、それに「弁解」を書きこむ。セリヌンティウスは
「メロス、俺を殴ってくれ。俺はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った。生まれてはじめて君を疑ったのだ。
もしかして、帰ってこないつもりだったのではないか、と。
だから、君が俺を殴ってくれなければ、俺は君を抱擁できない」
すると、メロスもあやまる。
「やはり、この三日の間、たった一度だけセリヌンティウスを疑ったのだ」と。
それから二人は、お互いを殴りあってから泣いて抱擁する。--この饒舌は、幸福を情緒的に解消してしまっている。それは一個の生きた太古の生物のように存在していた二人の共有の「沈黙」をお互いが取りのぞいて、幸福の思想化をさまたげてしまっている光景である。
言わんでもいいことをだらだらと語るメロスにしろ、セリヌンティウスにしろ、あまり友達になりたくない性格の男たちである。この程度の考えは誰でも、一瞬、頭をよぎったことくらいあるだろう。彼らのくどさにわれわれは辟易する。『走れメロス』はほとんど学園青春ドラマであり、われわれは気恥ずかしくて、笑いをこらえつつ、指の間から開いたほんのページをのぞき見てしまう。『走れメロス』を読んでいる最中に、どこからともなく、「大きな空に梯子をかけて、真っ赤な太陽両手でつかもう、誇りひとつを胸にかかげて、恐れを知らないこれが若さだ、そうとも、これが青春だ」と岩谷時子がつくった学園青春ドラマのテーマ『これが青春だ』を歌う布施明の元気な声が聞こえてきたとしても、それは幻聴ではない。メロスとセリヌンティウスではなく、松村雄基と山下真司のキャスティングの間違いではないのかと思ってしまうほどだ。登場人物は怪しげな独り言を口にし、その暗さで読み手をブルーにしてしまう。この独り言は内省ではなく、状況を説明するものであるから、果てしなく長い。逆に、独り言がないと、われわれは筋を見失ってしまうが、かりにそうなっても、この世の不幸は彼らのものであり、試練に耐えながら、目的を達成し、最後は、ごめんなさいごっこで決着をみるから心配はいらない。
『斜陽』においても、腰砕けになってしまうほどに素朴なお説教話となってしまった『走れメロス』と同様に、敬語の問題という無意味な「饒舌」を生んでしまうように、「弁解」の「饒舌」によって、「沈黙」をとりのぞいてしまっている次のような光景が目につく。
「よせ、よせ。ああ、あ、汝らは道徳におびえて、イエスをダシ使わんとす。チェちゃん、飲もう。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ」
駄目です。何を書いても、ばかばかしくって、そうして、ただもう、悲しくって仕様が無いんだ。いのちの黄昏。芸術の黄昏。人類の黄昏。それも、キザだね。
これは流行作家で飲酒に耽る上原の言葉であるが、『斜陽』の会話にはこのような体言止めが多い。体言止めは思考の飛躍を狙ったものではなく、沈黙が耐えられないので、とりあえず言葉を発してみた思考の停止程度のことにすぎない。
また、空虚で大袈裟な言葉が多すぎる会話は、内容も、さほどあるものではないことは次のような記述が告げている。
生きていたい人だけは、生きるがよい。
人間には生きる権利があると同様に、死ぬる権利もある筈です。
僕のこんな考え方は、少しも新しいものでも何でも無く、こんな当り前の、それこそプリミチヴな事を、ひとはへんにこわがって、あからさまに口に出して言わないだけなんです。
生きて行きたいひとは、どんな事をしても、必ず強く生き抜くべきであり、それは見事で、人間の栄冠とでもいうものも、きっとその辺にあるのでしょうが、しかし、死ぬことだって、罪では無いと思うんです。
思想? ウソだ。主義? ウソだ。理想? ウソだ。秩序? ウソだ。誠実? 真理?純粋? みなウソだ。
デカダン? しかし、こうでもしなけりゃ生きておれないんだよ。そんな事を言って、僕を非難する人よりは、死ね! と言ってくれる人のほうがありがたい。さっぱりする。けれども人は、めったに、死ね! とは言わないものだ。ケチくさく、用心深い偽善者どもよ。
結局、自殺するよりほか仕様がないのじゃないか。
このように苦しんでも、ただ、自殺で終るだけなのだ、と思ったら、声を放って泣いてしまった。
「ママ! 僕を叱って下さい!」
「どういう工合に?」
「弱虫! って」
「そう? 弱虫。……もう、いいでしょう?」
ママには部類のよさがある。ママを思うと、泣きたくなる。ママへおわびのためにも、死ぬんだ。
「僕を叱って下さい」というあたりから、みのもんたの人生相談に電話で出演した主婦の一言を思い出すのは、われわれだけではないに違いない。麻薬に溺れ自殺に向かうかず子の弟である直治の日記や遺書に見られるこれらの言葉の一部は、谷川俊太郎の『宙ぶらりん』や『うそだうそだうそなんだ』という詩において繰り返されることになるのだが、自殺を考えている自分自身を笑いながら観察してみたほうがいいのに、こんな通俗的なたわごとをわざわざ文学作品を通じて表現し、それを文学として認めているという実態は憂慮する必要があるだろう。「生が終って死が始まるのではなく、生が終れば、死も終るのだ。死はまさに、生の中にしか存在しないのだから」(寺山修司『幸福論』)。
I can't see you mama
But I can hardly wait
Ooh to touch and to feel you mama
Oh I just can't keep away
In the heat and the steam of the city
Oh it’s got me running and I just can't brake
So say you'll help me mama
Cos its getting so hard - oh
Now I can't keep you mama
But I know you're always there
You listen, you teach me mama
And I know inside you care
So get down, down here beside me
Oh you ain't going nowhere
No I won't hurt you mama
But it’s getting so hard - oh
Ha ha, ha ha ha ha, ha ha, argh
Ha ha, ha ha ha ha, ha ha, argh
Can't you see me here mama
mama mama mama please
Can’t you feel my heart
Can’t you feel my heart
Can’t you feel my heart oh
now listen to me mama
mama mama
You’re taking away my last chance
Don’t take it away
Can’t you feel my heart?
ha ha, ha ha ha, ha, argh
It's hot, too hot for me mama
But I can hardly wait
My eyes they're burning mama
And I can feel my body shake
Don’t stop, don't stop me mama
Oh make the pain, make it go away - hey
No I won't hurt you mama
But it’s getting so hard - oh
Now I can't see you mama
But I know you're always there
You taunt, you tease me mama
But I never never can keep away
It’s the heat and the steam of the city
Oh got me running and I just can't brake
So stay don't leave me mama
Cos its getting so hard - oh
Don’t go no no, don't go
No no no, don't go...
(Genesis “Mama”)
太宰はイマヌエル・カントが『純粋理性批判』で明らかにした「理性」の要求する次の「原則」をまったく顧みていない。
理性は与えられた条件付きのものに対して、条件の側における絶対的全体性を要求し、こうしてカテゴリーを超越論的理念に仕立て、経験的綜合を継続してついに無条件的なものに達することによって、この経験綜合に絶対完全性(全体性)を与える必要がある。理性は、条件つきのものが与えられていれば、条件の方も、従ってまた絶対に無条件的なものも与えられている。そして条件つきのものはかかる条件的なものによってのみ可能である」という原則に従って、このことを要求するのである。
理性は、カントによれば、推論の能力であり、それは現に与えられているものの存在理由やその原因・結果の条件に関する「完全性」や「全体性」に到達するまで問い続けることをやめない。けれども、人間の発する解答は限定を含んでおり、それは理性の求める「完全性」や「全体性」に対してはつねに不十分にならざるをえない。いかなる問いも原理的には人間にとって解答不可能であるわけだが、すべてが「ウソ」であるとしても、「ウソ」と指摘することによって、一切が終わるわけではない。何が正しいか否かという問いではなく、ある思想を体験することによっていかなる生の実質がもたらされるかという問いへと移行する必要がある。「ニヒリズムは、『徒労!』を観想しているだけのことではない、また、すべてのものは徹底的に没落するに値すると信ずるだけのことではない。それは手をくだすこと、徹底的に滅ぼすことである……このことは、たしかに、非論理的である。しかしニヒリストは、論理的であることの強要を信じてはいない……これは強い精神や意志の状態であり、かかるものには、『判断』による否定に立ちどまっていることは不可能である、──実行による否定がその本性からは生ずる。判断による無化に腕力による無化が助太刀する」(フリードリヒ・ニーチェ『権力への意志』二四)。太宰の作品の登場人物は「『徒労!』を観想しているだけのこと」あるいは「すべてのものは徹底的に没落するに値すると信ずるだけのこと」であって、「『判断』による否定に立ちどまっている」にすぎず、「実行による否定」にまで至っていない。ニヒリズムを克服するにはそれを避けるのではなく、むしろ、これを極限にまでおしすすめ、いきつくところまでいきついた地点を新たな認識の出発点とすることが求められる。つまり、太宰はあるべき世界や価値を見出すのではなく、生が能動的・肯定的なものとして承認される価値を今ある世界の中に創出する認識にまで到達していない。
さらに、上原は「僕は貴族は、きらいなんだ。どうしても、どこかに、鼻持ちならない傲慢なところがある」と言っているけれども、中心的人物は未熟さが目立ち、斜に構え、シニカルで、今までの引用からも明らかなように、その言葉にほとんど「鼻持ちならない傲慢なところがある」。『斜陽』には──特に、「最後の貴婦人」を母に持ち、「恋と革命のために」生きようとして、私生児を生んで「古い道徳」と闘おうとするかず子の言葉や手紙、日記などに──『聖書』からの引用がかなり見られるが、キリスト教の信仰を暗示させることなく、スノビズムを表わしているだけである。
ドナルド・キーンは、『太宰治の文学』において、太宰の作品に表われたキリスト教や西洋を次のように評している。
しかし私は太宰が外国をテーマを扱うことに何か妙に納得のいかないものを感じる。(略)「走れメロス」は、よく太宰の傑作の一つとして迎えられているのみならず、教科書にもひろく載せられている。しかし、ちょうど外国の作家が日本人について書いた小説が(日本の読者の目で見る限りでは)何かこう誤っているように思われるように、これらのヨーロッパ文学の翻案物は、私の心を動かさない。(略)
太宰が諸作品の中で幾度となくキリスト教に触れていることは、欧米の読者に太宰文学を評価しにくくさせているもう一つの原因である。時折キリスト教は、太宰の生活上の精神的空白を満たしていたもののように思われるのだが、晩年に紛れもなくキリスト教信者だと思っていた、と言う人もいる。しかし、太宰がキリスト教について書いたことは、アメリカのビート族が禅について書いていることと似ているように思われる。特に「斜陽」には聖書の引用句が多すぎて、私が翻訳する際に短縮する必要を感じた個所さえあった。聖書の引用句やしばしばキリスト教について書いていることは、太宰が実際上キリスト教の信者だったことを少しも暗示しないどころか、キリスト教を信じたいと欲していたことさえ暗示しない。キリスト教は太宰の好奇心をそそった。そして太宰は聖書の中に、彼自身の意志と情調を表現するのにふさわしい章句を発見したのである。しかし、彼の私生活でどの程度までキリスト教を信仰することができたにしろ、作品の中では、キリスト教は一種の謎めいた要素であって、重要なものではない。キリスト教に触れることで、太宰は彼が望んでいたような深みを作品に加えることはできなかった。
西洋やキリスト教は、太宰の作品において、表われてくる必然性がない。太宰の西洋文学やキリスト教に関する理解は紋切節の域を出ておらず、それらに関する言及が、モシェル・ド・モンテスキューやヴォルテールにとっての東方とは違い、現にある状態に対する浄化作用や相対化とはなっていない。太宰の作品の登場人物たちは物真似にほかならない仮面をつけてポーズをとり、新品と間違うほどに磨きあげたレンタルの言葉で、さしおさえられた館の中、自分たち自身についての自己満足的で聞いていると退屈なおしゃべりに没頭しているにすぎない。要するに、太宰の作品は、登場人物の会話から考えると、小賢しく喧嘩の弱い中途半端な「ただのグータラ亭主以下の甘ったれ」(寺山修司『愛人・山崎富栄』)の小説にすぎない。
中心的人物からでなく、テーマから読んでみると、『斜陽』は、四人の中心的人物によって、「真の革命のためには、もっともっと美しい滅亡が必要なのだと、古き美しさの挽歌であり、恋と革命とに生きる新しい人間の出発を模索した長編」(奥野健男)である。そうしたテーマから『斜陽』は、記念館となった彼の生家が「斜陽館」と命名されたように、当時の世相を反映していると社会にインパクトを与え、「斜陽族」という流行語を生んでいる。
太宰に最もこだわっている書き手であると同時に、彼の『走れメロス』を評価している吉本隆明は、「太宰治」(『悲劇の解読』所収)において、太宰と彼の文学についてテーマの側面から次のように考察している。
太宰治の作品のもっとも深いところからはひとつの声が聴こえる。じぶんは〈人間〉から失格している、じぶんは〈人間〉というものがまるでわからないと疎隔を訴えている声である。この声はかれが生涯の危機に陥ちこんだとき、かならず作品からしみでてくる。けれど太宰治のいう〈人間〉は人間の本質をさしてはいない。他者の気持ちの動きがつかめないために他者との関係の仕方がまるでわからないと呼びかけている。他者に投影された人間の在り方からじぶんが異類のように隔てられているといった叫びに似ている。その果てに他者の振舞いは、じぶんの心の動きからまったく予測できないという失墜感があらわれる。
太宰治の文学はこの世界の全貌を開示してみせるという意味では、けっして高度なものではない。人間とはなにか、その存在の仕方とはなにかという問いは、本質的にはかれの作品に一度もやってこなかった。ただ人間と人間との関係からこぼれ落ちる失墜感とはなにか、ひとが他者から疎隔されてしまうのはなぜかという問いは無限に展開されている。他者との関係で〈比量〉が利かないのに意味にみたされた世界は可能か、そういう世界に陥ち込んだものはどう受難するか。そこに作品が成立っている。
太宰の作品を「人間とはなにか、その存在の仕方とはなにかという問い」と切り離すことができないドストエフスキーやフランツ・カフカの作品と比較・検討することは意義深いものではない。太宰の作品から読みとるべきものは、そうした側面においては、何もない。彼の作品に見られると吉本の指摘する「ただ人間と人間との関係からこぼれ落ちる失墜感とはなにか、ひとが他者から疎隔されてしまうのはなぜかという問い」は、時代が変化すると必ずと言っていいほど、時代の雰囲気を敏感に嗅ぎとる嗅覚に恵まれた作家たちによって、それ以前にも何度も描かれ、その都度通俗的な成功を収めている。それは紋切り型のテーマであり、(反)政治的な行動主義と美学的な形式主義、あるいは革命精神と美学的洗練の混濁として典型的に作品化された。例えば、アメリカのロスト・ジェネレーションや日本の第三の新人、晩年の三島由紀夫らはその範疇に入るだろう。彼らの作品は自分たちの文学が発生してくる根本的な問題そのものを解きほぐすのではなく、自分自身が行動することができるためのシナリオを提供するだけである。太宰は、政治活動に関して言えば、学生時代に共産党の非合法運動に従事したにすぎないし、作品に政治的な行動主義が顕著に表われたケースはそれほど多くはないが、『冬の花火』によって占領軍指令部を挑発するなど反政治的な行動主義をとっている。しかし、美学的なるものと(反)政治的なるものは『斜陽』の中では依然として──道徳革命という道徳的なものへの移行という早急な結合こそ見られるものの──「正」・「反」・「合」といった弁証法的な統合をすることなく、主人公はその世界から脱出してしまい、作品が終わった後に統合されるかもしれないという淡い期待を読み手に抱かせるにとどまっている。こうした姿勢は美学的なものと(反)政治的なものによって真の問題から身を隠すための自虐的な反知性主義であり、文学史における一つの最も保守的なマンネリズムにすぎない。彼の行動は政治的抵抗ではなく、たんなる反抗だ。反抗は既存の秩序や権威、または父や兄などの先行世代の世界観の失墜に対する憤りであり、それが破壊されることによる復活への願い、あるいは破壊を通じてそれと自己同一しようとする望みである。残念なことに、太宰は、プロレタリア文学などの先行世代に比べて、意識的でありながらも、ほぼ同じ時期(一九四六)に書かれ、「堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなど上皮だけの愚にもつかない物である」という言葉によって閉じる──戦前から一貫とした視点を持ち続けた数少ない「知識人」の一人である──安吾の『堕落論』と比較するべくもなく、意識をさらに覚醒させることをせず、その意識によって獲得された時代の変化という歴史的ヴィジョンをくもらせてしまう。
しかし、『斜陽』を文学ジャンルから見るといささか情勢が変ってくる。吉本隆明は太宰治の作品を「悲劇」として「解読」しようとしているが、むしろ、それは、「マイ、コメデアン」と書かれているように、喜劇的な様相を呈しているように思われる。吉本の「悲劇」概念は自然のミメーシスであるかのようにも見られている文化的次元を指すものではないが、彼がとりあげている書き手──太宰治の他に小林秀雄、横光利一、芥川龍之介、宮沢賢治がある──を見ても、なぜこういうタイトルをつけたのか疑問である。悲劇は吉本が主張するほど簡単に演じられはしない。と言うのも、悲劇は感情移入や共感をめぐって成立しているわけではないどころか、むしろ、それを拒絶することによって可能になるからである。『斜陽』だけでなく、彼の作品は、一見したところでは、悲劇であるかに書かれている。だが、太宰にとって、悲劇的な様相は読み手を真の世界へと導くためのアイロニカルな契機にすぎない。悲劇は幻であり、実は、そこで真に具現しているのは喜劇なのである。四人の中心的人物はそれぞれおおかた素朴であり、読み手以上の能力を所有していないが、カナダの百科全集的な文学理論家であるノースロップ・フライの『批評の解剖』(一九六二)によると、悲劇が属している「高次模倣様式」とは中心人物がわれわれを超えた能力や権威を持ち、自然の内部にありながら、社会的な批判をも可能にするような文学様式であり、喜劇が属している「低次模倣様式」とは登場人物の行動の力がわれわれと同じレヴェルにある文学様式である。
悲劇と喜劇は、古代ギリシア演劇においては、明確に分割できるのだが、それ以後の作品によっては、悲劇と喜劇は完全に別なものとわけられないこともある。悲劇は涙をわかせるものであり、一方、喜劇は笑いを誘うものであるという分類は適切ではない。「喜劇自体の中に悲劇が潜在的に含まれている」場合、フライは『批評の解剖』において言う。「喜劇のカタルシスの背後にある祭儀の形式は、死のあとの再生であり、甦った主人公(英雄)の顕示または明示である」。
太宰は、『斜陽』において、死と再生を次のように暗示している。
どうやら、あなたも、私をお捨てになったようでございます。いいえ、だんだんお忘れになるらしゅうございます。
けれども、私は、幸福なんですの。私の望みどおりに、赤ちゃんが出来たようでございますの。私は、いま、いっさいを失ったような気がしていますけど、でも、おなかの小さい生命が、私の孤独の微笑のたねになっています。
けがらわしい失策などとは、どうしても私には思われません。この世の中に、戦争だの平和だの貿易だの組合だの政治だのがあるのは、なんのためだか、このごろ私にもわかって来ました。あなたは、ご存じないでしょう。だから、いつまでも不幸なのですわ。それはね、教えてあげますわ、女がよい子を生むためです。
私には、はじめからあなたの人格とか責任とかをあてにする気持はありませんでした。私のひとすじの恋の冒険の成就だけが問題でした。そうして、私のその思いが完成せられて、もういまでは私の胸のうちは、森の中の沼のように静かでございます。
私は、勝ったと思っています。
マリヤが、たとい夫の子でない子を生んでも、マリヤに輝く誇りがあったら、それは聖母子になるのでございます。
私には、古い道徳を平気で無視して、よい子を得たという満足があるのでございます。
死と再生という神話的ヴィジョンはロマン主義文学の作品にしばしば表現されている主題であるが、死と再生はある連続性に基づいている。あやまちがあり、それから死がふりかかり、そして再生の洞察か獲得される。死と再生は決して対立してはいない。死は再生の中にあり、再生は死の中にある。死と再生の間には現実的な分断はなく、差異は、ここでの語る主体の中には、存在しない。
「もともと太宰は明るさと暗さを対立的にとらえるのではなく、暗さの中に明るさを、明るさの中に暗さを見る眼をもっていた」と言う柄谷行人は、「『斜陽』について」において、この部分を次のように解説している。
「女がよい子を生む」ということは、どんな時代・社会にもかかわらず、戦争や政治や貿易などといったあらゆる人為的なもの、幻想的なものの底にある“自然”である。彼女はむしろそこから意味に憑かれた世界を見返している。チェーホフの『三人姉妹』のなかに、太宰が好んだせりふとして、「意味ですって、いま雪が降っている、それに何の意味があります?」という条りがある。よい子を生む、それはちょうど雪が降っているようなものだ。何の意味もないが、無意味でもない。おそらくかず子はそういう地平に降りて、「孤独に微笑」している。彼女は新生に賭けた者であるが、しかし滅びる者と対照的に区別されているのではない。作品の全体において、それらが互いに反照しあって、“斜陽”の一瞬を永遠に定着させているようにみえるのである。
柄谷は典型的なアイロニー劇であるアントン・チェーホフの『三人姉妹』の言葉を引用して、『斜陽』を読解しているが、アイロニー劇は「意味ですって、いま雪が降っている、それに何の意味があります?」というようなリアリズムを通過するとき、それは悲劇から喜劇へと近接していく。そこではアイロニーが性格を形成し、われわれに望ましい共感を誘うような社会をうちたてる。その社会の建設は、時間的には、筋を追っていくにつれて徐々にではなく、急転直下のうちに──特に、エンディング付近で──なされる。『斜陽』は結末で、突然、直治の自殺と上原との離別などによって新たな世界が提示されている。『斜陽』では過去・現在・未来という時間性は持続的と言うよりも、むしろ、日記や手紙、遺書といったフラッシュ・バックの技術において体現され、その速度はその隙間に負っている。それはアイロニーのもたらす時間概念である。『斜陽』はアイロニーの喜劇である。
太宰の作品において、杉並区天沼に住んでいた頃に発表した最初の読むに耐える作品である『魚服記』以来、アイロニーは重要な契機として扱われているが、アイロニーは必ずしも笑いを誘うとは限らない。太宰は、先に論じたように、一言余計に書き入れることがあり、アイロニーによって、読み手を笑わせるどころか、かえって不機嫌にさせることは少なくない。彼は抽象的な認識に対して直観的な認識を過剰に加える。太宰にとって、笑いは「直観的な認識と抽象的な認識との不一致」である。「笑いが生じるのはいつでも、ある概念と、なんらかの点でこの概念を通じて考えられていた実在の客観との間に、とつぜんに不一致が知覚されるためにほかならず、笑いそのものがまさにこの不一致なのである」(アルトゥール・ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』)。こうした笑いは現状をうまく説明しているかもしれないが、いささか病的であり、その笑いには対象のとうのものでさえも笑ってしまうような太っ腹さや健康さがない。アイロニカルな笑いは現状を軽蔑しているけれども、自分自身を笑い飛ばしていないため、当人以外は不快にさせることも少なくない。絶望的な状況を前にすると、それが自分自身を突き放してしまうがゆえに、人間は自己も世界も同時に笑い飛ばすほかなくなるのだ。失われてしまった自己の一貫性を強引に維持し続けようとすることではなく、新たに出発することによって、別の連続性をまた生成していこうとする精神的態度から真の笑い、すなわち「ユーモア」(ジクムント・フロイト)は生ずる。つまり、太宰は笑いが救いであるという地点にまで追いつめられてはいなかったために、また本質的に笑いを理解していないことから、彼が狙ったと思われる道化的な部分は自己憎悪と自己憐憫によって損なわれ、痛々しさが目立つうす寒い光景が提示されて、とても笑えない。
太宰の言語に関する繊細な感覚は彼の意図を裏切るとき初めて機能する。太宰の作品は、彼が意識したところとまったく逆の部分において、その意図した喚起力が働いている。太宰の作品には、それが必ずしも出来としては優れていないとしても、部分的には光るところがあることはかなり見られる。『斜陽』には前後と論理的な関係を持たない、詩的に印象づけることを意図したであろう文章が少なくない。こうしたちりばめられたシンボリックな表現は、必ずしも、成功してはいない。詩的なイメージは、むしろ、アイロニカルに、平坦な叙述において、西荻といった実在の地名や日付け、具体的な人物を登場させるという厳密さを追及するときに、機能している。そうした描写は簡略化され、氷山の一角だけが示されており、想像力を喚起させる。
『斜陽』に見られる次のような表現が詩的である。
私たちが、東京の西方町のお家を捨て、伊豆のこの、ちょっと支那ふうの山荘二引っ越してきたのは、日本が無条件降伏をしたとしの、十一月のはじめであった。
これが、あの、私の虹、M・C、私の生き甲斐の、あのひとであろうか。六年。蓬髪は昔のままだけけれども哀に赤茶けて薄くなっており、顔は黄色くむくんで、眼のふちが赤くただれて、前歯が抜け落ち、絶えず口をもぐもぐさせて、一匹の老猿が背中を丸くして部屋の片隅に座っている感じであった。
「日本が無条件降伏をしたとしの、十一月のはじめ」という言葉は、それに対するイメージが引き起こされ、所有している意味以上に、想像作用が知覚作用へと転換する効果として読み手に残る。こうした固有名詞は自立した意味として、作品に対して、解釈の画一化を阻み、その形成を活性化させる機能を果たしている。太宰は「私の虹」に関して「一匹の老猿が背中を丸くして部屋の片隅に座っている」というイメージを示している。そのイメージによって「私の虹」は現象としてではなく、物自体として提示されていることが可能になっている。この部分以外にも、かず子と彼女に『トロイカ』という文庫本を貸す若い将校とのやりとりを描写した印象的なシーンがあるが、その将校に関する外観は、三島由紀夫ならば丹念に記述するところであろうけれども、一切言及されていない。彼は人物の全体象をあますところなく描くのではなく、ラジオ・ドラマのごとく、外面的な様子のほんの一部だけ、すなわち必要最低限の部分だけ禁欲的に記述している。『葉』の中である人物に語らせた「ほんとうに、言葉は短いほどよい。それだけで、信じさせることができるならば」という主張はこういう部分で表われている。つまり、厳密さと厳密さへの情熱の間の緊張関係が詩的な思考の飛躍を、太宰の作品においては、感じさせる。
同様に、笑いを読み手に喚起するのは、彼が狙ったところではなく、次のような部分である。
犠牲者。道徳の過渡期の犠牲者。あなたも、私も、きっとそれなのでござましょう。
革命は、いったい、どこで行われているのでしょう。すくなくとも、私たちの身のまわりに於いては、古い道徳はやっぱりそのまま、みじんも変らず、私たちの行く手をさえぎっています。海の表面の波は何やら騒いでいても、その底の海水は、革命どころか、みじろぎもせず、狸寝入りで寝そべっているんですもの。
「人間は、みな、同じものだ」という
けれども、この言葉は、実に猥せつで、不気味で、ひとは互いにおびえ、あらゆる思想が姦せられ、努力は嘲笑せられ、幸福は否定せられ、美貌はけがされ、光栄は引きずりおろされ、所謂「世紀の不安」は、この不思議な一語らはっしていると僕は思っているんです。
太宰はこのようにヒステリックにぶちぶちと愚痴る。彼の陰鬱さは対象をそれに相応しくないものとして論ずる。モノローグは、俳優の田村正和が示しているように、ダイアローグにはないおかしさが漂う。太宰はこの世には希望なんてありはしないと言いながら、偏執狂的にアイロニーによって笑いをとらずにはいられない。ところが、彼が笑いを企てたものの、失敗し、そのことを愚痴り始めた瞬間にわれわれは笑いを覚えてしまう。われわれが爆笑するのは太宰の生きる愚痴といったクサさである。つまり、「太宰治の作品のもっとも深いところから」聴こえてくる「ひとつの声」、すなわち「じぶんは〈人間〉から失格している、じぶんは〈人間〉というものがまるでわからないと疎隔を訴えている声」がわれわれに、自分の考えていることと自分のあることが一致しないのはあたりまえじゃないのか、そこまで人はおまえのことなどかまってなんかいられないし、考えてもいないんだけどなと笑いを喚起する。
太宰はマルクス主義者でもなければ、戦後民主主義者でも、ヒューマニストでも、フェミニストでも、天皇制主義者でも、貴族主義者でも、理想主義者でも、在日韓国人でもない。彼は〈人間〉であることは存在の条件となるなどと信ずることができないショーペンハウアー主義者なのだから。彼の得たゆるぎない確信は〈人間〉から失格している自分は存在しなかったほうがましだったのであり、生きることの喜びがその苦痛を駆逐してくれるなどということは、嘲笑すべき自己欺瞞だということである。生まれついてから背負いこんでしまった肉体などというものは虚ろで「徒労」に満ちた〈人間〉にとって重荷なのだ。生きることに盲目的にとらわれて、互いに他人をおしのけてもそのゴールに到達しようというのは、「拷問に喘ぐ者たちの戦場」(『意志と表象としての世界』)にすぎない。「困難に満ちて楽しみのない一生のうちで、一体なにを勝ち得るというのか。食べることと産むこと、つまりは、個体は替われど同じ憂欝な行程を再び始める手立てを準備することにほかならない」(同)。生きている無数の人々に、首を横にふり。遠い目をしながら、とっとと死んでしまったほうがどんなにか幸せだったろうにと告げる彼のペシミズムはアイロニーによって一種のリアリズムとなっていることは否定できない。「一瞬の満足、要求に縛られた束の間の喜び、そして多くの長い苦痛、絶えざる闘争、食うか食われるかの全面戦争、抑圧、欠乏、窮乏、不安、阿鼻叫喚のみ、そして、これは末法まで連綿とこの惑星の地殻が割けめまで続いてゆくのだ」(同)。しかし、太宰の作品は自らが非難した状況そのものを作品自身が再現してしまい、表向きにはいかに悲劇的に見せようとしても、そうした差異を反復することによって同一としてしまうその試みは、マルクスが『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』の冒頭で言ったように、茶番劇にならざるを得ない。
太宰との間にフローベールの「ボヴァリー夫人は私だ」式の図式が成立している『斜陽』の四人の登場人物は典型的な喜劇の登場人物である。喜劇の登場人物は、フライの『批評の解剖』によると、「アラゾン」すなわち「ペテン師」、「エイロン」すなわち「自己卑下する韜晦者」、「ボモロコス」すなわち「道化もの」、「アグロイコス」すなわち「無作法な、文字通りの田舎もの」の四種類にわけられ、「アラゾン」と「エイロン」の闘いが「喜劇の筋立ての基礎」になり、「ボモロコス」と「アグロイコス」が「喜劇的な雰囲気の両極」をつくる。母は「エイロン」、上原は「アグロイコス」、直治は「ボモロコス」、かず子は「アラゾン」に対応する。
この四種類は、日本人にとっては、明の中期に呉承恩によって書かれた『西遊記』における三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄と対応させるとわかりやすくなるだろう。この場合、母は三蔵法師、かず子は孫悟空、上原は猪八戒、直治は沙悟浄にそれぞれあたると考えられる。
喜劇はそれぞれの人物にではなく、人物の交錯そのものに関心がある。柄谷は、『斜陽』を「明るさが暗さを喚起し、暗さが明るさを喚起する世界、四人の人物が交錯しあうときに生じる微妙な光と影の世界である」と述べている。主題も稚拙であり、登場人物も素朴であるにもかかわらず、『斜陽』があなどりがたい魅力を持っているのは、「明るさが暗さを喚起し、暗さが明るさを喚起する世界」を描いているとは完全に言いがたいが、この四人の交錯が見事だからである。
『斜陽』の死と再生の生成様式はこの四人の論理の錯綜を基盤にして、最終的に母と子の関係性へと向かう。だが、「女がよい子を生む」、すなわち「子」と言わずに、「よい子」と太宰が書くとき、『斜陽』の中では、再生はつねに母の側からなされたにすぎず、歴史はただ母の誕生と再生の間に生起するものでしかないということを意味している。出発点としての母は、子を経たとしても、依然として終着点を自らのうちに含んでいる。
こうした視点は『斜陽』だけには限らず、遺書においても見られるのだが、安吾は、『不良少年とキリスト』において、「子供が凡人でもカンベンしてやってくれ」という一節のある太宰の遺書をめぐって次のように言っている。
だが、子供が凡人でも、カンベンしてやってくれ、とは、切ない。凡人でない子供が、凡人でない子供が、彼はどんなにほしかったろうか。凡人でも、わが子が、哀れなのだ。それで、いいではないか。太宰は、そういう、あたりまえの人間だ、彼の小説は、彼がまッとうな人間、小さな善良な健全な整った人間であることを承知して、読まねばならないのである。
しかし、子供をただ憐れんでくれ、とは言わずに、特に凡人だから、と言っているところに、太宰の一生をつらぬく切なさの鍵もあったろう。つまり、彼は、非凡に憑かれた類の少ない見栄坊でもあった。その見栄坊自体、通俗で常識的なものであるが、志賀直哉に対する「如是我聞」のグチの中でも、このことはバクロしている。
「女がよい子を生む」ということは、柄谷が指摘するような「あらゆる人為的なもの、幻想的なものの底にある“自然”」ではない。「あらゆる人為的なもの、幻想的なものの底にある“自然”」は、太宰が提示したのとは逆に、子の側から女を見るときに表われてくる。「よい子」は女から見て、利他的であることを意味している。これは自分の言うことをよく聞くようにと教えこんだ判断であり、子の欲望が直接満たされる自己規定ではない。「よい」は、ニーチェの『道徳の系譜』によると、「騎士的・貴族的評価様式」に基づいた「力強い肉体、若々しい、豊かな、泡立ち溢れるばかりの健康、並びにそれを保持するために必要な種々の条件、すなわち戦争・冒険・狩猟・舞踏・闘技、そのほか一般に強い自由な快活な行動を含むすべてのもの」を前提にしている。「力を持つ」、「つねに創造する」、「生を楽しむ」といったことの自己肯定的な感情が子にとっての「よい」ことなのである。リビドーによる対象へのかかわりが行われ、女は子の超自我に自分と同じものをすえるのだ。子は、その自我の中で、女と自分を同一のものとして考え始める。
子は、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』の堅琴ひきの歌を引用して、女に対して次のように嘆くだろう。
あなたは、われわれを人生へ引き入れ、
哀れな男を罪におとしいれ、
あとはその男が苦しむに任せる。
なぜなら、どんな罪でもこの地上で罰せられるのだから。
子は女の自分から始まって自分に終わるような自己完結性を破綻させてしまう。子は女にとって自分の思惑ではどうにもならぬ突き放す存在であり、女は自分ではどうすることもできないものに支配される。女の「輝く誇り」などではなく、子そのものが価値なのである。「だれもがまだ目で見たことのないもの、いつか生まれてくる果実を、あなたがたの愛のすべてが、護り、いたわり、培っている。あなたがたの愛のすべてがあつまるところに、すなわちあなたがたの子どものもとに、あなたがたの徳のすべてがある!」(ニーチェ『ツァラトゥストゥラはかく語りき』)。「よい子」と言い、「子供が凡人でも、カンベンしてやってくれ」と書くとき、その主張は、子にとって、自己満足的な単純な説教に堕してしまう。
そうした自己完結性は、『斜陽』では、神話へと次のように回帰してしまう。
こいしいひとの子を生み、育てる事が、私の道徳革命の完成なのでございます。
あなたが私をお忘れになっても、また、あなたが、お酒でいのちをお無くしになっても、私は私の革命の完成のために、丈夫で生きて行けそうです。
あなたの人格のくだらなさを、私はこないだも或るひとから、さまざま承りましたが、でも、私にこんな強さを与えて下さったのは、あなたです。私の胸に、革命の虹をかけて下さったのはあなたです。生きる目標を与えて下さったのは、あなたです。
私はあなたを誇りにしていますし、また、生れる子供にも、あなたを誇りにさせようと思っています。
私生児と、その母。
けれども私たちは、古い道徳とどこまでも争い、太陽のように生きるつもりです。
どうか、あなたも、あなたの闘いをたたかい続けて下さいまし。
革命は、まだ、ちっとも、何も行われていないんです。もっと、もっと、いくつもの惜しい貴い犠牲が必要のようでございます。
いまの世の中で、一番美しいのは犠牲者です。
ここで太宰は「犠牲者」、すなわち生け贄を要求するという悲劇的な要素を提示しているかに見える。だが、「私生児と、その母」の悲劇は、『斜陽』よりも、むしろ、ナサニエル・ホーソンの『緋文字』のほうこそふさわしい、ヘスター・プリンは、確かに、「犠牲者」である。それは悲劇特有の「恐ろしい正当さへの感覚」と「不当さに対する憐れみの感覚」が逆説的に結びついている。舞台である一七世紀ピューリタン社会を意識させるため、その時代の英語でわざわざ書かれている『緋文字』において、犠牲者はあくまでも作品の中で生け贄の役割を担っているのに対して、『斜陽』においては、犠牲者は話が終わった後から犠牲者を体現していく。ピューリタンの社会はキリスト教悲劇の源泉である。悲劇はア・プリオリにそうなのではなく、歴史的に、ある特定の時期においてのみ生まれ得るものである。アイスキュロス・ソポクレス・エウリピデスのギリシア悲劇はソクラテス以前の歴史的・社会的状況であり、シェークスピアに代表されるキリスト教悲劇はデカルト以前の状況が可能にさせている。どちらの悲劇も主人公は男である。女は喜劇においてのみ主人公となっている。『緋文字』も、その意味では、悲劇ではない。キリスト教悲劇がもはや不可能だと知っていたから、ホーソンは『緋文字』の最後にヘスターを元の場所に戻している。一度は捨てた緋文字Aをつけたまま生き続けることを決意した彼女は死を運命づけているキリスト教悲劇的にではなく、プロメテウスのごとく、能動的な罪を自ら引き受け、ギリシア悲劇的に、さらしものなることを是認する。さらに、『緋文字』は、『斜陽』がかず子の出産までの物語なのとはは逆に、ヘスターが私生児を生んでからの出来事を描いている通り、ロマンスではなく、構成の点でも、近代小説である。近代小説の主人公が、本質的に、女である点からも、このことは強調されよう。近代は父、すなわち対立の死んだ時代であり、その代わりに母、すなわち抱擁が支配している。対立する相手を殺せても、抱擁するものを殺すことはできない。抱擁=所有によって、殺されるのは子のほうである。父の死が母の過剰を求める。しかし、父も母も意識しないで子が生きられる時代をわれわれは、むしろ、目指す。そうすれば、父も規範になろうとして無理することもないし、母も包みこもうと苦労することもない、父の復権も母の管理も時代をよくしない。子はただ発狂するか、自殺するか、他殺するだけである。父や母の過剰は子に自分のことを考えられなくする。人は自分の立場を掘り崩すことによってしか、他の人のことがわからないものだ。そうできないのは、現代に孤独が足りないからである。現代人は孤独であるように見えて、真に孤独ではない。なぜなら、それは、ヘスターの場合と違い、能動的なものではないからである。以上のように、『緋文字』の中では、アイロニーは『斜陽』よりもラジカルに働いている。「私生児と、その母」は、『緋文字』においては、「人身御供」であり、一方、『斜陽』においては、「人身御供ごっこ」(『批評の解剖』)である。メロドラマにありがちな嫁姑や継子いじめといった設定に基づいた作品もこの「人身御供ごっこ」の一種であろう。
悲劇は、オイディプスにしろ、プロメテウスにしろ、再生とは無縁である。悲劇はどうしようもなく救いようがない没落によって幕を閉じるが、その救いようのなさによって救われるような根源的な諸矛盾を具現化した文学形式である。フライは、『批評の解剖』において、「喜劇は一方の極でアイロニーと諷刺にまじり合い、もう一方の極でロマンスにまじり合う」と言った後で、さらに、ある喜劇の場合、「われわれは機智と目醒めた批評の知性の世界を去り、その対局の神話的な厳粛さに向かうことになる」と述べている。そうした喜劇では「幼年時代から死までの全行程を走り通し、最終の相で、母胎希求と心理学的に密接に結びついた神話になる」。かず子の人生の行程を中心にして筋立てられている『斜陽』にはアイロニーとロマンスがまじり合っている。また、そこに再生と死や生け贄といった神話が混入していることは明らかに認められる。「私生児と、その母」は神話へのアイロニーであり、「女がよい子を生む」ことは「母胎希求と心理学的に密接に結びついた神話」にすぎない。『斜陽』は神話が入りこんだ一種のメロドラマである。「もしわれわれが批評を捨て」、一部の熱狂的な信奉者たちのように、太宰の作品になすがままに「身を委ねるならば、快い戦慄を与えてくれるにちがいない」。『斜陽』では犠牲者が味わう矛盾が作品中で体現されることなく、彼らは舞台から消えていく。犠牲者を痛めつけるのが喜劇であり、それに耐えることが悲劇なのだから。
『斜陽』の喜劇性は次のようなエンディングによって、さらに、強調される。
私はもうあなたに、何もおたのみする気はございませんが、けれども、その小さな犠牲者のために、一つだけ、おゆるしをお願いしたい事があるのです。
それは、私の生まれた子を、たったいちどでよろしゅうございますから、あなたの奥さまに抱かせていただきたいのです。そうして、その時、私にこう言わせていただきます。
「これは、直治が、或る女のひとに内緒で生ませた子ですの」
なぜ、そうするのか、それだけはどなたにも申し上げられません。いいえ、私自身にも、なぜそうさせていただきたいのか、よくわかっていないのです。でも、私は、どうしても、そうさせていただかなければならないのです。直治というあの小さな犠牲者のために、どうしても、そうさせていただかなければならないのです。
ご不快でしょうが、ご不快でも、しのんでいただきます。これが捨てられ、忘れかけられた女の唯一の幽かないやがらせと思召し、ぜひお聞きいれのほど願います。
M・C マイ、コメデアン。
昭和二十二年二月七日。
かず子の「お願いしたい事」は直治の遺書に書かれてあった希望に基づいているが、彼女は上原にそれを告げていない。本心を語らないというのは、作家がペンネームによって本名を隠すように、アイロニーの常套手段である。かず子はその社会から白眼視されるが、かず子の行動によって上原の家庭に対する重要な危機に陥ると推測されるような深刻さは感じられない。『斜陽』は完全なメロドラマ的な筋書きに基づいており、作品上の社会に対立したりそこから排除される登場人物に読み手のメロドラマ的な共感は集中するが、それは社会の真の敵は社会の内なる精神というようなアイロニーの袋小路を露呈している。読み手にとってはその社会以上に大切なものとして同情されると同時になぜ本心を口にしないのかという憤りも喚起する。つまり、この結末は、貞節と公認道徳との勝利を期待している、あるいは私生児は社会道徳退廃の徴候であると信じて疑わない読者を嘲笑するメロドラマのパロディーである。
フライは、『批評の解剖』において、喜劇の結末に関して次のように言っている。
喜劇が終わったあとに現われる社会は、これとはあざやかな対照をなす一種の道徳的規範か、あるいは現実的には自由な社会を表わしている。その社会の理念が定義されたり、公式化されることはない。定義と公式化は『偏屈もの』に属していて、彼らは予言できる行動を望むのだから。われわれはただ、新しく結ばれた二人がその後幸わせに暮したということとか、あるいは少なくとも気まくれに支配されない冷静な生き方をしてゆくだろうということを、納得させられるだけなのだ。だからこそ、すべてが上首尾に運んだ主人公の性格が、未成熟のままになることがよくあるわけで、彼の本当の生き方は、劇が終わったところからはじまるのだから、彼が見かけよりは本当はもっと面白い人物なのだろうと信じる他はない。
「人間は恋と革命のために生まれて来た」と確信し、「革命」や「道徳革命」という言葉をふりまわすかず子は(書き手にそういうものが欠けていると思われるために)人をほんとうに愛するに足る誠実さがないために、彼女の提示する「道徳革命」は目的論的であって、既存の道徳、すなわち常識に正対するだけで、ニーチェのように道徳そのものの系譜へ向かうことはない。太宰が、アイロニーを用いる際、書き手と読み手の間に共有されている暗黙の常識が前提とされていて、それに読み手は同意することを促されてしまう。太宰への評価がわかれるのはこの常識の認知をできるか否かにかかっているからである。太宰の語りは七〇年代の深夜放送のパーソナリティのようだ。DJが主流の国の人々にはこれは理解できないだろう。『走れメロス』は、従って、『走れ歌謡曲』として執筆すれば傑作になったことは間違いない。かず子は、喜劇の約束通り、あまり興味深い人物ではないが、その社会においては、アイロニカルにも、魅力あふれる女性であり、かず子の勝利は共感と嘲笑の混合した新たな自分の社会の建設である。『斜陽』はメロドラマの精神そのものを標的にし、太宰は『シンデレラ』のようなメロドラマ的なロマンスを罵っている。太宰の作品において、悲劇はその死を通じて喜劇へと新生する。つまり、『斜陽』は死と再生の生成様式を所有した一つの歴史的世界である。
Take me now baby here as I am
Pull me close try an understand
I work all day out in the hot sun
Stay with me now till the mornin' comes
Come on now try and understand
The way I feel when I'm in your hands
Take me now as the sun descends
They can't hurt you now
They can't hurt you now
They can't hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us
What I got I have earned
What I'm not I have learned
Desire and hunger is the fire I breathe
Just stay in my bed till the morning comes
Come on now try and understand
The way I feel when I'm in your hands
Take me now as the sun descends
They can't hurt you now
They can't hurt you now
They can't hurt you now
Because the night...
Your love is here and now
The vicious circle turns and burns without
Though I cannot live forgive me now
The time has come to take this moment and
They can't hurt you now
Because the night...
(Patti Smith & Bruce Springsteen “Because The Night”)
太宰の文学的才能は、『近代能楽集』の三島のように、『右大臣実朝』や『新釈諸国噺』、『お伽草紙』といった形式が決まったものの中で発揮される。太宰の作品の力量は作品構成にある。テレビ・ドラマの脚本家としての能力を持った太宰は定まった形式の中でアイロニーを用いて、その意図を転倒する。太宰の作品には私小説と定義される可能性をはらんだものも少なくないが、それは私小説が斥ける構成力を持っており、家や家族のことを書かれていたとしても、私小説ととらえるべきではない。家や家族のことを題材にして作品を書いた太宰が喜劇の形式を選びとったのには必然的な理由がある。と言うのも、喜劇の理論に最も示唆を与えてくれるのは、フライの『批評の解剖』によると、ロマンスに示唆的なのがユングであり、悲劇の場合それがニーチェの理論であるように、フロイトだからである。「死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。鼠色のこまかい縞目が織りこめられていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った」。『晩年』においてこう書くとき、太宰は自分自身にアイロニーを向けている。このアイロニーが、すなわち「誤謬の訂正」が太宰の作品から〈人間〉の問題を奪う。太宰の小説は「人間そのものに付随した生理的な精神内容」である「虚無」に基づいた「心理通、人間通の作品で思想性はほとんどない」(『不良少年とキリスト』)。太宰の作品から「人間とはなにか、その存在の仕方とはなにかという問い」が発せられないのは、存在が形式の問題に置き換えられているからである。
人間の人生の機微に疎い太宰の『斜陽』を今日論ずる意義はかなり限定されたものでしかない。『斜陽』はテーマとしては政治的抵抗と言うよりも、失笑してしまうまでの凡庸な議論に堕してしまっている。即物的で荒っぽい通俗さが太宰の論理・倫理の台座である。しかし、『斜陽』を、文学ジャンルから考察してみると、別の結論が導かれてくる。それは堂々としたものと陳腐なものとの結合の喜劇である。そこでは陽気さと絶望は同じ源泉から生じ、男も女も凡庸で愚鈍なものを演じているにすぎない。この世には悲劇のヒーローやヒロインなど、ボクシングのグローブをはめた野球のプレーヤーのように、へたなジョーク程度におよびでない。人間存在は高尚な悲劇ではなく、アイロニーと絶望が背中合わせの饒舌で馬鹿げた喜劇なのである。だから、太宰は「安楽なくらしをしているときは、絶望の詩を作り、ひしがれたくらしをしているときは生のよろこびを書きつづる」(『晩年』)。要するに、『斜陽』が読むにたえるのは喜劇という形式の持つ魅力のおかげであり、日本文学の中で喜劇の解読としての可能性は今日においてもまだ十分に残している。
太宰は、それから、『人間失格』などを公表し、『斜陽』発表から一年後の一九四八年六月十三日に、玉川上水に山崎富栄と入水自殺した。遺体は津島修治の誕生日である六月十九日に発見された。『グッド・バイ』が未完のまま遺稿となる。
しかし、太宰は、日本近代文学において、最もすぐれた喜劇作家であるが、彼以降アイロニー作家や喜劇作家は登場してきたけれども、果たして彼を乗り越えているかどうかは疑問である。太宰の作品を、「生理的」に、溺愛することも、嫌悪することも無意味と言ってよい。われわれは彼が用意した喜劇を克服していく必要があるのだ。太宰の喜劇は、彼が好んだアントン・チェーホフの喜劇に比べると、本論の前半部分で考察したように、いろいろな問題点があって、不十分である。このロシアの作家は死にも、再生にも、「女がよい子を生むこと」にも、生を賭けることはない。だが、彼はすべてが「徒労」に終り消失してしまったとしても、にもかかわらずその限定の中で充実して生きるという認識を決して手放すことなどない。太宰の場合とはまったく正反対に、チェーホフの喜劇そのものが実はアイロニーであって、それが真に描いているのは、実は、悲劇である。
それぞれの人間は解決しなければならない真の問題を持つものだ。それには偽の問題に対してふんぎりをつけ、真の問題を解明する必要がある。真の問題とは「能動的ニヒリズム」、すなわち「精神の上昇した力の徴候としてのニヒリズム」に基づいているのに対して、偽の問題は「受動的ニヒリズム」、すなわち「精神の力の衰退と後退としてのニヒリズム」の呪縛にある(『権力への意志』二二)。太宰は真の問題ではなく、偽の問題の圏内だけで終始している。太宰が読まれているのは、偽の問題にとらわれているものたちに感情移入されているからである。真の問題が何であるか、自らの存在と結びついているため、語ることはできない。それはその生においてただ示されうるものだ。一方、偽の問題は、自己嫌悪と自己憐憫にとらわれ、自己を嫌うことによって自らを救うという病的な精神状態が生み出す。
太宰の作品には自虐的とも思われるほどの自傷行為的記述が見られるが、他方、女性に対しては極めてサディスティックである。彼にとって女性は自分の一部として扱っているから、自傷行為の変形として表われている。そうした彼の自傷行為は自分自身に直面することから逃避したことから生ずる。すなわち、サディスティックな行為は自己と他者や世界との違和感を瞬時に消滅してしまおうとする衝動であり、滅亡を通してそれらと自己同一することへの病的な願望の表象である。太宰にとって女性は、赤ん坊にとってのガラガラと同様に、ただ自らを慰めて欲しいために求めたにすぎない。「大人というものは佗しいものだ。愛し合っていても、用心して、他人行儀を守らなければならぬ。なぜ、用心深くしなければならぬのだろう。その答はなんでもない。見事に裏切られて、赤恥をかいた事が多すぎたからである。大人とは、裏切られた青年の姿である」(『津軽』)。「愛し合っていても、用心して、他人行儀を守らなければならぬ」のは、「見事に裏切られて、赤恥をかいた事が多すぎたから」ではまったくなく、自己の外に自分が信じてきた価値観や内的世界を一瞥にしない別の論理・倫理を持った他者が存在しているからである。彼の言う「青年」とは生の意欲を失った子供の姿でしかない。過ぎ去ったすべてを忘れ、つねに現にある一瞬一瞬を最大限に生きようとする意欲に基づいた無邪気さを持ちあわせた子供は、たかだか「見事に裏切られて、赤恥をかいた事が多すぎた」だけで何をわめいているのか未熟者が、と「青年」を嘲笑せずにはいられない。太宰の未熟さは坂口安吾と比較すれば明瞭になる。安吾は太宰と並べは大人に見えるが、一人になると子供に戻る。安吾は成熟した子供であったけれども、太宰は未熟な大人にすぎない。吉田和明は、『太宰治』において、太宰は「純粋性」を保持し続けるために「おとなの世界」に入ることを拒否したと言っているが、人は大人へと成長していく際、大半は成熟するのではなく、体制順応し、通俗化していくだけなのであって、未熟な太宰は十分通俗的であり、その意味で、「おとなの世界の住人」にほかならない。
真の問題は自分自身を肯定することから始まる。自己に対する働きかけの意欲によって、自分自身を愛することは初めて可能である。人生は自己と世界との一種妥協の産物だ。「じぶんは〈人間〉から失格している」としたら、太宰は生の出発点を最終的な到達点であるかのように訴えているが、それをあるがままに認めることからしか生は始まらない。「じぶんは〈人間〉から失格している」のなら、いつか〈人間〉が生まれ出るように、自らの生を奉仕することこそ望ましいだろう。
太宰に対して、三島は彼がふんぎりがつけられなかった自己憐憫や自己嫌悪に対するある種の訣別を行ったが、それは自己肯定ではなく、自己否定によってなされたにすぎない。ラジオとテレビの人である太宰は精神的弱さに対するルサンチマンを自己に向けて生を否定する形で晴らそうとしている。一方、戯曲家の三島は自分は違うとして、それを相対的に弱い人間や平凡な人間に対して晴らして優越感を味わっている。三島は目的論的構えによって生を規定し、彼には真に人生や意欲に関する認識が欠けている。太宰にしても、三島にしても、ルサンチマンを晴らすことに生の存在理由を見出し、自らの精神的な弱さのありようを意識化することを避けている。「彼は彼らの感じ方、考え方を自分の中に染み渡らせなければならない。彼らの教えを学びとるのではないのです。ただそれを自分のものにできればよいのです。真理と理性はおのおのの人間に共通なもので、それらを初めに言った人たちのものでも、後から言った人たちのものでもない。蜜蜂はあちらこちらの花からその密を吸い取り、それで自分の蜜をつくる。しかし、その時、蜜はもうすっかり蜜蜂のものになっている」(モンテーニュ『エセー』)。
日本では、太宰だけでなく、三島由紀夫や谷川俊太郎のように偽の問題にとらわれた作家のほうが、一般には、読まれている。日本において文学は健康ではなく、病気として理解されている。しかし、太宰や三島、谷川はただ克服されるべき作品としてのみある。彼らは何が真理であり何が虚偽であるかを問いただしたかもしれないが、真理の価値基準がいかなるものであるのかとは問わない。彼らに欠けているのは新たな価値創造である。問題は解くだけでなく、立てるものでもあろう。
この偽の問題の時期は誰もが一度は通過しなければならないことは間違いない。その上でなければ、人間は真の問題に向かうことはできない。真の問題が人間が生きる際に避けることのできない苦悩と不可分であるのに対して、偽の問題は概念の苦悩──アイデンティティの危機など──にすぎない。真の問題の苦悩に比べれば、偽の問題の苦悩は、冗談にすぎない。と言うのも、偽の問題の苦悩はたた自分の世界に没入し、自らを突き放すことができないことによって生じているにすぎないからである。偽の問題は一般的な概念の領域にあるため、感情移入され得る。真の問題はそれぞれの人間に固有であるから、感情移入は不可能である。真の問題を解明することはそれぞれの人間の持つ限界と可能性を熟知することから始まる。それをつきつめたとき、真の問題が解明される。真の問題の解明とは、偽の問題がもたらされる感情移入という感染症に対する免疫をつくりだすことでもある。
それゆえ、太宰に感情移入する読み手、愛読者は誠に幸せである、と同時に、誠に愚かであると断言するほかないだろう。と言うのは、実は、太宰は、『人間失格』によって、偽の問題にふんぎりがつき、『グッド・バイ』では真の問題の解明へと志向していたからである。
『グッド・バイ』は次のような一節で未完に終わっている。
運が悪い。ケイ子を引っぱり出すことは、まず不可能らしい。
しかし、ただ兄をこわがって、いつまでもケイ子との別離をためらっているのは、ケイ子に対しても失礼みたいなものだ。それにケイ子が風邪で寝ていて、おまけに引揚者の兄が寄宿しているのでは、お金にも、きっと不自由しているだろう。かえって、いまは、チャンスというものかも知れない。病人に優しい見舞いの言葉をかけ、そうしてお金をそっと差し出す。兵隊の兄も、まさか殴りやしいだろう。或るいは、ケイ子以上に、感激し握手など求めるかもしれない。もし万一、自分に乱暴を働くようになったら、……その時こそ、永井キヌ子の怪力のかげに隠れるといい。
まさに百パーセントの利用、活用である。
「いいかい? だぶん大丈夫だと思うけどね、そこに乱暴な男がひとりいてね、もしそいつが腕を振り上げたら、君は軽くこう、取りおさえて下さい。なあに、弱いやつらしいんですがね。」
彼は、めっきりキヌ子に、ていねいな言葉でものを言うようになっていた。
『グッド・バイ』は未完であり、展開がこれからどうなっていくかもわからないので、作品としての全体の出来を判断することはできないとしても、このようにこの作品では文体が大きく変わっていることははっきりと言える。語る主体は愚痴ることをやめ、「ていねいな言葉でもの」を言っており、落ち着き払い、「とても素直で、よく気がきいて」(『人間失格』)、生真面目さを感じさせる。それどころか、禁欲的ですらある。『人間失格』までの作品に頻繁に見られる過剰な羞恥心や負い目、罪悪感、シニシズムは──それらは平凡で通俗的な精神が高尚さに近づこうとする権力意識の表われであるが──もはやない。
Just as I thought it was going alright
I find out I'm wrong, when I thought I was right
S'always the same, it's just a shame, that's all
I could say day, and you'd say night
Tell it's black when I know that it's white
Always the same, it's just a shame, that's all
I could leave but I won't go
Though my heart might tell me so
I can't feel a thing from my head down to my toes
But why does it always seem to be
Me looking at you, you looking at me
It’s always the same, it's just a shame, that's all
Turning me on, turning me off,
Making me feel like I want too much
Living with you's just putting me through it all of the time
Running around, staying out all night
Taking it all instead of taking one bite
Living with you's just putting me through it all of the time
I could leave but I won't go
Well it'd be easier I know
I can't feel a thing from my head down to my toes
Why does it always seem to be
Me looking at you, you looking at me
It’s always the same, it's just a shame, that's all
Truth is I love you
More than I wanted to
There’s no point in trying to pretend
There’s been no-one who
Makes me feel like you do
Say we'll be together till the end
I could leave but I won't go
It’d be easier I know
I can't feel a thing from my head down to my toes
So why does it always seem to be
Me looking at you, you looking at me
It’s always the same, it's just a shame, that's all
But I love you
More than I wanted to
There’s no point in trying to pretend
There’s been no-one who
Makes me feel like you do
Say we'll be together till the end
But just as I thought it was going all right
I find out I'm wrong when I thought I was right
It’s always the same, it's just a shame, that's all
Well I could say day, and you'd say night
Tell me it's black when I know that it's white
It’s always the same, it's just a shame, that's all
That's all
(Genesis “That’s All”)
ドナルド・キーンは、『太宰治の文学』において、『人間失格』以後の彼の文学的可能性について次のように述べている。
太宰は「人間失格」を書き終えた後で何を書くことになったか。幼時から自分の身体中にためて来た毒素をやっとのことで吐き出したので、もはや同様の自伝的小説をこれ以上書けなかった。再出発しなければならなかった。いまや彼は辛辣で皮肉な調子を持たない作品を書けるようになった。死んだ時未完のままだった「グッド・バイ」は、純粋の喜劇小説になりえた。この小説は道化芝居に近く、談話体の会話のすばらしさは、太宰文学の中でも一きわ目だっている。ここで太宰は機知の本領を最もよく発揮している。
太宰にとって、作家の人生は『グッド・バイ』から始まるはずだったのである。彼は真に喜劇作家として出発することができる。太宰は,三島が近代能の戯曲家であるとすれば,近代狂言の最高の戯曲家になりえただろう。しかしながら、太宰は偽の問題から真の問題に移行することができない。何度か言及してきたように、最も笑えないものをおかしさとして提出したりするなど彼の選択は病的に誤っている。彼は最後の最後まで病的な選択をしてしまう。悲劇以上に、喜劇は長く通用する。アリストパネスの喜劇は後の喜劇の規範になっている。アドルフ・ヒトラーを諷刺したチャールズ・チャップリンの『独裁者』は『アカルナイの人々』の「法螺吹き兵士」を原形にした人物が登場しているし、『蛙』の冒頭で、時代遅れと軽蔑されている類いの冗談が、二千五百年もたった今日のテレビでそれと意識されず、笑いを誘っている。太宰の言語に対する真の感受性が生かされれば、それを新たな喜劇作品に流しこむことはたやすい。人間は自己肯定をして、自分の可能性と限界に直面したとき、初めて健康な選択をすることができる。可能性と限界に向かうことから逃げていた以上、選択が、その可能性において、正反対になるのは当然である。太宰は心中未遂や共産党への接近と離反、薬物依存、アルコール依存などを経験したが、彼はそこから何一つ自己超克の意欲を見出せない。ただし依存構造は意志の問題ではなく、精神科の治療対象である。彼は現実から突き放されることを拒む、現実と直面することから逃避している。太宰には愛も生も何一つとしてわからない。それを体験するよりも、死を選ぶ。『人間失格』を書き終えたことによって、太宰は初めて現実から突き放されたが、そういう事態は、『豊饒の海』以後の三島由紀夫と同様に、彼には認めることが決してできない。太宰や三島の死が神話化されるのは、彼らが偽の問題から真の問題へと移行するまさにその瞬間、それを拒み、文学的な可能性の種子を残していってしまったからである。従って、真の問題の範疇に生きた有島武郎の死には、彼らと違って、そういう神話化がない。真の問題へと移行していたならば、太宰も、かりに同じように心中したとしても、たんなる情死と片づけられ、神話化されることはなかったに違いない。
だから、アントン・チェーホフは、自分から影響を受けながらまったく正反対の姿勢に基づいた作品を書いた太宰治に向かって、おそらく、自分の『ともしび』の言葉を引用して、次のように言うだろう。
一つ聞かせてもらいたいもんだけどね、この鉄道が二千年後には、塵埃に化しちまうってことを、われわれが知っているとしたら、いったい何のために、わたしらは智慧をしぼって、工夫したり、月並みな型を見下そうとしてみたり、労働者たちに同情したり、横領をしたり、しなかったりする必要があるんだい? そのほかのことにしても同じさ……君も同意するだろうが、こんな不幸な思考方法のもとでは、何の進歩もあり得ないし、科学も、芸術も、いや、思想そのものも、あり得ないんだよ。
〈了〉
参考文献
奥野健男、『太宰治研究』、筑摩書房、一九六三年
ドナルド・キーン、『日本の作家』、中公文庫、一九七八年
坂口安吾、『堕落論』、角川文庫、一九五七年
太宰治、『斜陽』、新潮文庫、一九五〇年
寺山修司、『幸福論』、角川文庫、一九七三年
寺山修司、『さかさま文学史黒髪篇』、角川文庫、一九八一年
三島由紀夫、『私の遍歴時代』、講談社、一九六四年
吉田和明、『太宰治』、現代書館、一九八七年
吉本隆明、『悲劇の解読』、ちくま文庫、一九八五年
ノースロップ・フライ、『批評の解剖』、海老名宏他訳、法政大学出版局、一九八〇年
『ゲーテ全集』5、人文書院、一九八七年
『新潮世界文学』23、新潮社、一九六九年
『世界の名著』45、中公バックス、一九八〇年
『太宰治全集』別巻、筑摩書房、一九七二年
『ニーチェ全集』9~12巻、理想社、一九七七~八〇年
『日本の文学』65、中央公論社、一九六四年