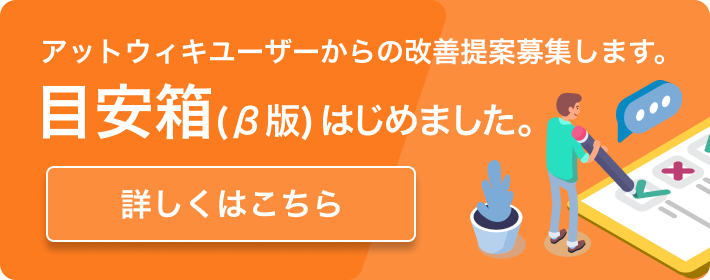投稿日:2010/09/26(日) 16:28:21
香りのいい紅茶を楽しみながら、特に何をするということもなく、
私たちはいつもの放課後を過ごしていた。
私たちはいつもの放課後を過ごしていた。
仮にも軽音部という看板を掲げている以上、差し迫った目標が無くとも練習するのが
当然なのだけれど、お茶の合間に気が向いたら練習という毎日に、
いつの間にか身体が慣れてしまっている。特に今日は、普段から率先して練習に励む梓が、
クラスの用事か何かで、まだ部室に顔を見せていない。つまり、だらけた雰囲気に
歯止めを掛ける人間がいないのだ。故に、常にフリーダムな律や唯はもちろん、
それを諫める役目などとっくに放棄したムギと私までもが、楽器にさわりもせず、
各自思い思いに時間を費やしている、というわけだ。
律は持ってきた雑誌を読むのに夢中らしい。唯はといえば、鏡や手帳やその他の小物を、
出したり片付けたり並べたりぶちまけたり、私には意味不明に見える作業に没頭していて、
部室の中はそこそこ静かだ。私は、ちょうど書きかけの詞があったことを思い出し、
今のうちに書けるなら書いておこうと、取り出したノートを広げている。
なんとなく書けそうな気はするものの、ぴったりのフレーズを探しきれずに
ひとり悶々としてきた頃、お茶のお代わりの準備にムギが席を立った。その動きにつられたのか、
手を止めて入り口の方を見ていた唯が呟く。
「あずにゃん遅いね。今日はもう来ないのかなあ?」
「そのうち来るだろ? ああ見えても、お茶とお菓子大好き人間だからな、梓は」
雑誌から顔も上げずに返答する律に、「それはそうだけど」と曖昧に微笑みながら、
唯は頬杖を突いた。あ、なんか浮かびそう。イメージ通りの言葉の欠片が、
すぐそこまで降りてきてる。私は、気合いを入れ直すべく、カップに残った紅茶を飲み干そうとした。
当然なのだけれど、お茶の合間に気が向いたら練習という毎日に、
いつの間にか身体が慣れてしまっている。特に今日は、普段から率先して練習に励む梓が、
クラスの用事か何かで、まだ部室に顔を見せていない。つまり、だらけた雰囲気に
歯止めを掛ける人間がいないのだ。故に、常にフリーダムな律や唯はもちろん、
それを諫める役目などとっくに放棄したムギと私までもが、楽器にさわりもせず、
各自思い思いに時間を費やしている、というわけだ。
律は持ってきた雑誌を読むのに夢中らしい。唯はといえば、鏡や手帳やその他の小物を、
出したり片付けたり並べたりぶちまけたり、私には意味不明に見える作業に没頭していて、
部室の中はそこそこ静かだ。私は、ちょうど書きかけの詞があったことを思い出し、
今のうちに書けるなら書いておこうと、取り出したノートを広げている。
なんとなく書けそうな気はするものの、ぴったりのフレーズを探しきれずに
ひとり悶々としてきた頃、お茶のお代わりの準備にムギが席を立った。その動きにつられたのか、
手を止めて入り口の方を見ていた唯が呟く。
「あずにゃん遅いね。今日はもう来ないのかなあ?」
「そのうち来るだろ? ああ見えても、お茶とお菓子大好き人間だからな、梓は」
雑誌から顔も上げずに返答する律に、「それはそうだけど」と曖昧に微笑みながら、
唯は頬杖を突いた。あ、なんか浮かびそう。イメージ通りの言葉の欠片が、
すぐそこまで降りてきてる。私は、気合いを入れ直すべく、カップに残った紅茶を飲み干そうとした。
と、そのとき、おもむろに私の方を見て、唯が言ったのだ。
「ねえ澪ちゃん、――恋ってどういうものなの?」
「ぶーーーーっ!!」
口に含んだ紅茶も、手が届きそうだった詞の欠片も、すべてが一瞬にして飛び散った。
私の正面にいた律は、「きたねーな、おい」と、呆れて自分の顔にかかった紅茶を拭っている。
ごめん律、悪気は無かったんだ。
「で、どうしたんだ唯、いきなり。澪に恋愛相談でもしたいのか?」
律が話を向けると、小首を傾げて唯は、
「んー、だって澪ちゃん、かわいい詞とかいっぱい書いてるでしょ? その澪ちゃんを、
恋愛のエクスポートと見込んで、相談したいことがあるんだー」
エクスポートって何だエクスポートって。それを言うならエキスパートだろ、輸出してどうする。
「ていうか、唯、確認なんだけど」
ようやく、お茶と歌詞の噴出ショックから立ち直った私は言った。
「もしかして私をからかうために聞いてるのか? それとも本気で?」
「からかうつもりなんかないよ? 私の周りにいる人では、澪ちゃんが
1番恋愛関係に詳しそうだから、いろいろ聞いてみたかったんだけど……」
そこで律が、余計な茶々を入れてきた。
「唯、おまえ全然わかってないなあ。澪はこう見えても、恋愛経験なんかないんだぞ?
だから、相談しても参考になる答えなんか返ってこないぞ?」
何を知った風な口を利いているのか、いつものことながら呆れてしまう。
律だって、恋愛経験なんか今までないくせに。
「ねえ澪ちゃん、――恋ってどういうものなの?」
「ぶーーーーっ!!」
口に含んだ紅茶も、手が届きそうだった詞の欠片も、すべてが一瞬にして飛び散った。
私の正面にいた律は、「きたねーな、おい」と、呆れて自分の顔にかかった紅茶を拭っている。
ごめん律、悪気は無かったんだ。
「で、どうしたんだ唯、いきなり。澪に恋愛相談でもしたいのか?」
律が話を向けると、小首を傾げて唯は、
「んー、だって澪ちゃん、かわいい詞とかいっぱい書いてるでしょ? その澪ちゃんを、
恋愛のエクスポートと見込んで、相談したいことがあるんだー」
エクスポートって何だエクスポートって。それを言うならエキスパートだろ、輸出してどうする。
「ていうか、唯、確認なんだけど」
ようやく、お茶と歌詞の噴出ショックから立ち直った私は言った。
「もしかして私をからかうために聞いてるのか? それとも本気で?」
「からかうつもりなんかないよ? 私の周りにいる人では、澪ちゃんが
1番恋愛関係に詳しそうだから、いろいろ聞いてみたかったんだけど……」
そこで律が、余計な茶々を入れてきた。
「唯、おまえ全然わかってないなあ。澪はこう見えても、恋愛経験なんかないんだぞ?
だから、相談しても参考になる答えなんか返ってこないぞ?」
何を知った風な口を利いているのか、いつものことながら呆れてしまう。
律だって、恋愛経験なんか今までないくせに。
「唯、律の言うことなんか真に受けるなよ?」
軽く律を睨んだあと、私は唯に向き直り、
「場所変えるか? ここじゃ、誰とは言わないが邪魔が入りそうだからな」
有効なアドバイスができるかどうかはともかく、もし唯が真剣に何かを相談したいのなら、
こちらも真剣に応えないと失礼だ。それに、恋愛話に関するなら尚更、ここではやりにくい。
ちょうどムギが戻ってきたので、唯と話があるからと簡単に事情を告げ、ついでに、
律が邪魔しに来ないよう見張り役もいっしょに頼む。ふたつ返事で引き受けてくれたムギに
感謝しつつ、私たちはゆっくり話せる場所を求めて部室を出た。
実は律よりもムギの方が興味津々な顔をしていたという事実には、気付かなかったことにしておこう。
軽く律を睨んだあと、私は唯に向き直り、
「場所変えるか? ここじゃ、誰とは言わないが邪魔が入りそうだからな」
有効なアドバイスができるかどうかはともかく、もし唯が真剣に何かを相談したいのなら、
こちらも真剣に応えないと失礼だ。それに、恋愛話に関するなら尚更、ここではやりにくい。
ちょうどムギが戻ってきたので、唯と話があるからと簡単に事情を告げ、ついでに、
律が邪魔しに来ないよう見張り役もいっしょに頼む。ふたつ返事で引き受けてくれたムギに
感謝しつつ、私たちはゆっくり話せる場所を求めて部室を出た。
実は律よりもムギの方が興味津々な顔をしていたという事実には、気付かなかったことにしておこう。
■
帰宅部組が残っているかと思ったけれど、3年2組の教室は無人だった。
内緒の話をするには好都合だ。
唯は自分の席に、その前の和の席に私が座り、取りあえず話を聞く体勢を取る。
「で、唯はどういうことを知りたいんだ? もしかして、……誰かに恋した、とか?」
「うーん、それがわかんないから澪ちゃんに聞きたかったんだよぅ」
迷子の子供のような情けない顔をしている唯がおかしくて、私はつい吹き出しそうになる。
なるほど。つまり、誰か気になる人が現れたのだが、それが恋と呼べる感情かどうか
わからない、というところか。おいしいものとかわいいものが大好きで、
年令相応の浮いた話なんて唯には無縁だと思っていただけに、驚くというよりは
感慨の方が大きい。そうか、唯も立派に成長したんだ。
内緒の話をするには好都合だ。
唯は自分の席に、その前の和の席に私が座り、取りあえず話を聞く体勢を取る。
「で、唯はどういうことを知りたいんだ? もしかして、……誰かに恋した、とか?」
「うーん、それがわかんないから澪ちゃんに聞きたかったんだよぅ」
迷子の子供のような情けない顔をしている唯がおかしくて、私はつい吹き出しそうになる。
なるほど。つまり、誰か気になる人が現れたのだが、それが恋と呼べる感情かどうか
わからない、というところか。おいしいものとかわいいものが大好きで、
年令相応の浮いた話なんて唯には無縁だと思っていただけに、驚くというよりは
感慨の方が大きい。そうか、唯も立派に成長したんだ。
「そうだなあ。初めのうちは、恋かどうかなんて意識する必要ないんじゃないか?
私の場合は、その人に対する『好き』がどんどん大きくなっていったあとで、
ああこれが恋なんだ、恋に違いない、って思ったけどな」
「あ、やっぱり!」
頼りなさげな顔から瞬時に花が咲いたような笑顔に変わった唯が、身を乗り出して私に迫った。
「さっきりっちゃんが、澪ちゃんは恋愛経験ないって言ってたけど、ちゃんとあるんだよね?」
「そりゃあもちろん――」
ある、と言いかけて止まる。私がその人に抱く感情は、私自身は恋と信じて疑わないのだけれど、
世間一般の基準から見れば大きくずれている。だから語尾は曖昧になる。
「と、とにかく今は唯のことだろ」
わざとらしいのは承知の上で、私は話を元に戻した。
「唯自身はどうしたいんだ? その人を好きなことは確かなんだろ?」
「うん、好き。大好きだよ。笑顔とか仕草とか見てるだけで、すっごく食べちゃいたいくらい」
「食べたい……のか?」
まさか唯、人肉に興味があったのか? 神様、さっき「唯も立派に成長したんだ」と思ったことは
撤回します……。
「それとねえ、ずっと抱きついたり頬ずりしていたい、かな?」
「聞いてると、なんだかペットに対する愛情みたいだな」
「ペットかあ。うん、そうだね。強がったりもするけど、実は淋しがり屋な猫みたいな子なんだもん」
その人のことを思い浮かべているのか、唯は、見てる方が幸せになれそうな顔で笑っている。
私の場合は、その人に対する『好き』がどんどん大きくなっていったあとで、
ああこれが恋なんだ、恋に違いない、って思ったけどな」
「あ、やっぱり!」
頼りなさげな顔から瞬時に花が咲いたような笑顔に変わった唯が、身を乗り出して私に迫った。
「さっきりっちゃんが、澪ちゃんは恋愛経験ないって言ってたけど、ちゃんとあるんだよね?」
「そりゃあもちろん――」
ある、と言いかけて止まる。私がその人に抱く感情は、私自身は恋と信じて疑わないのだけれど、
世間一般の基準から見れば大きくずれている。だから語尾は曖昧になる。
「と、とにかく今は唯のことだろ」
わざとらしいのは承知の上で、私は話を元に戻した。
「唯自身はどうしたいんだ? その人を好きなことは確かなんだろ?」
「うん、好き。大好きだよ。笑顔とか仕草とか見てるだけで、すっごく食べちゃいたいくらい」
「食べたい……のか?」
まさか唯、人肉に興味があったのか? 神様、さっき「唯も立派に成長したんだ」と思ったことは
撤回します……。
「それとねえ、ずっと抱きついたり頬ずりしていたい、かな?」
「聞いてると、なんだかペットに対する愛情みたいだな」
「ペットかあ。うん、そうだね。強がったりもするけど、実は淋しがり屋な猫みたいな子なんだもん」
その人のことを思い浮かべているのか、唯は、見てる方が幸せになれそうな顔で笑っている。
「けど、猫をかわいがるのと恋とは、ちょっと違うんじゃないか?」
「じゃあ澪ちゃんは、好きな人のことどんな風に思ってたりするの?」
「私か? 私は、そうだなあ……」
目を閉じてその人のことを考えてみる。いつも適当で、強引だったり
子供みたいなところもあったりするけど、私のことは常に気に掛けていてくれる。
私の先に立ったり後押ししたり、憎らしいくらいに私のことがわかっている、
それでいて押しつけがましいわけでもない。
「何かをしてあげたいとかしてほしいとか、全然思わないわけじゃないけど……、
そばにいてくれるだけで満足かな」
「うんうん、それわかるよ。私も、いつもそばにいたいと思うなあ。
いるべき場所にその子がいないだけで不安になっちゃったりするし」
「その人といっしょなら、無理に構えたり虚勢を張ったりする必要なんかないんだ。
何ていうか……そう、私を肯定してくれるんだ、どんなときも。月並みな言い方だけど、
その人がいなかったら今の私はないと思ってるよ」
扉を開くことをためらう私に、世界は怖くなんかないと教えてくれた。
音楽も、音楽を通じて知り合った仲間も、その人の存在なくしては巡り会えなかった。
「だから、いつになるかわからないけど、次は私がその人の役に立てたらいいなって――
いやいやいや、だから、私のことはどうでもいいだろ」
気が付けば、語りすぎた私の顔を、にやにやしながら唯は見ている。
「いいなあ。大人の恋って感じだね、澪ちゃん」
「ち、違うだろ、今は唯の話をするのが目的なんだから。唯は、何かしてあげたいとか
思ったりするのか?」
「私? んー、何ができるかなんて考えたことなかったし、恋かどうかもわかんないのに
偉そうなことは言えないけど……」
虚空を見上げて数秒、唯の笑顔は子供っぽいものから緩やかに変化し、
思い浮かべているであろう人に向かって、愛おしむような視線を向ける。
「私は、壁になりたい、かな。好きな子にはいつでも笑っててほしいから、すぐ近くで、
その子を悲しませるものを跳ね飛ばすような壁になれたらいいな」
一瞬、唯の顔や手足が生えた壁が、「ふんすっ!」と鼻息荒く向かい風に立ち向かう姿を
想像してしまった。そんなシュールな絵も似合う反面、独特の感性で表現される唯の想いは、
春のように柔らかく暖かで、包み込まれる人を幸せにするに違いない。
――唯、それは紛れもなく恋だよ。
「じゃあ澪ちゃんは、好きな人のことどんな風に思ってたりするの?」
「私か? 私は、そうだなあ……」
目を閉じてその人のことを考えてみる。いつも適当で、強引だったり
子供みたいなところもあったりするけど、私のことは常に気に掛けていてくれる。
私の先に立ったり後押ししたり、憎らしいくらいに私のことがわかっている、
それでいて押しつけがましいわけでもない。
「何かをしてあげたいとかしてほしいとか、全然思わないわけじゃないけど……、
そばにいてくれるだけで満足かな」
「うんうん、それわかるよ。私も、いつもそばにいたいと思うなあ。
いるべき場所にその子がいないだけで不安になっちゃったりするし」
「その人といっしょなら、無理に構えたり虚勢を張ったりする必要なんかないんだ。
何ていうか……そう、私を肯定してくれるんだ、どんなときも。月並みな言い方だけど、
その人がいなかったら今の私はないと思ってるよ」
扉を開くことをためらう私に、世界は怖くなんかないと教えてくれた。
音楽も、音楽を通じて知り合った仲間も、その人の存在なくしては巡り会えなかった。
「だから、いつになるかわからないけど、次は私がその人の役に立てたらいいなって――
いやいやいや、だから、私のことはどうでもいいだろ」
気が付けば、語りすぎた私の顔を、にやにやしながら唯は見ている。
「いいなあ。大人の恋って感じだね、澪ちゃん」
「ち、違うだろ、今は唯の話をするのが目的なんだから。唯は、何かしてあげたいとか
思ったりするのか?」
「私? んー、何ができるかなんて考えたことなかったし、恋かどうかもわかんないのに
偉そうなことは言えないけど……」
虚空を見上げて数秒、唯の笑顔は子供っぽいものから緩やかに変化し、
思い浮かべているであろう人に向かって、愛おしむような視線を向ける。
「私は、壁になりたい、かな。好きな子にはいつでも笑っててほしいから、すぐ近くで、
その子を悲しませるものを跳ね飛ばすような壁になれたらいいな」
一瞬、唯の顔や手足が生えた壁が、「ふんすっ!」と鼻息荒く向かい風に立ち向かう姿を
想像してしまった。そんなシュールな絵も似合う反面、独特の感性で表現される唯の想いは、
春のように柔らかく暖かで、包み込まれる人を幸せにするに違いない。
――唯、それは紛れもなく恋だよ。
「ねえねえ澪ちゃん、結局、私の『好き』は恋だと思う? 違うかなあ?」
「その答えは、唯のすぐ目の前にあるよ」
私は、既に決まっている私なりの回答を敢えて口にはしなかった。
他人に言われるより、自分で気付いた方がいいに決まってる。
「目の前……」
比喩表現を真面目に受けたのか単なるボケか、唯は視界のごく近いところを
凝視している。そして、さらりと言うのだ。
「澪ちゃんも、想いが通じるといいね」
「……」
私は1度も、自分の恋が片想いだなんて言ってないのに、しっかり唯にはバレているらしい。
まったく、唯の洞察力にはいつも敵わない。
「唯はまず自分のことに専念しろ。……私は、一方通行のままでいいよ」
告白なんてするつもりない。基本的に私を肯定してくれる人だから、想いを伝えても
完全に拒絶することはないだろう。逆に、そんな人だからこそ、私をあからさまに拒絶できずに
思い悩むという、苦しい立場に追いやってしまうだろう。私の大事な人を、
そんな目に遭わせるわけにはいかないのだ。
「澪ちゃん人気あるんだしさあ、片想いなんてもったいないよ? ていうか、
澪ちゃんが好きだってこと、その人もう気付いてるんじゃないのかなあ」
「まさか。いくら余計なとこだけ鋭い律でも、さすがに気付いてな――」
あ。……ちょっと待て。ナニヲイッタノ、ワタシ? 慌てて口を押さえたがもう遅い。
聞こえてしまっただろうか、ごまかすかしらばっくれるか。耳鳴りがしそうなくらい
頭に血が上ったまま恐る恐る唯の方を窺うと、満面の笑みで私を待ち受ける瞳に捉えられた。
「ゆ……い? なんか聞こえたか……?」
「はいっ、しっかりと聞こえましたー」
「その答えは、唯のすぐ目の前にあるよ」
私は、既に決まっている私なりの回答を敢えて口にはしなかった。
他人に言われるより、自分で気付いた方がいいに決まってる。
「目の前……」
比喩表現を真面目に受けたのか単なるボケか、唯は視界のごく近いところを
凝視している。そして、さらりと言うのだ。
「澪ちゃんも、想いが通じるといいね」
「……」
私は1度も、自分の恋が片想いだなんて言ってないのに、しっかり唯にはバレているらしい。
まったく、唯の洞察力にはいつも敵わない。
「唯はまず自分のことに専念しろ。……私は、一方通行のままでいいよ」
告白なんてするつもりない。基本的に私を肯定してくれる人だから、想いを伝えても
完全に拒絶することはないだろう。逆に、そんな人だからこそ、私をあからさまに拒絶できずに
思い悩むという、苦しい立場に追いやってしまうだろう。私の大事な人を、
そんな目に遭わせるわけにはいかないのだ。
「澪ちゃん人気あるんだしさあ、片想いなんてもったいないよ? ていうか、
澪ちゃんが好きだってこと、その人もう気付いてるんじゃないのかなあ」
「まさか。いくら余計なとこだけ鋭い律でも、さすがに気付いてな――」
あ。……ちょっと待て。ナニヲイッタノ、ワタシ? 慌てて口を押さえたがもう遅い。
聞こえてしまっただろうか、ごまかすかしらばっくれるか。耳鳴りがしそうなくらい
頭に血が上ったまま恐る恐る唯の方を窺うと、満面の笑みで私を待ち受ける瞳に捉えられた。
「ゆ……い? なんか聞こえたか……?」
「はいっ、しっかりと聞こえましたー」
……マズい。これは最高にマズい。背筋やこめかみやいろんなところを、
冷や汗が流れていく。
「頼む、唯、律には言わないでくれ。いや、律じゃなくても、誰にも言わないでくれっ」
「別にいいよ? そだよね、どうせなら自分の口でちゃんと言いたいもんね」
「そうじゃなくてっ!」
きょとんとした顔の唯を前に、言いたいこと、言わないといけないことが頭の中で整理できない。
「と、とにかく、律は関係ないんだ。あ、いや、関係ないっていうのは、私が一方的に想ってるだけで、
律はそういう趣味じゃないってことだぞ。だっておかしいだろ、同性が好きだなんて。
律はそんなんじゃないぞ、断じて。私がおかしいだけだからな?」
「澪ちゃん、落ち着いて」
「律に知られたらダメなんだ。今までどおりの友達ではいられなくなるし、もしかしたら、
律までみんなに変な目で見られるかもしれない。だから、頼む――」
「落ち着いてってば」
パニックのスパイラルに巻き込まれた私とは対照的に、唯は緩やかな動作で私の手を握る。
「大丈夫だよ、澪ちゃん。誰にも言わない。約束するよ?」
「……ホントか?」
「うん。それにね、――私も同じだから」
1度、更に力を込めて私の手をギュッと握り、
「そろそろ部室戻ろっか? あんまり遅いと、りっちゃんたち心配するよね」
唯は、私の不安も何もかも包み込むような穏やかな笑みで、私の手を引いて立ち上がった。
冷や汗が流れていく。
「頼む、唯、律には言わないでくれ。いや、律じゃなくても、誰にも言わないでくれっ」
「別にいいよ? そだよね、どうせなら自分の口でちゃんと言いたいもんね」
「そうじゃなくてっ!」
きょとんとした顔の唯を前に、言いたいこと、言わないといけないことが頭の中で整理できない。
「と、とにかく、律は関係ないんだ。あ、いや、関係ないっていうのは、私が一方的に想ってるだけで、
律はそういう趣味じゃないってことだぞ。だっておかしいだろ、同性が好きだなんて。
律はそんなんじゃないぞ、断じて。私がおかしいだけだからな?」
「澪ちゃん、落ち着いて」
「律に知られたらダメなんだ。今までどおりの友達ではいられなくなるし、もしかしたら、
律までみんなに変な目で見られるかもしれない。だから、頼む――」
「落ち着いてってば」
パニックのスパイラルに巻き込まれた私とは対照的に、唯は緩やかな動作で私の手を握る。
「大丈夫だよ、澪ちゃん。誰にも言わない。約束するよ?」
「……ホントか?」
「うん。それにね、――私も同じだから」
1度、更に力を込めて私の手をギュッと握り、
「そろそろ部室戻ろっか? あんまり遅いと、りっちゃんたち心配するよね」
唯は、私の不安も何もかも包み込むような穏やかな笑みで、私の手を引いて立ち上がった。
■
私たちが部室に戻ると、遅れていた梓は既にギターを抱えて練習に励んでいた。
唯を見るなり、「自分だけが練習しないならまだしも、澪先輩まで巻き込んで……」と、
少々ご立腹のようだ。まあ、その程度のお叱りで唯が動じるはずもないが。
唯が誰にも言わないと約束してくれた以上、私はそれを信じるしかないけれど、
そこはやっぱり気になるのが当然で、ベースを持っても練習に身が入らない。
そんな私の様子を見てとったのか、普段よりは早めの時刻に、律が「今日はもう解散!」の号令を発し、
部活終了となった。
唯を見るなり、「自分だけが練習しないならまだしも、澪先輩まで巻き込んで……」と、
少々ご立腹のようだ。まあ、その程度のお叱りで唯が動じるはずもないが。
唯が誰にも言わないと約束してくれた以上、私はそれを信じるしかないけれど、
そこはやっぱり気になるのが当然で、ベースを持っても練習に身が入らない。
そんな私の様子を見てとったのか、普段よりは早めの時刻に、律が「今日はもう解散!」の号令を発し、
部活終了となった。
ベースを片付けながらも、ついつい唯を気にしてしまう。律にバレては困るのはもちろん、
唯自身も私のことを異常者だと思ったかもしれない。
「あ……れ?」
ふと、さっきは自分がパニクっていたせいで聞き流したやり取りを思い出した。
確か唯は、「私も同じ」だと言ってなかったか? あれはどういう意味だ?
「ほれ、帰るぞ澪」
軽く後頭部を叩かれ我に返った。見れば私以外のみんなは帰り支度を済ませている。
「う、うん。ごめんごめん」
慌てて手早く片付けを済ませ、みんなを追うように私も部室を後にした。
唯自身も私のことを異常者だと思ったかもしれない。
「あ……れ?」
ふと、さっきは自分がパニクっていたせいで聞き流したやり取りを思い出した。
確か唯は、「私も同じ」だと言ってなかったか? あれはどういう意味だ?
「ほれ、帰るぞ澪」
軽く後頭部を叩かれ我に返った。見れば私以外のみんなは帰り支度を済ませている。
「う、うん。ごめんごめん」
慌てて手早く片付けを済ませ、みんなを追うように私も部室を後にした。
とりとめのない話をしながら歩くみんなから遅れること数歩、私は無言で考えていた。
唯は、私の恋する相手が律だとバレて慌てていたときに言ったのだ。
「私も同じ」だと。ということは、まさか唯も律のことを?
「いやいやいや、それは違うだろ」
そうじゃないとすれば、唯の好きな相手も同性、女の子だということか?
そういえば唯は、「実は淋しがり屋な猫みたいな子」と言っていた。今になって考えれば、
その表現は女の子に対する形容である方が無理がない。
では、やはり……そうなのか?
前を行く唯の、華奢な後ろ姿を見つめた。日頃から悩みなんて無さそうな顔をしているのに、
唯は唯なりに、いろいろなものに立ち向かって生きてるのかもしれない。
――もちろん、実際には何も考えてないという可能性もあるけれど。
唯は、私の恋する相手が律だとバレて慌てていたときに言ったのだ。
「私も同じ」だと。ということは、まさか唯も律のことを?
「いやいやいや、それは違うだろ」
そうじゃないとすれば、唯の好きな相手も同性、女の子だということか?
そういえば唯は、「実は淋しがり屋な猫みたいな子」と言っていた。今になって考えれば、
その表現は女の子に対する形容である方が無理がない。
では、やはり……そうなのか?
前を行く唯の、華奢な後ろ姿を見つめた。日頃から悩みなんて無さそうな顔をしているのに、
唯は唯なりに、いろいろなものに立ち向かって生きてるのかもしれない。
――もちろん、実際には何も考えてないという可能性もあるけれど。
いつもの信号で、私たち5人は二手に分かれた。
「また明日なー」
「はい、お疲れ様でした」
明るく手を振る唯たちを見送り、律と私は再び歩き出す。
「で、唯の恋愛相談はうまくいったのか?」
前置きなしに、律が言った。唯と私が部室に戻ってもその話題に触れてこなかったから、
忘れてるんだとばかり思っていたのに、敵はしっかり覚えていたらしい。
「しっかしあの唯がなあ。まあ高3にもなれば色気づいても無理ないか」
「おまえ、おもしろがってるのか真面目に心配してるのか、どっちなんだ?」
「それはもちろん、おもしろがってますわよ?」
口ではいい加減なことを言ってるくせに、いざというときには頼りになる律だから、
唯の恋も実は応援したいのだろう。
「……あ」
しかし、厄介なことがひとつ。もし唯の好きな相手が同性だと知ったら、
それでも律は変わりなく唯のことを応援するだろうか? 嫌ったり仲間はずれにまでは
しないにせよ、偏見を持たずに唯を見守ってくれるだろうか?
心持ち足取りが重くなった私は、律の後ろ姿を見つめて歩いた。律なら大丈夫だと思うけれど、
冷静に考えれば、大丈夫と言い切る確証なんてどこにもないのだ。
「澪、どしたー? 唯の相談相手で疲れたのか?」
遅れ気味の歩調に気付いたのか、律は振り向いてこちらを見る。しばらく無言で、
私も律の顔を見つめた。さりげなく私を気に掛けてくれるから、
不安なときはいつも律に頼ってしまうんだ、私は。
「なあ律」
「んー?」
「あのさ、……唯のことなんだけど」
律がどういう反応を見せるか怖くて、私は視線を逸らして言った。
「もし――もし唯の好きな相手が、ホントは好きになっちゃいけない人でも、
律は反対しないか? 唯のこと信じて応援してやれるか?」
「は? なに言ってんだ?」
「だから、唯の相手がどんな人間でも、律は唯を否定したりしないか?」
「また明日なー」
「はい、お疲れ様でした」
明るく手を振る唯たちを見送り、律と私は再び歩き出す。
「で、唯の恋愛相談はうまくいったのか?」
前置きなしに、律が言った。唯と私が部室に戻ってもその話題に触れてこなかったから、
忘れてるんだとばかり思っていたのに、敵はしっかり覚えていたらしい。
「しっかしあの唯がなあ。まあ高3にもなれば色気づいても無理ないか」
「おまえ、おもしろがってるのか真面目に心配してるのか、どっちなんだ?」
「それはもちろん、おもしろがってますわよ?」
口ではいい加減なことを言ってるくせに、いざというときには頼りになる律だから、
唯の恋も実は応援したいのだろう。
「……あ」
しかし、厄介なことがひとつ。もし唯の好きな相手が同性だと知ったら、
それでも律は変わりなく唯のことを応援するだろうか? 嫌ったり仲間はずれにまでは
しないにせよ、偏見を持たずに唯を見守ってくれるだろうか?
心持ち足取りが重くなった私は、律の後ろ姿を見つめて歩いた。律なら大丈夫だと思うけれど、
冷静に考えれば、大丈夫と言い切る確証なんてどこにもないのだ。
「澪、どしたー? 唯の相談相手で疲れたのか?」
遅れ気味の歩調に気付いたのか、律は振り向いてこちらを見る。しばらく無言で、
私も律の顔を見つめた。さりげなく私を気に掛けてくれるから、
不安なときはいつも律に頼ってしまうんだ、私は。
「なあ律」
「んー?」
「あのさ、……唯のことなんだけど」
律がどういう反応を見せるか怖くて、私は視線を逸らして言った。
「もし――もし唯の好きな相手が、ホントは好きになっちゃいけない人でも、
律は反対しないか? 唯のこと信じて応援してやれるか?」
「は? なに言ってんだ?」
「だから、唯の相手がどんな人間でも、律は唯を否定したりしないか?」
我ながらわかりにくいと思うけれど、洗いざらい真実をぶちまけるわけにいかず、
結果として質問のピントが曖昧だ。それでも、私は律にすがりたかったのだ。唯を否定しないでと。
そして――これは言ってから気付いたのだが――唯と同じく同性を好きになった私を否定しないでと。
しばらく不得要領な表情で私を見ていた律は、ふっと柔らかな微笑みを見せた後、
勢いよく笑い飛ばした。
「なーにバカなこと言ってんだよ。ほれ、行くぞ」
私の肩をポンポンと叩き、続く動作でそのまま私の手を握る。
「否定なんかするわけねーし? 危なっかしいことばっかしてるけど、ああ見えても唯は、
間違ったことはしないってわかってるさ。それに、相手の方だって十分しっかりしてるしな」
「……そっか」
律に手を引かれ、私もゆっくりと歩き出した。そっか。聞くまでもなかった。
人一倍みんなのことを見てる律が、仲間を否定するわけなんてないんだ。
と、引っ掛かる台詞が律の口から出たことが気になった。
「あれ? 律、唯の相手が誰だか、唯から聞いてるのか?」
「ん? いや、唯からは聞いてないけどな。んなもん、誰でも知ってるだろ?
知らないのは澪と、あとは相手本人だけじゃねーのか?」
え……。そんなに知ってて当然の秘密だったのか? もしかして知らない私がおかしいのか?
「じゃあムギも知ってるのか?」
「そりゃあ知ってるだろうな」
「梓も?」
「あ……?」
虚を突かれたような表情で、律の足が止まる。そして思い切り吹き出して言った。
「あー、梓は知らねーだろな、うん」
何がおかしくてたまらないのか不明だけれど、律は笑いをこらえるのに必死だ。
「なんだ律、『誰でも知ってる』なんて大げさなこと言ったくせに、
梓だって知らないんじゃないか」
「ごめんごめん、まあとにかく、澪が思ってるよりずっと、実はみんな恋をしてるってことさ」
「意味がわからん。っていうか無理にいい話系に持って行こうとしてるだろ?」
私は、呆れた風を装いながら、律の横顔を見た。命短し恋せよ乙女というけれど、
確かに命と比べたら、恋が成就するまでの時間は果てしなく長い。そしてもちろん、
成就するとは限らない。
――ま、しょうがないか。好きになったのは私の勝手だからな。
取りあえず今は、横に並んで歩けるだけ歩いていこう。それではダメだと自覚したときに初めて、
私の恋は恋と呼べるものになるのかもしれない。
結果として質問のピントが曖昧だ。それでも、私は律にすがりたかったのだ。唯を否定しないでと。
そして――これは言ってから気付いたのだが――唯と同じく同性を好きになった私を否定しないでと。
しばらく不得要領な表情で私を見ていた律は、ふっと柔らかな微笑みを見せた後、
勢いよく笑い飛ばした。
「なーにバカなこと言ってんだよ。ほれ、行くぞ」
私の肩をポンポンと叩き、続く動作でそのまま私の手を握る。
「否定なんかするわけねーし? 危なっかしいことばっかしてるけど、ああ見えても唯は、
間違ったことはしないってわかってるさ。それに、相手の方だって十分しっかりしてるしな」
「……そっか」
律に手を引かれ、私もゆっくりと歩き出した。そっか。聞くまでもなかった。
人一倍みんなのことを見てる律が、仲間を否定するわけなんてないんだ。
と、引っ掛かる台詞が律の口から出たことが気になった。
「あれ? 律、唯の相手が誰だか、唯から聞いてるのか?」
「ん? いや、唯からは聞いてないけどな。んなもん、誰でも知ってるだろ?
知らないのは澪と、あとは相手本人だけじゃねーのか?」
え……。そんなに知ってて当然の秘密だったのか? もしかして知らない私がおかしいのか?
「じゃあムギも知ってるのか?」
「そりゃあ知ってるだろうな」
「梓も?」
「あ……?」
虚を突かれたような表情で、律の足が止まる。そして思い切り吹き出して言った。
「あー、梓は知らねーだろな、うん」
何がおかしくてたまらないのか不明だけれど、律は笑いをこらえるのに必死だ。
「なんだ律、『誰でも知ってる』なんて大げさなこと言ったくせに、
梓だって知らないんじゃないか」
「ごめんごめん、まあとにかく、澪が思ってるよりずっと、実はみんな恋をしてるってことさ」
「意味がわからん。っていうか無理にいい話系に持って行こうとしてるだろ?」
私は、呆れた風を装いながら、律の横顔を見た。命短し恋せよ乙女というけれど、
確かに命と比べたら、恋が成就するまでの時間は果てしなく長い。そしてもちろん、
成就するとは限らない。
――ま、しょうがないか。好きになったのは私の勝手だからな。
取りあえず今は、横に並んで歩けるだけ歩いていこう。それではダメだと自覚したときに初めて、
私の恋は恋と呼べるものになるのかもしれない。
-終-
- 澪が本当に律の事が好きだっていうのが凄く伝わってきた… -- 名無しさん (2010-12-15 00:36:50)