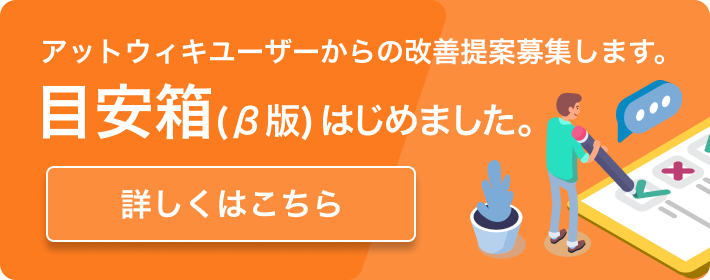―――― 1日目 Crimson Riot ――――
夜である。結局インデックスの説明を聞いていたら正午どころか、時刻はいつの間にか六時を回っていたのだ。冬の空は暮れるのが早く、完全に日の落ちた学園都市の道路を上条当麻は歩いている。無論、説明だけでこのような時間がかかるわけがない。もちろん、上条の理解できない単語がズラズラと並んでいたから、というだけではなく、御坂美琴からの訳の分からない電話や真面目に自分の身体に起こっている異変について知りたい上条に対してインデックスは二時間ほど説明すると飽きてきたのか、面倒くさそうに上条の質問に答えるだけになったのが原因でもあった。もちろん、間に昼食を取ったり、猫が行方不明になったりと諸々の事情があったのだが、これはそのさい置いておく事にする。だが、まぁインデックスの長い長い説明のお陰で今朝突然現れた、この紋章もとい令呪についてはなんとなく理解できたし、これから自分が巻き込まれそうな事件についても理解はできた。インデックスの話によればどうやら、体に令呪が刻まれてしまった以上はその聖杯戦争から逃れる術はない、とのことだった。十年前の聖杯戦争では監督役の代行者がその辺は管理していて拒否しようと思えば拒否できたらしいのだが、今回はインデックスにさえ分からないような突発的に発生した聖杯戦争であるため、もちろんそのような監督役の所在は明らかにはなっていない。隣人の魔術師兼多重スパイである土御門元春にも相談してみようかと試みたが今日は一日中留守にしているらしく、インターフォンに反応することはなかった。
「はぁ・・・・」
上条は買出しを終え、雑多な品物が無造作に挿入されたビニール袋を片手に提げながら深く溜息をついた。まったくこれは同考えても不幸な話ではある。訳の分からぬままに魔術師の殺し合いに参加するようなハメになり、その一環としてもちろん他のマスターやサーヴァントから命を狙われることになる。そのため、一人で出歩くなとインデックスには窘められたが上条にとっては聖杯戦争と言うものじたいに実感が湧かないのでどうにも危機感は湧かなかった。確かに不安はあるが恐ろしさというものは感じない。
「はぁ・・・・」
もう一度同じ様な溜息を吐く。もちろん、そんな溜息で上条当麻の憂鬱が解消されるはずもなく、ただ帰ってから待ち受けているインデックスとのサーヴァントの召喚なるものを控えていたずらに上条は口から空気を放出していた。インデックス曰く、サーヴァントの召喚には手間は掛かるがそう難しいモノではないらしい。問題は上条の『幻想殺し』が召喚にどのような影響を及ぼすのか、だそうだが、そもそも上条には聖杯戦争に参加しようとする意志さえない。だから、サーヴァントを召喚した後はちゃっちゃとこの令呪とやらを使ってマスターを降りようと考えていた。令呪はサーヴァントに対する三回の絶対命令権であることは聞いたし、これとサーヴァントがなくなればマスターとしての資格もなくなることも質問して確認した。召喚したサーヴァントには悪いが他の魔術師をあたってもらうことになる。もちろん、召喚自体に失敗してこの令呪が消えてくれれば上条としてはベストな流れであった。
「だいたい、何で俺なんだよ」
辺りに人がいないことを確認してひとりごちる。無論、独り言なのだから仮にソレが疑問形だとしても答えは返ってくるはずがない。そう、それは独り言のはずだったからだ。だが、その声はどこからともなく、いや何故か上条の頭上から返ってきた。
「はぁ・・・・」
上条は買出しを終え、雑多な品物が無造作に挿入されたビニール袋を片手に提げながら深く溜息をついた。まったくこれは同考えても不幸な話ではある。訳の分からぬままに魔術師の殺し合いに参加するようなハメになり、その一環としてもちろん他のマスターやサーヴァントから命を狙われることになる。そのため、一人で出歩くなとインデックスには窘められたが上条にとっては聖杯戦争と言うものじたいに実感が湧かないのでどうにも危機感は湧かなかった。確かに不安はあるが恐ろしさというものは感じない。
「はぁ・・・・」
もう一度同じ様な溜息を吐く。もちろん、そんな溜息で上条当麻の憂鬱が解消されるはずもなく、ただ帰ってから待ち受けているインデックスとのサーヴァントの召喚なるものを控えていたずらに上条は口から空気を放出していた。インデックス曰く、サーヴァントの召喚には手間は掛かるがそう難しいモノではないらしい。問題は上条の『幻想殺し』が召喚にどのような影響を及ぼすのか、だそうだが、そもそも上条には聖杯戦争に参加しようとする意志さえない。だから、サーヴァントを召喚した後はちゃっちゃとこの令呪とやらを使ってマスターを降りようと考えていた。令呪はサーヴァントに対する三回の絶対命令権であることは聞いたし、これとサーヴァントがなくなればマスターとしての資格もなくなることも質問して確認した。召喚したサーヴァントには悪いが他の魔術師をあたってもらうことになる。もちろん、召喚自体に失敗してこの令呪が消えてくれれば上条としてはベストな流れであった。
「だいたい、何で俺なんだよ」
辺りに人がいないことを確認してひとりごちる。無論、独り言なのだから仮にソレが疑問形だとしても答えは返ってくるはずがない。そう、それは独り言のはずだったからだ。だが、その声はどこからともなく、いや何故か上条の頭上から返ってきた。
「何を馬鹿な・・・・聖杯に選ばれたからであろうが」
「っ!!」
上空を仰ぎ見る。そこには誰もいない。だが、いる。確かにそこから男の声が聞こえてくる。野太い男の声がハッキリとその何もない空間から聞こえてくる。そして、明確な殺意。直感で分かる。逃げなければ殺される、と。
渾身の力で駆け出した。寮までの距離は三百メートルほど。全力で走れば一分掛からずに走り抜けられるだろう。だが、その一分を声の主は許すかどうか。もちろん、答えは否だった。
駆け抜ける烈風。一陣の風。吹き荒れる暴風はまるで嵐のようだった。いつの間に姿を現したのか、恐らく声の主であろう男は全力疾走していた上条当麻を抜き去り、巨大な壁となって屹立していた。月夜に照らされる豪奢な鎧に筋骨隆々とした体躯、二メートルを越しているであろうその長身はまさに壁と表現するよりは他ならなかった。そして、何よりも異様なもの。それは男が手に携える巨大で鮮やかな金刺繍が施された戟とその男の背後で嘶くまるで血に染まったような真っ赤な馬だった。たとえ魔術に精通していないものでも分かる溢れんばかりの威圧感と魔力。戦いなど経験したことのない人物であれば一瞬で気絶してしまいそうなそんな気迫が男からは所狭しと溢れていた。
「っ、誰だよ、テメェ」
声が震える。掌に汗が広がり、喉がチリチリと焼けるように痛い。
「誰?愚問だな。ほれ、貴様もマスターならサーヴァントを出せ。結界の中に入ってこれるのなら魔術しか有り得んだろう」
言われてやっと理解した。目の前の物体が何であるかを。目の前にいるのはさきほどインデックスと話していたサーヴァントという存在なのだろう。そして、これは聖杯戦争の戦いの一環で、他のマスターがマスターである上条当麻を殺しに来た、というただそれだけのこと。しかし、上条はあまりにもサーヴァントについて誤解していた。聞いた話ではサーヴァントは使い魔。いわゆる、蝙蝠やネズミを多少強力にしたものだと考えていたのだ。だから、今まさに自分の目の前にいる怪物がサーヴァントだということが理屈では分かっていても心が理解していなかった。一言にして言えば、有り得ない、である。
「ほら、どうしたサーヴァントを出せ。背後に控えているのだろう?」
「まだ召喚してねぇ・・・って、言っても信じてくれそうにはねぇな・・・っくそ、インデックスのやつ、サーヴァントはサーヴァントを知覚できるとか言ってたのに」
目の前の男は上条がサーヴァントの召喚を行っていることを知らないようだ。その様子からすると、結界(上条は存在すら気がつかなかったが)の中に入ってきた人物全てに攻撃を行っているのかもしれない。男はいまか、いまかと待ち遠しそうに豪奢な武器を構えている。体が震えた。走って逃げたとしても追いつかれる。まともに戦ってもおそらく勝ち目はない。ならば、上条の取るべき道はただ一つ。
「ほぅ?」
右の拳を深く落とし、左手の拳を腰の辺りへ持っていく。つまり、上条はこの目の前の化け物にたいして無謀にも臨戦態勢を取っているのである。
「馬鹿か?サーヴァントなしで俺と渡り合えるとでも?」
男の怒りが感じられる。さっきまでとは比べ物にならないような殺気が辺りを包み込む。無論、上条とてまともにやり合う気などない。賭けるのは自分の能力『幻想殺し』。サーヴァントとは聖杯が呼びだした言うなれば最上級の魔術である。上条の『幻想殺し』が魔術や超能力といった異能をことごとく打ち消すことができる。ならば、その例に従うならばこの目の前の魔力の塊だって殺せるはずである。もちろん、触れることができれば、の話だが。
渾身の力で駆け出した。寮までの距離は三百メートルほど。全力で走れば一分掛からずに走り抜けられるだろう。だが、その一分を声の主は許すかどうか。もちろん、答えは否だった。
駆け抜ける烈風。一陣の風。吹き荒れる暴風はまるで嵐のようだった。いつの間に姿を現したのか、恐らく声の主であろう男は全力疾走していた上条当麻を抜き去り、巨大な壁となって屹立していた。月夜に照らされる豪奢な鎧に筋骨隆々とした体躯、二メートルを越しているであろうその長身はまさに壁と表現するよりは他ならなかった。そして、何よりも異様なもの。それは男が手に携える巨大で鮮やかな金刺繍が施された戟とその男の背後で嘶くまるで血に染まったような真っ赤な馬だった。たとえ魔術に精通していないものでも分かる溢れんばかりの威圧感と魔力。戦いなど経験したことのない人物であれば一瞬で気絶してしまいそうなそんな気迫が男からは所狭しと溢れていた。
「っ、誰だよ、テメェ」
声が震える。掌に汗が広がり、喉がチリチリと焼けるように痛い。
「誰?愚問だな。ほれ、貴様もマスターならサーヴァントを出せ。結界の中に入ってこれるのなら魔術しか有り得んだろう」
言われてやっと理解した。目の前の物体が何であるかを。目の前にいるのはさきほどインデックスと話していたサーヴァントという存在なのだろう。そして、これは聖杯戦争の戦いの一環で、他のマスターがマスターである上条当麻を殺しに来た、というただそれだけのこと。しかし、上条はあまりにもサーヴァントについて誤解していた。聞いた話ではサーヴァントは使い魔。いわゆる、蝙蝠やネズミを多少強力にしたものだと考えていたのだ。だから、今まさに自分の目の前にいる怪物がサーヴァントだということが理屈では分かっていても心が理解していなかった。一言にして言えば、有り得ない、である。
「ほら、どうしたサーヴァントを出せ。背後に控えているのだろう?」
「まだ召喚してねぇ・・・って、言っても信じてくれそうにはねぇな・・・っくそ、インデックスのやつ、サーヴァントはサーヴァントを知覚できるとか言ってたのに」
目の前の男は上条がサーヴァントの召喚を行っていることを知らないようだ。その様子からすると、結界(上条は存在すら気がつかなかったが)の中に入ってきた人物全てに攻撃を行っているのかもしれない。男はいまか、いまかと待ち遠しそうに豪奢な武器を構えている。体が震えた。走って逃げたとしても追いつかれる。まともに戦ってもおそらく勝ち目はない。ならば、上条の取るべき道はただ一つ。
「ほぅ?」
右の拳を深く落とし、左手の拳を腰の辺りへ持っていく。つまり、上条はこの目の前の化け物にたいして無謀にも臨戦態勢を取っているのである。
「馬鹿か?サーヴァントなしで俺と渡り合えるとでも?」
男の怒りが感じられる。さっきまでとは比べ物にならないような殺気が辺りを包み込む。無論、上条とてまともにやり合う気などない。賭けるのは自分の能力『幻想殺し』。サーヴァントとは聖杯が呼びだした言うなれば最上級の魔術である。上条の『幻想殺し』が魔術や超能力といった異能をことごとく打ち消すことができる。ならば、その例に従うならばこの目の前の魔力の塊だって殺せるはずである。もちろん、触れることができれば、の話だが。
「おおおおおぉぉぉぉっっっ!!」
踏み込む。少しでも触れられれば、と考えて疾走する。男は呆れたように口元に小さな笑みを浮かべると手にする大きな戟を振りかざした。刹那、振り下ろされる天よりの一撃。もちろん、上条には剣戟さえ見えない。だが、その戟の終着点ぐらいならば誰だって予想できる。右手を翳すのは自分の頭上。どういう軌道だとしても関係ない。武器が振り下ろされる以上、狙われる部位は頭上以外にはまず考えられない。無論、それはサーヴァントの一撃。受け止めようとしたところで腕ごと切断されるのが当たり前である。だが、その頭上に翳された手は全ての異能を打ち消す奇跡の右手。何も能力を持たない上条が唯一能力として誇れる絶対なる守護者。ぶつかりあう武器と腕。瞬間、ガキィという音と共に両者がぶつかり合う。だが、それとて一瞬。上条の腕に触れた瞬間に男の得物はバキィンという音を立てて粉々に砕け散った。男の表情が驚愕に染まる。そんな馬鹿な、と目の前の光景に心が奪われる。その隙を上条当麻は見逃さなかった。
―殺せる
そう理解し、武器を砕いた右腕をそのままに体をそのまま前進させる。掌を返しただ男に触れようと手を伸ばす。距離はわずかに十センチ。一気に加速した上条の右腕がまさに男を捕らえようとした時、
踏み込む。少しでも触れられれば、と考えて疾走する。男は呆れたように口元に小さな笑みを浮かべると手にする大きな戟を振りかざした。刹那、振り下ろされる天よりの一撃。もちろん、上条には剣戟さえ見えない。だが、その戟の終着点ぐらいならば誰だって予想できる。右手を翳すのは自分の頭上。どういう軌道だとしても関係ない。武器が振り下ろされる以上、狙われる部位は頭上以外にはまず考えられない。無論、それはサーヴァントの一撃。受け止めようとしたところで腕ごと切断されるのが当たり前である。だが、その頭上に翳された手は全ての異能を打ち消す奇跡の右手。何も能力を持たない上条が唯一能力として誇れる絶対なる守護者。ぶつかりあう武器と腕。瞬間、ガキィという音と共に両者がぶつかり合う。だが、それとて一瞬。上条の腕に触れた瞬間に男の得物はバキィンという音を立てて粉々に砕け散った。男の表情が驚愕に染まる。そんな馬鹿な、と目の前の光景に心が奪われる。その隙を上条当麻は見逃さなかった。
―殺せる
そう理解し、武器を砕いた右腕をそのままに体をそのまま前進させる。掌を返しただ男に触れようと手を伸ばす。距離はわずかに十センチ。一気に加速した上条の右腕がまさに男を捕らえようとした時、
「戻れ!ライダー!!」
とどこからともなく消えた声とほぼ同時に必殺のつもりで放った右手をすり抜けるように男とその背後に立っていた馬はそこにいなかったように掻き消えてしまった。
「っ!?」
辺りを見回しても殺気どころか気配すらない。完全に男はこの近辺から消えていた。避けるタイミングなど与えず、自分でも惚れ惚れするぐらいに理想的に決ったはずの一撃が交わされたのだ。いや、あれは交わした、というよりはいなくなったというほうが妥当であった。それぐらい男は忽然と姿を消したのである。それだけではない。あの上条の一撃は普通ならばどうということもないただの打撃である。普通のマスターから見れば何もサーヴァントを撤退させるだけの攻撃でもなかったはずだ。それなのに、あの男のマスターはサーヴァントを引かせた。それはつまり、
「俺の事を・・・知ってんのか」
知人で魔術師かつ『幻想殺し』の能力を知っている人物・・・・を上条は頭の中で思い浮かべたがあまりにも多いので途中でやめた。この半年前後で戦ってきた魔術師はあまりにも多い。それにこっちは知らなくても向こうだけが知っている可能性も十分に考えられる。今はまだ具体的な答えを出すことなどできなかった。
「・・・」
上条当麻は自分の右腕、そして辺りを一通り見回してから当初の目的地である学生寮へと足を向けた。殺されかけた。その事実が上条当麻を締め付ける。聖杯戦争。魔術師同士の殺し合い。そんなモノに参加する気は毛頭ない。だが、例えばさっきのサーヴァントのマスターが自分の知人だとしたら。上条はその知人が殺し殺されるのをただ見ていることになる。
「・・・」
複雑な気持ちだった。止めるのならばそれだけの責任を背負い、やるのならばそれだけの覚悟を背負わねばならない。その覚悟と責任をどう持つのか、いやまず持てるのかどうかを上条は思案しつつ学生寮へと向かっていった。
「っ!?」
辺りを見回しても殺気どころか気配すらない。完全に男はこの近辺から消えていた。避けるタイミングなど与えず、自分でも惚れ惚れするぐらいに理想的に決ったはずの一撃が交わされたのだ。いや、あれは交わした、というよりはいなくなったというほうが妥当であった。それぐらい男は忽然と姿を消したのである。それだけではない。あの上条の一撃は普通ならばどうということもないただの打撃である。普通のマスターから見れば何もサーヴァントを撤退させるだけの攻撃でもなかったはずだ。それなのに、あの男のマスターはサーヴァントを引かせた。それはつまり、
「俺の事を・・・知ってんのか」
知人で魔術師かつ『幻想殺し』の能力を知っている人物・・・・を上条は頭の中で思い浮かべたがあまりにも多いので途中でやめた。この半年前後で戦ってきた魔術師はあまりにも多い。それにこっちは知らなくても向こうだけが知っている可能性も十分に考えられる。今はまだ具体的な答えを出すことなどできなかった。
「・・・」
上条当麻は自分の右腕、そして辺りを一通り見回してから当初の目的地である学生寮へと足を向けた。殺されかけた。その事実が上条当麻を締め付ける。聖杯戦争。魔術師同士の殺し合い。そんなモノに参加する気は毛頭ない。だが、例えばさっきのサーヴァントのマスターが自分の知人だとしたら。上条はその知人が殺し殺されるのをただ見ていることになる。
「・・・」
複雑な気持ちだった。止めるのならばそれだけの責任を背負い、やるのならばそれだけの覚悟を背負わねばならない。その覚悟と責任をどう持つのか、いやまず持てるのかどうかを上条は思案しつつ学生寮へと向かっていった。
―――― ――――