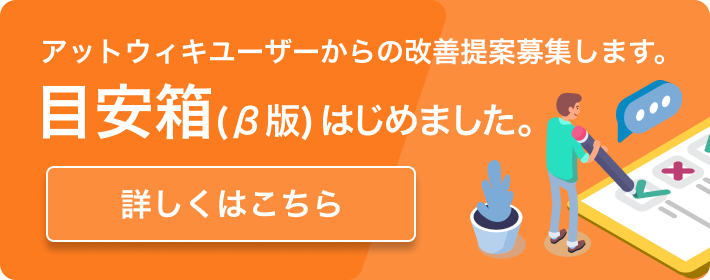完全下校時間を過ぎた静かな闇の道路を一台の無人タクシーが駆けていた。
ここは外の世界よりも科学技術が二、三〇年先を行っている学園都市。
こういった自動操縦のタクシーが存在していて不思議は無いし、案外、需要も多い。
学園都市の大半は学生なのだが、学生がいる以上は教えるための教師がいる。
教師という職業のストレスは半端ではない。何しろ、預かっているのは大事な大事な他人の子供であるし、常に言うことを聞いてくれるわけでもない。しかも教師の半分以上は治安維持のための警備員(アンチスキル)にもなっている。
これではストレスが溜まらない方がおかしくないくらいで、結果、二次会三次会当たり前の夜の飲み会は毎晩行われていると言っても過言ではない。
結果、代行運転代わりに無人タクシーを利用する者や歩いて次の店に向かうことが億劫な連中が使用することも多々あることになる。
もっとも、今この場を走っている無人タクシーに乗っているのは、そんな日ごろの不満の捌け口を求めて彷徨い歩く連中やそろそろ帰宅するかなといった連中ではない。
助手席には妹達(シスターズ)の一人で、上条当麻からは御坂妹と呼ばれる少女。後部座席にはインデックスと白井黒子という配置で、アパートを出てからしばらくの間、沈黙に支配されていた。
どこに行くのかは教えられていない。
しかし、この御坂美琴と瓜二つの少女の言葉にはインデックスも白井黒子も従わざる得なかった。
なぜなら、あの場に居合わせて、(まったく慌てなかった様子から)自分たちが揃っていると知っていて、しかも自分たちが探している人間の一人とそっくりなどという偶然はありえるはずが無いからである。
二つまでなら偶然だが、三つとなると必然、というのは世の常だ。
「結論から申し上げます、とミサカは前を見たまま、お二人に伝えます」
タクシーに乗って、十分くらい経過したところで、ようやく、御坂妹は口を開いた。
それはとても平坦な声で、何も感情が篭っていない事務的な口調に聞こえて。
ここは外の世界よりも科学技術が二、三〇年先を行っている学園都市。
こういった自動操縦のタクシーが存在していて不思議は無いし、案外、需要も多い。
学園都市の大半は学生なのだが、学生がいる以上は教えるための教師がいる。
教師という職業のストレスは半端ではない。何しろ、預かっているのは大事な大事な他人の子供であるし、常に言うことを聞いてくれるわけでもない。しかも教師の半分以上は治安維持のための警備員(アンチスキル)にもなっている。
これではストレスが溜まらない方がおかしくないくらいで、結果、二次会三次会当たり前の夜の飲み会は毎晩行われていると言っても過言ではない。
結果、代行運転代わりに無人タクシーを利用する者や歩いて次の店に向かうことが億劫な連中が使用することも多々あることになる。
もっとも、今この場を走っている無人タクシーに乗っているのは、そんな日ごろの不満の捌け口を求めて彷徨い歩く連中やそろそろ帰宅するかなといった連中ではない。
助手席には妹達(シスターズ)の一人で、上条当麻からは御坂妹と呼ばれる少女。後部座席にはインデックスと白井黒子という配置で、アパートを出てからしばらくの間、沈黙に支配されていた。
どこに行くのかは教えられていない。
しかし、この御坂美琴と瓜二つの少女の言葉にはインデックスも白井黒子も従わざる得なかった。
なぜなら、あの場に居合わせて、(まったく慌てなかった様子から)自分たちが揃っていると知っていて、しかも自分たちが探している人間の一人とそっくりなどという偶然はありえるはずが無いからである。
二つまでなら偶然だが、三つとなると必然、というのは世の常だ。
「結論から申し上げます、とミサカは前を見たまま、お二人に伝えます」
タクシーに乗って、十分くらい経過したところで、ようやく、御坂妹は口を開いた。
それはとても平坦な声で、何も感情が篭っていない事務的な口調に聞こえて。
「あの方とお姉様は、私たちの元で保護されています、と、ミサカは衝撃の真実を暴露します」
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!
当然、後部座席の二人は、背景ごと協調反転したような、声にならない衝撃を受けた。
あの方って、とうまのこと?
お姉様とは御坂美琴お姉様?
実にたっぷり三分は固まっていた二人は、今度は震える渇いた唇を紡ぎ、そう問いかけたかったに違いない。
もっとも言葉を発する前に御坂妹が続けてきた。
「ちなみに、あの方とは上条当麻様のことで、お姉様とは御坂美琴お姉様のことです、とミサカはお二人の想像に対して答えます」
完全に先読みされた答えに、再び、インデックスと白井黒子は衝撃に支配されることとなる。
あの方って、とうまのこと?
お姉様とは御坂美琴お姉様?
実にたっぷり三分は固まっていた二人は、今度は震える渇いた唇を紡ぎ、そう問いかけたかったに違いない。
もっとも言葉を発する前に御坂妹が続けてきた。
「ちなみに、あの方とは上条当麻様のことで、お姉様とは御坂美琴お姉様のことです、とミサカはお二人の想像に対して答えます」
完全に先読みされた答えに、再び、インデックスと白井黒子は衝撃に支配されることとなる。
上条当麻と御坂美琴の二人が救出されたのは、一〇七七七号が辿り着いた沿岸の流氷の下からだった。
ゲコ太ストラップを見つけた彼女がミサカネットワークに現状を配信することで、九九六九人の妹達の脳波とリンクし、夏に学園都市で問題になった『幻想御手(レベルアッパー)』の原理、共感覚性を利用して、普段は強能力(レベル3)でしかない自身のレベルを引き上げ、かつ、普段から装着している微弱な電磁波を読み取る特殊ゴーグルを活用した結果、AIM察知能力だけは、このとき、オリジナルである御坂美琴並みのレベルまで高めることができて、ゲコ太ストラップのさらに向こう、今にも消え入りそうな微弱な電磁波を察知したのである。
もちろん、それは上条当麻と御坂美琴の二人。
力を完全に使い果たし、ぐったりしていた少年を、正面から、優しく包み込むように抱え込んでいた少女という構図で海の底に横たわり、しかし、二人とも完全に意識を失っていた。
「――というわけなんだが、君たちから不機嫌オーラが立ち上っているのはどういうことなのか教えてくれないか?」
御坂妹に連れられて着いた先は、白井黒子も一度お世話になったことがあり、インデックスにいたってはなんとなく第二の自宅と化している気がする、カエル顔のいる第七学区の病院だった。
実のところ、真っ先に二人がいる病室にそれぞれ向かいたかったのだが、その前に、ということでカエル顔の医者のところに案内されたのだ。
「い~~~え~~~なんでも~~~」
「右に同じなんだよ~~~」
どうやら、上条と美琴が『抱き合って』発見された、という部分がお気に召さなかったようだ。
カエル顔の医者は呆れた溜息を一つつき、
「しかし、この話は続きがあってね」
『は?』
「二人は生きて発見されたわけだが、僕も見ていたけど、あの大きい岩の塊が海に落ちてから一〇七七七号さんに発見されるまで、どれだけの時間が経っていたと思う? 常識的に言って、二人が生きていること自体、あり得ないことだったわけなんだけど、それを可能にしたのが、あの態勢だった、と言ってもまだ、君たちはそんな心情でいられるかな?」
――!!
「極寒の氷水の中で周りは海水だよ。二人が生き残るためには酸素の供給を得て暖を取るしかない。暖はお互いの体温でも可能かもしれないが、もちろん、あの状況ではそれだけでは不充分だ。周りの水の冷たさは即座に体温を奪うし、それに何より、人は水の中で生きていくことはできない。
どうやら御坂くんは、自分の能力を最大限に活用したようだね。海水とは言え、水であることは間違いない。そこで彼女は『水』を『窒素』と『酸素』に電気分解し、必要な分だけの酸素を得ることに成功した。また、電撃を周囲に展開させることによって、体温とは別の暖も取ることを可能にしたようだ」
「……さすが短髪……学園都市の第三位だけあって頭良いし……」
インデックスが、まだどこかふてくされた表情で呟くが、
「ちょっと待ってくださいな。確か海水、というか塩水は電気など即座に流してしまうわけですから、広い海の中、電撃をその場に留めて置く、なんて芸当が可能なのでしょうか?」
白井黒子は違っていた。小学校で習った知識ではあるが、そう教えられたのだ。
「そうだね。君の言うとおりだ。確かに並みの電撃では不可能だろう。しかし御坂くんは超能力者(レベル5)の電撃使いだよ。もしかしたら常識枠外に拡散されない電気の使い方を知っていたのかもしれない。さすがに僕には分からない分野だがね」
カエル顔の医者が呆れて屈服する姿を捉えて、白井黒子の胸の内にどことなく優越感の火が灯る。
「……もっとも、それは相当、無理した方法だったようではあるがね」
「え?」
黒子のいぶかしげな声を聞いて、カエル顔の医者は一度、目を伏せた。
まるで何か、伝えたくないことを伝えなくちゃいけない、そんな葛藤を見せたのだ。
本人は気遣いのつもりだったのかもしれないが、本当に面白そうに見える表情を。
インデックスに嫌な予感が走る。
彼女は一度、この医者のこういう表情を見たことがあった。
それは最近になって知ったことではあるのだが、七月二十九日のあの日も、こんな表情をしていた。
ゲコ太ストラップを見つけた彼女がミサカネットワークに現状を配信することで、九九六九人の妹達の脳波とリンクし、夏に学園都市で問題になった『幻想御手(レベルアッパー)』の原理、共感覚性を利用して、普段は強能力(レベル3)でしかない自身のレベルを引き上げ、かつ、普段から装着している微弱な電磁波を読み取る特殊ゴーグルを活用した結果、AIM察知能力だけは、このとき、オリジナルである御坂美琴並みのレベルまで高めることができて、ゲコ太ストラップのさらに向こう、今にも消え入りそうな微弱な電磁波を察知したのである。
もちろん、それは上条当麻と御坂美琴の二人。
力を完全に使い果たし、ぐったりしていた少年を、正面から、優しく包み込むように抱え込んでいた少女という構図で海の底に横たわり、しかし、二人とも完全に意識を失っていた。
「――というわけなんだが、君たちから不機嫌オーラが立ち上っているのはどういうことなのか教えてくれないか?」
御坂妹に連れられて着いた先は、白井黒子も一度お世話になったことがあり、インデックスにいたってはなんとなく第二の自宅と化している気がする、カエル顔のいる第七学区の病院だった。
実のところ、真っ先に二人がいる病室にそれぞれ向かいたかったのだが、その前に、ということでカエル顔の医者のところに案内されたのだ。
「い~~~え~~~なんでも~~~」
「右に同じなんだよ~~~」
どうやら、上条と美琴が『抱き合って』発見された、という部分がお気に召さなかったようだ。
カエル顔の医者は呆れた溜息を一つつき、
「しかし、この話は続きがあってね」
『は?』
「二人は生きて発見されたわけだが、僕も見ていたけど、あの大きい岩の塊が海に落ちてから一〇七七七号さんに発見されるまで、どれだけの時間が経っていたと思う? 常識的に言って、二人が生きていること自体、あり得ないことだったわけなんだけど、それを可能にしたのが、あの態勢だった、と言ってもまだ、君たちはそんな心情でいられるかな?」
――!!
「極寒の氷水の中で周りは海水だよ。二人が生き残るためには酸素の供給を得て暖を取るしかない。暖はお互いの体温でも可能かもしれないが、もちろん、あの状況ではそれだけでは不充分だ。周りの水の冷たさは即座に体温を奪うし、それに何より、人は水の中で生きていくことはできない。
どうやら御坂くんは、自分の能力を最大限に活用したようだね。海水とは言え、水であることは間違いない。そこで彼女は『水』を『窒素』と『酸素』に電気分解し、必要な分だけの酸素を得ることに成功した。また、電撃を周囲に展開させることによって、体温とは別の暖も取ることを可能にしたようだ」
「……さすが短髪……学園都市の第三位だけあって頭良いし……」
インデックスが、まだどこかふてくされた表情で呟くが、
「ちょっと待ってくださいな。確か海水、というか塩水は電気など即座に流してしまうわけですから、広い海の中、電撃をその場に留めて置く、なんて芸当が可能なのでしょうか?」
白井黒子は違っていた。小学校で習った知識ではあるが、そう教えられたのだ。
「そうだね。君の言うとおりだ。確かに並みの電撃では不可能だろう。しかし御坂くんは超能力者(レベル5)の電撃使いだよ。もしかしたら常識枠外に拡散されない電気の使い方を知っていたのかもしれない。さすがに僕には分からない分野だがね」
カエル顔の医者が呆れて屈服する姿を捉えて、白井黒子の胸の内にどことなく優越感の火が灯る。
「……もっとも、それは相当、無理した方法だったようではあるがね」
「え?」
黒子のいぶかしげな声を聞いて、カエル顔の医者は一度、目を伏せた。
まるで何か、伝えたくないことを伝えなくちゃいけない、そんな葛藤を見せたのだ。
本人は気遣いのつもりだったのかもしれないが、本当に面白そうに見える表情を。
インデックスに嫌な予感が走る。
彼女は一度、この医者のこういう表情を見たことがあった。
それは最近になって知ったことではあるのだが、七月二十九日のあの日も、こんな表情をしていた。
「本人の前でショックを受けるのも失礼だから、手っ取り早くレッスン1……君は2だったかな?」
インデックスが一番聞きたくなかった台詞をカエル顔の医者は言ってしまった。
こんこん、と病室のドアを二回ノックした。
震える腕を何とか収め、何とか中の入院患者に聞こえるように気持ち大きく。
聞こえないことには何も始まらないから。
インデックスの心臓は既に破裂しそうである。何と言っても二度目なのだ。しかも二度とも自分を救ってくれた原因が、同じ結果を招いているのだ。
返事が返ってくるまでの間、今度はインデックスは十字を切ることなく、胸に手を合わせて祈っていた。
神様という存在をインデックスは信じている。そして自分は敬謙な神の徒であることを誇りに思っている。
はい? と少年の声が返ってきた。
あの日と同じく、恐る恐るインデックスはドアを開けた。
あの日と同じく、少年は白いベッドの上に上半身だけを起こして、ベッドの傍の、開いている窓の、ヒラヒラ揺れるカーテンの向こうへ遠くを見る目をしていた。
生きていた。
たったそれだけの事実に、インデックスは涙がこぼれそうになった。
この一ヶ月半、少年ことを、彼と過ごした思い出と供に考えない日は一度もなかった。
生きていた。
この事実にインデックスの胸にこみ上げるものがあった。
近づかずにはいられなかった。傍に行きたくて仕方がなかった。
病室のベッドまでの距離はそこまで長くはない。
それでも、今までのどんなことよりも、その距離まで走るインデックスは長く感じた。
そこにたどり着くまでが待ち遠しかった。もどかしかった。
しかし――
震える腕を何とか収め、何とか中の入院患者に聞こえるように気持ち大きく。
聞こえないことには何も始まらないから。
インデックスの心臓は既に破裂しそうである。何と言っても二度目なのだ。しかも二度とも自分を救ってくれた原因が、同じ結果を招いているのだ。
返事が返ってくるまでの間、今度はインデックスは十字を切ることなく、胸に手を合わせて祈っていた。
神様という存在をインデックスは信じている。そして自分は敬謙な神の徒であることを誇りに思っている。
はい? と少年の声が返ってきた。
あの日と同じく、恐る恐るインデックスはドアを開けた。
あの日と同じく、少年は白いベッドの上に上半身だけを起こして、ベッドの傍の、開いている窓の、ヒラヒラ揺れるカーテンの向こうへ遠くを見る目をしていた。
生きていた。
たったそれだけの事実に、インデックスは涙がこぼれそうになった。
この一ヶ月半、少年ことを、彼と過ごした思い出と供に考えない日は一度もなかった。
生きていた。
この事実にインデックスの胸にこみ上げるものがあった。
近づかずにはいられなかった。傍に行きたくて仕方がなかった。
病室のベッドまでの距離はそこまで長くはない。
それでも、今までのどんなことよりも、その距離まで走るインデックスは長く感じた。
そこにたどり着くまでが待ち遠しかった。もどかしかった。
しかし――
「あの……あなた、部屋を間違えていませんか?」
あの日と同じく、少年の言葉はあまりに丁寧で、不審そうで、様子を探るような声だった。
あの日と同じく、まるで顔を見たこともない赤の他人に電話で話しかけるような声だった。
――どうやら御坂くんの長時間にわたる電磁波に脳細胞が耐えられなかったようだね?
凍てつく夏の日の診察室で医者が放った言葉がインデックスに突き刺さる。
――酸素を作り出し、暖を取ることで命を救うことは可能にしたようではあるが、長時間、それも高い周波数に近い電磁波を浴び続けた結果、脳細胞ごと記憶が破壊されてしまったようだ。あれでは、また昨日までのことを思い出すことはないと思うよ。今回は文字通り、脳に直接スタンガンを打ち込まれたようなものだったからね。
っ……!
あの日と同じく、インデックスは小さく息を止める。
これでは本当にあの日と同じだ。
誰よりも深く危険に飛び込み、誰よりも強く能力を使い続けて、誰よりも激しく命の危機に瀕した結末が、命と引き換えに、またも記憶という名の心を奪ったのだ。
しかも、二度目もまた、インデックスを助ける、というただただシンプルな思いの元に、だ。
自分は神の使徒ではなかったのか。
自分は救いの手を差し伸べることに従事していたのではなかったのか。
それがどうだ。
本当に守りたかった存在を救えなかったばかりか、救われているのは自分だけではないか。
あのう……?
自分を心配する少年の声が聞こえる。
インデックスはそれが許せなかった。救われなければならないはずの少年の、卑しくも救われた自分を心配する声が許せなかった。自分自身が許せなかった。
だからこそ、彼を正面から見つめる。涙は何とかこぼれることを圧し留めた。笑顔を浮かべることもできたと思う。
絶対に、この少年の前で涙はこぼしてはいけない。そんな資格なんてない。
「大丈夫? 何か君、もの凄く辛そうだ」
なのに、少年はインデックスの心を木っ端微塵に打ち砕く。心の底を見透かしてくる。
どうして、あの日と同じやり取りを、またしなくてはならないのか。
しかし、これは自分に対する罰なのだ。償うべき罪なのだ。
インデックスは言い聞かせて、口を開く。
「大丈夫だよ」
毅然と言った。笑顔を浮かべて言った。
「大丈夫に決まってるよ」
「そう?」
少年の視線はいまだに疑念が渦巻いている。
そんな目で見てほしくない、インデックスは切に願うが、その願いが叶うことは許されない。許されるはずがない。
それなのに、
「あの、俺たちって知り合い?」
絶対に聞きたくない質問だった。
もう限界だった。耐え切れなかった。
そこに居たのは世界の魔道書一〇万三〇〇〇冊を記憶した完全記憶能力者でもなければ、神の敬謙な使徒でもなかった。
誰よりも何よりも大事な人を失った、ただただ打ちひしがれている一人の少女でしかなかった。
膝を付き、両手を付き、せめて顔は見られないようにするしかできなかった。
あの日と同じく、まるで顔を見たこともない赤の他人に電話で話しかけるような声だった。
――どうやら御坂くんの長時間にわたる電磁波に脳細胞が耐えられなかったようだね?
凍てつく夏の日の診察室で医者が放った言葉がインデックスに突き刺さる。
――酸素を作り出し、暖を取ることで命を救うことは可能にしたようではあるが、長時間、それも高い周波数に近い電磁波を浴び続けた結果、脳細胞ごと記憶が破壊されてしまったようだ。あれでは、また昨日までのことを思い出すことはないと思うよ。今回は文字通り、脳に直接スタンガンを打ち込まれたようなものだったからね。
っ……!
あの日と同じく、インデックスは小さく息を止める。
これでは本当にあの日と同じだ。
誰よりも深く危険に飛び込み、誰よりも強く能力を使い続けて、誰よりも激しく命の危機に瀕した結末が、命と引き換えに、またも記憶という名の心を奪ったのだ。
しかも、二度目もまた、インデックスを助ける、というただただシンプルな思いの元に、だ。
自分は神の使徒ではなかったのか。
自分は救いの手を差し伸べることに従事していたのではなかったのか。
それがどうだ。
本当に守りたかった存在を救えなかったばかりか、救われているのは自分だけではないか。
あのう……?
自分を心配する少年の声が聞こえる。
インデックスはそれが許せなかった。救われなければならないはずの少年の、卑しくも救われた自分を心配する声が許せなかった。自分自身が許せなかった。
だからこそ、彼を正面から見つめる。涙は何とかこぼれることを圧し留めた。笑顔を浮かべることもできたと思う。
絶対に、この少年の前で涙はこぼしてはいけない。そんな資格なんてない。
「大丈夫? 何か君、もの凄く辛そうだ」
なのに、少年はインデックスの心を木っ端微塵に打ち砕く。心の底を見透かしてくる。
どうして、あの日と同じやり取りを、またしなくてはならないのか。
しかし、これは自分に対する罰なのだ。償うべき罪なのだ。
インデックスは言い聞かせて、口を開く。
「大丈夫だよ」
毅然と言った。笑顔を浮かべて言った。
「大丈夫に決まってるよ」
「そう?」
少年の視線はいまだに疑念が渦巻いている。
そんな目で見てほしくない、インデックスは切に願うが、その願いが叶うことは許されない。許されるはずがない。
それなのに、
「あの、俺たちって知り合い?」
絶対に聞きたくない質問だった。
もう限界だった。耐え切れなかった。
そこに居たのは世界の魔道書一〇万三〇〇〇冊を記憶した完全記憶能力者でもなければ、神の敬謙な使徒でもなかった。
誰よりも何よりも大事な人を失った、ただただ打ちひしがれている一人の少女でしかなかった。
膝を付き、両手を付き、せめて顔は見られないようにするしかできなかった。
もう――圧し留める涙を堪えことはできなかった――
白井黒子は茫然自失に立ち尽くしていた。
インデックスが入っていった病室の、隣にある個室の病室。
部屋の間取りはほぼ同じ。真っ白い壁に、シンプルな白のベッド。
そこに一人の少女が横たわっていた。
まるで眠れる森の少女のように穏やかに安らかに。
しかし、そんな童話に出てくるような安らかな雰囲気はなく、頭部にはいくつか電極を貼り付けさせられ、かけられているシーツの中にも点滴用のチューブが差し込まれ、整った鼻と口元には酸素吸入用のマスクもかぶせられていた。
集中治療室でないことだけが救いだった。
――どうやら御坂くんは能力使用の限界を越えてしまったらしい。
先に白いシスターがショックを受けたその隣で、白井黒子もまた、あまりの衝撃に固まってしまっていた。
――限界を越えた能力使用と彼女自身の強過ぎる力を自分自身にも浴びせ続けた結果、全身の神経に支障を来たしてしまったようだ。五感、いや、脳の一部を除いた六感のすべてを失っている。あれでは、命に別状がないとは言え、もう二度と目を覚ますことはないと思うよ。上条くんの方は御坂くんが被さっていたおかげで、間接的に暖を取ることが大半だったから、脳細胞の破壊だけで済んだようではあったがね。
残酷な医者の言葉。
白井黒子が目指した少女は、これから先、自分の模範になることはない、と言われたのだ。
いったいどうしてこんなことになってしまったのか。
少女がとある少年に恋心を抱いていることは知っていた。
しかし、ここまでして尽くすことができるものなのだろうか。
しかも、少年は既に、この少女のことを思い出すことはないのだ。
もう二度と報われることがないというのに、どうして、ここまで突っ走ったのか。
彼女は学園都市の第三位。
そんな崇高な少女が後先考えずに行動するなんて、白井黒子には想像すらできなかった。
――呼吸が自力でできるくらいに回復したら親御さんが迎えに来るから。
もう、少女と一緒に居ることはできないという最後通告を突きつけられている。
ひと時は家族と供にいられるだろう。
しかし、その後は無残な結果が待っている。
学園都市の闇の部分が必ず御坂美琴を奪い返しに来る。
旅掛と美鈴を殺してでも奪っていく。
そして御坂美琴は垣根提督同様、永遠に意識を取り戻すことがないまま、利用され喰い尽くされるのだ。
もちろん白井黒子はそれを知らない。
だが、カエル顔の医者は知っている。学園都市がそういう町であることを知っている。
「お姉様……」
ふらふらと白井黒子は近寄っていき、
「お姉様……どうして……」
しゃがみこんで、その手を握り、しかし、握り返されることはない。
茫然自失から立ち直った白井黒子の胸にこみ上げるもの。
圧し留めることなくこぼれ続ける涙。
シーツを濡らし続けるが少女からの反応はない。
幾度となく呼びかけようとも少女の反応はない。
何度呼びかけただろう。どれだけ時間が経過しただろう。
白井黒子は限界だった。
もう淑女とか嗜みとかはどうでも良かった。
「うぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!! お姉様ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああ!!」
偉大なる先輩の胸に突っ伏して、誰憚ることなく声を上げるただの少女がそこにいた。
インデックスが入っていった病室の、隣にある個室の病室。
部屋の間取りはほぼ同じ。真っ白い壁に、シンプルな白のベッド。
そこに一人の少女が横たわっていた。
まるで眠れる森の少女のように穏やかに安らかに。
しかし、そんな童話に出てくるような安らかな雰囲気はなく、頭部にはいくつか電極を貼り付けさせられ、かけられているシーツの中にも点滴用のチューブが差し込まれ、整った鼻と口元には酸素吸入用のマスクもかぶせられていた。
集中治療室でないことだけが救いだった。
――どうやら御坂くんは能力使用の限界を越えてしまったらしい。
先に白いシスターがショックを受けたその隣で、白井黒子もまた、あまりの衝撃に固まってしまっていた。
――限界を越えた能力使用と彼女自身の強過ぎる力を自分自身にも浴びせ続けた結果、全身の神経に支障を来たしてしまったようだ。五感、いや、脳の一部を除いた六感のすべてを失っている。あれでは、命に別状がないとは言え、もう二度と目を覚ますことはないと思うよ。上条くんの方は御坂くんが被さっていたおかげで、間接的に暖を取ることが大半だったから、脳細胞の破壊だけで済んだようではあったがね。
残酷な医者の言葉。
白井黒子が目指した少女は、これから先、自分の模範になることはない、と言われたのだ。
いったいどうしてこんなことになってしまったのか。
少女がとある少年に恋心を抱いていることは知っていた。
しかし、ここまでして尽くすことができるものなのだろうか。
しかも、少年は既に、この少女のことを思い出すことはないのだ。
もう二度と報われることがないというのに、どうして、ここまで突っ走ったのか。
彼女は学園都市の第三位。
そんな崇高な少女が後先考えずに行動するなんて、白井黒子には想像すらできなかった。
――呼吸が自力でできるくらいに回復したら親御さんが迎えに来るから。
もう、少女と一緒に居ることはできないという最後通告を突きつけられている。
ひと時は家族と供にいられるだろう。
しかし、その後は無残な結果が待っている。
学園都市の闇の部分が必ず御坂美琴を奪い返しに来る。
旅掛と美鈴を殺してでも奪っていく。
そして御坂美琴は垣根提督同様、永遠に意識を取り戻すことがないまま、利用され喰い尽くされるのだ。
もちろん白井黒子はそれを知らない。
だが、カエル顔の医者は知っている。学園都市がそういう町であることを知っている。
「お姉様……」
ふらふらと白井黒子は近寄っていき、
「お姉様……どうして……」
しゃがみこんで、その手を握り、しかし、握り返されることはない。
茫然自失から立ち直った白井黒子の胸にこみ上げるもの。
圧し留めることなくこぼれ続ける涙。
シーツを濡らし続けるが少女からの反応はない。
幾度となく呼びかけようとも少女の反応はない。
何度呼びかけただろう。どれだけ時間が経過しただろう。
白井黒子は限界だった。
もう淑女とか嗜みとかはどうでも良かった。
「うぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!! お姉様ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああ!!」
偉大なる先輩の胸に突っ伏して、誰憚ることなく声を上げるただの少女がそこにいた。
それでも無情にも――先輩からは何の反応もない――