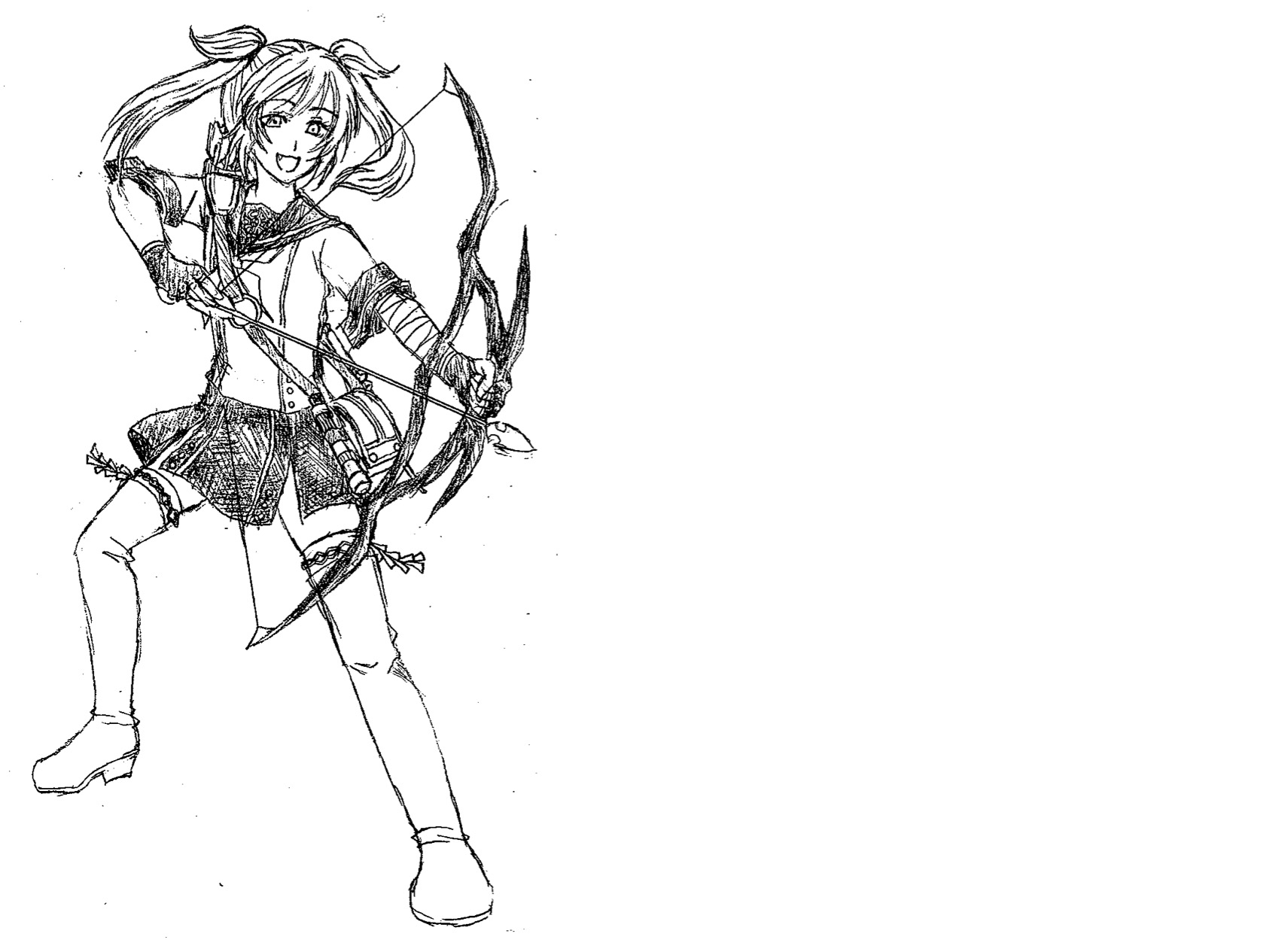第2話(BS22)「白球と翼」(
1
/
2
/
3
/
4
)
旧トランガーヌ子爵領北部を占めるモラード地方の北東部に位置するウリクルの村には、ブレトランドでも最も有名なゴルフ場である「ブランギース・カントリークラブ」が存在する。そのゴルフ場のオーナーのドミナス・ブランギース(下図)は、30年以上にわたってこの村の歴代領主に仕えてきた最古参の政務官であり、その類い稀な行政手腕に定評があると同時に、政財界および裏社会に幅広いコネを持ち、合法・違法様々な手段を用いて私腹を肥やしているという噂のある人物でもあった。
そんな彼の屋敷に、一人の「武具」の少女が仕えていた(下図)。彼女の名は、ベーナ。年齢は不詳だが、傍目には子供にしか見えない風貌である。もともと、彼女は別の世界で開発された「剣と盾が一体化した武具」だったが、幾多の戦いを経た末に廃棄された後、ヴェリア界を経由して、この世界に「オルガノン(擬人化された道具)」として投影された。ただし、彼女は殆どの記憶を全て失ってしまっているため、元の世界でどのような存在だったのかは、誰にも分からない。
当初、彼女はこのウリクルの村の山林の一角の頂上に休眠状態のまま突き刺さっていたところを、数ヶ月前のゴルフ場の増築工事の過程で発見され、ゴルフ場のオーナーであるドミナスによって引き抜かれて、そのまま彼に拾われることになった。ちなみに、本来の名前は別にあったが、ドミナスが「まったく似合わない」と判断した結果、今の名前をつけられたらしい。
現状、彼女の「所有者(主人)」はドミナスであるが、彼は「君主でも邪紋使いでもない私が武具を持っていても、宝の持ち腐れだ」という判断から、領主であるジェローム・ヒュポクリシス(後述)が出陣する際には、彼にベーナを貸し出すことが多い。ただ、それでもベーナの中では、自分を引き抜いてくれたドミナスへの忠誠心は極めて強く、領主の下で働くのも、あくまでドミナス自身がそれを望んでいるからであった。
そんなある日の昼下がり、彼女が住み込みで働いているドミナスの屋敷の入口の扉を叩く音が聞こえた。ベーナが扉の鍵穴から外を見ると、そこにいるのは、細身の長身で「紺色のスーツ」を着た男であった。少なくとも、ベーナには見覚えのない人物である。
「どのようなご用件でしょうか?」
扉を開けた上で彼女がそう問いかけると、その男は静かな笑顔で答える。
「ドミナス殿にお会いしたいのですが」
「では、お呼びしますので、しばらくこちらでお待ち下さい」
そう言って彼女はその客人を応接室へと案内した上で、屋敷の二階の奥の部屋にいるドミナスを呼びに行く。
「客人? 誰だ?」
「紺色のスーツを着た、ちょっとヒョロッとしたカンジの……」
彼女がそう説明すると、ドミナスは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。
「……俺は今、この家にいない。いいな?」
「……………えーっと、すみません、もう一度、お願いします」
「『俺は、今、この家に、いない』と言え。い・い・な?」
主人にそう言われたベーナは、筆記用具を取り出し、メモを取る。彼女は自分の記憶力に自信がないため、重要な案件の際は、どんなに短い伝言内容でも、いつもこうしている。
「分かりました」
そう言って彼女は再び応接室の前まで来て、扉の前で改めてメモ用紙を見て、内容をもう一度確認してから部屋の中に入る。
「すみません、今、ちょっと、家にいらっしゃらなくて……」
「そうですか、分かりました。では、また出直しましょう」
紺色のスーツの男は淡々とそう答えると、彼女に見送られて素直に帰って行く。それを見届けたベーナがドミナスの元に戻ってくると、彼はこう告げた。
「今後、あいつが来ても追い返せ」
「すいません、もう一度お願いします」
「『あいつがいる時には、俺はいない』いいな」
「分かりました」
ベーナは再びメモ帳を取り出してその旨をそこに書き記す。秘書官としては決して優秀とは言えない彼女だが、基本的に平和なこの村においては、武具としての自分を役立てる機会も少ないので、こうして日頃から少しでも主人のために働きたいと彼女は考えているようである。
「さて、ではそろそろ、私は領主殿のところに出立する。お前も一緒に来い」
「はい、お伴します」
そう言って、二人は外出の準備を始める。現在、彼が経営する「ブランギース・カントリークラブ」は九つのホールから成り立っているが、つい先日、新たに「10番ホール」が完成した。その10番ホールの杮(こけら)落としとなるゴルフコンペの開催が三日後に迫ったため、その内容およびゲスト参加者などについて、領主と確認したいというのが、主な理由であった。
「状況次第だが、お前にもいつも通り、客人の接待役として参加してもらう可能性もある」
彼が考える「理想のゴルフの接待役」とは、あまり足を引っ張りすぎない程度の打数で周り、最もスコアの悪い参加者と最下位争いをして、ギリギリで負ける、という役割である。ベーナはこれまで、そのための訓練も受けてきたが、もともとゴルフをするために作られた道具ではないこともあって、なかなかそう上手くはいかないことも多い。あまり器用に力の加減が出来るタイプではない彼女としては、なかなか気の重い話であった。
(まぁ、ご主人様がそう仰るなら、仕方ないですけどね……)
彼女としては、ドミナス個人に対して、個人レベルで好感を持っている訳ではない。だが、武具として生み出された彼女にとっては、自分の「持ち主」のために尽くすこと自体が、本能的な喜びなのである。いかにそれが無茶な要求でも、彼女の中には、断るという選択肢は無かった。
1.2. 旧友からの手紙
一方、その頃、この村の警備を担当する傭兵隊長クロー・クロー(下図)の元に、一通の手紙が届いていた。

クロー・クローという奇妙な名は、彼の育ての親が名付けた。と言っても、「クロー家」という家が存在する訳ではない。というのも、彼の育ての親の界隈には、そもそも「名」と「姓」という概念自体がない。なぜならば彼は、ドラゴンによって育てられた人物なのである(ちなみに、「クロー」という言葉が、ドラゴン語で何を意味する言葉なのかは彼も知らない)。
彼は本当の親を知らない。何者かによって捨てられていたところを、ドラゴンに拾われて育てられ、その親への憧れが興じて、気付いた時にはレイヤードラゴンの邪紋を刻んでいた。やがて、成人になると同時にドラゴンの里を出て、自分探しのために世界中を旅している中で、自分の長所を生かして糧を稼ぐ手段を模索した結果、必然的に傭兵という生業に辿り着いた。現在、彼は25歳。武人としては、まさに働き盛りの年代である。
そんな彼の元に届いた手紙の主は、かつて、とある戦場で共に戦ったことがある、アマルという名の青年である。彼は現在、アントリア北部のマージャ村に駐在武官として派遣されているのであるが、どうやら、彼の村の孤児院に最近入った子供が、2年前までクローが仕えていたウリクルの先代領主の息子である、と自称しているらしい。
2年前のアントリアからの侵攻作戦の際、先代領主のワイマール・エルメラ3世は、戦わずにあっさりと降伏したにもかかわらず、その数日後に路上で謎の変死を遂げた。おそらく何者かに殺されたのであろうと推測されていたが、ワイマールの息子はまだ幼かったため、その後継者としては認められず、アントリア騎士団から新領主としてジェロームという若い騎士が赴任することになったのである。
村人達はこの事態に困惑したが、敗戦国の民である彼等にその決定に異を唱える権利は無く、ワイマールに雇われていたクローもまた、あっさりと新領主と雇用契約を結び直した。自分の与り知らぬところで勝手に死んだ領主のために義理を通す理由は、彼には無い。あくまでも傭兵である以上、新たな領主が自分達の武勇に「金を払う価値」があると判断するならば、その申し出を断る理由は彼の中には無かったのである。
だが、ワイマールの妻とその一人息子は、ワイマールを殺した犯人(あるいはその黒幕)かもしれない者達が新領主に赴任した状況で、そのまま村で生活し続けるのは精神的に辛かったようで、その就任直後に忽然と姿を消した。その後の行方についてはクローは何も知らなかったが、その子供の証言によると、彼等はしばらく各地を転々としたものの、やがて母親が病没し、残っていた路銀も尽きて、路頭に迷っていたところを保護されたのだという。
その子供は最初は自分の素性については一切語ろうとはしなかったが、最近になってようやく少し打ち解け始めたところで、アマルに自分の境遇を明かすようになったらしい(ちなみに、手紙には書かれていないが、彼が心を開くきっかけとなったのは、アマルが大量に飼っている犬達のおかげである。ただ、そのくだりはこの物語には全く関係ないので割愛する)。
もっとも、あくまでもその子がそう言っているだけの話なので、果たして彼が本当にウリクルの先代領主の息子なのかは分からない。ただ、その子曰く、彼の父であるワイマールは「巨大な鴉のような、人のような怪物」に殺されたらしい。ワイマールの死因については、公的には未だ不明である。もしかしたら、この証言が何かの手がかりになるかもしれないし、ウリクル村の裏で何か今後良からぬことが起きるとしたら、それが影響している可能性もあるのではないか、というのが、このアマルからの手紙の概要であった。
その上で、彼の身柄を現領主が引き取る気があるなら、それはそれで相談には応じるが、最低限、一人の村人としての身の安全を保障する気がなければ、マージャの孤児院の院長は引き渡さないだろう、とも書き添えられていた。
(とはいえ、前回の雇い主の息子だから、直接的には今の俺には関係ない話なんだよな)
それが、クローとしての本音である。おそらく、現領主も、その子供がどこで何をしていようが、あまり興味を示さないだろう。手紙を読む限り、その子供が領主権の返還を要求している様子ではないようであるし、仮に要求してきたとしても、それに応じる義理も無ければ、そもそも領主個人の一存で決定出来るレベルの話でもない。
だが、先代領主の死因に関する情報については、一応、領主には報告しておいた方がいいだろう、と判断した彼は、領主の館へと向かうことにした。
もし、先代領主を殺したのが今の領主の一派の仕業なのであれば、この情報を伝えるのはヤブヘビかもしれないが、「怪物に殺された」という情報しかない以上、仮にその黒幕が彼等であったとしても、彼等が隠したければ「知らぬ存ぜぬ」を突き通せば良いだけの話であるし、クローとしてもそれ以上追求する気はない。
そして、もし、彼等も知らぬ何者かがその背後にいるのであれば、この村の安全を確保するためにも、そのような危険要素を排除しておく必要がある。実際、この村の近辺には、昔から大型の鴉の投影体がよく出没する。だが、彼等の大半は、ゴルフボールを盗んで行く程度の被害しかもたらさず、人を襲うこと自体が滅多にない。それ故に、先代領主の時代から、本格的な山狩はおこなわれず、そのまま放置されていたのであるが、もし、この情報が真実なら、今後は本格的な対策を講じる必要があるだろう。
1.3. 級友からの手紙
そして、そんなクローへの手紙と同時期に、この村にもう一通の手紙が届いていた。差出人は、ヴァレフール南部のテイタニアの街の領主の契約魔法師インディゴ・クレセント。そして宛先は、このウリクルの村の領主の契約魔法師ヴェルディ・カーバイト(下図)である。
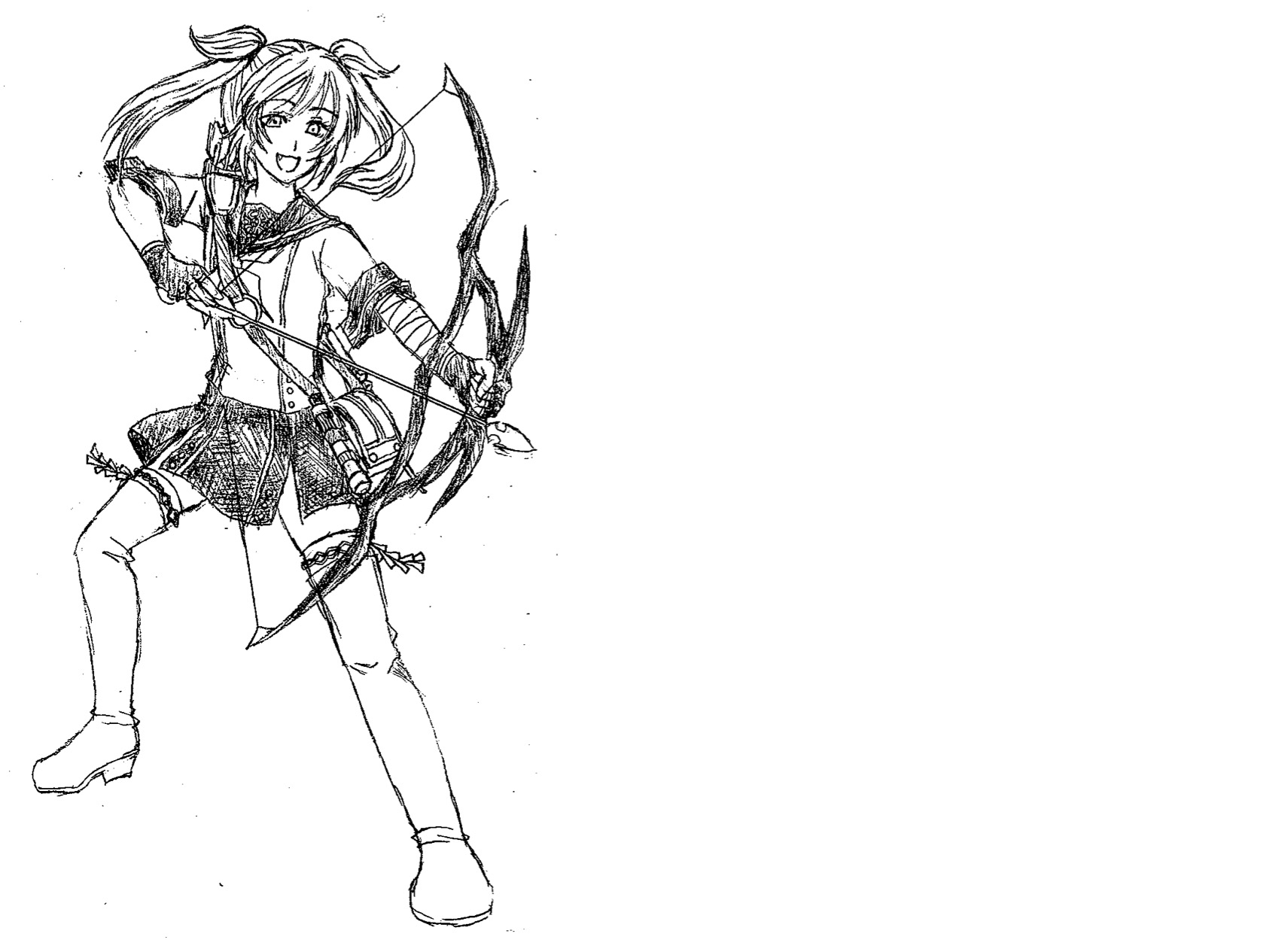
ヴェルディは、2年前に弱冠9歳にしてエーラムの魔法大学を卒業し、この村の契約魔法師として派遣された「天才少女」である。だが、そんな神童の彼女には、誰にも話していない「裏の経歴」があった。実は彼女は、エーラムに入門する以前に、闇魔法師組織パンドラで魔法を学んでいたのである。
彼女は本来は、大陸南西部の大国エストレーラの一角を占めるイェーガの領主の末娘であった(本当の名は「キュリー・スクア」なのだが、そのことは誰も知らない)。彼女は幼少期に微弱な聖印を自ら生み出していたが、同時に魔法師としての資質も持ち合わせていたため、次兄が彼女をパンドラに引き渡し、そこで聖印を抹消させ、魔法を習得させた。同じ魔法を学ばせるにしても、エーラムの場合はその後の契約相手が自分になるとは限らなかったため、自分の意のままに利用するためには、パンドラで学ばせる方が望ましいと考えたのである。
だが、彼女はそんな兄の思惑とは裏腹に、パンドラを脱走し、自らエーラムの門を叩いた。パンドラの非道な手段によって強制的に魔法の素養を更に強化されていた彼女は、その素養を生かしてあっさりと学位を取得するが、彼女はそんなパンドラの存在を許すことが出来ず、いつか自らの手で彼等を根絶やしにすることを密かに誓っている。
そんな彼女にとって、エーラム時代に心を許していた数少ない友人が、インディゴであった。彼はヴェルディとは対照的に、30歳を超えてから魔法師の資質に目覚めた変わり種であり、彼女より26歳も年上である。二人とも、静動魔法が専門であるが(正確に言えば、インディゴは本流の「黄」の系譜、ヴェルディは亜流の「山吹」の系譜なのであるが)、どちらも他の学生達と明らかに年代が違ったこともあり、学科内では「浮いた存在」同士であったため、いつの間にかなんとなく交流を深めていったようである。
そして、そのインディゴからの手紙によると、どうやら最近、パンドラのエージェントがウリクルに向かっている、という話を小耳に挟んだらしい。その人物の特徴は「背が高くて、細身で、紺色のスーツを着た男」であるという。その上で、手紙の最後にはこう記されていた。
「お前がパンドラのことを特に敵視しているからこそ、一応、伝えておいた。ただ、無茶はするな。敵の全容が分からない状態で、一人で戦おうとしてはならない。何かコトを起こすのであれば、予防策を張るにせよ、まずは周囲の者に相談してからにしろ」
その手紙を読み終えたヴェルディは、丁寧に畳んで大切にしまった後、静かにこう呟いた。
「心配してもらえるのは嬉しいけど、やっぱり僕、抑えられないな」
そして彼女は町の外に出て、その人物に関する情報を探そうとする。とはいえ、さすがに手がかりが何もない状態で見つかる筈もない。そんな中、村人達が「魔法師様、魔法師様」と彼女に話しかけてきた。見た目は子供だが、その実力が一線級の魔法師であることは、既にこの2年間の彼女の仕事っぷりを通じて、村人達の間では知れ渡っている。彼等にとって、困ったことがあればまず、領主か魔法師に相談するというのは、自然な流れになっていた。
「ここ最近、村に色々な怪物が出現するようになりまして……」
もともと、投影体と思き巨大鴉がゴルフボールを奪って行く被害は何度かあったのだが、最近は人を襲う魔物も現れているという。彼等が言うには、巨大鴉達が人を襲撃することは滅多になかったが、最近出現するようになった魔物達は、見境なく襲ってくるらしい。
「この件に関しては、私等ではどうにもならないので、領主様になんとかしてほしいのですが」
「そっか。じゃあ、私から話しておくよ。混沌退治なら、私も得意だし。まぁ、任しておいて」
ちなみに、彼女は一人称や口調がバラバラである。というよりも、そもそも人格そのものが不安定であるらしい。おそらくそれは、パンドラの育成期間の下で「通常とは異なる教育」を施された結果なのであろう。そんな彼女の立ち振る舞いは、時に村人達に不気味な印象を与えることもあるが、それを差し引いても彼女が「頼りにすべき存在」であることは、村人達には十分すぎるほどに実感していた。
1.4. おてんば姫の来訪
こうして、それぞれの理由で村の要人達が、この村の領主であるジェローム・ヒュポクリシス(下図)の館へと向かうことになった。
ジェロームは、アントリア北部の港町パルテノを活動拠点とする裕福な商家の出身である。彼の母は彼を生むと同時に、パルテノの領主令嬢の乳母となったことで、彼自身も貴族家と深い繋がりを持つようになり、やがて聖印を授かり、騎士の道を歩むことになった。そして、2年前のトランガーヌ戦役で、弱冠14歳ながらも功績を上げた彼が、この地の領主として赴任することになったのである。
もともと商家の出身ということもあり、彼は領主に就任して以来、民衆の自由な経済活動を重んじる施政方針を掲げているため、ドミナスを初めとする先代領主以来の村の有力者達ともすぐに友好な関係を結ぶことに成功し、今のところ治世は安定している。ウリクルは、モラード地方の「入口」に位置する土地でもあるため、この地の領主が自由主義経済を掲げてくれることは、商人達にとっても望ましく、その評判はすこぶる良かった。
そんな彼が住む領主の館の二階にある執務室に、まず最初に到着したのは、執政官のドミナスと、そのお供のベーナであった。ドミナス曰く、三日後に開催予定のゴルフ場の新コース(10番ホール)のお披露目会に、ジェロームの出身地であるパルテノの領主の娘であるマリベル・キャプリコーンが、ゲストの一人として参加予定だという。
「ほう、マリベル姫が」
ジェロームにとっては、懐かしい名であり、そして特別な名でもある。というのも、上述の通り、ジェロームの母はパルテノの貴族令嬢の乳母であり、そしてその貴族令嬢こそが、他ならぬマリベル姫であった。つまり、マリベルと彼は乳兄弟の関係ということになる。
「この機会にぜひ、姫との仲をお深め下さい。名門貴族家と縁を結ぶことは、あなたにとっても、この村にとっても、大きな利益となるでしょう。無論、あなたが『もっと格上の姫』をお望みなのであれば、その志は大いに歓迎致しますが」
現時点でも、マリベルと彼は既に肉親同然の関係である。それ以上に仲を深めるということが何を意味しているかは、ジェロームにも理解は出来る。ただ、それに関しては、彼自身が望むだけでどうにかなるという話でもなかった。
「姫との仲か。そうだな……、善処してみよう」
具体的に何をどう善処するつもりなのかは明言せぬまま、軽く受け流すように彼がそう答えると、突然、屋敷の外から、叫び声のような大声が聞こえてきた。
「領主様、領主様はおられるか!?」
真っ先に窓の外を見たのは、ベーナである。そこにいたのは、一人の兵士の姿であった。だが、ジェロームはその姿を見なくても、その声の主が誰かは分かった。それは紛れもなく、ジェロームがまだパルテノにいた頃から彼と顔馴染の、領主家直属の古参兵の声である。
「おぉ、私はここだ」
そう言って、彼は一歩遅れて窓越しに外を見て、その古参兵に声をかけた。
「お久しぶりでございます、ジェローム様。今現在、我々はマリベル姫の護衛として、この村の近くまで来たのですが……」
その兵士曰く、村の近くで通りすがりの村人が怪物に襲われている場面を目の当たりにしたマリベル姫が、村人達を助けるためにその怪物に襲いかかり、それに怯んだ怪物達が山林の奥地へと逃げて行くと、それを深追いして、彼女は護衛の兵達を置いて一人で突入してしまい、行方不明となってしまったのだという。
マリベル姫は、弱冠16歳ながらも剣技に優れた「おてんば姫」として有名であり、その剣技は並の兵士では到底太刀打ち出来ず、そして馬術にも優れている。その彼女が本気で追撃した結果、誰も追いつけなくなってしまったらしい。
「何をしているんだ!」
「申し訳ございません。我等、姫をお守りするために、皆が重武装で同行するようにエルネスト様から申し付けられておりまして……」
結果的に、その重武装故に彼女の追撃速度に追いつけなくなってしまったらしい。彼女の父エルネストは、まさか姫が自分から小柄部下を捨てて一人で突撃するほどの猪武者だとは思っていなかったようである。
「では、仕方あるまい」
そう言って、彼は急いで武具を着込む。まだ成長過程の年齢である彼は、体格的にはかなり小柄だが、その左手には、自分の身体と同じくらいの巨大な盾が装備されている。彼は「他人を守る能力」に秀でた騎士であり、その巨大盾によって、これまで多くの同胞達を救ってきた。
一方、ベーナもまた、そんなジェロームと目が合った瞬間、その意を察して、彼と共にそのまま部屋を出る。既に彼の実質的な「主武器」としての地位を確立しているベーナとしては、ここで彼と共に出陣しない理由はない。
すると、そんな二人が階段を駆け下りて行く途中で、逆にジェロームの執務室へと向かうために階段を上ろうとしていたクローとヴェルディと遭遇した。
「あれ? ジェローム様。珍しく忙しそうですね」
ヴェルディは自分の契約相手に対して微妙に失礼なことを言ってのけたが、ジェロームは、その程度のことで気分を害するような人物ではなかった。
「おぉ、ちょうどいい所で会った。そちらでも何かあったのか?」
領主のその問いに対して、今度はヴェルディよりも先にクローが答えた。
「実は、知り合いから手紙が届きまして」
「手紙か。ならば、後でいいな」
そう言って、彼はベーナを伴った状態で、クローとヴェルディの傍を潜り抜けるように階段を降りて行く。その急足の様子を見て、ヴェルディが問いかけた。
「出撃ですか?」
「あぁ。一緒に来てくれるか?」
「仕方ないですね」
ヴェルディはそう言って、すぐに後を追う。当然、クローもそれに続いた。そのまま四人は館の外に出て、伝令に来た古参兵と合流し、彼の指示する方向へ向かって走って行く。その過程で事情を説明されたヴェルディは、呆れた口調で淡々と呟く。
「一人で勝手に獲物を追って突撃ですか。なんだかまるで、躾の悪い獣みたい……、あ、いや、なんでもないです」
さすがに、姫の部下がいる状態でその発言はまずいと思ったのか、彼女は途中で口をつぐむ。
「まぁ、それで助かる人がいるのだから、良いではないか」
ジェロームはそう言ってさりげなく姫の行動を擁護しつつ、彼等は山林の中へと突入していくのであった。
そして、山林の中に入った彼等は、その古参兵の証言を元に、怪物達が逃げて行きそうな方向を予想しながら捜索を続けていくと、やがて、若い女性の怒号と、その女性が何かと戦っているような音が聞こえてくる。
彼等がその物音のする方向へと向かうと、そこにいたのは、何匹もの巨大な「百足」に取り囲まれた状態で長剣を振るって戦っているマリベル姫(下図)であった。姫は百足に噛まれて出血しながらも、その傷口を押さえつつ必死に奮戦し、次々とその百足達を倒していく。
「やれやれ。尻拭いするこっちの気持ちにもなってほしいな」
そう言いながら、ヴェルディは遠方から、姫の傷を回復させる魔法をかける。すると、その魔法を受けたことで援軍の存在に気付いた姫は、振り向きざまに(その魔法の主が誰なのかも分からない状態のまま)大声で素直に礼を言う。
「ありがとー!」
だが、それに対してヴェルディは淡々と返答する。
「お礼を言う暇があるなら、おとなしくしてほしいですね」
「だって、みんな遅いんだもん!」
その言葉にヴェルディは若干イラッとするが、そんな彼女を横目に、クローが自らの身体を「龍」に変えた上で、姫を助けるために真っ先に走り込んでいく。そしてジェロームは、おもむろにベーナに近付いた。
「よし、ベーナ、行くぞ」
その意を解したベーナは自らの身を「本来の姿」へと変える。正確に言えば、「本来の姿」に憑依するように存在していた「擬人化体」としての彼女の姿が消え、「武具」のみの状態となった彼女は、ジェロームに「装備」された状態となる。そして「彼等」はそのまま百足達に近付き、そして、「ジェロームの体に憑依した状態のベーナ」が、百足の身体を抉るようにその身で斬りかかり、百足は大量の血を流して悶え苦しむ。
突如現れたジェローム(とベーナ)に対して、その百足は牙を剥いて襲いかかるが、ジェロームはその攻撃を真正面から受け止めた上で、返す刀で斬り掛かる。だが、ジェローム自身は「攻撃」よりも「守り」の技術に特化した騎士ということもあり、その一撃は惜しくも避けられてしまう。しかし、その直後にマリベルが振り下ろした剣が、その百足にとどめを刺した。
一方、クローにも百足が襲いかかり、その龍鱗を食い破るように牙を立てる。だが、クローにとっては、その程度の出血は怯む理由にはならない。すぐにそれを自力で軽く止血した上で、龍化した拳の一撃であっさりとその百足を粉砕する。更に、後方からヴェルディの放った矢が残っていた百足の身体を貫き、百足達は完全に殲滅させられた。
「ありがとう、ジェローム。助かったわ。あなた達が来てくれなかったら、倒すまでもう少し時間がかかってたと思う」
倒した百足達の混沌核を浄化・吸収するジェロームに対して、マリベルはそう告げる。あくまでも、自分一人でも倒せたと確信しているマリベルだが、実際、彼女は一人でもあの百足の群れを殲滅出来るだけの力は持っている。ただ、その場合、彼女は相応の手傷を負っていたであろうし、その間に怪物の増援が現れたら、どうなっていたかは分からなかったであろう。
「ご無事で何よりです。ベーナ、もう戻っていいぞ」
ジェロームは姫に向かって軽く一礼しつつ、自身の腕に装着された武具に対してそう告げる。
「よいしょー」
そう言って、ベーナが「人の姿」に戻ると、マリベルは興味津々の表情を浮かべる。
「これが噂の、この村に伝わる伝説のオルガノンなのね」
「まぁ、山の上に刺さってたんだから、見てくれはそれっぽいよね。中身はどうかは分からないけど」
ヴェルディが冷めた口調でそう言っているところで、数十人の集団がこの場に近付いて来る音が聞こえてきた。どうやら、マリベルの護衛の兵達のようである。
「姫様、ご無事でしたか!」
その隊長らしき人物(下図)が姫を見るなり、そう叫ぶ。姫から事情を聞いた彼は、ジェローム達に対して、深々と頭を下げた。
「皆様、互助力頂き、かたじけない」
「護衛隊長さんかと思ったら、給料泥棒さんでしたか」
そう言い放つヴェルディであったが、さすがにジェロームが嗜める。
「そういうことを言うものではないぞ」
とはいえ、反論出来る立場でもないその隊長は、あえてその発言は聞き流したまま、改めて挨拶する。
「今回、姫様の護衛を仰せつかりながら、このような失態をおかしてしまい、申し訳ございません。隊長のシドウ・イースラーと申します」
彼はアンデッドの邪紋使いである。ジェロームがパルテノを去った後に同地の領主エルネストの下に士官したので、彼とは面識がない。
「姫様、人助けは結構ですが、あまり一人で先走ってはなりませぬ。戦場において単独行動は危険であると、お父上様も仰っていたではありませぬか」
シドウがそう言ったところで、ジェロームが何かを思い出したように口を開く。
「おぉ、そうだ。襲われていた人達は大丈夫だったのか?」
「えぇ。何人か噛まれていた者達もいましたが、我が隊の治療班がすぐに対処しました」
「そうか、それは何よりだ」
村を預かる領主としては、姫の活躍のおかげで村人達が助かったのであれば、それだけでも姫に対して深く感謝すべき案件であり、姫を助けたことで恩を着せられる立場でもない。ヴェルディとマリベルの間で微妙な遺恨を残しながらも、ひとまず彼等は互いの助力を讃え合いつつ、村へと帰還するのであった。
2.2. 行商人の一行
夕暮れ時が迫ろうとしている中、村へと帰還したジェローム達は、マリベル達を宿舎へと送り届けたところで、今度は西方からやってきた行商人の一行と遭遇する(下図)。その商隊主の名は、アストリッド・ユーノ。もともとジェロームの実家とは繋がりが深かったこともあり、彼の領主就任以来、頻繁にこの村を訪れるようになった豪商である。そして彼女もまた、今回の新ホールの杮落としのゲストとして招かれた人物の一人であった。
そして、実はクローにとっては、彼女は自分がこの村に来る前の雇い主の一人でもあった。そのこともまた、彼女がこの村と縁深くなった一つの要因でもある。
「お久しぶりね、クローさん」
「あぁ、これはこれは久しぶり。ところで、そいつらは新しい護衛かい?」
彼は、アストリッドの傍にいる四人(上図右側)を見ながら、そう問いかける。
「えぇ。と言っても、あくまで期間限定なんだけどね」
「まぁ、俺の時もそうだったしな」
「でも、私の商隊の護衛を務めた人は、出世するというジンクスもあってね。あなたとは入れ違いだったけど、最近出来たグリースっていう国の盟主様も、昔、私に雇われていたことがあった訳だし。あなたもきっと、そのうち、今以上の地位に上り詰めると信じているわ。そしたら、その時はまたよろしくね」
そんな会話を交わしている中、彼女の護衛の一人と思しき少年と目が合ったジェロームが、一瞬、驚いた表情を見せつつ、彼に語りかける。
「久方ぶりではないか、ロディアス」
「兄さん!? なんでここに?」
その「ロディアス」と呼ばれた少年は、ジェローム以上に驚愕の表情を見せる。彼は、ジェロームの3歳年下の実弟である。実家の後継者候補の一人であったが、数年前に出奔し、今は行方不明になったと聞かされていた。
「今はここに腰を落ち着けているからな。お前も元気そうで何よりだ」
「いや、まぁ、元気は元気なんだけど……、何があったの?」
「私は、この辺り土地の領主をやっている」
「そ、そうかぁ……。出世したんだね」
「あの行商人殿が言うには、お前も出世するそうじゃないか。良かったな」
ロディアスとしては、自分がなぜここにいるのかを問われると、色々と面倒なことになると思っていただけに、ジェロームが特に何も追求しようとしないことに、内心安堵していた(彼がここにいる理由については
ブレトランド八犬伝・簡易版を参照)。
ちなみに、彼女がここに来たのは、新ホールのお披露目に参加するだけでなく、本業である「新商品の売り付け」という目的もあった。彼女は、四人の「新入り護衛」の中で最も大柄な色黒の男に命じて、背負っていた荷物を下ろさせる。すると、その中には、キラキラ光ったゴルフボールと、丁寧に折りたたまれた布地の何かが入っていた。おそらく、後者はゴルフウェアであろう。
「なにこれー、きれー」
「成金趣味だな」
ゴルフボールを見たベーナとクローが対象的な反応をしている中、アストリッドは得意気に語り始める。
「このゴルフボールはね、ただ光ってるだけじゃないのよ」
「ほう?」
クローが興味を示すと、アストリッドは魔道具のような何かを取り出す。
「この『ロストボール・レーダー』があれば、このボールがどこにあるのか、すぐに探知することが出来るの」
つまり、このボールが森林の中に入り込んでしまっても、この魔道具があれば簡単に見つけることが出来る、という代物らしい。鴉によるボール盗難の被害に遭っている今のウリクルにとっては、非常に有用な新商品と言えよう。
「なるほど。それは便利だな」
「ついでに、あのボールを盗んで行く迷惑な鴉共の居場所も分かるかもしれないしね」
領主と契約魔法師がそう言って興味を示している中、先刻までその重い荷物を持っていた色黒の筋肉質の男が、クローに興味深い視線を向けながら話しかけてきた。
「ところで、アンタ、邪紋使いだよな?」
クローの邪紋は背中にある。普通ならば見える筈がない。だが、それでも彼はなぜか、クローが邪紋使いであることをすぐに見抜いたようである。
「あぁ、そうだが」
「すまないが、その邪紋を見せてもらえないか?」
普通、邪紋はあまり堂々と見せるものではない。無論、中にはそれを見せることによって相手を威嚇しようとする者もいるだろうが、他人の邪紋に興味を持つ者など、普通はあまりいない。いきなり、そんな不可解なことを言われたクローが一瞬、戸惑っていると、その意を介した色黒の男は、突然、服を脱ぎ出した。
「そうだな。いきなりこんなことを言うなら、まずは俺の方から見せるべきか」
そう言って、彼は自らの胸に刻まれた邪紋を見せつける。どうやら、彼もまた邪紋使いらしい。そして、クローは彼のその堂々とした態度が気に入ったようで、クロー自身もまた潔く、豪快に服を脱ぎ捨てて、背中を彼に晒す。
「これでいいか?」
そこには、龍の翼のような形をした邪紋が刻まれていた。二人の大柄な男が互いの肉体を見せ合っているこの状況に、周囲の者達がドン引きしていることにも気付かず、色黒の男はその背中の邪紋をまじまじと凝視する。
「うむ、そうか。残念だが、俺達が探している邪紋使いではないようだな。だが、お前は俺と似たような匂いを感じる。もしかしてお前、龍のレイヤーか?」
「あぁ」
クローは短くそう答えると自らの身を龍に変える。それを見た色黒の男もまた、彼と同様にその身を龍に変える。
「わー、ドラゴンだー」
ベーナが無邪気にそう喜ぶ。一方で、ヴェルディは淡々と冷めた視線でその様子を眺める。
「レイヤードラゴンは、頭の中も筋肉で出来てるのかな」
実際のところ、ドラゴンは決して頭が悪い魔物ではない。むしろ、高位のドラゴンに関しては、並の人間以上の叡智の持ち主も少なくはない。しかし、だからと言って「ドラゴンの力に憧れを持つ人間」もまた頭がいいとは限らない。
「お前、ノリがいいな。気に入った。この村で、どこか美味い酒場を知らないか? 俺が奢ってやるから、一緒に飲もうぜ」
「あぁ、それなら、とっておきの店を紹介してやるよ」
「じゃあ、ぜひ連れてってくれ。俺の名はラスティ。よろしく」
そう言って、二人の「龍の模倣者」達は、徐々に日が暮れようとしている中、村の酒場へと向かって行く。その後、二人は朝までひたすら飲み明かすものの、最終的にはラスティの方が先に酔いつぶれ、結局、酒の代金は(まだ理性を保っていた)クローが払うことになったという。だが、久しぶりに気の合う「同類」と飲み明かせたことで、彼は十分に満たされた気持ちになっていた。
2.3. 政務補佐官への疑惑
一方、ジェローム、ヴェルディ、ベーナの三人は、アストリッド達ともひとまず別れた上で、領主の館へと戻ろうとしていたが、その途上、ヴェルディがジェロームに語りかける。
「そうだ、領主様、さっき話そうと思っていたのが、どっかのお馬鹿さんのせいですっかり話が流れてしまったんだが……」
ヴェルディが言ってる「馬鹿」というのが、姫のことなのかその護衛のことなのか(あるいは両方なのか)は分からないが、どちらにしても、彼女にそういった態度を取り続けられるのは、外交上あまり望ましくはないので(契約魔法師は、場合によっては外交官的な役割を果たさねばならないこともある)、ジェロームはなんとか彼女の見識を改めさせようと試みる。
「この世界、馬鹿の方が幸せらしいぞ」
「まぁ、幸せになれなくても、求めたいものはありますから。そうそう、で、村の人達が言うには、人を襲う投影体が増えているようなのです。あの鴉共はボールしか持っていかない筈ですから、何か別の現象が起きているのかもしれませんね」
「鴉以外にも、か。もう少し、対策を厳重にしなければいけないかもしれんな」
実際、そのことは先刻の百足達からも想像は出来る。あのような魔物が頻繁に出没するようになるようなら、本格的な調査が必要だろう。
「あと……、これもさすがに報告しないといけないかなぁ」
「まだあるのか?」
「エーラム時代の先輩から手紙が来たんですけど、この村にパンドラが来ているかもしれないんですって。僕、調べてもいいですか?」
「まぁ、調べるなとは言わん。だが、さすがに、いざどうこうしようという時は必ず声をかけてくれよ」
「領主様の命令なら仕方ないですね。あ、ちなみに、その人の話によると、そのパンドラのエージェントってのは、紺色のスーツを着た細身で長身の男らしいです」
ここで、今まで黙っていたベーナが、露骨に驚いた表情を浮かべる。
「あれ? 何か知ってるのか?」
「さっき、ウチの御主人様のところに来たけど、追い返しちゃった」
そう言われたヴェルディは、ドス黒い笑みを浮かべながら口を開く。
「そっか……。とりあえず、彼が何か知ってるなら、話を聞きに行こうかな」
その様子を横目に見ながら、このまま彼女一人に任せる訳にもいかないと判断したジェロームも同行する形で、三人は、ドミナスの館へと向かうことになった。
*
こうして、陽が沈もうとする刻限になって、ベーナが領主と契約魔法師を連れて帰ってくると、その状況に驚いたドミナスは、怪訝そうな顔でジェロームに問いかける。
「何事ですかな、領主殿?」
「先刻、こちらに来たという紺色のスーツの男について、こいつが知りたがっていてな」
「教えてくれる?」
冷たい笑顔で小首を傾げながらそう問いかけるヴェルディに対して、ドミナスは不機嫌そうな態度で答えた。
「あいつは、関わるべき男ではない」
そう言われたヴェルディもまた、不機嫌そうな声で更に問いかける。
「もしかして、私が子供だからって、甘くみてるんじゃないです?」
「甘く見る以前の問題だな。そもそも、子供が関わるべき話ではない」
「パンドラだから、ですか?」
露骨に鋭く切り込んだその一言で、その場の空気は凍りつく。だが、ドミナスは平静を装いながら切り返した。
「……その話を、誰から聞いた?」
「誰からも何も、私はパンドラについては詳しいですから」
ヴェルディがパンドラに対して異常なまでの執着心を持っていることまでは、ドミナスは知らない。ただ、彼女ほど極端ではないにせよ、多かれ少なかれエーラムの人間がパンドラを敵視しているということは、常識レベルの話である。
「あいつ自身は『パンドラの人間』だと名乗っている。お前があいつを殺したいなら、好きにしろ。私には止める理由はない」
「で、そのパンドラの人間は、あなたに何の用があってここに来たんです?」
「さぁ、なぁ……。まぁ、私のようにあちこちに顔が広いと、色々なところで恨まれるのだよ」
そう言ってはぐらかすドミナスであるが、彼の口ぶりや仕草から、明らかに彼が何かを隠していることはヴェルディには分かる。しかも、それが相当後ろ暗い事情であることも察していた。
「ところでドミナスさん、僕がまだ11歳なのに、なんでこの村の契約魔法師が出来るか、分かります?」
「それは、お前の師匠がお前をここに派遣したからだろう?」
より正確に言えば、彼女の師匠であるカルディナ・カーバイトが「ドミナスのゴルフ場に遊びに来るための口実」を欲しがったから、なのであるが、今回の論点はそこではない。
「それはそうですけど、そういうことではなくて、なぜ僕が11歳であるにもかかわらず、魔法大学を卒業して契約魔法師になれたか、ですよ。答えは簡単。僕がエーラムに来る前から、魔法を習っていたからです。さて、それはどこだと思いますか?」
「ふむ……、それはつまり、その紺色のスーツの男は『お前の元身内』ということなのか?」
厳密に言えば「身内」と言うほど親しい関係ではない。少なくとも、ヴェルディはその男個人に関しては一切の心当たりがない。ただ、彼女自身が「元パンドラ」であるという経歴は、ドミナスも理解したようである。
「察しが早くて助かります。今の私はあの連中との繋がりはないですよ、むしろあの連中を一人残らず抹殺してしまいと思っています。あなたがこのまま黙り続けているなら、私はあなたをあの連中の仲間とみなします。それが何を意味するか、分かって頂けますか?」
ここで、今まで黙っていたベーナが口を挟んだ。
「それはつまり、私を敵に回すということですか?」
彼女にとっては、ドミナスは(色々と面倒な人物だと思ってはいるが)「主人」であり、眠っていた自分を呼び起こしてくれた「恩人」でもある。さすがに、これ以上、ヴェルディがドミナスに敵意を向けるのであれば、彼女も黙ってはいられなかった。
「もちろん、それでも私はやるつもりですから」
不敵に笑うヴェルディと、彼女を牽制するような視線を送るベーナが静かに激しい火花を散らす中、ジェロームはあえて静観していた。身内同士が諍いを起こすのは好ましくはないが、現状、このドミナスがパンドラと接触して「よからぬこと」を企んでいる可能性は十分にある以上、それをヴェルディが問い詰めること自体は、何も間違ってはいない。かといって、まだ証拠不十分なこの状況で、領主である彼までもがドミナスを責め立てるような態度を採るのも、やや早計と言えば早計である。
そして、ドミナスもまた、あからさまな敵意を向けられつつも、あくまでそれを軽く受け流すような態度で答えた。
「まぁまぁ、待て待て。そういうことなら、私を殺したところで、何の得にもならんぞ。私を殺せば、あいつが私を訪ねに来る理由もなくなるからな。理由は知らんが、あいつは私のところにやってくる。ならばむしろ、私を生かしておいた方が、お主にとって得ではないか?」
ドミナスが「理由は知らんが」というのが、明らかにただの「方便」であることは、ヴェルディには読み取れた。
「あくまで『話さない』と仰いますか」
「話して分かるとは思えぬし、そもそも、私が『本当のこと』を言うと思うか?」
自分を詰問するヴェルディに対して、ドミナスもまたあえて挑発するような態度でそう答える。
「なら、仕方ないですね。とりあえず、あなたを泳がせて、あなたのところに『例の人』が来てから考えることにしましょうか」
「それでいい。『まっとうなエーラムの魔法師』であれば、勢い余って私まで殺してしまうようなことはしないと、私は信用しているからな」
「私がまっとうな魔法師かどうかは、あなたの知るところではないですね。用が終わったら、殺すかもしれませんが」
互いに相手を見下すような視線をぶつけ合いながら、遠慮なく本音を言い合うこの二人の冷たい空気の中、再びベーナが口を開いた。
「ご主人、ご主人。色々と思うところはあるでしょうが、この人、この家に置けませんか?」
「ほう?」
「次に例の人が来た時に、そのまま『ばったり』合わせてしまえば良いのではないかと」
確かに、それが一番話が早いだろう。無論、それはドミナスが本当に「紺色のスーツの男が彼女に殺されても構わない」と思っている、ということが前提の上での提案なのであるが。
「なるほどな。で、『あいつ』は、お前一人でどうにかなる相手なのか?」
ドミナスはヴェルディに対してそう問いかけるが、彼女としても即答は出来ない。現実問題として、相手の力量についてはまったく分からないのが現状である。加えて、ヴェルディはあくまでも遠距離戦専門の魔法師なので、もし相手が接近戦を得意とする人物だった場合、狭い屋敷の中で遭遇するのは、あまり望ましい状況とは言えない。
ここで、今まで黙っていたジェロームが、ようやく口を開いた。
「ドミナス殿、私はこいつの面倒を見るつもりだから、こいつが泊まって行くなら、私の部屋も用意して頂きたい」
さすがにジェロームとしても、ここで優秀な魔法師を犬死にさせる訳にはいかない。彼女が得体の知れない相手と対峙するなら、自分が盾となって彼女を守るのは当然の義務と考えているようである。
実際のところ、ドミナスの屋敷は多くの客人を招くことを想定して設計されているため、客室にはいくらでも余裕はある。だが、その提案に対して、ドミナスは意外な反応を示す。
「それならむしろ、私が領主様の館に行った方が早い気がしますな。少なくとも、私の自宅に私がいない状況よりも、領主様の館に領主様がいないことの方が問題でしょう」
「おぉ、なるほど。それもそうだな」
突然の逆提案であったが、ジェロームにとっても、その方が上策であるように思えた。それに、もし彼が何か「良からぬこと」を企んでいた場合、彼の屋敷にジェロームやヴェルディが宿泊していた場合、どんな奸計を用いられるか分かったものではない。その意味では、ドミナスが自らこのような提案をしてきたということは、少なくともドミナスがジェロームやヴェルディに対して害を成そうとする意思を持っている可能性は低そうである。
「では、私はこの屋敷に残って、ご主人を訪ねてその人が来たら、領主様の館に行くように誘導すれば良いのですね」
ベーナは笑顔でそう言ったが、ドミナスはあっさりと否定した。
「いや、お前も来い」
「えぇ!?」
「そこの魔法師が、勢い余って私にまで矢を向けてきた時に、誰が私の盾になるんだ?」
「……分かりました」
こうして、急遽ドミナスとベーナの「領主の館への引っ越し作業」がおこなわれることになった。ただ、領主の館には客室が常備されている訳ではないため、今夜の間に引っ越すのは難しい。その上で、今夜中に「例の男」がドミナスに会いに来るかもしれないということで、結局、この日の夜はジェロームとヴェルディが、このドミナスの館に泊まることになるのであった。
2.4. ペアマッチ
翌朝、酒場から朝帰りしたクローが、前日言いそびれた「先代領主の息子の件」の報告のために領主の館へと向かうと、その玄関先に、一人の女魔法師(下図)の姿があった。
彼女の名は、カルディナ・カーバイト。ヴェルディの師匠であり、「裏虹色魔法師」の異名を持つエーラムの高等教員の一人であるが、教育者にあるまじき「遊び人」としても有名な放蕩魔法師でもある。彼女はこの村の「ブランギース・カントリークラブ」の「お得意さん」でもあり、クローにとっても「見慣れた来客」であった。
「おぉ、アンタか。またゴルフかい?」
「あぁ、明後日の新ホールのお披露目コンペに招待されたからな。行かない訳にはいかない。ところで、その私を招いてくれたオーナーと、この村の領主と、ウチのガキに挨拶に来たんだが、誰もいないんだ」
彼女は領主の館を親指で指差しながら、困った表情でそう告げる。通常なら、ドミナスもヴェルディも領主の館に出仕していることが多いため、ここに来れば三人に会えると考えていたようだが、完全にアテが外れてしまったようである。
「そうか。俺も領主に用事があったんだが……、さて、どこに行ったのかな」
「この村の領主は、そんな放浪癖だったか? 前に来た時は、そんなでもなかったと思うんだが」
そんな話をしているところで、その領主の館の入口に、今度はマリベル姫が現れる。
「あれ? ジェロームはどこに行ったの?」
「いや、むしろ俺が聞きたいんだが……」
クローは、貴族令嬢が相手でも万事この口調である。もともと、ドラゴンに育てられた彼には、人間界における身分や礼節という観念が欠けているらしい。また、マリベルの方も、基本的にざっくばらんな性格なので、明らかに平民であるクローからこのような態度を取られても、特にそのことを咎める気はなかった。
そして、そんな二人のやりとりに、カルディナが割って入る。
「あんたは?」
「パルテノの領主エルネスト・キャプリコーンの長女、マリベルよ。明後日開催予定のゴルフ大会に招待されたの」
「そうか。あんたが私の今回のコンペの対戦相手の一人、ってことだね。私はこの村の契約魔法師の師匠のカルディナだ。よろしく頼む」
そう言って、カルディナが右手を差し出すと、マリベルも素直にその右手を握る。
「えぇ、よろしく。本当はお父様が呼ばれてたんだけど、マージャの音楽祭と日程が重なってしまったから、私が来ることになったの。私はこの村のゴルフ場に来るのは初めてだけど、ゴルフにはそれなりに自信もあるしね」
マリベルの父エルネストは、ジェロームの就任以来、(彼の実質的な縁戚ということもあって)たびたび来賓としてこの地のゴルフ大会に招かれている。ただ、エルネストはゴルフ選手としても一定の評価を得ているが、それ以上に「芸術家将軍」の異名を持つ人物として有名であり、特にピアノの腕前に関しては、アントリア随一とも言われていた。それ故に、今回の新ホールの杮落としよりも、音楽祭への出場を優先することになったらしい。
「そうか。せっかくだから、もうちょっと張り合いのある相手とやりたかったんだがな」
「あら、少なくとも、魔法師さんよりは、遠くに飛ばせる自信はあるけど」
そう言いながら、マリベルは手を離して、背中に背負っていたカバンの中から、愛用のクラブを取り出し、カルディナに向ける。
「なかなか活きのいい姫様だな」
そう言いつつ、カルディナはニヤリと笑う。そんな二人を横から見ていたクローとしては、ひとまずこのまま客人を外に置いておく訳にもいかないと思い、衛兵に口利きして、二人を中に館の中の応接室へと招く。すると、その中には既に、アストリッドの姿があった。
「あんたも、今回参加するんだっけ?」
クローにそう問いかけられると、アストリッドは笑顔で答える。
「確かに私も招待されてはいるんですが、私の主目的は、むしろこの最新型ドライバーのテストなんですよ」
そう言って、彼女は一本の木製クラブを取り出す。それは、通常のドライバーよりもやや長く、ヘッド部分が独特の形状となっていた。
「これを使いこなせる人がいるなら、別に私が出なくてもいいんですが……、クローさん、あなた、やってみませんか?」
「お、いいねぇ。面白そうだ」
「これがあれば、飛距離は相当伸びる筈ですよ」
そんな二人のやりとりを見ていたカルディナが、ふと独り言のように呟き始める。
「ふむ、私としては、相手は誰でもいいんだが、さて、どうしたものかな。私は久しぶりに、あのガキと遊んでやろうと思って来たんだが、あやつはなかなか自分から、こういった遊びには手を出さんからな……」
そうこうしている中、やがてジェロームが、ヴェルディ、ドミナス、ベーナの三人(および、ドミナスが宿泊するために必要な日用品を運ぶ召使い達)を連れて、館へと戻ってくる。応接室に客人が来ていると聞かされたジェロームは、そのまま三人を連れた状態でその部屋の扉を開けた。
「あ、先生」
最初に声を上げたのは、ヴェルディであった。
「おぉ、ようやく来たか。元気そうで何よりだ。で、オーナー殿、今回の出場予定者は、私らだけでいいのかな?」
そう問われたドミナスは、応接室の中にいたカルディナ、マリベル、アストリッドの三人に目を向けながら、淡々と答える。
「はい。他にも何人かの人に打診はしたのですが、色々とご都合が合わず、今回、ゲストとして招待させて頂いたのは、御三名様のみとなります」
「ふむ。まぁ、しかしなぁ、私も子供相手に本気になるのもアレだしなぁ」
カルディナは、マリベルを挑発するような視線で見ながらそう言いつつ、何かを思いついたような表情を浮かべる。
「そうだ、ドミナス殿。一つ提案なのだが、今回のコンペ、ペアマッチにしないか?」
ペアマッチとは、二人一組になって、交互に打ち合う試合形式のことである。実力差のある者達が同じ組でコースを楽しむための手法として、様々な機会で用いられている。
「私のペアは、ハンディとして、こいつでいい」
そう言いながら、カルディナはヴェルディを指差した。
「ガキの相手はガキで十分だろう」
「ちょっと、私、いくらなんでもこんな小さな子と一緒にされるのは心外だわ」
11歳のヴェルディに対して、16歳のマリベルがそう言うと、ヴェルディは冷めた表情を浮かべながら口を開く。
「その小さな子にさっき助けられたのはどなたでしたっけ?」
「別に、あんた達がいなくても倒せたわよ。時間がかかっただけで」
「そうですか、じゃあ、次は助けには行きませんが」
これに対して、さすがに見かねたジェロームが、ヴェルディに視線で「その辺にしておけ」と訴えると、彼女もその意を察して矛を収める。
「……まぁ、領主様の命令なら行きますけど」
そして、まだ微妙に不服そうな顔のマリベルは、ジェロームの元に近寄っていき、その腕にしがみつく。
「じゃあ、私はジェロームと組むけど、それでいい?」
「私は、それで構いませんよ」
淡々とジェロームがそう答えると、ドミナスは「我が意を得たり」という表情を浮かべる。彼としては、この大会を通じて二人の仲を深めてもらいたいと考えていたため、この提案はまさに願ったりであった。
そして、アストリッドは傍にいたクローに声をかける。
「そういうことなら、私達も組んで出ることにしましょうか?」
「おぉ、せっかくだからな」
こうして、あっさりとゲスト側の3ペアが確定した。こうなると、ベーナとしては「自分は出場しなくてもいいのかな」と思いつつ、確認のためにドミナスへと視線を向けた瞬間、彼と目が合い、そして彼は不敵な笑みを浮かべる。
「では、領主様自身がプレイされるのであれば、私も久しぶりに自分で打ってみることにしましょう。私のペアはお前でいいな、ベーナ?」
そう言った彼の目は「役目は分かっているな?」と訴えていた。
(はぁ……、そういうことになりますよね……)
とはいえ、実際のところ、「程よく負ける」というのは、存外難しい。そしてベーナは、あまり器用な作業が得意ではない
「どうなっても知りませんよ」
「私は、お前を信用しているからな。その信用に足らなかった者がどうなるかは……、その時、考えようか」
こうして、今回の大会に出場する4組のペアが確定したのであった。
2.5. 山狩り
その後、クローがようやく手紙の件についてジェロームに報告する。先代領主の息子については、ジェロームとしては「どちらでも構わない」という方針を示したため、その息子自身が帰還を望まない限りは、このままマージャに留まり続けることになるであろう。
問題は、鴉の件である。鴉の類の魔物は、本来は人を襲わない筈。その話と少年の証言は矛盾している。その状況を踏まえた上で、ドミナスがジェロームに対して、投影体討伐を提案した。
「明後日のコンペの前に、少しでも危険な可能性は排除しておくべきでしょう。ひとまず、今から出撃の準備をして、明日、本格的な山狩りを決行するのはいかがでしょうか?」
そう進言するドミナスを、彼の従者は意外そうな瞳で見つめる。
「あぁ、ご主人、まともなこと言ってる……」
ベーナにとってはドミナスは「面倒な主人」ではあるが、彼は政務官としては極めて有能な人物である。そうでなければ、一代で巨万の富を稼ぐことなど出来はしなかったであろう。
「そうだな。とはいえ、私一人ではどうにもならん。皆、ついてきてくれるか?」
ジェロームがそう言うと、部下達は揃って頷く。
「私は傭兵ですからね。行けと言われれば行きますよ」
「領主様は、攻撃力がないですからね」
「私は、領主様の攻撃力ですからね」
こうして翌日、ジェローム、ヴェルディ、クロー、ベーナは、それぞれに部隊を率いて、魔物の出現率が高まったと言われている山林の一角へと出陣することになった。
*
そして、彼等が山奥に入っていったところで、異形の鴉達の集落を発見する。その中には普通の鴉程度の大きさの者もいれば、鷲や鷹よりも大型の、明らかに魔物としか形容のしようがないほどの大きさの鴉もいる。そしてその中心にいたのは、「鴉と人の中間のような姿の魔物」であった。おそらくそれは、地球もしくはそれに近い世界から投影されたと言われる、鴉型投影体の希少種「鴉天狗」であろう。
この山林はもともと混沌濃度が高く、鴉型のみならず、様々な投影体が存在する。それ自体は何十年も昔から続いているこの村の常態であった。だが、彼等は概ね、この山林から外には出ようとはしなかったため、歴代領主は無理に討伐しようとはしなかったのである。しかし、ここで彼等はその状況が少しずつ変わりつつあることに気付く。鴉型の投影体の数が明らかに以前よりも増えて、他の投影体達を捕食し、そこから逃げていく者達が山を下って行くのが見える。その中には、先日遭遇した巨大百足と同型の魔物達の姿もあった。
「こいつらが、この山林のバランスを乱しているんだな」
クローはそう呟く。ここにいる四人の部隊長の中で、最も昔からこの村にいるのは彼である。その彼が、明らかに鴉の数が増殖していると判断した以上、おそらくその推測で間違いはないだろう。もっとも、その原因は未だ不明ではあるが。
そして、ジェロームは、その状況を把握しつつも、まずは村へと向かう怪物達を食い止めに行こうとするが、それをクローが止める。
「まず、根本の問題を解決すべきではないか?」
「……分かった。では、まずは鴉達を討伐した上で、その後で下山して魔物達を止めよう」
村にはまだ戦力が残っているし、マリベル姫の護衛の兵達もいる。いざとなれば、カルディナも防衛戦に力を貸してくれるだろう。エーラムの高等教員は、集団戦においてはまさに一騎当千の存在である。鴉達に捕食される程度の魔物であれば、彼女一人でもどうにかなることは、ヴェルディには容易に予想がついた。
こうしてジェローム達は、まず目の前の鴉達を駆逐すべく、完全武装した状態で彼等の前に姿を現した。それに対して、鴉達は動揺しつつも、ひとまず様子を見ているようで、彼等の方から仕掛けてこようとはしない。
そんな緊迫した状況から、まずはヴェルディが全力の強弓を、指揮官と思しき鴉天狗に向かって放った。だが、敵がパンドラの一味かどうかが分からないせいか、いま一つその一撃に威力がなく、その一撃で倒しきるには至らない。それに続いて、クロー、そして(ベーナを装備した)ジェロームが突撃して鴉天狗を攻撃するも、ギリギリのタイミングで避けられてしまう。そして、ジェロームが聖印の力を使った瞬間、鴉天狗の目の色が変わり、露骨な敵意を彼に対して向ける。
「聖印だ……、母上の仇だ!」
彼はそう言いながら、一歩後退して態勢を立て直しつつ、彼の号令に合わせて、他の鴉達がジェロームに向かって次々と襲いかかる。だが、守り巧者のジェロームには全く通用しない。彼はその攻撃の全てを、「ベーナ」を使ってあっさりと受け流し続ける。
そんな中、ジェロームは自身の隊内の兵達が妙に騒がしい様子になっていることに気付く。そこには、見覚えのある人物の姿があった。
「投影体退治に私が行かないなんて、ありえないでしょ」
マリベル姫である。どうやら彼女は、密かにジェローム隊の中に潜んでいたらしい。彼女もまた、剣を振るって奮戦している。どうやら、自分も参戦したかったのを護衛隊長のシドウに止められたため、一人で勝手に潜り込んだ様子である。
ここで彼女に何かあった場合、色々な意味で重大な問題となりかねないのだが、それでも実際に彼女がいることで戦力にはなっているので、ジェロームとしてはひとまずその点については目を瞑った上で、敵陣の様相を冷静に分析する。
「あいつは、話が出来そうだな」
ひとまず、この状況を把握するためには、一定の理性を持つと思われる鴉天狗を捕らえる必要がある。そう考えた彼は、遠方にいるヴェルディ率いる弓兵に、自分達と乱戦状態にある鴉天狗達の「本隊」に向かって、一斉射撃をかけるように命じる。その意を受けたヴェルディは、味方への被害はジェロームが聖印の力で食い止めてくれると信じて射撃をかけるが、それでもさすがに味方を巻き込む攻撃だったこともあり、いま一つ精度が悪い。
(優しいですね。ヴェルディさん。これくらいなら、簡単に避け……)
武具状態のベーナはそう思いながらその矢雨を避けようとするが、ジェロームがそれを強引に引き戻す。
「お前が避けてどうする!」
(えぇー!? そんなー)
ベーナは攻防一体の武具である。彼女だけが避けても、彼女を装備している状態のジェロームが避けられない状態では、武具として避ける意味がない。ジェロームは避けようとしたベーナを盾にして、兵達を守りつつ聖印の力で降り注ぐ矢を受け止める。
(武具使いが荒いんだから、もう……)
そのままジェロームが鴉天狗に対して猛攻をかけ、更に側面からクロー隊が襲いかかる。龍化したクローの剛腕の一撃をまともに喰らった鴉天狗はその場に倒れ、それを見た彼の部下の鴉達は一斉に逃げて行く。こうして、ジェローム達も相応の被害を出したものの、どうにか目の前の脅威を払うことには成功した。
2.6. 詰問
そして、幸いにもまだ鴉天狗には息があったので、身動き出来ないように取り囲んだ上で、ジェロームが直接詰問する。
「お前には、聞きたいことがある」
「なんだ? 俺達とお前達の関係修復は、もう不可能な筈だが」
鴉天狗はジェロームのことを強く睨みつけながら、そう言い放つ。
「関係修復も何も、私はお前を知らないのだが」
「ほう? では、お前は『我が母をだまし討ちにした君主』ではないというのか?」
いきなり、鴉天狗から意味不明なことを言われたジェロームとその部下の者達は、いずれも揃って不可解な顔を浮かべる。
「何のことだ? さっぱり分からんが」
「お前の言うことが本当か嘘かは分からん。俺達も、2年前の幼かった頃の記憶しかないし、そもそも人間の顔の区別などつかないからな」
「2年前か……。ならば、ちょうど私がここに来た頃だな」
つまり、この鴉天狗の言っている「だまし討ち」なる行為が本当なら、それは先代領主の可能性もあるし、もしかしたら、トランガーヌ戦役の過程における両軍のいずれかの君主の仕業なのかもしれない。
「どちらにしても、我々はもう人間は信用しない。特に君主はな」
「そうか。信用しないのは構わんが、お前達は人間に仇なすつもりか?」
「無闇矢鱈に人間に戦いを挑んでも仕方がない。数は人間の方が多いからな。とにかく、我々は母上をだまし討ちにした君主を殺す。そのために力をつけてきた。それだけだ」
どうやら彼等の勢力が拡大してきたのは、その「母の仇」を取るためらしい。実際、彼等はこれまで人間を襲ったことは殆どない。ゴルフボールを盗んでいたのが、何か策略があってのことなのか、それとも下級の鴉達が本能でやっていたことなのかは分からないが、その過程で何人かの衛兵達と小競り合いが起きたことはあったものの、少なくともこれまで、集団で人間を襲うことがなかったのは事実である。
ここで、ベーナが人間体になって(擬人化体を出現させて)、鴉の前に現れる。彼女としては、んとか無駄な衝突を避けたいと考えていた。
「その君主の特徴とか、覚えていないかな? 聖印の形状とかでもいいんだけど」
「分からん。お前達だって、俺達の顔の区別などつかないだろう? それと同じことだ」
つまり、彼等は今後も「君主」に対しては無差別で攻撃する可能性が高い、ということになる。このまま放置しておけば、今後もジェロームや来賓の君主が狙われる可能性は高いだろうし、それぞれの君主が「身の潔白」を証明しようにも、聞く耳を持つ気はないらしい。そして、彼等がこの山林で勢力を拡大すれば、生態系のバランスが崩れて、彼等から逃れるために山を下った魔物達が人を襲う事例も増えることになるだろう。彼等の言い分に理があろうが無かろうが、この地に住まう人々を守る立場の者としては、看過出来ない事態である。
「何にしても、このまま放置しておく訳にはいかないな」
「そうだな。この地に通りかかった他の無関係な君主が襲われる可能性もある」
クローとジェロームがそう言うと、鴉天狗は更に鋭い瞳で彼等を睨みながら言い放つ。
「仮に俺を殺したとしても、他の6人の兄弟が、お前達を許しはしないぞ」
その語気からは、助命を乞う意志は感じ取れない。彼自身、もはや死を覚悟した上で、最後の恫喝を試みているようである。
「私を襲うのは構わんが、お前達こそ、他の人々を襲うようなら、私の方がお前達を許さないからな」
彼はそう言って、剣を持って鴉天狗の首を切り落とそうとしたが、既にベーナは彼の手から離れていたことを思い出す。そこで、ヴェルディが鴉天狗に向かって弓を構えた。
「待ってよ。ここで殺しちゃうのは、カラスさんがかわいそうだよ」
そう言ってベーナが割って入ろうとするが、ヴェルディは冷たく言い放つ。
「邪魔ですよ。どいてくれないと、誤射しちゃいますよ」
さすがに、ベーナもここで自らの身を呈してまで庇おうとする意思はないので、バツがわるそうな顔を浮かべながら、その場を退く。
「すみませんね、こういう人達なんで……。悪く思わないで下さいね」
次の瞬間、ヴェルディの放った一撃で鴉天狗は絶命し、その混沌核をジェロームが吸収する。生かしておいて「残りの6人」とやらの居場所を聞き出す選択肢も無くは無かったが、もはや彼がそれに応じそうな気配は感じられなかった。
2.7. 深まる疑惑
そして、ジェローム達はひとまず、村に降りていった魔物達を討伐するために、部隊の者達に下山を命じる。
「えー、帰るのー? あと6匹いるなら、とっとと倒しちゃおうよ」
ジェローム隊の中にいるマリベル姫がそうゴネるのに対し、ヴェルディが冷たく言い放つ。
「名家の方なら、人の土地の問題に、他の土地の人が干渉すべきでないことは分かりますよね? お帰り下さい」
「どこの土地が誰の物とか、そういうこと以前に、まず投影体を倒すことが私達の『君主』の使命でしょ?」
だが、それに対して、今度はジェロームが姫にこう告げた。
「えぇ。ですが、優先順位というものがあります。今は、この土地の領主である私が、村の人々の安全を優先するために下山すると判断した以上、それに従って下さい」
「……分かったわ。あなたの言う通りね、ジェローム」
そう言って、マリベルは素直に彼に従う。自分の乳兄弟のジェロームに「領主としての正論」を語られたことに、内心感服していた。
(いつの間にか、私よりも立派な君主になったのね……)
そんな感慨を抱いた彼女と共に、彼等は下山して村へと向かう。すると民家の領域に近付くにつれ、あっさりと撃退されたと思しき魔物達の死屍累々を次々と目の当たりにする。どうやら、カルディナと、マリベルの護衛兵と、そしてアストリッドの護衛兵達によって、いとも簡単に殲滅させられていたらしい。
村に被害が出ていないことに安堵した彼等は、ひとまず領主の館へと帰還する。すると、その館の中の廊下を歩いていたヴェルディとベーナが、ドミナスが借りている部屋から、ほのかに血の匂いがすることに気付く。
ヴェルディはすぐさま彼の部屋の扉を開けた。すると、その中にはドミナスが一人で悠然と佇んでいた。
「何がありました?」
「いや? 別に何も?」
鋭い視線で睨みつけながら問いかけるヴェルディに対して、淡々とそう言ってのけるドミナスだが、その口ぶりから、明らかに何かを隠している様子なのは、すぐにヴェルディには分かる。
「領主様のお館で流血沙汰を起こしておいて、何もなかったと言い放つとは……」
ヴェルディがそう言いながら露骨に敵意を向けるのを目の当たりにして、少し遅れて部屋の中に入ってベーナも「さすがに、これ以上、彼女との関係を悪化させるのはまずい」と実感する。
「ご主人、ご主人。隠し事はダメですよ。ちゃんと言って下さらないと」
ヴェルディを制するようにベーナもそう進言する。そして、ジェロームとクローもその部屋の中に入ってきた。
「何かあったのか?」
ジェロームにそう言われたドミナスは、諦めたような口調で呟き始める。
「子供は巻き込まない方がいいと思ったんだがな」
「下手な大人よりは、修羅場をくぐってきましたから」
そう言いつつ、警戒心を解こうしないヴェルディに対して、ドミナスは粛々と説明する。
「お主等がおらん間に、例の紺のスーツの男が来たから、お帰り願った。それだけのことだ」
「どこに行ったんですか?」
「さぁな。館から逃げた後のことは分からん」
どうやら、今度はその発言には嘘はないようにヴェルディには思えた。そして、部屋の中にも、大臣の服にも、血痕は残っていない。だが、確かに血の匂いはする。おそらく、彼等が戻ってくるまでの間に、服を着替えて、床を丹念に磨いてごまかそうとしたのであろう。
問題は、仮にパンドラのエージェントを相手に刃傷沙汰が発生していたとして、誰がドミナスを守ったのか、である。彼自身は「ただの一般人」の筈であり、もし相手が魔法師や邪紋使い(あるいは投影体)であった場合、まともに戦って勝てる筈がない。もっとも、その「紺色のスーツの男」の方も、ただの小間使いの一般人である可能性もある訳だが。
(この男、本当にドミナス殿なのか?)
そう不審に思ったクローは、改めてドミナスの出で立ちや雰囲気を凝視するが、ジェローム赴任以前から彼のことを知っているクローが見ても、明らかにドミナス本人であるように思える。
「ドミナス殿、何かあったのなら、私に声をかけてくれ。領主として、私もしっかりと対応する」
ジェロームがそう告げると、ドミナスも淡々とその言葉には同意する。とはいえ、果たして彼が心の底で何を考えているのか、この時点ではまだ誰にも分からなかった。
2.8. それぞれの特訓
「さて、ベーナよ。明日に向けて特訓でもするか」
一通りの追求が終わったところで、ドミナスは唐突に話題を変える。
「はて? 特訓とは、一体……?」
「我々が『ベスト尽くす』ための特訓だ」
「ベストを尽くすことなんて、ありましたっけ?」
「もう一度言う。『ベストを尽くす』ための特訓だ。何が『ベスト』かは、私が決める」
「……お伴します」
そう言って、彼はベーナを連れて、ゴルフ場に併設された「打ちっぱなしゾーン」へと向かう。
「よし、じゃあ、私らも特訓するぞ」
カルディナもまた、そう言ってヴェルディを連れて館を去って行った。ヴェルディとしても、ひとまずここは彼等と別れて独自に行動した方が得策と考えたようで、素直にその言に従う。
一方、一通りの役目を終えて傭兵隊の宿舎へと帰還したクローの元には、アストリッドの護衛のラスティが訪れていた。
「いやー、昨日はすまんかった。俺が奢るって言ったのに、結局、あんたに払わせちまって」
そう言って平謝りしつつ、彼の背中にはゴルフバックが背負われていた。
「実はな、俺もゴルフの腕にはちょっと自信があるんだ。だから、練習するなら、付き合ってやってもいいぜ」
実はラスティは貴族家の出身であり、「上流階級のスポーツ」としてのゴルフにも、ある程度精通しているらしい。
「特に、遠くに飛ばす技術に関しては、昔、ヴァレフールのドラコン(ドライビング・コンテスト)で優勝したこともあるからな。俺がコーチして、新型ドライバーを使えば、まさに鬼に金棒よ」
ちなみに、彼がドラコンで優勝したのは、レイヤードラゴンの力に目覚めるよりも前である(つまり、「ドラゴンだけに」という訳ではない)。「一般人」だった状態で、並み居る騎士達を相手にそこまでの結果を残せたということは、相当な実力者ということであろう。
「おぉ、そうか。それは心強いな」
こうして、二人が再び意気投合してゴルフ練習場へと向かっていく中、もう一人のアストリッドの護衛であるロディアスは、実兄であるジェロームの元にいた。
「兄さん、僕、パターゴルフなら得意だから、パターの練習なら付き合えるよ」
実際、彼はこの地を訪れる以前は、ヴァレフールで老騎士の侍従をしていたこともあり、彼のキャディーとして、幾度かのゴルフコースを回ったこともある。マリベルがまた一人で暴走するのが心配なジェロームとしては、ひとまず彼女も一緒にロディアスを伴ってゴルフの練習に従事することで、鴉達のことを忘れさせた方がいいだろう、と判断し、その申し出を受け入れることにしたのであった。
*
こうして、それぞれに明日のコンペに向けて、コンディションを整えていく。ただ、そんな中、ヴェルディだけは、師匠との特訓を終えた後、密かに「紺色のスーツの男」についての聞き込み調査をおこなっていた。すると、確かに「その男がドミナスの部屋に入って行くのを見た」という人物と、「その男が館の中庭を血を流しながら走っているのを見た」という人物に遭遇する。一方、ドミナスの部屋にその男以外の者が入ったのを見た者はいなかった。
つまり、状況的に考えて、ドミナスが一人で「パンドラのエージェント」を撃退したとしか考えられない。
(もしやあの政務官、邪紋使いか何かなのか?)
ドミナスにそのような力があるという話は聞いたことがない。だが、彼はいつも豪奢な服を着込んでいるため、その下に「何か」を隠していたとしても不思議はない。様々な可能性がヴェルディの頭の中を過る中、現状ではこれ以上追求する術がないため、やむなく静かに就寝することにした彼女であった。
2.9. それぞれの領主評
そして翌日、遂に新ホールのお披露目の日がやってきた。領主の館を間借りした一室にて、ドミナスはベーナに対して、ふと問いかける。
「ここ二年ほど、今の領主殿の武具として戦ってみた身として、彼のことをどう思う」
ベーナは、少し考えた上で答えた。
「武器のことを一番思ってくれる人ですよね」
昨日のような形で無茶な使い方もされるが、それは彼女の能力を信頼した上の行動でもある。実際、彼女の能力は、彼の下で存分に生かされていることは、彼女自身も実感していた。
「お前にとっては『扱いやすい君主』ということでいいのか?」
「そういうことになるんですかね。でも、どうしたんですか、突然?」
「いや、特に深い意味はない。ただ、お主の役に立つ君主ということは、私にとっても役に立つ君主、ということになるな」
そう言いつつ、ドミナスは一人密かにほくそ笑む。今後、領主と主人が衝突する可能性を危惧していたベーナとしては、ひとまずこのタイミングで「俺とあいつと、どっちにつくのか?」というようなことを聞かれなかったことに安堵していた。今の彼女にとっては、どちらも「守りたい人物」なのである。
*
一方、その頃、エーラムの最新デザイナーの手による最新のゴルフウェアを身にまとい、クローの宿舎を訪れていたアストリッドは、彼に対してこう問いかけた。
「あなた、この村に来てから、どれくらいになるんですか?」
「そうだな。前の主人の時から数えて、結構な年数になるが……」
「前の君主と比べてみて、今の君主のことはどう思います?」
そう言われたクローも、しばし考え込む。しかし、すぐに「考えても仕方がないこと」だという結論に到達した。
「うーん、まぁ、特に領主個人に対して思うところはないかな。俺は、今が楽しければそれでいいさ」
逆に言えば、「楽しく過ごすことが出来る環境」を、今の領主は提供してくれている、ということでもある。それだけでも、彼の中では十分な存在価値なのであろう。
「あなた方は、そういう心算で生きていった方が良いでしょうね。私も、物を高く買ってくれる領主様であれば、誰でもいいですから」
アストリッドは笑顔でそう語る。どうやら、傭兵にとっても、商人にとっても、少なくとも今の領主は「及第点以上」の存在と認識されているらしい。
*
そしてヴェルディもまた、師匠から同じような質問を受けていた。
「お主も、あのジェローム殿に仕えて2年近くになるが、お主から見て、どうだ? あの君主は?」
「そうですね……、私のことを理解した上で、自分の主張を受け入れてくれていますし、よく気遣ってくれてもいます。少し甘すぎるところもありますが、そこは僕が埋めていけば良いかと」
相変わらず不安定な一人称で、彼女はそう語る。
「まぁ、甘すぎるからこそ、お主を受け入れているんだろうな」
苦笑しながらカルディナは続ける。実際、彼女の弟子達の中でも、ヴェルディは特に「扱いにくい存在」であることは彼女も分かっていた。だからこそ、ヴェルディが今のこの地で、若い領主と良い関係を築けていることに安堵しているようである。
「まぁ、いずれにせよ、あの君主ならばお主を受け入れてくれると信じてお主を預けた私の判断は間違ってはいなかった、ということだな」
「先生は、ただ単に自分が遊ぶために私をここに派遣したのではなかったのですか?」
「いや、遊ぶため『だけ』ではない。それぞれの適性『も』考えてはいるんだ」
「やはり先生、さすがですね」
それが本音なのか皮肉なのか、どちらとも解釈出来るような微妙な言い回しではあったが、少なくともヴェルディが、今の職場に自分を派遣してくれたことをカルディナに感謝していたのは事実であった。
*
こうして、自分の臣下の者達がそれぞれの君主評を語っているとは露知らず、当のジェロームは、マリベル姫と二人きりで、ゴルフ場へと向かっていた。本来ならば部下達が彼女の身辺警護を続けるべきなのだろうが、そこは護衛隊長のシドウが「気を利かせた」らしい。
「なんだか、ちょっとギスギスしていない、この村?」
「そうか?」
ジェロームは、公的な場ではマリベルに対して敬語で話すが、二人きりになると、家族に接するようなラフな口調になることがある。やはり、彼の中では今でも彼女は「身内」という意識が強いのだろう。
「あのちっちゃい子もそうだし」
「確かに、彼女はたまに殺気立ったりするからな」
「ゴルフ場のオーナーさんも人相悪いし」
「彼は……、味のあるいい顔だと思うぞ」
というか、さすがに顔のことまで文句を言われても、ジェロームとしては反応に困る。
「とはいえ、それが日常であって、それで安定しているのであれば、多少ギスギスしていても問題はないだろう」
「まぁ、それならいいんだけど。で、あなたはどうするの? これから先も、ずっとここで領主を続けるつもりなの?」
「そうだな。この村が私を必要としてくれている以上、私はここに残るつもりだし、この村のために出来ることをしていくつもりだ」
そう言われたマリベルは、少し残念そうな顔を浮かべつつ、ふと奇妙なことを口にする。
「じゃあ、この村以上にあなたを必要としている人が現れたら?」
その質問の意味をジェロームが理解したのか否かは分からない。だが、彼は少し考えた上で、「ごく当たり前の返答」を口にする。
「ふむ、そうだな。まぁ、どちらにせよ、次の赴任先が見つかるまでは、私はここで任務を果たすのが私の使命だと思っている」
「……そっか。『あなたの代わり』がいればいいのね」
その言葉が何を意味しているのかについて、マリベルはきちんと説明しないまま、独り言のように続ける。
「まぁ、あなたが『こっち』に来なくても、もう一つ、選択肢はあるしね」
その言葉が何を意味しているのかについても、ジェロームは特に考えない。より正確に言えば、あえて聞かなかったことにした。そんな彼の「立場」と「心境」を察したマリベルは、ため息をつきつつ、話を続ける。
「何はともあれ、今日は頑張りましょう。あの、なんかムカつく魔法師には負けたくないし」
「あぁ、そうだな。皆が楽しむためには、私も楽しまなければな」
こうして、新コースの杮落としとなるゴルフコンペが始まった。このコンペの目玉は新設の10番ホールだが、通常の大会と同様に、1番ホールから4組8人が一つのグループとなって、順番に回っていく。そして、くじで順番を決めた結果、1番ホールは「マリベル・ジェローム組」「カルディナ・ヴェルディ組」「アストリッド・クロー組」「ドミナス・ベーナ組」の順番で打つことになった。ちなみに、1番ホールは350ヤードのパー4。このゴルフコースの中では、標準的な長さである。
まずはジェロームが、最初のティーショットを放つ。大きく振りかぶったそのドライバーによって弾かれたボールは、ティーから約120ヤードの位置に到達する。ミスショットという程ではないが、正直、彼としては今ひとつの伸びであった。
「大丈夫よ。次で私がグリーンに乗せるから」
そう言って励ますマリベルを横目に、今度はヴェルディがティーショットの体勢に入る。静動魔法師である彼女は、その気になれば魔法の力で打球を操ることも可能だが、ここはひとまず、正々堂々と勝負することにした。すると、彼女のドライバーはボールを真芯で捉え、見事に飛距離250ヤードのロングショットとなる。だが、運悪く、その落下先はバンカーであった。
「ふむ、私のサンドウェッジの出番をわざわざ作ってくれた、ということだな」
苦笑しながら師匠にそう言われたヴェルディが黙って俯くと、続いて「龍」の姿を発動させたクローがティーショットの準備を始める。彼は、どんな時でも手を抜くことは決してしない。新型ドライバーで大きな弧を描きながら放たれたショットは、ティーから約192ヤードという、まずまずの位置のフェアウェイに乗せることに成功した。
「やっぱり、あの新型ドライバーは、彼のようなパワーヒッター向きね」
アストリッドは満足気にそう呟く。そして、続く四人目はベーナである。彼女としては、どれくらいの手加減で打てば良いのか分からなかったため、ひとまず最初のティーショットは、何も考えずに全力で振り抜くことにした。ところが、その「全力」が空回ったのか、その飛距離は僅か80ヤードで止まってしまう。
(いい滑り出しだな)
ドミナスはベーナに対して目でそう訴えかける。別に手加減した訳ではなかったが、結果的に主人の望む形になったことに、ベーナは少し安堵していた。
そして、ベーナとペアを組むドミナスは、二打目を程良く飛ばして230ヤードのフェアウェイに乗せる。あと少し飛ばせばバンカーに入るところだったが、彼としては、最初のコースからあまりバンカーで長引かせて足を引っ張るのも良くないと考えているようである。
続いて、ジェロームの後を受けて放ったマリベルの二打目は、グリーンには届かず280ヤードの地点に留まる。一方、初打ではベストの位置に達していたクローのペアとなるアストリッドは、新型ドライバーを用いてグリーンオンを狙ったものの、打球がスライスしてしまい、あえなくOBとなってしまう。
「ごめんなさい、やっちゃいました」
苦笑しながら手を前で合わせて詫びたアストリッドからドライバーを受け取ったクローは、一打罰を受けた上での「四打目(実質、三打目)」で、どうにかグリーンの近く(通算飛距離327ヤード)まで運ぶことに成功する。そして、ベーナもまた三打目で、その少し手前(通算飛距離308ヤード)のフェアウェイに到達した。
一方、バンカーショットとなったカルディナの二打目は、落下地点がバンカーのど真ん中だったこともあり、あと一歩のところで、バンカーからの脱出に失敗する。やむなくヴェルディが三打目でどうにかバンカーから外に出した上で、続く四打目でカルディナがグリーンオンを狙うものの、あわやOBというギリギリのラインまで飛ばしてしまう。どうも、この魔法師師弟ペアは、今ひとつ力の加減が上手くいっていないらしい。
そんな彼女たちを横目に、ジェロームは三打目で見事にグリーン・オンに成功し、ドミナスもまた四打目できっちりとニアピンの位置に乗せる。一方、アストリッドの五打目は惜しくもグリーンには届かず、クローの六打目でようやくグリーンに到達。グリーンオーバーしていた魔法師組も、ヴェルディの五打目でどうにかグリーンに辿り着いた。
こうして、最初のホールはようやくパット勝負に突入する。マリベルは四打目となるパットであっさりとカップインに成功し、見事に「パー」でこのホールを終了したのに対し、アストリッド・クロー組とカルディナ・ヴェルディ組は、いずれもカップから遠い位置だったこともあって2パットを要してしまい、それぞれ「4オーバー(ダブルパー)」「3オーバー(トリブルボギー)」でこのホールを終える。そして、ピンそばにつけていたベーナは、きっちりと1パットで沈め、「ボギー」となった。
「やっぱり、こういうのはベストを尽くさないとね」
純粋にプレイとして上々の結果に終わったベーナは満足そうな表情を浮かべるが、それに対してドミナスから淡々と「次のコースからが本番だな」と言われて、ようやく「使命」を思い出す。ただ、そんな彼女の様子を見たジェロームは「なんだかんだで、あいつもちゃんと楽しんでいるな」と、少し安堵した表情を受けべていた。
3.2. 攻防〜2番ホール〜
続く2番ホールは、250ヤードのショートホールではあるものの、グリーンへと続くフェアウェイが大きく曲がっているので、OBに注意する必要がある。
そのことを肝に銘じつつ、まずはマリベルが一打目で思いっきり飛ばそうとするも、その気合が空回りしたのか、打球は117ヤード地点のバンカーに落下してしまう。
「ごめん、バンカーに……」
「うむ、まぁ、これくらいのハンディなら、どうということはないですよ」
そんな気落ちするマリベルに対して、追い打ちをかけるようにドミナスが告げる。
「姫様、順番が違っていませんか?」
1番ホールで最後にパットを決めたのはマリベルである。つまり、本来ならばこの最初のティーショットは、ジェロームが打たなければならない。それが一般的な「ペアマッチ」のルールであった。
「え? そうだったの? てっきり、ティーショットの順番も毎回変わるものだとばかり……」
「まったく、最近の小娘は、自分の順番すらも分からなくなってきたか」
カルディナはそう言ってマリベルを挑発するが、この件については、確認しなかったジェロームの責任でもある。そして、本来ならばペナルティが発生するところだが、今回はあくまで親善試合ということで、主催者であるドミナスの判断により、そのまま続行ということになった。
そして、彼女に続いて放たれたカルディナ、アストリッド、ドミナスのティーショットは、三人揃って144ヤード付近のフェアウェイに到達する。1番ホールではいい所がなかったアストリッドも、ようやく調子を出してきたようである。
そしてジェロームが二打目でバンカーからの脱出に成功するものの、続くマリベルの三打目は、勢い余ってOBになってしまう。どうやら、初打で色々と失敗してしまったことを、まだ引きずっているらしい。そんな彼女につられるように、ジェロームの五打目(実質、四打目)も、思ったほど飛距離は伸びなかった(通算飛距離225ヤード)
そんな「君主組」とは対照的に、ヴェルディはあっさりと二打目でグリーン・オンに成功する。一方、続くクローの二打目はグリーンを大きくオーバーしてしまうものの、かろうじてOBになる寸前でボールは止まる。そして、ほぼ同じ位置からベーナが放った二打目は、グリーンの手前にある池にハマってしまった。
「お、なんかいい音した!」
「まったく、しょうがないな、お前は」
呑気な感想を語るベーナに対して、ドミナスはそう言いながらも、その目は「よくやった」と訴えていた。池に落ちた場合はバンカーとは違って池の手前からの打ち直しになるため、泥沼化する可能性が低い分、他のプレイヤーに不快感を与えない「良いミスショット」なのである(ドミナスの中では)。
そして、マリベルが六打目であと一歩のところでグリーンに届かなかったのを確認した上で、ドミナスもまた四打目で、同じように「グリーン手前」に落とすことに成功する。このように、場の空気を読んだミスショットを絶妙なタイミングで繰り出すことこそが、「接待ゴルフ」の歴戦の猛者である彼の真骨頂であった。
一方、本気で不調に苦しんでいた君主ペアは、ここでジェロームが起死回生の一打を放つ。グリーン手前からの絶妙なアプローチショットが、見事に旗に吸い込まれるようにな軌道を描き、カップインに成功したのである。
「やるじゃない、ジェローム!」
そう言って、彼女はジェロームに抱きつく。自分が散々足を引っ張ってしまったこのホールではあったが、これで通算「+4」となり、魔法師組に引き離されずに済みそうな展開にまで引き戻すことが出来たことに、彼女は心底喜んでいた。
その後、結局、魔法師組はパットで2打費やした結果、このホールを「ボギー」で終了し、彼女達もまた通算「+4」で君主組とトップタイのまま2番ホールを終えることになる。一方、アストリッド・クロー組は、アストリッドが3打目でなんとかグリーンには乗せるものの、そこから3パットを費やしてしまい、「トリプルボギー」となってしまう(通算「+7」)。そして、ドミナス・ベーナ組もまた、ベーナの五打目でどうにかグリーンには乗せて、そこから2パットを費やすことで、「トリプルボギー」でこのホールを終了し、通算「+4」でトップの2ペアに並んだ。
ただ、この過程でカルディナは、一つ、気になることがあった。
(あの投影体の小娘が打った五打目、ドミナス殿がその直前に旗を抜いていなければ、チップインしていたのでは……?)
確かに、その直前でドミナスは旗を抜いていた。通常、グリーン近くからのショットの場合、旗を抜かないのが一般的だが、あえて抜いたのは、それを防ぐためだったのではないか、というのが彼女の憶測である。実際、彼女がみた限り、あの打球の軌道がそのままで旗が立っていれば、少なくとも旗に当たって、もっとピンそばに落ちていた筈である。
(あくまで、我々に花を持たせようという算段か。あまり露骨に舐めた態度を見せてもらっては困るぞ、オーナー殿)
カルディナは一人静かにそんな闘志を燃やしていたが、残念ながら、彼女がその闘志をぶつける機会は、この直後、思わぬ展開によって奪われてしまうことになる。
3.3. 暗雲〜3番ホール〜
彼等が続く3番ホールに足を踏み入れた瞬間、まだ昼前であるにもかかわらず、徐々に空が暗くなり始めていた。より正確に言えば、空が「黒く」なりつつあった。快晴の空を覆うように、空に黒い翼を持った巨大な生き物が現れたのである。それは、昨日の鴉天狗とよく似た姿の六匹の魔物達と、それに率いられた無数の鴉達であった。
その姿を見た瞬間、まっさきに叫んだのは、マリベルである。
「ドミナスさんとアストリッドさんは、下がって下さい」
「一般人」である彼等を巻き込む訳にはいかない、そう判断した彼女の宣言は間違ってはいないが、そこにヴェルディが淡々と言い放つ。
「マリベルさんも下がって下さいね」
「何を言ってるんですか、あなたみたいな子供を残して、ここで私が退く訳にはいかないでしょ」
そんな二人が口論している最中、ベーナもまたドミナスに進言する。
「ご主人、お下がり下さい」
「うむ、分かった」
そう言って、彼はあっさりとその場から姿を消す。アストリッドもまた、護衛の者達が待つ村の方角へと走り去って言った。一方、カルディナは少し達観したような表情で、この状況を見守りつつ、おもむろに口を開いた。
「私も下がっていいかな?」
カルディナが本気になれば、鴉達を容易に迎撃することも出来るだろう。だが、ここは弟子のヴェルディの面目を立てるためにも、彼女に任せるべきだと考えたようである。また、もしかしたらこの鴉達が「陽動」の可能性もある以上、ひとまず彼女は先に村に帰った方が良いかもしれない、という思惑もあった。
「出来れば、この姫様も連れて下がってもらえると助かりますね」
「分かった」
「ちょ、ちょっと待ってよ。私は君主なんだから……」
そう言って抵抗するマリベルであるが、カルディナは常磐の生命魔法の力で強化した腕力によって、強引に彼女を引きずり出す。
「姫、ここは彼等に任せましょう。別働隊がいるかもしれません。我々は村の警備に向かうべきです」
そう耳打ちすることで、ひとまずマリベルも納得し、彼女と共にゴルフ場から去っていく。
「勝負に水差しやがって!」
一人負け状態だったクローは、反撃の機会を与えられる前に邪魔されたことに憤りつつ、その身を龍に変えて戦闘態勢に入る。そして、そんな彼等の視界に、やがて一人の男が映った。空を覆う鴉天狗達を指揮しているように見えるその男は、「紺色のスーツ」に身をまとっている。
「ご主人、これは一体どういうことですか!?」
ベーナは思わずそう叫ぶが、ドミナスはもういない。そもそも、聞いたところで、彼がこの事態を予見していたかどうかも分からない。ひとまず彼女は武具化した上でジェロームにその身を委ね、そしてジェローム、クローと共に、その紺色のスーツの男に向かって接敵しようとする。
だが、そんな中、その紺色のスーツの男はジェローム達に向かって、火炎魔法を放ってきた。どうやら、やはり彼はパンドラの魔法師だったようである。ジェロームの聖印とヴェルディの魔法によってある程度までは軽減させたものの、彼等はそれなりに深い傷を負う。
そして、その男はジェローム達に向かって、こう叫んだ。
「邪魔だ! どけ、雑魚共!」
その口調は、三日前にドミナス宅を訪問した時とは別人のように殺気立っている。だが、この彼の口調から察するに、彼の目的はジェローム達ではないらしい。
「雑魚って言いましたね? それは、撤回してもらいますよ」
武具としての誇りを傷つけられたベーナは、ひとまずジェロームと共に、目の前の鴉天狗を攻撃する。クローもそこに加勢するが、それでも致命傷には至らない。そして、鴉天狗達はジェローム達の攻撃を受け流しつつ、そのまま彼等を置いて「先」に進もうとする。と言っても、村に向かっているようにも見えない。彼等が向かう先に何があるのかも、この状況ではよく分からない。
「奴等は、何が目的なんだ?」
ジェロームは困惑していたが、そんな中でヴェルディは鴉達には目もくれずに、紺色のスーツの男に向かって次々と全力で弓矢を打ち続ける。
「ずっと探してたんだから、遊んでくれないなんて、ひどいじゃん」
さすがに彼女からの連射をその身に受けて、紺色のスーツの男の表情に歪みが生じる。そこに更にジェロームと共に走り込んだベーナが渾身の一撃を加えようとするが、あっさりと避けられ、勢い余ったその一撃で、フェアウェイに大穴が空いてしまう。その隙に紺色のスーツの男はその場から逃げようと試みるが、さすがに四人全員からは逃げ切れそうにない。
「しつこいぞ、お前等! お前等には用はない!」
「そっちに用が無くても、私には用があるんだ♪」
そう言いながら、なおも追撃の構えを見せるヴェルディ達に対して、彼は再度火炎魔法を放つが、再びジェロームの聖印とヴェルディの魔法によって、なんとか全員、一命を取り留める。そして、改めて彼に接敵したベーナ(が憑依した状態のジェローム)が、再び全力の一撃を叩き込む。
「今度こそ!」
その一撃は紺色のスーツの男の身体を捉え、その身は真っ二つに切り裂かれた。こうして、どうにか彼等はパンドラの魔法師(と思しき人物)の撃退に成功したが、問題は、彼等を無視して飛び去って行った鴉達の動向である。このまま放置しておけば、村に甚大な被害が発生する可能性もある。
だが、その心配は杞憂であった。飛び去って行った鴉天狗達の大半は、カルディナが放ったと思われる魔法によって、次々と撃ち落とされていく。それでも、その魔法攻撃網を突破した鴉天狗の一部は、更にその先へと向かって行ったが、そこで「何者かの聖印の力」によって倒され、浄化されていた。といっても、その様子まで確認出来たのは、ヴェルディとジェロームの二人だけであった。
「あれは……、聖印?」
ヴェルディの目には、その聖印の力を使っている人物までは、はっきりと確認出来ない。ただ、その聖印に関しては、マリベルの聖印とは、形も規模も違うように思える
一方、ジェロームには、その聖印を用いて鴉達を浄化している者の姿もはっきり見えていた。自分の周囲に誰もいない状況で、自分一人の力であっさりと鴉天狗を倒して浄化している人物、それは、ドミナスであった。
「……これは、帰ってから、話を聞かなきゃいけないな」
彼はそうボソッと呟きつつ、皆を連れて村へと戻って行くのであった。
結局、カルディナ(とドミナス)の奮戦もあって、鴉天狗達は一人残らず撃退された。彼等によって率いられた鴉達の一部が暴走して村を襲おうとしていたが、それらもマリベル、シドウ、そしてアストリッドの護衛の四人によって、あっさりと殲滅させられ、村人への直接的な被害は殆ど発生しなかった。
ただ、鴉達の襲撃によって、10番ホールを含めた大半のコースが半壊してしまったため、その修繕のため、コンペはあえなく中止を余儀なくされてしまった。
「まったく、鴉くらいお前一人でどうにかならんのか」
「範囲攻撃魔法なんて、教えてくれなかったじゃないですか」
戦いを終えた魔法師の師弟は、そんなやりとりを交わす。もっとも、それはヴェルディが選択した山吹の系譜の問題なのであるが。
「まぁ、そうだな。まだちょっとお前には早かったかもしれんが、ともあれ、よく生き残った。最低限の仕事はしたと言って良いだろう」
そう言って、彼女は弟子の頭を撫でる。その横では、マリベルがジェロームに向かって飛びついていた。
「よかった、ジェローム、無事だったのね」
「まぁ、あれくらいなら大丈夫だ」
そうは言いつつも、結構な深手を受けている。実際、魔法師からの攻撃に加えて、もし鴉達が彼に集中攻撃をかけていたら、いかに彼といえども、無事だった保証はない。その意味では、あまり素直に「勝った」とも思えない結果であった。
一方、他の鴉達を撃退したラスティも、クローが帰還したことを喜ぶ。
「なんとか無事だったようだな」
「正直、ひたすら逃げられっぱなしで、厄介な相手だった」
実際、クローはこの戦いにおいて、敵の動きに翻弄されるばかりで、思うような戦果を挙げられないまま終わってしまった。村の治安を守る者として、不本意ではあったが、この雪辱は次の機会を待つしかないだろう。
そして、なに食わぬ顔で村に戻ってきたドミナスは、ベーナに対してこう問いかけた。
「ベーナ、お前は『何か』見たか?」
「えーっと、領主様が何か言ってたような気がするんですけど……」
「そうか……。ならば、これは直接話をしたほうが良いかもしれんな」
ドミナスは複雑な表情を浮かべながら、ベーナを連れて領主の館へと向かって行く。そしてこの時、ベーナは自分の中で「何か引っかかるもの」を感じていた。
(私、ご主人と聖印について、何か知っていたような気が……)
だが、それが何なのか、この時点ではまだ彼女は思い出せなかった。
4.2. 君主の資格
「領主様と二人きりで話をしたい」
ジェロームの執務室を訪れたドミナスは、彼にそう告げた。それに対して、その場にいたベーナとヴェルディは二人とも同席したいと言い出す。ドミナスは退席を命じるが、ヴェルディは退こうとしない。
「私はあなたの従者ではありません」
「そうか。だが、お主が同席するのなら、私は何も話さんぞ」
そう言われたヴェルディは、しぶしぶ部屋を後にする。
「……あとで教えて下さいね」
彼女はジェロームにそう告げるが、彼は「内容次第だな」とだけ答える。一方、ベーナに対しては、ドミナスは少し迷いつつも、そのままその場に残ることを許した。
「まぁ、どうせお前は知ってるしな」
「え?」
何のことを言われているのか分からない表情を浮かべるベーナを放っておいたまま、ドミナスは語り始める。ちなみに、この時点で、扉の外ではヴェルディが密かに聞き耳を立てていた。
「さて、領主殿、あなたは一体、何を見た?」
「私は『とある方』が聖印を使っているのを見ました」
「そうか……」
ジェロームの表情から、その「とある方」が誰なのかが既に知られていることを覚悟したドミナスは、少し間を空けて考えをまとめた上で、改めて口を開く。
「まず、一つはっきりさせておこう、マイロード。この村にいる『君主』は、あなた一人だ」
ドミナスはそう断言した上で、おもむろに話を続けた。
「君主とは、ただ聖印を使える者、というだけのことを意味する言葉ではない。聖印を使い、その力をもってこの世界を救おうとする者だけが、君主と呼ばれる資格を持つ。もし、マイロードの他に聖印を使う者がいたとしても、その志を持たない者は、君主とは言わない。少なくともエーラムは、そんな者のことを君主とは認めないだろう」
唐突に語り出した君主論であったが、ジェロームはひとまずその言い分を受け入れる。つまり、今、ジェロームの眼の前にいる「聖印を持つ者」には、「聖印を用いて世界を救おうという気がない」ということである。本人がそう言い切るのであれば、それはそうなのだろう。エーラムがどう判断するかは分からないが、一つの君主論として、間違ってはいない気もする。
「そうかもしれないな」
ジェロームは静かにそう答える。そして、ここに至って、ベーナはようやく思い出した。彼女の主人がかつて、とある(身長120cmの)暗殺者に「アントリアに尻尾を振る裏切り者」として殺されかけた時、彼が突然、聖印の力を発動させて撃退したことを。
その時、彼女は主人に「今見たことは忘れろ」と言われた。そして彼女は、本当にそのことを忘れてしまっていたのである。それがオルガノンとしての能力なのか、本能なのか、天然なのかは分からない。ただ、結果的に彼女はその主人の「言いつけ」を忠実に守っていたのである。
そんな彼女の感慨に気付く筈もないジェロームは、ひとまず彼の言い分をそのまま受け入れた上で、改めて問いかけた。
「お前はこの世界を救うつもりはないと言ったが、この村のために何かをする気はないのか?」
「この村の発展が私の蓄財に繋がる限り、私はこの村の発展に寄与するつもりでいますよ」
実際、彼はこれまでも、この村の発展に尽くしてきた。それは、村の人々を思いやる心でも、歴代領主への忠義心でもない。ただただ、自分の私腹を肥やすために、この村の経済的発展が不可欠だったが故の行動である。
「ほう、ならば俺から言うことは一つだ。お前は、お前のやりたいようにやれ。お前がこの村のためにならないと私が判断したら、その時は私がお前を止める」
それがジェロームの結論であった。少なくとも現時点においては、彼の掲げる自由主義経済論と、ドミナスの私財追求の姿勢は、矛盾なく両立出来る関係にある。もっとも、それは何か一つの契機によってバランスが崩れる可能性を孕んだ、非常に危うい協調関係ではあるのだが。
そして、その答えに満足したドミナスもまた、おもむろに返答する。
「あなたが何をどこまで把握しているのかは知りませんが、私からも一言だけ。あなたがこの村の君主にふさわしくないと『誰か』が判断した時は、その時は、その『誰か』が、あなたを始末することになるかもしれません」
この瞬間、ヴェルディが扉を開けて、矢をドミナスに向けて構える。扉の外で盗み聞きしていた契約魔法師の彼女としては(話の全容を理解していた訳ではないが)さすがに今の一言は聞き流せなかった。だが、そんな彼女とドミナスの間に今度はベーナが割って入り、「武具としての自分自身」を構える。
二人の小柄な少女が一触即発の危機を迎える中、ドミナスは眉一つ動かすことなく、淡々とジェロームに語り掛ける。
「少なくともあなたは、こうやって、身を挺してあなたのために尽くそうとする『子供』もいるし、今のところ、あなたがこの村の君主としてふさわしくないと思う者はいないでしょう。あなたに足りない者があるとすれば、しいて言えば家柄ですかな。ですが、それも『良き縁戚』を通じて、どうにかなりそうな雰囲気でもありますし」
「ふむ、家柄か」
ドミナスの言いたいことはジェロームにも分かるが、その件については、ここでこれ以上答える気もない。
「まぁ、その『何者か』がどう思っているのかは知らないが、私はあなたにそれなりに期待しているのですよ、マイロード」
いけしゃあしゃあとそう言ってのけるドミナスに対して、ヴェルディは更に殺意を募らせる。
「領主様、今すぐこいつを撃ち殺させて下さい!」
ヴェルディがそう言ったのに対して、今度はベーナがドミナスに向かって叫ぶ。
「ご主人、下がって下さい。私がこいつをぶち殺してやります!」
ベーナは、別にヴェルディ個人に対して恨みや憎しみがある訳ではない。だが、ヴェルディの尋常ならざるレベルの「殺意」に感化されて、ベーナの中の「武具」としての本能が湧き上がってきたようである。
だが、そんな二人の間にジェロームが割って入った。
「双方、落ち着け。私はこの村の、そしてこの国のためになることがしたいと考えているのだ。私は自由を望む者ではあるが、ここでお前達の自由を許すことは、この村やこの国のためにはならない以上、許す訳にはいかない」
彼がそう言うと、再びドミナスも口を開く。
「思った以上に話の分かるマイロードで安心しましたよ。そこのちっこいの、いや、ヴェルディ、だったかな。お主がパンドラを憎むというのであれば、まだもうしばらく私を泳がせておいた方が得策だぞ。おそらく今回の一件の結果として、またパンドラから『よからぬことを考える者』が私の前に現れる可能性はあるからな」
それを聞いたヴェルディは、明らかに不服そうな表情を浮かべながらも静かに弓を下ろし、ベーナも「自身」を下げる。
「そういうことなら、今は納めておいてやる。だが、お前があの連中と少しでも協力関係にあると分かったら、その時は……」
そう言って、あえてベーナを睨む。
「私は、パンドラを絶対に許さない」
ヴェルディはそう言い残して、その場を去って行く。そして、それを確認した上で、ドミナスとベーナもまた、執務室を後にするのであった。
4.3. 語られぬ真相
「結局、お前はずっと俺の言いつけを守り続けていたようだな」
紺色のスーツの男の件が解決(?)したことで、ドミナスは再び自身の屋敷へと帰還することになった。その準備の途上で、ベーナにそう語りかける。
「守れていたのかどうかは分かりませんが」
実際のところは、純粋に忘れていただけだったのだが、結果的にそれが彼の言いつけを守り続けることになっていたのは事実である。
「まぁ、ゴルフの件も悪くはなかった。惜しむらくは、2番ホールの最後で、カップに弾かれるようなパットを打てていたら、完璧だったが、まぁ、そこは私がこれから、おいおい教えていってやろう。『絶妙な外し方』というものをな」
彼はそう言いつつ、その勢いで自身の人生観について語り始める。
「この世の中、能力を持っていると知られると、ろくなことにならん。能力をひけらかしたい奴はいくらでもいる。そういう奴等同士で、勝手に争わせておけばいい」
どうやら、彼の中では、あえてゴルフを下手に見せるのも、聖印を持っていることを隠すのも、その根底にある理念は同じらしい。
「つまり、ご主人は『漁夫の利』を狙っている、と?」
「少し違うな。私は『三者で共存出来る道』があるなら、それでもいいと思っている。私は、この世界を救うことにも、『表の世界』での地位を得ることにも興味はない。私はただ、この世界を私の意のままに動かしたいだけだ」
「ご主人らしい解答ですね」
「そのために、邪魔なものをわざわざ使う必要はない。エーラムの作り出した『くだらないゲーム』に付き合う必要もないしな」
彼にとっては、皇帝聖印争奪戦という今のこの世界を動かしている基本原理自体が「くだらないゲーム」なのである。だからこそ、彼は自身の聖印の存在については、歴代領主の誰にも伝えたことはなかった。
ちなみに、先代領主ワイマールを殺したのは、あの「七匹の鴉天狗」の母親である(彼女は、パンドラの中でも特殊な「投影体の国」を作ることを目的とする「楽園派」の一員であった)。だが、彼女自身はワイマールに対して何らかの恨みがあった訳ではない。彼女を雇ってワイマールを殺害させたのは、他ならぬドミナスである。彼は、アントリアに従属することが決まった時点で、ダン・ディオードの新体制に取り入るためには、旧トランガーヌ系のワイマールを廃して、アントリア直属の新領主を招いた方が得策と考えたのである(ついでに言えば、自分の様々な「暗部」を知るワイマールを、この機会に殺しておいた方が得策だろう、という思惑もあった)。
だが、その殺害後、その鴉天狗(母)はドミナスに「口止料」としての「追加料金」を要求してきた。ここで彼女に従ったら、そのまま延々と毟り取られるだろうと判断した彼は、自らの聖印の力を駆使して、彼女を(彼女の本拠地である山林の中で、誰にも見つからないように)殺したのである。ドミナスのことを「ただの人間」と思って侮っていた鴉天狗(母)にとっては、彼がそこまでの戦闘能力の持ち主だったということは、完全に誤算であった(彼がワイマール暗殺を彼女に依頼したのは、自分の手で殺すとそれが発覚した時に厄介な事態を招くという危惧があったからであり、やろうと思えば、自分自身でワイマールを殺せる自信もあった)。
その後、パンドラの別の派閥(革命派)の「紺色のスーツの男」が、その鴉天狗の子供達が復讐しようとしていることを知り、ドミナスに対して、高額の報酬と引き換えに「鴉達の除去」への協力を申し出て来たのであるが、既にパンドラを信頼する気を無くしていたドミナスはその申し出を断り続け、最終的に「実力」でその紺色のスーツの男を追い返した結果、激怒した彼が逆に鴉天狗達と手を組んでドミナスを倒すために襲撃をかけてきた、というのが今回の一件の真相である。だが、領主が今回の件を「不問」とした今、この真実は誰にも話すつもりはない。
当然、ベーナもそんな詳しい事情まで分かる筈もない。ただ、彼女は、ドミナスの様子を見ながら、どこか不安な思いを抱いていた。彼がいずれ「人としての道」を外すのではないか、と。もしかしたらそれは、かつて自分が元いた世界で見てきた光景と、どこかでオーバーラップしていたのかもしれない。
「ご主人、『生きることから逃げるな』という言葉をご存知ですか?」
この文脈で彼女がこの言葉を持ち出すことの意味は、様々に解釈出来るが、ドミナスはひとまず、額面通りに受け止めた上で返答した。
「もちろん、逃げるつもりはない。だからこそ、君主同士のくだらない争いに巻き込まれて、早死にする必要もなかろう」
「そうですか。世の中に悲観し続けて変なことに走らなければ、私としては大丈夫でございます。それまではずっとお側にいますが、もし、あなたが人としての道を外すならば、その時は、私が迷わずその目を覚ましてあげましょう」
彼女が言うところの「人の道から外れること」の中に、今回の一件が含まれているのかどうか、ドミナスには分からない。ただ、少なくとも今のところは、彼女が自分についてくる気があるのであれば、その気が変わるまでの間、存分に利用し続ける腹積りでいた。
「分かった。では、ひとまず、次のコンペに向けて練習するか。今度は私が、ここ一番という時のための『ダフり方』を伝授してやろう」
「あ、その前に、一つお伝えというか、提案したいことが」
「ん? なんだ?」
「今回の戦いで、私、思いっきり、途中に穴を空けてしまったんですけど、そこ、『池』にしちゃいません?」
おそらく、あの「紺色のスーツの男」に、渾身の一撃を避けられた時の話であろう。確かに、そこには大きな「穴」が空いてしまっている。
「ふむ、そうだな。3番ホールには池も無かったし、ちょうどいいか。ついでに、他のホールについても、この機会に改装を考えてもいいかもしれん」
こうして、ドミナスの頭の優先事項は、さっそく次のコンペに向けての工事のスケジュール管理へと切り替わっていくのであった。
4.4. 友誼と誓い
「ごめんなさいね。やっぱり、私じゃ、この新型ドライバーは使いこなせなかったわ。結局、足を引っ張ってしまったわね」
そう言って、アストリッドは「暫定最下位」のまま終わってしまったことをクローに謝りつつ、彼に新型ドライバーを差し出す。
「多分、私がいなかったら、あなたはもっといい勝負出来てたと思うし、出来れば、もうしばらく、これを使い続けてほしいんだけど」
「ふむ、なるほど。分かった。このドライバーには、確かに可能性を感じる」
そう言って、彼はそのドライバーを受け取る。今回の事件で半壊したコースの修復にどれだけの時間がかかるかは分からないが、その時までに、休養日を利用して訓練に励もうという意欲で満ち溢れていた。
「次は、俺とドラコンやろうな。俺には今、果たさなきゃならない使命があるから、ひとまずお預けにするが、それが終わったら、実家に帰る前に、一度、ここに寄る」
「分かった。その時は、受けて立つぜ!」
そう言って、二人のレイヤードラゴンが硬く握手を交わす中、横から四人の護衛の一人である女邪紋使いが大声を上げる。
「いつまで油売ってるんだい、とっとと行くよ! だいぶ予定より遅れてるんだから」
彼女にそう言われると、ラスティは苦笑いしながら彼女について行く。大盾を持った護衛の男が深々と頭を下げるその横で、ロディアスは「じゃあ、兄さんにもよろしくね」と言って手を振る。こうして、アストリッド商隊の面々は、ウリクルの村を後にするのであった。
4.5. 幼魔法師の素顔
一方、「暫定トップタイ」のままコンペを強制終了させられたカルディナもまた、明らかに消化不良で不満気な様子であった。
「まったく、お前がちゃんと事前に鴉共を退治してくれていれば、あのまま最後まで楽しめたのにな」
「……それどころではないです」
口先を尖らせて、むすっとした表情で、ヴェルディはそう答える。
「ん? どうした? また何か嫌なことでもあったか?」
そう言われたヴェルディは、むくれた顔のまま、むぎゅー、とカルディナに抱きつく。「本当ならば殺さなければならない相手」を目の前にして、結局、彼の思惑通りに「生かして泳がせる」という選択を取らざるを得なくなったことに納得出来ず、かといって、それ以外の選択肢を見つけることも出来なかった自分に対して、苛立ちを覚えていたのである。
とはいえ、そんな愚痴を師匠にまでこぼすのは、彼女のプライドが許さない。だが、そんな彼女の態度から、師匠はその心境を概ね察したようである。
「そうかそうか、まぁ、お前も色々と疲れただろう。じゃあ、これから私と一緒にビルトに行くか? 一度、温泉にでも浸かって、ゆっくりするのもいいだろう。ゲルハルトも、お前のことは心配してたしな」
カルディナはこの後、競馬の村として有名なポーターに行く予定なのだが、その途中で一度(つい先日も行ったばかりなのだが)、温泉村であるビルトを経由することになる。まだエストの温泉宿の修復は完全には終わっていないだろうが、それでも通常の女湯自体は問題なく使える筈である。
ちなみに、ヴェルディの兄弟子にあたる現地の契約魔法師ゲルハルトが彼女のことを心配しているというのは、彼女が咄嗟に思いついた方便である。実際に心配しているかどうかは分からない。ただ、「ゲルハルトはロリコン」という(本人にしてみれば名誉毀損レベルの)思い込みを抱いてしまっているカルディナとしては「きっと心配しているに決まっている」と決めつけてしまっていたとしても、おかしくはない。
「……領主様にお許しをもらってきます」
そう言って、ヴェルディはトボトボとカルディナの客室を出ていった。その様子を、カルディナは暖かい目で見守る。彼女としては、ヴェルディが珍しく「年相応の姿」を見せてくれたことが、少し嬉しかったようである。
ちなみに、カルディナは自分の弟子達が(形式的には「養子」扱いなのだが)自分のことを「お母様」と呼ぶのを許さない。ただ、ヴェルディだけは(年齢的に妥当な歳ではあるので)そう呼ばれても良いかな、と密かに思っている。だが、おそらく今後も、彼女の方からそう呼ぶことはないだろう。
4.6. 姫の想い
「もうすっかり、立派な領主様になっちゃったのね」
ジェロームの私室にてティーカップを片手に持ちながら、マリベルはしみじみとそう語る。領主令嬢として温室で育てられた(時折、そこから抜け出していた)自分とは異なり、ジェロームは一人の騎士として戦功を勝ち取り、領主となり、そして領主としても着実にその任をこなしていることが、マリベルとしては羨ましく、妬ましく、そして頼もしくもあった。
「まだ、なかなか手の届かないことも多いんだがな」
そう語るジェロームに対して、マリベルは突然、またしても不可解な提案を掲げる。
「じゃあ、この村にもう一人『君主』がいた方が、あなたの助けになる?」
マリベルが、ドミナスの一件について知っている筈はない。つまり、彼の件とは無関係に、彼女は「誰か」がこの村に来てジェロームを手助けする、という選択肢を提示したのである。ジェロームがその意味を理解するためには一瞬の「間」が必要であったが、彼は淡々と答えた。
「そうですね……、いや、この状態で私はなんとかしてみせますよ」
この状況は二人きりであるにも関わらず、いつの間にか「敬語」になっている。もしかしたらそれは、彼の中での「防衛本能」なのかもしれない。少なくとも、今、「私情」にまかせて不用意な返答をすることは、あまり望ましくはないだろう。
「そっか。でもまぁ、どうしても人出が足りなくなったら、言って。多分、あなたのためならいつでも駆けつける、あなたと同年代の君主が、少なくとも一人はいるから」
「とはいえ、その君主様はきっと、その君主様の仕事があるでしょうし、私は自分のやるべきことは、出来る限り自分でやりたいと思っています。無論、私としては、その君主様の自由を止める気もありませんが」
本気で踏み込もうとするマリベルに対して、ジェロームはあくまで敬語口調の「公的な立場」を崩さぬまま、「煮え切らない返事」で返す。おそらくこの二人は、過去にも何度か、このようなやりとりを繰り返してきたのであろう。ジェロームがどこまで「マリベルの気持ち」に気付いているのかは分からないし、マリベルもまた、「ジェロームの本音」を計りかねている。そんな微妙な関係の、16歳の二人であった。
そして、このタイミングで、部屋の扉を叩く音が聞こえた。ジェロームが入室を許可すると、そこにいたのは、むくれた様子のヴェルディである。
「りょうしゅさま……」
「ん? どうした?」
「すこし、『おやすみ』をいただきたいのですが……」
「そうか。まぁ、ここ最近、色々と忙しかったしな。いいぞ、ゆっくり休め」
実際のところ、まだこの後の事後処理の段階でヴェルディの力が必要になることもあるかもしれないが、彼女の方から休暇を願い出ることなど、今まで一度もなかったため、よほど疲弊しているのだろう、と察したようである。
だが、彼女としても、契約魔法師としての責任感はある。そして、パンドラへの復讐心も、今まで以上に熱く燃え上がっていた。
「何かあったら、すぐ呼んでください。すぐに戻って来ますから!」
先刻までの少し気の抜けた口調から一変し、微妙に強い語気で彼女はそう語る。
「まぁ、何かあることなんて、そうそうないだろうけどな」
「だといいですね」
そう言って、ヴェルディが部屋から出て行こうとすると、マリベルが「ふと思いついた本音」を口にする。
「あの子、きっと美人になるわよね……。その前に…………、『5年』かな。5年以内に結論を出した方がいいかもしれないわね、『その君主』は」
この時点でヴェルディは11歳。マリベルとジェロームは16歳である。
「5年か、5年の間に、私はどこまで成長出来るんだろうな」
最後まで、そう言ってはぐらかすジェロームに対して、マリベルは軽くため息をつきながら、笑顔でその場を去ろうとする。
「じゃあ、改修工事が終わったら、また来るから」
しかし、彼女がそう言って部屋を出ていこうとした瞬間、一度は外に出ようとしていたヴェルディが、領主の背中に寄っていって、ピタッとくっつく。
「どうした? 疲れたか?」
ジェロームにそう問われたヴェルディは、それに対しては何も答えぬまま、マリベルの方に向かって(ジェロームからは見えない角度で)、満面の「女の笑顔」を見せた。
「……『5年』は長いかな。『3年以内』にケリをつけなきゃいけないかもしれないわね」
マリベルは密かにそう呟きつつ、11歳の少女に向かって静かな「大人気ない闘志」を燃やしながら、領主の館を後にするのであった。
最終更新:2015年08月29日 11:31