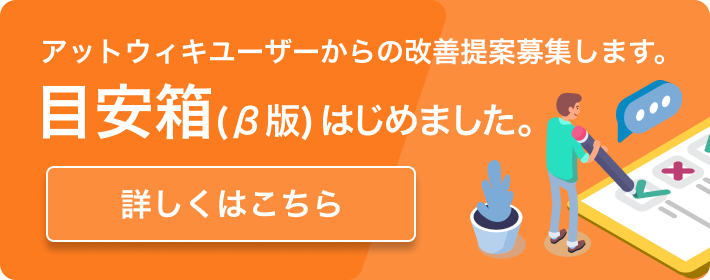『資本論』再入門
─規範的読解
Seibun Satow
Dec. 20, 08
「はじめに行いありき。だから、かれらは、考えるまえにすでに行っていたのである」。
カール・マルクス『資本論』
第1章 甦る『資本論』
2004年5月、突然、レフ・トルストイの『アンナ・カレーニナ』が全米でベストセラー化する。オプラ・ウィンフリーが自分の番組でその長編小説を紹介したからである。この出来事は時代を超えた文豪の作品の力と言うよりも、かのTVパーソナリティの影響力を世間に印象づけることになる。このアフロ・アメリカンの司会者は、08年大統領選挙の民主党候補として、バラク・オバマを支持し、彼がヒラリー・クリントンとのレースに勝った一因とされている。
けれども、今、欧州最大の経済国で起きているある大著のちょっとしたブームには、そういったマスメディアの影響は見られない。ドイツにおいて、2008年11月12日付『しんぶん赤旗』(電子版)によると、カール・マルクスの『資本論』が流行し、この10月から、31大学で『資本論』講座が開設され、10月31日付週刊誌『シュピーゲル』(電子版)はそれを「小さな10月革命」と呼んでいる。講座を組織しているのは、連邦議会で54議席を有する左翼党の学生組織である。かつては頻繁に論じられたマルクスだが、東西冷戦終結以降、大学での講義は激減している。同組織は、昨年、「マルクス新発見」プロジェクトを立ち上げ、各地で専門家の援助を受けながら、この10月から自主的に講座を始め、全国で約2000人の学生が参加している。
左翼党は、ドイツの連邦・地方議会で議席を持つ最左派の政党である。2005年5月、ゲルハルト・シュレーダー首相の新自由主義経済の路線に反発したオスカー・ラフォンテーヌ元財相ら「社会民主党(SPD)」の最左派が一斉に離党し、「労働と社会的公正のための選挙オルタナティブ(WASG)」を結成する。同年7月には、旧東ドイツのドイツ社会主義統一党の流れを汲む「民主社会党(PDS)」は「左翼党―民主社会党(Die Linkspartei.PDS)」に改称している。2007年6月、両党が合併し、「左翼党(Die Lonke)」が誕生する。
『資本論』は、デイヴィッド・リカードゥを批判的に受け継ぎながら、古典派経済学者が市場経済に基づく資本主義を自由であり、なおかつ秩序立てられているとするのに対し、その歴史性を明らかにしている。これがメイン・テーマである。2008年10月16日付週刊紙『ツァイト』(電子版)は「資本主義がどのように機能しているか、貧富の差がなぜ大きくなっているのか知りたいと思う人が増えている」と主催者の言葉を紹介し、「主流となっているいわゆる新自由主義は席を譲ろうとはしないだろう」としながらも、ブレーメン大学の政治学者が「マルクスが大学講座に復活するのは十分可能だ」と言っていると伝えている。また、10月31日付『タッツ』紙(電子版)は、ベルリン・フンボルト大学の受講者が「金融危機は資本主義のシステム的な誤りがあることを印象づけている」や「資本論は今日、以前よりずっと現代的になっている」と意見を述べたと報道している。ただ、この若い読者たちは、正直、『資本論』読解には相当苦心している。さらに、11月16日付『朝日新聞』は『資本論』を刊行しているベルリンの出版社に販売状況を取材している。2006年、同社の『資本論』の発行部数は約750冊だったが、今年は10月までにこの全3巻1万ページに及ぶ大著が2500冊以上が売れ、金融危機が起きた10月だけで550冊が出荷され、来年4月を目処に印刷していた残り2000冊も底をつくのも時間の問題だと見通している。しかも、各種言語版を含めてネット上で無料公開されている事情も考慮すれば、驚異的な数字である。
以上を要約すると、左翼党の学生組織がフィリップス社の創業者ジェラルド・フィリップスの叔父の再検討を促すプロジェクトを進めていたときに、金融危機が発生し、それが追い風となって『資本論』が復活したということになる。
これは、フョードル・ドストエフスキーの19世紀ロシアを舞台にした小説が現代にも共通するところがあるというようなよくある古典のリバイバルではない。孫が乱暴な運転をしているのを見かける度に、小言を言う老人がいる。でも、若者は「うっせーなー、年寄りは引っこんでな。クルマの運転もしたこともねえくせに」と聞く耳を持たない。運転マナーの悪化はどんどんエスカレートしていき、「オレだけは大丈夫だ」と飲酒運転さえも常態化してしまう。しかし、ある日、とうとう大事故を起こしてしまう。そのとき、「じいさんの言う通りだった。話を聞いときゃよかった」と祖父のことを思い出す。まるでこんな具合だ。
工場制度の巨大な突発的拡張可能性と、その世界市場への依存性とは、必然的に、熱病的な生産とそれに続く市場の過充とを生みだし、市場が収縮すれば麻痺状態があらわれる。産業の生活は、中位の活況、好況、過剰生産、不況という一連の諸時間に転化する。
(『資本論』第1巻第4篇)
しかし、先の世界恐慌の際に、新たな経済政策として国際的に権威を持ったのはケインズ主義であり、マルクス主義ではない。今回の金融危機には、ケインズ主義を批判して勢力を伸ばしたマネタリスト流の経済理論の招いた帰結という批判も少なくない。現状を乗り越えるためであるなら、ジョン・メイナード・ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』を再検討する方が筋は通る。実際、宇沢弘文と間宮陽介は、『世界』2009年1月号で、「いま、ケインズを読む意味」という議論を展開している。
もっとも、不況で生き抜く経済活動はどういうものかを知ろうとするなら、長寿企業にその知恵を聞いた方がいい。日本に創業200年以上の長寿企業が多いことはよく言われるが、アメリカにも4社ほどある。そこまでではないものの、キャンベル・スープ・カンパニーは創業130年であり、その間28回の不況を生き残ってきている。今回で29回目であるが、切り抜けることはまず間違いない。長寿企業は、概して、「本業に専念しろ」や「目先の利益にとらわれるな」という至極当然の内容の家訓社訓を守っている。経営に王道はないというわけだ。
激しい競争は、しばしば、原点を見失わせる。激烈化する競争の状態で、ライバルを蹴落として、生き残ることに躍起になり、往々にして勝者になること自体が目的化してしまう。しかし、その間に、そもそも自分たちが消費者やユーザーから選ばれてきた原点を忘れてしまう。そうなると、その産業・分野の弱体化が進み、何らかの危機の後、原点回帰の動きが求められる。これは経済活動だけでなく、政党や教育機関の間でも見られる傾向である。
アラン・グリーンスパン前FRB議長は、2008年10月23日、米下院の公聴会において、現在の金融危機を「一世紀に一度の信用津波(a once-in-a century credit tsunami)」と言い表し、その深刻さを多くの政治家や経営者たちもすぐに理解する。
イギリス政府は、同年11月24日、200億ポンドに及ぶ景気対策を発表する。第二次世界大戦に費やしたイギリスの戦費の総額が、現在の価値に換算すると、9000億ポンドであるから、戦争並みの事態に直面していることがわかる。また、米政府から約1500億ドルの支援を受けたアメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)は、11月25日、エドワード・リディCEOの今年と来年の年間報酬を1ドルとするなど役員報酬の制限策を表明する。退職金を支払う予定は今のところない。
まるでスプラッシュ・マウンテンに乗っているように、一気に景気が落下していく実感があるが、9・15、いわゆるリーマン・ショック以前から、欧米ではサブプライム・ローン問題の表面化に伴う金融機関の経営不振が起きている。ドイツにおいても、2007年7月、ドイツ産業銀行(IKB)が政府系金融機関(KfW)によって救済され、翌年の1月、ザクセンLBが州立銀行最大手バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行(LBBW)によって救済買収されている。最大手のドイツ銀行を始めとして多くの金融機関も巨額な損失を計上し、経営規模の縮小や海外市場からの撤退などを余儀なくされている。
全米経済研究所(NBER)は、2008年12月1日、2007年12月から雇用と実質所得が減少に転じたことを重視し、アメリカが大幅な「景気後退期」を迎えていたと発表している。2001年11月から続いた景気拡大期は6年1ヶ月で終わり、以降、幅広い経済活動がマイナス成長になる後退期が一年近く続く戦後3番目の長期に亘っている。エコノミストの間では、73年から75年と81年から82年に記録した戦後最長の16ヶ月を越え、29年8から33年3月まで続いた大恐慌期の43ヶ月以来の長期に及ぶのではないかという見方も出ている。
歴史上、何度かバブル経済と呼んでいいような現象が起きている。2008年11月20日付『朝日新聞』の「経済気象台」によると、バブル経済は、80年代後半の日本の経験を踏まえるならば、地価と株価が3倍を目指して急騰する現象である。1986年頃から株価と地価の上昇が始まり、88年と89年は激しく急騰する。株価は、89年末、4年前の約3倍の3万8915円に達し、また、地価も86年から急上昇し、91年にほぼ3倍になっている。いずれも3倍に到達した後、反落していく。合衆国における今回のバブルでも、株価は、95年から07年までの間に3倍を超え、住宅価格は、97年から06年で、3倍に達している。
これを引き起こすのが、いわゆる金あまりである。企業と家計の負債残高の名目GDPに対する比率がその指標となる。日本で、85年度に264%が89年度には5319%と50ポイントも上がり、アメリカにおいても、97年からの10年間でこれまた50ポイント以上増えている。金融機関の負債残高の名目GDPに対する比率も急上昇している。バブル経済を防止するには、企業や家計、金融機関の負債残高の対名目GDP比率が急上昇していないかを監視・牽制する必要がある。合衆国の金融当局は、今回、不十分な対策しかとってこなかったと言わざるをえない。
ドイツは、世界的な不況にあっても、景気後退が確認されているものの、悪化の程度が比較的軽くすんでいる。独連邦統計局は、11月13日、08年7~9月期の実質GDPの速報値を発表している。それによると、前期比0.5%減で、4~6月期の0.4%減に続き2四半期連続のマイナス成長であり、これは03年前半以来の景気後退である。金融危機の深刻化と世界的な景気低迷によって、輸出が落ち込み、英国や米国などと比べて、個人消費はわずかにプラスであるが、低調であることは確かである。相対的に他の欧州諸国よりも消費の力がまだあるため、ドイツが抜け駆けもできないし、また国政選挙が控えているせいもあろうが、アンゲラ・メルケル首相も付加価値税の減税には消極的態度を示している。けれども、経済は、国際的に、さまざまな面で関連している。ドイツだけこの世界的な景気後退を免れることはありえない。しかも、ドイツを含めたEU内の多くの諸国でユーロという共通通貨を用いているのに、統一した財政政策を打ち出せる組織体や金融機関を監督する中央集権的な機関もない。ユーロ圏内で、金融・財政政策や規制が一体としてとれない現状がある。この統一性の脆弱さのために、今後もがユーロ安が進みかねない懸念がある。新車の販売が急激に落ち込んでいるのを始めとして、ドイツ政府は、来年以降も当分の間、厳しい経済状況が続くと予測しており、これまでは軽かった雇用情勢の悪化につながる危険性がある。
自動車産業は裾野が広いため、各種のニュースでしばしば解説されている通り、その影響は多くの連鎖をもたらす。リチャード・ワゴナーGM会長兼CEOは、11月18日、米上院銀行住宅都市委員会の公聴会において、国内自動車メーカー1社が経営破綻した場合に初年度で300万人が失業し、個人所得は1500億ドル減少、政府は3年間で合計1560億ドルの税収を失うと証言している。GMの全従業員数が25万2000人、フォードが22万4000人、クライスラーが6万3000人であるから、トータル53万9000人、1社平均18万人弱となる。経営破綻ともなれば、ビッグ3の従業員1人に関連して16人以上が道連れになる計算である。しかも、一社の破綻の悪影響はその傘下だけにとどまらない。12月16日、デトロイトで開催されたフォードのイベントにおいて、アラン・ムラーリー社長は、GM救済は部品調達網の維持などの点でフォードにとっても不可欠であるとの見解を表明している。先の試算がどこまで他国にも適用できるかは定かではないけれども、自動車産業の不振は、それだけ国や地域経済に及ぼす影響は大きいことは確かである。
2008年、日本で、小林多喜二の『蟹工船』がブームとなっているが、これには世界的金融危機とは直接的な関係はない。ネット上で無料で閲覧できるこの古典が、今なぜ売れているのかとメディアで話題になっている。2008年1月9日付『毎日新聞』に掲載された高橋源一郎と雨宮処凛の対談の中で、紹介されたのが元々の発端である。彼らは、現代日本でのワーキングプアに陥っている若者たちの状況が『蟹工船』の世界に通じていると指摘する。今日の非正社員者は、『蟹工船』で描かれる劣悪な労働環境下に置かれた労働者にシンパシーを覚え、たちまち流行爆発が起き、「2008ユーキャン新語・流行語大賞」においてそのタイトルが入賞している。さらに、『蟹工船』は彼らに闘うことを指南する。真っ先に人員整理の対象となった非正社員たちは立ち上がり、組合を組織したり、街頭でデモをしたり、裁判所に解雇無効の仮処分申請を行ったりするなど泣き寝入りはしない姿勢を見せている。この新たな労働運動は「『蟹工船』効果」と呼ぶことができるかもしれない。
『蟹工船』どころか、今や、派遣切りが横行する日本では、ジョージ・オーウェルの『動物農場』が流行するかもしれなくなっている。スターリン体制のそれを諷刺したこの小説は1954年にイギリスでアニメ映画化され、2008年12月20日、それが初公開される。働けなくなったら殺される作品内の動物たちが、雇用の調整弁扱いされる非正社員と重なって見える。ヘンリー・フォードは、自社の労働者もその消費者であるとして、T型フォードを開発・販売し、従業員に買えるだけの賃金を支払い、モータリゼーションの最初の基礎をつくったが、今日の経営者たちにはその認識を忘れてしまっているようだ。
しかし、ドイツでの『資本論』ブームはかのプロレタリア文学の復活のケースとは異なっている。先に言及したように、10月段階でのドイツの景気は、他の欧米諸国と比べて、落ちこみが緩かである。また、この新しい読者は大学生や大学院生などが中心であり、ワーキングプアではない。『資本論』は、多岐に亘る問題についての複雑で難解な記述に覆われた理論的な著作である。印象的ないくつかのフレーズや労働者階級の置かれた悲惨な境遇の告発を別にすれば、読者が自分の体験と重ね合わせて情緒的に共感・感動することは少ない。日々報道されるニュースに振り回されるのではなく、資本主義の本質を知りたいという動機からそのページを開いているのだろう。
彼らは60年代のような読み方はしていない。学生運動が隆盛を極めた当時は東西冷戦下であり、『資本論』も既存左翼組織や新左翼運動の中で読まれている。それは、時として、教条主義的だったり、恣意的だったりしている。マルクスにかぶれることは、大人になる通過儀礼とさえ見なされてもいる。一方、今の読者は、ベルリンの壁をよく覚えていない、もしくは1989年11月9日以後に生まれた若者たちであり、『資本論』に対して無知であると同時に無垢である。よく知らない反面、先入観もない。『パルプ・フィクション』を見て初めてジョン・トラボルタを初体験したようなものだ。今時のあっさりと読めてしまう作品に物足りず、重厚な古典に向かってみようという知的スノビズムもないまま、同時代的な作品として読んでいる。それは、ある意味、読解の原点とも言える。
第2章 マルクスを読む
古典は、リバイバルすると、それが「今、なぜ」受容されているのかとジャーナリズムの好奇心を刺戟する。『資本論』は、マスメディアの反応を見るなら、明らかにクラシックである。古典は、その前提となっている社会や時代が過ぎ去り、それに関する読解や研究が蓄積された作品を指す。古典の読解は、こうした共通認識を前提にしているため、敷居が高くなりがちである。一見さんお断りというわけだ。思いつきや思いこみだけでその作品に関する自分の意見を表明することは、ものを知らない自惚れ屋と冷笑されかねない。
『資本論』を蘇えらせる企ては、歴史的に見て、大きく二つに分類できる。一つは『資本論』の分析の方法論を他領域に援用するアナロジー型、もう一つは新しい思想潮流によって『資本論』を再解釈するモード型である。吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』は前者、ルイ・アルチュセールの『資本論を読む』は後者に属するだろう。
流行した作品は、そのブームが過ぎ去ると、急速に古びていく。それをめぐる言説も活気を失い、閉塞状況に陥る。そこで、新しいアプローチを用いて潜在的可能性を見出し、従前の言説を活性化させる試みがとられる。しかし、それらは往々にして急進的であるため、一般にまで普及することは少ない。
マルクスはたんなる経済学者ではない。『資本論』の経済思想と直接的には関係のない他領域の著作──政治学や歴史学、社会学、文学理論、文化人類学、言語学など──が数多く出版されている。中には、アントニオ・ネグリのように、そこに資本主義分析と革命思想のすべてがあるとして、『経済学批判要綱』を『資本論』以上に評価し、『マルクスを超えるマルクス』を公表する思想家さえいる。むしろ、経済学以外の領域での『資本論』のアップデートが目立つほどだ。
マルクスに影響を受けた経済学者は、ルドルフ・ヒルファディングやローザ・ルクセンブルクのようなマルクス主義経済学者からラディスラゥス・フォン・ボルトケヴィチやヨゼフ・アロイス・シュンペーターなど非マルクス主義経済学者まで広範囲に亘る。その経済学の分野でのマルクスに対する意欲的な刷新が始まるのは、ケインズ登場以降である。その画期的な試みの一つはジョーン・ロビンソンによる『マルクス経済学』だろう。これは第一版が1942年、第二版が1966年に出版されている。彼女は、マルクスを初期ケインズ主義者、すなわちケインズに先立つケインズ主義者として位置づけている。
しかし、マルクスからケインズ主義を考えたのはこの彼女が初めてではない。彼女は、ケインズ主義の影響力に陰りが見え始めた1980年代、ポスト・ケイジアン経済学を提唱しているが、そこで参考としたのが、マルクス読解を通じてケインズを超えるケインズ主義を導き出したミハウ・カレツキである。
世界恐慌からの脱却におけるケインズの果たした役割はしばしば神話化されている。しかし、いざその1936年に刊行された『雇用・利子および貨幣の一般理論』に目を通すと、政策提言らしきものはほんのわずかであることに拍子抜けする。『一般理論』はあくまでも理論的著作、より正確に言えば、従来の経済学に対する批判書であって、こうすれば経済がよくなる道筋を記した処方箋ではない。『資本論』からマルクス主義が形成されたわけではないのと同様、『一般理論』からケインズ主義が必ずしも生まれたわけではない。
一般的にケインズ主義と見なされている学説──失業問題の対策として、赤字予算に陥ってでも、公共事業や貨幣供給量を拡大すべきだという意見──を主張する経済学者は、ケインズ以前にも少なくない。その一人がポーランド出身の経済学者ミハウ・カレツキである。彼はケインズが『一般理論』を発表する3年前に、有効需要の原理を始めとするケインズ体系の基本的考えの多くを公にしている。のみならず、ケインズを超えて、不完全競争にそれらを導入することさえ試みている。しかも、彼はこの理論をケインズとは無関係に、マルクスの著作の研究から考案している。ロビンソンがマルクスを初期ケインズ主義者と系譜を書きえるのも、この経緯を知るなら、当然だろう。
カレツキの影響は、ロビンソンの他、ニコラス・カルドアやリチャード・グッドウィン、森嶋通夫などにも及んでいる。けれども、カレツキは、当時、二つの理由からケインズのような名声を手にすることができない。
第一に、彼はこの画期的理論をポーランド語で出版している。残念ながら、ポーランド語と経済学を同時に理解できる人は、世界的に見て、少数にとどまる。実際、彼の名前がポーランドの外でも知られるようになったのは、英訳や仏訳が出版されてからである。しかし、そのときにはもうケインズ主義が広まった後だったため、その奇妙でわかりにくいエピゴーネンと見なされただけである。
第二に、彼の叙述は難解である。複雑な代数式で表現されていたり、一つのモデルについて諸条件を変えた四つないし五つのヴァージョンを提示したりしている。これは、確かに、科学的態度である。IPCCによる温室効果ガスの排出シナリオが示している通り、科学では条件が変更されれば、結論も異なるものだ。けれども、読者にとってこの科学的姿勢はじれったく、ただ一つの結論を明確に提示してもらいたい。カレツキの場合は、擁護者も批判者も、彼のヴァージョンの中から自分に都合のいいのを取り出して自説を展開するため、議論も深まらず、時として、不毛に終わってしまう。
カレツキと比べて、ケインズの手法はシンプルである。マーク・ブローグは、『ケインズ以前の100大経済学者』の中で、それを三つに要約している。「ケインズの新しい点といえば、まず第一に、ほとんどもっぱら集計的、マクロ経済的変数だけを用い、経済全体を商品、債権、労働の市場にまとめる傾向であり、第二には短期分析だけに集中して、先行者の主要分析の焦点であった長期分析は片隅に閉じ込めていく傾向であり、第三には経済状態を変化させるものに対する調整の比重全体を、価格よりもむしろ産出量と所得にかける傾向であった」。
このケインズ主義のブームが過ぎ去ったとき、ロビンソンなどポスト・ケイジアンによってそれを甦らせる試みとしてマルクス=カレツキが呼び出される。しかし、マネタリズムの勢いをとめることはできない。東西冷戦の終結と共に、『資本論』を読んでからマルクス主義者になった者はいないとさえ言われているにもかかわらず、マルクスの威光も消えていく。新自由主義経済が何らかの問題を引き起こすと、度々、マスメディアの見出しに「マルクス」が踊ることはあっても、資本主義批判の象徴として用いられているにすぎない。
ケインズ主義とマネタリズムの興亡の間にも、マルクス派・非マルクス派を問わず、『資本論』に記された経済学上のアイデアが本当に妥当であるかが激しく議論されている。「搾取の証明」はその代表である。この命題は、価値と価格の一致や価値による価格の規定、労働価値を生産の価格に転形する転形問題などさまざまな派生的な論争を巻き起こしたが、そのほとんどが誤りだと今では判明している。数少ない成果は、置塩信雄が1950年代に発見し、森嶋通夫が1960年代に世界的に知らしめた「マルクスの基本定理(Marxian Fundamental Theorem) 」である。これは本来数式が用いられているのだが、要点は次のようになる。すべての産業で利潤が出ている経済を仮定する。労働者は賃金によって商品を購入するが、その純生産にはある労働時間が必要である。ところが、その賃金を得るために働いた労働時間は、それより短くなってしまう。これがマルクスの経済学から理論的に導き出される「搾取」であるとすれば、「搾取の証明」は不可能だということになる。
資本家階級と労働者階級の間で階級闘争が起こり、資本主義体制が終焉を迎え、社会主義体制が過渡的に生まれた後に共産主義体制が成立する。このよく知られたマルクスの未来予測が的中しないことは、歴史を蜜までもなく、明らかである。労働者階級は資本主義の発達と共に増加していく。資本主義はかつてないほどの経済成長を可能にする。それ以前では年2%もすれば、驚異的な伸びである。前年より増えた利益をどのように分配するかが両階級の関心事である。これは絶対利得であり、ノンゼロサム状況であるため、闘争は激化しにくい。先進国では、階級闘争を通じたプロレタリア革命は勃発しないと言ってよい。
他方、労働者階級が未発達で、小作農の比率が大きい地域では、状況を改革するために、革命に至る蓋然性がある。小作農は地主に搾取されていると感じ、農地解放を政府に要求する。しかし、地主階級の政治的・経済的影響力により、それは進まない。土地の所有権は、近代においては、一元的である。その争奪はゼロサム状況、すなわち相対利得に基づいている。誰かが得をすれば、誰かが損をする。土地を持つものと持たざるものとの間の闘争は激化しやすく、暴力的衝突から内戦・革命へ向かうことが予測される。闘争や戦争はノンゼロサム状況ではなく、ゼロサム状況から生じる。その辺の見極めがマルクスは悪かったと言わざるを得ない。
言うまでもなく、東西冷戦終結後もマルクスは読まれ続け、論じられ、ポスト・マルクス主義も登場している。マルクス=レーニン主義から解放され、自由にマルクスが読めるという気運さえ生まれている。『資本論』はその影響力が大きかったために、従来から権威主義的な見解を解体する、あるいはテキストを断片化するという戦略を理論家たちがとらざるをえなかったことは否定できない。アントニオ・グラムシは、ロシア革命を「資本論に反する革命」と呼んでいる。しかし、何しろジャン=フランソワ・リオタールに終わったと言われた当の「大きな物語」であり、低迷期に入っていたのは明白である。こういった時期にこそ冒険的な考察が登場するものだが、アントニオ・ネグリ=マイケル・ハートなどを別にすれば、多くは知的シーンを幾分活性化するだけで終わる。そのダブルスにしても『資本論』を甦らせるまでには至らない。
この時期、日本ではマンガ家の青木雄二が『資本論』の復権を行っている。それはポスト・マルクス主義ではなく、教条主義的なマルクス主義理解である。彼は、マンガや講演を通じて、一般大衆に向けてその古臭い思想を新鮮味溢れるように伝える。新自由主義経済が伸張する中、一定範囲ながら、『資本論』を思い出させることに成功している。この青木雄二の試みは、標準的な読みの力強さを再認識させ、新しい読みによって知的シーンを活性化する時代の終りを告げている。
経済学では、マルクス経済学を複雑系やカオスなど非線形科学と関連させて読み直す試みも始まる。『資本論』の経済学は均衡経済学ではない。現代経済学の主流である新古典派は、限界革命以降の均衡を前提としている。「均衡(Equilibrium)」は、自然科学の用語の「平衡」のことである。力学的平衡や化学平衡として用いられるが、時間が経過しても、ある系内で配置や性質が変化しない状態である。熱力学において、外界との質量的相互作用、すなわち構成粒子と共にエネルギー交換を行わない「閉じた系(Closed System)」を呼ぶ。そこで温度の異なる二つの容器を接触させておくと、両者が同じ温度に落ち着き、熱平衡状態にヤッする。ただ、化学反応などでは平衡状態にある系のミクロ的な活動は、そのマクロな性質を一定に保とうとする。全体を見れば平衡であるが、部分的には非平衡だというわけだ。一方、閉じた系ではない「開いた系(Open System)」において、平衡状態には至らないのに、自己組織化と呼ばれる現象が立ち現われ、安定化することがある。人間の身体は外界の変化にさらされているが、体温はほぼ一定している。身体は開かれた系であり、「非平衡(Non equilibrium)」でありながら、「自己組織化(Self-organized)」されている。こうした非線形によって『資本論』を読む試みは極めて魅惑的であるが、それを経済学に導入するには、数理モデルが不可欠である。コンピュータ・シミュレーションを可能にするコンピュータ・プログラム、すなわちアルゴリズムの考案が必須である。しかし、非線形の研究自体が発展途上であるため、将来に期待するというのが現状である。現段階では、非線形経済学は現代経済学の完成度とは比較にならない。とは言うものの、今回の急速な世界規模のリセッションは、初期値敏感性を持つカオスの数理モデルを用いて、今後分析され、その監視は高まっていくだろう。
非線形の存在は、19世紀末、三体問題を通じてジュール・アンリ・ポアンカレが口火を切って以降、ヨハン・フォン・ノイマンなど数多くの自然科学者がそれに言及していくものの、あくまでマイナーな扱いである。1883年に没したマルクスがそんな非常識な科学を知るよしもない。非線形の研究が本格化したのは、1960年代に従前の学問体系が行きづまり、学際的な研究にその活路が見出され、安価で性能のいいコンピュータが普及した後のことである。
経済学も自然科学の手法を部分的に採用している。現代の科学は非線形現象を扱うため、どちらが原因でどちらが結果なのか判断しかねることも少なくない。それを科学の限界として、非科学的思考に活路を見出すことは極めて短絡的である。デフレと不況の関係において、90年代、日銀や政府、経済学者の間で、意見が割れている。リフレ派は長期不況の原因がデフレと見なす。それに対し、日銀派はデフレを長期不況の結果と考えている。両者共に長期不況とデフレが起きていることは認めるが、その原因と結果に関する認識はまるで正反対である。それを議論することは経済学の発展に寄与する点では歓迎すべきものである。しかし、社会は現実の政策を必要としている。科学では、こうした堂々巡りに陥った場合、「予防舷側」に則り、いずれの説が正しくても対応できるような措置をとる。政府や日銀には予防原則に基づいた政策施行が望まれるが、中途半端に終わりかねない。結局のところ、非線形を踏まえるならば、多角的に考えてやりくりするほかない。
今回の『資本論』の復活は、特定政党の組織が関与しているとは言え、地道な草の根レベルの活動を抜きには語られない。従来の知的シーン先導の「資本論を読む」とは、間違いなく、異なっている。ブームと言いながらも、マルクスはもう過大に期待されてはいない。バブルはとうにはじけている。プラトンやアリストテレスのように、巨大ではあるが、等身大に見られている。
バブル経済には、経済学的分類ではないけれども、二種類ある。一つは資産バブル、もう一つはイノベーション・バブルである。いずれのバブルでも、崩壊後、パニックと景気後退がおとづれる点では共通している。多くの人が金を失い、企業倒産が相次ぐ。しかし、遺産継承という点で両者には違いがある。
資産バブルは、主に、不動産や外国為替、証券への投機として発生する。金余りから都市部やリゾートの土地が買い漁られ、金融市場に金が流れこむ。住宅や土地の価格の上昇を見越して、業者や個人が金を借り、濡れ手で粟とばかりに、さらに株や不動産に投資する。はじけた後は差し押さえられた物件、買い手のつかない空き地、紙くず同然の証券が残される。経済や社会に与えるダメージは大きく、牽引できるだけの新たなイノベーションが見つからない場合は、立ち直るまでに、10年かかると見た方がよい。
他方、イノベーション・バブルは新たな産業・技術革新に対する過剰投資から生じる。大半の企業がいずれ消えていくことは推測できるが、それがどこで一体いつなのかまではわからない。将来的に必要なインフラであることは間違いない。いつかは整備されるだろう。けれども、バブルが始まれば、短期間で膨大な資金が集まるため、その速度は飛躍的短くなる。破綻しても、一握りの企業が残り、それをインフラとして社会に浸透させる。これは、ある意味で、ヨゼフ・アロイス・シュンペーターの言う「創造的破壊」である。黄金時代とはそれは定着して、意識されなくなったしまった状態を指す。運河や鉄道、自動車、ICTなどイノベーション・バブルの遺産である。インフラは絶頂期にではなく、一時的な流行が去った後に、衰退期に浸透する。
宗教のばあいでも、芸術のばあいでも、思想のばあいでもそうであるが、それらのものが地下深く真に根をおろすのは、運動の興隆期ではなく、かえって、衰退期であって、プロレタリア文学運動もまた、その例外ではないということは、いま、ここで、あらためてことわるまでもあるまい。それが、どうしてもそうおもえないようなものは、運動の興隆期には、極左的言辞を弄し、形勢不利とみるや否や、いちはやく口をぬぐって、保身の術を講じたような連中だけだ。
(花田清輝『プロレタリア文学批判をめぐって』〉
『資本論』が復活したのはドイツだけではない。2008年12月、日本のイーストプレス社から「まんがで読破」シリーズの一冊として『資本論』が刊行されている。青木雄二の企てを超えるものではないけれども、この現象に驚いたロシアのテレビ局RTRが早速それを報道している。原著ではなく、マンガという点で、読者層は『蟹工船』と重なっているかもしれない。
たしかに、われわれは皆『資本論』を読んできたし、いまも読んでいる。もうすぐ百年にもなろうという年月に、われわれの歴史のドラマと夢のなかで、論争と対立のなかで、いまもわれわれの唯一の希望にして運命である労働運動の挫折と勝利のなかで、われわれは毎日、誠実に『資本論』を読んできた。われわれが「この世に生まれて」このかたずっと、上手下手はともかくわれわれのために『資本論』を読んでくれた人びとの著作や言説をたよりにして、われわれは『資本論』を読み続けている。その種の人びとは、時代遅れのものもいれば、まだ生き続けているものもいるが、エンゲルス、カウツキー、プレハーノフ、レーニン、ローザ・ルクセンブルク、トロツキー、スターリン、グラムシ、労働者組織の指導者たち、彼らの味方と敵─哲学者、経済学者、政治家罫線などがそうである。
(ルイ・アルチュセール『資本論を読む』)
第3章 規範的読解
こうした新しい読者に必要なのは先進的ではなく、標準的なあるいは規範的な解釈である。しかし、それは『資本論』の経済学の現代的意義、すなわち『資本論』から見た現代ではない。現代経済学によって再構築された『資本論』の経済学、すなわち現代から見た『詩本論』の経済学である。なるほど、『資本論』に関する詳細な註解書も、国内外を問わず、数多く刊行されている。しかし、汎用性の低いマルクス主義用語に覆われた解説書やいわゆるわかりやすい『資本論』入門は、その意義は認めるとしても、お呼びではない。
前知識がないまま、『資本論』を読んだ場合、初歩的な誤読が起こる危険性が十分ありうる。まず、『資本論』の概念には、現代経済学の用語と異なっていることも少なくない。『資本論』では、文脈によって、「流通」が「市場」という意味で使われている。また、『資本論』には、今日から見直すと誤りであったり、見当外れの予想だったり、解けない問題であったりする記述がしばしば見受けられる。先に言及した「搾取の証明」がその一例である。しかも、日本には、マルクス経済学の豊かな伝統があり、それは多くの示唆にみちている。蓄積されてきたマルクスの経済学的に関する研究を踏まえていないと、マルクスを救済しようと強引に読んだり、こじつけたりする護教論に終始してしまいかねない。経済学の専門家や研究者たちは現代経済学のリテラシーを共通認識として持ち、そうした経済学的思考に基づいて『資本論』を読解する。『資本論』を読むには現代経済学のリテラシーを身につけておかなければ、その落とし穴に陥ってしまう危うさがある。
1980年代から本一般化した思想潮流であるポストモダニズムは体系化ではなく、断片化を志向している。規範を解体することに新たな可能性を見出していたと言えなくもない。その後、インターネットが普及し、そうした思想的作業が現実にも現われてくる。体系の基礎である規範的知識がないまま、膨大な情報の集積の中から我流で理解してしまう人も少なくない。イスラム過激派が全体との整合性を無視して、自分に都合よく『コーラン』の一節を切りとっているように、そうした者は本質的・総合的な認識を欠いた議論に陥る。ネットは、多くの人々に、それ以前には困難だった情報・知識へのアクセスを容易にしたものの、そこから本質を洞察する力を教えてはくれない。
加えて、9・15以降の経済混乱に伴い、今までは経済をさほど気にもとめなかった人たちも人事ではないと慌てて関心を持ち始めたものの、「ダウ平均」といった基礎的な知識さえないために、何がなんだかさっぱりわからない。加えて、変化がめまぐるしく、経済に詳しくても、「証券化」がどのように行われるかの概要を知らない人も結構いる。体系的・総合的知識がないと、マスメディアやインターネット上で伝えられるニュース・意見をわかった気になってしまう。経済学に関するリテラシーが決定的に不足している。経済学をめぐって語る場合、専門家同士を別にすれば、今やリテラシーから語らねばならない。
ところが、ドイツの現状が示す通り、経済学者の間でも『資本論』離れが進んでいる。読まなくなったのは、何も、一般読者だけではない。今回の復活劇によって専門家が再び『資本論』に向かっているほどだ。
こうした状況では、初心者と専門家をつなぐ読解が必要である。経済学的な核心や理論的な要点を俯瞰的見地から知的に論じた『資本論』再入門が求められる。それはどちらの立場からも読めるテキストである。
しばしばテレビの政治や経済をめぐるトーク・ショーで、「マクロ」や「ミクロ」という用語が説明のないまま、使われている。これは、確かに、経済学に通じているものには常識的概念である。しかし、実は、それが選択肢の秩序の形態を意味する点を理解して言及している司会者やコメンテーターは必ずしも多くない。
経済学はその対象と分析方法から「ミクロ経済学(Microeconomics)」と「マクロ経済学(Macroeconomics)」に二分される。一般的に、新古典派は前者、ケインズ派は後者と見なされている。現在の経済政策の大半は直観的に実施されているわけではなく、ミクロかマクロいずれかの経済学理論を論拠としている。また、財政学のように、それらとは無関係に発展してきた学問も、その現代経済学によって再構成されている。こうした現状から、ミクロ経済学ならびにマクロ経済学の規範的な理論を学んでおくことは重要である。
ミクロ経済学は、消費者の家計と企業などの個別経済主体の行動を基礎として、市場における生産物・生産要素等の価格決定のメカニズムを分析する。そのため、「価格理論」とも呼ばれる。
他方、マクロ経済学は国民経済や地域経済を対象として、その経済の総体的な経済活動を分析する。一国の経済を分析し、国民所得がいかなる水準で決定し、どのように変化するかを明らかにするため、「国民所得理論」とも呼ばれる。
ミクロ経済学では、経済活動はすべて「選択」だということになる。選択肢は、そのため、序列化される。一方、マクロ経済学では、状況に応じて選択肢の中からどれにするか「判断」をすることは重要となる。選択肢は、当然、併列化される。いずれにせよ、複数の選択肢を用意する必要があると現代経済学は教えてくれる。経済をめぐって無条件にただ一つの道しかないと迫る意見には警戒せねばならない。/span>
専門家にしても、誰もがかつては初心者であり、リテラシーを意識して経済学を習得するが、そのうち、それが無意識化してくる。しかし、他者と向き合う際には、再度リテラシーを意識化しなえればならない。ネイティヴ・スピーカーは自分の言語のリテラシーをあまり意識せず、使っている。それを外国語として考えるとき、リテラシーは顕在化してくる。リテラシーは他者にしか意識されない。他者とコミュニケーションする際、リテラシーは不可欠である。
人は損はしたくないし、できれば、得をしたい。そこで、経済活動では、その後に望ましくない結果になってしまうとしても、そのときなりの人は合理的に考え、行動する。経済学は、稀少性のある諸々の経済的資源を効率的かつ公正に管理することを考える学問である。稀少性は相対的であるため、さっきまで高かった資源が、あっという間に低くなってしまうことはよくある。好況期には、企業は人手をかき集め、不況になれば、解雇する。さらに、現代経済学では、均衡を念頭に置きつつ、市場機構のメカニズムについて理論的に検討し、実際の動きによって生じるさまざまな問題を考察する。市場のお仕組みから問題を考えるのが現代経済学の認識である。
経済活動における市場の重要さに関する認知は、かつてより一般の間にも浸透している。石油の価格は、第二次世界大戦後、メジャー、すなわち需要側が決めていたが、第一次オイル・ショックさ示している通り、OPEC、すなわち供給側にその決定権が移っている。しかし、現在ではさらに事情が変わっている。2008年上半期に原油価格が急騰し続けたのは、需給のバランスではなく、思惑にゆれる市場の動向が主な理由である。
しかし、市場は、何も、証券や外国為替、先物の取引の場だけを指すわけではない。具体的な例として失業問題を現代経済学的に考えてみよう。
前近代的な農村社会では、失業問題は原則的に存在しない。農業において、失業があるとすれば、賃労働者を雇用するプランテーションだけであって、自作制でも、地主制でも、労働者と失業者という区別がない。自作制の場合、一家総出で働いた方が収穫量が増加して、家計も助かる。定率小作制では、収穫量が多いほど自分の収入が増えるため、小作人の家族や親類縁者が参加することも歓迎する。また、定額小作性では、払う額が決まっている以上、父親が働こうが、息子が来ようが地主には興味がない。失業は賃労働を前提とする産業社会の到来と共に顕在化した問題である。
現代経済学によれば、発生させる直接的なきっかけにかかわらず、労働力の価格である貨幣賃金が下がらず、労働市場の需給の調整作用が十分に機能できないため、労働力の超過供給が瞬時に解消しない状態が失業である。上がりすぎた貨幣賃金が速やかに下落しないのは、市場外的要因にある。労働組合の圧力、最低賃金制や失業保険など法的・制度的規制、雇用主や労働者の非合理的な判断・行動、経営陣の市場環境の変化を見誤った見通しなど市場以外に原因がある。
主流である古典派経済学によれば、賃金・物価が伸縮的であるならば、労働市場において雇用均衡が成立し、完全雇用が実現される。その際に、せいぜい労働者個人の事情による失業──自発的失業や摩擦的失業──が残るだけである。一方、新古典派と対立すると見られているケインズ派は賃金の伸縮を否定する。そのため、労働市場での需給の均衡は成立しないのであり、完全雇用は実現しない。しかし、賃金・物価の硬直性が市場メカニズムを阻害するのだから、失業が解消されないという考えであり、新古典派とそれほど隔たっているわけではない。両者の違いは賃金・物価が伸縮的であるか硬直的であるかの点だけであって、いずれも市場メカニズムの均衡は認めている。
オランダで実施されているワーク・シェアリングも、暗黙の契約理論に伴う賃金の硬直性の問題から編み出された試みである。暗黙の契約理論とは、正式の労働契約はないけれども、長年の慣習から、企業と従業員の間で暗黙の了解があり、賃金が硬直的に規制されている状態である。高止まりした賃金を下げられないのであれば、不況期に、レイオフしない代わりに、一人一人の労働時間を短縮させ、仕事を労働者全体で分け合うほうがよい。一人当たりの労働時間は減るが、賃金率は下がらない。レイオフしないために、好況期になった際の新規採用に伴う技能の習得期間の必要もない。
参考までに、ケインズ自身は、労働市場の賃金の伸縮性ではなく、生産物に対する需要、すなわち有効需要が完全雇用実現のポイントだと考えている。有効需要が不足しているために、資本設備の稼働率が低下して、失業が生まれてしまう。賃金・物価が伸縮的であったとしても、有効需要不足があれば、非自発的失業が存在するとケインズは指摘する。
ところが、『資本論』の経済学では、有効需要不足が解決されても、非自発的失業が存在すると分析する。マルクスの相対的過剰人口論によれば、失業は資本主義的蓄積に伴う不可避的な事態である。労働力は資本自身によって供給できない商品であるため、その価格が高くなっていっても、供給はそれに追いつかない。労働力が相対的に不足したまま、蓄積が続けば、労賃はさらに上昇する。これを抑制するのが失業である。
(略)労働の価格上昇の結果、利得の刺激が鈍くなるので、蓄積が衰える。蓄積は減少する。しかし、その減少につれて、その減少の原因もなくなる。すなわち資本と搾取されうる労働力とのあいだの不均衡もなくなる。したがって資本主義的生産過程のしくみは、自分が一時的につくりだす障害を、自ら取り除く。労働の価格は、ふたたび資本の増殖欲に適合する水準まで下がる。
(『資本論』第1巻第7篇)
このマルクスの記述は労働市場における需給の均衡を前提としていない。非平衡でありながら、一定の秩序を持った自己組織化として捉えているとも読める。『資本論』が非線形によって読み直す可能性があるというのはこうした点である。現代経済学で見たときに、こういった可能性が顕在化する。市場がオープン・システムであるとすれば、将来的には、均衡ではなく、自己組織化など非線形の体系に基づいて経済学も再構築されていくに違いない。その意味で、マルクスをそういった視座から読むのは極めて示唆的であろう。
古典の規範は社会・時代の変化にさらされ、研究・実践が加えられながらも、ある一定秩序を保ち、自己組織化している。規範的読解は、無知で無垢なヴァーチャル・リーダーに対して、その領域のリテラシーを意識しつつ、標準的な認識、すなわち思想のコアを示すことである。テキストをあくまで等身大として読む。規範を共通認識とすることで、その古典は持続的に読まれている。そういった持続可能な読解はどんな急進的な読解以上に根源的である。先進的な読解が花盛りの状況は、表面的には、豊かに見えても、一般的な読者が離れているため、土壌が痩せており、長続きしない。すたれてきたのを挽回しようと、さらに過激さに走ると、負のスパイラルに陥ってしまう。激しい変化が常態化している現代社会では、これ見よがしの新奇さには辟易する。新しさはいずれ飽きがくる。定着したものは飽きられない。定着した作品は受け継がれ、つねに同時代的に読まれる。規範は、初心者だろうと、熟練者だろうと、共通の基盤となる。規範という共通理解に意識的に立脚し、再入門を繰り返す。規範的読解は読みにおける正の連鎖をもたらすだろう。
かつて『資本論』が社会に影響を与えてきたが、今は社会も『資本論』を変えている。『資本論』と社会は双方向の関係にある。
だから、さあ、『資本論』を読め!
たとえわれわれがマルクスの基本的な考え方や、中心になる結論のすべてではないがその多くを却下するとしても、『資本論』全三巻は、そしてとくに前二巻は、分席上すぐれた項目を数多く含んでおり、近代経済学者はそこから依然として多くを学びとることができよう。たとえば、大企業の成長、所有権と経営権の分離、資本主義下での労働者の訓練方法に関する失業の機能的役割、景気循環過程での貨幣資金変化の意義、固有の周期をもつ景気循環、技術進歩が利潤率に及ぼす効果、技術進歩の資本節約的性質など、このリストは無限に拡大されうる。単純ではあるが、近代成長理論でさえ、そのなかにみいだすことができるのである。マルクスは、依然として読む価値がある。
(マーク・グローブ『ケインズ以前の100大経済学者』)
〈了〉
参考文献
カール・マルクス、『資本論』全9巻、岡崎次郎訳、国民文庫、1972~75年
カール・マルクス、『資本論(まんがで読破)』、イーストプレス社、2008年
合原一幸、『カオス学入門』、放送大学教育振興会、2001年
伊藤誠、『「資本論」を読む』、講談社学術文庫、2006年
岩井克人、『ヴェニスの商人と資本論』、ちくま学芸文庫、1992年
祝い克人、『貨幣論』、ちくま学芸文庫、1998年
宇野弘蔵、『資本論の経済学』、岩波新書、1969年
片桐薫編、『グラムシセレクション』、平凡社ライブラリー、2001年
柄谷行人、『マルクスその可能性の中心』、講談社学術文庫、1990年
高木保興、『開発経済学』、放送大学教育振興会、2005年
都甲潔他、『自己組織化とは何か』、講談社ブルーバックス、1999年
鍋島直樹、『ケインズとカレツキ』、名古屋大学出版会、2001年
新井田宏、『経済学入門』、放送大学教育振興会、2000年
新井田宏、『現代経済学』、放送大学教育振興会、2001年
丹羽敏雄他、『数理モデルとカオス』、放送大学教育振興会、2005年
野村進、『千年、働いてきました』、角川one文庫、2006年
花田清輝、『ザ・清輝 花田清輝全一冊』、第三書館、1986年
森嶋通夫、『マルクスの経済学』、高須賀義博訳、東洋経済新報社、1974年
吉本隆明、『言語にとって美とはなにか』1・2、角川ソフィア文庫、2001年
ルイ・アルチュセール他、『資本論を読む』全3巻、今村仁司訳、ちくま学芸文庫、1996~97年
マーク・グローブ、『ケインズ以前の100大経済学者』、中矢敏博訳、同文館、1989年
マーク・グローブ、『ケインズ以後の100大経済学者』、中矢敏博訳、同文館、1994年
ジョン・メイナード・ケインズ、『雇用・利子および貨幣の一般理論』、塩野谷祐一、東洋経済新報社、1995年
アントニオ・ネグリ、『マルクスを超えるマルクス』、清水和巳他訳、作品社、2003年
ジョーン・ロビンソン、『マルクス経済学』、戸田武雄他訳、有斐閣、1955年
ジョーン・ロビンソン、『マルクス主義経済学の検討 マルクス・マーシャル・ケインズ』、
都留重人他訳、紀伊国屋書店、1956年
『AERA Mookマルクスがわかる。』、朝日新聞社、1999年
『世界』2009年1月号、岩波書店、2009年
DVD『エンカルタ総合大百科2008』、マイクロソフト社、2008年
しんぶん赤旗
東洋経済web
ABC.com
asahi.com
BBC NEWS
NIKKEI NET
Reuter
Вести.Ru