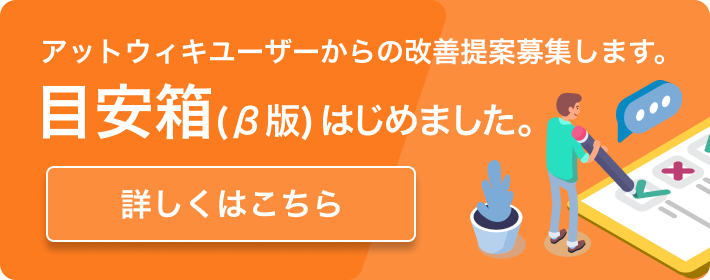映画と間接性
Seibun Satow
Oct, 7. 2010
「誰にも見えないところまで見ろ、そして、それが誰にも見えるようになるまで見ろ」。
ギー・ド・モーパッサン
映画が抽象的な問題や具体的であっても時空間を限定できない問題を扱うのは難しい。言語が一般性・抽象性を言い表わせるのに対し、映像は物質の表面を写し撮るだけであり、個別性・具体性しかとり扱えない。映像で「ペン」と表わすには、どれか具体的なペンを映さなければならないが、大量生産品であろうと、それは他ならぬ個別的なものである。また、「愛」は物質ではないので、直接映し出すことは不可能である。言語がプラトン的イデアだとすれば、映像はアリストテレス的形相であるとも言える。
映画は、名作になるかは別にして、ウッドストックという出来事を撮るのにさほど困難を伴わない。それを一定の時間・空間によって制限することが可能であり、視点をどこに持っていくかが監督の関心事である。
他方、映画にとって、死刑をテーマにすることは難しい。死刑を続けている地域は世界的に限られている。しかし、時間的には際限がない。死刑制度は刑罰論の範疇に入り、今日に至るまでさまざまな議論の蓄積がある。ある事件を撮っても、死刑制度全般をつかんだことにはならない。スナップ・ショットにとどまる。それがブラックウェルダー事件であったとしても、同様である。
フロリダ州刑務所に仮釈放なしの終身刑で服役していた49歳のジョン・リチャード・ブラックウェルダー(John Richard Blackwekder)は、一生刑務所に閉じこめられているのは耐えられないとして死刑判決を得るために、39歳の他の服役囚を絞殺する。2004年5月26日、彼は、望み通り、処刑される。執行前日、メディアのインタビューに対して、「殺した相手には謝罪するが,こんな人生は終わりにしたかった」と応えている。
この事件は死刑と終身刑のどちらが残虐かつ重いのかを再検討する契機にはなるとしても、死刑制度全般を捉えているわけではない。これは映像の限界に起因する。具体的な問題を抽象化すると、それを汎用的に考えることが可能になる。ところが、映像の場合、この抽象化が苦手である。個別的・具体的な問題に寄り添うのは得意であるが、汎用性が求められる場面では全体像を把握する妨げになることがある。
けれども、抽象的な問題や時空間の制限ができない問題を扱うのがまったく不可能というわけでもない。むしろ、それこそが映画表現者の力量が試される領域である。
黒澤明監督の『天国と地獄』(1963)は子どもを対象とした営利誘拐をとり扱っている。監督は、この映画の制作に際して、当時の誘拐罪に対する刑罰が未成年者略取誘拐罪で3ヶ月以上5年以下の懲役〈刑法第224条〉、営利略取誘拐罪で1年以上10年以下の懲役〈刑法第225条〉)と軽く、また親族以外の場合には適用されない規定に憤っていたと伝えられている。この傑作は1964年刑法一部改正のきっかけになっている。
なお、子どもを対象とした営利誘拐は、20世紀に入って、初めて登場した犯罪である。その最初が1932年に起きたリンドバーグ愛児誘拐事件である。未成年者略取身代金目的誘拐を絞殺することは20世紀の一側面を浮き彫りにするのにつながる。
下手な映画監督は、法律の穴を直接的に扱ってしまう。先に述べた通り、映像の限界から全体像を捉えられないため、言葉に頼ることになり、説教がましくなる。ところが、『天国と地獄』では、偶然の展開から法律の問題点が明らかになり、しかも娯楽性の強いミステリー仕立てであるため、それが前面に押し出されていない。
日本で『黒い雨』というのあったね。えらい違いだね。『黒い雨』は初めから原爆の場面がパーッとワンシーン、出てきた。次は雨が降ってきた。あー。初めから分かってる。『黒い雨』で、そんなタイトルが出たら、初めから原爆の雨だ、分かっちゃうね。怖さが、あんまりに鮮やかに下手だね。
というわけで、そういうのがあったけど、まあ、面白かったな。『生きものの記録』、良かったね。
(淀川長治『淀川長治の映画塾』)
さらに、形而上学的問題を扱った成功作もある。それがM・ナイト・シャマラン監督の『ヴィレッジ(The Village)』(2004)である。これは社会契約論とプラトンの洞窟の比喩を描いている。
舞台は1897年のペンシルヴァニア州である。そこの深い森に囲まれた人口約60人の小さな村で、人々は自給自足・相互扶助の生活を営んでいる。ただし、村人は森の外に出てはいけないという掟を義務付けられている。鍛冶職人のルシアス・ハントは外の世界への好奇心を日々募らせていた。彼は、村の指導者エドワード・ウォーカーの娘で、盲目のアイヴィーと交際している。幼なじみのノア・パーシーは、精神の不調に陥り、いつも村と森の境界をさまよい歩く。しかし、彼はアイヴィーを愛しており、ルシアスを憎んでいる。
アイヴィーの姉キティの結婚式の前日、ノアの手に不吉な色とされる赤い花が握られていたことから事態が急変する。血なまぐさい出来事が続き、ノアがルシアスを刺してしまう。アイヴィーは恋人を救う医薬品を手に入れるため、禁断の森を抜け、町に出る決心をする。外の出た彼女の前に広がっているのは。21世紀の社会である。目の見えないアイヴィーにはそれが何なのかを理解できない。村は現代社会での生活に傷ついた人々が同意の上で国立公園内に建設した共同体である。アイヴィーは薬を手に入れ、再び森に入るが、ノアが現われ、彼女に襲いかかる、しかし、ノアは転落して死に、アイヴィーはルシアスが待つ死に帰る。これがあらすじである。
この村人たちは社会契約を結んでいる。彼らは万人の万人に対する闘争状態の中で傷ついた人たちである。それを抜け出すために、現代社会から離れ、社会契約をしてこの村を建設している。ただし、その契約は次の世代に相続されていない。世代間継承がどうありうるのかが社会契約論の課題の一つだと指摘できる。
また、アイヴィーは、プアトンの『国家』第7巻における洞窟の比喩も体現している。地下の洞窟に住む囚人がいる。彼らは、子どもの頃から手足も首も縛られ、ずっと洞窟の奥を見ているだけで、振り返ることもできない。入口のはるか上方に火が燃えていて、その後から照らしている。火と人々の間に道があり、それに沿って低い壁がある。その火によって人間や生物、道具などの影が壁に映り、音や声も聞こえる。実像を見たことがないけれども、世界はそういうものだと信じこんでいる。ある時、誰かがそこから脱出し、外界を見聞きした後で、洞窟に戻り、その様子をみんなに話す。しかし、鎖から解放されても、誰もそれを信じず、秩序を乱す嘘つきとして、逆に彼を殺してしまう。しかし、抜け出たものが盲目であったとしたら、このプラトンの比喩は成り立たない。
しかも、この映画にはさらに細工がされている。今、映画館でスクリーンを見ている観客はまさに洞窟の中の囚人と同じ状況にある。中には、隣に座る友人や恋人、家族にこう感想を漏らすものもいるだろう。「無理な設定だよ。こんなの現実と違う。所詮、映画だ」。映画が終われば、観客たちは外へ出て行く。しかし、彼らはいつかまた映画館の中に入り、作り物だと承知の上で、光源を背中にスクリーンに映る映像を見つめる。
なお。プラトンのこの著作のタイトルは、厳密には国の制度の意味なので、『国制』の方がふさわしい。英語を始めとする多くの翻訳では『共和国』と訳されているが、明治時代において天皇制の国家への批判と受けとめられかねず、『国家』と訳出されている。
このように形而上学的問題を扱いながらも、『ヴィレッジ』には難解さは感じられない。サスペンス仕立てにすることで、社会契約論や洞窟の比喩がトリック・アートの如く隠れている。人によってはそれに気がつかないかもしれない。問題意識と複雑な構造を認知できるかどうかは鑑賞者の識見に任されている。映画は部分しか映せないが、巧みな工夫によって、想像力が全体像を把握するように働く。
間接性をうまく用いることで、映画の可能性はさらに広がっていく。黒澤明監督は映画の可能性を拡充した重要な一人であることを否定する人はいないだろう。元プロ野球選手の豊田泰光は、最も素晴らしい日本の野球映画として、監督の『野良犬』(1949)を挙げている。後楽園球場のシーンがどんな野球を描いた映画よりもその魅力を伝えている。実は、『野良犬』は間接性の中で監督が創作した作品である。それによって監督がシナリオと映画を再認識し、その可能性を広げている。黒澤明を成長させたのはこの狂気の作業だと言って過言ではない。
そのため、私は、この映画のシナリオを、先ず小説態で書いた。
私は、ジョルジュ・シメノンが好きだったから、シメノン風に社会犯罪小説を書いた。
それには、四十日ほどかかったが、それをシナリオに直すには、せいぜい十日間もあれば済むと思ったら、とんでもない事で、いきなりシナリオを書くよりも四苦八苦して、なんと五十日以上かかってしまった。
よく考えれば当然の話で、小説とシナリオはまったく別のものなのだ。特に、小説では自由な心理描写も、シナリオでナレーション無しに、描写するとなると、実に不自由千万なのだ。
しかし、一度小説体に書いたばっかりに、思いもかけぬ苦心をしたこの作業のおかげで、私はシナリオと映画というものを再認識すると同時に、小説の独特の表現形式の中から映画に取り入れたものも少なくない。
〈黒澤明『蝦蟇の油』〉
〈了〉
参照文献
大越義久、『刑罰論序説』、有斐閣、2008年
黒澤明、『蝦蟇の油』、岩波書店、1984年
淀川長治、『淀川長治の映画塾』、講談社文庫、1995年
プラトン、『国家』下、藤沢令夫訳、岩波文庫、1979年
DVD『単語区と地獄』、監督黒澤明、東宝、2003年
DVD『ヴィレッジ』、貫禄M・ナイト・シャマラン、ポニーキャニオン、2010年