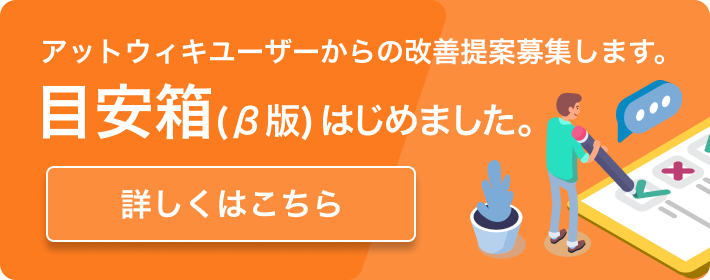転向
─中野重治の『村の家』
Seibun Satow
31.Oct,1992
「しばしば勇気の試練は死ぬことではなく、生きることだ」。
ヴィトリオ・アルフィエリ『オレスト』
1 吉本隆明の転向論
カール・マルクスの『経済学・哲学草稿』が発見され、日本では五・一五事件が起こり、ドイツではナチス政権が誕生する前年でもある一九三二年(昭和七年)、日本の警察は一九二七年にコミンテルンが天皇制打倒を第一目標として要求したマルクス主義者たちへの取り締まりをこれまでにないほど強化し始める。この取り締まりは、実は、もともとマルクス主義運動そのものの撲滅を目的としたものではなく、一九三一年に始まった満州事変とそれに続いて一九三七年に必然的に引き起こされることとなる日中戦争のための国内安定を目的とした後方支援の色彩が強い。その年の三月から四月にかけて、主要な関係者たちは一斉に検挙・逮捕される。日本が国際連盟から脱退した翌年の一九三三年、小林多喜二が、警察の取り調べ中、拷問によって虐殺され、同年、獄中にあった日本共産党幹部佐野学・鍋山貞観の二人が『共同被告同志に告ぐる書』と題された共産主義運動から転向するという声明を発表する。それをきっかけとして、佐野や鍋山に続き、数多くのマルクス主義政治活動家、文学者たちが転向を公表し始める。
この転向は、日本近代文学史において、重要な主題の一つであると言っていいだろう。転向をめぐってすでに多くの論考がなされているが、その中で最も代表的かつ規範的な考察の一つとして、吉本隆明の『転向論』(一九五八)があげられる。
吉本隆明は、『転向論』において、日本における転向を次のように定義している。
わたしの欲求からは、転向とはなにを意味するかは、明瞭である。それは、日本の近代社会の構造を、総体のヴィジョンとしてつかまえそこなったために、インテリゲンチャの間におこった思考転換をさしている。したがって、日本の社会の劣悪な条件に対する思想的な妥協、屈服、屈折のほかに、優性遺伝の総体である伝統に対する思想的無関心と屈服は、もちろん転向問題のたいせつな核心の一つとなってくる。
習慣的な意味で、転向というとき、共産主義者が、共産主義をすてて、主義に無関心となることや、すすんで他の主義に転ずることをさしており、もっと狭義には、共産党員が組織から離脱して、組織無関心になることを意味している。このような転向の定義は、昭和八年、佐野学、鍋山貞親が「共同被告同志に告ぐる書」を公表して、政治思想上の転換を声明したとき使用され、それにつづくマルクス主義政治運動家、文学者の錯綜した屈服と屈折に対して慣用されてきた。しかし、これらの転向は、けっして別種のものではなく、転向のなかの特殊な一つのケースにすぎない。ただ、日本の社会構造をつかまえることが必須の課題である革命的な自己意識のあいだにおこり、しかも、長期間の投獄か、死か、という権力からの強制によって自己意識の変換を迫られたため、日本的転向の特長が、このケースにもっとも鋭い形で、象徴的に集中せざるをえなかったのである。転向論が、ここを中心に展開されたのは当然だが、転向のカテゴリーをここに限定することは、それほど意味があるとは、おもわれない。わたしのかんがえでは、「非転向」的な転向も、「無関心」的な転向もありうるのだ。
(略)わたしは弾圧と転向とは区別しなければならないとおもうし、内発的な意志がなければ、どのような見解をもつくりあげることはできない、とかんがえるから、佐野、鍋山の声明書発表の外的条件と、そこにもりこまれた見解とは、区別しうるものだ、という見地をとりたい。また、日本的転向の外的条件のうち、権力の強制、圧迫というものが、とびぬけて大きな要因であったとは、かんがえない。むしろ、大衆からの孤立(感)が最大の条件であったとするのが、わたしの転向論のアクシスである。生きて生虜の恥ずかしめをうけず、という思想が徹底してたたきこまれた軍国主義下では、名もない庶民もまた、敵虜となるよりも死を択ぶという行動を原則としえたのは、(あるいは捕虜を恥辱としたのは)、連帯認識があるとき人間がいかに強くなりえ、孤立感にさらされたとき、いかにつまずきやすいかを証しているのだ。
吉本は、転向と「権力の強制、圧迫」による弾圧を区別し、転向の日本における特徴を「大衆からの孤立(感)」の視点から明らかにしようとしている。吉本の考察はその前年に発表された本多秋五の『転向文学論』を踏まえている。本多秋五は、従来、共産党からの離反を転向と定義してきたのに対して、転向を、吉本の説明によれば、「輸入思想の日本国土化の過程に生じる軋り」であると見なす。一方、吉本の『転向論』のモチーフは、転向を本多のような倫理的基準からではなく、社会的構造とその認識の側から扱うことにある。人間は意志的に善も悪もなし得ないのであって、善や悪とされているのは「関係の絶対性」(吉本隆明『マチウ書試論』)によって規定された相対的なものにすぎず、意志的な行為と考えているものはまったく責任と呼べるものではない以上、道徳的基準によって転向を論ずることは意義深いものではない。吉本は、そうした認識から、転向を「日本の近代社会の構造を、総体のヴィジョンとしてつかまえそこなったために、インテリゲンチャの間におこった思考転換」と定義する。吉本はこれまでの素朴な転向=非転向という二項対立によって解釈されてきたこの問題に新たな視点を提示する。吉本は、今までの転向をめぐる論議は氷山の一角を見ていたにすぎないとして、現実認識に関する自己批判としてとらえ、「『非転向』的な転向も、『無関心』的な転向もありうる」、と告げる。世界的にも、アルベール・カミュのように、マルクス主義から他の政治思想への転向もあれば、逆に、ジャン=ポール・サルトルように、他の政治思想からマルクス主義への転向もあり、両者共に弾圧されていたわけではない以上、転向と弾圧は明確にわけられている。ただし、「マインド・コントロール」が一般的に知られることになった現在では、あのような状況下では転向声明は同情すべきことだったと推測しなければならない。従って、弾圧は転向のきっかけとなったかもしれないが、転向は弾圧とは明確に区別されなければならない。
日本の転向を論ずる場合に、ある前提を考慮しなければなるまい。日本の転向の特徴を語る際に忘れてはならないことは、理論的な指導者たちから亡命者をほとんど出さなかった点である。亡命を視野に入れず、鶴見俊輔のように、転向をただ「権力の強制、圧迫」の問題としてしまうのは不十分である。と言うのも、日本の転向は、実は、マルクス主義を放棄するか否かが必ずしも問われることではなく、非合法組織(共産党)を通じた政治活動から身を引くことを意味しているにすぎない。例えば、蔵原惟人は、政治活動から身をひき、合法的な範囲で著述活動をするが、マルクス主義は放棄しないとして下獄している──彼は政治活動を続けるか否かに基準にすればそれは転向であり、マルクス主義を放棄するか否かを基準にすればそれは非転向であるわけで、蔵原は転向でも非転向であり得る(マルクス主義者であることと共産党などの非合法組織に属していることが同じ意味として一部で考えられていたことが、転向と弾圧が混乱されてしまった理由の一つであろう)。日本の地理的事情や日本語の置かれている世界的な位置も考慮しなければならないだろうが、アメリカ・メキシコ・カナダの共産党結成に協力した片山潜らもいたにもかかわらず、日本の理論的マルクス主義者からは、モスクワ詣ではかなり行われていたし、知的影響をまったく残さなかった野坂参三らはアメリカに亡命しているものの、亡命といった行動は実行されず、主張すらされない。
しかし、マルクス主義にとって、亡命することは必ずしも致命的な問題ではない。例えば、カール・マルクスも亡命者であり、ウラジーミル・レーニンやレオン・トロツキーも西欧諸国に亡命している。彼ら自身は転向するよりも、むしろ、亡命を選ぶ。彼らは亡命をして、それぞれ自己批判をし、理論をさらに展開している。マルクスの『資本論』や『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』といった著作は亡命下において書かれたものである。マルクスが初期から後期へと転回するには、当時資本主義が最も発達していたイギリスへの亡命が不可欠である。その亡命が彼の転回を強いている。初期マルクスは後期マルクスによって、その後期マルクスも大英博物館で執筆された『資本論』によって発見されたものだ。マルクスは、実は、イギリスどころか、経済的に許されれば、アメリカへの亡命すら考えている。ところが、日本においては、知的に優れた理論的マルクス主義者からはほとんど亡命者を出すことなく、転向者を大量に出している。
このような事態を引き起こした理由の一つとして、当時の日本のマルクス主義者の組織が一様に弱体であった点があげられる。日本のマルクス主義組織は亡命して新たに組織の立て直しをできるほどの強度を持ち合わせていない。実際、警察の取り締まりは(認定されてしまえばいかなる弁解も聞き入られることがなく、火炙りにされてしまう)魔女狩りと言うよりも、むしろ、(それを放棄すると宣言すれば許されてしまう)ガリレオ・ガリレイの宗教裁判に近い──ピーター・ゲイが『自由の科学』で明かにしているように、直観だけで宇宙の無限説を唱えそれに殉死したジョルダーノ・ブルーノの場合、自説を支えるものがほぼ自らの信念だけであったためそれを撤回するか否かは根源的な問題であったのに対して、天文学的データによって裏打ちして地動説を主張したガリレオ・ガリレイの場合、彼が自説を撤回するか否かはまったく問題ではないのであって、あの裁判は「それでも、それ(=地球)は動く」という伝説を残すためだけにあるようなものである。マルクス主義が宗教的だと言われる所以はここにもあり、こうしたことのために、マルクス主義は、帰納法や演繹法、背理法などの思考・認識パターンが必ず前提にしている「反証可能性」を与えていないから、科学ではないとカール・ポパーに言われてしまう。組織が弱かったために、別に撲滅を目的としていなかったにもかかわらず、国家権力による取り締まりによって、日本のマルクス主義政治団体は崩壊してしまう。
日本のマルクス主義者たちにおいて、ドイツのマルクス主義者たち──フランクフルト学派のマックス・ホルクハイマーや手オドール・W・アドルノら──が亡命してナチズムを批判したように、軍国主義政府を批判したケースはまったくない。当時、最も日本の全体主義を根本的に批判していたのは、マルクス主義者ではなく、共産党嫌いの坂口安吾の『日本文化私観』(一九四二)であり、武田泰淳の『司馬遷-史記の世界』(一九四三)などである。前者は日本の精神状態を病として真っ向から批判することであり、後者は「ほめ殺し」の戦略である──元マルクス主義者であったが、この時点ではすでに転向していたにもかかわらず、ガリレオのような態度をした武田泰淳はマルクス主義を真に理解していたと言えるかもしれない。この両者とも、当時のマルクス主義者の批判以上にラディカルであったけれども、検閲をまったく受けていない。特に、坂口安吾の批判は日本近代文学史上最もラディカルなものの一つであるが、戦前・戦中・戦後を通じて一貫しており、転向とは一切無縁である。安吾は、共産党が「専制、ファッショの徒」であり(『戦争論』)、共産党の根本にあるのは「通風孔」のない「神がかり」(『戦後合格者』)にすぎず、「資源豊かならざる小さな国土と多すぎる人口、この日本の現実を見るならば、日本の経済を安定せしめる方法は、ハッキリしている筈である。つまり、貿易である。搾取階級がなくなろうと、なくなるまいと、貿易に依存せずに、日本がどうなるものでもない。外貨を獲得することだ。貧弱な物資でヤリクリを上手に、合理化してもタカが知れており、共産主義だの経営の合理化だのとチャチなお題目や空念仏を唱えるよりも、ホテルをつくり、道路を良くし、外国から旅行客をつれこむ方が、どれくらい実質的であるか分らない。その方が、はるかに日本の生活水準を高くする方法なのである」(『インテリの感傷』)と共産党のスローガンを批判している。安吾は、戦後になって合法化されたにもかかわらず、組織としてほとんど何のヴィジョンも提示できずにいる日本の共産党の政治団体としての問題点を追及している。転向は、あくまでも組織に関わる問題である弾圧とは区別しなければならない。
吉本隆明は、『転向論』において、「佐野、鍋山的な転向」は「日本的な封建制の優位に屈したもの」であり、「小林、宮本の『非転向』的転向」は「日本的モデルニスムスの指標として、いわば、日本の封建的劣性との対決を回避したもの」であると見なした上で、佐野・鍋山、小林・宮本らを超えるものとして、武田泰淳の「ほめ殺し」を見抜いていた中野重治(一九〇二─一九七九)の転向を次のように評価している。
わたしは、中野の転向(思考的変換)を、佐野、鍋山の転向や小林(多)、宮本、蔵原の「非転向」よりも、はるかに優位におきたいとかんがえる。中野が、その転向によってかい間見せた思考転換の方法は、それ以前に近代日本のインテリゲンチャが、決してみせることのなかった新たな方法に外ならなかった。わたしは、ここに、日本のインテリゲンチャの思考方法の第三の典型を見さだめたい。中野に象徴されるこの第三の典型の優位性が崩壊にたちいたったのは、昭和十年代の後期太平洋戦争下においてであった。ここから日本的転向の問題は、また、別個の課題にさらされるのである。また、それかわたしたちまったく別個の思想的典型を創造すべき課題を負わせている理由でもある。
吉本によれば、「大衆からの孤立(感)」による「大衆の動向」が転向の最大の条件である。共産党への忠誠度によってではなく、日本の大衆が生きている封建的優性との対決によって自らの真理は証明される。視野に亡命を入れることなく、吉本は転向を日本的封建制に対する態度から、日本的封建制の優勢に屈する佐野・鍋山型、日本の封建的劣性との対決を回避する小林・宮本型、敗北を通してそれと対決する中野型の三つに抽出している。これら三つの転向のうち、中野の転向だけが日本的封建制と対決し、「それ以前に近代日本のインテリゲンチャが、決してみせることのなかった新たな方法」である。
その中野重治の転向に至る経緯は次の通りである。『春さきの風』などを発表しすでに文学者としての名声をつかんでいた中野は、一九三〇年に共産党への活動資金提供の治安維持法違反容疑によって逮捕・起訴され、予審終結後、保釈される。保釈中の一九三一年に中野は共産党に入党する。その後、一九三二年、日本プロレタリア文化連盟(コップ)に参加していた中野は保釈を取り消され、治安維持法違反から約二年間拘置される。一九三四年に共産党員であることを認め、共産主義運動から身を引くことを約束し、懲役二年執行猶予五年の判決を受け、出所する。中野は、出所後、再び筆をとり、一九三五年自分の転向に関する小説群──四月に、『鈴木・都山・八十島』、五月に『村の家』──を発表する。
吉本は中野の転向を日本的封建制との対決として評価しているが、それが正当な指摘とは言い難いことは、転向後の一九三六年に発表した『閠二月二十九日』において、反合理主義や反論理主義を擁護する小林秀雄や横光利一に対する次のような彼の批判が告げている。
あらゆる問題は論理の立ち得る「危険な箇所」に立っているのだ。反論理主義者はそれを避けたいとあせっている。論理そのもの、小林のいわゆる「解析」する論理を怖れているのだ。「日本人は曖昧で通じる特別な感覚を、たしかに外人よりは多く持っていると見える。」という横光は、彼自身の論理の喪失と反論理主義へのずれこみとを、日本人のカンのよさで大目に見てくれと持ちかけることで、実は彼の仕事の本質の論理追跡を避けようと努力しているに過ぎない。
こういうでたらめな、反合理主義的な(横光利一の言葉にすると「心理の勝った」)傾向にたいして私は戦ってゆきたいと想う。彼らは手妻使いのように言葉を混乱さして、のらくらものの文学青年だけでなく一人前の作家たちまでが部分的にしろ手妻にひっかかって、わけのわからぬ心得顔をしようと稽古しているありさまを見ると、わけのわかるもの、論理的に辿れるもの、論証されるもの、「常識的」なものをさえ私はかかげたい。独断と逆説とによる卑俗さをロココ的なものかのように振りまわす伊達者たちは、外国の作家、特にフランスの作家たちを引き合いに出したがっているが、フランス近代文学の伝統はそういうものの克服の上に立っている。アンシクロペジストたちや幾何学におけるデカルトはこの伊達者連中に穢されるにはあまりに叡智に充ちている。日本文学は自分が伸びるためには、これらの伊達者のビラビラを草鞋でとりのけねばなるまい。
中野は、彼らの源流であるフランスで流行している反合理主義や反論理主義はあくまでもルネ・デカルトや百科全集派という合理主義や論理主義の伝統の上に立脚し、それに対する批判として機能しているのであって、日本のようにそうした合理主義や論理主義の伝統のないところでそれを唱えることは不徹底だと主張しているのではない。そもそも反合理主義や反論理主義は中途半端なものであり、フランスの「この伊達者連中」は反合理主義・反論理主義の克服を試みたデカルトや百科全集派の掌を世界の果てだと思いこんで飛びまわる孫悟空にすぎない。日本にはまだデカルトや百科全集派がいないため、日本人は必ずしも曖昧ではないにもかかわらず、小林秀雄や横光は日本人を曖昧なものに戦略的にしている。「国民生活という規模で合理主義を『心得』ることのできなかったわが国民の一部、なまけものの文学青年と一部の文学者たちとがそれを崇め奉って拝んでいる」。文学者は合理性・論理性をつきつめなければならない。文学は論理的・合理的な認識に基づいている必要がある。それは、言うまでもなく、作品が論理的・合理的でなければならないということではない。小林秀雄や横光利一はそれらを混同してしまっている。中野には、彼の小説には「心理」的説明が欠けているように、それが反合理主義・反論理主義であるために是認することはできない。中野自身があまり合理的・論理的に見えないとしても、彼はあくまでも合理性・論理性の認識に立脚している。しばしば中野を志賀直哉と同一視する傾向にあるが、中野自身「『暗夜行路』雑談」において志賀を厳しく批判しているように、志賀にはこうした認識に欠けている。中野は合理的・論理的たらんとするが、自分自身の存在そのものがはらんでいる反合理・反論理を、もう自分の力ではどうにもならないギリギリの地点で、合理化・論理化できないがゆえにそのまま肯定し提示する。中野は日本的封建制の問題以上に、このような普遍的な問題意識を抱えている。中野は、吉本の言う日本的封建制は必ずしも反論理主義・反合理主義を意味しているわけではない以上、吉本の主張するような、日本的封建制との対決を必ずしも意図していない。中野が決意しているのは反合理主義や反論理主義との闘いである。日本的封建制との対決を試みるならば、むしろ、『大日本主義の幻想』を書いた石橋湛山のように、商業資本主義をとことん追及したほうがよい。
2 柄谷行人の転向論
吉本と同様に中野重治を評価している柄谷行人は、『近代日本の批評──昭和前期Ⅰ』において、吉本とは別の観点から「転向」を次のように述べている。
私はとりあえず「昭和的なもの」を一つの転向として見ようと思う。昭和初期十年間は、ふつうプロレタリア文学とその崩壊・転向として語られている。その意味での転向の問題や抵抗の問題が本格的に見られるのは、むしろ昭和十年代である。昭和初期において重要な「転向」は、いわば「大正的なもの」からの転向である。それがマルクス主義を中心として生じたからといって、マルクス主義に限定されはしない。たとえば、それは小林秀雄にも谷崎潤一郎にも生じた。したがって、この問題はマルクス主義の哲学や文学理論のなかだけで考察することはできない。この「転向」は、いわば「大正的なもの」からの切断であるがゆえに、その意味は、さまざまな角度から考察されるべきである。
第一に、昭和初期には、マルクス主義への転換が「転向」と呼ばれたことに注意すべきだ。これは福本の理論とともにもちこまれたものである。福本とともに、マルクス主義に主体の問題が導入された。マルクス主義はたんなる世界観や歴史観ではなく、主体にとっての自己変革、したがって「転向」としてとらえられたのである。藤田省三が指摘するように(『転向』上所收)、マルクス主義の放棄がのちに転向と呼ばれたのも、佐野・鍋山の声明にみられるように、それが「自己変革」としてなされたからであって、そのこと自体、最初の「転向」に存した問題にもとづくのである。
もともとは宗教的な概念である「転向」が、マルクス主義者になること、さらにそれを放棄することにかんしていわれたのには、正当な理由がある。それは、たんにマルクス主義の運動がユダヤ=キリスト教的な宗教的な運動に似ているというようなことではない。むしろ日本おいて、ユダヤ=キリスト教的な宗教が、マルクス主義がもたらしたような「転向」の深刻さ、社会的な意味を与えなかったことにこそ、注意すべきであろう。
共産党幹部佐野・鍋山の転向声明(一九三三年)は、マルクス主義の放棄ではなく、コミンテルンの日本情勢分析の誤りを正し、天皇のもとでの共産主義を実現しようというものであった。つまり、転向は主体的な自覚あるいは発展としてなされたのであり、第一次の「転向」と形式的には同じであった。(略)
二度目の「転向」は、ある意味で、最初の「転向」あるいは「転回」がいかなるものであるか、いかなる深度によってなされたかによって決まっている。一度目の天候が単に「観念的意向」でしかないならば、二度目のそれは、たんに観念と現実のギャップによるものでしかないだろう。しかし、「転向」は、倫理的問題でないとしても、吉本隆明のいうような認識的問題でもない。それは、「大正的なもの」の切断がいかになされたかに依存するというべきである。事実、昭和十年代における数少ない抵抗者は、このような「切断」を反復することによってのみありえたのである。(略)
中野重治やその他の数少ない例外をのぞいて、転向は、いわば「大正的な」主体の問題をぶりかえすことになった。
吉本が「転向」を「プロレタリア文学とその崩壊・転向として」、すなわちあくまでもマルクス主義からの転向に限定して考えているのに対して、柄谷は「転向」を「大正的なもの」、すなわち「適度に内面的で、教養主義的、人格主義的な傾向」との「切断」にまで拡大・比較して考察している。転向を「主体にとっての自己変革」とする柄谷は、それを「認識的問題」とする吉本と違って、非転向的な転向や無関心的な転向を必ずしも強調しない。彼は、その代わり、小林秀雄や谷崎潤一郎も転向のカテゴリーに入れている。日本的な自己充足的な状態から世界との緊張の状態への転換を第一次の転向、その逆が第二次の転向である。その一種として、マルクス主義への転換が「第一次転向」であり、マルクス主義からの転換が「第二次転向」であるが、この二つは同じ構造をしている。「第二次転向」を規定するのは「第一次転向」である。それゆえ、佐野や鍋山は転向によって元に戻っただけにすぎない。柄谷によれば、佐野・鍋山の転向声明は、吉本とは逆に、労働者や大衆の心情を汲み入れた結果である。実際、マルクス主義政治思想が天皇制の下で可能だともともと考えていた彼らにとって、コミンテルンが要求した天皇制打倒など最初から不可思議なスローガンである。しかし、中野重治の転向は、後に述べるように、それらと同じ構造をしていない。
日本のマルクス主義の歴史で、転向が本格的に問題となるのは、自己批判を強いられることになったジェルジ・ルカーチの理論が、フランクフルトで研究していた経歴を持つ福本和夫を通じて、一九二七年(昭和二年)から影響を及ぼしてからである。ルカーチはマルクス主義運動に初期マルクスを導入したが、レーニンやグレゴリー・ジノヴィエフ、コミンテルンらから批判され続け、理解されることは長い間なく、その生涯において、政治的転換をかなり重ねている。「史的唯物論の通俗的公式においては、主体的な側面(すなわち意識)は客観的な経済発展の諸法則の受動的な関数であるとされている。若きルカーチの問題は、ある意味では彼がこの見解を受け入れていたということにあった。しかし、彼はまた歴史のなかに意識的実践の創造性の余地を発見しようと試みもした。彼は繰り返して客観的過程を考察し、主体的な実践、すなわち自由が、その過程に入り込むことができ、歴史的な力となりうる分岐点を探し出そうとした」(アンドリュー・アラトー『若きルカーチと西欧マルクス主義の起源』)。ルカーチはマルクス主義を社会科学的理論ではなく哲学として扱い、階級闘争や階級意識を通じた主体の変革を中心的課題とする。マルクスとフリードリヒ・エンゲルスを分離し、後者を批判したルカーチの『歴史と階級意識』は、弁証法的方法の自然への適用の可否、マルクス主義における方法の重視、理論と実践の統一性という三点をめぐって、極左派=修正主義として、発表直後からさまざまな論者から批判される──その中には、この本はおびただしい専門用語の羅列によって書かれており、予備知識のない読者には全然理解できない、それは、プロレタリアートへの接近を目指すことを当然の責務としている共産主義にとっては、ブルジョア的であるという眩暈をもよおすような馬鹿げたものもある(「プロレタリアート」とは、本来、古代ローマの無産階級、すなわち没落中小農民の最下層の貧民である「パンと見世物を要求する浮浪者」を意味している。ユリウス・カエサル登場はるか以前の紀元前二一八─二〇一年の第二回ポエニ戦争、いわゆるハンニバル戦争によって、中小農民は、自腹をきっての出兵、戦場化したための耕地の荒廃、さらに戦後の属州からの安価の穀物の流入、奴隷制による大土地所有の発展の前に、没落し、ローマなどの都市部に流れこんでいる。彼らは選挙権を所有しており、略奪をともなう戦争を望み、野心家の私兵化となってしまう。プロレタリアートという言葉にはもともとは否定的な意味がある)。また、『歴史と階級意識』において、実践的な政治的党派を通して階級意識は表面化してくるが、労働と闘争という契機を欠落させたため、そのヴィジョンは組織論において破綻を示し、さらなる弁証法の運動を希求しており、弁証法的契機としては、到達点とはなりえず、そこから、逆に、マルクス主義の教条化を決定的に顕在させることになる。こうした内容のため、彼は一九二四年にコミンテルンから自己批判を迫られる。ルカーチは、自己批判をして二八年から二九年にかけていわゆる「ブルーム・テーゼ」の作成に加わるが、これもコミンテルンから拒否される。彼は、結局、二九年にモスクワへの亡命を余儀なくされ、七一年に亡くなるまで、この間に、『若きヘーゲル』や『理性の破壊』などを執筆しながら、そこにとどまることになってしまう。ルカーチの理論は五十年代になってスターリニズム批判として復活するが、六十年代後半になると、『ドイツ・イデオロギー』以後のマルクスの作品に向かったルイ・アルチュセール──『資本論を読む』・『マルクスのために』──によって、厳しく批判されることになる。実際、マルクス自身は、その初期の青年ヘーゲル派的な思想を自己批判しているわけだから、当然と言えば当然であろう。ルカーチに基づいた福本和夫の理論は、多くの共産主義者を震撼させ、自然発生的に現われた労農主義的な思想などからの転向を引き起こす。この福本主義を通じて、日本では、初めて革命運動の前衛組織が思想的・政治的に確立している。Tessek parancsolni! 福本和夫の強い影響下にあった中野は一九二八年に『春さきの風』を発表する。この年から一九三一年までがプロレタリア文学の全盛期である。しかし、ハンガリー本国でさえも拒まれたルカーチの理論が一国の共産党の中心的思想になるなどというのは画期的なことであるが、共産主義政治をめぐる激しい思想闘争によって組織的な分離・結合が進行し、ルカーチと同様、まもなく福本主義は批判されるようになる。『歴史と階級意識』は、モーリス・メルロ=ポンティの『弁証法の冒険』によると、「一時は西欧マルクス主義の聖典であった」。ルカーチが依拠したのは亡命実行以前の初期マルクスであり、当然、ルカーチは転向を繰り返していたことからも、(発達した資本主義国への)亡命といった可能性は最初から否定されているわけで、日本のマルクス主義がそのルカーチに負っているかぎり、マルクス主義者たちから亡命が主張されることはない。
そのプロレタリア文学を読んでみると、柄谷の言うこの第一次転向が明らかとなる。大正末期から昭和初期にかけて、空前の円本ブームなどによって大衆文化が確立していたが、第一次世界大戦後の経済恐慌、関東大震災、世界恐慌による経済混乱と農村恐慌によって社会不安が増大する。プロレタリア文学はこうした歴史的・社会的な背景から生まれている。一九二一年(大正十年)に、『種蒔く人』が創刊されたのを出発点として、一九二四年には『文芸戦線』の発刊、一九二五年に、日本プロレタリア文芸連盟の結成と急速に勢いを増す。当初、プロレタリア文学は、『セメント樽の中の手紙』(一九二六)の葉山嘉樹に代表されるように、労働者による自然発生的な運動であったが、青野李吉らの主張によって社会改革の政治的な色彩が強くなっている。
プロレタリア文学が登場する前に文学界に君臨していたのは「反自然主義のチャンピオン」と呼ばれた芥川龍之介であり、第一次転向は芥川に対する批判の形態をとっている。例えば、プロレタリア文学の作家たちは、宮本顕治の『敗北の文学』を代表に、芥川は労働者階級から遊離したプチ・ブルジョア階級の作家であったから自殺してしまったのだという意見を発表している。彼らの政治的意見は、芥川の自殺に対する強迫観念を利用して、文学的には主張されている。こうした経過を経て、プロレタリア文学はマルクス主義的な政治的目的への奉仕を強いられることになる。この強制力が、彼らにとって、耐え難いものだったことは否定できない。もともとプロレタリア文学はマルクス主義とは直接的な関係を持っていなかったのだから、転向は、柄谷の指摘する通り、この時期に用意されていたと言っていいだろう。芥川に対する批判を「第一次転向」とするならば、プロレタリア文学の作家たちだけでなく、当然、芥川に対する代表的な文学的批判者である谷崎も小林秀雄も転向のカテゴリーに入らざるを得ない。
坂口安吾は、『新らしき文学』(一九三三)において、そのプロレタリア文学をめぐって次のように批判している。
現在プロレタリア文学は、その反逆的な闘争的な点に於て一つの意義と役割をもつが、人間を安易に仮定し、文学の唯一の領域たる個体を、血と肉に縁のない概念の中へ拉し去り曖昧化し、科学への御用的役割を務めるのは凡そ意味ない。文学本来の面目に反している。
現在ソヴィエト・ロシヤに於て文学に課せられた一つの課題は社会的な感情を探り出し書きあらわすことであるというが、文学の反逆的な役割を巧に瞞着した為政者の手腕もさる事ながら、漠然として社会感情を探しあぐねるロシヤ作家のだらしなさは滑稽である。文学は永遠に政治に対する反逆である。個人のために血と肉の人間悲劇を語らなければならない。
日本のプロレタリア文学は一つの宣伝文として或いは有効である。なぜなら科学と協力し妥協することによって、一つの昂奮をもたらすことができるから。しかしそれは文学本来の昂奮でなく、感銘でない。むしろ完全に非文学的なものである。やがて政治の御用文学となるそれである。それはもはや文学でない。
文学が扱うのは、「個体」であって、「科学」の扱う一般性ではない。しかし、プロレタリア文学は個人についてではなく、階級をめぐって書かれており、労働者や農民といったプロレタリアートとブルジョアジーとの関係をという一般的な問題系にある。プロレタリア文学はそれが基づいている「科学」によって読まれているのであって、作品そのものの持つ魅力はほとんどない。プロレタリア文学は「科学」に基づいた政治に奉仕しているが、そもそも文学は「永遠に政治に対する反逆」であって、政治に従うべきものではない。プロレタリア文学は「科学」という虎の威を借る狐にすぎない。
プロレタリア文学はマルクス主義の外皮を被ってはいるが、それを文学として存立するために利用したにすぎず、マルクス主義など不必要である。本来、文学としてとても扱うことができないものでも、マルクス主義という衣装をまとうとき、馬子にも衣装の諺のように、とりあえず文学として論議される対象となる。しかし、目を奪われているのはマルクス主義という衣装であって、その作品ではない。
いかに同時代的に影響を与えていたと言っても、すでに当時から批判されていたことだが、小林多喜二や宮本百合子らプロレタリア文学の作品は、主題も非常に素朴であり、表現も稚拙であり、読むに耐えるものではない。例えば、『蟹工船』が文学史に上るのは、警察の拷問によって惨殺された小林多喜二の作品だからであって、その逆ではない。そうした前知識のない読み手によって『蟹工船』が高い文学的評価を受けるかどうかははなはだ疑問である。それらは文学と言うよりも、むしろ、ルポルタージュを部分的にとり入れたプロパガンダ的な作文と言っていいだろう。ルカーチも、『ヴィリ・ブレーデルの長編小説』(一九三一)において、プロレタリア文学におけるルポルタージュ的な要素を弁証法の欠如であると厳しく批判している。このルカーチのエッセーをきっかけとして「ルポルタージュ=形象化論争」がヨーロッパでは起こっている。こうしたプロレタリア文学のほとんどの作品にはマルクス主義にとって肝心の弁証法が体現されてはいない。福本和夫によって階級意識や階級闘争、主体性が日本のマルクス主義運動に導入されたにもかかわらず、そこにはマルクス主義の根本にある弁証法が表われていない。例えば、プロレタリア文学は資本家や警察は圧迫者であり、労働者や農民は被迫害者であるという素朴な図式によって成立している。被害者意識やルサンチマンに満ちあふれた作品が始まってから終わるまで、この図式は決してゆるがない。労働者や農民は作品が終わっても、必ずしも、勝利者になることはなく、資本家や警察によって迫害されたままで、この二項対立は弁証法によって合一されることはない。プロレタリア文学は知的なものを排除し、そこにあるのは「都会の文化や伝統的な文化を直ちにブルジョア文化と片づけ、職工達の小学校だけの教養や農村の貧しい教養をプロレタリヤ的だと云って謳歌した反動性」(安吾『地方文化の確立について』)にすぎない。
転向以前に発表された中野重治の『春さきの風』も、やはり、この図式に基づいている。
「おまえは村田の女房か?」
「そうです。」
「名前は?」
「村田ふく。」
「村田なに?」
「ふ、く。」
高等は形相を変えた。
「ふ、く。何だ、それは? そんなことだから検束されたり、監獄へぶち込まれたりするんだ、馬鹿。」そして吐き棄てるようにいった、「それでよく人の女房が勤まるな。」
母親が答えた。言葉が口から出るのにつれて顔が蒼くなっていった。
「わたしらは労働者ですから、金持ちのお嬢さんのような教育は受けておりません。これで十分女房の役が勤まります。」
高等は持っていた鉛筆を放し、椅子から腰を上げ、非常に大きな平手打ちを母親の左頬にくれた。
大きな手形が顎から瞼、眉の上へかけて赤黒く浮き上った。
「はいれ!」
風の音の中で母親は死んだ赤ん坊のことを考えた。
それはケシ粒のように小さく見えた。
母親は最後の行を書いた。
「わたしらは侮辱の中に生きています。」
それから母親は眠った。
この時期の中野の作品は、他のプロレタリア文学の作品と同様、弁証法が内的論理として、体現されていない。それは私小説と言ってよい。プロレタリア文学の作品は「不快」に始まって「調和的気分」に終わるという気分の移行によって形成されている志賀直哉の私小説と同じ構造を所有している。転向後プロレタリア文学の作家たちは私小説を書き始めたが、もともと彼らはプロレタリア文学の作品を私小説のヴァリエーションとして、志賀直哉の私小説の中にもルポルタージュ的な作品が少なくないように、書いている。例えば、小林多喜二や宮本百合子は、中野とは違って、公然と志賀を評価している。私小説は気分を作用する主体とし、それ以外を客体とする散文形式であり、そこでは、中心的人物に主体性はない。一方、プロレタリア文学の作品において、中心的人物には、厳密な意味においては、主体性がなく、共産主義のテーゼに従うだけである。作用する主体である気分は、プロレタリア文学において、共産主義や共産党、党の方針という主題の形をとっている。プロレタリア文学において、共産主義は到達されるべき理想である。
しかし、マルクスは、『ドイツ・イデオロギー』において、共産主義について次のように書いている。
共産主義とは、われわれにとって成就さるべきなんらかの状態、現実がそれへ向けて形成されるべきなんらかの理想ではない。われわれは現状を止揚する現実の運動を、共産主義と名づけている。この運動の諸条件は、今現にある前提から生じる。
ところが、私小説は静的であり、マルクス主義のような動的側面に乏しく、プロレタリア文学は、その形式において、「現状を止揚する現実の運動」を秘めておらず、革命的ではない。志賀直哉の私小説は内村鑑三の告白、すなわち内村の唯一神教的なキリスト教に対するンチ・テーゼとして出発したわけだが、転向の図式はこの私小説と主体性に基づいた告白、すなわち志賀直哉と内村鑑三との関係に負っている。キリスト教の場合、その入信にしても棄教にしても、志賀がそうであるように、内村に対する個人的な崇拝・離反から生まれているけれども、内村という個人が党などに変わっただけで、マルクス主義の場合も、これとまったく同じ構造を所有している。福本和夫や小林秀雄はマルクスの名によってプロレタリア文学を批判している。しかし、マルクスを用いてプロレタリア文学を批判することは、マルクスにとって「政治と文学」といった問題はありえなかったし、もともとマルクス主義とプロレタリア文学は無関係だったわけだから、さほど困難ではない。むしろ、プロレタリア文学はマルクス主義に従属していたのではなく、マルクス主義を従属させようとしている。このようなプロレタリア文学の作家たちによって、主体性を導入しようとした福本主義が否定されることになるのは、当然のことであろう。
ところが、この時点で私小説を書きながらも、中野重治は、他のプロレタリア文学者とはすでに異なっている。と言うのも、『むらぎも』が明らかにしているように、むしろ、プロレタリア文学の作家たちが批判していた芥川を評価しているからである。芥川の作品は古典に題材をとった前期と「『話』のない小説」の後期とに大きく二つにわけられるが、彼は後期の作品によって前期の作品を自己批判している。後期の作品は前期の作品が追及していた主体性批判であったけれども、それでは、安吾が『文学のふるさと』で紹介している彼の遺稿が示しているように、不十分なことは承知していつ。芥川の遺稿は、プロレタリア文学者などの彼に対する批判以上に、すぐれた批判になっている。
安吾は、『文学のふるさと』において、プロレタリア文学からの批判とは逆に、芥川には生活があったと次のように指摘している。
とにかく一つの話があって、芥川の想像できないような、事実でもあり、大地に根の下りた生活でもあった。芥川はその根の下りた生活に、突き放されたのでしょう。いわば、彼自身の生活が、根が下りていないためであったかも知れません。けれども、彼の生活に根が下りていないにしても、根の下りた生活に突き放されたという事実自体は立派に根の下りた生活であります。
つまり、農民作家が突き放したのではなく、突き放されたという事柄のうちに芥川のすぐれた生活があったのであります。
プロレタリア文学者は芥川を「突き放し」ていたかもしれないが、「芥川のすぐれた生活」は「突き放されたという事柄のうちに」ある。彼らには、芥川と違って、「突き放された」ような認識はない。中野だけが芥川の認識に気づいている。中野の転向は、その根本において、ほかのプロレタリア文学者たちとは異なり、独特なものであると言っていいだろう。
3 転向と沈黙
中野の転向の独自性の一端を自らの転向体験をモチーフにした『村の家』の次の箇所が告げている。
彼は再び保釈願いを書き、政治活動をせぬという上申書を書き、(しかし彼は、彼の属していた団体が非政治的組織であり、彼が非合法組織に加わっていなかったという彼自身の主張はどんな意味ででもふれなかった。)一方病室にはいれるよう要求し、看守長に会って、下獄する場合東京もしくは東京近県で服役できるかどうかを検べた。
彼は病室に入れられた。隠されている病名は肺浸潤であることを知り、目方が四四・五キロにへったことを知った。
ある日彼は細い手でお菜を摘まみ上げ、心で三、四の友達、妻、父、妹の名を呼びながら顎をふるわせて泣き出した。
「失わなかったぞ、失わなかったぞ!」と咽喉声でいってお菜をむしゃむしゃと喰った。彼は自分の心を焼き鳥の切れみたいな手でさわられるものを感じた。一時間ほど前に浮かんだ、それまで物理的に不可能に思われていた「転向しようか? しよう………?」という考えがいま消えたのだった。ひょいとそう思った途端に彼は口が乾上がるのを感じた。昼飯がきて受け取ったが、病気は食い気からと思って今朝までどしどし食っていたのがひと口も食えなかった。全く食欲がなく、食欲の存在を考えるだけで吐きそうになった。両頬が冷たくなって床の上に起き上がり、きょろきょろ見廻した。どうしてそれが消えたか彼は知らなかった。突然唾が出てきて、ぽたぽた泪を落としながらがつがつ噛んだ。「命のまたけむひとは──うずにさせその子」──おれもヘラスの鶯として死ねる--彼はうれし泪が出てきた。
主人公勉次は病気とそれがもたらすかもしれない狂気への恐怖によって「政治活動をせぬという上申諸」を書くが、彼は非合法組織、すなわち共産党に所属していたということは自白しない。これは、蔵原惟人らと比較すると、転向の基準としてはいささか特異である。勉次がこだわっているのは、政治活動を続けるか否かでもマルクス主義を放棄するか否かでもなく、党員であるかを認めるか否かにあるけれども、これは、他の党員たちが彼が党員であることを認めていることからも、警察にとってもさほど問題にならない。弁護士も彼に「無駄」だと提言している。柄谷行人は、『中野重治と転向』において、中野のこうした態度は転向=非転向の単純な論理の図式に回収されるのを拒むためだと言っている。対立は差異性ではなく、構造的な同一性によって生じるのであり、確かに、中野は「政治と文学」や「転向と非転向」といった二項対立を退けている。と言うのも、彼にとって、それらが二者択一といった選択の問題ではないからである。政治的に意味があっても、芸術的・文学的にはとるにたらない作品が書かれていることの是非を問題にするような論争は、中野には、本質的に意味をなさない。中野にとって、『むらぎも』で述べているように、文学は「才能」の問題ではなく「道徳」の問題である。「才能」のせいにして文学を放棄するか否かということを問題にするのは、いわゆる責任転換しているのであって、「道徳的」ではない。自分の「道徳的」な姿勢によって書くか否かが決定される。書くということはその人間の持つ道徳的な姿勢による。存在と認識の乖離が不可避的である以上、書くことはひとを傷つけまた自分を傷つけざるを得ないが、それにもかかわらず、書くという行為に自らの人間性を賭けざるを得ないことによって書くことは始まる。書くことはそういう自らを裏切らざるを得ないというおそれとおののきの経験とともにあり、つねに「道徳的」なものだ。書くことはその不可能性において始まる。書くことは才能によるのではなく、この不可能性に賭けられるか否かにかかっている。中野にとってそのような「道徳」の問題である文学に政治的な価値があるかどうかという選択は根本的にあり得ない。
さらに、柄谷は中野の作品に見られる「わかりにくさ」を彼が「差異への感受性」として表明する「感じ」に帰着させている。しかし、中野の「感じ」は、むしろ、同一への感受性、すなわち直観である。中野は差異にこだわっていたが、それは構造的同一性を見出す直観力が引き起こしている。自分自身に対してもその直観力は例外なく働くけれども、彼ら自身は党派によってしか生きられない。でも、中野にとっては一人の人間として生きることが先にあるということから、その同一性からこぼれてしまう自分自身がある。中野は健康である。病気は定義を前提にするが、健康を定義することはできない。健康は健全ではなく、「道徳的」に丈夫だということを意味している。「政治と文学」や「転向と非転向」といった二項対立は、「道徳的」に、病的である。健康なる者は自分を絶対化せずつねに自分を相対化すること、すなわちこの程度の苦痛や苦悩はたいしたことではないと自らに言い聞かせることを忘れない。中野にとって、「道徳的に外れてしまうこと」はそれを忘却した自己欺瞞・自己倒錯にほかならない。
中野は、「『文学者に就て』について」において、道徳について次のように述べている。
僕は君が僕の考え方に賛成するだろうと思う。しかしそれならば僕は、まだ肝腎なものがぬけているといわなければならない。君の支払勘定にあらゆるものはのっているが、最大のもの──「転向の事実」はのっていない。君の言葉によれば、これは、転向作家たちから第一義的なものを奪ったし、将来にわたって奪っているものである。そのため君に「むしろ死ぬべきであった」という非難にさえ頭を垂れさしたものである。それがのっていない。君のは大福帳が間違っているのだ。「文学のために命がけの政治的経験」を目たたきとともに葬り去った最大の政治的経験は君の支払勘定にははいらないのか。「敗れはしたが命をかけた経験」ではない、「命をかけた(?)のに自ら敗れたという経験」──これこそがすべての作家もかつてなめなかった第一義的な敗北、深い恥にみちた最大の支払なのである。そしてそのことによってそれが、もしわれわれがそうするために努力しとおすならば、第一義的な文芸実践の最も強い土台の一つとなれるのだ。
中野の「道徳」はこのような認識に基づいている。転向を「敗れはしたが命をかけた経験」とすることは自己倒錯・自己欺瞞にすぎない。むしろ、「命をかけた(?)のに自ら敗れたという経験」こそが転向にはあり、これはかつてなかった経験であって、そうすることによってのみ、生を肯定できる。転向は、本多の主張とは違う意味で、倫理的である。
確かに、中野の作品には心理的な説明がないため、その「道徳」は認めがたい。肝心の転向に関しては、『村の家』の中で、「明くる日朝早く弁護士が来た。勉次は問題の点を認めることにすると答えた」と書いているだけである。中野の作品にはこうした詩的とも言える省略が少なくない。彼の文体はどこか寡黙である。作品を内省的に書いてはいるが、転向を内面の問題としても、外面の問題としても、描いてはいない。その主人公はつねに事後的に振り返って内省し始める。福田恆存は、『中野重治』において、中野に対して「近代人の自意識」がなく、彼が『斎藤茂吉ノオト』を書いたのは「茂吉の近代性を押し立てることによつて自己の古さをカヴァーしようとしている」からだと指摘している。中野が自意識を持っていないことに関して、柄谷も彼を自意識の他なるものとして理解している。けれども、それだけで不十分である。しばしば志賀直哉も自意識を持たないとされているからである。中野は、「『暗夜行路』雑談」において、志賀直哉を「甘え」た「気随息子」がそのまま老けた「老人」であると糾弾している。さらに、『小僧の神様』に関して、「最初は真実に立っていた。ただ最後へきて──主人公が移動してしまうが──柄にもないことを止めれば、小僧に鮨が食えなくなることについての自己の(正邪にかかわらぬ)断定を避けたところに隙ができてしまった」と批判する。中野は志賀の作品に見られるアイロニーを嫌う。と言うのも、アイロニーは自己欺瞞と自己倒錯、自己嫌悪と自己憐憫に基づいているからである。そのようなアイロニーに満ちた志賀の私小説は生の否定といった病的な精神が生み出したものだ。中野の認識をもたらしたのは絶対的な他者性への意識などではなく、それは生きることそのものへの意識である。
中野の作品は転向によって変わり、真に輝き始める。それは突然変化したということではない。それにより自分自身の問題意識が明確に顕在化し、自覚したとことを意味する。転向以前に書かれたエッセーを読むならば、その点がはっきりする。転向前の作品にも、確かに、中野らしさが出てはいるものの、先の引用が明らかにしているように、他のプロレタリア文学の作品とあまり違いはない。中野について語られる際に言及されたり、引用されたりするのは、ほぼ転向後に書かれた作品であり、一種のルポルタージュである『春さきの風』に至っては、ほとんど語られることがない。なるほど『むらぎも』は転向前の中野を知る資料として重要ではあるが、あくまで転向後に書かれた作品である。
転向後に書かれた『村の家』は、『春さきの風』とは違って、私小説ではない。『村の家』は弁証法的なスタイルで求心的に話が進んでいく。中野は、転向後、初めて弁証法を内的論理に据えた作品を書き始め、それを主に対話として現われる。『村の家』において登場人物はそれぞれに対して同意することはない。勉次、父親の孫蔵、母親のクマ、妻のタミノ、弁護士などそれぞれが対話を通じて関係しつつ、統合されることなく一つの全体性を形成している。それはヘーゲル的な弁証法ではない。そこではおのおのがそれぞれ違ったものとして生きている。
『村の家』の弁証法の特徴は、政治活動をしないという上申書を獄中で書いて出獄し、その後、郷里に戻ってきた主人公と父親の孫蔵との次のような会話が示している。
「それじゃさかい、転向と聞いた時にゃ、おっ母さんでも尻餅ついて仰天したんじゃ。すべて遊びじゃがいして。遊戯じゃ。屁をひったも同然じゃないかいして。竹下らアいいことした。殺されたなア悪るても、よかったじゃろがいして。今まで何を書いてよが帳消しじゃろがいして。(略)あかんがいして。何をしてよがあかん。いいことしたって、してれやしてるほど悪るなるんじゃ。あるべきこっちゃない。お前、考えてみてもそうじゃろがいして。人の先に立ってああのこうのいうて。(略)本だけ読んだり書いたりしたって、修養ができにゃ泡じゃが。お前がつかまったと聞いた時にゃ、お父つぁんらは、死んでくるものとしていっさい処理してきた。小塚原で骨になって変えるものと思て万事やってきたんじゃ……」
孫蔵は咳払いをして飲んだ。勉次も機械的になめた。
「いったいどうしるつもりか?」孫蔵はしばらくして続けた、「つまりじゃ、これから何をしるんか?」
「…………」
「お父つぁんは、そういう文筆なんぞは捨てべきじゃと思うんじゃ。」
「…………」
「お父つぁんらア何も読んでやいんが、輪島なんかこのごろ書くもな、どれもこれも転向の言いわけじゃっじゃないかいや、そんなもの書いて何しるんか。何しるったところでそんなら何書くんか? 今まで書いたものを生かしたけれや筆ア捨ててしまえ。それや何を書いたって駄目なんじゃ。今まで書いたものを殺すだけなんじゃ。それや病気ア直さんならん。しかし百姓せえ。三十すぎて百姓習うた人アいくらもないこたない。タミノじゃって田んぼへ行くのがなんじゃい。そんなこってどうする? さきもいうた通りじゃ。借金は五千円じゃ。そっても食うだけや何とかして食える。食えんところが何じゃいして。食えねえや乞食しれやいいがいして。それが妻の教育じゃ。また家長たるべきもの、一家の相続人たるべきものの踏むべき道なんじゃ。」
「…………」
孫蔵はまた飲んだ。
「よう考えない。我が身を生かそうと思うたら筆を捨てるこっちゃ。……里見なんかちゅう男は土方に行ってるっちゅじゃないかいして。あれは別じゃろが、いちばん堅いやり方じゃ。またまっとうな人の道なんじゃ。土方でも何でもやって、その中から書くものが出てきたら、その時にゃ書くもよかろう。それまでお父つぁんも止めたアも言やせん。しかし我が身を生かそうと思うたら、とにかく五年も八年とア筆を断て。これやお父つぁんの考えじゃ。お父つぁんら学識アないが、これやお父つぁんだけじゃない、誰しも反対はあろまいと思う。七十年の経験から割り出いていうんじゃ。」
ある考えを信じ、それを実現しようとして個人でのみ行動しようとしたが、結局やめてしまったことには転向は無縁である。それは変化にすぎない。転向は他者との契約関係において生じる。発話行為は、他者とのコミュニケーションの中では、契約として機能する。中野の作品の対話は沈黙が重要な効果を果たしている。主人公勉次は父親の言葉を一方的に聞いているだけで、その解答は沈黙によってなされ、転向の言い訳はまったく口にしていない。言い訳や誓いは負い目といった心の弱さの現れであり、自己絶対化であるからなどという素朴な理由で、また自分の世界を保持するためという幼稚な理由で、他者とのコミュニケーションを拒んでいるわけではない。私には私なりの考えがあるから、黙るのではない。彼が沈黙してしまうのは、告げなければならないがゆえに伝えられない何ものか、すなわち告げてはならぬ何ものかに囚われているからである。彼の沈黙の理由は沈黙そのものによって見出されるべきものだ。そこからすべてが生まれてくる。この沈黙は実存の条件であると同時に倫理の条件である。勉次はなぜではなく、いかにして語ろうとするがゆえに、沈黙する。沈黙の中に不可避的な自分自身の存在の根源性がある。
こうした沈黙によって表わされた中野の転向に関する記述は、近代文学以前を感じさせる。しかし、それは柄谷の指摘するような福音書的なものではない。転向を語る際に、確かに、福音書に言及することは欠かせない。転向はもともと宗教的概念であり、転向に際して一つのモデルとなるのは、イエスに対するペテロの裏切りだからである。
転向には自己批判や懺悔がつきものであるが、宗教の転向は政治のそれと違う。どちらも未来に向けたあるいは未来から見られた時間帯の中で思考していることは変わらないけれども、政治においては、転向者はあくまで此岸のことだけを考えればよいが、宗教の場合、彼岸での禍いを覚悟しなければならない、すなわち死んでからも苦しむことになるという決まり文句によって彼らをしめつける。この世が終わってもあの世が待っているというわけだ。政治では、その理想の達成は、自分の死後、その人から離れて次に続くものに期待することしかできない。しかし、キリスト教において転向が問題となるのは、福音書にはペテロの死後に関する記述がないように、それが現世を強く意識しているからである。けれども、中野の転向はペテロの転向と、根本的に、異なっている。
吉本は、『沈黙の有意味性について』において、『マタイによる福音書』でペテロが三度裏切る話について、次のように書いている。
ペテロが前日、師イエスにむかって、わたしはあなたを裏切るようなことはありませんと告げたとき、ペテロはたんにイエスにたいする信仰を告白したにすぎず、ペテロの言葉をとりまいている情況は〈無〉にひとしいものであった。しかし人間が喋言ったこととちがうことを実現してしまうためには現実の方からある必然の契機が加担しなければならない。そしてある意味からは、人間はかならず語った言葉とは別のことを実現してしまうような存在本質である。
福音書において、転向は内面的・心理的な問題とてして扱われておらず、発話と沈黙のレヴェルにおいて把握されている。ペテロは自ら立てた誓いに対して裏切ってしまう。転向は誓いに対する裏切りである。転向は認識と行為の乖離に、「現実の方からある必然の契機」が加担することによって、生ずる。それは言っていることとやっていることが一致しないという事態にほかならないが、人間の生の不可避的な条件である。沈黙はそうした倫理的なものから発生しているのであって、人間の弱さなどではない。
「ある意味からは、人間はかならず語った言葉とは別のことを実現してしまうような存在本質である」のは「関係の絶対性」によって規定されているからだけではなく、言葉の持つ不可避的な条件によるからである。人間は自分とまったく他のものと生きていかざるを得ない。そのため、沈黙したとしてもそれもまた他のものによって解釈される。沈黙もまた言葉の一つである。「関係の絶対性」に強いられながら人間はおのれに対して自分自身を相対化することは十分に可能だ。「関係の絶対性」に規定されているにもかかわらず、人間は自らを突き放し、それを笑い飛ばすという自由がある。福音書において転向が描かれているのは、福音書に笑いが登場していないからである。ペテロはイエスを三度否認し、泣く。しかし、もしここでペテロが笑ったとしたら、転向は存在しないだろう。ペテロが転向するのは、イエスを三度否認することではなく、その後に泣くことによってである。それ以前に、ペテロが「あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度知らないと言うだろう」と離したイエスに「そうかもしれません」とか、「いえ、三度ではなく、四度知らないと言うしょう」とユーモアをこめて答えたなら、転向はありえない。中世の教会権力からとことん憎まれたエラスムスは「真理も笑いながら語るべきである」と言ったが、笑いを登場させると、転向は成立しなくなる。フリードリヒ・ニーチェは、福音書を批判するために、笑いながら生まれた宗祖の語りの『ツァラトゥストゥラはかく語りき』に笑い、「哄笑」を導入する。
沈黙し続ける主人公は、父親の筆を折れという強い勧めに対して、次のように反応している。
勉次はいろんなことがわかったように思った。家族関係のさまざまな糸、家と家とのつながりへの生き方のいろんな反映、自分たちの眼の狭さ、父が上京して開いたという会議でのタミノの言葉の父による誤解──しかしすべてを彼の裏切りが与えていた。父の誤解をいくら解いても誤解を生ましたものにふれることはできない。父のいう通りである。タミノやトミや何十人かのその仕事仲間にたいしては責任を感じていたが、父親にたいしてそれと同質のものを感じていなかった自分の姿は見るにたえなかった。
「どうしるかい?」
勉次は決められなかった。ただ彼は、いま筆を捨てたら本当に最後だと思った。彼はその考えを論理的に説明されうると思ったが、自分で父にたいしてすることはできないと感じた。彼は一方である罠のようなものを感じた。彼はそれを感じることを恥じた。それは自分に恥を感じていない証拠のような気がした。しかし彼は、何か感じた場合、それをそのものとして解かずに他のもので押し流すことは決してしまいと思った。これは彼らの組織の破壊を通して、自分の経験でこの二年半の間に考え積ったことである。自分は肚からの恥知らずかも知れない。しかし罠を罠と感じることを自分は拒むまい。もしこれを破ったらそれこそしまいだ。彼は、自分が気質的に、他人に説明してもわけもわからぬような破廉恥漢なのだろうかという、漠然とした、うつけとした淋しさを感じたが、やはり答えた、「よくわかりますが、やはり書いて行きたいと思います。」
「そうかい……」
孫蔵は言葉に詰ったと見えるほどの侮蔑の調子でいった。彼らはしばらく黙っていた。勉次は自分の考えは正しいと思った。しかしそれはそれきりの正しさで、正しくなるかならぬかはそれから先のことだと感じた。彼は何の自信もなかった。彼は多少の酔いを感じ、ふぬけのように労れた。
勉次は行ってきたことや考えてきたことが、自分にとってですらも絶対的に正しかったとも絶対的に過ちであったとも思っていない。勉次は説明できると感じながらも沈黙してしまう。それは、勉次の転向は人間の関係において、自己をつらぬくことが誰かを犠牲にするほかないという認識から生じているのではない。自己完結的な孫蔵によって、勉次は相対化されている。孫蔵は決して具体的な生活から離れた意見を述べることはなく、勉次に論理的に自分の考えを主張し、一歩も譲らない。それに対して、勉次は沈黙によって耐えている。孫蔵と勉次の二人の会話が弁証法的であるのは、二人の会話が交差するとそれぞれの思わぬ本質を露呈するからである。会話は、主人公にとって、最終的結論を出すことはない。孤独に突き放すだけである。彼を沈黙させるのはこの孤独であり、それは、人間が一個の「個体」として生きようとするときに、生じてくるものである。
4 自己超克としての転向
中野にとって、転向は突然降って沸いたように現われてきたものではない。じわじわと中野に浸透してきている。しかし、それは内面のドラマではない。自分自身がそれまでかたく信じてきたものの上に、新たな考えが、自らの意図に逆らうかのように、覆い被さってくる。中野にとって、その事態は必ずしも好ましくははい。
中野は、「『文学者に就て』について」において、小林多喜二を思い出しながら、次のように述べている。
弱きを出したが最後僕らは、死に別れた小林の生きかえってくることを恐れはじめねばならなくなり、そのことで彼を殺したものを作家として支えねばならなくなるのである。僕が革命の糖を裏切りそれにたいする人民の信頼を裏切ったという事実は未来にわたって消えないのである。それだから僕は、あるいは僕らは、作家としての新生の道を第一義的生活と制作とより以外のところにはおけないのである。もし僕らが、みずから呼んだ降伏の恥の社会的個人的要因の錯綜を文学的綜合の中へ肉づけすることで、文学作品として打ちだした自己批判をとおして日本の革命運動の伝統の革命的批判に加われだならば、僕らは、そのときも過去は過去としてあるのではあるが、その消えぬ痣を頬に浮べたまま人間および作家として第一義の道を進めるのである。
何のこだわりもなく、転向していくことは、すなわち転向することを自明の条件とすることは中野にはできない。と同時に、彼は過剰な罪の意識を持つことは転向を覆い隠すための身振りにすぎないとも感じている。中野は何が起ころうとも信じていくことを決意していたにもかかわらず、転向してしまう。彼は信じていようとするがゆえに転向する。中野はそれに負い目を持つことなく、文学作品を通して自己批判を行おうとする。中野にとって、転向が重要ではない。新たな考えが入って自分を占めてしまうことが大きい。
だが、父親の孫蔵はそういう勉次には不満を感じている。孫蔵には、息子が決意したものを翻したこと、すなわち信じていたものに殉死しなかったことや負い目一つ感じず恥知らずにもまた書こうとしていることが許しがたい。この孫蔵に対する解釈は多岐にわたっている。吉本隆明は、『転向論』において、彼を「日本封建制」の権化としてとらえているし、柄谷行人は、『死語をめぐって』において、彼を「知識人に対して職人の名において語るもの」としてとらえている。あるいは、父と子、すなわち世代間の対立としてとらえているものもいる。おそらく、それらの解釈は、部分的には、間違っていない。
しかし、孫蔵に関する次のような説明がそれては不十分なことを明らかにしている。
孫蔵は正直者で通っている。それも百姓風な頑固ものではない。永くあちこち小役人生活をして、地位も金も出来なかった代わりには二人の息子を大学へ入れた。先代の太兵衛はわけもわかる代り名うての頑固ものだったが、孫蔵の方は十七、八貫もあるからだて口喧嘩一つしたことがない。喧嘩話を持ち込む近所合壁の嫁姑は、太兵衛には頭ごなし叱りつけられたものだったが、孫蔵になってからは世間話をしているうちに自分から取り下げるような具合である。長男の耕太が、大学を出て一年たたずに死んだ時も孫蔵は愚痴一つこぼさなかった。どこかに火事でもあれば、一里半や二里のところは真夜中でも草鞋ばきで見舞いに出かける。代々酒のみの家で、孫蔵も酒量ではひけを取らなかったが、声が大きくなるくらいで乱れたことはない。(略)それやこれやで彼は、家族からも親類うちからも、村のものからも尊敬されている。
孫蔵は人望もあり、寛大で、子供に対して理解力ある親である。彼は、妻のクマと違って、「息子が刑務所に入っていることに何のひけ目も感じなかった」。と言うのも、「うちの教育方針は決して悪るない。いい悪いは知らんがまちごうてはいぬつもりじゃ」からである。孫蔵は共産主義活動に必ずしも否定的ではないが、そんなことをしている間は地に足が着いていない証拠だと感じ、肯定的でもない。それは若いときのはねあがりのすること、若気のいたりである。孫蔵は、それだけでは、なかなか図式的には扱いにくい存在であるが、彼の本質は息子との対話によって顕在化する。
孫蔵は勉次をたんなるロマン主義者と見なしている。しかし、孫蔵もまたもう一つのロマン主義者である。転向する前の勉次と孫蔵は、それぞれニーチェが『反時代的考察』の中で提唱した人間像、すなわち「ルソーの人間」と「ゲーテの人間」、沈黙する勉次は「ショーペンハウアーの人間」に対応させることができよう。ニーチェは、『この人を見よ』において、『反時代的考察』がアルトゥール・ショーペンハウアーの理解に役立つとは考えてはおらず、自分自身だけを語っていることを否認しないと明かしている。ニーチェは、この著作において、ルソーやゲーテ、ショーペンハウアーを、『悲劇の誕生』におけるリヒャルト・ワーグナーと同様に、比喩として取り扱っている。
まず、「ルソーの人間」は、「最大の火」を持ち、「最も通俗的な影響を及ぼす」。彼は「自然だけが善だ、自然人だけが人間だ」と叫ぶ。だが、そうしたことはただたんに現にある自分自身を否定しているにすぎない。「ルソーの人間」は熱狂的な革命への行動的な希求を持つと同時に、強い現実否認と本来性への憧憬をも持っている。あるいは、それは青年期的な急進的で素朴なロマン主義的精神と言ってもいいだろう。
次に、「ゲーテの人間」は、「ルソーの人間」が浸った熱狂的な状態への「鎮静剤」である。「ゲーテの人間」はファウストによって象徴的に描かれている。ファウストは、一見したところでは、ルソー的なロマン主義的精神を体現しているようであるが、実は、決定的な行動を避けており、「ルソーの人間」とは異なっている。「ゲーテの人間」は「諦念」に基づいた「高次の様式における静観的人間」であり、「保守的調和的な力」を持っている。しかし、同時に彼にはたんなる俗物に成り下がってしまう危険性がある。あるいは、それは「ルソーの人間」によって体現されるロマン主義的精神が世俗的な現実社会によって挫折し、世俗的な現実社会との通俗的内面化による調停した結果の姿と言ってさしつかえないだろう。
最後に、「ショーペンハウアーの人間」は、「ゲーテの人間」に欠けているメフィストフェレース的な「悪」を保持している。そのため、「ショーペンハウアー的人間像がわれわれを鼓舞してくれる」。「ショーペンハウアー人間」は「ゲーテの人間」の「単に観想すること」に、さらに、人間の自己自身に対する「誠実」の能力を加えて持っている。「自己自身を認識された真理にいつでもその第一の犠牲として捧げ、どういう苦悩が自己の誠実から湧き出て来ざるをえないか」を見据え、それに従うことに生きる本質的な意味を認める人間が「ショーペンハウアーの人間」である。しかし、この「ショーペンハウアーの人間」は、人間の諸矛盾を顕在化させてしまうために、悪意ある皮肉屋として疎んじられてしまうことも少なくない。だが、彼の態度はたんなる弱者の悪意ではない。「ショーペンハウアーの人間」の持つ「否定や破壊」、さらにそこから派生してくる「苦悩」を自らわが身にひきうけることを忘れない。それにより、「ショーペンハウアーの人間」は、言葉や思想をたんなる観想や調和の視座に貶めることなく、真に現実的かつ活動的なものにする。「ルソーの人間」から「ゲーテの人間」への移行は成熟ではなく、通俗化、すなわち、はねっかえりが、たんに年をとるとともにすっかり落ち着いて、足を洗うという通俗化なのであり、「ショーペンハウアーの人間」への移行だけが成熟である。勉次の感じた孫蔵の主張の「罠」はこの通俗化にほかならない。「ショーペンハウアーの人間」への移行はたんに「ルソーの人間」が表わしているロマン主義への回帰ではなく、「ゲーテの人間」がもたらす鎮静化という「罠」に陥ることなく、その先にあるその精神の成熟する可能性の希求である。「ショーペンハウアーの人間」は「ルソーの人間」が抱く理想と憧れをそれが現実の中で容易には生き延びられないことを十分踏まえた上で、にもかかわらず、生の目標を「個々の生存をいかに肯定するか」に定めることによって、生き延びさせる可能性を求めている。
だが、そう解釈したとしても、主人公が「いま筆を捨てたら本当に最後だと思った」ということには謎が残る。父親はとにかく一度筆を捨てて働いてみて、その後で落ち着いた上で、それでも書く意欲が起こったら、また始めたらいいと言っている。父親が指摘するように、作家活動を一度休業して働いて、その後に、書くこともできるにもかかわらず、続けなければ、自分は終わりだと感じている。それは、意地や自尊心、虚栄心ではないし、書くことが好きだからでもない。一度筆を置いて他の仕事をメインにすると、何かが失われてしまう。筆を捨ててしまうと、本物の自分自身と偽者の自分自身をロマン主義的につくりあげ、内面に逃げこむという通俗的なことをするからである。また、共産党員であることを認めるか否かもこの次元にある。政治活動をするかしないかは行為であって、内面の問題ではない。他方、共産党に属しているか否かは行為ではなく、認知の問題であり、内面化の「罠」が潜んでいる。それに同意するとき、内面化が始まる恐れがある。主人公が結局その点を認めるのは、誰かに責任転嫁する可能性がなくなり、自己欺瞞・自己倒錯による内面化する危険性が失われたからである。日本の歴史上、柄谷行人の『近代日本の批評 昭和前期[Ⅰ]』によれば、初めて自己批判が問題になったのはマルクス主義においてである。中野の転向はこの自己批判である。一方、彼以外の転向者は自己憐憫・自己嫌悪を意味している。「近代人の自意識」を持つものたちにとって、内面の存在など自明の条件であり、内面化に対する抵抗など意味をなさない。しかし、中野にとっては、内面はニヒリズムの一種である。中野は、他のものとその違いに触れたとき、「錯乱」せざるを得ない。
中野が真に転向するのは転向声明を出したときではなく、父親との対話の弁証法によってである。中野は父親と対話をする前は「ショーペンハウアーの人間」ではなく、まだ「ルソーの人間」に近い。ここで「よくわかりますが、やはり書いて行きたいと思います」と言うとき、転向は主体の問題ではなく、意志の問題になる。転向者の中で転向を意志の問題としてとらえていたのは中野重治だけである。「恥知らず」なのかもしれないと思いながらも、「罠」を感じるがゆえに、書くことを意志する。そのとき、中野は、転向において、負い目を生み出すことなく、肯定的な生きることの価値を創造しようという意欲が明確に生じている。意志は自意識以前のものであり、その領域の問題として転向を把握するならば、そこに心理的・内面的説明は入りこむことができない。それにより、中野は転向において新たな価値を創造する。転向の価値基準はその意欲にある。意欲に価値基準を置くならば、転向のことで言い訳することなど不必要だろう。中野重治は意志の人間である。
実は、転向の問題が起こるはるか以前に、転向の問題に悩み、それが、最終的には、意志の問題と理解していた書き手がいる。夏目漱石である。
漱石は、一九〇五─〇六年の断片において、次のように書いている。
二個の者がsame spaceヲoccupyスル訳には行かぬ。甲が乙を追ひ払ふか、乙が甲をはき除けるか二法あるのみぢや。甲でも乙でも構はぬ強い方が勝つのぢや。理も非も入らぬ。えらい方が勝つのぢや。上品も下品も入らぬ図々敷方が勝つのぢや。賢も不肖も入らぬ。人を馬鹿にする方が勝つのぢや。礼も無礼も入らぬ。鉄面皮なのが勝つのぢや。人情も冷酷もない動かぬのが勝つのぢや。文明の道具は皆己れを調節する機械ぢや。自らを抑へる道具ぢや、我を縮める工夫ぢや。人を傷けぬ為め自己の体に油を塗りつける(の)ぢや。凡て消極的ぢや。此文明的な消極な道によつては人は勝てる訳はない。──夫だから善人は必ず負ける。君子は必ず負ける。徳義心のあるものは必ず負ける。清廉の士は必ず負ける。醜を忌み悪を避ける者は必ず負ける。礼儀作法、人倫王常を重んずるものは必ず負ける。勝つと勝たぬとは善悪、邪正、当否の問題ではない──power デある。──willである。
マゾヒストの谷崎潤一郎であれば、女の前に進んではいつくばり、踏んでくれることを乞い、恍惚の表情をして、「二個の者がsame spaceヲoccupyスル」ことは可能であると呟くところであり、彼には転向など問題にはならない。漱石のこの言葉が転向の問題を要約している。転向は「二個の者がsame spaceヲoccupyスル訳には行かぬ」という状態から生まれてくる。「二個の者がsame spaceヲoccupyスル訳には」行くのであれば、転向の苦悩は無意味になる。谷崎の弁証法は、中野とは逆に、下向きである。「二個の者」のいずれかを意識的に選びとれるものではない。転向は主体性、すなわち自意識による選択の問題ではない。どちらか「強い方か勝つ」という転向は強い=弱いという次元にあり、それは「善悪、邪正、当否の問題」てはない。それは健康=病気という衛生学基準である。「礼儀作法、人倫王常」などの既存のものに頼るものは、佐野や鍋山などのように、勝つことができない。そのため、転向は意志(will)や力(power)、すなわち「力への意志(will to power)」の問題にほかならない。
ニーチェは、『ツァラトゥストゥラはかく語りき』において、力への意志を次のように語っている。
わたしが生あるものを見いだしたかぎり、そこにはかならず力への意志があった。そして服従して仕えるものの意志のなかにさえ、支配者となろうとする意志があった。
弱者が強者に仕えるのは、より弱い者に対して支配者になろうとする弱者の意志が、かれを説き伏せるのだ。このよろこびだけは、かれは捨てようとは思わない。
そして、小さなものが、自分よりもっと小さなものに対して支配のよろこびと力を味わうために、自分より大きなものにみを捧げるのと同じように、最も大いなる者も、さらに身をささげるのであり、それは力のよろこびを味わうために──生を賭けるということになる。
すべての和解よりさらに高いものを、意志は意志しなければならない。意志は力への意志なのだ。──だが、どうして意志がそうするようになれるだろう? 誰一人意志にむかって、逆もどりして意志することを教えたものはいなかった。
力への意志が生の根源であるのは、生が「つねに自分で自分を克服しなければならないもの」であるからである。意識による解釈、自意識による選択は生を否定する。意識による価値基準を排して、意識によっては解釈されない根源的衝動性である力への意志を価値の根本の据える必要がある。「力への意志は解釈する(──機関の形成にさいして問題なのは解釈である)。すなわち、この意志は、度合いを、力の差異性を、限定し規定する。たんなる力の差異性はいまだ差異性としておのれを感じえないかもしれない。そこには生長しようと欲する何ものかが現存していて、このものが他のあらゆる生長しようと欲する何ものかをおのれの価値にもとづいて解釈するのでなければならない」(ニーチェ『力への意志』)。生が自己超克を企てるとき、意志は意志する。それこそが力への意志である。それよって生きている中野の行動が意識化されていないのは当然だ。
中野にとって、転向は自己超克である。彼以外の転向の場合、自己の同一性・一貫性・連続性の確保や保持のために転向が行われており、マルクス主義に固執するかそれ以前に回帰するか、すなわちどちらを真の自己とするかの違いだけで、自己超克からはほど遠い。転向は現にある人間の意識を意志を価値基準に置いて、超克することである。真の転向は、それによって、自己超克により自らの生を肯定することにほかならない。
さらに、ニーチェは、『ツァラトゥストゥラはかく語りき』において、そうした生の態度について次のように語っている。
苦痛はまたよろこびであり、呪いはまた祝福であり、夜はまた太陽なのだ、──去る者は去るがいい! そうでないものは学ぶがいい、賢者はまた愚者だということを。
あなたがたはかつて一つのよろこびに対して「然り」と肯定したことがあるのか? おお、わが友人たちよ、もしそうだったら、あなたがたはまたすべての痛みに対しても「然り」と言ったわけだ。万物は鎖でつなぎあわされ、糸で貫かれ、深く愛しあっているのだ。──
あなたがたがかつて、ある一度のことを二度あれと欲したことがあるなら、「これは気にいった。幸福よ! 束の間よ! 瞬間よ!」と一度だけ言ったことがあるなら、あなたがたは一切が帰って来ることを欲したのだ!
──一切を、新たに、そして永遠に、万物を鎖でつながった、意図で貫かれた、深い愛情に結ばれたものとして、おお、そのようなものとして、あなた方はこの世を愛したのだ!
──あなたがた、永遠のものたちよ、世界を愛せよ! 永遠に、また不断に。そして、痛みに向かっても「去れ、しかし帰って来い」と言うがいい。すべてのよろこびは──永遠を欲するからだ。
自分の持っている力を出しつくした上で、その結果として表われてきたものをあるがままに認め、肯定する。どんな生でもたった一回であっても、生が肯定される瞬間があったなら、「よろこび」によって、生や世界に対して「去れ、しかし帰って来い」と言い、それを「然り」と言い得るものにする。転向は、中野にとって、「命をかけた(?)のに自ら敗れたという経験」である。しかし、それは「もしわれわれかそうするために努力しとおすならば、第一義的な文芸実践の最も強い土台の一つ」となる。転向に対して何の自己倒錯・自己欺瞞を抱かず、あるがままに認め、それを自らに引き受けるとき、転向経験に「然り」と告げられる。転向はそうした倫理的規範と実存的側面の両面において、反復ではなく、反芻することによって、生の条件になる。
中野の転向は「旅」などではなく、「政治的移動」である(中野重治『わが杜甫のすべて』)。佐野や鍋山にとって、転向は故郷から出かけてまた戻ってきて、故郷を再発見するための「旅」にすぎなお。一方、小林多喜二や宮本百合子は故郷からかたくなに「旅」にでかけようともせず、異郷を知りもしない。彼らに対して、中野にとって、転向は故郷から異郷へ向かっての二度と戻ることのない「政治的移動」である。それは、むしろ、政治亡命と言ってもいいだろう。日本の知的なマルクス主義者の中で、実質的に、亡命したのは、転向を意志の問題として認識していた中野重治だけだ。彼は、ノスタルジーを拒絶して、時間的差異の中に自らの言葉を確立しようとする。自己とそれに対する否定的自己意識から防御する弁証法によって、時間が経つにつれ、流動的に彼の言葉は形成されていく。そのように形成された言語であるため、中野は原稿の初出時の間違い──単純な記憶違いでさえも──を訂正しない。一度書いてしまえば、時間的状況のため埋めることのできぬ隔りが確かにあり、その時点にはもう二度と戻ることはができない。中野にとって、転向はこうしたものだ。
確かに、理論とその思想家を必ずしも同一視することはできない。しかし、思想家の生き方は、知らず知らずのうちに、理論となってしまうものであり、理論は、思わぬ形で、思想家を束縛するものである。しかも、それはその思想家にとって認めたくないものであることのほうが多い。公に彼らが表明している立場を言語がその正反対の主張をも導き出し、その言語は思想家を逆に従わせてしまう。そうした事態をまったく顧みなかったり、それから自由であると考えていたりしていたら、これほどおめでたい話もそうめったにない。その思想家にできるのは、自由のない自分自身を笑い飛ばす自由があるだけである。
中野は決して「わかりにくい」わけではない。中野は自意識の人間でないだけだ。自意識の人間には彼は「わかりにくい」であろう。しかし、中野の魅力とその「わかりにくさ」は意志で生きているところにある。
中野は、『身分、階級と自我』において、自意識について次のように述べている。
しかもわれわれが自我という場合、われ・個の実在ということよりも、そのことの意識・自意識ということに重みを置いて問題はとらえられていものと私は思う。そうして、われわれにおいて重要なのは、意識でなくて実在であり、そういって言いすぎならば、実体とその活動とにいっそうの重要性があり、実体とその活動が弱い場合、またはそれが拘束された場合、自我とその意識とはそのものとして強まる傾向があるということを事実として言いたい。やや極端にいえば、自意識としての自我=自我意識の旺盛には、おそらく必ず、あるいはややもすれば、実体としての個の相対的衰弱と頽廃とがあるのではなかろうか。近代的自我と自我意識とは、少なくとも現実には、多弁なデカダンスに陥る危険を持っている。
中野にとって、「近代的自我と自我意識とは、少なくとも現実には、多弁なデカダンスに陥る危険」を持つ病的なるものである。彼は「近代的自我と自我意識」以上に、「実体とその活動」を重視する。それは「われ・個の実在」としての「活動」、すなわち意志である。中野は意志によって生きることを肯定する。自意識に対してはそこに自己欺瞞と自己倒錯を認め、「罠」を感じる。その転向の独自性を認めた吉本や柄谷は自意識の人間には到達できない何ものかを彼に見出している。中野は意志の人間だ。「わかりにくい」と見なす多くの文学者たちは病的であり、自意識の病にかかっている。自意識で生きていない人間にとって、すべては自分とは他なるものであり、自意識の持つ錯誤、すなわち他なるものの忘却に陥らない。そのため、中野は自意識の持つ生の否定という病を感ずることがない。
中野重治は、確かに、転向している。しかし、他のプロレタリア作家と比較するなら、それは、むしろ、亡命と考えるべきである。他の転向から中野を見るのではなく、転向を中野の作品を通して認識するとき、転向の本質が顕在化してくる。彼以外のものにとって、転向は主体の問題であり、それは彼らに何の変化ももたらしていない。ただ一人、転向を力と意志の問題として理解していた中野においてのみ、転向は自己超克となっている。それは生を肯定する。真の転向はそのような力への意志による。中野重治の『村の家』は転向を意志による生の肯定として語る作品にほかならない。
〈了〉
参考文献
中野重治、『本とつきあう法』、ちくま文庫、一九八七年
『中野重治全集』全28巻、筑摩書房、一九五九~八〇年
『現代文学大系36』、筑摩書房、一九六六年
『日本文学全集35 』、新潮社、一九六七年
『日本文学全集42』、集英社、 一九六九年
『日本現代文学全集70』、講談社、一九六九年
『日本の文学41』、中央公論社、一九七九年
柄谷行人、『終焉をめぐって』、講談社学術文庫、一九九五年
柄谷行人編、『近代日本の批評〈1〉昭和篇上』、講談社文芸文庫、一九九七年
坂口安吾、『坂口安吾全集』14~16、ちくま文庫、一九九一年
中野重治研究会編、『中野重治と私たち』、武蔵野書房、一九八九年
夏目漱石、『漱石文明論集』、岩波文庫、一九八六年
夏目漱石、『僧籍日記』、岩波文庫、一九九〇年
平野謙、『中野重治研究』、筑摩書房、 一九六〇年
福田恆存、『福田恆存評論集』3、新潮社、一九六六年
吉本隆明、『マチウ書試論・転向論』、講談社文芸文庫、一九九〇年
K・マルクス=F・エンゲルス、『ドイツ・イデオロギー』、真下信一訳、国民文庫、一九六五年
K・E・クレア=D・ハワード編、『レーニン以後のヨーロッパ・マルクス主義』、現代の理論社、一九七三年
ピーター・ゲイ、『自由の科学 ヨーロッパ啓蒙思想の科学』1・2、中川久定他訳、ミネルヴァ書房、一九八六年
ジェルジ・ルカーチ、『歴史と階級意識』、城塚登他訳、白水社、一九九一年
F・ニーチェ、『ニーチェ全集』4、9~10、12~13、15、ちくま学芸文庫、一九九三~九四年
Andrew Arato. The Young Lukaacs and the Origins of Western Marxism. Seabury Pr. 1979
『現代思想臨時増刊総特集 現代思想の109人』、青土社、一九七八年