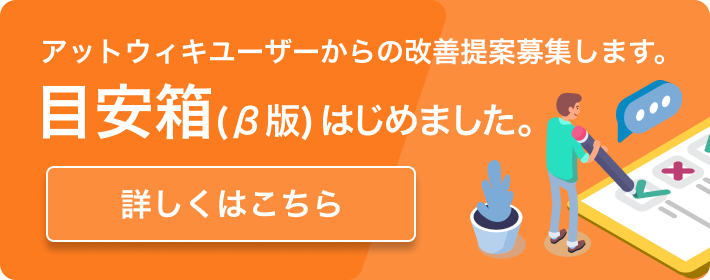夜の森――
ほとんどのポケモンは眠りについている頃。
聞こえるのはホーホーたちの鳴き声だけ……
ほとんどのポケモンは眠りについている頃。
聞こえるのはホーホーたちの鳴き声だけ……
その中で、飛び回るホーホーが一羽。
「ホーホー、見つけた?」
後ろから声をかけたのは、ユリだ。
ホーホーは首を横に振る。
残念そうに俯くユリの後からまた人物が現れる。
「なぁ、どうしてもゲットするのか?」
と、ハヤトが質問してきた。
ユリは頷く。
「うん。絶対捕まえたい。
ボク、ピッピ大好きだから!」
「ホーホー、見つけた?」
後ろから声をかけたのは、ユリだ。
ホーホーは首を横に振る。
残念そうに俯くユリの後からまた人物が現れる。
「なぁ、どうしてもゲットするのか?」
と、ハヤトが質問してきた。
ユリは頷く。
「うん。絶対捕まえたい。
ボク、ピッピ大好きだから!」
二人が夜の森の中彷徨っているわけ。
それは昼間、ユリが森へ入っていくピッピを見つけたからだ。
ユリが言うには、ピッピは以前からお気に入りのポケモンだったらしい。
おかげで日が沈み、月が昇っても、二人はまだピッピを探し回っていた。
それは昼間、ユリが森へ入っていくピッピを見つけたからだ。
ユリが言うには、ピッピは以前からお気に入りのポケモンだったらしい。
おかげで日が沈み、月が昇っても、二人はまだピッピを探し回っていた。
突然、ホーホーが鳴き声をあげる。
二人はハッと振り向いた。
「あ!」
反射的にユリが指差した。
その先に、薄桃色の小さな体が見受けられる。
「ピッピだ!」
そのユリの言葉がピッピを驚かせたらしい。
ピッピはビクッとして森の奥に駆け出す。
二人はハッと振り向いた。
「あ!」
反射的にユリが指差した。
その先に、薄桃色の小さな体が見受けられる。
「ピッピだ!」
そのユリの言葉がピッピを驚かせたらしい。
ピッピはビクッとして森の奥に駆け出す。
ユリは歓喜しながらピッピの後を追いかける。
「お、おいユリ、待っ」
慌てるハヤトにホーホーがぶつかり、ハヤトは体制を崩す。
すると、どうやら頭の上のムックルが起きてしまったらしい。
ねぼけたムックルはハヤトを攻撃し始めた。
つばさでうつがハヤトを襲ってる間にもユリは駆けていた。
ぐっすり眠るポケモンを掻き分けながら。
当然、ポケモンの方もたまったものではない。
するどく、荒い鳴き声が森中に響く。
ねむりから覚まされた怒りが、ポケモンを奮い立たせていく。
きりさかれる木々や砕かれる岩。
ちかくにいるユリは、まったく気づいていなかったが。
勿論、その目にはピッピしか写っていなかったわけだ。
だけど、その足もついに止まる。
ピッピが洞窟へと入っていったのだ。
洞窟の中は暗くてよく見えない。
ユリが入るのを躊躇っていると、ハヤトが追いついた。
「おい、ユリ!速く行け!」
急ぎの様子のハヤトに気づいて、ユリは不思議そうに振り向く。
「どうしたの?ハヤト。いったいなに――」
その時、ユリはようやく森中のポケモンの怒りに気づいた。
目前まで、目を血走らせたリングマたちが迫っていたのだ。
「ユリ!そこ、入るぞ!」
ハヤトはあのピッピの入った洞窟を指す。
有無を言わさず、二人は洞窟に突入していった。
暴れまわる野獣たちを背に、二人は暗闇へ紛れていく。
「お、おいユリ、待っ」
慌てるハヤトにホーホーがぶつかり、ハヤトは体制を崩す。
すると、どうやら頭の上のムックルが起きてしまったらしい。
ねぼけたムックルはハヤトを攻撃し始めた。
つばさでうつがハヤトを襲ってる間にもユリは駆けていた。
ぐっすり眠るポケモンを掻き分けながら。
当然、ポケモンの方もたまったものではない。
するどく、荒い鳴き声が森中に響く。
ねむりから覚まされた怒りが、ポケモンを奮い立たせていく。
きりさかれる木々や砕かれる岩。
ちかくにいるユリは、まったく気づいていなかったが。
勿論、その目にはピッピしか写っていなかったわけだ。
だけど、その足もついに止まる。
ピッピが洞窟へと入っていったのだ。
洞窟の中は暗くてよく見えない。
ユリが入るのを躊躇っていると、ハヤトが追いついた。
「おい、ユリ!速く行け!」
急ぎの様子のハヤトに気づいて、ユリは不思議そうに振り向く。
「どうしたの?ハヤト。いったいなに――」
その時、ユリはようやく森中のポケモンの怒りに気づいた。
目前まで、目を血走らせたリングマたちが迫っていたのだ。
「ユリ!そこ、入るぞ!」
ハヤトはあのピッピの入った洞窟を指す。
有無を言わさず、二人は洞窟に突入していった。
暴れまわる野獣たちを背に、二人は暗闇へ紛れていく。
「どうやら、だいぶポケモンたちから離れたようだな……おい。
ライトか何かないのか?」
「みえないからよくわからない。
はじめに買ってから一度も電池変えてないからどうにも」
「出口を探してみるか。仕方ない。
なぁ、そういえばピッピはどうなったんだ?」
「いるよ。この洞窟の中に」
そうして二人は、出口を探しながら歩き出す。
外だとまだ、夜行性のポケモンの鳴き声や、寝息などが聞こえてきた。
だが、洞窟の中は何にも聞こえない。
目を開けても閉じてもあまり差は無い。
不安が二人の体で渦巻く。
時々、ひんやりとした風を感じると、異常なまでにホッとするのだった。
ライトか何かないのか?」
「みえないからよくわからない。
はじめに買ってから一度も電池変えてないからどうにも」
「出口を探してみるか。仕方ない。
なぁ、そういえばピッピはどうなったんだ?」
「いるよ。この洞窟の中に」
そうして二人は、出口を探しながら歩き出す。
外だとまだ、夜行性のポケモンの鳴き声や、寝息などが聞こえてきた。
だが、洞窟の中は何にも聞こえない。
目を開けても閉じてもあまり差は無い。
不安が二人の体で渦巻く。
時々、ひんやりとした風を感じると、異常なまでにホッとするのだった。
何分歩いただろうか。
二人は前方で光が差し込む穴を見た。
逸りながら二人は穴から外へ出る。
実質、まだ洞窟の中なのだろう。
けど上にはぽっかりと穴が開いていて、そこから月光が差し込んでいる。
その光を受けているのは、大勢のピッピたちだ。
二人は前方で光が差し込む穴を見た。
逸りながら二人は穴から外へ出る。
実質、まだ洞窟の中なのだろう。
けど上にはぽっかりと穴が開いていて、そこから月光が差し込んでいる。
その光を受けているのは、大勢のピッピたちだ。
ピッピたちは寄り添いながら、上空を仰いでいる。
薄桃色の体は僅かばかり輝いているように見えた。
ふんわりとした白い光が空間を満たせている。
ユリとハヤトがいた洞窟の中とはうってかわって。
暖かそうな、安心して見ていられる雰囲気を醸し出している。
「……綺麗」
顔を紅潮させたユリが呟く。
「『つきのひかり』だな。回復しているようだ。
きっと睡眠の代わりになっているんだろう。
どうする?どれかゲットするのか?」
ユリは返答に困っているようだ。
ハヤトはそんなユリの様子をチラッと見て、暫く黙っていた。
薄桃色の体は僅かばかり輝いているように見えた。
ふんわりとした白い光が空間を満たせている。
ユリとハヤトがいた洞窟の中とはうってかわって。
暖かそうな、安心して見ていられる雰囲気を醸し出している。
「……綺麗」
顔を紅潮させたユリが呟く。
「『つきのひかり』だな。回復しているようだ。
きっと睡眠の代わりになっているんだろう。
どうする?どれかゲットするのか?」
ユリは返答に困っているようだ。
ハヤトはそんなユリの様子をチラッと見て、暫く黙っていた。
ふと気づくと、ユリの前に一匹のピッピが近寄っていた。
ユリは屈んで、ピッピに触れる。
(……あ、この子)
「この子、さっきボクたちの前に出てきたピッピだ」
「?わかるのか」
ハヤトが訝しげに聞く。
「うん」
ユリは頷くと、モンスターボールを取り出す。
ピッピは何も反抗しない。ただ、無垢な瞳でユリを見上げたままボールに収まった。
(この子、ボクたちをここに連れてきたかったのかな?)
ユリはそう思いながら、立ち上がる。
「さて、用は済んだんだ。さっさとここを出るぞ」
歩みだすハヤトの後を追って、ユリはその場を後にする。
何故だろう。見送っているピッピたちが応援しているように、ユリは感じた。
ユリは屈んで、ピッピに触れる。
(……あ、この子)
「この子、さっきボクたちの前に出てきたピッピだ」
「?わかるのか」
ハヤトが訝しげに聞く。
「うん」
ユリは頷くと、モンスターボールを取り出す。
ピッピは何も反抗しない。ただ、無垢な瞳でユリを見上げたままボールに収まった。
(この子、ボクたちをここに連れてきたかったのかな?)
ユリはそう思いながら、立ち上がる。
「さて、用は済んだんだ。さっさとここを出るぞ」
歩みだすハヤトの後を追って、ユリはその場を後にする。
何故だろう。見送っているピッピたちが応援しているように、ユリは感じた。
とある町――
ジムリーダーのデンジは青ざめていた。
(な、何者なんだ?この子……)
デンジの前で、クサイハナを戻す少女。
しずかだ。
「さぁ、バッジは?」
話しかけられて、デンジは急いでバッジを取りに戻る。
(……クサイハナ相手にオクタンが負けたのはわかる。
電気技は効果今ひとつだから、くらいにくいのもわかる。
なのになんで……なんでこんなに圧倒的な強さを感じるんだ?)
得体の知れない恐怖が、デンジの思考を蝕む。
ジムリーダーのデンジは青ざめていた。
(な、何者なんだ?この子……)
デンジの前で、クサイハナを戻す少女。
しずかだ。
「さぁ、バッジは?」
話しかけられて、デンジは急いでバッジを取りに戻る。
(……クサイハナ相手にオクタンが負けたのはわかる。
電気技は効果今ひとつだから、くらいにくいのもわかる。
なのになんで……なんでこんなに圧倒的な強さを感じるんだ?)
得体の知れない恐怖が、デンジの思考を蝕む。
(あの人がついていなかったら、クサイハナに進化するのが遅れていた。
まさか気づかない内に『かわらずのいし』を持っていたなんて、あたしにわかるわけないもの。
……ふふ、驚きはしたけど、これはこれでよかったのかもね)
しずかは微笑んでいた。
自分の欲望が満たされていく。それが、嬉しかった。
バッジを受け取ると、何も言わずにジムを後にする。
まさか気づかない内に『かわらずのいし』を持っていたなんて、あたしにわかるわけないもの。
……ふふ、驚きはしたけど、これはこれでよかったのかもね)
しずかは微笑んでいた。
自分の欲望が満たされていく。それが、嬉しかった。
バッジを受け取ると、何も言わずにジムを後にする。
「勝てましたか?」
外に出た直後に話しかけられ、しずかは右を向く。
「ええ。当然よ。ミカンさん」
すると、しずかの右のミカンは意を決したように頷く。
「では、これであなたの目的が終わったのですね」
「まだあるかも知れないけど……今のところはそうよ」
しずかの答えを受け、ミカンは話を進める。
「それでは一緒に来てもらいます。
鋼同盟本部へ」
目を見開くしずかだったが「なるほど」と呟く。
「こういう算段だったわけね。あたしについてきた理由は」
「わかっていましたか?」
「大体はね」
短く問答を終え、二人はポケモンセンターへ向かう。
満天の星空が、町を照らしていた。
外に出た直後に話しかけられ、しずかは右を向く。
「ええ。当然よ。ミカンさん」
すると、しずかの右のミカンは意を決したように頷く。
「では、これであなたの目的が終わったのですね」
「まだあるかも知れないけど……今のところはそうよ」
しずかの答えを受け、ミカンは話を進める。
「それでは一緒に来てもらいます。
鋼同盟本部へ」
目を見開くしずかだったが「なるほど」と呟く。
「こういう算段だったわけね。あたしについてきた理由は」
「わかっていましたか?」
「大体はね」
短く問答を終え、二人はポケモンセンターへ向かう。
満天の星空が、町を照らしていた。
ここはロケット団支部。
もっとも、すでに廃墟となっていたが。
そこに出木杉が現れ、再建したのだ。
自分専用の基地といったところか。
もっとも、すでに廃墟となっていたが。
そこに出木杉が現れ、再建したのだ。
自分専用の基地といったところか。
ロケット団本部にも、ギンガ団本部にも繋がるモニター室。
そこが出木杉の部屋でもあった。
そこが出木杉の部屋でもあった。
「出木杉さま~。今さっき一人最終ジムをクリアしましたよ~」
いきなりモニター室の扉が開けられる。
ぼさぼさの髪が広がっている猫なで声の少年だ。
その様子を見て、出木杉はただ笑うだけ。
「へぇ、意外と速かったな。メソウ、誰だそれは?」
「しずか、という女の子です~」
甘ったるい伸ばし声。でも、出木杉は何も感じていない様子だ。
「しずちゃんか。確かに彼女の実力は未知数だったなぁ。
たまに遊びに行くとポケモングッズがあったからもしや、と思ってたけど、これほどとは……
ところで、他の連中は?」
「全員三つ目のジムもクリアしてま~す」
出木杉は目を輝かせていた。
「予想以上のペースだ!これは面白くなってきた」
いきなりモニター室の扉が開けられる。
ぼさぼさの髪が広がっている猫なで声の少年だ。
その様子を見て、出木杉はただ笑うだけ。
「へぇ、意外と速かったな。メソウ、誰だそれは?」
「しずか、という女の子です~」
甘ったるい伸ばし声。でも、出木杉は何も感じていない様子だ。
「しずちゃんか。確かに彼女の実力は未知数だったなぁ。
たまに遊びに行くとポケモングッズがあったからもしや、と思ってたけど、これほどとは……
ところで、他の連中は?」
「全員三つ目のジムもクリアしてま~す」
出木杉は目を輝かせていた。
「予想以上のペースだ!これは面白くなってきた」
メソウが部屋をあとにして、出木杉は一人呟いた。
「博士。もうすぐあなたの野望が果たせそうだよ……」
ふと、出木杉はモニターをつける。
「博士。もうすぐあなたの野望が果たせそうだよ……」
ふと、出木杉はモニターをつける。
「はい。出木杉さま!」
出てきたのはロケット団の下っ端だ。
出木杉は「あれ?」と首を傾げる。
「サカキはどうした?」
「はっ!サカキさまは今、ジムに戻っていられますのでここには」
「回線を繋げ」
不満そうに出木杉が告げる。
「は?」「サカキのところへだ!下っ端と話す気などない」
あまりの気迫に、下っ端はたじろく。
「は、はい!今すぐに!」
暫く映像が途切れる。
出てきたのはロケット団の下っ端だ。
出木杉は「あれ?」と首を傾げる。
「サカキはどうした?」
「はっ!サカキさまは今、ジムに戻っていられますのでここには」
「回線を繋げ」
不満そうに出木杉が告げる。
「は?」「サカキのところへだ!下っ端と話す気などない」
あまりの気迫に、下っ端はたじろく。
「は、はい!今すぐに!」
暫く映像が途切れる。
やがて、回線が繋がり、モニターにサカキが現れる。
「どうされましたか?出木杉さま」
「ああ、サカキ。一言ジムに戻るなら言ってくれればよかったのに」
出木杉は〔さっきの下っ端との態度とまるで違い〕明るく言う。
「急用でしたのでつい」
「?なんだ急用って?」
「トレーナーです。ジムの者たちは歯が立たなかったようでしたので、私が相手することに。
その少年、ゲーム参加者の一人でスネ夫というそうです」
「どうされましたか?出木杉さま」
「ああ、サカキ。一言ジムに戻るなら言ってくれればよかったのに」
出木杉は〔さっきの下っ端との態度とまるで違い〕明るく言う。
「急用でしたのでつい」
「?なんだ急用って?」
「トレーナーです。ジムの者たちは歯が立たなかったようでしたので、私が相手することに。
その少年、ゲーム参加者の一人でスネ夫というそうです」
(ま~だかなぁ)
スネ夫はジム内のベンチで暇を持て余していた。
ジムのトレーナーは既に一掃してある。
全員チルットのうたうで眠っている。
あとはジムリーダーと戦い、バッジを貰うのみ。
それなのに、ジムリーダーが来るまで大分時間が経っていた。
さらに来てからも連絡があるとか何とかいって奥の扉に入ってしまった。
(くそ、僕をこんなに待たすなんて。
でも、確かあのジムリーダーは……)
「待たせたな、少年」
サカキが奥の扉から現れる。
「すまない。待たせてしまった」
スネ夫は定位置につこうとして、はたと止まる。
(ちょっと挑発してみようかな……クク)
悪知恵がスネ夫の頭を過ぎる。
すぐにスネ夫は実行に移した。
「別にいいんですよ。ロケット団の首領さん」
サカキはハッと息を呑んだが、目を閉じてにやりとする。
「そうか、少年。君もフスリの振興内にいたな。
確かに、私はロケット団元首領、サカキだ。だが今はもう違う」
「知ってるよ。出木杉でしょ」
スネ夫は愉快そうに口端を吊り上げる。
「……そうか、そこまで知っているのか。
だが、それが一体何になる?知っているからといってどうということは」
「簡単ですよ」(よーし、かかれ!)
「僕にジムバッジをください。
でないと、今から警察を呼びますよ?」
スネ夫はジム内のベンチで暇を持て余していた。
ジムのトレーナーは既に一掃してある。
全員チルットのうたうで眠っている。
あとはジムリーダーと戦い、バッジを貰うのみ。
それなのに、ジムリーダーが来るまで大分時間が経っていた。
さらに来てからも連絡があるとか何とかいって奥の扉に入ってしまった。
(くそ、僕をこんなに待たすなんて。
でも、確かあのジムリーダーは……)
「待たせたな、少年」
サカキが奥の扉から現れる。
「すまない。待たせてしまった」
スネ夫は定位置につこうとして、はたと止まる。
(ちょっと挑発してみようかな……クク)
悪知恵がスネ夫の頭を過ぎる。
すぐにスネ夫は実行に移した。
「別にいいんですよ。ロケット団の首領さん」
サカキはハッと息を呑んだが、目を閉じてにやりとする。
「そうか、少年。君もフスリの振興内にいたな。
確かに、私はロケット団元首領、サカキだ。だが今はもう違う」
「知ってるよ。出木杉でしょ」
スネ夫は愉快そうに口端を吊り上げる。
「……そうか、そこまで知っているのか。
だが、それが一体何になる?知っているからといってどうということは」
「簡単ですよ」(よーし、かかれ!)
「僕にジムバッジをください。
でないと、今から警察を呼びますよ?」
サカキは眉を吊り上げる。
「何を言っているのだ?少年。
そんなことできるわけが」
「残念だけど、僕は既に警察に知れ渡ってるんだ。
フスリの時に、町を救ったとしてね。
警察も僕の言うことを全く聞かないということは、無いんじゃないかなぁ~?」
(しめしめ、これでバッジをくれれば万々歳。でなければ……)
スネ夫が頭の中で算段している間に、サカキの顔が紅潮してくる。
「少年、この私をなめているのか?」
「何言ってるんですか。あなたが賢明なお人がどうか判断しているんですよ」
(さあ、できればYESと言って欲しいが)
「ふふ、少年。君はどうやら頭が切れるようだな」
サカキが不敵に笑う。
「……だが、私は自分なりに考えてみたよ。
そしてこれが私の答え。
少年、君がこの私から逃げられると思っているのか?」
(NOか!)
頭の中で舌打ちしてジムの外に駆け出すスネ夫。
その背後でポケモンが繰り出される。
「ダグトリオ、サイホーン!あいつを逃がすな!」
サカキの鋭い指示がスネ夫の耳にも届いた。
「ドガース!」スネ夫が繰り出す。「えんまく!」
ジムの入り口は煙が充満する。
「何を言っているのだ?少年。
そんなことできるわけが」
「残念だけど、僕は既に警察に知れ渡ってるんだ。
フスリの時に、町を救ったとしてね。
警察も僕の言うことを全く聞かないということは、無いんじゃないかなぁ~?」
(しめしめ、これでバッジをくれれば万々歳。でなければ……)
スネ夫が頭の中で算段している間に、サカキの顔が紅潮してくる。
「少年、この私をなめているのか?」
「何言ってるんですか。あなたが賢明なお人がどうか判断しているんですよ」
(さあ、できればYESと言って欲しいが)
「ふふ、少年。君はどうやら頭が切れるようだな」
サカキが不敵に笑う。
「……だが、私は自分なりに考えてみたよ。
そしてこれが私の答え。
少年、君がこの私から逃げられると思っているのか?」
(NOか!)
頭の中で舌打ちしてジムの外に駆け出すスネ夫。
その背後でポケモンが繰り出される。
「ダグトリオ、サイホーン!あいつを逃がすな!」
サカキの鋭い指示がスネ夫の耳にも届いた。
「ドガース!」スネ夫が繰り出す。「えんまく!」
ジムの入り口は煙が充満する。
今、町は戦場と化したのである――
(もしサカキがNOと言った場合、僕のとるべき道は一つ)
スネ夫は夜道を行く人々を掻き分けながら駆ける。
(警察で全てをばらす。
そうしてサカキを連行し、どさくさに紛れてバッジを奪う!
くぅ~!なんてナイスな作戦!我ながらしびれるぅ!!)
などと考えてる間に、追っては近づいていた。
遠くからサカキが指示を出す。
「ダグトリオ、マグニチュード!」
すばやいダグトリオは、既にスネ夫のすぐ後ろについていたのだ。
振動がスネ夫と周囲を巻き込む。
もちろん周りの人々も、突然の災害に慌てふためいていた。
「ドガース!こっちへ!」
スネ夫はドガースにつかまる。
すると、その体は浮き上がった。
「へへ、ドガースの特性は『ふゆう』。
地面に埋まったままのダグトリオの攻撃なんてもう」
「ロックブラストォ!」
スネ夫の背後から岩が無数に飛んでくる。
「くそ、サイホーンか!これはまず、うわぉ!」
岩の一つがドガースに激突する。
「とっしん!」
すかさず、サカキの指示。
空気をぶち抜く勢いでサイホーンが走ってくる。
落下するドガース目掛けて。
息を呑んで、スネ夫はドガースを蹴って上に跳ぶ。
「戻れ!」
スネ夫は空中でドガースを戻す。
スネ夫は夜道を行く人々を掻き分けながら駆ける。
(警察で全てをばらす。
そうしてサカキを連行し、どさくさに紛れてバッジを奪う!
くぅ~!なんてナイスな作戦!我ながらしびれるぅ!!)
などと考えてる間に、追っては近づいていた。
遠くからサカキが指示を出す。
「ダグトリオ、マグニチュード!」
すばやいダグトリオは、既にスネ夫のすぐ後ろについていたのだ。
振動がスネ夫と周囲を巻き込む。
もちろん周りの人々も、突然の災害に慌てふためいていた。
「ドガース!こっちへ!」
スネ夫はドガースにつかまる。
すると、その体は浮き上がった。
「へへ、ドガースの特性は『ふゆう』。
地面に埋まったままのダグトリオの攻撃なんてもう」
「ロックブラストォ!」
スネ夫の背後から岩が無数に飛んでくる。
「くそ、サイホーンか!これはまず、うわぉ!」
岩の一つがドガースに激突する。
「とっしん!」
すかさず、サカキの指示。
空気をぶち抜く勢いでサイホーンが走ってくる。
落下するドガース目掛けて。
息を呑んで、スネ夫はドガースを蹴って上に跳ぶ。
「戻れ!」
スネ夫は空中でドガースを戻す。
サイホーンはスネ夫の足元を掠め、高層ビルに激突する。
凄まじい破壊音が響く。
ビルは衝突箇所からひび割れ、崩れていく。
「ぅ、ぅわぁあ!!」
危機を感じたスネ夫は目を見開いて駆け出す。
間一髪、ビルは先ほどまでスネ夫がいた方向へ傾きそして――
「ぎゃぁあああ!!」「うわぁあああ!??」「ひぃぃいおああ――?!」
悲鳴が次々と、スネ夫の耳に飛び込んできた。
(やばいぞ絶対死人でたっての、マジやべえってこれ!!
で、でも足止めにはなったな……うわ、なんてこと考えているんだ僕は)
一喜一憂しているスネ夫の背後で、ドミノ倒しにビルが倒壊していく。
砂塵が巻き上げられ、アスファルトはめくれ飛び、絶叫が飛び交い――
凄まじい破壊音が響く。
ビルは衝突箇所からひび割れ、崩れていく。
「ぅ、ぅわぁあ!!」
危機を感じたスネ夫は目を見開いて駆け出す。
間一髪、ビルは先ほどまでスネ夫がいた方向へ傾きそして――
「ぎゃぁあああ!!」「うわぁあああ!??」「ひぃぃいおああ――?!」
悲鳴が次々と、スネ夫の耳に飛び込んできた。
(やばいぞ絶対死人でたっての、マジやべえってこれ!!
で、でも足止めにはなったな……うわ、なんてこと考えているんだ僕は)
一喜一憂しているスネ夫の背後で、ドミノ倒しにビルが倒壊していく。
砂塵が巻き上げられ、アスファルトはめくれ飛び、絶叫が飛び交い――
サカキは目の前の惨劇を目の当たりにして、思考が止まった。
自分のポケモンが町を壊してしまった。
最早栄光は、富や名声は塵となって消えたも同然。
……そんなサカキが考えられること。
それはこうなる前に、もっとも強く思っていたこと。
スネ夫を止める、いや、殺すこと。
「ダグトリオォ!サイホーン!!
あの少年を殺せえぇぇぃ!!」
サカキのいかれた声色が、ポケモンたちを駆り立てる。
自分のポケモンが町を壊してしまった。
最早栄光は、富や名声は塵となって消えたも同然。
……そんなサカキが考えられること。
それはこうなる前に、もっとも強く思っていたこと。
スネ夫を止める、いや、殺すこと。
「ダグトリオォ!サイホーン!!
あの少年を殺せえぇぇぃ!!」
サカキのいかれた声色が、ポケモンたちを駆り立てる。
「グラエナ!」
スネ夫はグラエナを繰り出し、その背に乗る。
(こっちの方が速いや)「走れぇ、交番まで!」
グラエナが駆け出すと共に、背後で爆発音がする。
スネ夫が振り向くと、猛進する二体の姿が見えた。
ダグトリオとサイホーンだ。
「まだ来るか!?こうなったら」
スネ夫はチルットを繰り出す。
「うたうで眠らせちまえ!!」
チルットの和やかな歌が、荒げる二体に向けられる。
その柔らかく、ゆったりとした歌は普通の生物なら簡単に眠っただろう。
だが、二体は止まらなかった。
スネ夫はしばらく粘ったが、観念して「グラエナ、チルット、行くぞ!」と走り出す。
(な、何でうたうが聞かない?
あいつらは凄いスピードで走っている。走って、……そうか!走っているからだな!!
自転車に乗りながら夕暮れの放送を聞いてると訳わからなくて思わず笑っちまうのと同じだ!!)
スネ夫が一人合点をついていると、後ろから声が届く。
「じしん!!」
恐怖の型破り全体攻撃の前兆によって、スネ夫は瞬時に青ざめる。
「と、跳べえグラエナ!」
スネ夫は必死に指示するが、それは無駄な足掻きだった。
周りの建物が倒壊する。人も、ポケモンも巻き込んで――
目の前で崩れ落ちる様々なものを前にして、スネ夫の耳は壮絶な破壊音しか聞こえなかった。
「ムウマぁ!」
スネ夫は最後の賭けで、ムウマを繰り出す。
「サイケこうせん!」
ムウマの攻撃が、倒壊する建物を支えている内に、スネ夫の意識は遠のいた。
スネ夫はグラエナを繰り出し、その背に乗る。
(こっちの方が速いや)「走れぇ、交番まで!」
グラエナが駆け出すと共に、背後で爆発音がする。
スネ夫が振り向くと、猛進する二体の姿が見えた。
ダグトリオとサイホーンだ。
「まだ来るか!?こうなったら」
スネ夫はチルットを繰り出す。
「うたうで眠らせちまえ!!」
チルットの和やかな歌が、荒げる二体に向けられる。
その柔らかく、ゆったりとした歌は普通の生物なら簡単に眠っただろう。
だが、二体は止まらなかった。
スネ夫はしばらく粘ったが、観念して「グラエナ、チルット、行くぞ!」と走り出す。
(な、何でうたうが聞かない?
あいつらは凄いスピードで走っている。走って、……そうか!走っているからだな!!
自転車に乗りながら夕暮れの放送を聞いてると訳わからなくて思わず笑っちまうのと同じだ!!)
スネ夫が一人合点をついていると、後ろから声が届く。
「じしん!!」
恐怖の型破り全体攻撃の前兆によって、スネ夫は瞬時に青ざめる。
「と、跳べえグラエナ!」
スネ夫は必死に指示するが、それは無駄な足掻きだった。
周りの建物が倒壊する。人も、ポケモンも巻き込んで――
目の前で崩れ落ちる様々なものを前にして、スネ夫の耳は壮絶な破壊音しか聞こえなかった。
「ムウマぁ!」
スネ夫は最後の賭けで、ムウマを繰り出す。
「サイケこうせん!」
ムウマの攻撃が、倒壊する建物を支えている内に、スネ夫の意識は遠のいた。
「……ねん、少年!」
間近で声を掛けられ、スネ夫は目を開ける。
目の前にはサカキがいた。
スネ夫は思わず身構えるが、思うように体が動かない。
「落ち着け、少年。これを見ろ」
サカキはなだめるようにそう言うと、手錠を抱えられた手首を見せる。
スネ夫はぽかんとして、辺りを見回す。
ここは病院のようだ。
部屋は純白に彩られ、窓の外からは赤い光がチカチカと差し込み、そしてスネ夫はベッドの中にいた。
「……い、いったい何が?」
スネ夫は自分の喉の枯れように驚きながらサカキを見る。
「少年。君はビルの倒壊の中、奇跡的に助かったらしい。
それはともかく、これを」
サカキが差し出したのはバッジだ。
スネ夫は息を呑み、サカキに確かめる。
「い、いいんですか?」
サカキは頷くと、スネ夫の手のひらにバッジを握らせる。
「この町を壊した時点で、ジムリーダーのサカキは死んだ。
私の負けの証として、君の勝ちの証として、このバッジを受け取って欲しい」
スネ夫は出来る限り力強くバッジを握る。
今、四つのバッジが揃った。
(あっけないや)
スネ夫は暫く空虚な気分に陥った。
間近で声を掛けられ、スネ夫は目を開ける。
目の前にはサカキがいた。
スネ夫は思わず身構えるが、思うように体が動かない。
「落ち着け、少年。これを見ろ」
サカキはなだめるようにそう言うと、手錠を抱えられた手首を見せる。
スネ夫はぽかんとして、辺りを見回す。
ここは病院のようだ。
部屋は純白に彩られ、窓の外からは赤い光がチカチカと差し込み、そしてスネ夫はベッドの中にいた。
「……い、いったい何が?」
スネ夫は自分の喉の枯れように驚きながらサカキを見る。
「少年。君はビルの倒壊の中、奇跡的に助かったらしい。
それはともかく、これを」
サカキが差し出したのはバッジだ。
スネ夫は息を呑み、サカキに確かめる。
「い、いいんですか?」
サカキは頷くと、スネ夫の手のひらにバッジを握らせる。
「この町を壊した時点で、ジムリーダーのサカキは死んだ。
私の負けの証として、君の勝ちの証として、このバッジを受け取って欲しい」
スネ夫は出来る限り力強くバッジを握る。
今、四つのバッジが揃った。
(あっけないや)
スネ夫は暫く空虚な気分に陥った。
「……少年。話したいことがある」
突然、サカキが改まった様子で言う。
「私は町中で君の様子を見ていた。
そして、この話を聞くのに相応しい人物だと、私は確信した」
(僕の町での様子?何か凄いことしてたっけ)
スネ夫は眉をひそめながら、話を待つ。
「……ロケット団ができて間もない頃だ。
遠い外国の高原で、団員の研究者が新種のポケモンを発見した」
サカキは、どこか遠くを見るように語りだす。
「そのポケモンを捕まえることは叶わなかったが、その体の一部は採取された。
そして研究者たちは、その採取した部分から遺伝子を取り出した。
やがて、研究によりその遺伝子は全てのポケモンの頂点に立つ種のものと判明したのだ。
ふふ、そうなると研究者たちは心を躍らした。
人間の飽くなき探求心がそんな考えを生み出したのだよ。
最強のポケモンを作ろう――とね」
一息、サカキはどこか物悲しそうにいれる。
スネ夫は黙って聞いていた。
何故か、ゲームでは完全無視していたのに、今はじっくり聞きたい。
サカキが伝えようとしていることをしっかり受け止めてやりたい。
「研究は成功した」
おもむろにサカキは告げる。
「最強の人造ポケモン。
それはあまりに強力で、横暴で、凶悪だった。
ロケット団の手では抑えられないほどに。
だからロケット団はそのポケモンを封印した。
扱えない兵器など要らないからな」
突然、サカキが改まった様子で言う。
「私は町中で君の様子を見ていた。
そして、この話を聞くのに相応しい人物だと、私は確信した」
(僕の町での様子?何か凄いことしてたっけ)
スネ夫は眉をひそめながら、話を待つ。
「……ロケット団ができて間もない頃だ。
遠い外国の高原で、団員の研究者が新種のポケモンを発見した」
サカキは、どこか遠くを見るように語りだす。
「そのポケモンを捕まえることは叶わなかったが、その体の一部は採取された。
そして研究者たちは、その採取した部分から遺伝子を取り出した。
やがて、研究によりその遺伝子は全てのポケモンの頂点に立つ種のものと判明したのだ。
ふふ、そうなると研究者たちは心を躍らした。
人間の飽くなき探求心がそんな考えを生み出したのだよ。
最強のポケモンを作ろう――とね」
一息、サカキはどこか物悲しそうにいれる。
スネ夫は黙って聞いていた。
何故か、ゲームでは完全無視していたのに、今はじっくり聞きたい。
サカキが伝えようとしていることをしっかり受け止めてやりたい。
「研究は成功した」
おもむろにサカキは告げる。
「最強の人造ポケモン。
それはあまりに強力で、横暴で、凶悪だった。
ロケット団の手では抑えられないほどに。
だからロケット団はそのポケモンを封印した。
扱えない兵器など要らないからな」
「それから暫くして、出木杉さまが現れた。
出木杉さまは何故か、その最強のポケモンのことを知っていた。
私は……それを隠した。
怖かったのだ。
だから出木杉さまもそのポケモンの居場所は知らない。
だが、手に入れようとしている!」
「サカキ、時間だぞ」
病室の扉の外から声がする。
警察だ。
「お願いだ、少年」
サカキは警察の声など聞こえないように話を続ける。
「そのポケモンが出木杉さまの手に渡ったらきっと大変なことになる!
それを食い止めてくれ!」
スネ夫はハッとする。
「あ、あんた出木杉に逆らうの?」
サカキは息を小さく捨てる。
「さぁな。だが、あんな小僧の手に渡っていい代物じゃないことは解っている」
「おい、サカキ!時間だ!速く出ろ!」
「少年、そのポケモンの居場所は――」
「サカキ!いい加減にしろ!」
警官が病室に雪崩れ込んでくる。
サカキが腕を掴まれる中、スネ夫の頭では、サカキの伝えた場所が反芻されていた。
(カデンの……洞窟)
そこへ出木杉が行くことを防ぐ。でなければ
《きっと大変なことになる!》
出木杉さまは何故か、その最強のポケモンのことを知っていた。
私は……それを隠した。
怖かったのだ。
だから出木杉さまもそのポケモンの居場所は知らない。
だが、手に入れようとしている!」
「サカキ、時間だぞ」
病室の扉の外から声がする。
警察だ。
「お願いだ、少年」
サカキは警察の声など聞こえないように話を続ける。
「そのポケモンが出木杉さまの手に渡ったらきっと大変なことになる!
それを食い止めてくれ!」
スネ夫はハッとする。
「あ、あんた出木杉に逆らうの?」
サカキは息を小さく捨てる。
「さぁな。だが、あんな小僧の手に渡っていい代物じゃないことは解っている」
「おい、サカキ!時間だ!速く出ろ!」
「少年、そのポケモンの居場所は――」
「サカキ!いい加減にしろ!」
警官が病室に雪崩れ込んでくる。
サカキが腕を掴まれる中、スネ夫の頭では、サカキの伝えた場所が反芻されていた。
(カデンの……洞窟)
そこへ出木杉が行くことを防ぐ。でなければ
《きっと大変なことになる!》
「サカキさん!」
スネ夫は連れ出されるサカキの背中に向かって叫ぶ。
「どうして、どうして話してくれたんです?僕なんかに」
サカキはスネ夫をちらりと見て、微笑む。
「君と、パートナーとの信頼の強さを見せてもらった」
(パートナー?……それってまさか)
「君が見つかった時そばにいたポケモン。
今頃ポケモンセンターに運ばれているだろう。力を尽くして」
「おい、行くぞ!」
警官が強引にサカキを連れ出す。
バタン、と扉が閉じられる。
残されたスネ夫は一人、思考を巡らせていた。
《君と、パートナーとの信頼の強さ》
《そばにいたポケモン》
《力を尽くして》
感情が洪水のように流れてきた。
スネ夫は駆り出される。感情の波に押されて。
病院を抜け出し、向かう先はポケモンセンター。
「ムウマ!」
スネ夫はセンターに入り、ジョーイさんに詰め寄る。
「ムウマ、ムウマは!?ムウマはどこに!?」
「お、落ち着いてください!」
ジョーイはスネ夫を抑えて、宥める。
「先ほどの騒ぎの被災ポケモンならあちらの部屋で」
話を聞き終わらない内に、スネ夫はジョーイの指した方向へ走る。
やがて扉が見えてきて、スネ夫はこじ開けた。
「ムウマ!」
スネ夫は連れ出されるサカキの背中に向かって叫ぶ。
「どうして、どうして話してくれたんです?僕なんかに」
サカキはスネ夫をちらりと見て、微笑む。
「君と、パートナーとの信頼の強さを見せてもらった」
(パートナー?……それってまさか)
「君が見つかった時そばにいたポケモン。
今頃ポケモンセンターに運ばれているだろう。力を尽くして」
「おい、行くぞ!」
警官が強引にサカキを連れ出す。
バタン、と扉が閉じられる。
残されたスネ夫は一人、思考を巡らせていた。
《君と、パートナーとの信頼の強さ》
《そばにいたポケモン》
《力を尽くして》
感情が洪水のように流れてきた。
スネ夫は駆り出される。感情の波に押されて。
病院を抜け出し、向かう先はポケモンセンター。
「ムウマ!」
スネ夫はセンターに入り、ジョーイさんに詰め寄る。
「ムウマ、ムウマは!?ムウマはどこに!?」
「お、落ち着いてください!」
ジョーイはスネ夫を抑えて、宥める。
「先ほどの騒ぎの被災ポケモンならあちらの部屋で」
話を聞き終わらない内に、スネ夫はジョーイの指した方向へ走る。
やがて扉が見えてきて、スネ夫はこじ開けた。
「ムウマ!」
バァ!――という感じで、目の前にムウマが現れた。
スネ夫は口を開けたまま腰を抜かす。
「ム、ムウマ?」
ケタケタと、相変わらずの笑い声が聞こえてくる。
間違いなくムウマの鳴き声。
スネ夫はいつもなら怒るところだ。
立ち上がり、ムウマを見据えて、そして――
(……あれ?)
頬を伝う感触に、スネ夫は首を傾げる。
(何だか熱いなぁ。目が……体が)
「こ、ヒクッ、このやろ、ム」
気がついた。
スネ夫は、自分が泣いていることに。
(な、何で泣くんだよ!僕は、僕は……)
「ム゛ウマ゛アァぁ!」
スネ夫は堪えきれず、ムウマに飛びついた。
ムウマは目を見開いていた。
スネ夫は口を開けたまま腰を抜かす。
「ム、ムウマ?」
ケタケタと、相変わらずの笑い声が聞こえてくる。
間違いなくムウマの鳴き声。
スネ夫はいつもなら怒るところだ。
立ち上がり、ムウマを見据えて、そして――
(……あれ?)
頬を伝う感触に、スネ夫は首を傾げる。
(何だか熱いなぁ。目が……体が)
「こ、ヒクッ、このやろ、ム」
気がついた。
スネ夫は、自分が泣いていることに。
(な、何で泣くんだよ!僕は、僕は……)
「ム゛ウマ゛アァぁ!」
スネ夫は堪えきれず、ムウマに飛びついた。
ムウマは目を見開いていた。
――この世界では、ゴーストタイプは特殊な存在だ。
姿も消せるし、物体を擦り抜けることも容易い。
だから、この世界でゴーストタイプに触れられることが出来る人間は
そのゴーストタイプのポケモンに認められているということなのだ――
姿も消せるし、物体を擦り抜けることも容易い。
だから、この世界でゴーストタイプに触れられることが出来る人間は
そのゴーストタイプのポケモンに認められているということなのだ――
スネ夫は涙が枯れるまで泣いていた。
いつも親にやっていたようなうそ泣きじゃない。本当の涙を流していた。
ムウマに抱きついたまま。
いつも親にやっていたようなうそ泣きじゃない。本当の涙を流していた。
ムウマに抱きついたまま。