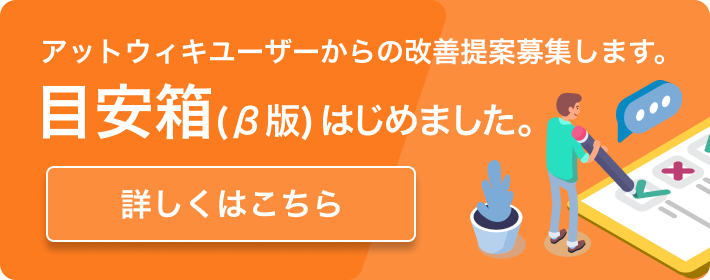深々。
降り積もる雪は白く、軽い。
夜の闇に雪の景色は、古ぼけた街道をモノクロに染めていく。
まるで褪せた写真のように味気ない背景は、時間の止まったような感覚すら覚えさせる。
冷えて行く温度が、周囲から全ての熱量を消し去るにつれて、現世からも隔離される浮遊感が、木製の建屋に染みていく。
町は眠っている。
何もかもを知らないで、ただいつもと同じだけの自分だと思っている。
その歴史情緒溢れる一角の、垣根の向こうに孕んだ物を知らないでいる。
きっと誰もが夢にも見ないのだろう。
変わることを。
変わってしまった事を。
止まる景色の中で、積み重なる白い嵩だけが、時間の経過を知って居た。
時計の音は小さく、意識しなければそのかち、かち、とした鼓動は聞き取れなかった。
どこまでも無音に思える周囲に、自分だけが溶け込んでいない。
灯りの無い室内は暗く、窓の外は白く。
まるで現実感を感じさせないものが、網膜を叩いている。
眠気が頭の中に広がってきたのを機会に、ようやく時計を確認して見たら、そろそろ日付の変わる頃合いだった。そろそろ明日の準備を済ませて、シャワーを浴びて髪の毛を乾かし、暖かいベッドに潜らなければ。だって明日だっていつも通りに学校はあるし、機能もあまり寝ていないし、大体、肌に悪い。
そもそもあまり几帳面な性分では無いし、片付けるのなら明日でもいいのではないか。
けれど床の汚れは今のうちに拭いておかないと、この年代物の畳に引導を渡してしまうだろう。第一これ、どうすれば取れるんだろう。染み抜きとか使ってどうにかなる物なのか、ちょっと解らない。
どこまでも無音に思える周囲に、自分だけが溶け込んでいない。
灯りの無い室内は暗く、窓の外は白く。
まるで現実感を感じさせないものが、網膜を叩いている。
眠気が頭の中に広がってきたのを機会に、ようやく時計を確認して見たら、そろそろ日付の変わる頃合いだった。そろそろ明日の準備を済ませて、シャワーを浴びて髪の毛を乾かし、暖かいベッドに潜らなければ。だって明日だっていつも通りに学校はあるし、機能もあまり寝ていないし、大体、肌に悪い。
そもそもあまり几帳面な性分では無いし、片付けるのなら明日でもいいのではないか。
けれど床の汚れは今のうちに拭いておかないと、この年代物の畳に引導を渡してしまうだろう。第一これ、どうすれば取れるんだろう。染み抜きとか使ってどうにかなる物なのか、ちょっと解らない。
そこまで考えて、妙に冷えた思考に驚きを覚えては見たが、こんなものか、という白けた感慨が続けて出てきてしまうのだ。中々薄情な物ではないか。
そもそも悲しんだり驚いたりする資格などあるのだろうか。今更しおらしいリアクションをしてみた所で、多分、全て遅い。でもただ一つ、弁明が許されるとすれば、別にこういった事を望んだ覚えなど一度も無かった筈なのだ。
退屈が嫌いで、飽きが溜まらないのは確かで、常に変化を求めて生きて来た。
それは貪欲と言うべき程ではあったが、だからと言って日常に安らぎを覚えない訳では、勿論無い。平凡な女子高生で有るのだ。そんな大それたことを望みはしない。
そもそも悲しんだり驚いたりする資格などあるのだろうか。今更しおらしいリアクションをしてみた所で、多分、全て遅い。でもただ一つ、弁明が許されるとすれば、別にこういった事を望んだ覚えなど一度も無かった筈なのだ。
退屈が嫌いで、飽きが溜まらないのは確かで、常に変化を求めて生きて来た。
それは貪欲と言うべき程ではあったが、だからと言って日常に安らぎを覚えない訳では、勿論無い。平凡な女子高生で有るのだ。そんな大それたことを望みはしない。
ただ、珍しい服とか、好きな歌手の新譜とか、少しばかり大人の真似事みたいな恋だとか、そういう物に憧れた程度。料理に混ぜる鷹の爪くらいの刺激があれば、きっと満足だったのではないか。
けれど目の前に在るのは、まるで劇薬だ。
鍋の中にぶちまけられたのは、胡椒や塩ではなく猛毒だ。
与えられた刺激が最後、御馳走様が南無阿弥陀仏。
妙な笑いが、口から洩れた。
妙な笑いが、口から洩れた。
ぬるりとした感触を、右手の中で握りしめる。手にしっかりと馴染む、持ちやすい柄と、園先につながる銀色の刃がきらりと光る。
畳の上に横たわる、肉色のズタ袋。
顎の下をずたずた。
腹の上をざくざく。
十七年の生活の中で、一度も見た事が無い家族の表情。
歪んだ顔。
けれど、もう動く事もない。呻く事もない。
私の眼には真っ赤に映る。
純白の窓の外。漆黒の部屋の中。
目の前だけが、深い赤。
汚れたキャンバスに、勢い任せにぶちまけた赤い絵の具。
闇の中で色が見えるわけもないのに、とてもとても鮮やかに、深紅に映る。
純白の窓の外。漆黒の部屋の中。
目の前だけが、深い赤。
汚れたキャンバスに、勢い任せにぶちまけた赤い絵の具。
闇の中で色が見えるわけもないのに、とてもとても鮮やかに、深紅に映る。
綺麗な、赤。
生まれて初めて綺麗と感じた赤。
だけど少し錆びたような
だけど少し錆びたような
―――赤銅の色。
▼
赤銅京都
▼
『赤銅色』
銅と金の合金である、赤銅を思わせる色。しゃくどういろ、もしくはあかがねいろ。
黒褐色肌や、髪の毛の色の形容として用いられる。
なお、赤銅に発熱処理を加えると、青紫がかった黒色に変色する――――――――
黒褐色肌や、髪の毛の色の形容として用いられる。
なお、赤銅に発熱処理を加えると、青紫がかった黒色に変色する――――――――
▼
青。
それが私にとっての絶対であり、崇拝対象となる。
それが私にとっての絶対であり、崇拝対象となる。
かつてシャガールの絵を視た時、私の頭は青に染められた。 優れた芸術というのは、その凄さが言葉で説明できなくても、心に響き、魂を穿つと言う。 少なくとも小学生のころ、まだ存命だった父と共に訪れた美術館で、私はその間隔を確かに味わった。
マルク・シャガールとは、とてつもなく綺麗な青色を使う画家で、私の美的センスの根底を固めたのは、まちがいなく彼なのである。
それからというもの、私の中で「青」は新しい物。特別な、新鮮な色としてインプットされた。
青は私にとって特別な色であると断言する。
マルク・シャガールとは、とてつもなく綺麗な青色を使う画家で、私の美的センスの根底を固めたのは、まちがいなく彼なのである。
それからというもの、私の中で「青」は新しい物。特別な、新鮮な色としてインプットされた。
青は私にとって特別な色であると断言する。
逆に古臭い物は、私の眼には赤茶けて映る。 まるで錆びた鉄のような、苦くて酸っぱくて、眼に痛い色。 鳥居の赤。夕焼けの赤。日の丸の赤。イライラする。
この街は真っ赤だ。大人も、子供も、同級生も、みんなみんな真っ赤な錆びだ。
新しい風の無い、死んだ空気の香りに、いつだって胸がむせる。焼けて焦げそうになる。
そんな赤さの象徴である私の名前など、最も強い嫌悪の対象でしかない。
この街は真っ赤だ。大人も、子供も、同級生も、みんなみんな真っ赤な錆びだ。
新しい風の無い、死んだ空気の香りに、いつだって胸がむせる。焼けて焦げそうになる。
そんな赤さの象徴である私の名前など、最も強い嫌悪の対象でしかない。
赤石 紅子。
ふざけた様な名前だが、れっきとした私の本名である。
生まれた瞬間に「紅く在れ」と言われているとしか思えないようなこの名前は、勿論全く好き」ではない。 この名前、近所にある稲荷の千本鳥居で出会った両親が、それにちなんで神様の加護が有るように、と名付けたそうだ。 だが自分の名前にどんな意味や願いが込められていようと、流石に首をかしげたくなるようなセンスじゃあないか。 おかげで私は「あかちゃん」等と言う不快極まりない仇名を賜り、小学生の時点で既に、名前を変えたい一心で強い結婚願望を抱いてしまうほど 捻くれた人格形成に一役買ってくれた。
そういう訳で思春期の私は、信心深い両親が嫌いで、要らん縁結びをした神様が嫌いで、ついでに古臭いこの街が大嫌いだった。
ここは四季に色づく町、古都、京都。
山河とビルが同居し、和と洋の建築が適合する風景。 現代と歴史が手を取り合って、この街の絶妙なバランスは出来ている。
住み慣れた人間でこそ有り触れたものと感じるそれは、本来とても特別な空間。
かつての都であるその町の表情は、如実に季節の色を反映する。
「忘れられた日本の姿」というものがこの街のセールスポイントであり、周知の認識でもあった。
生まれた瞬間に「紅く在れ」と言われているとしか思えないようなこの名前は、勿論全く好き」ではない。 この名前、近所にある稲荷の千本鳥居で出会った両親が、それにちなんで神様の加護が有るように、と名付けたそうだ。 だが自分の名前にどんな意味や願いが込められていようと、流石に首をかしげたくなるようなセンスじゃあないか。 おかげで私は「あかちゃん」等と言う不快極まりない仇名を賜り、小学生の時点で既に、名前を変えたい一心で強い結婚願望を抱いてしまうほど 捻くれた人格形成に一役買ってくれた。
そういう訳で思春期の私は、信心深い両親が嫌いで、要らん縁結びをした神様が嫌いで、ついでに古臭いこの街が大嫌いだった。
ここは四季に色づく町、古都、京都。
山河とビルが同居し、和と洋の建築が適合する風景。 現代と歴史が手を取り合って、この街の絶妙なバランスは出来ている。
住み慣れた人間でこそ有り触れたものと感じるそれは、本来とても特別な空間。
かつての都であるその町の表情は、如実に季節の色を反映する。
「忘れられた日本の姿」というものがこの街のセールスポイントであり、周知の認識でもあった。
だとしても、である。 京都と言う町に生まれた人間が、古風に育つとは限らない。 そもそもこの街が人気を持つのは、ありふれた文明社会に飽きた人が、「古い」という「新しさを求めているだけに過ぎない。
それは街の歴史を懐かしむノスタルジイなんてものではなく、やはり自分にとって非日常となる体験の刺激でしかない。 そういう刺激を好むなら、そこが京都でもタージ・マハールでも、趣味にさえ合えば、彼らは関係ないのだろう。
結局人間なんていうのは、自分の日常から脱却して、常に新しい何かを求める生き物なのだ。
それならば、人を最も苦しめて死に追いやる毒は、「退屈」であると断言できるんじゃないだろうか。
それは街の歴史を懐かしむノスタルジイなんてものではなく、やはり自分にとって非日常となる体験の刺激でしかない。 そういう刺激を好むなら、そこが京都でもタージ・マハールでも、趣味にさえ合えば、彼らは関係ないのだろう。
結局人間なんていうのは、自分の日常から脱却して、常に新しい何かを求める生き物なのだ。
それならば、人を最も苦しめて死に追いやる毒は、「退屈」であると断言できるんじゃないだろうか。
だから、田舎の人間が都会の華やかさに憧れ、都会の人間が田舎ののどかさを愛するように、
歴史の街で生まれた私が「新しさ」を求めてるのは当然の事だろう。 正直言って私は、この街の古臭い空気やはっきりしない住民、辺りに漂う、まるで夕暮れ時のような後ろ向きさに閉口している。 この新しい世紀に、この街ときたら、未だに恥の美学やら、暗喩の奥ゆかしさなんてものを有り難がっているのだから救えない。
そのくせ礼儀作法に五月蠅い旧型人間どもは、人への不満だけは一人前にコレクションしているのである。 NOと言えない日本人と言うやつが見たければ、此処にわんさか生息していると観光客に教えて差し上げたい。
歴史の街で生まれた私が「新しさ」を求めてるのは当然の事だろう。 正直言って私は、この街の古臭い空気やはっきりしない住民、辺りに漂う、まるで夕暮れ時のような後ろ向きさに閉口している。 この新しい世紀に、この街ときたら、未だに恥の美学やら、暗喩の奥ゆかしさなんてものを有り難がっているのだから救えない。
そのくせ礼儀作法に五月蠅い旧型人間どもは、人への不満だけは一人前にコレクションしているのである。 NOと言えない日本人と言うやつが見たければ、此処にわんさか生息していると観光客に教えて差し上げたい。
成長し、十七を数えた私は、この街からしてみればエキセントリックな人間といえる。
頭を茶髪に染め、海外のブランドを好み、常に先鋭的なファッションを好む様は、年齢的に珍しくはあるまい。 学生と言う人種はことさら、これらに敏感で、私にとっては正直、居心地のいい生活環境なのである。
赤石さんはいつもお洒落だね。
新しいことはいつも赤石さんが最初に見つけて来るんだよ。
しまいには、赤石さんが眼を付けた物は流行るとまで噂されている。
私自身、そう持て囃されることが嫌ではなかったのだが、だからといって皆の中心人物に祭り上げられると言うことはなかった。 それは私が積極的に、他人との関わり合いを避け続けていたからに他ならない。 だって、いくら学生で新しい物に憧れている連中だからと言って、根っこがやはりこの街の人間。 なぁなぁで周りに合わせ、空気を読み合い、異口同音で流行の尻尾だけ追っている。 真似をしても開拓しようと言う気持ちがさっぱりありゃしない。
頭を茶髪に染め、海外のブランドを好み、常に先鋭的なファッションを好む様は、年齢的に珍しくはあるまい。 学生と言う人種はことさら、これらに敏感で、私にとっては正直、居心地のいい生活環境なのである。
赤石さんはいつもお洒落だね。
新しいことはいつも赤石さんが最初に見つけて来るんだよ。
しまいには、赤石さんが眼を付けた物は流行るとまで噂されている。
私自身、そう持て囃されることが嫌ではなかったのだが、だからといって皆の中心人物に祭り上げられると言うことはなかった。 それは私が積極的に、他人との関わり合いを避け続けていたからに他ならない。 だって、いくら学生で新しい物に憧れている連中だからと言って、根っこがやはりこの街の人間。 なぁなぁで周りに合わせ、空気を読み合い、異口同音で流行の尻尾だけ追っている。 真似をしても開拓しようと言う気持ちがさっぱりありゃしない。
なにせ、あいつら根っこが古臭いのだ。