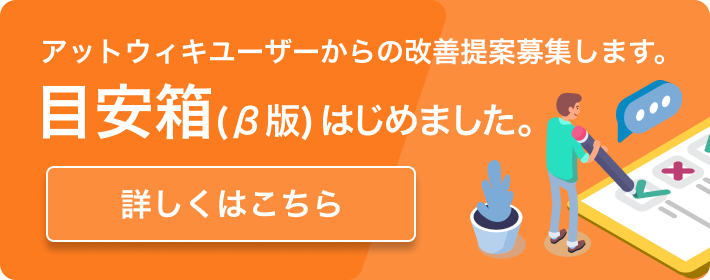邪気眼を持たぬものには分からぬ話 まとめ @ ウィキ
LAIKA:1
最終更新:
jyakiganmatome
-
view
1.
街中が真夜中でした。
家々の灯りはすっかり消えうせて、今は道の端に寂しく立った街灯だけが、ぼんやりと光を放っています。月は出ていません。空には薄い雲が満遍無く漂っていて、星の見えない曇り空でした。街灯の灯りは芒洋とした光の輪を地面に落とし、赤茶けたタイル張りの地面を浮かび上がらせています。そこはまだ古い趣を残した、外国の町並みでした。
そんな真夜中の街の中、一軒だけ、灯りのついた建物があります。
路地裏に少しだけ入ったところに、看板が出ていました。壁から生えた黒い鉄棒に、ねじれた鎖で木の板が吊るされいます。ぼろぼろな看板でしたが、そこには「バー・LIAR 宿泊も可」と書かれていました。看板が出ているその店は上半分がすり硝子になった、やっぱりボロボロなドアが入り口で、光はそこから漏れているのでした。
店内は、ドアから入って、向かって右の壁一面が横長なカウンター、左側が簡単なテーブルと椅子の空間になってます。入って正面奥には、2階へ上がるための階段になっていました。
カウンターの向こう側には、主人が座っています。痩せているけど背が高い、初老の犬の獣人でした。眼鏡を乗せ、バーテンダーのような服を着て、小さな椅子に腰掛けたまま、新聞を広げています。主人の背後の棚に置いてあるグラスや酒瓶は埃を被っていて、客もやる気も全く無いというのが丸わかりでした。主人の頭の上の壁には立派で古い針時計が掛かっていて、今の時間が午前1時だという事を告げていました。
主人は黙って、黙々と新聞に目を通しています。店内には、他に誰も居ません。2階は真っ暗で、泊まっている客も居ないようでした。閑古鳥が鳴いているという状況の見本のような状態でしたが、主人はむしろ静かで良いとでも言うように、ただただ新聞読み続けます。5分ほどでがさがさとページを捲り、最後まで読んだら、また最初に戻ります。どうやら読んでいるというよりは、どちらかと言うとただの暇つぶしのようでした。
家々の灯りはすっかり消えうせて、今は道の端に寂しく立った街灯だけが、ぼんやりと光を放っています。月は出ていません。空には薄い雲が満遍無く漂っていて、星の見えない曇り空でした。街灯の灯りは芒洋とした光の輪を地面に落とし、赤茶けたタイル張りの地面を浮かび上がらせています。そこはまだ古い趣を残した、外国の町並みでした。
そんな真夜中の街の中、一軒だけ、灯りのついた建物があります。
路地裏に少しだけ入ったところに、看板が出ていました。壁から生えた黒い鉄棒に、ねじれた鎖で木の板が吊るされいます。ぼろぼろな看板でしたが、そこには「バー・LIAR 宿泊も可」と書かれていました。看板が出ているその店は上半分がすり硝子になった、やっぱりボロボロなドアが入り口で、光はそこから漏れているのでした。
店内は、ドアから入って、向かって右の壁一面が横長なカウンター、左側が簡単なテーブルと椅子の空間になってます。入って正面奥には、2階へ上がるための階段になっていました。
カウンターの向こう側には、主人が座っています。痩せているけど背が高い、初老の犬の獣人でした。眼鏡を乗せ、バーテンダーのような服を着て、小さな椅子に腰掛けたまま、新聞を広げています。主人の背後の棚に置いてあるグラスや酒瓶は埃を被っていて、客もやる気も全く無いというのが丸わかりでした。主人の頭の上の壁には立派で古い針時計が掛かっていて、今の時間が午前1時だという事を告げていました。
主人は黙って、黙々と新聞に目を通しています。店内には、他に誰も居ません。2階は真っ暗で、泊まっている客も居ないようでした。閑古鳥が鳴いているという状況の見本のような状態でしたが、主人はむしろ静かで良いとでも言うように、ただただ新聞読み続けます。5分ほどでがさがさとページを捲り、最後まで読んだら、また最初に戻ります。どうやら読んでいるというよりは、どちらかと言うとただの暇つぶしのようでした。
主人が2回ページを捲った時です。からん、とドアについていたベルが鳴りました。
新聞の方向から顔は動かさずに、目線だけを、主人はドアへ向けました。
そこには獣人の少女が立っていて、店内の様子を伺っていました。恐らく種類はオオカミで、年齢は9歳か10歳、もしくはそれより少し上でしょうか。「少女」と「幼女」の中間ほどでした。赤くて厚いコートを着て、深くフードを被っています。髪は暗い色のぼさぼさしたブロンドで、それなりの長さがありました。そのせいで顔が見え辛いですが、幼いながらも整った、可愛らしい顔立ちをしています。しかしその表情は幼さとはかけ離れた精悍さがあり、それはどこか切羽詰ったような印象を主人に与えました。身に付けているものは全部薄汚れていて旅人のような風貌ですが、それにしては手ぶらなのが不思議な、どこかちぐはぐで捉え所の無い印象の持ち主です。
主人は新聞に視線を戻しました。どうやら、客が居ようがやる気はないようです。
少女がゆっくりとカウンターの主人に向かって歩いてきました。頑丈な造りのブーツを履いているせいで、こつこつと高い足音がします。少女が目の前まで来ると、主人は新聞をがさがさ捲りながら、面倒くさそうに、
「こんな時間に何の用だ、お穣ちゃん。泊まりか? まさか酒じゃないだろう」
少女は、一泊させて、とだけ言って、カウンターの上に泊まれるだけのお金を置きました。それはとてもその年頃の少女が持てるような金額ではありませんでしたが、主人はそれを見ると黙って立ち上がりました。そして壁の棚の引き出しから鍵をひとつ取り出すと、背中ごしに少女に向けて投げました。そこには「301」と書かれていて、どうやら部屋の番号のようでした。
「勝手に泊まってきな。うちは食事はつかないからな。シャワーは湯が止まったらそれまでだ。鍵はかかる」
少女はお礼を言って、すぐに階段を登っていきます。2階分の階段を登る足音が段々小さくなって、やがて扉を開け閉めする音と、鍵のかかる音が聞こえました。
しばらくして、すぐにシャワーを使っているらしい水音が、うっすらと聞こえ始めました。その音を遠くに聞きながら、主人はカウンターから出て、部屋の隅に置いてあった電話をとり、どこかに電話をかけ始めました。
新聞の方向から顔は動かさずに、目線だけを、主人はドアへ向けました。
そこには獣人の少女が立っていて、店内の様子を伺っていました。恐らく種類はオオカミで、年齢は9歳か10歳、もしくはそれより少し上でしょうか。「少女」と「幼女」の中間ほどでした。赤くて厚いコートを着て、深くフードを被っています。髪は暗い色のぼさぼさしたブロンドで、それなりの長さがありました。そのせいで顔が見え辛いですが、幼いながらも整った、可愛らしい顔立ちをしています。しかしその表情は幼さとはかけ離れた精悍さがあり、それはどこか切羽詰ったような印象を主人に与えました。身に付けているものは全部薄汚れていて旅人のような風貌ですが、それにしては手ぶらなのが不思議な、どこかちぐはぐで捉え所の無い印象の持ち主です。
主人は新聞に視線を戻しました。どうやら、客が居ようがやる気はないようです。
少女がゆっくりとカウンターの主人に向かって歩いてきました。頑丈な造りのブーツを履いているせいで、こつこつと高い足音がします。少女が目の前まで来ると、主人は新聞をがさがさ捲りながら、面倒くさそうに、
「こんな時間に何の用だ、お穣ちゃん。泊まりか? まさか酒じゃないだろう」
少女は、一泊させて、とだけ言って、カウンターの上に泊まれるだけのお金を置きました。それはとてもその年頃の少女が持てるような金額ではありませんでしたが、主人はそれを見ると黙って立ち上がりました。そして壁の棚の引き出しから鍵をひとつ取り出すと、背中ごしに少女に向けて投げました。そこには「301」と書かれていて、どうやら部屋の番号のようでした。
「勝手に泊まってきな。うちは食事はつかないからな。シャワーは湯が止まったらそれまでだ。鍵はかかる」
少女はお礼を言って、すぐに階段を登っていきます。2階分の階段を登る足音が段々小さくなって、やがて扉を開け閉めする音と、鍵のかかる音が聞こえました。
しばらくして、すぐにシャワーを使っているらしい水音が、うっすらと聞こえ始めました。その音を遠くに聞きながら、主人はカウンターから出て、部屋の隅に置いてあった電話をとり、どこかに電話をかけ始めました。
主人は電話を終えると溜息をつき、
「悪いな、お穣ちゃん。俺も仕事なんだ」
カウンターに戻って椅子に腰掛けると、新聞を広げました。
「悪いな、お穣ちゃん。俺も仕事なんだ」
カウンターに戻って椅子に腰掛けると、新聞を広げました。
2.
だいたい1時間たちました。
また、店のベルが鳴りました。今度は少女ではなくて、大きな身体をした獣人の男が入ってきました。
まるで軍人のようないかつい顔つきの、どうやら大型の犬の獣人です。そしてその体躯もまた、軍人のようでした。かといって身体が引き締まっているわけではなく、まるで筋肉と脂肪で身体が膨れ上がってしまったかのような、そんな体型でした。背中には、小ぶりなバッグを背負っています。大男はずかずかとカウンターまで来ると、椅子にどっかりと座りました。大男が座ると、小さな椅子が更に小さくなったかのように思えます。
「よう。で、どうなんだ。上玉なんだろうな?」
にやにや笑いながら、大男が聞きました。主人は大男のその下卑たような笑い顔を見て、傍目には分かりませんが、少しだけ顔をしかめました。どうやら主人はこの大男が嫌いなようでしたが、大男はそれに気付いていないようです。主人は黙って、ポケットから鍵を取り出してカウンターに置きました。鍵の札には「301」と書かれています。
「3階のいつもの部屋だ。小さい子で、9歳か10歳だ。雌の、多分オオカミだろう。旅人かと思ったが、荷物は無かった。武器は持ってるかどうか分からんが、注意しろよ」
主人の注意を聞いて、大男は鼻で笑いました。
「おいおいお前、冗談だろ。オンナノコ? そんなの銃持ってたって怖かねぇよ。一回腕でも何でも押さえちまえばお終いだって。……寝てるんだろ?」
主人は、多分な、と答えました。少女の寝ている部屋からはあのあとすぐに物音一つしなくなって、部屋の前まで行って耳を済ませてみても、やっぱり音はしませんでした。大男はそれを聞いて、また下品に笑いました。
「雌ってのはいいな。すげぇいいよ。売れる相手が多くなるからよ」
「早く行け」
「へへへ……なあおい、ヤっちまっていいんだろ?」
「好きにしろ。お前の『商品』だろう。俺は知らん。ただし、部屋は汚すな」
大男はまた、一層下品に笑いました。そして立ち上がって、右のポケットに入っている小型の拳銃を確認しました。
「じゃあちょっとよ、部屋借りるぜ。できるだけすぐ終わらせるからよ」
「お前が早漏じゃないのは知ってる。でも急げよ」
大男はにやにや笑いを浮かべたまま、バッグを担ぎなおして、静かに階段を登っていきました。こういう事に慣れているのか、その身体からは想像できないほど、足音はしませんでした。
その巨体が階段の闇に消えるのを主人は見送って、
「……」
しかめっ面のまま椅子に座ると、新聞を広げました。
また、店のベルが鳴りました。今度は少女ではなくて、大きな身体をした獣人の男が入ってきました。
まるで軍人のようないかつい顔つきの、どうやら大型の犬の獣人です。そしてその体躯もまた、軍人のようでした。かといって身体が引き締まっているわけではなく、まるで筋肉と脂肪で身体が膨れ上がってしまったかのような、そんな体型でした。背中には、小ぶりなバッグを背負っています。大男はずかずかとカウンターまで来ると、椅子にどっかりと座りました。大男が座ると、小さな椅子が更に小さくなったかのように思えます。
「よう。で、どうなんだ。上玉なんだろうな?」
にやにや笑いながら、大男が聞きました。主人は大男のその下卑たような笑い顔を見て、傍目には分かりませんが、少しだけ顔をしかめました。どうやら主人はこの大男が嫌いなようでしたが、大男はそれに気付いていないようです。主人は黙って、ポケットから鍵を取り出してカウンターに置きました。鍵の札には「301」と書かれています。
「3階のいつもの部屋だ。小さい子で、9歳か10歳だ。雌の、多分オオカミだろう。旅人かと思ったが、荷物は無かった。武器は持ってるかどうか分からんが、注意しろよ」
主人の注意を聞いて、大男は鼻で笑いました。
「おいおいお前、冗談だろ。オンナノコ? そんなの銃持ってたって怖かねぇよ。一回腕でも何でも押さえちまえばお終いだって。……寝てるんだろ?」
主人は、多分な、と答えました。少女の寝ている部屋からはあのあとすぐに物音一つしなくなって、部屋の前まで行って耳を済ませてみても、やっぱり音はしませんでした。大男はそれを聞いて、また下品に笑いました。
「雌ってのはいいな。すげぇいいよ。売れる相手が多くなるからよ」
「早く行け」
「へへへ……なあおい、ヤっちまっていいんだろ?」
「好きにしろ。お前の『商品』だろう。俺は知らん。ただし、部屋は汚すな」
大男はまた、一層下品に笑いました。そして立ち上がって、右のポケットに入っている小型の拳銃を確認しました。
「じゃあちょっとよ、部屋借りるぜ。できるだけすぐ終わらせるからよ」
「お前が早漏じゃないのは知ってる。でも急げよ」
大男はにやにや笑いを浮かべたまま、バッグを担ぎなおして、静かに階段を登っていきました。こういう事に慣れているのか、その身体からは想像できないほど、足音はしませんでした。
その巨体が階段の闇に消えるのを主人は見送って、
「……」
しかめっ面のまま椅子に座ると、新聞を広げました。
大男は部屋の鍵を静かに回して、開けました。かちゃりと小さな音が、静まり返った廊下に響きます。大男は念のためにそのままたっぷりの時間待ってから、そろりとノブを回して、ドアを開けました。
部屋の中は薄暗い空間でした。広くはありませんが、家具も何も無いせいで、がらんとして見えます。入ってすぐ左手にはシャワールームのドアがあり、少し奥に入ると、簡単な机とベッドが置かれたスペースになっています。ベッドは一番奥の壁際に置いてあって、その上の壁には嵌め殺しの窓がありました。さっきまで空を覆っていた雲は段々晴れてきていて、今は少しですが星も見えています。部屋が薄明るいのは、カーテンの無いその窓から、ぼんやりと月の光や、街灯の光が入ってきているからなのでした。
少女はベッドで眠っているようでした。
大男はバッグを一度床に降ろして、そこからロープや、手錠や、ガムテープを取り出しました。『商品』を“梱包”するための道具です。バッグの中には他にも『商品』を入れるための大きな布袋なども入っていましたが、そちらには縛ってから『商品』を入れるので、今はまだ取り出しません。
足音を立てずに、部屋に入ります。静かにドアを閉めると、後ろ手で鍵をかけました。慎重にやったので、ほとんど音はしませんでしたが、大男はここでも念のために、しばらく時間を置きました。
その間に、大男は少女の様子を観察します。ベッドの上の布団は小さく膨らんでいて、一定の間隔で上下に動いていました。耳を済ませれば、小さく整った寝息も聞こえてきます。ベッドの横には脱いだらしいブーツが並んでいて、テーブルの上には畳まれたコートや、ズボンや、下着まで置いてありました。どうやらシャワーを浴びて、そのままベッドに入って寝てしまったようです。部屋の中にはまだシャワーの水の匂いが残っていて、その湿気のせいか、少しだけ生暖かいように感じられました。
大男はゆっくりと歩き出して、少女に近付きます。テーブルの横まで来たところで、その上に持っていたロープやガムテープや手錠を、静かに置きました。視線はずっと少女を見ています。大男はズボンのポケットから小さな拳銃を取り出して、右手に持ちます。そのまま左手だけで、器用にズボンと下着を脱ぎました。大男の股間についているそれは既に怒張し切っていて、平均的なそれの大きさよりも、二回りほど大きな巨根でした。少女は相変わらず、静かに寝息を立てています。
大男は拳銃の安全装置を外すと、まだ引金に指はかけないまま握り締め、そろりとベッドの横に立ちました。薄明かりに浮かんでいる少女の横顔は、大男が想像していたよりもずっと可愛らしく愛らしく、彼の興奮を煽りました。
大男は務めてゆっくりとその布団に手を掛け、そして、掴んだ瞬間一気に引き剥がしました。そこからは打って変わってとても素早い動作で動き、大男はあっという間に少女の両腕を左手ひとつで纏め上げると頭の上に押さえ込み、拳銃越しに右手でその口を押え、悲鳴を上げられないようにしました。
少女が目を覚ましました。最初は驚いたように大男を見上げていましたが、すぐにその右手に握られている拳銃に気付いたようで、動きが止まります。大男は少女のその様子に気をよくしたようで、
「へへっ……そうそう、イイ子にしとけよ。俺だって『商品』は綺麗に扱いたいんだよ。見えるだろ? 何だか分かるよな? だったら静かにしてろ。叫ばないって約束してくれるならよ、右手だって離してやる」
少女は、
「…………」
しばらく大男を黙って見ていましたが、やがて頷きました。
「よーしよし……いいか、少しでも大声出したら殺すからな」
大男は注意しながら、少女の口を塞いでいた右手を、拳銃と一緒に剥がしました。左手はまだ、少女の両腕をその頭の上に押さえつけてます。少女は叫び声を上げませんでしたが、かといって特別に怯えた様子も見せず、そのやや吊りあがった、大きくて金色をした丸い眼で、大男をじっと見ています。大男はその従順だけれど反抗的な所に、更に気を良くします。
にやにやと笑いながら、大男は少女の身体を嘗め回すようにして観察し始めました。自分の身体の下の少女はとても小さく、今はシャツ1枚の姿です。黒と白の横縞模様の、だぼだぼな7分袖のシャツだけを着ています。ワンピースよりも丈が短いので、少女の幼く太い脚の間にぷっくりと浮かんだ秘所も、半分ほど見えていました。大男のそれが、また硬くなりました。大男はやや特殊な嗜好の持ち主でした。
大男は、少女が叫んだり舌を噛んだりしないように、その口の中にハンカチを詰め込みました。すると次は拳銃が少女のシャツの裾の下に入り込んで、捲り上げていきます。下から順番に、細く幼い割れ目と、くびれの無い太い腰と下腹と、臍と、左右対称に6つある乳首が現れました。首元までシャツを捲くられると、少女はそこで初めて大男から眼を離して横を向きました。大男は、少女のその未発達で、まるで幼児のような身体と、更にそれと吊り合わない大人っぽい動作に一層興奮したらしく、我慢できないとでも言うように少女の膝の下に自分の腕を入れると一気に持ち上げて、露になったその小さい裂目に自分の先端を押し当てました。少女はそっぽを向いたまま、別段抵抗しません。
しかし大男の一物がその入り口を押し広げて中へと侵入してくると、その顔が痛みに歪みました。大男のそれは、少女の小さい膣には大きすぎるほどでした。でも大男はそんな事は意にも介さずに、止まらず奥まで突き刺しました。少女のうめき声が大男の耳にも届いて、大男は身体を震わせて悦楽します。そのまま、すぐに大男は腰をゆっくり前後に動かし始めました。
一回動くごとに、少女が声を出します。だけどその声ははっきりした意味の無い、まるで泣き声のような声でした。大男は右手に拳銃を握っているせいで少しやり辛そうにしながら、それでも少女のその狭苦しい肉の感触に心を奪われているようで、何度も何度もその中で自分の一物を往復させます。そのうちに、大男の動きはどんどん速くなっていって、少女のうめき声は一層大きくなってきました。大男は少女を好きなように犯しながら、
「へへっ、なあおい、俺はよ、別に悪い事してる訳じゃねぇんだよ……どうせお前さん、これから売られたらよ、毎日毎日これなんだからな。だからな、俺が最初に、何されても平気になるように教えておいてやるんだよ。これからどういう生活する事になるかさ。……ああでもな、お前さんならよ、心配しなくてもな、多分平気だよ……これだけ具合良けりゃよ、貰い手なんて幾らでも出てくるしな。ほらっ、もっと善がれって、気持ちよくなっておかないとな、これから大変だからさ。毎日毎日、自分からケツ突き出して穴広げて、ご主人様犯してくださいって言うだけの暮らしになるんだぜ、お前」
大男は好きなように少女を蔑みながら、その奥を突き上げ続けました。少女はその言葉には反応しないで、ただ突き上げられるたび、声を上げました。気が付けばその声には、痛み以外の、犯される快感による嬌声が混ざり始めていました。大男はそんな少女をいたく気に入ったようで、いい子だと褒めながら、その首筋や頬を舌で舐めて、一層激しく動きます。古いベッドは大男が動くたびにぎしりぎしりと軋み、その音が少女の喘ぎ声と混ざりながら、狭い部屋に響きました。少女の表情がやがて悩ましげなものになり始め、その手がシーツを握り締め始めます。大男は腰を振りつつ少女の腕から左手を離して、その開いた手で、少女の乳首をつねって引っ張りました。少女の身体が小さく震えました。大男は、こっちでも感じるのかこの淫乱めだとか、そんな言葉で少女を更に責めます。
やがて、少女の身体を好きなように蹂躙していた大男の口数が段々少なくなってきて、どうやら絶頂が近いらしい事が分かりました。その口からは涎が垂れていて、涙を浮かべた少女の赤く染まる頬に垂れ落ちました。
大男は拳銃をベッドの上に置くと、両手で少女の腰を掴み、持ち上げました、簡単に持ち上げられた少女の腰を前後に動かしながら、自分は今までで一番激しく腰を叩きつけました。少女が一際大きくその身体を仰け反らせて、ついに大きな悲鳴が上がりました。しかし大男はまるでそういう器具であるかのように少女を扱い、既に慣れきったその狭い膣の肉が裏返りそうなほど勢い良く、自らの一物を出し入れします。水音といっしょに、手拍子するような音が響きました。
大男が少女を抱え込むように身体を丸めて呻いて、その行為が終わった事を告げました。少女と大男の隙間からは、少しだけ血の混じった、どろりとした液体が流れ出してきました。
暫くの間、大男は少女を抱えたまま、その中に自分の欲望の全てを吐き出し続けていました。しかし数分経つとようやく満足したのか、やっと顔を上げて、満足そうな下品な笑いを浮かべながら、自分にたった今犯されたこの愛くるしい少女の顔を見ておこうと視線を下ろしました。こいつなら、或いは自分が買い取って、延々と飼ってやってもいいと、そうも考えていました。
大男の咽に、ナイフが刺さりました。
一瞬だけ、大男は自分に何が起きたのか分かりませんでした。彼には自分に向かって右手を伸ばしている少女しか見えませんでしたが、しかし突然首を焼いた痛みとできなくなった呼吸と、慌てて添えた手に触れた冷たい金属のおかげで、それに気が付くことができました。
少女が、たった今自分の咽にナイフを突き刺した少女が、顔や胸元に血を浴びている少女が、静かな眼で大男を見上げていました。その顔は涙や、涎や、血で汚れていましたが、やっぱりとても可愛らしいものでした。
「!……っ!……っっ……!!!」
大男は声の代わりに血の泡を口と咽から噴出して、ベッドから転がり落ちました。そのまま走って逃げようとしたようですが、
「……っっ!!!」
走り出す一瞬前に、その左の太股にもう一本、ナイフが刺さりました。大男に刺さったナイフはどちらも小さく柄の無い、金属の塊のような黒いナイフです。それでもその刃は生き物を殺すためには十分な大きさでした。それは今の今まで、ずっと少女の枕の下に隠してあったのでした。
大男は床を這ってドアまで行こうとします。けれど太股に刺さったナイフは神経を切断していて、その左足はいまやただの錘でしかありませんでした。
一瞬だけ振り返った大男の視界に、ベッドの上でハンカチを口から引き抜く少女が見えました。
少女は汚れたシャツを脱ぐと、その幼い体つきを薄明かりに照らされながら、ベッドと壁の隙間に手を入れました。
引き抜かれた少女の手には、巨大な刃物が握られていました。
刀身も、グリップも、ナックルガードも、全部が真っ黒な、まるでククリナイフのような形をした刃物です。刃の長さがゆうに50センチはあろうあかという、それは生き物を殺すためだけに造られた刃物でした。
血の気の無い大男は、その刃の塊を見て更に顔を青くしながら、
「……!!!……っっ!……!!」
何を言っているか分かりませんでした。
少女がベッドから降りて、ゆっくり大男に近付きます。巨大な刃は、少女が歩くたびに床と擦れて音を立てました。
薄く、少女は笑っているように見えました。でもそれは、ひょっとしたら光の具合でそう見えただけかもしれません。そんな笑っているのかいないのか分からない少女は刃物を握りなおしながら、
「おじさん、悪く無かったよ。上手だった」
ナイフが振り上げられました。
それが振り下ろされる瞬間、少女は冗談のように言いました。
「でも、パパの方が上手だったかな」
部屋の中は薄暗い空間でした。広くはありませんが、家具も何も無いせいで、がらんとして見えます。入ってすぐ左手にはシャワールームのドアがあり、少し奥に入ると、簡単な机とベッドが置かれたスペースになっています。ベッドは一番奥の壁際に置いてあって、その上の壁には嵌め殺しの窓がありました。さっきまで空を覆っていた雲は段々晴れてきていて、今は少しですが星も見えています。部屋が薄明るいのは、カーテンの無いその窓から、ぼんやりと月の光や、街灯の光が入ってきているからなのでした。
少女はベッドで眠っているようでした。
大男はバッグを一度床に降ろして、そこからロープや、手錠や、ガムテープを取り出しました。『商品』を“梱包”するための道具です。バッグの中には他にも『商品』を入れるための大きな布袋なども入っていましたが、そちらには縛ってから『商品』を入れるので、今はまだ取り出しません。
足音を立てずに、部屋に入ります。静かにドアを閉めると、後ろ手で鍵をかけました。慎重にやったので、ほとんど音はしませんでしたが、大男はここでも念のために、しばらく時間を置きました。
その間に、大男は少女の様子を観察します。ベッドの上の布団は小さく膨らんでいて、一定の間隔で上下に動いていました。耳を済ませれば、小さく整った寝息も聞こえてきます。ベッドの横には脱いだらしいブーツが並んでいて、テーブルの上には畳まれたコートや、ズボンや、下着まで置いてありました。どうやらシャワーを浴びて、そのままベッドに入って寝てしまったようです。部屋の中にはまだシャワーの水の匂いが残っていて、その湿気のせいか、少しだけ生暖かいように感じられました。
大男はゆっくりと歩き出して、少女に近付きます。テーブルの横まで来たところで、その上に持っていたロープやガムテープや手錠を、静かに置きました。視線はずっと少女を見ています。大男はズボンのポケットから小さな拳銃を取り出して、右手に持ちます。そのまま左手だけで、器用にズボンと下着を脱ぎました。大男の股間についているそれは既に怒張し切っていて、平均的なそれの大きさよりも、二回りほど大きな巨根でした。少女は相変わらず、静かに寝息を立てています。
大男は拳銃の安全装置を外すと、まだ引金に指はかけないまま握り締め、そろりとベッドの横に立ちました。薄明かりに浮かんでいる少女の横顔は、大男が想像していたよりもずっと可愛らしく愛らしく、彼の興奮を煽りました。
大男は務めてゆっくりとその布団に手を掛け、そして、掴んだ瞬間一気に引き剥がしました。そこからは打って変わってとても素早い動作で動き、大男はあっという間に少女の両腕を左手ひとつで纏め上げると頭の上に押さえ込み、拳銃越しに右手でその口を押え、悲鳴を上げられないようにしました。
少女が目を覚ましました。最初は驚いたように大男を見上げていましたが、すぐにその右手に握られている拳銃に気付いたようで、動きが止まります。大男は少女のその様子に気をよくしたようで、
「へへっ……そうそう、イイ子にしとけよ。俺だって『商品』は綺麗に扱いたいんだよ。見えるだろ? 何だか分かるよな? だったら静かにしてろ。叫ばないって約束してくれるならよ、右手だって離してやる」
少女は、
「…………」
しばらく大男を黙って見ていましたが、やがて頷きました。
「よーしよし……いいか、少しでも大声出したら殺すからな」
大男は注意しながら、少女の口を塞いでいた右手を、拳銃と一緒に剥がしました。左手はまだ、少女の両腕をその頭の上に押さえつけてます。少女は叫び声を上げませんでしたが、かといって特別に怯えた様子も見せず、そのやや吊りあがった、大きくて金色をした丸い眼で、大男をじっと見ています。大男はその従順だけれど反抗的な所に、更に気を良くします。
にやにやと笑いながら、大男は少女の身体を嘗め回すようにして観察し始めました。自分の身体の下の少女はとても小さく、今はシャツ1枚の姿です。黒と白の横縞模様の、だぼだぼな7分袖のシャツだけを着ています。ワンピースよりも丈が短いので、少女の幼く太い脚の間にぷっくりと浮かんだ秘所も、半分ほど見えていました。大男のそれが、また硬くなりました。大男はやや特殊な嗜好の持ち主でした。
大男は、少女が叫んだり舌を噛んだりしないように、その口の中にハンカチを詰め込みました。すると次は拳銃が少女のシャツの裾の下に入り込んで、捲り上げていきます。下から順番に、細く幼い割れ目と、くびれの無い太い腰と下腹と、臍と、左右対称に6つある乳首が現れました。首元までシャツを捲くられると、少女はそこで初めて大男から眼を離して横を向きました。大男は、少女のその未発達で、まるで幼児のような身体と、更にそれと吊り合わない大人っぽい動作に一層興奮したらしく、我慢できないとでも言うように少女の膝の下に自分の腕を入れると一気に持ち上げて、露になったその小さい裂目に自分の先端を押し当てました。少女はそっぽを向いたまま、別段抵抗しません。
しかし大男の一物がその入り口を押し広げて中へと侵入してくると、その顔が痛みに歪みました。大男のそれは、少女の小さい膣には大きすぎるほどでした。でも大男はそんな事は意にも介さずに、止まらず奥まで突き刺しました。少女のうめき声が大男の耳にも届いて、大男は身体を震わせて悦楽します。そのまま、すぐに大男は腰をゆっくり前後に動かし始めました。
一回動くごとに、少女が声を出します。だけどその声ははっきりした意味の無い、まるで泣き声のような声でした。大男は右手に拳銃を握っているせいで少しやり辛そうにしながら、それでも少女のその狭苦しい肉の感触に心を奪われているようで、何度も何度もその中で自分の一物を往復させます。そのうちに、大男の動きはどんどん速くなっていって、少女のうめき声は一層大きくなってきました。大男は少女を好きなように犯しながら、
「へへっ、なあおい、俺はよ、別に悪い事してる訳じゃねぇんだよ……どうせお前さん、これから売られたらよ、毎日毎日これなんだからな。だからな、俺が最初に、何されても平気になるように教えておいてやるんだよ。これからどういう生活する事になるかさ。……ああでもな、お前さんならよ、心配しなくてもな、多分平気だよ……これだけ具合良けりゃよ、貰い手なんて幾らでも出てくるしな。ほらっ、もっと善がれって、気持ちよくなっておかないとな、これから大変だからさ。毎日毎日、自分からケツ突き出して穴広げて、ご主人様犯してくださいって言うだけの暮らしになるんだぜ、お前」
大男は好きなように少女を蔑みながら、その奥を突き上げ続けました。少女はその言葉には反応しないで、ただ突き上げられるたび、声を上げました。気が付けばその声には、痛み以外の、犯される快感による嬌声が混ざり始めていました。大男はそんな少女をいたく気に入ったようで、いい子だと褒めながら、その首筋や頬を舌で舐めて、一層激しく動きます。古いベッドは大男が動くたびにぎしりぎしりと軋み、その音が少女の喘ぎ声と混ざりながら、狭い部屋に響きました。少女の表情がやがて悩ましげなものになり始め、その手がシーツを握り締め始めます。大男は腰を振りつつ少女の腕から左手を離して、その開いた手で、少女の乳首をつねって引っ張りました。少女の身体が小さく震えました。大男は、こっちでも感じるのかこの淫乱めだとか、そんな言葉で少女を更に責めます。
やがて、少女の身体を好きなように蹂躙していた大男の口数が段々少なくなってきて、どうやら絶頂が近いらしい事が分かりました。その口からは涎が垂れていて、涙を浮かべた少女の赤く染まる頬に垂れ落ちました。
大男は拳銃をベッドの上に置くと、両手で少女の腰を掴み、持ち上げました、簡単に持ち上げられた少女の腰を前後に動かしながら、自分は今までで一番激しく腰を叩きつけました。少女が一際大きくその身体を仰け反らせて、ついに大きな悲鳴が上がりました。しかし大男はまるでそういう器具であるかのように少女を扱い、既に慣れきったその狭い膣の肉が裏返りそうなほど勢い良く、自らの一物を出し入れします。水音といっしょに、手拍子するような音が響きました。
大男が少女を抱え込むように身体を丸めて呻いて、その行為が終わった事を告げました。少女と大男の隙間からは、少しだけ血の混じった、どろりとした液体が流れ出してきました。
暫くの間、大男は少女を抱えたまま、その中に自分の欲望の全てを吐き出し続けていました。しかし数分経つとようやく満足したのか、やっと顔を上げて、満足そうな下品な笑いを浮かべながら、自分にたった今犯されたこの愛くるしい少女の顔を見ておこうと視線を下ろしました。こいつなら、或いは自分が買い取って、延々と飼ってやってもいいと、そうも考えていました。
大男の咽に、ナイフが刺さりました。
一瞬だけ、大男は自分に何が起きたのか分かりませんでした。彼には自分に向かって右手を伸ばしている少女しか見えませんでしたが、しかし突然首を焼いた痛みとできなくなった呼吸と、慌てて添えた手に触れた冷たい金属のおかげで、それに気が付くことができました。
少女が、たった今自分の咽にナイフを突き刺した少女が、顔や胸元に血を浴びている少女が、静かな眼で大男を見上げていました。その顔は涙や、涎や、血で汚れていましたが、やっぱりとても可愛らしいものでした。
「!……っ!……っっ……!!!」
大男は声の代わりに血の泡を口と咽から噴出して、ベッドから転がり落ちました。そのまま走って逃げようとしたようですが、
「……っっ!!!」
走り出す一瞬前に、その左の太股にもう一本、ナイフが刺さりました。大男に刺さったナイフはどちらも小さく柄の無い、金属の塊のような黒いナイフです。それでもその刃は生き物を殺すためには十分な大きさでした。それは今の今まで、ずっと少女の枕の下に隠してあったのでした。
大男は床を這ってドアまで行こうとします。けれど太股に刺さったナイフは神経を切断していて、その左足はいまやただの錘でしかありませんでした。
一瞬だけ振り返った大男の視界に、ベッドの上でハンカチを口から引き抜く少女が見えました。
少女は汚れたシャツを脱ぐと、その幼い体つきを薄明かりに照らされながら、ベッドと壁の隙間に手を入れました。
引き抜かれた少女の手には、巨大な刃物が握られていました。
刀身も、グリップも、ナックルガードも、全部が真っ黒な、まるでククリナイフのような形をした刃物です。刃の長さがゆうに50センチはあろうあかという、それは生き物を殺すためだけに造られた刃物でした。
血の気の無い大男は、その刃の塊を見て更に顔を青くしながら、
「……!!!……っっ!……!!」
何を言っているか分かりませんでした。
少女がベッドから降りて、ゆっくり大男に近付きます。巨大な刃は、少女が歩くたびに床と擦れて音を立てました。
薄く、少女は笑っているように見えました。でもそれは、ひょっとしたら光の具合でそう見えただけかもしれません。そんな笑っているのかいないのか分からない少女は刃物を握りなおしながら、
「おじさん、悪く無かったよ。上手だった」
ナイフが振り上げられました。
それが振り下ろされる瞬間、少女は冗談のように言いました。
「でも、パパの方が上手だったかな」
3.
少女は大男の死体の横のドアを開けてシャワールームに入ると、しばらくシャワーを浴びました。血や、涎や、その他の体液を洗い流しました。
数分経ってから、少女は身体を拭きながら出てきました。しかし、全身拭いたかと思ったところで、股の間から、奥に出されてまだ残っていた男の体液が太股を伝って流れ落ちてきて、
「……」
溜息をつくと、また中に戻りました。
数分経ってから、少女は身体を拭きながら出てきました。しかし、全身拭いたかと思ったところで、股の間から、奥に出されてまだ残っていた男の体液が太股を伝って流れ落ちてきて、
「……」
溜息をつくと、また中に戻りました。
少女が一階へ降りて行くと、主人はものすごく驚き、がたんと椅子から立ち上がると新聞を取り落としました。
「な……そんな……お穣ちゃん、あんた、何で……」
黙ったまま、少女は主人の目の前の席に座りました。フードは被っていましたが、赤いコートは前が開かれていて、換えていないシャツにべったりとついた血の跡は良く見えました。少女は主人にただ、
「咽が渇いてるから、飲み物が欲しいの」
と言いました。
主人はぼーっとしたまま、まだ状況が理解できていないような感じで、黙って少女の前に水の入ったコップを置きました。少女がそれを手にとってちびちびと飲み始めると、
「お穣ちゃん……部屋に、男が来なかったか。でかい奴で……その、何と言うか……」
「うん。来たよ」
「じゃ、じゃあその、何で……だって、確かに……」
主人には、大男の一連の下衆な行為の物音が聞こえていました。なのにどうしてこの少女は何食わぬ顔で戻ってきて、そして大男は居なくて、少女のシャツには血がついているのでしょう。
少女は水を一口飲んで、
「死ぬ前にくらい、いい気持ちにさせてあげようと思って。でも、思ったよりも上手だった」
主人は全身の力が一気に抜けてしまうような、そんな不可思議な感覚に囚われました。それでも何故か、恐怖だけは、不思議と感じられません。それがこの少女の愛らしい見た目のせいなのか、それともさっきから付きまとっている現実感の無さなのかは、分かりませんでした。
主人は力なく、椅子に座りました。暫くの間、少女がコップを置いたり持ったりする音だけが響きました。
やがて主人は大きな溜息をついて、床に落ちっぱなしになっていた新聞を拾いました。でも、もう眼は通しません。
「お穣ちゃん。お前、名前は」
「ライカ」
「ライカ? 犬のか? スプートニクの?」
「本当はそうだったけど、今は違う。漢字で『来禍』。“来る”に“わざわい”って書くの」
少女の指がカウンターの上で滑りました。『来』と『禍』。
主人は一度眼鏡を外して、目頭を揉みました。そしてまた眼鏡をかけると、頭の上の時計に目を遣りました。午前4時前でした。
「お穣ちゃん……お前さんは、一体、何なんだ?」
「知りたい?」
「ああ」
少女が身を乗り出して、主人の耳元に口を近づけて、そして答えました。
その答えを聞いて、主人はまた、とても大きな溜息をつきました。
「……俺は、もうすぐ消えるのか」
「まだ分からない。どうするか、まだ決めてないから。一応、色々と、その世界の中を見て回ってみて、それで決めることにしてるの」
「……そうか」
主人は空になったコップに、また水を入れて持って来ました。
「だがな……それも仕方ないだろう。こんな世界の、こんな仕事ばっかりしてる俺だ。消されてもしょうがないさ」
「別に、あなただけ消えるわけじゃないよ」
「同じだろ。自分だけが消えようが、他の奴らも一緒に消えようが、死ぬのには変わり無い」
「大切な誰かとか、居ないの?」
「………………ああ、居ないね」
「私は居た。もう、居ないけど」
「…………」
少女はまた水を飲みました。そんな少女を尻目に、主人は立ち上がり、2階に向かいました。
戻ってきました。その顔はなんだか、とってもどんよりしていました。
主人は壁に寄りかかってしばらく深呼吸していましたが、やがて少女を見つめて、悲しそうに言いました。
「……悪かった」
少女は、気にしてないよもう慣れたから、と答えて、空にしたコップを置きました。その表情はやはりどこか切羽詰ったようで、それでいて穏やかなようで、だけどとても幼く無邪気な、しかし全てを見通しているような、曰く形容し難い雰囲気を纏っていました。
主人はそこでようやく、少女にささやかな恐怖を覚えました、しかしそれは具体的な恐怖があるわけでもなく、ただただ芒洋な恐怖です。死や闇が怖いというような、「わからないもの」を怖がる種類の恐怖に思えました
目の前のこの少女を、自分は理解できない。主人はそう思いました。
それはまるで、言葉が分からない外国の文章を突きつけられたような感覚でした。一つ一つの文字や、単語は理解できるけれど、それが一繋がりの文章になってしまうと、途端に意味がぼやけて、理解できなくなってしまう感じでした。この少女もまた、姿や、動作や、喋り方や、そういった細かい部分部分は理解できるけれど、しかしそれが一繋がりの『ライカ』という存在そのものになってしまうと、とたんに全てが矛盾しあって、理解できなくなってしまう。そんな感じなのでした。
少女が立ち上がりました。
「もう行くね。ありがとう」
そして何の心残りも無いという風に、ドアへ向かいます。
店主は放心したようにその赤いフードを見ていましたが、突然、
「まっ、待ってくれ……!」
少女を呼び止めました。赤いフードが立ち止まって振り返ります。
しかし主人は、結局何も言えませんでした。まるで自分が何で呼び止めたのか忘れてしまったかのよな感じがして、言葉が出ませんでした。実際、彼は自分でも無意識のうちに呼び止めていたのでした。
「いや……何でも無い。済まん」
少女は頷いて挨拶すると、ドアをくぐって出ていきました。
「な……そんな……お穣ちゃん、あんた、何で……」
黙ったまま、少女は主人の目の前の席に座りました。フードは被っていましたが、赤いコートは前が開かれていて、換えていないシャツにべったりとついた血の跡は良く見えました。少女は主人にただ、
「咽が渇いてるから、飲み物が欲しいの」
と言いました。
主人はぼーっとしたまま、まだ状況が理解できていないような感じで、黙って少女の前に水の入ったコップを置きました。少女がそれを手にとってちびちびと飲み始めると、
「お穣ちゃん……部屋に、男が来なかったか。でかい奴で……その、何と言うか……」
「うん。来たよ」
「じゃ、じゃあその、何で……だって、確かに……」
主人には、大男の一連の下衆な行為の物音が聞こえていました。なのにどうしてこの少女は何食わぬ顔で戻ってきて、そして大男は居なくて、少女のシャツには血がついているのでしょう。
少女は水を一口飲んで、
「死ぬ前にくらい、いい気持ちにさせてあげようと思って。でも、思ったよりも上手だった」
主人は全身の力が一気に抜けてしまうような、そんな不可思議な感覚に囚われました。それでも何故か、恐怖だけは、不思議と感じられません。それがこの少女の愛らしい見た目のせいなのか、それともさっきから付きまとっている現実感の無さなのかは、分かりませんでした。
主人は力なく、椅子に座りました。暫くの間、少女がコップを置いたり持ったりする音だけが響きました。
やがて主人は大きな溜息をついて、床に落ちっぱなしになっていた新聞を拾いました。でも、もう眼は通しません。
「お穣ちゃん。お前、名前は」
「ライカ」
「ライカ? 犬のか? スプートニクの?」
「本当はそうだったけど、今は違う。漢字で『来禍』。“来る”に“わざわい”って書くの」
少女の指がカウンターの上で滑りました。『来』と『禍』。
主人は一度眼鏡を外して、目頭を揉みました。そしてまた眼鏡をかけると、頭の上の時計に目を遣りました。午前4時前でした。
「お穣ちゃん……お前さんは、一体、何なんだ?」
「知りたい?」
「ああ」
少女が身を乗り出して、主人の耳元に口を近づけて、そして答えました。
その答えを聞いて、主人はまた、とても大きな溜息をつきました。
「……俺は、もうすぐ消えるのか」
「まだ分からない。どうするか、まだ決めてないから。一応、色々と、その世界の中を見て回ってみて、それで決めることにしてるの」
「……そうか」
主人は空になったコップに、また水を入れて持って来ました。
「だがな……それも仕方ないだろう。こんな世界の、こんな仕事ばっかりしてる俺だ。消されてもしょうがないさ」
「別に、あなただけ消えるわけじゃないよ」
「同じだろ。自分だけが消えようが、他の奴らも一緒に消えようが、死ぬのには変わり無い」
「大切な誰かとか、居ないの?」
「………………ああ、居ないね」
「私は居た。もう、居ないけど」
「…………」
少女はまた水を飲みました。そんな少女を尻目に、主人は立ち上がり、2階に向かいました。
戻ってきました。その顔はなんだか、とってもどんよりしていました。
主人は壁に寄りかかってしばらく深呼吸していましたが、やがて少女を見つめて、悲しそうに言いました。
「……悪かった」
少女は、気にしてないよもう慣れたから、と答えて、空にしたコップを置きました。その表情はやはりどこか切羽詰ったようで、それでいて穏やかなようで、だけどとても幼く無邪気な、しかし全てを見通しているような、曰く形容し難い雰囲気を纏っていました。
主人はそこでようやく、少女にささやかな恐怖を覚えました、しかしそれは具体的な恐怖があるわけでもなく、ただただ芒洋な恐怖です。死や闇が怖いというような、「わからないもの」を怖がる種類の恐怖に思えました
目の前のこの少女を、自分は理解できない。主人はそう思いました。
それはまるで、言葉が分からない外国の文章を突きつけられたような感覚でした。一つ一つの文字や、単語は理解できるけれど、それが一繋がりの文章になってしまうと、途端に意味がぼやけて、理解できなくなってしまう感じでした。この少女もまた、姿や、動作や、喋り方や、そういった細かい部分部分は理解できるけれど、しかしそれが一繋がりの『ライカ』という存在そのものになってしまうと、とたんに全てが矛盾しあって、理解できなくなってしまう。そんな感じなのでした。
少女が立ち上がりました。
「もう行くね。ありがとう」
そして何の心残りも無いという風に、ドアへ向かいます。
店主は放心したようにその赤いフードを見ていましたが、突然、
「まっ、待ってくれ……!」
少女を呼び止めました。赤いフードが立ち止まって振り返ります。
しかし主人は、結局何も言えませんでした。まるで自分が何で呼び止めたのか忘れてしまったかのよな感じがして、言葉が出ませんでした。実際、彼は自分でも無意識のうちに呼び止めていたのでした。
「いや……何でも無い。済まん」
少女は頷いて挨拶すると、ドアをくぐって出ていきました。
4.
主人は壁にもたれたまま、しばし天井を見つめていました。頭の中では色々な事がぐるぐると回っていましたが、そのどれもが明確な形になっているわけではなく、つまり何も考えていないのと同じでした。
やがて視線を下ろした主人の視界に、木目の浮かんだ床に浮かび上がる白いものが見えました。それはドアの横にぽとりと落ちていて、良く見るとどうやら紙切れを折りたたんだ物のようです。
「……」
主人はふらふらと近付いて、それを拾い上げました。
紙切れには、幼い字で、短い文章が書かれていました。
やがて視線を下ろした主人の視界に、木目の浮かんだ床に浮かび上がる白いものが見えました。それはドアの横にぽとりと落ちていて、良く見るとどうやら紙切れを折りたたんだ物のようです。
「……」
主人はふらふらと近付いて、それを拾い上げました。
紙切れには、幼い字で、短い文章が書かれていました。
『この世界は、壊さないでおくことにしたよ』
主人は紙切れをポケットに仕舞って、店の隅に置いてある電話を取り、ダイヤルを回しました。
たっぷり時間が経ってから、電話がつながりました。
たっぷり時間が経ってから、電話がつながりました。
「俺だ……ああ。そう。悪かったな、こんな時間に。……そのな……実はな、仕事を辞めたんだ……いや、違うんだ。自分から。そう。そう……。それでな、俺もお前も、もう歳だろ……引越しでもしようかと思ってるんだ。いや、ついさっき決めたんだが……どこか、田舎に家でも買ってさ。そうか。うん……いや、良かった。え? いやあ、まあな……ちょっとな……。でも良かったよ、反対されるかと……うん。……ああ、いいな、海の見える場所か。そりゃいい。老人の二人暮しにはぴったりだ……」
END.