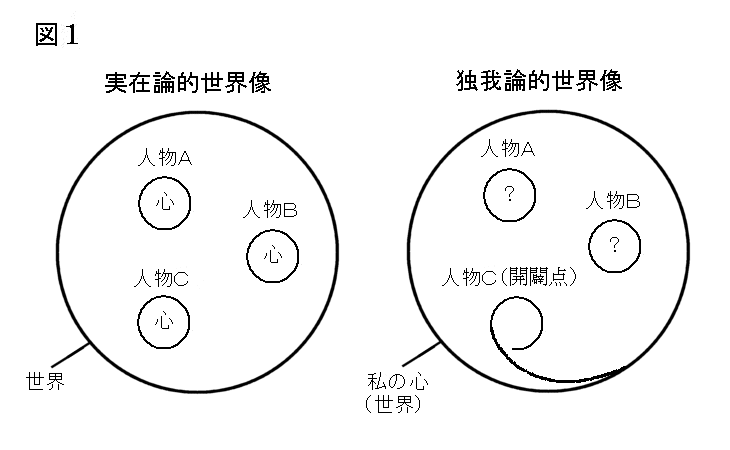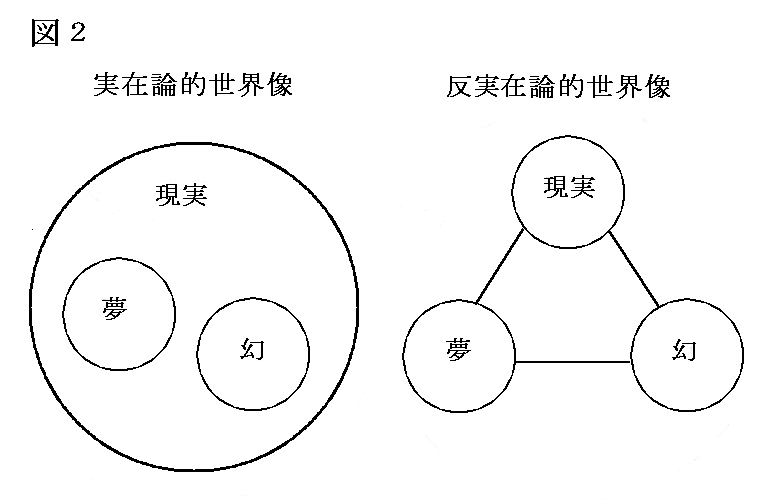1 観念論の困難
私は超能力で自由自在に空を飛べる。何年か前には地上から三千メートルぐらいの高空を飛んだことがある。綿のような白い雲を突きぬけ遥か下方の街並みを見ながら飛び続けたのだが、飛んでいる最中ふいに超能力が消えて転落してしまうのではないかという不安もよぎった。そんな不安を駆逐するように自分は空を飛べるのだと強く信じて風を切りながらひたすら飛び続けた。転落の恐怖と戦いながら遥かな高空を飛び続けるのは痺れるほどの快感であり、これは人生で五番目ぐらいの素晴らしい経験だった。
夢での経験を上のように位置づけていけない理由はない。特に私は存在論的に反実在論の立場である。この立場では夢の経験も現実の経験も「経験」ということで共に等しく貴賎がないと考えるのだから、夢での経験を現実ではないからと言って否定する必要がない。消えない夢はもはや夢ではなく現実であり、消えていった現実はもはや現実ではなく夢である。これが反実在論の世界観である。したがって私が遥か高空を飛んだ経験は現実と貴賎がないれっきとした事実である。――これまではそう思っていた。
私はゼノンのパラドックスとカントのアンチノミーの論証によって反実在論が論理的に妥当な存在論だと確信し、そして反実在論の立場から世界の構造を無矛盾に説明しようとしてきた。そしてその説明は成功していると信じていた。ところが、最近その信念に疑問が生じてきた。
私は確かに空を飛ぶことができる。しかしいつでも自由自在に飛べるというわけではない。私が空を飛べるときは「夢」というカテゴリーに分類される世界いるときに限られていて、「現実」に分類される世界にいるときは、私は決して空を飛べない。――これは実に不思議である。
反実在論では現実世界も夢の世界も同じようなものである。なにしろ物質的な対象が経験に先立って実在することを否定する思想なのだから、世界にあるものは見るもの聞くもの触れるもの一切が対応する実在を持たない観念(「現象」や「クオリア」も類義語である)に過ぎないのである。夢の経験も錯覚の経験も現実の経験も、みな同じく「経験」ということで貴賎がないのである。
ここで用語の解説をしておこう。「反実在論」「独我論」「観念論」とは、いずれも一つの哲学的立場の各面であると考えて差し支えない。この哲学的立場では、物質的対象を巡る議論においては、実在論に対して反実在論である。他我問題を巡る議論においては、他我の実在論に対して他我は不可知だとする独我論である。ただ観念論という語は複雑で多様な使われ方をしている。バークリーは現象主義的な観念論であり、カントは物自体を措定した二元論的な観念論であり、ヘーゲルは汎神論的な観念論である。少なくとも現代の心の哲学では物的一元論(唯物論)や二元論に対する心的一元論を指す場合に観念論という語が使われており、私はその意味で観念論という語を用いることにする。
反実在論・独我論・観念論というのは、一つの哲学立場が論点の違いによって自らの立場を表すために使い分けている語たちなのである。これ以降の論述で使用される反実在論・独我論・観念論の各語は、意味は異なっていても一つの哲学的立場から主張されているのだと考えてよい。
私は第2章「
無限論」において、無限についてのパラドックスを詳細に検討した結果、反実在論は論理的に正しいと結論した。ならば夢と現実に決定的な差異がないとなる。では、なぜ私は現実世界で空を飛べないのだろう?
物理法則が牢固としてあるからだ、と単純に考えるのは間違いである。物理法則とは時間・空間・物質というものたちの「実在」によってその普遍性が保障されるからだ。しかし反実在論では経験に先立って存在する実在なるものを認めない。したがって反実在論では昨日の物理法則と今日の物理法則が同一であるのは「全くの偶然」であって、夢の世界の物理法則がころころ変わるように、現実でも物理法則がいつ変わっても何の不思議もない。ところがいつ変わってもよいはずの物理法則が全く変わらないように思える。なぜ現実はこれほど別格に牢固なのだろう?
私の胸に疑念が生じている。夢と現実は峻別するべきものではないか、そして現実において規則性が厳密に成り立っていることの根拠として実在論が妥当な存在論である可能性を認めるべきではないか、と。
ただし実在論が妥当だと仮定して、時間・空間・物質というものが経験に先立って実在することを認めたとしても、それだけで物理法則が普遍的であることを説明できるわけではないことには留意すべきである。デイヴィッド・ヒュームは因果関係の実在性を懐疑し、それは人の心によって見出される帰納的推論にすぎないとして演繹的推論のような厳密性がないとした。因果と帰納法の妥当性についてのヒュームの懐疑は、物理法則の普遍性――自然の斉一性の懐疑につながっている。二〇世紀初めの科学哲学初期に活躍したカール・ポパーは、ヒュームの懐疑が反駁不可能であることを認めて、科学と疑似科学を分けるものは反証可能性にあるとする「反証主義」を提唱したことはよく知られている。それ以降も帰納法の妥当性を巡る議論は続いているが、今日の科学哲学でもヒュームの懐疑は反駁不可能とする意見が支配的である。
ヒュームが提起した帰納法の妥当性、それと関連する因果関係の実在性という問題は、哲学史上最大級の難問であって、実在論を選択すれば物理法則の普遍性が直ちに証明されると安易に考えることはできない。
ところで物理法則の普遍性(自然の斉一性)の問題と、物質的対象の実在性の問題は大いに異なるは私も承知している。帰納法による推論の厳密性を否定している論者でも物質の実在性は自明な前提としているケースが多い。しかしよく考えてみれば物質の実在というものも結局は知覚現象の規則性から帰納的に推論され、その存在が措定されたものに過ぎない。したがって物質の実在性も、その物質たちに成立している物理法則の普遍性も、共に究極的には現象の規則性という問題に還元されるのである。
とはいえ、物質の実在を措定する実在論ならば反実在論よりも因果関係や自然の斉一性を懐疑する必要性が少ないことは事実である。今日の多くの実在論者はヒュームの懐疑は事実上棚上げし、割り切って考えている。帰納法に論理的な厳密さを求めるのはどだい無理な話で、帰納法は信頼性・蓋然性が高いのであればそれでよく、物理法則の普遍性は時間・空間・物質というものの実在性によって担保されるのだと、大半の実在論者たちは考えている。実際そのように考えれば世界の大半の現象は説明可能である。実在論ならば現実世界というものが確固としてあって、その内部にいる人間が夢や錯覚という非現実的な経験をしていると考え、なおかつその非現実的な経験も特定の脳の状態と相関しているというように理路整然とした説明が可能である。
しかし私は反実在論者である。時間・空間・物質というものが経験に先立って実在することを認めないのだから帰納法と物理法則の普遍性は蓋然性が低いとみなさなければならない。反実在論では、夢も錯覚も現実も存在論的身分に差異がない。
だから私は――滑稽なことであるが、毎日のように空を飛ぼうと試みる。道を歩いているとき、高いビルを見かけるとその屋上に向かってジャンプする。河川があるとそれを一気に飛び越えようと思ってジャンプする。夢の世界なら身体がふわりと浮き上がってスーパーマンのように高速で空を飛べるのだが、現実の世界では重い重力の鎖に引き戻されてすぐ地に落ちる。何度試みても私は空を飛べない。論理的に考えるならば私が突然空を飛べるようになっても何ら不思議はないというのに、この世界はそうなっていないようなのである。
一般の人ならこんな滑稽なことはやらないだろう。帰納法は論理的な確実性がないから自分は空を飛べるかもしれないと思ったとしても、数回飛翔を試みて失敗したならすぐやめてしまうだろう。しかし私はやめることができない。それは私が反実在論者だからである。時間も空間も物質的対象も実在しないと確信している。そして帰納法も物理法則も蓋然性が低いと確信している。だから毎日必ず空を飛ぼうと試みなければならない。もちろん、こんなことは馬鹿らしいと思って止めてしまいたくなることがある。しかしそんなときにヒュームの亡霊が私の脳裏にひょっこり現れて、例のふくよかな顔に微笑を浮かべ、「千回失敗したから千一回目も失敗するなんて論理的な根拠がないでしょう」と囁いてくる。ヒュームの言葉には説得力がある。だから私は滑稽な試みをやめることができない。ただの一度でも空を飛ぶことに成功したなら、反実在論が存在論的に正しいという証明になるからだ。
それでも私は現実世界で空を飛ぶことに成功したことがない。
何年もこのような空しい試みを続けていると、さずがに自分の哲学――反実在論に疑問が生じてくる。
私はかつてヒュームに倣って、「規則」とは人の心にのみ存するのだと信じていた。たとえば、或る人が道を歩いていると小石が一つ転がっている。更に歩くと小石が二個ある。更に歩くと小石が三個ある。更に歩くと小石が四個ある。その人は小石の配列に規則を見出して、今度は小石が五個あるに違いないと思うだろう。――この場合重要なのは、道に転がっているのは「小石」であって「規則」ではないということである。規則は有限の経験から一意に定めて無限に演繹することはできない。規則とは帰納的に見出されたものであり、論理的必然性がない。必然性の欠如が示すことは、規則とは人の認識に存するものだということである。「規則」「因果」「法則」といったものは人の認識にのみ存するのである。
しかし私は、このような規則性の懐疑主義的解釈を根拠として、現実世界で牢固として存在する現象の規則性の問題を解消するのは無理であると徐々に思うようになってきた。
信原幸弘は物的一元論の立場から心的一元論に対し、次のような批判を行っている。
物を心に還元することは、心を物に還元することよりもはるかに困難であるように思われる。たとえば、物をさまざまな観点からの知覚的な集まりに還元しようとする現象主義的な試みがある。机は、いろいろな角度から見た、その見え姿の集まりだというわけである。しかしこのような還元はいま現に意識に立ち現れている現実的な現れだけでなく、可能的な現れをも必要とする。机を見るときに、じっさいに意識に現れるのは、ある特定の角度からの見え姿だけである。そのほかの見え姿は意識に現れない。それらは、そのほかの角度から見れば、意識に現れるであろう可能的なものにとどまる。しかし、可能的な現れというのは、いったいどのような存在なのだろうか。それは、じっさいに意識に現れるものではない。そうだとすれば、それはどこに、どのように存在するのだろうか。可能的な現れは、一見、現実的な現れからの類推によって容易に理解できそうにみえるが、いざその存在のありかたを確定しようとすると、まったく不可能になる。
この信原の批判は、大森荘蔵の「立ち現われ一元論」を標的としたものであるように思われる。大森は現象主義的な立場から、人の経験の規則性を「無限集合」の概念で説明していた。たとえば机の知覚像は、あらゆる視点から無限にありうる。しかしそれぞれの知覚像は微妙に異なっている。それら知覚像の無限集合を表現する言葉として「机」という語やイメージがあるとする。しかしこの無限集合を人は作り上げることができない。できるのは特定の視点を与えられた時にどう見えるかということである。つまり人は「見え姿」作成のアルゴリズムを知っているのである。これをたとえれば、人は想像し得る無限の掛け算をやることはできないが、掛け算のやり方――アルゴリズムを知っていれば、任意の二つの数字を与えられればどんなパターンの掛け算もやることができるように。なお大森は後に現象・知覚像の規則性を、「思いのこもった立ち現われ」の概念で説明するようになる。これは意識に立ち現れる物質的対象の知覚は、知覚していない部分への思いを伴っているとみなすものであるが、根本的には無限集合による説明方法と同じものである。
かつて私は大森と同様の現象主義的な立場から現象の規則性を説明しようとしてきたのだが、現象主義的な説明方法には重大な困難があると認めざるを得なくなってきた。
通常の百円硬貨は片面に 100というアラビア数字が刻印されていて、その反対の面には桜の絵柄が刻印されている。、現実世界でその百円硬貨を転がしてみよう。上に 100の刻印があれば下には桜の刻印がある。これは論理的に必然である。偽造硬貨でもない限り上に 100がありながら下にも 100があるなどということはあり得ない。しかし夢の世界なら、上に 100があるのに下にも 100があるということがありうるのである。実際に私はそれに類した不合理な夢をよく見ることがある。ところが現実の世界で私はそんな不合理な経験をしたことが一度もない。なぜ現実の世界ではこんなに厳密に規則が成り立っているのだろう? ――実在論者ならこのような現象の規則性は簡単に説明できるだろう。現実世界の百円硬貨は「実在」だからであり、夢の世界の諸現象は対応する実在をもたないからである、と。しかし夢も幻も現実も等しく「経験」ということで存在論的身分に貴賎がないとする反実在論の立場では、現実世界で現象の規則性が厳密に成り立つことは説明困難なのである。
さらに反実在論では知覚経験の「重なり」が説明できない。手に持ったスマートフォンで音楽を聴いているとしよう。目を閉じればスマートフォンの視覚像は消滅する。しかし耳から聞こえる音楽は消えることがなく、手にあるスマートフォンの触覚も消えることがない。そして目を開ければ再びスマートフォンの視覚像が現れる。実在論者ならスマートフォンが実在することを根拠にそれら知覚現象の規則性を説明するだろう。しかし反実在論者はそうすることができない。スマートフォンという実在物は認めないのだから、目を閉じてスマートフォンが消え、次に目を開けたときスマートフォンが現れるのは「偶然」と考えざるを得ない。さらには目を閉じて音楽が聞こえ続けるのも、手にスマートフォンの感触があり続けるのも、「偶然」と考えざるを得ない。視覚・聴覚・触覚がそれぞれスマートフォンという同一の対象を指示しているにも関わらず、反実在論者はそれら感覚たちの「重なり」は全く偶然だと考えなければならない。
反実在論の困難はさらにある。反実在論では「世界」とは現象(クオリア)の集合に過ぎないのだから、「私」は世界内部に存在せず、あえて言うと「世界」と「私」は一致する。このような観点をウィトゲンシュタインは「主体は世界に属さない。それは世界の限界である」と表現している。実在論では世界内に多くの人がいて「私」もその内の一人にすぎないとみなすが、反実在論では世界そのものが「私の現象」なのだから、「私」が世界内部にいて諸々の現象を経験しているのではなく、諸々の現象があるということが、すなわち「私」と「世界」があるということである。
ここでまた用語を解説しておこう。本論で単に " 私 " と表記する場合、それは世界内に固有名詞を持って存在し、指示対象となり、世界の開闢点である人物を意味する。そして "「私」" と括弧つきで表記する場合はウィトゲンシュタインが言うような世界の限界としての主体であり、指示対象となり得ない「世界」と一致する「私」を意味する。
「私」と「世界」が一致するとした場合、疑問が生じることになる。この世界はなぜだかこの文章を書いている特定の人物であるこの私から開闢されているのだが、世界の開闢点が世界内に登場している理由がわからないのだ。たとえば『2001年宇宙の旅』や『ローマの休日』のような通常の形式の映画は三人称視点で描かれている。人は我を忘れて映画に見入っているとき自分の身体の存在を忘れることがある。そのような場合、反実在論では「私」は映画と一致すると考えてよい。すると映画の世界にこの私が登場しなくても映画を見ることができるように、この世界にこの私が登場していなくても「私」は世界を見る(というより世界が存在する)ことが論理的には可能である。ところが、なぜだかこの世界はそうはなっておらず、この文章を書いている私が世界の開闢点となっている。
さらに疑問がある。「世界」イコール「私」は現象(クオリア)の集合なわけであるが、「意志」に分類できる種類のクオリアによって動かすことができるのが、世界内に多数登場する生物たちのうち、世界の開闢点であるこの私という人物のみであることが、反実在論では説明困難であるように思えるのだ。
しかし実在論ならばそれらは何ら問題ではない。実在論では「私」と「世界」は一致しない。「私」とは常に世界内部に存在している特定の人物であるこの私と完全に一致する。つまり私は世界を開闢する存在ではなく、単に特定の「視界」を開闢する存在にすぎない。そして私が自分自身の身体しか動かせないのは神経生理学的に当然のことであり、そこには何の不思議もない。
以上のような実在論による優れた説明能力に対し、反実在論の説明能力は全く比較にならないほど劣っていることは認めざるを得ない。ならば反実在論の妥当性を懐疑するしかない。
ところで、反実在論は他者の身体の実在を否定するのだから、他我を否定しているのと同じことである。ただし観念論者だったバークリーもカントも他者の物質的身体の実在は否定しても他我までは否定してはいないので、物質的対象の実在の否定が直ちに他我という心的対象の否定につながるわけではない。しかし観念論では「世界」とは「私の観念」に過ぎないのだから、私の観念にすぎない他人の身体に他我が相関していると考えるのは困難であり、やはり反実在論は厳密に考えると独我論に到達せざるを得ない。かつて私はそう考えて、他我について考えるのをやめることにした。しかし反実在論に対する疑問が、独我論に対する疑問にもつながっている。
以下は抽象化した実在論と独我論の世界像である。
図1では世界全体を大きな円で、個別の人物をその内の小さな円で表している。実在論的世界像では世界に複数の人物が対等に存在し、それぞれの人物内部に「心」があることを表している。独我論的世界像では世界そのものが「私の心」であり、私の身体(人物C)は「私の心(世界)」の開闢点であることを表し、また自分以外の人物の内に「?」で、他者の心は不可知であることを表している。これまで私は認識論的独我論の事実を重んじ、独我論的世界像を信じていたが、今はその信念が揺らいでいる。
ショッピングモールを歩いていて、モール内にある鏡を見るときなど、私は疑問に思うことがある。鏡には多数の人々と共に私が映っている。鏡に映った私は何ら特別な存在ではない。多くの人の一人に過ぎない。独我論的世界像は単なる思い込みではないか。自分の一人称視点で認識した世界より、鏡に映った三人称視点の世界こそが真の世界――つまり図1の実在論的世界像の方が正しいのではないか、と。
もちろん、鏡で自分を見ても所詮鏡像は自分の視野の内部に過ぎない。ウィトゲンシュタインならば「主体は世界に属さない」と言うだろう。またトマス・ネーゲルならば「鏡にはその中の人々の誰が〈私〉であるかが書かれていない」と言うだろう。――しかしそれらは認識論的独我論の問題にすぎない。認識論的独我論が事実だからといって、ただちに存在論的に自分が特別であるという結論が導かれるわけではない。確かに私は世界で唯一の存在である。しかし「特殊」と「唯一」は異なる概念である。私が唯一であることから、私が特殊であることは直ちに導けない。存在論的な特殊性を主張するならば更なる根拠が必要である。唯一性と特殊性はあくまで慎重に使い分けるべき概念である。
たとえば六面体のサイコロがあって、各面に①から⑥までの文字があるとしよう。その場合、「⑥は唯一である」と言うことは可能であるが、「⑥は特殊である」と言うことはできない。
物理主義ならば、自分が比類ない固有のパースペクティブで世界を認識しているという認識論的独我論の事実も、それは世界内に存在する特定の人物の脳状態と数的に同一なのだ、と説明可能である。
ショッピングモールにある鏡を見て私は想いに耽る。鏡の中に独我論者がいる。この人物は世界に多数いる人物の中で自分だけは特別な存在だと思い込んでいる。鏡の国には他にも多数の人々が登場している。その人たちと比べてこの独我論者が特別だとする確実な根拠は見つけ難い。鏡の国の独我論者――それは巨大な迷妄の中を彷徨っているだけの哀れな存在かもしれない。
私は今一度、自分が反実在論を選択した場所に戻って、自分の哲学を再検証しなければならない。それはカントの『純粋理性批判』を再検証することでもある。
2 『純粋理性批判』の目論見1――世界の観念性の証明
私とカントには共通点がある。それは「無限」の問題をきっかけに反実在論を選択したということである。カントは自らの反実在論を超越論的観念論として主張した。私は現象主義(現象一元論・心的一元論)として主張してきた。いずれも時間・空間・物質的対象が経験に先立って存在することを否定するものであり、双方に重大な差異はない。ここでは双方をまとめて観念論と呼ぶことにする。
カントは私にとって偉大なる師であり、同じ観念論者として最強の友であった。そのカントの『純粋理性批判』(以下『批判』と略す)を再検証してみたい。ただし『批判』は膨大な分量の書物であり、その全体を検証するというわけにはいかない。検証は「世界の観念性の証明」と「現象の規則性」という二つの論点に絞ることにする。
まず『批判』の目論見を把握しておこう。カント自身は『プロレゴメナ』において、『批判』の目論見として「純粋数学はどうして可能か」「純粋自然科学はどうして可能か」「形而上学一般はどうして可能か」の三つを挙げているが、これは正確ではない。私見であるが、カントはバークリーの観念論と混同されることを忌避して、「世界の観念性の証明」という『批判』の根幹にある目論見を明言するのを控えたのだと思われる。
私の解釈では『批判』の主要な目論見は以下の三つである。
目論見1: アンチノミーの論証によって実在論の矛盾を示し、現象世界が観念であることを証明すること。
目論見2: 世界の観念性の証明は現象の規則性の根拠(時間・空間・物質的対象の実在)の否定でもあるため、現実に成立している現象の規則性の根拠が人のア・プリオリな認識の形式であることを証明すること。
目論見3: 目論見1と目論見2によって理性の限界を画定し、経験可能性を超えて理性を使用する独断的形而上学を否定し、形而上学の役割を画定すること。
この三つにカントが『プロレゴメナ』で挙げた「純粋数学はどうして可能か」を目論見4として加えてもいいかもしれないが、ここではあえて省き、後に論じることにする。目論見2が「ア・プリオリな綜合判断はいかにして可能か」というよく知られた『批判』のテーマである。なお目論見1と目論見2によって理性の限界が画定され、それによって自由・神・魂の存在証明が不可能であること示されたわけであるが、しかしそれらの非存在が証明されたわけでもないことは重要な点であり、それが後の『実践理性批判』へとつながることになる。ただ厳密には『批判』でもカントは第三アンチノミーや「超越論的方法論」で実践理性を論じているので、『実践理性批判』はその拡張バージョンということになる。ちなみに『批判』のとてつもない難解さはカントが件の目論見を明確しないで、かつ目論見の順序通りに書いていないことも一因である。
カントの目論見1である世界の観念性の証明を再検証してみよう。これは第2章で詳説したのでここでは要点だけ再論することにする。
カントが反実在論の妥当性を確信したのは「無限」の問題が実在論では解消できないからである。実在論といってもさまざまな立場があるが、以下の二つはいずれの実在論にも共通する特徴である。
世界の独立性: 人間の認識活動とは独立に世界は存在する
真理対応説 : 人間の世界認識は実在世界と正確に対応している
世界の独立性を簡単にたとえると、太陽や海は人が見る前から存在しており、人が見るのを止めれば消えるわけではないということである。真理対応説を簡単にたとえると、人が高さ 7メートルの桜の樹を見る場合、実在の桜の樹は高さ 7メートルであり、決して高さ 3センチではないということである。これら世界の独立性と真理対応説は「実在論の二つのドグマ」と呼ぶべき、実在論が実在論であるためのミニマルな条件である。
この実在論の二つのドグマを認めると、エレア派のゼノンが考案したものを始めとする無限についてのパラドックスが解決不可能になる。カントはこれを「純粋理性の二律背反」――アンチノミーとして定式化し、現象世界が観念であることの論拠とした。
第一アンチノミーは時間と空間の無限大の問題である。
定立 : 時間と空間は有限でなければならない。仮に時間が無限ならば、現在までに終わらないはずの無限の時間が終わったことになる。
反定立: 時間と空間は無限でなければならない。仮に時間が有限であったとしても、その時間より前の時間が考えられてしまう。
無限大の問題をわかりやすく説明すると次のようになる。――今日が一日目、明日が二日目、明後日が三日目とカウントしていくとしよう。このようなカウントは論理的に終わることは無い。しかし過去とは「終わっている」ものだから現在までに終わらないはずの無限のカウントが終わったことになる。これは現在までに自然数全てを数え終わったに等しいことになり、矛盾である。そして、そのようなカウントはカウントする人間の活動がなければ無意味だと否定することはできない。実在論とは、人の認識活動とは独立に物事が存在していると考える。つまりカウント可能なものがカウントする人間の活動から独立して存在すると考えるのだから、実在論では過去の時間が無限に実在すると想定せざるを得ない。これは端的な矛盾である。
ところで時間は始まりを持つとすることでこの矛盾を解消することはできない。仮にビッグバン(あるいは神による世界創造)によって時間が始まったとしても、時間が始まる「原因」はあったことになる。その原因を或る種の時間だと考えれば結局時間・因果関係は無限に遡行できることになって、カウント可能なものが現実に無限に実在しているということになる。したがって実在論は矛盾している。
第二アンチノミーは無限分割の問題である。
定立 : 世界を構成する究極の要素は一定の大きさを持たねばらない。物体が無限に分割できるとすると矛盾である。
反定立: 世界には究極の要素は存在しない。一定の大きさの要素があったならば、それは分割可能な空間に対応した分割可能な部分を持つからだ。
これはゼノンのパラドックスと同じものである。無限分割の問題をわかりやすく説明すると次のようになる。――私がこれから道路を歩くとしよう。その場合実在論では、「道路には私の足に踏まれる可能性のある全地点があらかじめ存在している」という前提がなければならない。全地点があらかじめ存在していなければ私は歩くことはできない。地点とは私が道路を踏んでから存在を始めるのではなく、踏む前から人の認識活動とは独立に存在していると考えるのが実在論である。私は歩幅 1メートル以内ならどんな幅でも歩くことができる。0メートルから 1メートルの範囲内において、私が踏めない地点は論理的に存在しない。すると僅か 1メートルの長さの中にも地点は無限個存在することになる。したがって無限の地点を通過するというのは自然数を全て数え尽くすというのに等しい矛盾なので、実在論が正しいなら私は僅か 1メートルも歩けないことになる。したがって実在論は矛盾している。
反実在論では、地点や時点が人に経験される前から存在していることを認めない。道路の或る位置に私の足がある場合、他の地点はまだ存在していない。他の地点とは私が足を移動させると同時に存在を始めるのである。そして過去の無限とは人が経験する現在を起点にして、可能的に無限に経験を遡行できるということにすぎない。このように反実在論なら空間と時間の無限分割・無限延長の問題を解消できるので、反実在論は正しいということになる。
以上の論証によって、カントの目論見1である「世界の観念性の証明」が成功していることは明らかである。
※第三アンチノミー(自由と因果)と、第四アンチノミー(神の存在)は世界の観念性の証明とは関係ないので省略する。
『批判』の検証からは外れるが、もう少し「無限」の問題について論じておこう。
無限である可能性を持つ対象には以下のものがある。
Inf_1: 時間の無限小
Inf_2: 時間の無限大(因果系列の無限大)
Inf_3: 空間の無限小
Inf_4: 空間の無限大
存在論においては、上の四種の無限をただの一つでも認めることはできない。「無限のものが存在する」というのは「限りが無い」という無限の概念と矛盾しているからである。上の四つを全て回避できるのは反実在論のみである。
なお現代の物理学では、粒子の運動は連続的でなく断続的であるゆえに、無限分割の問題は回避できるとする見方もあるが、それでも特定の地点には粒子が存在できないことを証明できなければ、「空間には地点が無限に存在する」という矛盾を解消したことにはならない。
数学的には無限級数の収束という概念によって無限分割の問題は解決できるとされる。たとえば「0.999... = 1」という定義は「総和(summation:Σ)」の概念に基づけば正しい。しかし数学は「地点の実在性」などという形而上学にコミットしていない。数学が間違っているというわけではない。数学と哲学では論点が全く異なっているということなのである。
たとえば 10引く 3はテーブルの上に小石を 10個置いてから 3個取り、残りを数えるという仕方でも計算できる。しかし無限はそのような仕方では計算できない。「1.999...から 0.999...を引けば 1になる」という計算は確かに正しいが、それは純粋な概念に基づいて正しいのであって、その概念と対応する実在はない。つまり数学における無限の計算とは、いわば概念のパズルなのである。
もちろん、対応する実在を持たない単なる概念である数学的無限が、なぜ物理的世界に適用できるのかという疑問はあるだろう。それは物理的世界そのものが、直観と直観に源泉を持つ概念から構成されているにすぎないからだと考えるべきなのである。これがカントの構成主義的観念論、いわゆる超越論的観念論から読み取れる存在論である。
ここで新しい数学の基礎を構築しようなどという大仰なことを目論むつもりはないし、そんな学識もないが、カントが取り組んだ「純粋数学がなぜ可能か」という問題、および数学がなぜ現象世界に適用できるのかという問題について、カントの説を若干補完修正しておきたいと思う。第4章で論じたように私はカントの経験的実在論を否定するため、補完修正が必要なわけである。
数学には少なくとも次の三種類の要素が必要である。
数の概念: 1、2、3、4、......
操作概念: 足す、引く、掛ける、割る、繰り返す、停止する、等しくする(同一性)、......
純粋直観: 長さ、広さ、......
もちろんそれら三つは緊密に関係しあっているが、重要なことは三つを峻別して理解しなければならないということである。この三つを峻別しないことからゼノンのパラドックスを始めとする無限についての各種パラドックスは生じるのである。
カントが時間と空間が純粋直観だと言うのは、「長さ」や「広さ」が純粋直観であると言うことと同じである。では「長さ」や「広さ」の直観とは何かというと「印象」である。つまり長いものや広いものが実在しているのではなく、「長いという感じ」「広いという感じ」があるのである(カントの経験的実在論によれば個別の長いものや広いものが実在しているとされるが、私はそれを否定する)。
世界には 1メートルの長さのものがあり、3キロメートルの長さのものがある。しかし「長さ」そのものには長さがない。「長さ」や「広さ」とは純粋直観によって得られた「印象」であり、長いものや広いものがそれら自体で存在しているわけではない。つまり最初に 1メートルのものを認識してから「長さ」があると思うのでなく、事態は逆であって、最初に「長さ」の印象を得て、次に 1メートルという「数」の概念が与えられるのである。
「長さ」や「広さ」の下位分類として、「丸さ」や「四角さ」という幾何学的直観があるだろう。それらが一つの単位(単称項)となり、数の概念の基礎となる。そして丸いものや四角いものという幾何学的対象にはアプリオリに「足す」や「割る」という操作可能性が伴っている。さらにその操作を「連続させる」という概念も伴い得る。これが「無限」の概念の元である(この操作可能性という考え方はカントの「図式論」と同じである)。
決して世界そのものが経験に先立って存在し、その世界に直観および数と操作の概念が適用できるのではない。事態は逆であって、世界は純粋直観に数と操作の概念が加わって構成されているとみなすのである。
たとえば風景画があるとしよう。その絵には窓が描かれ、遠近法で窓の向こうにビルが描かれているとしよう。窓とビルの「距離」というのは、もちろん絵なのだから実在しない。しかし人は絵の内容から距離を推定することができる。つまり遠近法という技法が絵に奥行き直観させ、知性が距離を想定するわけである。――直観と知性との協働で世界が構成されるという観念論の主張とは、大雑把にたとえるとこういうことなのである。
「モリヌークス問題」と呼ばれるものがある。触覚だけで球体と立方体を区別できる先天的な盲人が、手術で視覚を得たとして、その人は対象に触れずに視覚だけで球体と立方体を判別できるか、というものである。この問題を考案したモリヌークス自身は「できない」という答えを用意していた。ジョン・ロックも同意している。実際に先天的盲人の開眼手術に成功した例でも、患者は直ちには球体と立方体を判別できないという。
モリヌークス問題とは、経験に依拠しない判断を可能にさせるア・プリオリな人の直観とは何であるかを問うものである。手術によって初めて視覚を得た人は、確かに二つの物を見てどちらが球体なのかどちらが立方体なのかを理解できないろう。しかし長いものと短いもの、大きいものと小さいものの区別はできるはずである。つまり初めて視覚を得た人でも、高さ一センチの立方体と高さ一メートルの立方体の区別はできるということである。これは当然で、双方には認識のしやすさという点で歴然と差があるからである。したがって「長さ」「広さ」とはアプリオリな純粋直観であり、純粋な印象である。それに知性が操作と数の概念を適用するのである。
※実際に開眼手術を行った患者に対する観察事例では、ほとんどの患者は視覚像の大小の区別はできないという。しかし同時に視覚像の明暗の区別(光の強さ)は区別できるという。光の強さは視覚対象の大きさに比例するのでこの観察結果は矛盾しているようにも思える。これは観察方法に問題があると思われる。厳密な方法、たとえば一面黒塗りの部屋の壁際に高さ一センチの白い立方体を置き、その反対の壁際に高さ一メートルの白い立方体を置いて患者に判別させるという方法なら、患者は二つの立方体の大小を判別することができるはずである。
以上は視覚についての考察であるが、触覚についても同じことが言える。長さ・広さ・大きさ・小ささ、それらは純粋直観である。それら純粋直観と知性との協働で世界は構成されていると考える。この構成主義的観念論ならばアンチノミーを回避でき、世界が無矛盾に説明できるのである。
無限についての各種パラドックスが回避できるという理由で、やはり反実在論は妥当な形而上学だと考えるべきである。
しかし前節で検証した通り、時間・空間・物質的対象の実在を否定しまう反実在論では現象の規則性の説明できないのであった。世界が観念に過ぎないのならば、夢も現実も存在論的身分に差異がないはずである。なぜ「現実」に分類される世界ではこれほど厳密に現象の規則性が成り立ち、自然科学が普遍的に成り立つのだろう?
この謎を解明しようとしたのが、カントの目論見2、観念論の立場から自然科学が普遍的に妥当する理由を解明しようとした偉大な試みであった。
3 『純粋理性批判』の目論見2――自然科学の根拠付け
カントは1770年に大学教授に就任するために書いた「可感界と可想界との形式と原理」、いわゆる「就任論文」で既に時間と空間の観念性を主張していた。もっともこの時期のカントは「観念論者」を自称してはいないが、時間と空間が主観的なものだとすることは、それらによって規定される物質世界が観念だと主張することと紙一重であり、カントもそれは自覚していたはずである。
「就任論文」から『批判』の出版まで十年の歳月を要したのは、観念論の立場から現象の規則性を説明する理論の構築に十年を要したと考えてよい。これが「沈黙の十年」と呼ばれる期間の実態であると私は思っている。カントがいかに困難な問題に取り組んだかということは観念論者になってみないとわからない。世界が観念ならば夢も現実も根本的な相違がないはずなのに、現実では牢固として規則性が成立しており、ニュートン力学が全盛を誇っている。これは一体どういうことかとカントも困惑したはずである。観念論の立場から何とか現象の規則性を説明し、自然科学が普遍的に妥当する根拠を解明しなければならない。
カントが出した結論は「認識のコペルニクス的転回」であった。人の経験から独立した対象があって、それを人が認識するという伝統的・表象主義的な考え方を転倒させ、人が認識する現象世界とは感性・悟性という人の認識能力によって「構成」されるものであるとした。これが認識のコペルニクス的転回である。
※以下『批判』からの引用の出典表記は第一版をA、第二版をBと表記し、その後に頁をアラビア数字で示す。日本語訳は原佑 訳『純粋理性批判』を用いる
基本的な用語を解説しておこう。「感性」とは物自体から触発されて「多様なもの」を直観する能力である。「悟性」とはその直観に規則を与えつつ対象を判断・思惟する能力である。カントの認識論は、基本的には感性と悟性の二元論である(A51=B75)。
なお悟性とは広い意味があり、その内容は「生産的構想力」「再生産的構想力」「狭義の悟性(カテゴリー、統覚)」「判断力」「理性」に分けることができる。
さらに理性は「純粋理性」と「実践理性」に分けられる。純粋理性とは理論哲学(論理学・形而上学)において、経験に依拠せずに推論する能力である。実践理性とは実践哲学(倫理学・政治学など)において、経験に依拠して推論する能力である。
現象の規則性に関わる部分は構想力から統覚までということになる。
カント自身は人の認識のプロセスを次のように説明している。
① 感官によるア・プリオリな多様なものの通観
② 構想力によるこの多様なものの綜合
③ 根源的統覚によるこの綜合の統一
上の三つが意識の根源的能力とされる(A94=B127)。
まず『批判』からカント哲学のエッセンスというべき部分を引用しておこう。以下の文は認識論と存在論にまたがるカント形而上学の根幹を表すものである。
それらの現実的な諸物が私にとって対象であり、過去の時間において現実的であるのは、経験的な諸法則にしたがうところの可能的な諸知覚の背進的系列(それが歴史を手引きするにせよ、原因と結果の足跡をたどるにせよ)が、要するに世界経過が、現在の時間の条件としての流れ去った時間系列に帰着するということを、私が表象するかぎりにおいてのみであるが、それにしてもこの流れ去った時間系列は、そのときにはやはり、可能的経験の脈絡のうちでのみ現実的なものとして表象され、それ自体そのもので現実的なものとして表象されるのではないのであって、かくして、太古以来私の現存在に先立って経過した全ての出来事は、現在の知覚からはじまってこの現在の知覚を時間の面で規定する諸条件へとさかのぼる経験の連鎖をどこまでも延長しうるという可能性以外の何ものをも意味しないのである。(A495=B523)
カントにおいては、時間・空間・因果系列は「今・ここ・私」から可能的に無限に開かれているということである。過去とは、「世界経過が、現在の時間の条件としての流れ去った時間系列に帰着するということを、私が表象するかぎりにおいてのみ」ある。つまり過去とは私が表象する限り現実的ではあるが、過去それ自体は実在ではなく可能的な存在に留まるのである。アリストテレスの用語で言うならば過去とは「可能的無限」として存在しているのであって、「現実的無限」として存在しているのではないということである。
なお重要な点は、件の文はアンチノミーの論証と併せて理解しなければならないということである。時間・空間・因果系列が無限であることはできない。無限の実在とは矛盾だからである。しかし逆に時間・空間・因果系列の限界を思考することもできない。限界を想定しても「それより先」が思考できてしまうからである。これがアンチノミーであった。しかし時間・空間・因果系列、そしてそれらによって規定される「世界」そのものが、ア・プリオリな人の認識能力によって、認識の度ごとに構成されるとするならば、アンチノミーが回避できるわけである。カントにとって「世界」とは、中島義道の言葉を借りるなら「一つの統覚にとっての世界」なのである。件の文がカント哲学のエッセンスであるゆえんである。
カントにおいては、仮に或る統覚によって構成された世界より前に、別の統覚で構成された世界があったとしても、世界と世界の同一性、および統覚と統覚の同一性は問えないという前提がある。カントの認識論の実質は独今論に近い。もちろんカントは「今・ここ・私」しか存在しないと主張してはいない。カントにおいては今ここにいる私と、以前別の場所にいた私との同一性そのものが統覚によって一挙に構成されるのである。仮に以前別の場所にいた私が一つの統覚世界内部に存在せず独立して存在していたと仮定するならば、更にそれ以前の私、更にまたそれ以前の私、更に私の原因である親、親の原因である先祖、とたちまち無限後退のアンチノミーに陥ることは明白だからである。したがってカントにおいて現実的なものは「今・ここ・私」のみであり、他の時点や地点は可能的存在に留まる。
そして他の時点や地点を可能的なものとするだけでカントは「経験的実在論」を主張できると考えていた。それが「経験一般の可能性の諸条件は、同時に経験の諸対象の可能性の諸条件であり、それゆえにア・プリオリな綜合判断において客観的妥当性をもつと、(A158=B197)」という言葉に表れている。
私の関心は現象の規則性がなぜ成り立つかということである。第一節で検証したように観念論では規則性が現実に成立していることの説明が難しい。カントの超越論的観念論ならばその困難が克服できるだろうか?
カントにおいて現象の規則性とは、人の認識を可能にする悟性のカテゴリーと同種のものである。カテゴリーに従って認識対象が構成されるゆえにア・プリオリな総合判断は可能であり、現象は対応する実在をもたなくとも、つまり世界が観念であっても、自然科学が普遍的に妥当するとされる。
カントはまず「超越論的感性論」において感性の役割を説明し、続いて「超越論的論理」の「超越論的分析論」で悟性の役割を説明している。
以下、超越論的分析論から現象の規則性に関わる具体的な記述を検証してみよう。
カントはまず「連想」と「親和性」の概念によって規則性を説明している。日光の下に暖かい石があったならば、人は日光が石を暖めたのだと推測する。このような意識内における現象の結合の規則が「連想の規則」である。そして連想の規則を可能にならしめるのが「親和性の規則」であり、これが自然法則に適合するものとして措定されている。
この法則は、すべての現象を、それ自体で連想されえうるような、だから再生産においてあまねく連結する普遍的な諸法則に従っているような、感官のそうした与件としてあまねくみなしうるものにほかならない。諸現象のすべての連想のこうした客観的根拠を私は諸現象の親和性と名づける。しかしこの客観的根拠を私たちは、私に所属すべきすべての認識に関しての、統覚の統一の原則において以外には、どこにも見いだすことはできない。(A122)
もちろん上の文だけでは何を言っているのかわからない。親和性の概念は引き続いて説明される悟性の役割と併せて理解しなければならない。
私たちは悟性を規則の能力として特徴づけることができる〔……〕感性は私たちに形式(直観)を与えるが、悟性は規則を与える。悟性は、諸現象で何らかの規則を探し出すことを意図しながら、それらの諸現象をくまなく探索することに、いつでもたずさわっている。規則は、それが客観的であるかぎりにおいて(したがって対象の認識に結びついているかぎりにおいて)法則と呼ばれる。たとえば私たちは経験をつうじて多くの法則を学ぼうとも、これらの諸法則はいっそう高次の諸法則の特殊規定でしかなく、それらの高次の諸法則のうち最高の諸法則(あらゆる他の法則がそれに従うところの)はア・プリオリに悟性自身に由来するのであって〔……〕悟性はそれ自身自然にとっての立法であり、言いかえれば悟性なしではどこにも自然はなく〔……〕(A126)
「統覚」は悟性の最高原理とされる。『批判』の第二版では規則性について具体的に論じる前に統覚の機能が明確に説明されている。
感性との連関におけるすべての直観の可能性の最高原則は、超越論的感性論によれば、直観のすべての多様なものは空間と時間という形式的条件に従うということにほかならなかった。悟性との連関におけるすべての直観のまさに同じ可能性の最高原則は、直観のすべての多様なものは統覚の根源的・綜合的統一の諸条件に従うということである。〔……〕このように結合されうることなしでは直観のすべての多様な諸表象によっては何ひとつとして思考ないしは認識されえないからである。というのは、与えられた諸表象は、我思考すという統覚の作用を共有してはおらず、だからこの作用によって一つの自己意識において総括されないであろうからである。(B136)
統覚とは、諸現象を一つの意識においてにまとめるということ、換言すれば諸現象を「今・ここ・私」というパースペクティブから一挙に統一する役割を担うということである。統覚は「超越論的哲学がそこに結び付けられなければならない最高点」、また「この能力こそ悟性自身である」とも書かれている(B134)。以下では統覚の綜合がカテゴリーに従うことが説明されている。
すべての綜合はカテゴリーに従っており、また経験は連結をえた諸知覚による認識にほかならないから、カテゴリーは経験の可能性の条件であり、それゆえすべての対象にもア・プリオリに妥当する。(B159)
この経験的綜合は、超越論的綜合に、したがってカテゴリーに依存しているから、すべての可能的知覚は、したがってまた経験的意識につねに達しうるすべてのものも、言いかえれば、自然のすべての現象は、その結合からみれば、カテゴリーに従わざるをえないのであって、自然(たんに自然一般として考察された)は、この自然の必然的合法則性の根源的根拠としての(形式からみられた自然 natura formaliter spectata としての)そうしたカテゴリーに依存する。(B164-5)
以上の引用文は、カントの構成主義的な観念論の性格がよく表れている。感性が直観した多様なものを悟性がカテゴリーに従って認識するゆえに、規則性が成立するというわけである。
しかし規則性の根拠をカテゴリーに置くことによって、それで現象が生起する規則性に「例外」が生じない理由を説明できるかというと疑問である。たとえば夢の世界では突然物理法則が変わって私が空を飛ぶということが可能になる。しかし現実の世界では物理法則は全く変わらず私は飛ぶことができない。物理的対象が対応する実在を持たず、現象(観念)に過ぎないというのなら、夢も現実も存在論的身分は同等のはずである。つまり夢の世界も現実世界もともに主観によって「構成」された世界であることに変わりがないということである。一体なぜ、現実世界で物理法則が突然変化してはいけないか、不規則な現象が構成されてはいけないかということをカントは説明できていない。
さらに『批判』を検証していこう。カントは引き続き超越論的分析論において、超越論的判断力の「超越論的理説」として、「純粋悟性の図式機能」というものを想定している。
〔……〕純粋悟性概念のもとへの経験的直観の包摂は、したがって現象へのカテゴリーの適用は、いかにして可能であるのだろうか?〔……〕明瞭なのは、一方ではカテゴリーと、他方では現象と同種的であるにちがいなく、前者が後者へと適用されることを可能ならしめる第三のものがなければならいということである。媒介の働きをすることの表象は、純粋であって(あらゆる経験的なものを含まず)、しかも一方では知性的であるとともに、他方では感性的でなければならない。そうしたものが超越論的図式にほかならないのである。(A137-9=B176-8)
カントの言う図式機能とは、直観を悟性のカテゴリーに包摂する機能である。以下では図式機能の具体的な働きが説明されている。
三角形の概念は、どのような形の三角形にも妥当する。それに対して個別の三角形の形象は常に三角形という領域の一部だけに制限されている。したがって、三角形の図式は思想の内にのみ現存する。図式は空間における純粋形態に関しての、構想力の綜合の或る規則を意味する。経験された対象の形象は決してその経験的概念に達することはできず、むしろ経験的概念は、或る種の普遍的概念にかなって「規則」としての構想力の図式と直接的に連関する。たとえば犬という概念は、人の構想力がそれにしたがって或る四足の動物の形態を普遍的に描くことができる一つの規則を意味するのである。(A141=B180)
〔……〕
外的感官のすべての量の純粋形象は空間、感官一般のすべての対象の純粋形象は時間。悟性の概念としての量の純粋図式は数である。数は一を一に順次加算することを包括する一つの表象。それゆえ数は直観一般の多様なものの綜合の統一以外の何ものでもない。(A143=B182)
空間と時間の表象はつねに再生産的構想力と連関するたんなる図式であって、この再生産的構想力が経験の諸対象を招き寄せるが、そうした経験の諸対象なしでは空間と時間はいかなる意義をももたないであろう。しかもこのことは、全ての概念に区別なく当てはまるのである。それゆえ経験の可能性は、あらゆる私たちのア・プリオリな認識に客観的実在性を与えるものにほかならない。
〔……〕
かくして、ア・プリオリな綜合判断が可能となるのは、私たちが、ア・プリオリな直観の形式的な諸条件、構想力の綜合、および超越論的統覚におけるこの綜合の必然的統一を経験的認識一般と関連付けて、経験一般の可能性の諸条件は、同時に経験の諸対象の可能性の諸条件であり、それゆえにア・プリオリな綜合的判断において客観的妥当性をもつと、そう言うときである。(A157-8=B196-7)
人は色んな三角形の図を思い浮かべることができるが、「普遍的三角形」は図として思い浮かべることはできない。それはプラトンのイデアのように別世界に存在するのでなく、悟性の図式機能として存在し、時間と空間という図式と連動して、構想力によって可能的な諸々の三角形たちを表象させ得るための、いわば規則だということである。
以上のような図式や悟性による現象の規則性の説明で、果たして実在論者は自然科学がア・プリオリな綜合判断だと納得できるだろうか。それは無理な話である。カントは観念論者が成せねばならない最も重要なこと――夢と現実が峻別可能な理由を説明できてはいない。そもそも図式機能自体が規則そのものを創造する能動的な作用である。これは超越論的観念論が構成主義であるから当然なのであるが、構成主義ならば現実世界で夢と同様の不合理な現象が構成されてはいけない理由というのがないはずなのである。
ところで上述のようにカントは図式を感性と狭義の悟性の中間に位置づけるような記述をしているが、構想力の位置づけは曖昧で広義の悟性の一形態として考え(B153)、感性と悟性の二元論を固持していたとも思われる。このことについて岩崎武雄は次のように論じている。
先天的総合判断の客観的妥当性を基礎づけるためには、この二元論的立場が絶対に要求されるのである。この二元論的立場が崩れれば、すでにわれわれの批判して来たように、先天的総合判断は全く主観的な夢や幻の対象に対しても妥当することになり、その客観的妥当性を保障されないことになってしまわねばならない。〔……〕認識論的主観主義を捨てまいとすれば、この二元論的立場こそ認識の客観的妥当性を基礎づけ得る唯一の道だからである。
岩崎の言う「認識論的主観主義」とは超越論的観念論のことである。構成主義的な観念論では夢と現実を峻別することが困難なことを岩崎も看破していた。
しかし感性と悟性の二元論ならば現実世界で成立する現象の規則性を、先天的――ア・プリオリな総合判断だと言えるかというと、それは無理である。カントの規則性の説明は一種の「仮説演繹法」になっているのである。まず帰納法によって仮説を立て、その仮説を演繹することによって諸現象が説明できるなら、その仮説が妥当だとする――このように帰納法と演繹法を組み合わせて諸現象を検証し、説明する方法が仮説演繹法である。
カント自身は「超越論的論理学」の題名の下に件のように論じたのだが、私から見ると少しも「論理学」になっていない。確かに「人の経験を可能にする条件」として規則性の根拠を件のように措定すれば人の経験は説明できるかのように思える。しかし仮説演繹法はそれ自体帰納法に依存しており、帰納法は人の心の習慣であり論理的根拠がないとしたヒュームの懐疑を超えられない。カント自身はヒュームの懐疑を克服したと自任しているのだが(A760-6=B788-794)、それは大いなる勘違いである。悟性のカテゴリーが「ア・プリオリ」だというのも帰納法に依存した仮説演繹法なのである。
カントの論証は不十分なのである。夢の世界ならば百円硬貨の上面に桜の刻印があって、次に下面を見たら 100の刻印ではなくやはり桜の刻印だったという不合理なことがあり得る。しかし現実世界ではなぜだかそのような不合理がない。超越論的観念論は構成主義であるにもかかわらず、なぜ現実では不合理な現象が構成されないかということを、カントは論証し得ていないのである。
もっとも『批判』の中で現象の規則性の説明となりうる部分は上に引用した箇所だけではない。他の箇所を検討してみよう。
「超越論的対象」によって現象の規則性を説明する方法がありうるかもしれない。『批判』第一版においては現象の規則性を説明する上で、超越論的対象は通常の実在論が言う意味での「実在」に近い役割を担っていたように解釈できる。超越論的対象は「私たちの認識においてつねに同一のもの」「私たちの経験概念一般に、対象との連関を、言いかえれば、客観的実在性を与えうるものにほかならない」とカントは述べている(A109)。
実在論者ならば、視点の移動によって机や家などの見え姿が規則的に変化する理由を、それら机や家の「実在」によって説明できる。しかし観念論者であるカントはそのような説明方法を用いることができないので、実在の代替として措定したものが机や家に対応する超越論的対象ということである。もちろん超越論的対象とは物体的なものとして実在しているものではない。物体的なものとするならばジョン・ロックなどの表象主義と変わりがない。したがって超越論的対象とはあくまで個別の表象の関係点に措定された理念的なものに留まることになる。カント自身も「消極的意味におけるヌーメノン」と位置づけている(B307)。
超越論的対象の存在論的位置づけが理念的なもの、つまり意識内在的なものに留まる限り、それによっては現象の規則性を実在論者のように厳密な仕方で説明することはできず、夢と現実を峻別することもできない。ならばカントの観念論はバークリーの現象主義的観念論と変わりがないということになる。実際にカントの『批判』の第一版はバークリーの観念論と同一視され、少なからぬ批判を受けることになる。
バークリーと同一視されたことに反発したカントは、第一版を大幅に加筆修正して第二版を著すことになる。客観世界――外的対象の実在性を証明しようとした第一版の「第四誤謬推論」も大きく書き換えられ、第二版では「観念論論駁」と題された。
まず第一版の「第四誤謬推論」における外的対象の証明方法を見ておこう。
私は外的な諸対象の現実性に関して推論する必要はないが、それは、私の内的感官の対象(私の思惟)の現実性に関して推論する必要のないのと同様である。なぜなら、両者はいずれも表象以外の何ものでもないのであって、この表象の直接的知覚(意識)は同時にその現実性の十分な証明であるからである。
それゆえ、超越論的観念論者は経験的実在論者であって、現象としての物質が現実性を持つことを承認するが、この物質の現実性は推論される必要はなく、直接的に知覚される。(A371)
この証明法では、物質の知覚が直ちに物質の現実性の証明とされており、「存在するとは知覚されることである」というバークリーの観念論との相違が判然としない。これではバークリーの観念論と同一視するなという方が無理であろう。カントが書き直しを迫られたのは当然である。
加筆修正された『批判』第二版の、「観念論論駁」においてカントはまず次のような定理を置いた。
私自身の現存在の、たんなる、しかし経験的に規定された意識が、私の外なる空間における諸対象の現存在を証明する。(B275)
そして次のように証明が行われる。
私は私の現存在を時間において規定されているものとして意識している。すべての時間規定は知覚における何か持続的なものを前提する。しかしこの持続的なものは私の内なる或るものではありえない。というのは、時間における私の現存在こそこの持続的なものによってはじめて規定されうるからである。それゆえ、この持続的なものの知覚は私の外なる物をつうじてのみ可能であって、私の外なる物のたんなる表象をつうじてでは不可能である。
〔……〕
私たちがあらゆる時間規定をおこないうるのは、外的関係の転変(運動)、しかも空間における持続的なものと連関した外的関係の転変(たとえば、地上の諸対象と関係した太陽の運動)をつうじてのみあるというだけではなく、そのうえ私たちは、実体の概念の根底に直観として置きうる持続的なものを、たんに物質以外には何ひとつとしてもたず、この持続性すら外的経験から汲みとられるのではなく、ア・プリオリに、すべての時間規定の必然的条件として、したがってまた外的な諸物の現存をつうじての私たち自身の現存在に関する内的感官の規定として、前提されるのである。(B275-8)
上の証明においては、人の持続的な内的経験を成立させるためには、持続的な外的対象の実在が必要であるということが主張されている。外的対象の実在性は全ての時間規定・内的感官の規定の必然的条件としてア・プリオリなものとされる。
件のカントの文を字義とおりに解釈すると、あたかも意識の外的対象が伝統的な実在論の言うとおりに実在しているという主張のようにも受け取れる。第一版からの劇的な書き換えである。第二版の主張が第一版の主張と矛盾していると指摘する論者も少なくないのだが、それもあながち誤読とは言えないだろう。しかしカントの表現は非常に紛らわしいものの、最初に引用したカント形而上学のエッセンスと言える部分(A495=B523)が、第二版でもそのまま残されていること、また時間と空間が表象依存的で感性の形式であること(超越論的実在性の否定)が繰り返し強調されていることから、観念論論駁において強く主張される「外的対象の実在」とは、それもまた人の認識能力によって構成されたものであることは明白である。
すなわち「私の意識」に対して「意識外部の実在」と表現すると紛らわしいのだが、カントにおいて双方はともに感性・悟性という人の認識能力によって構成されたものなのである。つまり超越論的観念論の根幹は第一版から変更されていない。
第二版のカントからすると外的対象――客観世界の経験的実在性は自明なことであって、主観的世界が客観的世界内部に位置づけられることは最初から前提とされている。夢や幻の経験(内的経験)は、客観世界――外的な空間的対象の実在性があって初めて可能になる経験なのである。要するに夢や幻などは外的対象と対応しない(脳が勝手に作り出した)経験というわけである。この夢と現実の区別の仕方は通常の実在論者と変わりがないものであり、カントが「経験的実在論」を主張したのにはこの空間論に基づいている。
ところで第一版では現象の規則性に重要な役割を果たしていたと思われる超越論的対象は、第二版でその役割を大きく縮小させられている。それはカントが第二版において空間の実在性の自明性を強めたことに反比例したものとみなせるだろう。
では、カントの主張するように観念論の世界であっても空間の実在性は自明なものとして認められるだろうか? それは無理な話である。カントにおいてはその空間的対象――客観的世界もまた物自体ではなく人の認識能力によって構成されたもの、端的に言うと観念の世界なわけである。いくら「経験的実在論」と言って空間・客観の実在性を自明な前提としても、超越論的観念論では世界そのものが主観によって構成されるとする大前提があるのだから、それで現象の規則性が現実に成立している理由の説明に成功しているとは思えない。外的対象も構成されるものであるという大前提ならば、現実でも夢と同様の不規則な現象が構成されていいはずである。
カントはとりあえず夢と現実の区別が可能な理由を述べてはいる(A376-7、B278-9)。しかしそのカントの説明は最初から空間・外的対象の実在性を前提した上で成されていて、要約するならば夢と現実が区別可能なのは外的対象は現実的であるからであるということであって、全く論点先取に陥っている。これでは外的対象の現象の規則性がなぜ成立するかという問題に対して解答したことにはならない。
※ちなみに中島義道は、カントにおいては客観的時間は構成されるものであるという前提で、夢や幻は客観的時間が構成されることによって、非客観的な時間系列であることが判明するのだとカントの時間論を解説している。
結局、カントは現実世界において夢の世界と同様の不規則な現象が構成され得ないことを証明していない。カントの「観念論論駁」が成功していないことは明らかだと思われる。
ところで、現象の規則性の根拠を物自体に求める方法を検討するべきかもしれない。人の認識能力のみによっては現実世界において成立している現象の規則性の説明が不可能だとするなら、人の認識能力外部に規則性の根拠を措定するしかないということである。カントにおいては、感性が物自体に触発されることから認識が始まるのだった。経験的実在論を成り立たせる外的感官の対象――空間が物自体からの触発によって構成されるとするなら、現象の規則性の根源は物自体にあるとみなすことも可能であるように思える。
※触発は物自体からでなく超越論的対象からだと主張する論者もいるし、物自体と現象とによる二重触発を主張する論者もいるが、ここでは立ち入らないことにする
現象の規則性の根拠を物自体だとした場合、時間・空間・カテゴリーを物自体に適用することを禁じた超越論的観念論の原則に反するように思われるかもしれない。その原則に反したならば直ちに物自体がアンチノミーの餌食になることになる。しかし物自体は時間と空間内部には存在しないとしても、物自体からの触発によって時間と空間が構成されると仮定するならば、とりあえず最初に引用したカント認識論のエッセンス部分(A495=B523)とは矛盾することはなく、現象の規則性は説明できそうにも思える。
しかしそのように考えても肝心の問題である夢と現実の峻別ができない。それ自体は時間と空間内部に存在せず、カテゴリーも適用できないとされる物自体が、なぜ感性を欺くことなく触発し、現実世界で現象の規則性を正確に成立させているのだろう?
物自体が不可知なものとされている以上、この疑問は解消不可能であるように思える。そもそも現象の規則性の根拠を物自体と仮定するならば、それは現象の規則性から外的対象の実在性を推論するという伝統的二元論の方法と(真理対応説は拒否するものの)大きく変わりがないということになる。またカントが「蓋然的観念論」と批判したデカルトの方法を超えてはいないということにもなる。極端な解釈であるが、物自体を神と置き換えればバークリーの観念論とも大差がないと思われる。
そもそもカントは物自体について積極的に語ってはいない。また「物自体からの触発」と直接書いてもいない。物自体の役割や概念が明白でないことから、後の哲学者たちは「二世界解釈」「形而上学的二側面解釈」「方法論的二側面解釈」など、物自体についての様々な解釈を生じさせることになる。
私の解釈であるが、カントが物自体を措定したのは案外単純な理由だったと思われる。それは現象が突然生じ、消えていくことの不合理を解消するためであろう。表象主義を前提とする実在論では、現象(二次性質)が生じる理由を物質の一次性質からの「触発」によって説明する。しかし観念論では物質的対象の実在を否定するので、一見現象は無から生じるように思われる。しかしこれは不合理である。「何ものも無からは生じず、何ものも無へ転化することはできない」という命題についてカントは短く言及している(A186=B229)。無から現象が生じるのは矛盾であり、だから物自体が必要だということである。物自体は生成消滅する現象の基体としてやむを得ず措定したものだから、「触発」の概念は表象主義と同様に使用されていても、積極的な役割を担っていないと思われる。
とりあえず以上の検証によってカントが夢と現実の峻別に成功してはいないことは明らかになったであろう。カントの形而上学は仮説演繹法の域を超えるものではないのである。
現実世界で百円硬貨を転がしてみれば、上面に 100の刻印があれば下面には桜の刻印がある。上面に桜があれば下面には 100がある。いくら硬貨を転がしても同じことである。しかし夢の世界なら上面に桜があるのに下面にも桜があるということがあり得る。カントが「観念論論駁」で最も成さなければならなかったことは、夢と現実がなぜ峻別可能かということであり、現実世界ではなぜ規則性が厳密に成り立つのかということの説明である。超越論的観念論では物質的対象の実在(超越論的実在)を否定する。世界とはその瞬間ごとに「構成」される現象世界なのである。ならば現実世界でも不合理な現象が構成されることがあり得るにも関わらず、現実世界で不合理な現象が「構成されてはいけない理由」というものをカントは一切説明していない。
これはカントと同じ観念論者である私としては落胆せざるを得ないことである。
ちなみに同じく反実在論者である大森荘蔵もカントと類似の空間論で現象の規則性を説明しようとしたことがある。第1節で論じたように反実在論では知覚経験の「重なり」が説明困難である。手に持ったスマートフォンで音楽を聴いているとする。目を閉じればスマートフォンの視覚像は消滅するが、耳から聞こえる音楽は消えることがなく、手にあるスマートフォンの触覚も消えることがない。そして目を開ければ再びスマートフォンの視覚像が現れる。実在論者ならスマートフォンが実在することを根拠にそれら現象の規則性と重なりを説明できるが、反実在論では説明困難である。このような問題に対し、大森は『新視覚新論』第一章で、視覚空間と触覚空間は異なるとしたバークリーを批判し、空間はカントの言う意味でア・プリオリであり、「唯一」のものであるとすることで現象の重なりを説明している。また第三章でも空間がカントの言う意味で唯一であることが論じられ、次のように述べている。
〔……〕「直接見えているもの」の風光の大筋はそれを囲む広大な「かくれて見えないもの」によって定まるのである。
われわれの全生活は常にこの四次元宇宙の中にある。ただこの宇宙が絶えずその姿を変えてわれわれに立ち現れている。われわれが移動し姿勢を変え視線を移すにつれてその姿が変わる。
大森は現象一元論者であったが、現象の規則性が成立するためには空間の唯一性が必要条件であるという着眼はカントと同様である。
ところで大森は二元論であるカントの観念論を「加工主義」と呼んで嫌っていた。確かに不可知な物自体を措定した上で、人の認識を感性・悟性、また悟性を構想力・狭義の悟性・判断力・理性と細かく分割してしまうカントの方法は、一切を「立ち現われ」の内に一元的に圧縮しようとした大森の方法とは対極的である。しかし、にも関わらずカントと大森は存在論の最も重要な点で共通点がある。それは反実在論という点だけではない。その点ならバークリーもヒュームも同様である。カントと大森の最大の共通点は「今・ここ・私」だけが「現実的」であると考えたことである。カントの場合「今・ここ・私」の外部世界は「可能的」な存在に過ぎない。もし過去が実在するなら直ちにアンチノミーに陥いることになる。だからこそカントにとって「世界」とは中島義道が言うように「一つの統覚にとっての世界」なのである。本節冒頭で引用したカント認識論のエッセンス(A495=B523)が、「今・ここ・私」のみの現実性を示唆しているゆえんである。大森においては「今・ここ・私」外部を認めるならば、実在と現象の二元論、現在と現在以外の二元論に陥って、それらの相互作用というものを想定しなければならなくなる。それゆえ大森は「立ち現われ」一元論を選択し、立ち現われ外部は不可知としたのだった。
このように見ていくとカントと大森の哲学的方法やその哲学内部は全く異なるものの、両者の存在論は「今・ここ・私」という世界のみが現実的であるとする点で共通しているのである。大森は経験主義的な立場から経験されないものの実在性を認めず、カントはアンチノミーを根拠に経験されないものの実在性を認めなかったが、結論は同じである。カントにおいては世界自体が統覚を最高原理とした人の認識能力によって「構成」されるのであり、大森はその世界自体が自動的に「立ち現れる」ということである。実質的な差異はその程度である。カントの物自体とはあくまで仮想的な実体(noumenon)であり、不明瞭な概念で現象の立ち現われに積極的な役割を果たしていないことに大森は着目すべきだった。観念論者であるカントが物自体を措定したのは、現象が無から生じるのは矛盾だという前提があったからであり、物自体は現象の生成と消滅の基体としてやむを得ず措定したものにすぎない可能性がある。また人の認識の過程を細かく分割するカントの方法も心理学的な人の認識の構造分析だと解釈することが可能である。つまりカントの哲学的方法は大森の哲学に還元的に解釈することが可能だったように思われる。ちなみに大森は終生の課題としてゼノンのパラドックスに取り組んでいた。もし大森がカント哲学を積極的に自らの哲学に取り入れていたなら、ゼノンのパラドックスをカントの方法で解消することができただろう。
本題に戻ることにする。大森もまたカントと同じ空間論を主張していたということは、カントと同じ困難を抱え込まざるを得ないということである。すなわち、現実世界で突然不規則な現象が現れてはいけない理由というものを説明できないということである。そして、その困難はこの私も同様である。
カントと大森と私とではそれぞれ考え方は異なるものの、反実在論者であるという点では共通している。この反実在論の最大の弱点は、物質的対象の実在を認めないために、第1節で検証したように現象の規則性が説明できないということである。観念論の立場からまっとうに現象の規則性を説明しようとした唯一の哲学者であるカントの試みは失敗に終わっていると判定せざるを得ない。
カントの挫折は反実在論の挫折である。ここにおいて私は、ひょっとしたら実在論が正しいのではないかと思い始めてきた。
4 純粋理性と実践理性の境界
私はバークリーや大森荘蔵に近い現象一元論の立場から、夢も現実も幻もそれぞれ「存在する」ということで同等であり貴賎がないのだと考えていた。しかし反実在論ではこれまで検証してきたように現象の規則性が全く説明できない。したがって夢と現実と幻はそれぞれ存在論的身分は同等ではなく、現実のみが特権的な存在であり、夢と幻は現実内部に位置づけられるべきではないかと考えざるを得なくなった。
夢と現実と幻の関係は、実在論と反実在論では次のようになる。
実在論では現実の内部に夢や幻の世界が位置づけられる。対して反実在論では現実も夢も幻も同等の存在である。実在論では物質的対象の実在を認めて、その実在する物質が現実世界の特権性の根拠となる。夢や幻での経験は全てその現実世界に位置する脳の作用で説明可能ということである。対して反実在論では物質的対象の実在を認めないので、実在論のように現実・夢・幻の区別ができない。観念論者であるカントも夢や幻の経験は外的な空間的対象の実在性があって初めて可能になる経験だと考えていた。しかしその外的な空間的対象の実在性の論証――「観念論論駁」が成功していないことは先に検証した通りである。世界がそのつどごとに構成されるとする観念論では、外的な空間的対象そのものに「不規則」が生じてはいけない理由というものがないのである。現象の規則性という観点からすると、反実在論は明らかに敗北している。
しかし、ここで『批判』の目論見を想起しなければならない。それは以下のようなものであった。
目論見1: アンチノミーの論証によって実在論の矛盾を示し、現象世界が観念であることを証明すること。
目論見2: 世界の観念性の証明は現象の規則性の根拠(時間・空間・物質的対象の実在)の否定でもあるため、現実に成立している現象の規則性の根拠が人のア・プリオリな認識の形式であることを証明すること。
目論見3: 目論見1と目論見2によって理性の限界を画定し、経験可能性を超えて理性を使用する独断的形而上学を否定して、形而上学の役割を画定すること。
第2節で検証した通り、アンチノミーの論証によって世界が観念であることを証明しようとしたカントの目論見1は明らかに成功しているのである。ところが現象の規則性の根拠が人のア・プリオリな認識の形式であることを証明しようとしたカントの目論見2は成功していないのである。
これは一体どういうことだろう?
「無限」の問題を検証し、実在論が論理的に矛盾していることは証明されたと私は考える。しかし観念論の立場から現象の規則性を説明しようとしたカントの試みが成功していないこともまた明らかだと思える。
ここに一種のアンチノミーが出来したように思える。新アンチノミーとでも言うべきものは以下のようなテーゼから成り立つ。
正命題: 実在論は正しい。反実在論では現象の規則性が説明できないが、実在論ならば規則性を説明できるからである。
反命題: 反実在論は正しい。実在論が正しいなら時間と空間は無限の部分を持たなければならないが、無限の実在とは矛盾だからである。
ところがこの新のアンチノミーをよく検討してみると、厳密にはアンチノミーになっていないのである。反命題の主張は実在論が論理的に矛盾していることの論証に成功している。しかし正命題の主張は反実在論が論理的に矛盾していることの論証に成功していない。なぜなら現象の規則性を説明できないということは何ら「矛盾」ではないからである。極端な話であるが、百円硬貨の見え姿にせよ物理法則の普遍性にせよ、現象の規則性が成り立っているのは全て「偶然」だと仮定することも可能なのである。
カントの理論哲学においては神・自由・魂の不死を探求することはカテゴリーを超越論的に使用することであり、純粋理性の誤謬推理であった。しかし同時に神・自由・魂の不死が理論的に否定されたわけでもないことが重要な点であり、それらは実践理性の要請として求められるということが、『実践理性批判』で論じられたのであった。しかし現象の規則性の根拠が人の認識の形式にあると仮定したカント形而上学の挫折は上に論じた。つまりカテゴリーを超越論的に使用することが純粋理性の誤謬推理ではなく、カテゴリーの普遍的妥当性の根拠を求めること、つまり現象の規則性には根拠があるという前提自体が純粋理性の誤謬推理なのである。
規則性には根拠がなくても構わない。重要なことであるが、反実在論や観念論とは自然科学を否定するものではない。実在論では自然科学の成功――現象の規則性が成立する理由をほぼ必然的(「ほぼ」としたのはヒュームの懐疑を完全に克服しているわけではないからである)として説明できるのに対し、反実在論ではそのような必然性に基づく説明ができないということのみなのである。
ヒュームが懐疑した因果の問題の本質とは、単に因果の実在が証明できないということではない。甚だしく反直観的であっても、因果が実在しないと仮定しても全ての現象は説明可能だということである。因果の実在を否定してそれが人の心にのみ存するものだと仮定しても自然科学の成功は説明可能であり、現象の規則性の必然性を否定しても致命的な不都合がない。この事実にはヒューム本人も驚いたはずである。
ヒュームは哲学を懐疑論に座礁させたというカントの批判は間違いであって、ヒュームは純粋理性のまっとうな道を進んで、まっとうな終着点へと導いたのである。ただしカントが現象の規則性の根拠を求めたことは間違いだと言うつもりはない。現象の規則性の根拠を求めることもまた実践理性の要請だということである。
新アンチノミーという擬似アンチノミーによって、私は純粋理性と実践理性の境界を画定することができた。その上で私は実践理性の要請に従い、改めて現実世界で規則性が成立する根拠を探求していきたい。
第1節で詳説したように反実在論には多くの困難がある。カントの超越論的観念論でも現象の規則性を説明することはできなかった。単に論理的に矛盾していないからという理由で反実在論は妥当な存在論だと結論するのは拙速に思える。現象の規則性を説明しようとするならば経験に先立つ「実在」を措定するのが妥当だと思える。しかし実在論は明白に矛盾しているのであった。
実在論と反実在論という相克する理論を融合させるアクロバットな案があれば問題は一挙に解決するかもしれない。実は、私はそのための素案を既に持っている。次の章ではその素案を基に新たな形而上学を構築していくことになるだろう。それはカントを超えていく試みである。
飯塚一「カントの数学論について」哲学論叢 39(別冊) 2012年
犬竹正幸「『純粋理性批判』における図式論の意義」哲学論叢 (1985), 12: 13-22
犬竹正幸『カントの批判哲学と自然科学』創文社 2011年
井上義彦「カントの認識批判における図式と象徴 -図式論に寄せて-」長崎大学教養部紀要. 人文科学. 1979, 19
井上義彦「カントの「観念論の論駁」考」長崎大学教養部紀要. 人文科学篇. 1980,20(2)
井上義彦「カントにおける自己関係性と物自体のアポリア -二重触発の問題-」長崎大学教養部紀要. 人文科学篇. 1989, 30(1)
岩井拓郎「『純粋理性批判』における感覚と対象」東京大学大学院人文社会系研究科・文学部哲学研究室論集 (32), 2013年
岩崎武雄『岩崎武雄著作集 第七巻 カント『純粋理性批判』の研究』新地書房 1982年
岩田淳二「ヒンダークスのカント「触発論」の解釈とその批評」哲学 Vol. 1973
大森荘蔵『大森荘蔵著作集 第二巻 前期論文集 II』岩波書店 1998年
大森荘蔵『新視覚新論』東京大学出版会 1982年
香川豊『カント『純粋理性批判』の再検討』 九州大学出版会 1998年
香川豊「相関者としての超越論的対象と物自体」甲南女子大学研究紀要第43号 2007年
城戸淳「カントにおける自己意識の問題 ――超越論的主観と統覚の総合的統一」人文科學研究 110, 1-34, 2002-12
黒崎政男「カント「沈黙」の十年の意義 現象概念の確立過程」哲学 Vol. 1982 (1982) No. 32 P 104-115
黒積俊夫「統覚中心的カント解釈の検討」名古屋大学文学部研究論集 四十周年記念論集 哲学. v.35 1988年
重松順二「『純粋理性批判』における感性と統覚の両義的関係」九州大学哲学会47
渋谷久「カント『純粋理性批判』における物自体の問題」哲学 Vol. 1967
竹田青嗣『完全解読 カント『純粋理性批判』』講談社選書メチエ 2010年
千葉清史「純粋理性批判』第二版「観念論論駁」の論証上の性格」哲学論叢 (2012), 39
千葉清史「二世界解釈と二側面解釈:そもそも何が問題だったのか?」『近世哲学研究』(18) 2014年
千葉清史「「物自体は実在するか」という伝統的な問題の解決によせて」山形大学大学院社会文化システム研究科紀要(12) 2015年
千葉清史「カント自由論における自我の二面性テーゼと二世界解釈との融和」山形大学紀要(人文科学)第18巻第3号 2016年
鳥居修晃『視覚の世界』光世館 1979年
鳥居修晃「人間の視・触覚融合-先天性盲人が初めて見た世界」『日本ロボット学会誌』第8巻第6号 1990年
中島義道『空間と身体 続カント解釈の冒険』晃洋書房 2000年
中島義道『カントの時間論』岩波現代文庫 2001年
中島義道『カントの自我論』岩波現代文庫 2007年
中島義道『カントの読み方』ちくま新書 2008年
長田蔵人「カントのアンチノミー論と図式論 -「現象の解明」をめぐる転換-」哲学論叢 (2013), 40: 24-24
信原幸弘『意識の哲学―クオリア序説』岩波書店 2002年
松井隆明「フッサールとアリソン流カント -超越論的観念論と物自体の問題-」東京大学哲学研究室『論集』33号 2014年
村田貴信「〈超越論的〉対象の二義性と「批判」:「超越論的」と「ア・プリオリな総合」」九州大学哲学会 1999年
隈元忠敬 編『知のアンソロジー ドイツ的知の位相』ナカニシヤ出版 1996年
鳥居修晃・望月登志子『先天盲開眼者の視覚世界』東京大学出版会 2000年
日本カント協会編『日本カント研究2 カントと日本文化』理想社 2001年
日本カント協会編『日本カント研究4 カント哲学と科学』理想社 2003年
マルティン・ハイデガー『ハイデガー全集3 カントと形而上学の問題』門脇卓爾 訳 創文社 2003年
イマヌエル・カント『カント全集〈3〉前批判期論集(3)』福谷 茂 他訳 岩波書店 2001年
イマヌエル・カント『カント全集 12 自然の形而上学』犬竹 正幸 訳 岩波書店 2000年
イマヌエル・カント『純粋理性批判 上・中・下』原佑 訳 平凡社ライブラリー 2005年
イマヌエル・カント『プロレゴメナ』篠田英雄 訳 岩波書店 1977年
イマヌエル・カント『実践理性批判 1・2 』中山元 訳 光文社古典新訳文庫 2013年
P.F.ストローソン『意味の限界 『純粋理性批判』論考』熊谷直男・鈴木恒夫・横田栄一 訳 勁草書房
L.ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』野矢茂樹 訳 岩波文庫2003年
最終更新:2017年06月16日 20:03