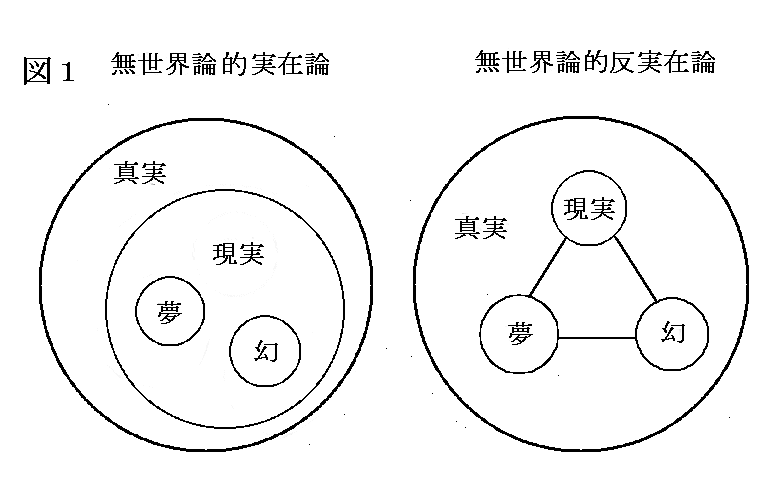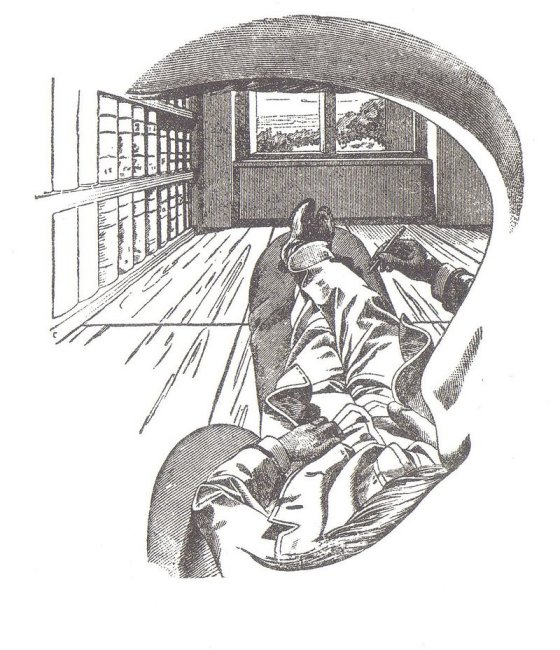1 実践理性の方向
その昔、自宅のテレビで映画『2001年宇宙の旅』を見た。映画にモノリスが登場したとき、私は大いなる哲学的驚愕に打ち震えた。宇宙には人知を遥かに超越した何かが確かにあって、モノリスがその何かを象徴していることは、青年だった私にも理解できた。映画を見終えても、私はしばらくテレビの前で呆然としていた。映画を通じて宇宙の神秘を垣間見たという感慨を堪能していたのだ。
ところがそれから何十年も経ち、今DVDで『2001年宇宙の旅』を見直しても、私は大した感慨を得ることができない。
それは今の私が哲学をやっているからである。宇宙にモノリスがあろうとアリスが迷い込んだ不思議の国があろうと、存在するものは単に存在するだけで、「不思議」とは人の心にのみあるのだ。そのこともまた不思議ではない。存在には謎がない。人は自分が理解できないことを謎や不思議と呼び、素朴な常識から逸脱した出来事を奇跡や神秘と呼んでいる。「謎」「不思議」「奇跡」「神秘」、それらは人の心にのみ存するのであって、世界はただ端的にあるようにあるだけなのだ。――この真理を悟ってしまったのだ。
サイコロを振って⑥の目が三連続で出たなら、大抵の人は「偶然」だと思うだろう。しかし⑥の目が三億連続で出たら、それは「必然」であり、何かサイコロに仕組みがあるに違いないと思うだろう。しかしサイコロに何の仕組みがなくても⑥の目が「偶然」三億連続で出る可能性はある。仮に偶然三億連続で出たならば人は「奇跡」だと思うに違いない。しかしよく考えると三連続と三億連続に決定的な差異はなく、「偶然」と「必然」と「奇跡」に明確な境界線などないのである。仮に無限大の存在者が三連続と三億連続に決定的な差異を主張する人々を見たなら、何という矮小な生き物だろうと苦笑するかもしれない。
規則性というものは世界に存在しない。規則とは人の心にのみ存在するのである。これは事実だと改めて確認しよう。
私はかつて「宇宙にはなぜ何もないのでなく、何かがあるのか?」という、いわゆる「究極の問い」を考究した結果、人が経験する現象の規則性や物理法則の普遍性は全くの偶然であり、根拠など必要ないのだと結論したことがある。つまり究極の問いには原理的に解答があり得ない。「宇宙がなぜあるか」という問いに答えがないのなら「宇宙がどのようにあるか」という問いは重要な問題ではない、と考えたわけである。
そもそもゼノンとカントによって行われた時間の非実在の論証は、同時に因果関係の非実在の論証でもある。因果関係が実在しないならば、世界全体は巨大な一枚絵のように「あるようにある」だけであって、その絵の「技法」としてのみ時間や因果を認めることができるということになる。つまりは現象に規則性が成り立っていること、物理法則が普遍的に成り立つことは、単に宇宙という巨大な絵が「人には規則性があるように見える」ようにしてあるだけで、「原因」を求めるのは的外れである、とかつて私は考えたのである。――しかしこのような考えは何かが間違っている。
「世界がなぜ存在するか」という究極の問いには解答がないのだから、「世界がなぜこのように存在するか」という問題にも解答がない。これは確かである。仮に人類が遥かな未来に科学的知識の極限に到達し、世界がどのようなあり方で存在しているかを十分理解したとして、それでも「なぜ世界はそのようなあり方で存在しているか」と問うことができる。しかしその問いに解答がないことは明らかであろう。人間理性は、最終的には究極の問いで行き詰ることが決定している。しかし現象の規則性が現実に成立していることをいきなり究極の問いで解消してしまうのは拙速である。それはカテゴリー錯誤の疑いがある。
或る人が道を歩いていると小石が一つ転がっている。更に歩くと小石が二個ある。更に歩くと小石が三個ある。……仮に小石の発見を十億個まで続けたとしても、道に転がっているのは「小石」であって「規則」ではない。規則性とは人の心にのみ存するのである。それは事実として認めたとしても、しかし人の心にある規則性に対応するものが外部世界に存在するならば、それは規則性が外部世界にあるのと実質的には何の変わりもないことも事実である。
人は外部世界に規則性を見出せるから生存できる。サイコロの同じ目の三連続と三億連続に差異を見出せるから生存できる。規則性や因果性はまさにカントの意味で「ア・プリオリ」な人間存在の条件なのである。
人が経験する現象に規則性が成立しているという事実があるのならば、単に反実在論の立場から「偶然」として片付けるのではなくて、実在論のように必然性を見出そうとする試みは形而上学的な意義がある。
第5章にて、私は理論哲学によっては現象の規則性の根拠を解明することはできないと結論した。つまりサイコロの同じ目が三億連続出ても「偶然」である可能性が否定できないならば、規則性に根拠があるか否かを論理的に判断することができないということである。そして私は理論哲学によって規則性の根拠を求めたカントの超越論的観念論は、純粋理性の誤謬推理であると結論した。
しかしカントが規則性の根拠を求めたことが間違いだというのではない。規則性がア・プリオリな人間存在の条件ならば、実践理性が規則性の根拠を探求することは必然なのである。論理と常識はしばしば相克する。しかし論理と常識の間には形而上学がある。
次のようなケースを想定してみよう。都会の歩道に一辺が五メートルほどもあるコンクリートの立方体が転がっているとする。これは「不自然」であると人々は思うだろう。しかしコンクリートの塊について何とか納得のいく理由を捜し求めるに違いない。たとえば近くでビルが建設中であり、これはそのビルのために用意されたものかもしれない、などと。
では、歩道に転がっているのが仮に純金の塊だったらどうだろう。巨大な純金の塊が街の歩道に転がっていることは、コンクリートの塊が転がっているより遥かに「不自然」だろう。しかし人はそのようなケースでも何とか理に適った説明を模索するはずだ。たとえば、その金塊は政府の金準備(中央銀行が輸入代金の決済等のために保有している金)のためのものであり、政府が移送中に何らかのアクシデントがあって放り出されたのかもしれない、などと。
では、仮に純金の塊から羽根の生えた小さな妖精が出てきて、妖精が魔法の杖をくるりと回して金塊と妖精が同時に消えたとしたらどうだろう。これは単に金塊が転がっているより遥かに「不自然」であり、理に適った説明が不可能だろう。このようなことがあると人は夢か幻を見たのかと思うだろう。
理性の「理」は理由の「理」である。英語では理性と理由はともに reasonである。世界にどのような現象が去来しようとも人は自らの本性に従って理に適う説明を求めるわけであるが、歩道にコンクリートの塊が転がっている場合は理由を自然に説明できるのに対し、純金の塊が転がっている場合は自然な説明が難しくなり、純金から妖精が出てくるという場合に至っては自然的な説明が不可能になる。
以上の考察から明らかなように「自然さ」「不自然さ」というものを探求していくと、現象の不自然さが増すごとにそれは形而上学的不可能性も高まり、不自然さはその極限において論理的不可能性に到達する、と結論できる。
人間が本性として物事の「理」を求めるのは哲学的合理性とも一致しているのである。
ここで原子の実在性を巡るマッハとボルツマンの論争を紹介しておこう。マッハは現象主義的な立場から知覚不可能な原子という仮説を嫌って原子論を主張するボルツマンを批判した。確かに論理的な観点からは原子というものを措定せずとも知覚される現象の規則性は説明可能である。ならば仮説を排除して現象をありのままに記述するという「思惟経済」にも理あるし、むしろ実証主義的な立場からすればそれは当然の方法論でもある。――しかし結果は周知の通り原子論に軍配が上がった。
マッハとボルツマンの論争から得ることができる教訓は、形而上学的な仮説を立てても、それで現象が上手く説明できるなら、その仮説が真である可能性が認められるべきだということである。――念のために書き加えなければならないが、この教訓自体が帰納法の妥当性を前提にしているため、ヒュームによる帰納法に対する懐疑を放置したままだということである。しかしマッハとボルツマンの論争が教訓にならないという証明もありえないのだから、これを教訓とすることに差し支えはないだろう。
色々と思考実験や例を挙げたのだが、私の主張は要するに、哲学は「論理的」なだけでは物足りないということである。論理的整合性を重んじるのは当然だとしても、それだけでは情報量が貧しく、世界の諸々の現象について僅かの説明しかできない。証明不可能な思弁的形而上学に陥るリスクはあっても、仮説を立てて「自然的」に現象を説明する試みは有意義なものだということである。
哲学は論理的かつ自然的であることが望ましいのである。これが実践理性の進むべき方向である。
形而上学的仮説には意義がある。カントが超越論的観念論という、一種の「仮説演繹法」によって現象の規則性を探索したことは、実践理性の正しい方向であった。とはいえ、カントの超越論的観念論によっては、現実世界で厳密に成立する現象の規則性が説明できないことは第5章で検証した通りである。では、現象の規則性が現実世界で成り立っていることについて、いかなる仮説を立てて説明すればいいのだろう?
2 実在論の可能性
カントは観念論の立場から現象の規則性を説明しようとしたが、第5章で検証したようにその試みは失敗に終わった。カントが成功しなかったのは、存在論としては構成主義的な観念論だからであり、時間と空間を含めた世界自体が「一つの統覚の世界」だからである。カントによれば世界は人の認識能力によって瞬間ごとに、そのつど構成されるのである。仮に他の統覚によって構成された世界があるとしても、それらは不可知であり、統覚と統覚、世界と世界の同一性を問うことはできない。――このような構成主義的観念論では現実世界で厳密に成立する現象の規則性が説明できない。
通常の百円硬貨の片面には 100の刻印があり、その反対面には桜の刻印がある。カントの観念論では百円硬貨を転がして上面に 100の刻印が見えて、「次に」硬貨の下面を見れば桜の刻印があることの必然性が証明できない。「上に 100があったのに下を見てもやはり 100だった」という現象が構成されてはいけない理由というものがないからである。私は夢の世界でそのような不合理な経験をすることがよくあるが、現実世界でそのような経験をしたことがない。あくまで物質的対象の実在を否定するカントの観念論では夢を現実を峻別することができない。
私はカントに近い観念論の立場から、これまで実在論を峻拒してきたのだが、ここにおいて重大な転向をせざるを得なくなった。
夢と現実を峻別するためには、「実在」というものを認めるしかない。時間と空間、それらによって規定される物質的対象が「経験に先立って」存在していなければ現象の規則性は説明するのは困難だからだ。
しかし第2章と第5章で検証したように、カントのアンチノミーの論証が成功していることは事実なのである。この点を忘れてはならない。ゼノンとカントが証明したように実在論は矛盾している。矛盾しているものは存在できないのだから実在論は間違いである。しかし反実在論では現象の規則性が説明できない。と言っても現象の規則性が説明できないことは矛盾というわけではない。――これが第5章第4節で論じた「擬似アンチノミー」という問題であった。
実在論と反実在論という相克する理論を融合させるアクロバットな案があればこのジレンマは一挙に解決するかもしれない。
私の発想は、実在論と反実在論をそれぞれ限定的に認めて融合させようというものである。この問題については、科学哲学の領域で議論されている「構造実在論(Structural Realism)」がヒントになった。
構造実在論は科学的実在論に指摘される「悲観的帰納法」に対処するためジョン・ウォーラルが 1989に提唱した。ただしウォーラルはアンリ・ポアンカレの哲学に想を得ているため、構造実在論の原型は二〇世紀初頭にまで遡ることになる。この時代にはバートランド・ラッセルやアーサー・エディントンも構造実在論と類似の主張をしている。
科学の歴史では、現象を説明するため作られた仮説が後になって廃棄されるということが少なくない。エーテル、絶対時間、絶対空間、熱素、フロギストンなどがそうである。したがって現在成功しているかのように見える科学理論も将来的には破棄されるかもしれない、と考えるのがラリー・ラウダンが主張した「悲観的帰納法」である。
それに対しウォーラルは次のように反論する。確かにフレネルの光学理論は経験的に成功したがエーテルを措定していた点で間違っていた。ニュートン力学は経験的に成功したが絶対時間や絶対空間を措定していた点が間違っていた。しかしフレネルの方程式自体は後のマックスウェルの理論に受け継がれており、ニュートン力学の数学的構造は後の相対性理論に限定的に受け継がれている。この事実から科学が記述する世界の数学的構造は悲観的帰納法を回避可能であるとみなすことができる、と。そしてウォーラルは「ニュートンが実際に発見したことは、彼の理論の数学的方程式で表現された現象間の関係である」と論じている。
ウォーラルは科学的実在論を擁護するために、物理的対象自体は不可知であるものの、現象間の関係の記述――世界の数学的構造のみは実在的なものとして認識できると考えたわけである。
その後、ジェームズ・レディマンとスティーブン・フレンチは独自の構造実在論を提唱し、自分たちの立場を「存在論的構造実在論(Ontic Structural Realism(以下 OSRと略す)」と称し、ウォーラルの立場を「認識論的構造実在論(Epistemic Structural Realism(以下 ESRと略す)」と呼んで区別した。
OSRと ESRはともに世界の構造のみが認識できるとする立場であるが、ESRが構造の背後に不可知な実体を想定するのに対し、OSRそのような実体を否定する点にある。OSRによれば、世界には不可知な実体など存在せず、むしろ現象間の構造こそが根源的で存在論的に実在的なものである。そして物理的対象は構造のノード(結節点)や、交差点へと還元されるとする。
レディマンらが OSRを主張する動機は、ESRが動機とした悲観的帰納法に加えて、量子的対象の決定不全性問題がある。たとえば電子は個体性があるとも解釈されるし、個体性がないとも解釈される。つまり量子的対象は粒子としてマクロな対象と同じように個物として扱われることもあるが、同時に量子場理論において「場」という非個物として扱われることもある。このような決定不全性問題から、OSRは量子的対象の非実在を主張し、量子的対象を数学的に記述した構造こそが真に実在的なものであると考えるわけである。
以上、構造実在論について簡略に説明したが、この立場が実在論としてはかなりラディカルな主張であり、反実在論と紙一重の主張であることは明らかだろう。実際に伝統的な実在論の立場から多くの批判が寄せられている。存在論的構造実在論は観念論に近い立場だとみなされることもある。トーマス・リックマンによれば、(構造実在論の原型である)エディントンの認識論は、カントの超越論的観念論に近いものである。
とはいえ、構造実在論が実在性を懐疑する対象は、あくまで電子やニュートリノのようなミクロな対象に限られ、太陽やリンゴといったマクロな対象の実在性は懐疑していない。この点が心の外部世界の実在性を否定するジョージ・バークリーや大森荘蔵のグローバルな反実在論との決定的相違である。
そこで私は、グローバルな構造実在論(Global Structural Realism:以下 GSRと略す)を提唱する。これは実在論と反実在論を調停する案というべきものである。GSRと従来の実在論との相違は、太陽やリンゴなどマクロな対象も、心に現れる現象と同じものは心の外部世界には実在しないと考えることである。GSRとバークリーの観念論との相違は、構造実在論が主張する意味での数学的構造が「経験に先立って」存在していると考えることである。つまり知覚対象の時間的空間的構造、エネルギー量などの実在は認め、また直接知覚できない粒子についても、物理学で記述される電荷やスピンといったものの実在は認めるわけである。
GSRによれば、世界に存在するのは現象(クオリア)と、その現象の数学的構造、および現象を去来させる世界の数学的構造のみである。単純に「現象と構造の二元論」と理解しても差し支えない。
なおウォーラルやレディマンは、悲観的帰納法を回避するため、また量子力学の決定不全性問題に対処するためにそれぞれの構造実在論を提唱したが、私はアンチノミーという純粋に論理的な問題に対処するため GSRという独自の構造実在論を提唱するのである。GSRならば、カントのアンチノミーを回避できる可能性が高い。
GSRの重要な特徴は、物理学で記述される時間と空間、および物質的対象が人の経験に先立って存在することを認めるものの、時間の「長さ」や空間の「広さ」は、人の純粋直観であるとして物理世界に存在することを否定することである。
無限分割や無限延長とは「広がり」や「長さ」といった知覚対象に対して成されるものである。しかし物理学で記述される数学的構造とは抽象的な「数値」として存在しているだけである。
たとえば「農地Aは広さ 1マイル四方です。1マイルは 1760ヤードで、1ヤードは 3フィートです」と言っても、ヤード法を知らない一般の日本人はこの説明で農地Aの広さを理解できない。この説明の中には「長さ」が登場しないからである。物理学で記述される時間と空間には元から「長さ」や「広さ」がないのである。1時間とは 1秒の 3600倍という「比」を表すものに過ぎない。1キロメートルとは 1メートルの 1000倍という「比」を表すものに過ぎない。長さや広がりといったものは第5章で説明したように純粋な人の直観であって、「長い」「広い」という印象である。長さや広さはそれ自体で実在しているものではない。科学で記述可能な数値や比と、人の直観が協働することによって初めて、素朴実在論的な意味での時間と空間が現れるのである。
ところで、GSR単独ではアンチノミーを完全に回避することはできない。仮に時間が実在しているのならば、物理学が記述する時間は抽象的な数値に過ぎないとしても、その時間は無限に延長可能になり、カントの第一アンチノミーが解消できないからである。したがって私は GSRを四次元主義と組み合わせる。
四次元主義は、相対性理論が記述する四次元連続体(四次元多様体)は単なる記述方法や説明の道具ではなく、一つの実体だと考える。この存在論は四次元連続体をパンの塊のような図で説明するので「ブロック宇宙説」とも呼ばれる。四次元主義ではそのブロック宇宙の内部に太古の恐竜も、西暦 2017年現在の出来事も、現在から 3000年後の未来の出来事も、全て存在していると考える。
この四次元主義と GSRの合成理論ならば、アンチノミーを完全に回避することができる。ブロック宇宙自体には始まりも終わりもなく、そのままの姿で永久に存在し続けるとされる。これが永久主義である。したがってビッグバンによる宇宙誕生の瞬間も、遥かな未来の宇宙消滅の瞬間も永久に存在しているとするのだから、宇宙の始まりに関するアンチノミーは存在しない。
さらに時間と空間の無限分割――ゼノンのパラドックスとカントの第二アンチノミーも回避できる。時間の「長さ」や空間の「広さ」は物理的世界には存在しないからである。世界の数学的構造が人の感覚器官(身体もまた構造のみが実在的である)を通じて、人の意識に道路やテーブルを現象させる。その道路やテーブルには「長さ」や「広さ」があるが、それらは純粋直観であり、意識内在的な「印象」である。その印象は「可能的に無限に」分割できることが示唆されている。しかし永久主義に基づくならば、永久主義は決定論に直結するのだから、「分割回数」も決定していることになる。四次元主義と GSRの合成理論においては、無限はあくまで「可能的」に留まり、「現実的」な無限は存在し得ない。
以上の説明を要約すると、私は伝統的な実在論に対しては時間の「長さ」や空間の「広さ」の実在を否定し、伝統的な反実在論に対しては時間と空間の数学的構造のみは経験に先立って実在することを肯定するわけである。
この形而上学は実在論の困難と反実在論の困難の双方を回避できるように思える。実在論の困難とは時間と空間の無限延長と無限分割を認めざるために矛盾していることである。反実在論の困難とは経験から独立した実在を認めないために現象の規則性が説明できないことである。私は実在論と反実在論の双方を部分的に否定し、部分的に肯定することによって双方を融合させ、双方の困難を一挙に解決しようとするわけである。
ただしこの形而上学にも一つ大きな困難があるように思われる。幾何学をどのように説明するかということである。
空間の長さや広さを純粋直観とした場合、心の外部世界に長さのない三角形や長さのない正方形が存在することになるが、それらは矛盾概念であるように思えるからだ。どのような三角形であれ、三角形であるためにはその一辺は一定の「長さ」がなければならないからだ。
次のように考えることはできる。――世界に存在するのは三角形そのものではなく、人の意識に三角形という現象を現す構造なのだ、と。これはコンピュータープログラムとの類比で理解すべきかもしれない。パソコンのモニターに三角形を映し出すプログラムはある。しかしそのプログラム自体に幾何学的な三角形の図が描かれているわけではないのである。プラグラムは三角形であれ円形であれバラの花であれエーゲ海であれ、どんな型でも色彩でもモニターに出力することができる。しかしプラグラム自体には形も色もない。C言語であれ Perlであれ、どのようなプログラムも最終的には「0」と「1」の二進数で記述される機械語に翻訳されてストレージに記録され、そして CPUにより実行されるのである。
ジョン・ロックの分類による物質の一次性質には、物質の「形」や「延長」が含まれていたが、私はそれらを二次性質に属するものとする。一次性質に属するものは抽象的な「比」や「数値」のみとするわけである(これは以前デイヴィッド・チャーマーズが構想していた「情報の二相理論」に近いものかもしれない)。
以上のような考え方によって、私は実在論と反実在論を融合させ、それぞれの長所を取り入れた形而上学を構築することができたと思う。
とは言っても物理的世界に「長さのない三角形」があるというのは、釈然としない説明だと多くの人が感じるだろう。この点については次のような批判が想定される。――長さ 10センチのコップがある場合、人は視覚的に 10センチの長さを感じることができ、かつ触覚的に 10センチの長さを感じることができる。視覚と触覚が「10センチ」という同一の「長さ」を指示対象として持つのは、10センチの長さそのものが経験に先立って存在していなければならない、と。
このような批判に対しては、バークリーが『視覚新論』で展開した空間論を援用して反論することができる。
まずバークリーはロックによる一次性質と二次性質の区別を批判し、色(二次性質)は物の形が見えるところに存在するのだから、色が心の内にしか存在しないならば、延長や形(一次性質)も心の内にしか存在しないはずだと主張した。
上の前提を置くならば、必然的に触覚的空間と視覚的空間は異なるものだということになる。つまり空間は最低でも二種類あるということになる。バークリーによれば双方の知覚には必然的結合はなく、人が経験によって双方の間に関連を見出すことによって「習慣的結合」が生じているのみである。。
大森荘蔵は『新視覚新論』第一章で、バークリーの洞察力を高く評価しながらも、空間は唯一であるとする論証を試みている。大森の論証は成功していないと私は思うのだが、大森の動機は理解できる。バークリーの説では視覚像と触覚像の重ねあわせの必然性が説明できないからである。
なお素朴実在論者からすると空間が一つなのは自明な前提であり、バークリーと大森の議論は意味不明だと思われる。彼らは心的一元論者であり、その立場から触覚と視覚が経験する空間の相違、および唯一性を考究した点に意義があるのである。
私が判断するに、バークリーも大森も部分的に正しく、部分的に間違っている。つまり長さ 10センチのコップがある場合、「10センチのコップ」という知覚対象は唯一であるが、10センチという「長さの感じ方」は二つあり、つまり視覚と触覚で異なるということである。
そもそも感覚とは何か?
「視覚」とは、対象の大きさや光の強さなどを「見る」ということである。物の大きさも光の強さも感じない視覚などないのである。つまり視覚像とは現れた時点で「長さ」や「広さ」の印象を持っているのである。
「触覚」とは、対象の大きさや硬さ温度などを「感じる」ということである。物の大きさも硬さも温度も感じない触覚などないのである。
視覚が対象を感じるということは即ち対象の「大きさを感じる」ということとイコールである。したがって視覚が対象の「大きさを見る」と言った時点で、それは触覚が対象の「大きさを感じる」ことと存在論的に異なる――すなわち「視覚像」と「触覚像」が感じた「大きさ」は存在論的に異なるということが証明されているのである。
10センチのコップの「見える大きさ」と「触れる大きさ」は同じ「大きさ」ではなく、存在論的に異なるのである。ただ 10センチのコップという「対象」は同じである。人は同一の対象を異なる仕方で感じているのである。
私は視覚や触覚でコップの大きさを感じることができる。しかしその視覚像や触覚像にある「大きさ」は純粋直観であり、コップという対象の「大きさ」を正確に表象しているわけではない、というよりコップには元から「大きさ」がないのである。頭の中に定規を突っ込んで視覚像の正確な大きさを測ることなどできないし、触覚像も同様である。
ただし対象間に感じる「比」や「関係」のみは実在的である。コップがテーブルの上にあり、テーブルの幅がコップの長さの 10倍ならば、コップとテーブルの「比」「関係」は、構造実在論が言う意味で実在的であり、視覚も触覚もその比や関係を把握することができる。このような意味において、大森が視覚像にせよ触覚像にせよ身体との「関係」でそれらを定位するとみなしたのは正しい。そしてバークリーが、視覚と触覚が感じる延長が異なるとみなしたのも正しい。
「大きさ」や「長さ」は純粋直観であり、「印象」である。これは第5章第2節でも論じたが、その印象に対し「数」や「操作」の概念を適用することによって現象世界は構成されると考えるべきである。
なお視覚と触覚の相違についてはモリヌークス問題を援用することもできるだろう。第5章で紹介したように、触覚だけで球体と立方体を区別していた先天的な盲人が手術で視覚を得ても、直ちに視覚だけでは球体と立方体を判別できないのであった。
モリヌークス問題が示唆していることは、「視覚が感じる長さ」と「触覚が感じる長さ」は、それぞれ独立の「長さ」だということである。視覚的な長さと触覚的な長さは、バークリーが言うように双方の長さを照合させ続ける経験を積み重ねてこそ、初めて同定可能になるのである。決して、長さそのものが物理的世界に存在して、視覚と触覚がそれらを指示しているわけではない。視覚と触覚が指示する物理世界にある同一の対象――「10センチのコップ」とは、抽象的な構造であり、それは科学によって記述することができるのみなのである。
以上のような考え方によって、実在論と反実在論の双方の欠点を克服可能な形而上学を構築することができると思う。
構造実在論の原型となったポアンカレの構造主義はカント哲学の影響も受けている。構造実在論は超越論的観念論の一形態ともみなされることもある。私はウォーラルやレディマンの構造実在論を更に反実在論寄りにすることで、アンチノミーという論理的問題を解消し、実在論と反実在論を融合させることに成功し、超越論哲学の最終形態に到達することができたと思う。
ところで、実在論と反実在論を融合させた私の形而上学なら、心脳問題が解決する可能性が開かれると思われる。
3 心脳問題と他我問題
構造実在論の主張を要約すると、人が認識できるものは「現象」と、その現象を去来させる世界の「構造」だけだということになる。電子や陽子など物質的対象を不可知、または実在性を否定するのだから、これは現象主義や観念論の主張に接近しており、心脳問題については心的一元論の利点を取り入れることが可能になる。
グローバルな構造実在論ならば、或る種の心脳同一説として、心の脳の同一性を無理なく説明できるように思う。これは基本的には私が第3章で構想した「現象主義的心脳同一説」と同型のものであるが、第3章の段階では「経験に先立つ存在」を認めていなかったため、現象の規則性についての説明力が不足していた。
ここで現代における心脳問題を手短に要約しておこう。
心脳問題の最大の困難は「心的因果」の問題である。たとえば時計を見て「電車の発車時間に遅れそうだ」と思ったなら、身体は駅に向かって走り始める。あるいは走っている最中に石につまづいて転び、アスファルトで膝を強打したなら、膝に「痛み」が発生する。――このような経験は誰にでもあり、心と体が因果的に関係し合っていることを疑う人は皆無だろう。デカルトが実体二元論を提唱し、心と体の相互作用を主張したのはもっともなことである。
ところが、この心と体の因果関係を具体的に解明するのは非常に難しい。デカルト以降、心脳問題に取り組んだ哲学者は夥しく、さまざまな解決案が提唱されたが、それらの案はおよそ次の四つの立場に大別される。
① 実体二元論: 心と物質は異なる実体であり、それらが相互作用する
② 性質二元論: 心と物質は同じ実体の二つの性質である(中立一元論も類似の立場である)
③ 物的一元論: 物質だけが実体であり、心的なものは物質に還元して説明される
④ 心的一元論: 心だけが実体であり、物質は心に表れたときにだけ存在する
④の心的一元論では第5章で詳説したように現象の規則性が説明できないのであった。①の実体二元論と②の性質二元論は現代でも支持する論者は僅かにいるのだが、この立場には致命的な難点が指摘されている。それは「物理領域の因果的閉包性」という原理に反するということである。
物理領域の因果的閉包性: 物理的現象は、物理的現象以外のものを原因として持たない
この原理は経験的に確かめられ、ほぼ確実な原理だとされている。すると心的なものは、それを実体とみなすにせよ、性質とみなすにせよ、物理領域の因果的閉包性によって物的なものに作用することができないということになり、心的なものがなぜ存在するのかわからなくなるのである。
いや、それを言うなら③の物的一元論も同じことではないか、と思う人もいるだろう。物質だけが実体的ならば、実体でない心的なものがなぜ存在するかわからないはずだ、と。ところがそうではない。現代の精練された物的一元論(唯物論)は、心的なものなど幻か錯覚のようなものだと存在を否定したりしない。物的なものと心的なものは同一の対象であり、観測のされ方が異なるだけだと主張するのである。つまり「痛み」にせよ「軽快なメロディー」にせよ、それら心的現象の実在性は認めた上で、それらは物理的な脳の状態と「同一」だと主張する。これが心脳同一説である。
なお心脳同一説は、狭い意味では「タイプ同一説」に分類され「トークン同一説」と区別される。機能主義や表象説など現代の物理主義はトークン同一説を前提にしているが、心的な状態は必ず特定の物理的状態と同一だと考える点では同じであり、ここでは双方をまとめて「同一説」と呼ぶことにする(同一説を物的一元論でなく性質二元論に分類する論者もいるが、ここではジョン・サール(2004)に倣って物的一元論に分類する)。
同一説では私に「痛み」があった場合、「痛み」は私にしか観測できない側面である。その痛みと同一である脳の状態は客観的に観測できる側面である。つまり明けの明星と宵の明星が見え方が異なっていても同一の星(金星)であるように、心的なものと物的なものは観測のされ方が異なるだけで、同じ対象なのだと考えるわけである。この考え方ならば、物理領域の因果的閉包性に反することなく心的因果を認めることができるのである。たとえば「電車の発車時間に遅れそうだ」という心的現象は特定の脳の状態と同一である。その心的現象=脳の状態を原因として、「駅に向かって走る」という結果が生じるとするのだから、説明に無理がない。
同一説は心的因果を説明できる唯一の理論とみなされ、ゆえに現代の心の哲学では物理主義――物的一元論がほぼ支配的となっている。
このような物的一元論全盛の状況下において、デイヴィッド・チャーマーズは物理的性質が同一でありながら、心的状態が欠如した人物――哲学的ゾンビが思考可能であると主張した。これは同一説の弱点を明快に指摘したものである。たとえば私に「痛み」のクオリアがあるとき、自分の脳の状態を fMRIなどで見たなら、物的一元論では、痛みのクオリアと脳の状態は「同一」だとみなさなければならない。しかしこれは同じ時点に認識される異なる存在者が同一だと主張するもので、不合理に思える。哲学的ゾンビが「思考可能」であることは否定できない。
チャーマーズが指摘したことの要点は、心的状態と物的状態が「同一」であるという説明には意味論的に無理があるということである。確かに心的なものと物的なものが同一だという主張は、「明けの明星と宵の明星は同一である」や「水とH2Oは同一である」という説明とは全く異なっている。
しかし同一説が心的因果を説明できる唯一の理論であることは確かなように思える。同一説は何らかの意味において必ず正しいはずである。心的状態と物的状態が「同一」であることを無理なく説明できるのならば、問題は解消するかもしれない。
そこで私が考案したのが、脳状態を心的状態の「科学的な構造」とみなそうということである。世界のどのような現象も普遍的な物理法則によって存在し、科学的に記述可能である。たとえば「ロケットの打ち上げ」という現象は、ロケットの形状、質量、エンジン推力、加速度・空気抵抗、燃料の化学反応など、様々な科学的要素の総合として記述可能である。大森荘蔵の「重ね描き」に即して言うと、「ロケットの打ち上げ」を知覚した場合の視覚や聴覚の経験を記述したものが日常言語による描写であり、「ロケットの打ち上げ」についての科学的要素の記述の総合が科学言語の描写である。重ね描きにおいては、日常言語による記述と科学言語による記述は、同一の対象の記述である。
グローバルな構造実在論(GSR)を前提にすれば、「重ね描き」を心脳関係にも適用できると私は考える。通常の実在論では物理的な脳は実在しているとされるのだから、心的状態と物的状態が同一であるとする説明には無理がある。しかし GSRでは、その脳の実在を否定し、脳の視覚像という現象と、科学的に記述される脳の構造のみの実在を認め、その構造の方が心的状態の科学構造だとみなすわけである。この説明ならばゾンビ論証で示された「同じ時点に認識される異なる存在者が同一」だとする無理がない。
たとえば私に「痛み」があるときに、自分の脳を fMRIや鏡で見たとしても、「痛み」と「脳状態」は同一ではない。「痛み」と同一なのは構造実在論が言う意味における脳状態の「構造」の方である。眼に見える脳状態とはその構造を「表象」したものである。私が感じる痛みは主観的にしかアクセスできない「現象的側面」であり、脳の状態は客観的にアクセスできる「科学的側面」である。このように考えれば「説明のギャップ」と呼ばれる問題は解消するはずである。
もちろん、「痛み」の科学的構造がなぜ「脳状態」として見えるのかという疑問はある。しかしこれは因果的な説明が可能であると思える。
そもそも椅子にせよテーブルにせよ外部世界の構造が見えることに必然性はないのである。仮に伝統的実在論(形而上学的実在論)が正しくても外部世界が見えることの必然性は証明できない。外部世界を五感で感じる得ること、および五感が存在することは、ア・プリオリな人間存在の条件とでもみなすしかないものである。そして五感と脳は因果的につながっている。
テーブルを見た場合の科学的・因果的説明を単純化すると次のようになる。――テーブルに光が反射して人の網膜に入り、視神経の活動電位が発生してニューロンが発火し、神経伝達物質が放出されて次のニューロンを発火させ、その活動が脳にまで伝達され、そして脳に複雑なニューロンの発火パターンが形成される。――この因果的説明の最終段階にある脳の状態の「構造」が、視覚的クオリアの科学構造だとみなすのである。そしてクオリアの科学構造が「脳の状態」として見えるのは、テーブルという視覚対象から網膜・神経・脳と、全て因果的につながっているからだとみなす。つまりテーブルから脳までの一連の物理状態は全て因果的に不可分のものであり、一つの因果系列なわけだから、テーブルが見えるということは即ち脳状態が見えるというわけである。
以上の説明によって「構造が見える」ことの不思議さは完全に解決、とまではいかないまでも大きな難点ではなくなったように思える。
ところで以上のように GSRという或る種の実在論が正しいと前提した場合、他我問題についても重要な示唆が得られる。
GSRでは特定の心的状態は特定の脳の状態の科学構造と「同一状態」として成立していると考えるので、他人に心があることは当然のこととみなされる。他人も私と同様の身体を持ち、五感を持ち、脳を持つ。脳が活動して特定の状態になれば、それが特定の心的状態と相関しているとみなすのは自然な考えである。
意識に相関した脳活動 (NCC) の研究が進められている。脳の特定の部位が損傷すると、特定の意識活動に障害が生じることがわかっている。たとえば後頭葉にある一次視覚野が損傷すると空間情報の把握能力が低下する。fMRIなどで他人の脳の状態を調べて、特定の部位が活動していれば、その部位に対応した意識活動が、おおよそであるが推測できる。
心的一元論では他我の実在性を認めることは極めて困難であった。世界は「私」の観念(クオリア)なのだから、私の観念に他人の心が相関していると考えることはできない。たとえば夢にも他者は登場するが、夢の他者に「心」がある考えるのは滑稽なことである。心的一元論では夢の他者も現実の他者も観念とみなすのだから変わりがない。私は以前に現象一元論を徹底した結果、他我の実在を認めることは困難であり、他我が存在しない証明もできないが、別の宇宙に等しい他我について語ることは無意味だと結論した。――今にして思えばこの考えは「不合理」ではなくても「不自然」であった。世界には多くの他者がいて私と同様の身体や神経系を持っている。世界には何十億の身体と神経の活動があるにもかかわらず、心的状態を生じさせるのが「私の身体と脳」だけだということの理由を、心的一元論では全く説明できないのであった。
しかし GSRという或る種の実在論を肯定して物質的対象が或る意味で存在することを認めるならば、他我の存在は自動的に認められる。他我について「自然な説明」ができるのである。もちろんこれは他我の存在を証明し得たということではない。しかし説明に矛盾がないならば、実践理性は自然な説明で満足すべきなのである。
とりあえず他我問題はこれにて一件落着、と言いたいのだがそうはいかないようである。次節以降はこその問題も含めて論じることになる。
4 無世界論と実在論
私は構造実在論と四次元主義を組み合わせて或る種の実在論を構築した。しかしこの実在論は私の形而上学の一つである無世界論と調和しないように思える。
ここで無世界論について手短に再論しておこう。
無世界論とは、人の直接経験(現象・観念・クオリア)の明晰性を否定するものである。たとえば道の前方にヘビを見て足を止める。ところがよく見るとヘビだと思ったものは朽ちた縄だったということがある。最初見たヘビは錯覚だったのだが、しかし「錯覚であるヘビの視覚像」だけは実在的である。――これが錯覚論法と呼ばれるもので、直接経験だけは懐疑できないとする論法である。しかし無世界論はその直接経験を懐疑するものである。
カントによれば現象は物自体ではないが、経験的に実在性を持つ。これが「経験的実在論」と呼ばれるものである。しかし経験的実在論が正しいとすると、現象世界そのものにアンチノミーが生じることになる。
私がこれから道路を歩くとしよう。その場合カントの経験的実在論によれば道路は現象なのであるが、その現象は実在性を持つ(この点はバークリーも大森も同様である)。ならば「道路には私の足に踏まれる可能性のある全地点が存在している」という前提がなければならない。すると僅か 1メートルの長さの中にも地点は無限個存在することになる。
現在の視覚像というものが仮に、「私の右足が左足より 20センチ先にある」というものだったとしよう。ならば、私の右足が存在できる地点は左足の 20センチ先のみだっただろうか? そんなはずはない。現象世界が経験的実在性を持つというのならば、「私の右足は左足より 21センチ先にあることも可能だった」という事実を認めなければならない。ひとたびその事実を認めたならば、空間的な「現在の知覚」の中には、それが僅か 1メートルの長さであっても地点は「無限個存在する」という事実を認めなければならない。
無限の部分を持つ存在とは矛盾なので、経験的実在論は間違いであり、道路の視覚像は実在ではない。現象であっても空間が実在するならば「地点」というものも実在する。これはニュートン的な意味での絶対空間でもライプニッツ的な意味での相対空間でも同じことであり、ユークリッド空間でも非ユークリッド空間でも同じことである。そして地点の数が有限個であることはできない。しかし地点が無限個実在するならば矛盾である。従って空間はカントが言う超越論的実在論の意味では実在しないことはもちろん、経験的実在論の意味でも実在しない。
この場合の「実在ではない」というのは、視覚像は対応する実在を持たないというバークリー的な意味での反実在論ではなく、視覚像そのものの実在性を否定するのである。つまり私の経験する視覚像は何らかの意味において存在していることは否定しないが、私が信じているような明晰な存在ではないということである。――このように経験の明晰性を否定するのがエレア派由来の無世界論である。
私が無世界論の立場を選択した理由はもう一つある。それは時間・変化の矛盾が観念論でも実在論でも解決できないからである。
変化とは「異なるものでありながら同一のものである」という矛盾概念である。或る交差点の信号が「青」だったとしよう。数秒後に信号が「黄」になったとしよう。この場合、事実のみを記すならば、「時点Aでは青である」「時点Bでは黄である」となり、「青が黄になる」という場合の、「なる」という事実は客観世界のどこにも見当たらない。もし青が黄になるというのが事実ならば、青と黄は異なるにも関わらず同一であるということであり、これは矛盾である。
この単純強固な変化の難問を、単純軽薄な方法で解決しようとしたのが四次元主義である。四次元主義の問題についても要約しておこう。四次元主義は永久主義を前提し、世界における変化の実在を否定しながらも、一つの存在者が時間的幅を持ち、かつ時点によって異なる性質を持つとすることで、変化の矛盾を解消しようとした。
四次元主義はワーム説と段階説の二つがある。ワーム説では時間によって変化する性質が「一つの存在者」の一時的性質だとして変化を説明するが、それは変化を説明するのに「一つの存在者」という変化を通じて同一なものを前提しており、論点先取に陥っている。対して段階説では、変化する性質はそれぞれ独立した存在者だとみなすが、そうすると或る性質が別の性質に「なる」という変化の本質が消滅してしまう。
四次元主義は実質的には変化を説明してはいないのである。ただし四次元主義のワーム説は何らかの意味において正しいと私は思っている。ワーム説では人の経験の明晰性を自明なものとして認めているが、その明晰性を否定すれば無世界論に近いものになる。
私はかつてヒュー・プライスの次の文に形而上学的な示唆を受けたことがある。
ひとはときどき、ブロック宇宙は " 静的 " であるという。だが、これはややもすると誤解をまねきやすい。ある時間的枠組みがあって、そのなかに四次元のブロック宇宙が終始同じ状態で存在する、というような言い方だからだ。もちろん、そんな枠組みなどありはしない。時間はブロックのなかに含まれているわけだから、ブロック宇宙を静的というのは、それを動的ないし可変というのと同程度に間違っている。ブロック宇宙はそんなものではない。なぜなら、それはふつうの意味での存在物といえるようなものではない。
このプライスの文を無世界論と牽強付会するのは拙速だろう。しかしブロック宇宙を「ふつうの意味での存在物といえるようなものではない」と看破した点は重要である。人が認識可能なものは空間的な対象であるか時間的な対象であり、いわば「ふつうの意味での存在」でしかない。これは当然で、カントの言う意味でア・プリオリに認識能力が制約されているからである。しかし時間と空間が融合したブロック宇宙の実態とは、時間的でも空間的でもない「ふつうの意味での存在」ではないはずである。ならばそれは人の認識能力では理解不可能なもののはずである。あるいはブロック宇宙こそが、カントの想定した物自体なのかもしれない。
ところで永久主義を前提する四次元主義に対して、現在主義ではブロック宇宙の実在性を否定し、それは相対性理論を記述するための道具的なものにすぎないとみなす。そして現在主義は、現在のものだけが実在し、過去のものは既になく、未来のものはまだないと主張する。これは素朴な人の直観と相性がよい形而上学である。
しかし「無からは何も生じない」という原理がある。それと対になる「存在するものは無にならない」という原理がある。現在主義では「ない」ものであった未来が「ある」ものである現在になり、「ある」ものであった現在が「ない」ものである過去になると主張しなければならない。さらに変化の実在を認めた場合は、カントが指摘した通り、過去の変化の回数が無限であることを認めなければならないが、無限の過去とは矛盾概念である。つまり現在主義には「無からの生成」と「無限」という二つの矛盾があるので全く認められない。
さらに現在主義では「クオリアの構成原理」という難問がある。痛みのクオリアがどのように構成されるかという問題は、自動車がどのように構成されるかという問題とは全く次元が異なるのである。脳の物理状態が或る状態になったら突然クオリアが「創発する」と考えるはナンセンスであるように思える。対してラッセルやチャーマーズのように意識は物質が普遍的に持つ性質だとみなす「汎経験説」と呼ばれる立場があって、この立場では物質に「原意識」のようなものを想定する。しかしそれは「赤」のクオリア四つと「青」のクオリア三つ合わせると「かゆみ」のクオリアになると言うようなもので、やはりナンセンスであるように思える。しかし仮に四次元主義が正しいならば、クオリアは永久に四次元主義の特定のポジションにあり、「構成」されることがないのだから、クオリアの構成原理を考える必要がない。この点でも現在主義は永久主義に大きく劣っている。
なお四次元主義は世界における変化の実在を否定するが、人の意識変化は認めるので現象世界において現在主義と同じ問題が生じることになる。
時間論の一種として独今論についても再論しておく。独今論は現在だけが実在し、過去は実在しなかったし、未来は実在しないだろうという主張である(四次元主義の段階説も実質的には独今論に近い)。
独今論は甚だしく反直観的ではあるものの、論理的可能性はあるように思える。
第4章でも私は独今論を検討し、「青が黄になる」にせよ「黄が赤になる」にせよ、二つの性質を「なる」でつなぎ、その「なる」ものが永久的に「ある」のななら、時間変化特有の動性を認めながらもアンチノミーを回避できると考えた。つまり「青→黄→赤」を一つの存在者だと考えようとすると、「青=黄」かつ「黄=赤」、しかし「青≠赤」と推移関係において矛盾が生じることになるが、「青→黄」のみなら矛盾はないので、独今論は論理的に可能な時間論だと考えたのである。
しかしこの考えは間違っていた。人が現実に変化を感じているとするなら、たとえ現在だけが実在するという主張であっても、その現在は無限小であることはできず、一定の「幅」がなければならない。しかし幅があるというのなら、それは既に過去と未来を持つ「時間」であって、独今論ではないはずである。
次のように考えることもできる。「青が黄になる」という存在者のみが永久的に存在するとしよう。しかしその存在者は、たとえ「青」「黄」という二性質間の変化であっても、変化である限りは変化の回数が数えられるのでなければならない。変化が「実在する」というのならば、それは人が変化の回数を数える行為に関わらず、変化が実在するということなのである。ならばその実在する変化に対してカントの第一アンチノミーが適用されることになる。「青が黄になる」という存在者が永久的に存在するとすると、「青が黄になる」という変化は無限回あったことになり、矛盾である。逆に「青が黄になる」という存在者が突然無から生じたと考えることもできない。
結局、独今論は矛盾した時間論である。
なお独今論と四次元主義の段階説は、空間の明晰性を認めるため無限分割の問題を解決できない可能性が高い。
アンチノミーを真に解決できるのは無世界論のみである。したがって無世界論は論理的に妥当な形而上学である。
逆説的な言い方をすると、変化の実在――変化を知覚する人の感覚の明晰性を否定する無世界論のみが、変化を合理的に説明できるのである。つまり「現象が変化しているように思える」という「錯覚」があることを認められるのである。
人が認識する現実、人が思考可能な時間論はいずれも矛盾している。したがって権利上は現実を超えた真実がなければならないのだが、人は認識能力が制限されているため、その真実にアクセスする権利が与えられていない。「現在の知覚をメタ知覚する」ことはできないということである。したがって私はカントの経験的実在論を否定し、人が経験している現象・現実は、人が認識している通りには存在しないと考える。これが無世界論の立場である。
しかし人の経験の明晰性を否定する無世界論は、いわば反実在論の極限であり、それは本章でこれまで論じてきた実在論と調和しないように思えるのである。
反実在論では現象の規則性がどうしても説明できないことから私は或る種の実在論を構築した。しかし経験の明晰性を否定するならば、「現象の規則性の認識」もまた否定すべきであるように思えるのだ。
もちろん無世界論では、諸現象は私が認識している通りの明晰なあり方をしているのではないとするが、逆に言うと、私がこれまで経験してきた物事は、何らかの意味で実在的だとみなすことが可能ではある。――しかしこのような考え方はあまりにもご都合主義であるとも思える。現前する現象の明晰性を否定していながら、その現象から推測された「現象の規則性」を一体なぜ信じることができるのだろう?
私は、自分が自己矛盾に陥っていると思わざるを得ない。
次のような考え方をすることはできる。――人の諸知識の確実性には度合いがある。デカルトは方法的懐疑によって全てを疑おうとしたが、決して疑えないものとして「我」を発見した。デカルトに倣って人の諸知識の確実性を吟味して格付けし、確実性の高いものを信じればいい、と。
一口に「知識」と言っても様々であり、以下の知識は性質が異なっている。
K_1: 五ひく三は二である
K_2: 私の腕に痛みがある
K_3: 花火が見えて三秒後に爆音がしたので花火との距離は約千メートルである
K_4: 私の自宅から四百メートル先に駅がある
K_5: 紀元前にソクラテスという哲学者がいた
K_6: 彼女は足をくじいたので痛がっている
K_7: 十年前私は崖から落ちる夢を見た
K_1は論理的判断による知識である。K_2は直接経験による知識である。K_3は物理学的知識に基づく知識である。K_4は経験に基づく知識である。K_5は社会的に承認された知識である。K_6は経験と推測に基づく知識である。K_7は個人の記憶に基づく知識である。
一般に人は K_1から下に行くほど知識の確実性は低くなっていくと考えている。しかし私は感覚による判断の確実性を否定しようというのである。
感覚は曖昧なもので、五時間ぐらい経ったと思っても実際は一時間だったりすることがある。一旦この事実を認めてしまうと「実際は一時間」という判断もまた感覚を根拠にしているのだから、感覚を根拠にする判断は全て絶対的な確実性がないということになる。
もっとも極端な消去主義のように感覚・クオリアの存在を完全に否定するのではない。また或る種の唯名論を主張しているのでもない。また逆にプラトンのイデアを想定するのでもない。つまり「痛み」を感じているとき、その痛みの明晰性を否定すると言っても、痛みが何らかの意味において存在していることは認めるのである。経験・クオリアの総体こそが私の哲学における不可知な「物自体」だとみなすのである。それは「私自体」でもあるだろう。
人は空間が曲がることをイメージできないが、相対論によると空間は曲がる。人の感覚や常識とは生存活動のために備わっているものであり、真理の探求の際にはそれらは障害になるかもしれず、一旦捨てる必要がある。
感覚・クオリアをそのように位置づけた上で、改めて知識の確実性について考える必要がある。
まず絶対確実とみなせるのが、デカルトのコギトと、古典的な論理法則、そして論理法則に還元可能な数学的真理である。これらは疑うことが不可能である。
次に確実なのは言葉の意味である。たとえば私に痛みがある場合(正確には痛みがあると判断している場合)、実際には痛みがないということは思考可能である。しかし「痛み」という言葉の意味を考えているとき、実際には「痛み」という言葉の意味がないということは思考困難だからである。さらに、痛みは「消える」ことによってその明晰性を失うのだが、「痛み」という言葉の意味が消えるということは思考困難である。
現象の規則性と物理法則にも、言葉の意味に近い確実性が与えられるように思う。宇宙ロケットの打ち上げを見る場合、私はそのロケットが最先端の科学技術の集積であると信じる。打ち上げられたロケットが空の彼方へ消え、それから何日か経ったなら、私はロケットの打ち上げを見た経験は夢か幻だったかもしれないと疑うことができる。しかしロケット打ち上げに要した科学技術が夢か幻だったかもしれないと疑うことは難しい。なぜなら「ロケットの打ち上げ」という言葉があるということは、それはロケットの打ち上げに必要な科学技術があるということに等しいからである。「自動車」や「コンピューター」も同様であって、それらの言葉があるということは、それらを存在させる科学技術があるということに等しいはずである。
以上のように、現前する現象の明晰性を否定しても、現象の規則性と物理法則の存在は、コギトや論理法則ほどの確実性はないものの、それなりに確実性が高いものとして認めることができるように思える。
それにしてもこのような考え方は、我ながらご都合主義に過ぎるという忸怩と懸念が拭えない。ロールシャッハテストの無意味なインクの染みに普遍的な意味を見出そうとしているような徒労感もある。私は現象の明晰性を否定していながら、その現象から推測された現象の規則性だけは認めようというのである。やはりこれは自己矛盾である疑いが否定できない。
無世界論はコギトと論理法則以外の全てを否定し得る威力がある。無世界論という摩訶不思議の世界で現象に規則性を見出しても、そんなものはすぐに消えてしまうのではないか。規則性とは同じ現象を「多く」経験することから見出されるものだが、その「多く」というのも一つの「印象」に過ぎないはずである。
サイコロを振って⑥の目が三回出たら「偶然」で、三億回出たら「必然」だと私は判断する。偶然と必然を分けるものは、つまるところ三億回は「多い」という印象に過ぎない。
もちろん本章第1節で論じたように、人は三回と三億回に差異を見出すことが出来るから生存できる。規則性や因果性はまさにア・プリオリな人間存在の条件なのである。
たとえ無世界論が正しいとしても、現象の規則性を求めることは「実践理性の要請」なのである。
このように結論しても、私は自分が無世界論に到達してから行っている哲学が完全に間違っているのではないかという不安を拭えない。
そもそも私は変化と時間の実在を否定することによって因果関係の実在を否定した。しかし認識に先立つ実在を措定することは、認識の「原因」を要求することである。これは矛盾しているのではないか?
しかし因果関係や相互作用は実在しないのだけど、「因果関係や相互作用に見えるものは何らかの意味である」わけである。世界が巨大な一枚の絵だったとしても、その絵が時間と空間という根源的形式によって描かれているのなら、人から見て因果関係や相互作用は実在するのと同じであり、人が経験する現象の規則性にはア・プリオリな根拠があるということになる。
しかし変化・相互作用が実在しない世界で、夥しい物事、そして(他我を認めるのだから)心的状態たちが、相互作用しているように見える状態で、永久的に存在しているというのは、摩訶不思議という言葉でも全然物足りないほど圧倒的に不思議なことである。
この問題は「究極の問い」そのものかもしれない。自分の哲学に対する不安や懸念は、最終的には究極の問いに回収されるのかもしれない。
5 死と実践理性の彷徨
私はグローバルな構造実在論という仮説によって、現象の規則性という反実在論が抱える難問を解消し、同時にアンチノミーという実在論が抱える論理的問題も解消した。
しかしこの構造実在論を前提した場合、死んだらどうなるかという問題が大きく影響を受けることになる。私はこれまで、自分が死んだらこの世界が消えると思っていたのだが、認識に先立って世界が存在するとしたならば、私が死んでもこの世界は消えないということになる。
それならば、私は死んだらどうなるのだろう?
実在論的説明を受け入れると、私の身体が死んで消滅するのならば、一見「私」も消滅するように思われる。もちろん論理的に考えるとそれは不可能である。なぜならば無から何も生じないように、存在しているものが無になることはない。ならば何らかの意味において「私」はこの私の身体が消滅した後も存続を続けることになるはずだが、実在論的な探求方法では、私の身体の消滅後を説明できるのは四次元主義ぐらいなものである。
無世界論と四次元主義を組み合わせて私の生と死を説明するならば次のようになるだろう。――私の経験する現象たちは、四次元時空の特定のポジションを時空ワームとして占めて永久的に存在している。時空ワーム内にある現象は、私が認識している通りの明晰なあり方をしているのではないが、何らかの意味において存在しており、(変化は実在しないのだから)私はそれら性質を一挙に経験している(正確には一挙に経験するということが「私」である)。未来の経験は既に存在し、過去の経験はいまだに存在し、現在の経験は私が思っているようには明晰に存在しない。――これが無世界論と四次元主義による「私」のあり方の説明である。
「私」とは「この人生」が全てであり、この人生のみが永久的に存在するということになる。
私は現象の規則性を説明するために実在論と妥協した。しかし実在論を認めるならば「私」は物質的実在によってその全体量がこの人生に制限されることになる。
「私」はほんとうにこの人生で完結しているのだろうか?
四次元主義を前提にするなら「私」はこの一つの人生で完結していると考えるのが妥当であるように思える。しかし今この瞬間だけが「私」の全てだとする或る種の独今論の可能性も完全には否定できない。また観念論が論駁されたわけではないことも想起すべきだろう。現象の規則性が成立していることは「偶然」だと仮定しても矛盾でも何でもないのであった。観念論が正しければ「私」全体はこの宇宙より遥かに長大なもので、この人生など砂漠の砂ひと粒に満たない儚い幻のようなものかもしれない。
さらに四次元主義が正しいと仮定しても、「私」が四次元時空の別のポジションを占める時空ワーム(他人)とつながっていると想定することも可能である。これは或る種の輪廻転生を認めることでもある。論理的可能性を考えるならば輪廻転生も荒唐無稽として一蹴することはできない。
それにしても、死後や「私」の全体量などのは原理的に確かめようがないものであって、実証主義的・実用主義的な傾向が強い現代の哲学者たちなら、このような問題は信仰の領域に留めるべきだとして語ることさえ憚るだろう。しかし私からするとそんな体裁や世間体に拘った哲学など軽蔑すべきものである
「私」の全体量とはこの私の最も重要な問題なのである。
私は心の哲学から自分の哲学活動を始めた。それはクオリアというものが「私」であると思ったからである。次に人格の同一性と時間の哲学を研究し始めたのは、そのクオリアがいかに時間変化を通じて同一であり得るかを知りたかったからである。私はずっと「私」を研究しているのである。
「汝自身を知れ」という格言がある。「私」の全体量を知ることができなければ、私は自身を知ることができない。「私」を探求する過程で最大のハードルとなるのが時間変化の問題である。「我思うゆえに我あり」と「私」を発見したつもりでも、その「私」は変化によって次の瞬間消えてしまうように思われる。デカルトはこの問題を深刻に受け止めていた。それが実体二元論と世界連続創造説として表されていると私は解釈している。
私は時間変化を否定して無世界論という極端な反実在論を構想した。この理論哲学だけでは「私」の全体量は全く不明であり思考することも適わない。しかしそれにグローバルな構造実在論を加えて、四次元主義が何らかの意味において正しいと仮定すると、「私」の全体量は明白であるように思える。ただし構造実在論と四次元主義は実践理性の要請として仮構したものである。理論哲学の段階に留まって思索を巡らすならば、他に多くの可能的な「私」のあり方が見出せる。
以下に思考可能な死後のあり方と「私」の全体量を並べてみる。
D_1 : この人生が「私」の全てであり、(死んでも)この人生が永久に存在する
D_2 : 輪廻転生があり、「私」の全体量は最大でもこの宇宙の歴史未満である
D_3 : 死後は全く未知の世界があり、「私」の全体量は全く不明である
D_4 : 今この瞬間のみが「私」の全てであり、この瞬間が永久に存在する
D_5 : 私の全経験は私の認識通りに存在せず、全く不明なものだけが実在する
D_6 : この私の死によって「私」は無になる
D_7 : 宇宙はループしており、この私が誕生した時点に戻る
D_1は前述の通り四次元主義を前提にした世界観である。D_2は四次元主義を前提に輪廻転生を認めるものである。D_3は観念論を前提にしたものであり、この世界は夢の一つのようなものだとみなすものである。D_4は独今論である(四次元主義の段階説も実質的にはこの立場に近い)。D_5は極端な無世界論である。D_6は時間論において現在主義を前提にした世界観である。D_7は或る種の永劫回帰説である。
それぞれの可能性を検証してみよう。D_2の輪廻転生は形而上学的に否定はできないものの、輪廻を統制する未知の原理があると想定するのは存在論的にかなり過剰かつ冗長であるように思える。また心脳問題については同一説が妥当であるとするならば、「私」は特定の脳と相関していなければならないので輪廻というのはかなりの飛躍となる。もっとも「私」と特定の脳の相関関係に必然性はない(これは第一章で「独在性のアポリア」として詳述した)ので、この私が千年後の特定の生物と相関して「私」の全体を成している可能性は否定できない。
D_3の観念論的世界像は現象の規則性が説明できないのだった。しかし規則性が説明できないのは致命的ではないので、論理的にも形而上学的にも可能性は否定できない。仮に観念論的世界像が正しければ、この人生は夢の一つのようなものである可能性が高く、「私」の全体量は全く不明である。死んだらどうなるかわからないという問題は、明日見るであろう夢が全くわからず、夢でどんな奇想天外な体験をするかわからないことと同じである。
D_4の独今論は既に検討したのだが、やはりこの立場では人の時間認識が説明しがたいように思われる。しかし現在経験の明晰性を否定する無世界論が正しいと前提すると、その「明晰性を否定された現在経験」のみが永久に存在するという新たな独今論の可能性が生じてくる。この新たな独今論の可能性は排除できない。
D_5は極端な無世界論である。現在経験の明晰性を否定するならば、過去の経験の明晰性も何もかもを、すなわちコギトと論理法則以外の全てを否定するということである。現象の規則性も私も過去の経験も「何らかの意味において存在する」のではなく、全くわからないとする極端な「不可知論」でもある。これは形而上学的に否定できないものの、人の認識をほとんど否定して絶対確実な知識のみを残そうとするのは、輪廻転生とは真逆のベクトルの過少な形而上学であると思える。
D_6は現在主義に基づけば事実であるように思えるが、既に論じたように現在主義は無からの生成と形而上学的無限という二つの矛盾を認める理論なので、全く可能性がない。とはいえ人は誰しも自然的態度に基づいて自分が死ねば無になるという直観を抱いている。それは自分の誕生から死まで時間は一方向に流れているという「時間の矢」の感覚があるからである。この感覚と論理が相克する問題は第4章で詳説した。人は感覚よりも論理による判断を信じるべきである。「二たす三は五である」ことを信じる者は、「存在するコギトは無にならない」ことを信じるべきである。双方は同じ論理に基づいた確証なのだから。
D_7は現在主義と同様に形而上学的無限を認めなければならないので矛盾である。もちろん、ループする世界内に存在する人間は、世界のループ回数に関わりなく全ての経験は「初めて」であり、一回限りなのだと主張することは可能だろうが、それは人の認識の事実であって、世界の存在の事実ではない。世界のループが実在するというのなら、ループの回数は人が数える行為に関わらず実在するということなのだから、ループ回数は二回であることも百回であることもできず、無限回ということになり、アンチノミーに至ることになる。
上の七つの分類に加えて神学的な立場から天国や地獄の存在可能性を主張する論者もいるだろうが、私はそのような可能性は全く語る価値がないものだと考える。論理的な可能性がないというのではない。私が列挙した七つの死後の形はいずれも論理的あるいは経験的な根拠があるが、天国や地獄や神などは人間の想像の産物であって有力な根拠を持たないからだ。
以上の検証によって、最も形而上学的に可能性が高そうなのはやはり D_1ということになるだろう。D_1は矛盾がなく過剰な仮説を立てていない。四次元主義は永久主義を前提とするが、ブロック宇宙内部には「見かけだけの時間」があり、この私の肉体が死んだなら、物理法則によってその肉体が分子や粒子に分解されると予測できる。「私」とは「この人生」が全てであり、ブロック宇宙の特定のポジションを占めるこの人生のみが永久的に存在するということになる。
D_1の可能性が高いことを認めざるを得ないのだが、しかしこれは受容できるだろうか?
ビル・ゲイツのように若くして成功し未曾有の栄達を重ねた人ならば、その人生が全てで、かつ永久的であることは素晴らしいと思うだろう。しかしそんな人はごく稀にしかいない。極端な話であるが、何の罪もないのに十歳の若さで惨殺された人ならば、その人生が全てであることは永遠の地獄でしかない。
稀に死んで無になりたいと言う人がいる。しかし永久主義が正しいとすると、人生は永久に存在しているわけだから死によって人生を消滅させることができない。死んでも無になれないというのは悲惨なことかもしれない。
奴隷制度は永遠にあり、魔女裁判の拷問は永遠にあり、戦争では女子供が永遠に殺されている。天国などあるわけはない。輪廻転生もたぶんない。これでは何の救いもない。永劫回帰を想定したニーチェのように「この瞬間」の永遠を肯定できるよう努力すべきだ、などと言っても意志や努力ではどうにもならない不幸もあるのだ。――こんなことが認められるわけがない。
しかし世界は人間の理想などに全く配慮せず、ただあるようにあるだけである。
巨象は自らの足跡を顧みて何を踏んだかなど気に留めたりしない。世界の人間に対する態度は凄烈に無情である。人間の理想や願望など全く顧みることなく世界はただ静謐にあるだけである。
しかし世界が人間の理想や常識におかまいなくあるというなら、死後についての各説の妥当性の高さを云々すること自体が妥当ではないようにも思われる。輪廻転生は過剰な仮説であると思うし、独今論や極端な無世界論は過少な仮説だと思うが、そういう私の「思い」自体が俗人の価値観に基づいている。世界は人間の常識などに構わずただあるようにあるだけなのだから、論理的かつ形而上学的に可能なものならば、死後には何があっても不思議ではないし、「私」の全体量がどれだけ長大でも短小でも不思議ではない。
不思議や神秘や奇跡とは所詮人の価値観に過ぎないのである。宇宙にモノリスがあろうとアリスが迷い込んだ不思議の国があろうと、そんなものは奇跡でも不思議でもない。世界は人の常識や理想など全くお構いなしに、ただあるだけなのだ。
仮に、奇跡とは因果律から逸脱した出来事だとしよう。すると世界の存在自体には原因がないのだから、ここで因果律は破れている。物語の世界に奇跡はあっても現実世界に奇跡などないと多くの人は思っているだろうが、現実世界が存在すること自体が驚愕すべき奇跡であり、また自分が存在することも驚愕すべき奇跡だということになる。したがって物語の登場人物が奇跡に遭遇したときのように、人は世界と自分の存在の奇跡に驚愕すべきなのだ。
現実世界に奇跡はある。これは紛れもない真実である。
やはり上で検討した D_1から D_5までの五つの世界観は論理的な矛盾がないため、いずれも可能性を否定することができない。
そうは言っても D_1の可能性が高く思われる事実は否定しようがない。
「私」の全体量がこの一つの人生で完結し、かつこの人生の諸経験が何らかの意味で永久に存在している可能性が高いことは認めざるを得ない。
では人生が一回で完結していることを認めたくない人間はどうすればよいのだろう。やはりニーチェが想定した永劫回帰を受け入れて、その人生が永遠に存在することを肯定できるるように独力するしかないのだろうか? これはあまりにも陳腐だという気がする。人生は一つしかないなんてことは誰でもなんとなくわかっていることであって、だからこそ皆ただ一度の人生を精一杯生きようと多かれ少なかれ努力しているのである。哲学者が永劫回帰や四次元主義などと大仰な概念装置を使って、人生の肯定の努力などと言うのは余計なお世話に過ぎない。
若くして非業の死を遂げざるを得なかった人は少なくない。そんな悲劇を思いやると人生の肯定など単なるたわ言にしか聞こえない。
では、救いとは何だろう?
死んでから神に会うとしよう。神が「同じ人生をもう一度繰り返すか、無になるか、どちらかを選びなさい」と言ったとして、無の方を選択した者は人生の失敗を認めたことになる。
「〔......〕するぐらいなら死んだほうがましだ」という言い回しはよく使われる。〔......〕の部分には無数の言葉が入りうる。これは人がやむを得ぬ最後の救済手段として、素朴心理学的な意味での死――無への転化を認めていることなのだと思う。しかし形而上学的に無が完全に否定されてしまったなら、最後の救済手段が消滅することになる。
十代の若さで惨殺された人に救いはあるのだろうか?
無世界論では人の経験の明晰性を否定するのだった。ならばその人は惨い死に方をしたのだけれど、その経験はその人が思っている通りの仕方では存在していないと考えることができるかもしれない。
私はかつて足を捻挫し、痛みに苦しみながら歩いていたことがある。あのときの足の痛みは、私が思っているような明晰な在り方では存在しなかったと考えるのである。そして、世界は永久に存在しているからといってあの足の痛みが「繰り返す」と思ってもいけないのである。その考え方は直ちに無限についてのアンチノミーに陥ることになるからである。
私の人生の経験はそれぞれ「一回限り」と考えてはいけない。しかし「複数回ある」と考えてもいけない。つまり時間はループしないが、経験が一回きりと考えても、消えると考えてもいけないわけである。
まるでネーティ・ネーティ(~ではない、~ではない)という消去法によってアートマン(真我)を示そうとしたウパニシャッド哲学のようであるが、このような方法でしか真の「私」は示すことができないのだと思う。
私はヘーゲルの哲学をよく理解しているわけではないが、『精神現象学』には「消えることが消える」という謎めいた文があって、それを読んだときこの人は何らかの真理を捉えた哲学者なのだと思った。単に「消える」というなら消えたものがあったことになる。しかし「消えることも消える」というなら、消えたものは元から私が思っているような明晰な存在ではなかったということである。もちろんヘーゲルの場合は自らの弁証法の一段階として件の文を書いたのだろうから、私の無世界論と親和的だと解釈するのは牽強付会だと承知している。しかし「消える」こと、また「消えることが消える」ことは現象学的な事実であって、物事は全て空間的な明晰性を維持することができず、単に消えるのではなく、消えることまでが消えるという魔法のような時間変化に晒されることになる。
ものごとが消えるということはどういうことだろう。無からは何も生じないなら、存在するものが無になることもない。しかし現実には全ての経験は消えていく。この現実は矛盾しているので間違いである。現実を超えた真実があるはずである。消えたものは元から私が思っているような明晰なイメージでは存在しなかった、そう考えるしかない。いくら現在のこの経験は存在すると確信しようと、その確信も消えていく。そして消えたという認識も消えていく。
カレンダーをぼんやり見ながら、このカレンダーは消えるのだと思うことがある。そして実際にカレンダーは消えていく。電車の窓外に広がる景色を見ながら、この景色は消えるのだと思うことがある。そして実際に景色は消えていく。夢の中でこれは夢だと気づき、この世界は消えていくのだと思うことがある。そして実際に夢の世界は消えていく。この現実世界もまた私の人生の終わりに消えていくだろう。
消えて良いのだ。ものごとは全て消えることによって存在の明晰性を否定され、そして消えることも消えることによって矛盾もまた消えていく。――これが無世界論の世界観である。
以上のような無世界論の解釈に基づき、十代の若さで惨殺された人や、魔女狩りで拷問された人の悲惨な経験は何らかの意味であったのだけれど、それはその人たちが認識した通りには存在しないのだと考えて、苦しみと恐怖を和らげることができるかもしれない。救いとは経験が「ない」可能性のことなのかもしれない。もちろん、それは完全な「ない」ではない。経験は「ある」のだけど、人が思っているような在り方では存在しないのである。仏教の「色即是空、空即是色」というのは、あながち間違いではないのかもしれない。
四次元主義はたぶん正しいと思われる。ならば「私」の全体量はこの人生で閉じており、この人生が永久に存在するということになる。しかし人生の各時点での経験は私が思っているようには存在していない。――このように考えるなら、全ての人はこの世界の現実を受容できるかもしれない。
しかしこれは随分と消極的な救済方法であると思われる。他に救いの道はないのだろうか?
・現実と実践理性
観念論が否定されたわけではないことを想起すべきだろう。もし観念論が正しければこの人生は夢の一つのようなものである可能性が高く、「私」の全体量は全く不明であり、死んだらどうなるかわからないという問題は、明日見るであろう夢が全くわからず、夢でどんな奇想天外な体験をするかわからないことと同じである。これは死後というものについて、私の考えうる限り最も明快な説明方法であり、第4章の段階では、私はこの説明方法に満足して観念論者として死を迎えるつもりだった。ところが現実世界で厳密に現象の規則性が成立しているという問題から、私は実在論者に転向せざるを得なくなった。
私を混乱させている元凶は現象の規則性であるように思える。夢の世界がそうであるように現実世界でも不規則な現象が生起するならば、世界が観念なのは明らかだということになり、実践理性の要請などと言って余計な形而上学を構想しなくてもよかったのである。
私が実在という問題に拘らざるを得ないのは、この問題が「私」の全体量という問題に決定的に関わっているからである。実在というものを認めたならば、「私」の全体量は実在というものに制約されることになる。実在の問題は死んだらどうなるかという問題と同じであり、形而上学と実存哲学の双方にまたがる哲学最大の問題なのである。
私は無世界論という世界観に実在論を取り込もうとしたが、実在論を徹底的に拒否して、無世界論と反実在論のみを認める方向もあり得るはずだ。
無世界論は論理的に正しいのだから否定のしようがない。しかしその無世界論にも実在論と反実在論がありうる。無世界論的反実在論では、世界とは「私」のみであり、現前する現象以外のものも何らかの意味で存在していることを認めるが、それはあくまで「私」の性質である。過去・現在・未来の全ての現象はひとつらなりのクオリアとして存在し、「私」を構成しているということである。対して無世界論的実在論では「私」の外部を認めることになる。
無世界論的実在論と無世界論的反実在論では、夢と現実と幻の位置づけは次のように異なる。
無世界論的実在論では真実の中に現実があって、夢や幻はその現実内部にある。対して無世界論的反実在論では、真実の世界の中に、夢も現実も幻も同等の身分を持って存在していることを表している。
これまで私が経験してきた現象の規則性は全て「偶然」だと仮定しても論理的には何ら問題ではないのであった。そもそも四次元主義も似たようなものである。四次元主義では時間変化は実在しないとするのだから、因果関係・相互作用はみかけだけのものだということになる。したがって現象の規則や物理法則が存在しているとしても、それらの存在は「偶然」だと考えるしかないのである。コンビニのレジで私が 1022円を出したのは店員が「1022円になります」と言ったことが原因で「生じた」出来事ではなく、単にブロック宇宙内部に永久的に存在していたのである。全ての出来事は何らかの原因によって生じたのではない。全ての出来事には「始まり」も「終わりも」ない。全ての出来事は永久に時間と空間という形式で描かれたブロック宇宙内部に存在しているわけである。
四次元主義による現象の規則性――つまり世界を説明する能力は、観念論と大きな差がないように思われるのである。
物理法則があるから現象に規則性が見出せるのか、現象に規則性があるから物理法則が見出せるのか、どちらが正しいのだろう? 宇宙には物理法則など存在しない。人が現象に規則性を見出してそれを物理法則と呼んでいるだけである。そう解釈しても物理学は何の影響も受けないし何も変える必要がないだろう。特に変化の実在を否定する四次元主義ならば、そう考えるべきなのである。
「私の全経験は既に存在していて、その経験たちは偶然時間と空間という形式によって描かれている」――この説明だけでは四次元主義なのか観念論なのか区別がつかないだろう。
観念論の可能性は捨てがたい。
四次元主義と観念論を融合させることもできるのである。
ここで再びマッハの自画像を引用する。
観念論的四次元主義とは、世界とはマッハの自画像のように、私の一人称視点で描かれた現象世界のことである。マッハの自画像は二次元的な描写であるが、理論的にはマッハの全人生を描いた「四次元的自画像」もありうるのである。
観念論的四次元主義でも世界の科学的・数学的構造は、構造実在論の意味で認識から独立して存在することを認めることができる。これがバークリーの観念論との相違である。つまり私の全経験は普遍的な物理法則によって描かれているのである。ただし観念論的四次元主義は「世界」と「私」はイコールの関係になるので独我論となる。ウィトゲンシュタインが言うように、主体は世界に属さない。
世界は偶然にもこのようなあり方で、永久に存在している――観念論的四次元主義ならばそう考えることができる。もちろんそんな偶然があるわけはないと素朴な人は直観的に否定するだろう。しかし因果律に依拠しないで、世界は偶然このようなあり方で永久に存在していると主張する点では、物理主義的な四次元主義も同じなのである。もちろん、どちらの四次元主義も因果というものを完全に否定するわけではない。世界は時間と空間という形式で「偶然」描かれているのだから、「因果関係に見えるようなものはある」ことだけは認めるのである。しかし世界内のどのような物事も、何かを「原因」として「生じた」わけではない。
確率が甚だしく低いことを表すのに「チンパンジーがランダムにタイプライターを打ってシェークスピアの作品ができるほどの確率」というたとえがある。これは「無限の猿定理」と呼ばれる。四次元主義ではブロック宇宙というものが何の原因もなくただ永久に存在していると考えるのだから、世界の存在理由として無限の猿定理さえ持ち出すことができない。シェークスピアの作品も、世界そのものも、何の理由もなくただ「ある」だけなのである。
あらためて、「世界にはなぜ何もないのではなく何かがあるのか」という究極の問い――形而上学の根本問題に戦慄せざるを得ない。この問いは神を想定したり現在主義によって変化を肯定しても解消できない。依然として神はなぜ存在するのか、変化する宇宙はなぜ存在するのか、と問えるからである。究極の問いでは確率や因果的説明の説得力など消滅してしまう。
やはり観念論が正しいのかもしれない。
夢で美しい女性と会話したことがある。これは楽しい経験だった。その数日後に現実で美しい女性と会話する機会に恵まれて、これも楽しい経験だった。そののち、夢と現実の女性との会話を比較して、どちらの経験が楽しかっただろうかと考えたが、意外に判断は難しかった。どちらの経験も存在したという点では同じであり、消えたという点でも同じだからだ。
世界は観念である。これは観念論が正しいからという理由ではない。私は元から諸観念のつらなりであるものを「世界」と呼んでいたということを、改めて思い知ったのである。実在世界というものは諸観念のつらなりから推定されたものである。実在論は正しいのかもしれない。しかし仮にそうであっても、私が世界と呼んでいるものは観念の世界である。したがって私が死ぬときにこの世界は消えていく。
では死んだらどうなるのかと再び考えざるを得ない。実在論が正しければ或る種の四次元主義が正しいはずである。しかし観念論の可能性は放棄できない。
可能世界は無限に考えられるが、人はいくつかの可能世界を現実に体験しているのである。目を閉じて音楽に聴き入っているときは一次元の世界を体験している。我を忘れて絵画に見惚れているときは二次元の世界を体験している。我を忘れて映画に見入っているときは特定の人物を世界の開闢点として持たない世界を体験している。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』のようなPOV形式の映画の場合は世界の開闢点となる人物がいる世界を体験している。FPSのような本人視点のゲームに没頭しているときは(世界内の特定の人物のみ操作できるので)この世界と同じ構造の世界を体験している。
この世界は観念であって、この世界が本人視点のゲームのような構造であるのは「偶然」と考えてもよいのである。
私が観念論を捨てきれないのには二つの理由がある。一つは前述のように四次元主義による現象の規則性の説明能力が観念論と大きな差がないからである。もう一つは時間の「長さ」や経験の量の「多さ」というものが純粋直観だと信じているからである。人の規則性についての信念とは同一の規則に基づく現象を「多く」経験することから形成されるのであるが、それらも実在でなく純粋な「印象」だといということになり、規則性についての信念の根拠が揺らぐのである。
明日、太陽が西から昇っても何も不思議はない。
この世界に私が存在しなかったということは思考可能である。では、私はどれぐらいの確率で存在することが可能だったのであり、どれぐらいの確率で存在しないことが可能だったのか、と問うことは可能だろうか? たぶん不可能だろう。
或る日本人が「世界人口が七十億人で日本の人口が一億二千万人だから、自分が日本に生まれる確率は約六十分の一だった」と言ったとしよう。このような計算は完全にカテゴリー錯誤である。
様相や確率とは世界を予測するのに役立つというのみであって、世界を決定するものではない。確率が一億分の一の宝くじを買ったとしよう。その宝くじの運命を決めるのは確率ではなく、あえて言うなら現実である。当たるにせよ外れるにせよ現実は確率という人の認識能力におかまいなく到来する。
現実はただあるだけであり、一億分の一の宝くじに当たったら人は「奇跡」だと思いたくなるだろうが、世界には奇跡など存在しない。逆に一億分の一の貧乏くじを引いてしまったら人は「凶運」だと思いたくなるだろうが、世界には凶運など存在しない。現実はただあるだけであり、その現実に対して奇跡だとか凶運だとかいっても無意味なのである。死後の現実もまたそうであり、死後には「奇跡」も「凶運」もなく、現実がただあるようにあるだけである。
しかし私は、死後はあるようにあるだけだと思索を止めることができない。
実は、死んだらどうなるかということを、生きていながら確認する方法が一だけつある。それはこの世界が観念であることを証明することである。
私がこの現実世界で奇跡と呼ぶに値することを起こせたなら、世界が観念であることが証明されるのである。だから私は滑稽な試みをやめることはできない。超能力で空を飛ぼうと毎日のようにジャンプをする。もし空を飛べたなら、世界が観念であることが証明されるのだ。多くの人が往来する雑踏を歩いているとき、私は人々に対し「あなたたちは実在しないんでしょう?」と心の中で呼びかけてみることがある。そのとき人々が一斉に私の方を振り向いて「そうです。私たちは実在せず、あなたの観念にすぎません」と言ったなら、世界が観念であることが証明されるのだ。もちろん何千回と失敗を続けたなら、さすがに実在論が正しいように思えてくる。しかしそんな思いにかられたとき、私の脳裏にヒュームの亡霊がひょっこり現れて、「千回失敗したから千一回目も失敗するとは限らないよ」と囁いてくる。ヒュームの言葉には説得力がある。
直観や常識は当てにならない。アインシュタイン以前の人は空間が伸びたり縮んだりするなど想像すらできなかっただろう。人間が神のまばたき程度の束の間の歴史で培った直観や常識などその程度のものである。
もし私がこの現実世界で空を飛べたなら、この現実世界でただの一つでも「奇跡」と呼ぶに値することを起こせたならば、観念論が妥当だと証明され、夢と現実と幻はそれぞれ存在論的に対等だということになる。そして死んだらどうなるかわからないという問題は、明日見るであろう夢が全くわからず、夢でどんな奇想天外な体験をするかわからないことと同じだと考えればいいのである。そして「私」の全体量がこの人生で完結していない可能性が高まるり、この世界が無数にある諸可能世界の一つにすぎない可能性が高まるのである。
哲学の道に終わりはない。しかしもしも空が飛べたなら、その瞬間私の哲学は終わるのだ。牢固とした現実というものを夢と同じカテゴリーに放り込んで、苦難に満ちた哲学の道から足を洗って飛び去ることができるのである。
観念論が論理的に否定できず、私が突如空を飛べるようになる可能性があるならば、空を飛ぼうと試みる価値はある。実在論は正しいと思われるが、観念論は完全に放棄できない。まことに滑稽であるが、これが実践理性の要求であり、実践哲学なのである。
実践理性は死ぬまで彷徨し続ける定めにある。
・最期のために
死の間際に私は何を思うだろう。実在論はたぶん正しいだろうが、しかし私は、自分で構築した無世界論と四次元主義と構造実在論を組み合わせた複雑な形而上学など確信できない。作家の瀬田栄之助は「死を前にしては、ニーチェもキルケゴールも役に立たなかった」と語ったという。これは当然である。死という圧倒的現実に対して哲学者の小理屈など通じるはずがない。
奇妙な言い方かもしれないが、死への不安や恐怖に苛まれることは、死ぬよりつらいことである。だから「ぽっくり逝きたい」という人が多い。死を迫るのを自覚して日々仏壇を前に経を唱えていた老人を知っている。溺れるものが藁に縋っていると一笑に付すことができないほど、死という現実は圧倒的に重いものである。以前その老人は孫である私の顔を見ると満面の笑みで顔を輝かせたものだった。しかし死が近くなってからは私が顔を出しても力ない笑みを浮かべ、彼方を見るような遠い目で私を見るようになった。死の重圧は小理屈をこねてもどうにもならないほど重いのだと少年だった私は思い知らされた。
その後、私自身も何度か死を覚悟せざるを得ない状況に陥り、死の圧倒的な重圧を自らの身で感じることになった。特に二十代の若さで死に直面したときの悲嘆と絶望の凄まじさはとうてい筆舌に尽くせるものではなかった。これまで私は何度か死地を切り抜けてきた。しかしやがては捕まることになる。
死の圧倒的な重圧に対抗できるものは単純堅牢な論理で構築された信念のみである。私はカラシニコフに倣った絶対に疑い得ない哲学を抱えて、死の深淵に飛び降りることになるだろう。これは第4章第8節で解説した。
「無からは何も生じない」「存在は無に転化しない」――この二つの信念は論理的に正しい。ならばそれらを前提に「私は存在する、ゆえに私は無に転化しない」と言えることになる。この単純堅牢な絶対に壊れない哲学のみが命を預けるに値する。
しかし哲学を学んだものなら三段論法は必要あるまい。「私はある」それだけでよいと承知だろう。「私」が「ある」ものなら「ない」にはならないのだから。
いやさらに哲学に通じた者ならば、「私」すら不要かもしれない。「ある」と言った時点でそれは「私」の存在を表しているのだから、ただ「ある」と言うだけでよいのである。
素朴なイメージでの死とは、自分が「ない」に転化することである。その迫りくる「ない」という圧倒的重圧に対抗できるものは、イエス・キリスト云々でもなく南無阿弥陀仏云々でもなく超越論的観念論云々でもなく量子力学云々でもなく、単純堅牢な論理に基礎づけられた「ある」だけなのである。
死は「ない」という化けの皮をかぶってやってくる。私たちは、その死をただ「ある」と言って受容すればいいのである。
大森荘蔵『新視覚新論』東京大学出版会 1982年
野内玲「科学的知識と実在 ~科学的実在論の論争を通して~」2012年
信原幸弘 編『心の哲学 新時代の心の科学をめぐる哲学の問い』新曜社 2017年
ジョージ・バークリー『視覚新論』下條信輔 植村恒一郎 一ノ瀬正樹 訳 勁草書房 1990年
ヒュー・プライス『時間の矢の不思議とアルキメデスの目』遠山峻正、久志本克己 訳 講談社 2001年
セオドア・サイダー『四次元主義の哲学―持続と時間の存在論』中山康雄 他訳 訳春秋社 2007年
Ladyman, J. (1998), 'What is Structural Realism?', Studies in History and Philosophy of Science, 29, pp. 409-24.
Worrall, J. (1989), 'Structural Realism: The Best of Both Worlds?', Dialectica 43, pp. 99-124.
Bitbol, M. (2002) 'Transcendental Structuralism in Physics: An alternative to Structural Realism'.
Ryckman, T. (2005) ,'The Reign of Relativity: Philosophy in Physics 1915-1925', Oxford Studies in the Philosophy of Science.
Ladyman, J. and Ross, D. (2007),'Every Thing Must Go',Oxford University Press.
French, S. and Ladyman, J. (2010) ,'In Defence of Ontic Structural Realism',Scientific Structuralism pp 25-42.
Russell, B. (1927). 'The Analysis of Matter', London: Routledge Kegan Paul.
Frigg, R. & Votsis, I. (2011) 'Everything you always wanted to know about structural realism but were afraid to ask',European Journal for Philosophy of Science 1 (2):227-276.
Isaac, A. M. C. (2012) 'Structural Realism for Secondary Qualities',Erkenntnis June 2014, Volume 79, Issue 3, pp. 481-510.
Poincare, H. (1902) 'Science and Hypothesis',translated by William John Greenstreet(1905),New York: Dover.
Poincare, H. (1905) 'The Value of Science', translated by George B. Halsted(1907), NEW YORK THE SOIENCE PRESS.
最終更新:2017年09月16日 16:42