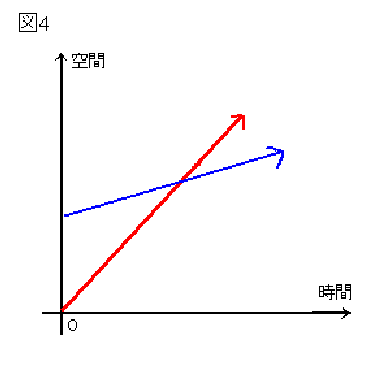1 夢の懐疑
幼い頃に恐ろしい体験をした。或る真夏の夜、私は両親と二人の兄弟と共に、家族五人で一つの部屋で寝ていた。家の一階北側の部屋で、中庭に面した窓を網戸にして涼を取っていた。エアコンがまだ高価だった昭和の時代のことである。
深夜、どさっと何かが落ちるような音がして目が覚めた。見ると畳の上でどす黒い異形のものが蠢いていた。蛇だった。一匹の大きな蛇が長い総身を奇怪に絡めて波打っているのだった。誰かが悲鳴を上げた。父が大急ぎで網戸を外して手に持ち、その網戸で蛇をつついたり掬ったりして、なんとか掃き出し窓から庭へ払い出した。そしてガラス戸を厳重に閉めた。どこから蛇が侵入したのかわからない。皆で室内を入念に点検した。天井から落ちてきたように思えたが、天井に穴など開いているわけではなかった。訝りながらも、しばらくして皆はまた眠りに付いた。しかし私は恐怖と興奮のためになかなか眠れなかった。
実家は関西の地方都市郊外にあり、周囲は水田が多く近くには里山もあった。そのため夏になると家の庭でも蛇を見かけることが度々あった。特に青大将は「人家に住む」と言われるほど人の生活と関わりが深い。鼠を追って天井を徘徊していた青大将が寝室に落ちてきたとしても不思議ではなかった。
中学生になってから、家族団らんの時にふと幼い頃の蛇の体験を思い出した。「そういえば昔でかい蛇が寝室に落ちてきて大変だったな」と私は話しだした。すると意外な反応が返ってきた。両親と兄弟の四人は、ぽかーんと呆気も露わな顔で私を見るのだった。「何の話?」と誰かが言った。つまり私以外の誰も蛇が寝室に落ちてきた体験を憶えていないのである。「それ夢見たのと違う?」また誰かが言った。そんなわけはない。畳の上で奇怪にうねる大きな蛇の姿を鮮烈に記憶している。あれが夢であるわけがない。現実に間違いない。しかし私がいくらあの出来事の詳細を話しても、誰も思い出さなかった。一体どういうことなのか。やがて誰かが言った次の言葉に私は納得せざるを得なかった。
「そんな大変なことがあったら皆憶えているはずだ」
寝室に蛇が落ちてきた出来事を憶えているのは家族のうち私だけであり、他の四人は憶えていない。多数決で私の蛇の体験は夢だということになった。確かにそんな大事があったのに他の四人が憶えていないのは不自然であり、あの蛇は夢だと考えるしかないように思えた。
しかし本当にそうだろうか、と今でも考えることがある。「そんな大変なことがあったら皆憶えているはずだ」という言葉には説得力がある。しかしその言葉は「多数決は正しい」という意味でしかないようにも思える。真実は多数決で決まるものなのか。やはり蛇の体験は現実の出来事であり、他の四人が忘れているのだという可能性は否定できない。夢だったのか現実だったのか――いや、もし蛇の体験が夢だったというなら、その他の幼い頃の様々な体験もまた夢だという可能性があるのではないか。一体何が現実だったのか。いや、そもそも現実とは何か。夢だったのかと懐疑しているこの現実も夢なのではないか?
何が本当の現実なのか――ひとたびこのような懐疑を抱いたならば、それは直ちに燎原の火の勢いで常識を焼き尽くし、その焼け跡に哲学の精神が立ち上がってくる。
ほんとうに「ある」といえるものは、一体何なのか?
デカルトが方法的懐疑として始めた夢の懐疑は底が深い、というより底が無い。底が無いとはどういうことか。現実と夢、実在と非実在といった峻別を
形而上学的に行うことが不可能だということである。ヒラリー・パトナムはデカルトの方法的懐疑の現代版と言える「
水槽の脳」という思考実験を行っている。この私は水槽の中に入れられた脳かもしれない。科学者がその脳に電極を差し込み、電極の配線をコンピューターに繋ぎ、私に仮想現実を見せている。私の肉体も多数の他者も毎日行く会社も、全て映画『マトリックス』のような仮想現実かもしれない、というのが水槽の脳の懐疑である。ただしこの思考実験は懐疑主義を批判するためのものである。私が仮想現実の世界にいることが事実だったとしても、それを確かめる手段が存在していない。仮に私が水槽の中で目覚めて、自分が水槽の中の脳だと確かめたとする。しかしその姿もまた仮想現実かもしれないからだ。そのような懐疑に満ちた世界においては、結局何が真実で何が絶対確実な知識なのかを知る手段が人間にはない。したがって懐疑によって諸々の知識の確実性を否定する懐疑主義は無意味だ、というのが建設的な結論となる。
しかしパトナムの水槽の脳は、単に懐疑主義を批判するためだけのものではなく、形而上学的実在論を否定するためのものでもある。パトナムは当初形而上学的実在論の擁護者であったが、後にその立場を放棄している。水槽の脳の思考実験で明らかなように、人間は神の視点で世界を見渡すことができないために、決して認識できない形而上学的な「実在」を云々することは無意味だというのである。このパトナムの転向は哲学者として誠実なものであろう。
しかし人間は形而上学的な意味での実在や真理を決して知りえないというならば、私が幼い頃に見た寝室の蛇は何なのか。あの恐怖の経験は何だったのか。蛇の存在論的な身分が問題となる。
・錯覚論法と幻滅論法
水を満たしたコップの中に箸を入れると、光の屈折で箸が曲がって見える。私は箸が本当は真っ直ぐであることを知っている。なら眼に見えている曲がった箸は何なのか。それは実在しないといわれても、今確かに見えている曲がった箸の心的イメージが存在することは事実である。これは錯覚論法と呼ばれる。幻であれ錯覚であれ、知覚経験は確かに存在し、その経験が錯覚か事実かは「後に」判断されるというものである。
科学的には次のようにも考えられる。網膜が光を捉え、視神経を経て脳のC線維が発火したら「赤」の
クオリアが生じると仮定する。しかし眼を閉じていても夢を見ていた場合などにC線維が発火することはあり得る。その場合、現実に赤いものが存在するか否かに関わらず、C線維の発火と赤のクオリアの存在は事実として認められるということである。
大森荘蔵はこの錯覚論法を発展させて「幻滅論法」というユニークな論考を行っている。大森は夢、幻、現実等々全ての経験を「立ち現れ」として対等に扱い、或る立ち現われを真実と分類し、別の立ち現われを虚偽と分類するのは、事実に基づくものではなく分類の仕方の違いに過ぎないと主張する。大森にとっては夢も幻も現実も、全ての立ち現われは等しく存在する、というより「存在する」という点において同じ資格を持っているとみなすのである。
大森はデカルトの方法的懐疑からこの論理を導出している。デカルトは『方法叙説』4部で次のように述べていた。
私は夢見ており、私の見たり想像したりするものは全て偽であると私は想定したのだけれども、しかしそれらのものの観念が私の中に真実にある、ということは否定できなかった。
ここでデカルトがいう「観念」は大森のいう「立ち現れ」の一分類といえる。大森は論文「ことだま論」において件のデカルトの文を引用した後、次のように述べている。
すなわち、デカルトにとって、夢の事物であれキマイラであれ、また眼前に見えるランプであれ、「それ自身において見られ、他のものと関係せられないならば」、それらの立ち現れは最も強い意味で「真」なのである。立ち現れたから立ち現れたのである。したがって、それらの立ち現れは最も原初的な意味で「存在」したのである。夢の立ち現れ、キマイラの立ち現れも「存在」したのである。
大森からすれば、諸々の立ち現われは生活実践上、実用的に分類され、後になって実在や幻と呼ばれるカテゴリーに入れられるのである。実在や幻という概念はあくまで立ち現れ内のカテゴリーであって、立ち現れの本性は幻も現実も「存在する」ということで貴賎が無い。ここにおいて幻は滅せられ、いずれの経験も立ち現れという根源的な存在者として認められる――これが幻滅論法である。
このような大森の論理は、物質世界が客観的に実在するという「
実在論」の否定を含意しており、
現象主義や主観的観念論とも呼ばれる。現代ではあまり評判はかんばしくない立場であるが、しかしここでは
実在論論争はさて置く。問題なのは私が幼い頃に見た蛇である。あの蛇は錯覚論法や幻滅論法によって確かに存在したことが確認された。しかし夢と現実を峻別することができないということは、巨大な問題が派生するのではないか。
2 現象主義と可能世界論
私は空を飛ぶことができるという信念を持っており、自分の恋人はマリリン・モンローであるという信念を持っている。そして事実として私は空を飛ぶ経験をしたし、モンローとデートの経験もしている。ただしそれら経験の事実は「夢」というカテゴリーに分類されるものである。
夢とは、現実とは異なる一つの完結した世界である。私が「現実」というカテゴリーに分類した世界では、私は日本という国に住んでいるという信念を持ち、空を飛びたいが飛べない人間であるという信念を持っている。端的に言うならば、夢の世界と現実の世界は信念の体系が異なるというだけである。いや、現実世界は夢から覚めても続いていくだろう、と反論する者がいるかもしれないが、それは間違っている。その現実世界なるものが夢より多く持っているものは、せいぜい「長く続いている」という信念ぐらいのものであり、それもまた今まで見終わった夢にもあったかも知れないものだ。夢も現実も大森の幻滅論法を援用して言うならば、最も原初的な意味で「存在」した世界なのである。夢と現実の区別を形而上学的に行うことは決して出来ない。これがデカルトの夢の懐疑と、それの現代版と言えるパトナムの水槽の脳の懐疑によって明らかにされたことである。
夢が現実と同じ地位を獲得したということはどういうことか。それは、世界には「この世界」だけでなく「別の世界」があると認めるということである。異なる信念の体系の世界である。
分析哲学では「可能世界」の存在論について議論されている。ソール・クリプキを代表とする「現実主義」の立場では、可能世界は思考の検証装置に過ぎず、存在するのは現実世界だけだと考える。対してデヴィッド・ルイスを代表とする「可能主義」の立場では、可能世界は現実世界と同じように存在すると考える。可能主義は「多元宇宙論」の一種であり、論理的にありうる世界(様相)は全て存在すると考えるため、様相実在論とも呼ばれる。ロバート・ノージックが提案した「豊饒性の原理」も様相実在論とほぼ同様の考えである。ノージックの薫陶を受けた物理学者のブライアン・グリーンも豊饒性の原理に基づいた多元宇宙論を提案している。また物理学者のマックス・テグマークも、論理的にありうる全ての数学的構造の世界が実在しているとする「究極集合」を主張する。
私がマリリン・モンローと結婚する可能世界というのは随分馬鹿げて思える。私は無名の日本人でありモンローは有名なアメリカ人の女優である、とか言う以前にモンローは私が生まれる前に死んでいる。しかし現象主義的な可能世界論では、私がモンローと結婚する夢を見たなら、その世界は「この現実」と同じ身分で存在したと言えることになる。
いや、夢は終わるものだがこの現実世界は持続するものだと実在論者は反論するだろう。しかし現象主義の世界観では、自分の死と共に世界も消滅するのである。現象主義者は「この現実世界」の消滅を自分の「死」と推定する。ならば夢の世界も現実世界もその根本――「世界」が消滅するということにおいて変わりがないということになる。
心理学者の
渡辺恒夫は自身のブログで次のように述べている。
「夢は覚める」という言い方は、自然的態度に基づいた言い方だ。現象学的には「夢はいつか終わる」としか言えない。そして、いつか終わる点にかけては、この覚めた世界、現実世界も同じことだ。
〔……〕
夢から覚めることが「現実」という別の夢の始まりだとすると、現実という夢から覚めることは、さらに別の夢の始まりを意味することになる。
渡辺は現象主義者ではないが、夢と現実は峻別できないという着眼は大森と同じである。
現象主義の立場からすると、私が空を飛ぶ夢を見たなら、私が空を飛ぶ可能世界は存在したということになる。そして私がモンローと結婚する夢を見たなら、私がモンローと結婚する可能世界は存在したということになる。なお留意すべき点であるが、夢と空想は全く異なる。私が空を飛んでいるところを想像すれば、その想像図は確かに存在するのだが、そこには「想像している現実の私」が想像図に浸透しているのである。
現象主義と可能世界論の関係で確かなことがある。現象主義では夢の世界を「この現実」とは異なる世界として実現したと認めざるを得ないのだから、他の論理的にありうる可能世界も全て存在可能だと認めるしかない、ということである。
ただし論理的にありえても、件の現象主義的な可能世界論では一つだけ実現不可能な可能世界がある。
デイヴィッド・チャーマーズが想定した「
哲学的ゾンビ」の世界である。ゾンビ世界は
現象的意識が一切欠如した世界のことだから、現象主義的には想像不可能ということである。
形而上学的に夢と現実を峻別することはできない。にも関わらず、いや現実とは特別な世界なのだ、とどうしても思いたくなる。今の私は夢を見ているのかもしれないが、やがて目覚めて現実世界に戻るのではないか、と。パトナムの思考実験は極端な例であり、「この現実」には「現実性」という特権があるように思えるからだ。
・現実性
「現実性」について論考してみたい。あくまで「この現実世界」の特権性に拘る者はいるだろうし、それは当然である。私は今頬をつねれば痛い。これこそ現実性であり、この現実性があることが現実世界の特権なのだと思いたくなる。しかしその「現実」とは何か。この問題が難解なのは夢の懐疑や水槽の脳の懐疑があるからだけではない。「この現実」もやがて過去となって現実性を失うからである。いや、今の私はリアルタイムで現実性を体感しているのだと思っても、思うと同時にそれは過去という非現実になっている。時間の哲学では「今」という時点の捉え難さが問題となっている。現実性はその「今」と相関しているから捉え難いのである。
現実である「今」は常に把握困難な速さで飛びすさって過去という非現実になっていく。「今」が捉え難いならば確実に存在したと言えるのは、「経験済み」の判が押された過去だけとなる。その過去は現実性を失っているのだから、現実だと思っている私の経験は全て幼い頃に見た蛇の夢に等く、逆に夢は現実に等しいということになる。つまり私が蛇を見た経験はほんとうに存在したのかわからない、というのでなく「経験」というものに対して「ほんとう」を問題にすることが無意味なのである。夢の懐疑や水槽の脳の懐疑は経験の真偽を問うことの無意味さを告げている。思い出の写真などを引っ張り出して、やはり過去はほんとうにあったのだと思っても無駄である。それは現在の経験であるし、その現在経験も夢に等しい過去となるのだ。
覚めない夢はもはや夢ではなく現実であり、消えていった現実はもはや現実ではなく夢である。これが現象主義の世界である。
大森荘蔵は論文「色即是空の実在論」で次のように述べている。
過去の実在性を経験できる場所は想起の経験をおいて他にはないだろう。
〔……〕
想起と独立に、想起以前にある過去というものを捉えようとしても煙のように消えていまう。結局想起から離れて自前で実在する過去などというものを把握した人間はいない。そのような実在過去の意味を人間は制作できなかったと思うほかはない。ではすると、私が何かを想起するとき、しかも上に述べた実在の確信をもって想起するとき、それは何らの実在にも対応しない妄想の類なのか。その通りであって、その実例をわれわれが夢と呼ぶ想起で経験しているのである。つまり、実在する過去というものの意味をわれわれが手にしていない以上は、すべての想起は夢なのである。人生夢の如しなどという感傷的比喩ではなくて、われわれの過去は夢以外のものではない。それに対応する現実は実在しないのだから。
ただし大森の場合は現在の特権性を否定しているわけではなく、逆に現在の特権性に拘っている。大森にとって過去とは「過去形の現在経験」ということになる。大森の哲学は直接経験に拘るため「現前主義」や「現前の形而上学」とも言われる。私の立場も基本的に大森と同じ現前主義である。現実の特権性を否定し、夢も現実も同じようなものだとしても、それらは「経験された存在」として、「経験されない存在」とは峻別するからであり、過去経験も想起される限りでその存在が認められるからである。これが現前主義であり、現象主義である。
入不二基義は直接大森に言及しているわけではないものの、このような現前主義を拒否して、独自の「現実性」についての哲学を展開している。入不二は次のように述べる。
どんな内容・質を持つ「感覚」であっても、それだけで現実性が与えられるわけではない。たしかに、現に感覚していること(現実の感覚)ならば、現実性を与えることができるが、それは、あらかじめ現実性を「感覚」に付与しているからにすぎない。同じことは、「現前」や「直接経験」についてもいえる。たとえば、何かが現前することや何かを直接経験することが、現実性を与えると誤解してはならない。話は逆である。「現前」や「直接経験」は、「現に」や「今まさに」という副詞性があらかじめ刷り込まれているのでない限り、それだけでは(すなわち「現前する何か」「直接経験の内容」によっては)、現実性を与えることはできない。逆に、たとえ「現前」していなくとも、たとえば「潜在」という仕方であっても、「現に潜在している」かぎりは、それもまた「現実」であることに変わりはない。その意味で、「現実性」は、「現前」「直接経験」とは別のことである。
入不二の形而上学は、現実性を様相の一つとしたカントに反し、現実性こそが様相の開闢点である。これは
永井均が〈私〉を様相の開闢点としたことと似ているが、入不二にとっては永井の〈私〉でさえも、「現実の〈私〉」や「現実でない〈私〉」というように、相対化されて様相内部に位置づけられる。
入不二の現実性についての論考は、着眼すべき点が微妙にずれているという印象を私は受けている。まず「現実」が捉え難いものであることは既に述べた。いくら自分の頬をつねって痛みを感じ、この痛みこそが現実性だと思っても、その思いは既に過去という非現実の一種である。いや、頬をつねり続けて持続的に痛みを感じることはできるし、痛みながら「これが現実だ」と言うこともできるだろう。しかしその確実に思える現実もまた過去のことである。
「今」に痛みがあるというのは素朴心理学的な態度であり、哲学的にその「今」を定義するのは難しい。時間軸上で過去と未来に挟まれた「今」は無限小であるしかないが、無限小とは一切幅の無い理論上の時間である。それは自然科学の道具であり、現実的に存在できない虚構である。人は虚構の時間の中に痛みを感じることはできない。ただし「今」とは無限小のものではなく一定の幅を持っているのだという意見もある。しかし時間が実在すると仮定するなら、それは無限分割可能な連続体であるしかない(ここではプランク時間という物理学の仮説はさて置く)。それは過去と未来に分割可能である。人は過去の痛みを感じることはできないし未来の痛みも感じることはできない。また幅の無い境界としての「今」の中にも痛みはない。ならば「今」の中に現実や感覚があるのではなく、むしろ感覚の中に「今」や現実があるというのが合理的結論になる。入不二は現実性を感覚や直接経験、つまりクオリアより根源的なものと考えたが、それは順序が異なっており、クオリアがなければ現実性もないというのが私の考えである。
しかし入不二の立場からは次のような反論があり得るだろう。現実性の本質は「無内包」であり、内包であるクオリアには依存しないのだ、と。入不二は次のような論法で「無内包の現実」を抽出している。
「この今」「現実的な現在」だけに特有の「内包」を探そうとしても無駄である。たとえば「直接経験」のようなものを、その「内実・中身」にすることはできない。なぜならば、過去にもその時点での「直接経験」はあったのだから、「直接経験」という点だけでは、過去と現在(この今)を区別することはできないからである。
〔……〕
「この今の」「現に起こっている」は、「直接経験」ではない無内包のものであらざるを得ないのである。
また入不二は『あるようにあり、なるようになる 運命論の運命』で、次のように述べている。
現実は、それが全てでそれしかなく、様相を持たず、特定の中身・様態に依存しない。この全一的で・無様相で・空っぽのあり方こそ、ことばの正確な意味において、「絶対現実」(対を絶する現実)と呼ぶのが相応しい。「絶対現実」とは、「現に」という現実のことであり、その全一性・無様相性・無内包性を集約した表現である。
上の文に続いて入不二は、全一的で無内包の「絶対現実」が、特定の内容・様相を持った「相対現実」へと転落してしまうことを論じている。ちなみにこの「絶対現実」と「相対現実」の区別、そして前者から後者へ転落するプロセスの説明は、永井均の「独在性」の問題――世界の中で自分だけが特別な〈私〉であることの主張が、他者からも同様に〈私〉であると主張され続けられてしまう構造(独在性の累進構造)と、同型である。ちなみに永井は入不二の「無内包」の概念を自身の独在論に取り入れて、〈私〉は
無内包の現実性であると主張するようになっており、入不二の「現実性」と永井の〈私〉は、近似的な概念となっている。
しかし私の立場からすると、無内包の「現実」や〈私〉というものは理解し難い概念である。
ここでデカルトの方法的懐疑が想起されるべきだろう。デカルトは『方法序説』において、疑うことが可能なものは全て疑った後、決して疑い得ないことを発見した。それがかの有名な「我思う、ゆえに我あり」であるが、しかしデカルトはその後も慎重に分析を続け、『省察』で次のように論じている。
私は在る。私は存在する。これは確かである。ではどれだけの間か? すなわち私が考える間である。というのも、もし私がすべての思考をやめるなら、その瞬間に私が在ることをまったく停止する、ということがおそらくありえるからである。(第二省察)
「私」が思うゆえに存在するのなら、思うことをやめれば「私」は存在しない可能性がある。双方は対の論理になっているのに、後者は見落とされがちである。疑い得ない「私」を発見したことのみにあぐらをかかず、その「私」が存在しなくなる可能性とその条件を真摯に見定めた点にこそ、デカルト哲学の真髄がある。この最も哲学的純度の高いデカルトの洞察を敷衍して考察を進めるなら、「現実性」や〈私〉があるから「痛い」や「甘い」や「美しい」があるのではない。事態はその逆であって、「痛い」や「甘い」や「美しい」があるということが即ち「現実性」や〈私〉があるということになるはずである。
デカルトの根本原理に従うならば、思うゆえに「私」が存在するのだから、思うことをやめれば「私」は存在しない。ところが「無内包」を認めると、思うことをやめても「私」が存在することになる。これはデカルトの根本原理を前提すると矛盾である疑いが強い。したがってデカルトの哲学的純度を維持しようとするなら「無内包の現実」は認められない。
ところで〈私〉の哲学と違って「現実性」の哲学では、世界に何もなく考える者もない場合、「何もない現実」というものが想定できるかもしれない。しかしその想定には暗に「何もない現実」を思考している何者かが前提されている。したがって現実性とはあくまで誰かの視点依存的な概念なのである。誰の視点にも依存しない現実とは「真実」や「実在」に他ならない。――このように説明すれば上で私が述べた「クオリアがなければ現実性もない」という言葉の意味も理解できるだろう。
なお、私の立場からすると入不二が「無内包」の概念を抽出する過程には矛盾があるように思える。「この現実」は全一的なものであり、対抗馬がいない。他人にも現実に心があるかもしれないというのは事実だし、他の時点も(永久主義を前提するならば)現実に存在するかもしれない。しかしそれらは必ず「かもしれない」という但し書き付きで表現されなければならないものである。他の「現実かもしれない」ものたちを、「この現実」と同格のものとして論点先取的に前提した上で現実性の無内包を主張するのは、人の認識能力を超えた飛躍を行っており、既に「現実性」の意味と矛盾しているのである。認識論的事実を述べるならば、他人の心も他の時点も、あくまで「現実かもしれない」ものに過ぎないのである。端的な「この現実」のみが真に「ある」と言えるものであり、他の「現実かもしれないもの」たちは「ない」に等しいと言って差し支えないほど絶対的な認識論的懸隔がある。
「現実性」とは単に様相の一概念であるのみではなく、人の認識能力を制限するものでもある。全ての時点と地点を平等に見渡せる神においては、全ての時点と地点が現実化しているだろう。しかし人にとって現実化している時点と地点は「今・ここ・私」だけである。人はその現実から他の全てを推測しているのが事実なのである。
たとえば「私は昨夜カレーを食べた」と言う場合、その意味は他人にもわかるだろうが、事実はわからない。「私は歯が痛い」と言う場合も同じことで、クオリアの私秘性というのは事実へのアクセス不可能性ということである。いや、「カレーを食べた」の場合は昨夜の私の行動を調査すれば事実が判明するのではないか、と思うかもしれない。しかしいくら調査しても発見できるのは事実の痕跡であって、事実自体ではない。「事実」とは広範な概念であって、これを哲学的に厳格化すると「真実」となる。真実にアクセスできないという問題は、他人のクオリアも過去も実在も同じで、その問題ゆえに認識依存的な「現実」と、認識を超えた「真実」の峻別が要請される。認識(クオリア)だけが与えられていて、真実を経験できないというのが人の現実である。人には「真実」が与えられていない。
「今・ここ・私」だけが「現実」なのである。その現実はデカルトの「私」と一致する。
しかし私の全身が「痛み」に支配されていたとしても、その痛みのみが「私」というわけではない。痛みを「私」と定義してしまえば、次に現れるクオリアとの同一性を考えることができなくなる。したがって「私」とは、次々に生起する一連のクオリアの総体のことであるだろう。――ここで困難な問題が生じることになる。それぞれが全一的で排他的なクオリアたちが、一体どのようにして「つながる」ことができるかということである。この問題こそが入不二や永井が提起した問題と重なっていながら、重心が異なる「現実性」の真の問題だと私は考える。
前章にて私が出した解答は一種の永久主義・四次元主義である。永久主義と言っても多様な立場があるが、現代では一般的に相対性理論から導出された四次元多様体(ブロック宇宙)を実体とみなし、存在者は空間を占めるだけでなく時間的幅を持つと考えるので四次元主義と呼ばれる。この立場では実在世界の変化を認めず、過去・現在・未来の事物が全て四次元多様体内部に実在していると考える。人は過去・未来に痛みを感じることができず、幅の無い「今」にも痛みは無いというなら、痛みの場所として四次元時空を考えるしかない。つまり永久主義を選択するしかないと私は考えたのである。
しかしここで新たな問題が生じるのだった。クオリアとは常に変化しているように思える。そして変化があるなら時間もあるはずである。永久と変化は相克する概念である。永久主義の立場を選択した場合、現に変化している(と思われる)知覚現象と、変化の実在を否定する理論とのギャップが大きな問題となる。この問題こそが前章で私が行き詰ったものである。
次節にて、改めて「変化」について論考してみたい。
3 マクタガートに見る「変化」の難問
変化とは「なる」ことである。或る状態から別の状態に「なる」ことが変化である。「時間が流れる」や「時間が推移する」という言い方で変化を表す場合もあるが、それらも或る状態から別の状態に「なる」ことを表しているのだから、変化の本性を最も縮約した言葉は、やはり「なる」ということになる。
時間の非実在を主張したマクタガートは、変化の問題について注目すべき洞察を行っている。それは時間特有の変化に晒されるものを、「人」や「物」ではなく「出来事」と考えたことである。一般的に人は「彼は変わった」という言い方をするが「彼の死は変わった」という言い方はしない。つまり出来事は元から変化しないものであり、それ自身すでに変化・発生・消滅といった概念を含んでいる。出来事に到来する変化とは、過去・現在・未来という、時制変化のみということになる。
マクタガートの主張を敷衍して「なる」について考えてみよう。「物」については、「青いつぼみが赤い花になる」という場合の「なる」は客観的に登場しない。或る時点では「青いつぼみ」の物があり、別の時点では「赤い花」の物があるだけであり、人が双方に「同一性」を見出さなければ前者が後者に「なる」と言うことはできない。しかし「出来事」については、或る時点では「現在」であったはずの「タイタニック号の沈没」は、別の時点では「過去」に「なる」。一見、ここでは「なる」が客観的に表現されるように思える。「物」は変化せず、また過去・現在・未来という時制変化からも逸れるが、「出来事」はそれ自体変化しないものの、過去・現在・未来という時制変化に晒される。――これがマクタガートが時間特有の変化は物でなく出来事にあると考えた理由である。
マクタガートは一見「なる」を客観的に捉えたように思える。しかし、そもそも「出来事」とは何かということをよく吟味してみれば、マクタガートの論理に綻びが見えてくるはずだ。例として「タイタニック号の沈没」という出来事を解体してみよう。それは結局以下のような複数の「物」の「結びつき」であろう。
物1: 洋上にあるタイタニック号
物2: 氷山に接触しているタイタニック号
物3: 船体の半分が海中にあるタイタニック号
物4: 船体の全てが海中にあるタイタニック号
それら複数の物の「結びつき」は、もちろん客観世界に存在しているのではなく、人の主観によって見出されたものに過ぎない。「出来事」とは人の心の中にしかないのではないか?
なお入不二はマクタガートによる「物」と「出来事」の区別を批判して次のように述べる。
〔……〕「出来事についての時間変化」からもまた、同一不変の「(高階の)こと」を切り出すことができるはずである。たとえば、「出来事Eが現在のことから過去のことになる」から「出来事Eがある時点 t1で現在であることを」を切り出すというように。
※ちなみに伊佐敷隆弘によれば、マクタガート自身もこの困難に気づいていたという。
この論理からすると、出来事Eが或る時点で「現在」であり、別の時点で「過去」であることは永久に変わらないということになる。マクタガートと入不二の主張の違いをわかりやすくすれば次のようになる。
マクタガートの主張: 「タイタニック号の沈没」という出来事はそれ自体変化しない。しかしその出来事は過去・現在・未来という時制変化に晒される。
入不二の主張 : 「タイタニック号の沈没」という出来事は、一八九九年では未来であるということ(高階の出来事)、二〇〇一年では過去であるということ(高階の出来事)は永久的であり、過去・現在・未来という時制変化に晒されない。
確かに、入不二の言うように「高階のこと」は永久に変わらない。とすると出来事が時制変化に晒されるとしたマクタガートに反して、「高階の出来事」を想定することによって、出来事もまた変化せず、「なる」が客観的に存在しないと考えることができてしまう。つまり「出来事は現在であるものが過去になる」と言う場合の「なる」は、結局「物」と同様に人の主観によって見出されたものということであり、変化の本質である「なる」がここでも消去される。
ただし入不二は変化を否定するわけでなく、続けて次のように述べている。
〔……〕そして、同一不変の「こと」(「Xがある時点 t1でPであること」)が、現在のことから過去のことになるのと同じように、同一不変の「(高階の)こと」(「出来事Eがある時点 t1で現在であること」)自体もまた、まさに現在のことからやがて過去のことになる。
〔……〕
すなわち、時間特有の変化は、「こと」の高階化に伴って、さらに高階の変化として取り出される。時間特有の変化は、変化の中から切り出される固定的なものに対しての、さらなる高階の変化として、原理的にはどこまでも高階化しうるのでなければならない。通常、困難や欠点として指摘されることの多い、この無限後退(の可能性)は、むしろ時間変化の「高階性」を示唆していると見なすべきである。
時間特有の変化の特異性は、ものと出来事という区別に基づくのではなく、その「高階性」にある。
〔……〕
時間変化が「高階の変化」であるということは、変化の中からどんなに固定的なものを切り出したとしても、その固定的なものへも波及せざるを得ない変化だということであるということは、時間変化の「高階性」は、時間変化の「汎浸透性」でもある。時間変化に晒されることから、逸れる固定的なものなどない。
時間特有の変化を「高階性」としたのは優れた洞察であると思う。しかしこの入不二の論法は、見方を変えれば変化の実在性を否定する論法と読み変えることができる。つまり、「出来事Eは或る時点で現在であったこと」という高階の出来事もまた、より高階の出来事を想定すれば永久的であるしかない。そのより高階の出来事もまた更に高階の出来事を想定すれば永久的である。「無限後退の可能性」を認めるのならば、アキレスが亀に追いつけないように、結局どの階層の出来事も、過去から現在に「なる」ことはなく、現在から未来に「なる」こともない。時制変化はどの出来事にも訪れないということになる。
あえて言うなら、より高階の出来事を想定し、後退を続ける主観的視点のみが時間の本性としてある、ということになる。客観的な「なる」がどこにも見出せないなら客観的な変化はない。変化の本質である「なる」は、入不二の論理でもやはり主観によって見出されたものだということになる。
しかし仮に時間が客観的なものでないのは事実だとしても、意識内容――クオリアは現に変化しているのだから、時間は主観的には存在するのではないか、と言うこともできる。入不二は時間が実在しないというマクタガートの「実在観」を批判して次のように述べている。
「実在」には、「全体」「完全なるもの」という意味も含まれている。〔……〕
主観的なものと客観的なもの両方を合わせてこそ、「完全なるもの」のはずだからである。つまり、「実在的(real)である」ことと「客観的である」こととは、イコールではない。あるいは、「主観的である」ということは、必ずしも「実在的(real)ではない」ことを意味しない。
この入不二のマクタガート批判は説得的である。マクタガートは主観によって捉えられる現象(クオリア)の変化は認めていた。現象の変化を認めながら時間の非実在を主張したのは、マクタガートの時間論の最大の瑕疵であるだろう。もっともマクタガートは明らかにカント哲学の影響を受けており、カントにおける物自体と現象との二分法が、マクタガートにおいて永久的な実在と変化する現象という形で引き継がれたことは間違いない。入不二が指摘したマクタガートの瑕疵はカント哲学にもあったものであり、またさらに遡るならば、永久的な実体と変化する(錯覚としての)現象を分けたエレア派にもあったと言えるものである。つまりこの問題は哲学において歴史的な課題の一つということになる。
カントがエレア派の哲学から多かれ少なかれ影響を受けていることは事実であろう。アンチノミーの議論は明らかにゼノンのパラドックスが原型である。しかしカントと
パルメニデスには一つ大きな違いがある。カントが明確に物自体と現象世界を分け、「超越論的観念論」かつ「経験的実在論」という
二元論の立場を取ったのに対し、パルメニデスはクセノファネスから継承したとみられる全一的な存在者を措定し、
一元論を徹底していたことである。
エレア派は変化は不可能であり、感覚が捉える現象の変化は錯覚のようなものであるという。しかし「錯覚」とは何か。前述したように錯覚論法によれば変化する現象の「経験」は確かに存在することになる。エレア派についての一次資料は僅かなのでここからは推測になるのだが、パルメニデスやゼノンもそんなことは承知の上で、現象の変化は錯覚だと主張していたのだと私は考える。
虚心坦懐に内省してみれば、実は現象は変化していないと考えることもできるのではないか。自分の経験をよく内省してみると、実はクオリアの「変化」を観測しているわけではないと気付くはずである。例えば交差点の信号が「青」→「黄」→「赤」と変化するのを見た場合、そこには「青」があってそれが消え、「黄」が生じてそれが消え、次に「赤」が生じたように思われるのだが、それは人が元の経験を反省して理性で分割・再合成したものである。ちなみにその「元の経験」をウィリアム・ジェイムズは「純粋経験」と呼んだ。
実際に人が経験しているのは、
「青のクオリア」→「黄のクオリア」→「赤のクオリア」
ではなく、
「青→黄→赤」のクオリア
である。「青→黄→赤」は一つのクオリアでなければならない。
クオリアは「生じない」し「消えない」と考えるしかない。クオリアが生まれたり消えたりするのは論理に反している。しかし連続的に生成し、消滅するクオリアたち全てを一個の存在者と見て、それが不生不滅だとするならば、論理に反しないのである。事実として、私は変化を感じているように思っているのだが、実際に経験しているのは「変化」そのものではなく、「変化しているような感じ」が「ある」のである。「AはAである」「BはBである」とAとBの存在を固定してしまえば、AがBに「なる」という変化は不可能である。しかしAとBが個別に存在することを否定して、「AがBになる」というものが「ある」すると考えるなら、同一律にも矛盾律にも反しないのである。
――以上が前章にて、変化の矛盾に対して私が出した解決案だった。しかしこの案は単純な理由で失敗したのだった。「青→黄→赤」は一つのクオリアだと考えようとしても、「赤」が登場した時点で「青」は完全に「ない」になっているからである。
この問題を解決するためのヒントを、私は先の入不二の議論から得た。入不二は次のように述べていた。
時間特有の変化は、変化の中から切り出される固定的なものに対しての、さらなる高階の変化として、原理的にはどこまでも高階化しうるのでなければならない。
つまりクオリアをB系列上に整然と並べるのは間違いだということである。これはベルクソンによる「時間の空間化」批判と通底する洞察であると思われる。
たとえば交差点の「青」が消えて「黄」が生じ、「黄」が消えて「赤」が生じるのを見た場合、以下のようにクオリアを時間軸上に定位させて理解するのが一般的である。
〔……〕[青]→[黄]→[赤]→〔……〕
_____________________________________→ 客観時間 →
上の「→」は消滅と生成を表している。〔……〕は、クオリアの数が可能的に無限であることを表している。私の発想は「→」を消去し、複数のクオリアが断続的に生起しているのでなく、実はひとつのクオリアだけが存在し、多様に見える複数のクオリアはその内部の性質として重層的にあるとみなすことである。つまりほんとうに存在しているのは、ひとつらなりのクオリアとしての、
〔……〕{([青]黄)赤}〔……〕
_____________________________________→ クオリアの性質 →
だろうということだ。上の[ ]内で最初の「青」を表現し、それを次の( )に含めて「黄」の内部性質として表現し、その黄も{ }に含めて「赤」の内部性質として表現している。この知覚モデルはベルクソンの用語で言う「イマージュ」に近い(ベルクソンはエレア派に対し変化を肯定するための存在論を構想したのだが)。
入不二が見た「時間の高階性」は、私にとっては「クオリアの高階性」なのである。クオリアは(時間という形式を内包して)どこまでも高階性を持つ。そして、その高階性によってどこまでも「変化」の本質である「なる」は否定される。入不二の言葉をもじって表現するならば「通常、困難や欠点として指摘されることの多い、この無限後退(の可能性)は、むしろクオリアの「高階性」を示唆していると見なすべきである。私と入不二は同じものを見ているにも関わらず、正反対の解釈をしているということである。
かくして時間と変化は客観的世界だけではなく、主観的世界からも実在性が排除されることになる。そして変化の実在を否定しながらも、クオリアの「変化している感じ」は説明可能である――。
いや、やはり問題は解消されていないように思える。「クオリアの高階性」という着眼は現象学的に意識経験の真理の一端を捉えた感はあるのだが、前章で行き詰った「変化」についての根本的な問題が放置されている。
私の論証は変化の説明として基本的に失敗している。次節にてその失敗を検証し、「変化」の概念が孕む問題を徹底的に純化して、問題の根幹部分を析出したい。
4 変化のパラドックス――四次元主義の破綻
変化とは「ある」ものが「ない」ものに「なる」ことであり、「ない」ものが「ある」ものに「なる」ことである。これは存在者が無から生成することであり、また存在者が無へ転化することである。それは論理的に不可能である。なぜならば「なる」とは「存在者が存在する」ということと、「存在者が非‐存在する」ということが同一だという矛盾だからである。――これが前章第1節における私の論証であった。
今一度、変化のパラドックスを確認しておこう。異なる時点に異なるものたちが並んでいるだけなら変化とは言わない。逆に異なる時点に同じものたちが並んでいるだけでも変化とは言わない。したがって変化とは同一でありつつ相違すること、相違しつつも同一であり続けるという矛盾したものである。
物の変化を実体と属性の関係として理解する素朴な方法はある。実体・主体を主語で、属性を述語で表現するのが変化についての素朴な人の理解方法である。これは必ずしも実在論を前提しなくても、観念論でも可能な方法である。つまり「自我」や「魂」を主体として、意識内容をその属性として説明するのである。しかし哲学的には、このような方法は私が考え得る限り最も拙いものである。主体や属性というのは世界の事実ではなく、人の認識の都合で便宜的に定められた規約的なものにすぎないからだ。仮に何らかの主体があって「痛み」は属性だったとしよう。では属性としての痛みはどこに消えて行くのか? 属性や述語などと口先だけで上手く言っても、ものごとが消えることの摩訶不思議は何も解消しない。
消えるものは「部分」であって、「全体」は消えないのだという考え方もあるだろう。しかしこれは
表象主義的な前提を置いている。つまり部分を認識する「私」という主体があって、それが別の部分に視点を移動しているのだとする素朴な知覚理論を前提しているわけである。部分を認識している「私」を想定しても、その「私」が別の部分を認識するならば、以前の部分は私の意識内部から消える。その「消える」ということをやはり説明できない。
以上の問題を解決するため、私はエレア派と同様に変化の実在を否定した。経験されるクオリアたちは多様である。私はそれらが「ひとつらなりの存在」だとして変化の非実在という前提と整合的に説明したつもりである。しかしここで問題となるのは、その「ひとつらなりの存在」の全体像をイメージすることができないということである。
幼い頃、私は寝室に落ちてきた蛇を見た。その蛇は夢か現実かに関わらず確かに「ある」と言えるものだった。そして変化の実在を否定し、蛇はクオリアの性質として「ある」というのなら、そのひとつらなりのクオリア全体は永久であるしかない。ここに理論と直感との調停し難い相克が生じる。直感に基づいて言うなら、私は幼い頃からずっとあの蛇を見続けてきたというわけではない。蛇は消えていたはずである。また変化を否定するならば、バークリーのように「知覚=存在」として、あの蛇を想起した時だけ蛇が存在するとも考えることができない。
交差点の信号が「青」→「黄」→「赤」と変化するのを見た場合、そこには「青」があってそれが消え、「黄」が生じてそれが消え、次に「赤」が生じたように、「なる」が連続するように思われる。しかし実際に「なる」という出来事があって、「青」が消滅し「黄」や「赤」が生成するなら、それは「存在者が存在する」ということと、「存在者が非‐存在する」ということが同一だという矛盾である。
ここで実在世界の変化を否定する「永久主義」を前提として、人の感じている変化の感覚を説明する立場を紹介し、検証してみたい。
物理学者のブライアン・グリーンは相対性理論の解釈によって時間の実在を否定し、全ての物事が四次元時空に永久的に存在しているとする立場から、人が経験している時間の流れの感覚を鮮やかに説明している。
壊れたDVDプレイヤーで『風と共に去りぬ』を見ているものと想像しよう。そのDVDプレイヤーは、前後にランダムにジャンプする。ある画像が一瞬スクリーンに現れたと思ったら、すぐまた別のシーンの画像が現れるのだ。コマが前後にジャンプするのを見て、ストーリーを理解するのは難しい。しかしスカーレットとレットにとっては何の問題もない。どのコマでも、二人はそのコマでいつもすることをするだけだ。〔……〕二人はそれぞれのコマで、前にそのコマで考えたのと同じことを考え、同じ記憶をもつのである。とくに重要なのは、二人がそうして考える内容と記憶とが、時間は常に未来に向かって均一に流れるという感覚を二人に与えていることだ。
時空の中のどの時刻も(つまり、どの時刻でスライスした時空の断面も)、一本のフィルムのなかの一コマのようなものである。光線に照らし出されようが、照らし出されまいが、そのコマが存在していることに変わりはない。スカーレットとレットと同じく、ある瞬間に存在しているあなたにとっては、その瞬間こそ「今」であり、「今」であり続ける。しかも、個々の断面のなかにいるあなたの思考と記憶は、時間はその瞬間に向かってよどみなく流れてきたと感じさせるのに十分なぐらい豊富かつ鮮明だ。「時間は流れる」というこの感覚をもつためには、それまでの各時間のコマが次々と照らし出されていく必要はないのである。
このグリーンの考え方は、哲学における四次元主義に該当する。四次元主義については第1章第5節で紹介したので、ここでは要約だけしておく。四次元主義は永久主義を前提とした理論であり、物体は時間的に「延続」しており、三次元空間に現れるのは「一時的内在的性質」に過ぎず、四次元時空の中にこそ完全に存在すると考える。
四次元主義は「ワーム説」と「段階説」に分けられる。四次元主義によれば物体や人は時間的に延続した時空ワームである。ワーム説ではその時空ワームが基礎的な存在者であると考える。段階説の「段階」とは「ワーム」から切り取られた諸々の段階を指しており、その個別の段階たちが基礎的な存在者であり、物体や人は諸段階の集合体と考える。
四次元主義は
人格の同一性を次のように説明する。ワーム説によれば昨日の「私」と今日の「私」は同一ワーム内にあるゆえに数的に同一の存在者であり、それぞれの時間で異なった性質を持つ。一方の段階説によれば昨日の「私」と今日の「私」は異なる段階であり、数的にも異なる存在者である。
グリーンは段階説の立場から一見、変化を上手く説明しているように思える。人が時間変化の本質だと思っている時間の流れの感覚も、永久的な存在者として整合的に説明されている。実際グリーンと同じように時間を説明をする物理学者は少なくない。
しかしグリーンの説明では、やはり変化の矛盾は解消できない。それは次のような理由による。
変化とは、或る物事が別の物事に「なる」ことである。これは当然である。第3章第7節でも論じたことであるが、全ての物事が永久的に存在しているとする宇宙モデル(ブロック宇宙)では、その内部の物事が別の物事に「なる」ことはあり得ない。
以下にブロック宇宙の概念を簡潔に表してみよう。[1] や [2] はグリーンが解説したDVDのコマに相当する
[1] ― [2] ― [3] ― [4] ― [5] ― ……
ブロック宇宙内部にいる者は変化を経験することができない。仮に[1]が交差点の信号の「青」であり、 [2] が「黄」ならば、青が黄に「なる」ということを人は感じることができない。もちろん人がブロック宇宙の外部にいて「青」から「赤」へと視点を移動するのならば「なる」を感じることはできるだろう。しかし人はブロック宇宙の内部にいるのだから鳥瞰的に観察することはできない。
もちろん「青が黄になる」というのも一つのクオリアとして存在しているのだと仮定することによって、「なる」の説明を試みる方法はある。しかしその方法は上手く行かない。なぜなら「青」の状態から「青が黄になる」という状態に「なる」ことを感じることができないからである。また「青が黄になる」という状態から「赤」に「なる」ことを感じることもできない。持続的かつ多様にクオリアが変化しているよう思えることを説明できないのである。
いや、「青」は今の「赤」とは、それぞれ永久的でありながら数的に異なる存在者だとするのが段階説の説明であった。数的に異なる存在者ならば、そもそも「青」を感じている「私」と、「青が黄になる」を感じている「私」とは別の存在者だとして変化の問題を解消できると考えることができるかもしれない。しかしこれは「ここ今主義」や「
独今論」と呼ばれる立場と根本的に差異がない。仮に今の「青」が「私」であり、それが段階説の説明するように孤立して時空の一点に存在しているのなら、「私」は永久的に「青」であり続けるしかない。それが消えるという変化がなければ「黄」にも「赤」にも「なる」ことはできない。ならば、なぜ私は「なる」を感じているのだろう?
この私が時空の一点に位置する存在者ならば、他の時空点は決して認識できない。四次元時空を鳥瞰する存在者でなければ、四次元時空全体を記述できない。段階説においては、他の諸々の段階とは「今・ここ・私」には経験不可能なものである。経験不可能であることがわかっている存在について語るのは事実上、別の宇宙について語っているのと同じことである。他の別の段階たちは、あくまで「今・ここ・私」から推測された仮説的な存在にすぎないということである。四次元主義は永久主義を前提しているために、世界における変化と因果の実在を否定するものである。したがって「今」の段階が因果的に引き起こされたと考えることができず、「今」の外部があると主張できる根拠がないのである。「ここ・今・私」である段階が孤立して存在することが論理的に可能なのであるから、別の宇宙に等しい別の段階たちを措定しなくても、「今・ここ・私」である段階は完結して存在可能なのである。
このようにして段階説を詳しく吟味していくと、限りなくここ今主義・独今論へと接近することになる。
段階説の困難を回避するために私が案出した戦略は、「青→黄→赤」を一つのクオリアだとみなし、それが永久的に存在するとするとみなすものである。「青」にせよ「熱い」にせよ「郷愁」にせよ、クオリアは全一的な性質がある。クオリアたちは他の何かに還元して説明することができない。これが全一性である。「青」のどこを探しても「郷愁」はなく、「郷愁」のどこを探しても「熱い」はない。「痛み」にせよ何にせよ、クオリアは「ない」ものと繋がることはできない。映画のフィルムの或る一コマと別の一コマがつながっているようなイメージで、或るクオリアと別のクオリアがつながっていると考える段階説は間違いである。人の経験するクオリアはフィルムのコマのような明確な境界を持たず、みなグラデーションのようになだらかにつながっている。そのなだらかにつながった一連のクオリア全体を、一つのクオリアとみなそうというわけである。これは四次元主義の一種であるワーム説に近い考え方である。この方法ならば「青が黄になる」、「黄が赤になる」という人が経験する変化の感じ、変化の本質である「なる」を、一つのクオリアの性質として説明できると考えたのである。
ところが、これも上手く行かないのだった。なぜならば「青が黄になる」に続けて、「黄が赤になる」というクオリアがあるとした場合、「赤」が「ある」になった状態では最初の「青」が完全に「ない」になっているからである。これは変化のパラドックス――無からの生成と無への転化を認めるものであり、すなわち「存在者が存在する」と「存在者が非‐存在する」が同一だとする完全な矛盾である。
つまり変化の理論としての四次元主義的な戦略の根底にある困難とは、異なる性質を同一の存在者の時間内性質だと考えようとしても、「なる」によってつないで「一つのもの」とみなせるのは、二つの性質のみだということである。「青が黄になる」というクオリアがあるなら矛盾ではない。「黄が赤になる」というクオリアがあるのも矛盾ではない。しかし「青が黄になり、そして黄が赤になる」というクオリアは矛盾であるゆえに存在できないのである。なぜなら「赤」が「ある」ものであるならば「青」は完全に「ない」からである。すると「青→黄→赤」を一つのクオリアと考えようとしても、「青=黄」かつ「黄=赤」、しかし「青≠赤」と推移関係において矛盾が生じるということである。
四次元主義が変化の説明に失敗していることは明らかである。
ところで変化を説明する理論としては、四次元主義と対立する立場として三次元主義がある。三次元主義では一つのものは時間的幅を持たず、相反する複数の性質を持つことはないと考える。たとえば「丸く、かつ四角いものはない」というように。そして三次元空間に存在するものが時間を通じて「存続」すると考える。三次元主義は一般的に時間の形而上学として、現在のものだけが存在するとする現在主義を前提としている。
しかし私の立場からすると、現在主義は無からの生成と、無への転化を認める理論であり、検討の余地が全くない矛盾した理論である。仮に私が「痛み」を感じたとする。次にその痛みが消えたとする。現在主義では、痛みは無から生じ、無へと消えたことになる。いやもちろん物理主義的な立場から物質的実体を措定し、物質は時間を通じて位置を変化しながら存続するのだと考えることはできるが、それでも痛みのクオリアにはついて何の説明もできない。せいぜい物質的な脳がクオリアを生じさせると主張するぐらいなものであり、これはチャーマーズが提起した意識のハード・プロブレムに解答できない。ちなみにチャーマーズはサールとの議論で、脳が意識を引き起こすというサールの主張を「万能の呪文」と呼んでいる。つまり現在主義は魔法を認めているようなものである。これが四次元主義ならば、変化の説明には失敗しているものの、永久主義を前提としているためにクオリアの生成と消滅という困難は回避できるのである。
現在主義は素朴実在論や素朴心理学と親和的であるかもしれない。また存在者の数を少なくするという「節約の原理」に適合するという考え方もあるだろう。しかし形而上学は人の素朴な直観と整合させる必要は全くなく、また節約の原理が適用できるのは、適用することによって矛盾が生じない場合に限られる。無からの生成と無への転化を認める現在主義は、完全に阻却されるしかないものである。
以上の検証によって「変化」の概念が孕む問題は純化され、その根底にある問題が明確化されたはずである。
まず現在主義は明白に矛盾しており論外である。一方、永久主義を前提した四次元主義では、存在者は時間的幅を持つとして変化を説明可能であるように思えたものの、異なる存在者・一時的内在的性質を同一のものだと考えようとしても、「なる」によってつなぐことができるのは二つの性質のみである。「青が黄になる」というクオリアがあるなら問題ではないし、「黄が赤になる」というクオリアがあるのも問題ではない。しかし「青が黄になり、黄が赤になる」というクオリアは存在できない。したがって「青=黄」かつ「黄=赤」、しかし「青≠赤」と矛盾が生じるのである。
変化は論理的に不可能である。ならば一体、人はなぜ変化を感じることができるのだろう?
もう一つの問題がある。マクタガートは時間をA系列とB系列に分け、B系列は時間にとって本質的ではなく、A系列こそが本質的だと考えた。しかしA系列は矛盾を含むゆえに時間は実在しないと主張し、主観的な変化の認識――C系列のみを認めた。つまりマクタガートによれば「変化」は実在するが「時間」は実在しないということである。しかし第3章第7説でも論じたことであるが、マクタガートの理論には深刻な不整合があるように思える。
仮に今現前しているクオリアをQ1としよう。次に現れるクオリアをQ2とする。その次に現れるクオリアをQ3とする……。このように意識の変化を認めるならば、それがB系列のように「順序」、あるいは「時間の矢」がなくても、今のクオリアは「現在」であり、その前のクオリアは「過去」であり、次に現れるクオリアは「未来」ということになってしまう。これはA系列と変わりがないように思える。
確かにC系列は通常の意味での「時間」ではないかも知れないが、それは或る種の時間であり、要するに「変化」が存在することは「時間」が存在することの十分条件であるように思えるのだ。
そして時間が実在するならば、カントのアンチノミーを回避することはできない。「現在」がC系列上の或るポジションから別のポジションにランダムにジャンプするとしよう。「現在」の「移動回数」は観察者がカウントするに関わらず決定していなければならない。ここから形而上学的無限という矛盾が帰結することになる。
第3章で論じたように、時間が実在するとした場合、以下のように二つの矛盾が生じるのだった。
変化に基づく矛盾: 変化とは「ある」と「ない」という相互排他的なものが同一であるとする矛盾である
無限に基づく矛盾: 時間が実在するなら、時間は無限に分割・延長可能であるが、無限の実在とは矛盾である
私は確かに変化を感じているように思える。しかし変化は矛盾であるので、私は第3章で無時間論を構想したが、それは上手く行かなかった。この章におけるこれまでの論考によっても、未だ私はこの二つの矛盾を解消できないでいる。
矛盾したものは存在することができない。時間が実在するのならば二つの矛盾がある。私は次のように確信せざるを得なくなった。変化の矛盾を解消するには、大きな犠牲を払う必要がある。それは常識を完全に放棄することである。
現に私が感じている変化の感覚を説明する方法が二つあり得ると考える。次節よりそれらを検討してみよう。まずは独今論である。
5 独今論
変化の感覚を説明する方法の一つは、「この現在」の時点だけが実在し、他の時点は実在しないとするものである。これは分析形而上学で「ここ今主義(here-now-ism)」と呼ばれる。また永井均の用語である「独今論」は、ここ今主義と類似の意味である。独我論が「私」の実在性のみを認め、他者はその「私」に現れるものだとみなすように、独今論は「現在」のみの実在性を認め、「過去」と「未来」は「現在」への現れだとみなす。独今論は時間における独我論である。
※ところで永井の場合は独今論を独在論とパラレルな問題とみなしているので意味が輻湊しているのだが、ここでは野矢茂樹(2002)に倣って単に時間における独我論という意味で用いることにする。
独今論が論理的に成り立ち得ることは、ラッセルの「世界五分前創造説」によって示唆されている。太古の化石も、十六世紀にダヴィンチによって描かれた『モナ・リザ』も、十年前の私の写真も、そのような姿形で、全て神によって五分前に創造されたと仮定しても、論理的な不整合があるわけではない。ならば五分前に創造されていようと三秒前に創造されていようと論理的には同じことである。
なお、五分前創造説が
独我論につながるか否かという問題がある。過去において「時間の長さ」を感じた人物の実在を認められないと考えるならば、現在の人物だけが実在的であるとする一種の独我論である。しかし時間の長さも無時間的なクオリアに還元できるという考え方もありうる。たとえば神が五分前に時間の長さをクオリアとして感じたソクラテスを誕生させ、そして消滅させたとすれば論理的に不整合がない。物理的・客観的な時間とは単なるパラメーターに過ぎず、人がそこに「長さ」を感じなければ「時間の長さ」ということに意味がないと考えることができるからだ。時間の長さのクオリアについてはアインシュタインの次の言葉が理解の補助となるだろう。「美女と一時間一緒にいると一分しか経っていないように思えるが、熱いストーブの上に一分座らせられたらどんな時間よりも長いはずだ。相対性とはそれである」――この言葉は主観的な時間の長さの感覚が、客観的な時間の長さ(わかりやすく表現すれば時計の針の回転数)と正比例していないことを巧みに表している。
そもそも客観的な時間の長さというものは存在していないのである。客観的にあるのはアリストテレスが時間の本性として分析したように「運動の数」のみなのである。ならば論理的には何億分の一秒の内に熱いストーブの上に十年間座ったような感覚を得ることが可能だということになり、五分前に創造された世界の内に一生分の時間の長さを感じたソクラテスの生と死が含まれていても何ら不思議はないということになる。
ところで、五分前創造説はそれだけでは独今論にはならない。なぜなら時間は未来に向かって流れて行くように感じられるからだ。したがって仮に世界が五分前に創造されていたとしても、今から十分後の世界は創造から十五分が経過したということになる。それに対し独今論は「この現在」のみが存在するという存在論であるからだ。したがって「未来」の到来を否定した上で、「未来のないこの現在」が永久的に存在し得ることを論証することが、独今論が可能的な時間論であることの論証になる。
果たして未来が到来しないなどということが思考可能だろうか?
素朴に「現に未来に向かって時間が進んでいる」と思いたくなる。しかしその思いもまた「現在」の経験に過ぎず、未来が到来したことの証明ではない。そしてその現在は五分前、あるいは三秒前に創造されていたとしても不整合はないのだった。いや、三秒前に創造されていたことを認めたとしても、「認めた時点からさらに時間は進んでいる」と思いたくなる。しかしそういう思いがあってもやはり同じことである。「認めた時点からさらに時間は進んでいる」という思いを含めて世界が三秒前に創造されていて、未来は到来していないと考えても不整合はない。また「私は二時間前のことを憶えているので現在だけが存在するなんてあり得ない」と思っても無駄である。その思いもまた「現在」の経験なのだから。結局、人は「時間が流れている」という印象を伴った「この現在」しか経験していないのが現実である。
したがって未来は存在論的に消去することが可能であり、「この現在」のみが永久的に存在するとする独今論は論理的に成り立つことを認めざるを得ない。
ここで次のような批判があるかもしれない。――この現在のみが存在するということは不自然である。ラッセルの五分前創造説は「神」の存在に依拠して成り立っているが、現実には神の存在など信じる根拠がない。ならば歴史は実在しなければならない。仮に映画を見ているのが「現在」ならば、その映画は過去に作られていなければならない。もちろん映画の撮影機材も作られていなければならないし、映画に最新のコンピューターグラフィックスが使用されているならば、コンピューターが発明される歴史的経緯も実在していなければならない、等々。
しかしそのような批判は「因果関係」の実在性に依拠にしたものである。因果関係とはカントが論じたように人の認識能力の一種に過ぎないのである。この問題は第三章の第7節で詳述した。「変化」は「無からの生成」を認めるものであり実在性を認めることができない。仮に変化の矛盾を棚上げしても、「時間」には「無限」という固有の矛盾があって実在性を認めることができない。また仮に時間の矛盾を棚上げしても「因果」には無限後退、循環論法、究極の問いという固有の問題があって、やはり実在性を認めることができない。因果は三重の論理で否定されるということである。
因果が実在しないならば、この現在のみが実在すると仮定しても論理的に何ら問題はない。独今論はやはり可能的な時間論である。
独今論の問題は大森荘蔵の「立ち現れ」一元論と関係してくる。大森によれば、過去は「想起」という形で立ち現れる。確実に存在していると言えるのは「今・ここ・私」の経験である「立ち現れ」のみである。
大森の過去論のポイントは、想起という経験は過去の経験の再生ではないということであり、「過去形の現在経験」として初めての経験であるということである。たとえば昨日転んで足に痛みを感じたことを想起する場合、「昨日は足が痛かった」という過去形の「立ち現れ」を初めて経験するということである。大雑把に言うと過去そのものが立ち現れるわけである。
ただし大森自身は「立ち現れ」以外は何も存在しないと主張していたわけではない。大森によれば人は原理的に「立ち現れ」以外のものを経験することはできないのだから、想起の原因としての過去があったと仮定しても、それはカントの「物自体」同様に不可知のものであり、「過去自体」として峻別されるべきものなのである。
つまり人は原理的に「知覚で知覚を知覚する」ことはできないということである。先ほどあった意識内容を反省してみても、反省という意識は反省の対象となる意識内容とは論理的に異なるのである。いくら過去の知覚を顧みても元の知覚には決して到達できないわけであり、これが「過去自体」が不可知であることの理由である。
これは大森にとって深刻な問題であった。私にとっても深刻な問題である。実在論者なら過去自体を懐疑する必要性が少ないだろう。実在論者は物質的実在を措定して、人が経験する物質的なものは過去の「痕跡」を残しているとみなすことができるからだ。たとえば五十歳の人が自分の人生を集積したアルバムを見るならば、アルバムには自分の五十年分の記録があるとみなせるわけである。しかし大森のように実在論を峻拒した現象主義的な立場では、アルバムを見てもそのアルバムに対応した実在を認められない。アルバムは「存在=知覚」としたバークリーの言う意味での存在として突如立ち現れてくるのである。その知覚的な存在を立ち現す「原因」を求めたくても、「知覚で知覚を知覚する」ことの不可能性があるのだから、現象主義の立場では「過去自体」は全くアクセス不可能なのである。
大森と違ってバークリーもヒュームも「観念についての観念」という存在を措定することの困難にあまり頓着した形跡が見られない。表象主義を前提していたロックと異なり、現象主義では或る観念と別の観念は論理的に異なるのだから、「昨日足が痛かった」という観念があっても、それは昨日の「足の痛み」という観念を表象しているとみなせず、昨日の足の痛みの存在を全く保証しない。それどころか「昨日足が痛かった」という観念から昨日の「足の痛み」の観念を推測すること自体が存在論的には不純なのである。実在論を峻拒するならば、過去自体は語ること自体が無意味なのである。
このような現象主義の困難を理由に、大半の哲学者は表象主義を前提とした実在論の立場を選択している。しかし実在論を選択すると必然的に「物と心」の二元論に陥ることになる。ひとたび物と心を異なる存在と認めたなら双方の軋轢は調停しがたいことを大森は直観しており、したがって「立ち現れ」一元論を徹底することになる。なお、私が大森同様に現象主義を選択するのは二元論を拒否するためだけではない。第2章でも論じたように物質的実在というものがあるとしたら、それは無限の部分を持つという矛盾した存在だからである。そして第3章でも論じたように、物質的実在を措定してもクオリアが変化するという摩訶不思議を解消するのに何の役にも立たないこと、また因果関係は実在しないゆえに、物質的実在を措定しても知覚の因果的説明にならないことなども根拠としてある。
反実在論が直観に反することは確かである。しかし直観は公理ではない。形而上学において何よりも重要なのは論理と整合させることである。形而上学においては、直観はそれ自体が問われべきる対象なのである。
因果の実在が論理的に否定されるならば、過去を含め「立ち現れ」外部の存在を一切否定すること、つまり独今論は可能となる。憶測であるが、大森は終生立ち現れ外部など実は全く存在していないのではないか、という悪魔の囁きに似た懐疑を抱き続けていたように思う。立ち現れ以外のものを全て否定してしまえば、そこで完全に論理的に整合的な時間論が完成することを大森は承知していたはずだからである。もちろんこれは非常識の極限であり、大森は誘惑に抗い続けて終ぞ悪魔の時間論を選択することはなかった。
悪魔の時間論は常識から甚だしく逸脱する。しかし形而上学において重要なのは論理と整合させることであった。悪魔の囁く時間論に可能性が認められるならば、真摯に耳を傾けて熟考しなければならないだろう。
そして私は悪魔の囁く時間論を吟味した結果、次のように結論する。
独今論は論理的に可能な時間論として認められるべきである。この世界は「この現在」のみしか存在していない可能性は有力である。「有力」としたのは、単に独今論が成り立つかもしれないという理由のみではない。既述したように時間が実在するとしたら、変化に基づく矛盾と、無限に基づく矛盾という、二つの矛盾がある。しかし独今論ならその二つの矛盾を回避できるのである。独今論の世界では「この現在」しか存在しないのだから、変化がなく時間もそれ以上流れない。したがって独今論は矛盾がない完全な時間論なのである。なおかつ「この現在のクオリア」だけが「実体」として存在すると仮定するなら、現在と過去、物と心の二元論の難問がないことになり、理想的な存在論でもある。
それでも独今論など認めたくはない。その理由など説明する必要はないだろう。
改めて独今論の内実を仔細に吟味してみよう。この現在だけが存在し、他の過去や未来は現在への現れとみなすならば、当然「この現在」の「幅」というものが問題になる。これはアウグスティヌスの現在中心主義からも読み取れる問題である。過去と未来は現在に張り付いた皮一枚のような存在だとして、その皮一枚にどれだけの要素が圧縮されているかということである。ラッセルの五分前世界創造説を参考にし、かつ「時間の長さ」の感覚をクオリアの性質に還元できると仮定すれば、皮一枚の過去を持つこの現在には可能的に無限の要素が圧縮できるはずである。
過去の経験とは、時間の経過によって徐々に「遠く」なっていくわけではない。ふとしたことをきっかけに遠い昔のことを昨日のことにように思い出す――そんな経験をしたことは誰でもあるはずだ。過去の経験とはB系列上に行列のように並んでいるわけではない。過去の経験は「過去」という一つのものの内部に圧縮されて存在している。ならばこの現在の経験には自分の人生経験全体が圧縮されているのかもしれない。――この考えはベルクソンが、過去というものが「記憶」という形で保持されつつ現在に浸透していると考えたことと同型だろう。
しかしそう考えてクオリアの多様性を認めようとしても、存在論的には問題がある。「時間の長さ」の感覚を物理的時間と切り離して、純粋にクオリアの性質に還元しても、「三つ以上の性質」があるならば件の変化の矛盾が顕在化してしまう。交差点の信号が「青」から「黄」になり、次に「赤」になるとしよう。この場合「青が黄になる」というクオリアがあるなら問題ではないし、「黄が赤になる」というクオリアがあるのも問題ではない。しかし「青が黄になり、黄が赤になる」というクオリアは存在できないのだった。赤が「ある」と言えるものならば青は完全に「ない」ものでなければならないからである。「なる」によってつなぐことができるのは「二つの性質」のみであり、したがって「青=黄」かつ「黄=赤」、しかし「青≠赤」と矛盾が生じるのである。これが四次元主義による変化の説明の躓きであった。
つまり「この現在」に三秒であれ五分であれ、どれだけの時間的幅を認めたとしても、「この現在」が有することができる性質とは、「或るクオリアが別のクオリアになる」という、二つの性質だけだということである。これが独今論を前提とした場合に帰結する人の意識経験の真理であるはずだ。
ただし独今論の世界では「二つの性質」だけが存在し得るとしても、その性質は「青」と「黄」のような明晰性があるものではないだろう。私が交差点で「青が黄になる」を見た場合、実際に経験しているのは単純な「青」と「黄」という二つの性質ではなく、「(青を含む)数十年分の人生経験の印象」と「黄」かもしれない。つまり私はこれまでの人生で多くの経験をしてきたように思うのだが、「知覚で知覚を知覚する」ことはできないのだから、実際には「多くの経験をしてきた」という不明瞭な印象だけがあるのかもしれない。つまり交差点で「青が黄になる」を見た場合、「(青を含む)不明瞭なクオリア」が、現前する明晰なクオリアである「黄」と「なる」でつながると考えるわけである。
以上のように考えてみると、独今論も実は単純な時間論ではないということになる。「二つの性質」だけが存在するとしても、現前するクオリアにつながる「過去自体」としてのクオリアの捉えがたさは変わらない。
いずれにせよ独今論の重要な前提は、現在経験されている「このクオリア」の明晰性を肯定する、というものである。この点が次に検証する無世界論と決定的に異なることになる。
6 無世界論
変化の感覚を説明するもう一つの方法は、変化の感覚自体を錯覚として否定するものである。これはエレア派のパルメニデスによって主張され、後に「無世界論」とも呼ばれるようになった。
ところで
スピノザのような
汎神論もまた無世界論と呼ばれることがあるが、これは「神の他にはいかなる実体も存在しない」という意味で、世界が実体であることを否定するものである。対してパルメニデスの場合は「感覚によって認識される世界は存在しない」という意味である。両者共に世界には唯一の実体しか存在しないと考えた点では同じであるが、無世界論といっても内容は大きく異なっている。
以下に引用するパルメニデスの断片7は、人の認識をロゴス(論理)と感覚に分け、ロゴスの優位を説くものであると一般的に解釈されている。
なぜならあらぬものがあるというこのことが馴らされることはけっしてないだろうから。
むしろあなたは、探求のこの道からあなたの考えを遠ざけなさい。
また、多くの経験から生まれた習慣が、あなたを強制してこの道を行かせ、
目当てをもたない目と雑音に満ちた耳と舌とを働かせることがあってはならない。
そうでなく、ロゴスによって判定しなさい、
わたしから語られた、多くの異論を引き起こす吟味批判を。
パルメニデスによれば、真理はロゴスに基づいて思考することによって到達できる。そしてロゴスに基づいて思考するならば「ある」と「ない」は絶対的に相互排他的なものであり、「ある」が「ない」に、あるいは「ない」が「ある」に「なる」ことはありえない。「なる」という変化は世界の事実ではありえない。世界が変化していると思うのは感覚に基づいて思考したための臆見である。――パルメニデスが「合理主義」の祖と呼ばれるゆえんである。
アリストテレスは『生成消滅論』第一巻八章においてパルメニデスの哲学を以下のように評している。
理論的には、これらの見解は論理の当然の帰結であるとは考えられるけれども、しかし事実の上で見るなら、このような考え方をするのは、狂気の沙汰に近いものだと思われる。
山川偉也は上のアリストテレスの文について次のように述べている。
アリストテレスのこうした感想は、おそらく、彼以外のひとびとのものでもあったろう。エレア派の厳密論理は万人を承服させずにはおかなかった。しかし、その論理は、かならずしも、ひとびとを「無世界論」者にしたわけではない。論理によって事実を裁断するか、それとも事実のほうに論理を従わせるかの選択を迫られたとき、ひとびとは迷わず後者の道を選んだのである。ものが多に分かれて存在すること、少なくとも感覚的には、ものの生成消滅、運動変化はまぎれもない事実であることを、人々はエレア派の論理の圧力に抗して、擁護しなければならなかったのである。
しかし私は、感覚よりも論理を重んじる。上のアリストテレスの「事実」という表現は意味的に曖昧で、感覚による判断は疑わしいとするエレア派の哲学に対して、感覚による判断は正しいとする論点先取の可能性がある。要するに感覚上の事実は、必ずしも「真理」の根拠にはならないということである。
次の二つの事実を比較してみよう。
事実1: 2たす3は5である
事実2: 私の足には痛みがある
事実2がこの私の経験であるならば、どちらの事実も私にとって真理であるように思える。しかし両者の明証性は同じレベルではない。事実1は疑うことが不可能な真理であるのに対し、事実2はたとえ自分の経験であっても疑うことが可能である。デカルトの欺く神を想起するまでもない。「知覚で知覚を知覚する」ことはできないのだから、「私の足には痛みがある」と信じていても、その信念が正しいか否か心的内容を反省した場合、その「反省経験」は元の心的内容とは別の心的内容だということになり、「過去自体」には決して到達できないからである。足の痛みが一時的なものでなく、持続的なものであっても同じことである。反省の対象となる経験そのものは「痛み自体」と呼んでも良い。
「知覚で知覚を知覚する」ことはできないという事実からは二つの問題が生じる。一つは前節で大森荘蔵の過去論について論じたように、現在の知覚と過去の知覚は論理的に異なるのだから、過去自体は全く不可能だということ。もう一つは現在の知覚も知覚できないということである。知覚(クオリア)とは端的に与えられたものであり、それ以上遡行不可能なものである。それ自体が存在であり、かつ認識でもある。
哲学の伝統的な問題に「人は存在を正確に認識しているか」というものがあるが、「認識」自体も存在の一種(一部)なのだから、「人は認識という存在を正確に認識しているか」という問題もあり得るはずなのである。もちろん単なる反省を超えた「認識のメタ認識」など人にはできない。つまり形而上学には権利上「メタ認識論」というべきものがなければならないのだが、人は原理的にメタ認識論にコミットできないのである。
要するに「存在すること」と「認識すること」は論理的に別のことである。「認識が存在すること」は懐疑不可能だとしても、「〈認識という存在〉を認識していること」は無謬性を主張できる根拠がなく、懐疑の対象にすることが可能なのである。これが「2たす3は5である」という事実1との決定的な相違である。
次のように語ることもできる。私に痛みのクオリアがあった場合、私は「痛み」だと思っている「これ」を完全に理解していない可能性を認めるのである。あるいは、今私の前にパソコンのモニターがあるが、私がパソコンのモニターだと思っている「これ」を、私は完全に理解していないかもしれないのである。
私はジェイムズのように言語化以前の「純粋経験」を想定しようとしているのではない。たとえば痛みがあった場合、「痛み」という言葉で表現されたものは、元の純粋経験を完全には表していないかもしれない。しかし「痛み」と呼ぶに値する何らかの「悪しき経験」が生じていることはジェイムズも否定してはいない。私は彼ら「純粋経験」までも懐疑の俎上に載せようというのである。
それにしても、痛みを感じている最中に「私はほんとうに痛みを感じているのか?」と懐疑することは無意味どころか馬鹿馬鹿しいように思える。しかし「これは痛みでなく実は甘さなのだ」と考えてはいけない理由とは何だろう? 自分で自分の感覚を「確かめる」ことは原理的にできない。しかし確かめることができないということを根拠に、痛みを感じている場合に「私が痛みを感じていることは真理である」と言うことは一つの飛躍がある。それは「真理」でなく「現実」と言うべきものであるからだ。
※第2節で言及した入不二の「現実性」の哲学についての補足になるが、ここに視点依存的な「現実」概念と、視点に依存しない「真実」概念との差異がある。
人は痛みが現れた後で痛みの存在を認知するのではない。痛みは「痛い」という判断と共に現れる。人はその判断が真であるか否かを検証する術がないのだが、「検証できないから真である」とは限らない。これこそ感覚に基づく判断が論理に基づく判断より信頼性で劣る理由である。
論理法則は疑うことは不可能である。そして論理的に矛盾したものは存在できない。感覚で捉えられる世界が矛盾しており、かつ感覚が疑い得るものならば、エレア派が主張した通り感覚による判断が間違っている可能性――感覚により判断された(時間空間という形式を持つ)世界が実在しない可能性を認めるべきなのである。
地獄の門をくぐる者が一切の希望を捨てなければならないように、形而上学の門をくぐる者は一切の常識を捨てなければならない。それがどれほど大切なものであっても、形而上学の領野において認められるものはただ理に適うもののみなのである。素朴実在論的世界像とは社会的存在としての自分に刷り込まれた「物語」であり、私はいわば物語の主人公として存在しているのだが、世界の真実を探求するためにはその物語の世界から抜け出さなければならない。
エレア派の哲学は、感覚世界を論理的に分析すれば至る必然的な結論であるよう私には思われる。しかし「狂気の沙汰」と言ったアリストテレスの心情は理解できる。問題の所在は感覚上の事実と論理上の事実が整合しないことで、この世界のあり方自体が狂気であるように思われる。ただ次のように考えて世界の「狂気」を和らげることができるかもしれない。――時間論において永久主義の立場をとる哲学者や物理学者が失念しがちなのは「空間」の問題である。相対性理論は時間と空間が不可分に結びついていることを証明した。つまり時間と空間は単独では実在でない。ブロック宇宙とは「動的な時間」でも「静的な空間」でもない。ヒュー・プライスはブロック宇宙が普通の意味での存在物ではないことを強調している。にも関わらず第4節で紹介したグリーンは人の感覚を「空間」という固定的なイメージを用い、映画のフィルムのように横一列で並べて表現していた。これはミンコフスキー時空によって「事象」を説明する相対性理論の解説方法に倣ったものだろうが、クオリアを説明する方法としては根本において間違っているのである。したがって「青」「黄」「赤」のクオリアを見た場合、実はそれらのクオリアは、私に記憶された通りの明晰なあり方で存在していない可能性が認められるべきなのである。
前章で私は変化の実在を否定するため、ひとつらなりの全一的クオリアを考案した。「青」出現し、それが消えて「黄」が現れ、それが消えて「赤」が現れるのならば論理に反しているのだが、「青→黄→赤」を一つのクオリアだとみなし、それが永久的に存在するとみなすならば、論理に反していないと考えた。しかしこのような四次元主義的方法では上手く行かないのだった。したがって、個別のクオリアの明晰性を否定するエレア派の方法論を真面目に検討するべきだろう。ブロック宇宙が「動的な時間」でも「静的な空間」でもないものならば、「青」「赤」といった個別のクオリアは人の信念の通りに明晰に存在していない可能性があるということである。
私が幼い頃に寝室で見た蛇は確かに「ある」し、永久に「あり続ける」と言えるのだが、そのあり方は、記憶された通りの素朴なイメージでのあり方をしていないのだと考えることが可能なのである。蛇が「消えた」というのは或る種の事実であるとしても、それは限定的な意味での事実であり、素朴なイメージでの「消え方」をしていないのだと考えることが可能なのである。仮にあの蛇が「消えた」というのなら、蛇が消えた次に何かが「生じた」と考えるしかない。しかしそれでは「順序」が生じてしまい、それは或る種の時間の実在を認めることになる。時間の実在は「変化」と「無限」という二つの矛盾を帰結させるのだった。したがって、蛇が消えたことを認めてはならない。いかなるクオリアも消えること、また生まれることを認めない。これが無世界論である。
交差点の信号が「赤」になっても、「青」は消えていないと考えるのである。論理に従うならば、「青」は消えていないと考えるしかない。――しかしこれだけでは無世界論にはならない。現前するクオリアまでも否定しなければならない。もし「私は青を見ている」という信念の通りに「青」が存在するなら、「赤」は存在することができないからだ。
無世界論の重要な前提は、現在経験されている「このクオリア」の明晰性を否定する、というものである。この点が前節にて検証した独今論と決定的に異なることになる。
しかし、以上の考えは我ながら正気の沙汰とは思えない。エレア派の論理の正しさを認めながらもそれを退けたアリストテレスの心境には共感せざるを得ない。独今論が悪魔の囁く時間論ならば、無世界論は妖精の囁く時間論とでも言うべきだろう。妖精(Fairy)は次のように言う。「あなたは今痛みを感じていると信じていても、実はあなたが信じているような痛みはないのよ」――そんな馬鹿なことがあるはずはないと思いたくなる。私が転んで痛みを感じ、「痛い!」と叫んだときに存在しているものは何なのだ? それが痛みでないなんて、猫が消えて猫の笑顔だけが残ったと言うに等しい、全くナンセンスなお伽の国(Fairy land)のお伽噺(Fairy tale)である。
しかし「知覚で知覚を知覚する」ことは不可能なのだった。ならば「それが痛みでないはずはない」と言ったとしても「物自体」や「過去自体」と同様に、「痛み自体」と言うべきものを捉えていない可能性を認めるしかないように思える。ナンセンスであることは必ずしも論理的不可能性につながらない。
また、無世界論にはベルクソンの「持続」の哲学を援用できるかもしれない。ベルクソンの言う「記憶」とは通常の意味と異なっており、過去の経験の全てを蓄積したものである。その記憶が知覚に浸透し、人の経験を成立させ続ける運動が「純粋持続」である。
メロディーは単なる個別の音の集合ではない。それぞれの音が相互に浸透し合って有機的な一つの全体――数的に同一な存在者を形成する。メロディーを構成する一つの音は、それのみでは単純な音の知覚に過ぎない。しかし前後に連続する他の音と相互浸透し合うことによって、聴く者に固有の質感や印象を感じさせる。ベルクソンにとって純粋な持続としての意識と時間は、空間的なものと異なり分割できないもの、性質の要素を個別の部分に還元できないものとして、その内に差異を含みながらも通時的に同一のものなのである。
たとえばラストシーンが同じでも、ラストに至るまでのストーリーが全く異なる映画を作ることができる。それら映画を見たならば、同じラストシーンを見てもまるで異なる印象を得ることになる。つまり現在私が空間的に明晰に認識しているつもりのものにも「他の何か」が浸透しているのである。私がバラを見ている場合、バラ以外のものはないように思える。しかし「他の何か」が浸透していると考えることが可能なのである。
つまり一切の知覚には、「それ」のみではなく、「他の何か」が浸透していると考えることが可能なのである。そして現前するクオリア以外のものが浸透している可能性さえ証明できれば、ベルクソン的には十分なのである。このベルクソンの哲学から「時間」を抜いてしまえば、無世界論の妥当性が示されるかもしれない。時間こそが存在の本性だと考えたベルクソンにとっては大迷惑な牽強付会であるだろうが。
しかし私は時間を全否定するのではない。エレア派の言う通り「一」なる実体は時間の内には存在しないだろう。しかし時間は実体の性質として存在していると考えることができる。個別的なクオリアは或る意味で時間的な存在なのだ。
「明晰とは何か?」と井上忠に問われた大森荘蔵は「空間として見ること」と答えたという。それは事実だと思う。逆に考えると、存在の本質が空間でなく時間ならば、世界に明晰なものは何もないということになるだろう。つまり明晰化とは知性による意識内容の分断・空間化・固定化なのだが、存在の本質は時間的で固定化できるものは何もないとしたらどうだろう。たとえば「Aが真であるのは、Bであるとき、かつそのときに限る」というような真理条件の記述は、空間化された「とき」を使用しているので間違いであるかもしれない。
空間的なものとは固定的で明晰なものであり、時間的なものとは動的で明晰ではないものである。人の意識・クオリアが時間を本性とするならば、それは動的で捉えがたいものであり、明晰なものではないということである。
人は完全に静止しているものを見ることはできない。或るものが静止しているように見えても、それは動的な意識の内容物として動的に存在している。
念のため今一度付言するが、私は自分が転んで「痛い!」と叫んだときに、実は「痛み」がないのだと言っているのではない。「痛み」のクオリアというものが時間軸上に定位できず、空間的な明晰性を有して存在しているのではないと言っているのである。時間変化から無理に切り取って固定した「痛み」の記憶は、「痛み」の本質的なあり方を保存していない可能性を示唆しているのである。
ここで再び入不二の文を引用する。
時間変化に晒されることから、逸れる固定的なものなどない。
〔……〕
時間的変化とは、固定的で不変のものとして取り出される一者に対してこそ(対してさえ)、さらに生じるはずの変化であり、その変化を逸れるものなどなかった。すなわち、時間的変化の特異性とは、その「高階性」や「汎浸透性」にあった。
では「固定的で不変の一者」とは何だったのか。詰まるところ、一者とは、特定の「もの」や「出来事」ではなくて、端的な現在(絶対的な現在)のことであった。すなわち同一不変の「もの」や「出来事」に定位しておいて、「それ(と指示できる何か)」が過ぎ去るのではなく、端的な現在の現実性(これ)こそが、過ぎ去るのでなければならない。
これが入不二の最も優れた洞察であり、重大な問題提起だと私は受け取っている。「時間の高階性」と言う場合の「時間」とは、通常の物理的・線形的な「時間」の概念とは全く異なっている。入不二が言う時間の高階性とは「A=A」というような素朴な意味での同一律さえ脅かすものである。なぜなら「時間変化の中に定位できる固定的なものなど何もない」からである。たとえば「2014年 5月 1日に痛みを感じたのは事実である」と言っても、それは経験の真実を表していない。その本性が時間で固定できないはずの「痛み」というものを、無理に切り取って空間的に固定したものだからである(ベルクソンの時間の空間化批判が想起される)。時間内部において定位できる固定的なものが何もないなら、同一律が成り立たない。同一律は「A=A」という形式であるように、変化の中で何かを固定できることを前提としているからだ。
「端的な現在の現実性」さえもが常に過ぎ去るものであり、現在が本質的に「動的」なものならば、「A=A」というように「現在=現在」と、現在を「静的」に捉え理解することは間違いだということである。入不二の洞察は、入不二本人の意図に逆らって、「端的な現在の現実性」さえも否定しまうものだと読み替えることができる。「端的な現在の現実性(これ)」と言っても、言った瞬間に過去という非現実になっている。現在を静的・空間的に捉えることができないなら「現在の痛み」も、その痛みの「現実性」も捉えることができないということである。人は自分の現在の経験さえも「理解」しているとは言えないだろうと私は懐疑する。頬をつねり続けて持続的に痛みを感じ、「痛みはあるし持続しているのだ」と言うことはできるだろう。しかしその確実に思える痛みの現実も必ず過ぎ去って夢や幻に等しい過去となる。時間・クオリアの高階性によって。
※ただし私の言う「現実性」が特定の内包を持つものであるのに対し、入不二の「現実性」は無内包であったことが想起されるべきである。
誤解のないよう付言するが、私は同一律や矛盾律のような論理学の基本法則を否定するのではない。同一律や矛盾律は疑うことができないア・プリオリな真理である。ただそのア・プリオリな真理も、知性によって把握し、「言語」というア・ポステリオリな形式で表現する場合には、ア・ポステリオリな真理に堕落してしまうということである。「高階性」を本性とする「時間」は知性で把握できない。把握したものは「時間」ではなく「時間の痕跡」なのである。それはア・ポステリオリな真理である。ちなみにこのア・ポステリオリな真理を巡って、かつて差異だとか差延だとかいうポストモダン思想が流行していたことは記憶に新しい。それらは真理を探究するものでなく、真理の影を探究するような学であり、私の関心の対象ではない。
人は「知覚で知覚を知覚する」ことはできない。ならば「私は今痛みを感じている」という信念があったとしても、その信念を正当化する術はない。人は経験自体を決して把握できないのかもしれない。
エレア派の主張したように、感覚で捉えられるこの世界は実在していない可能性を認めるしかない。仮に感覚で捉えられた通りに実在しているとすれば、「変化」と「無限」という二つの矛盾があるからである。無世界論では、エレア派の主張したように、論理によって把握されるもののみを認めるのである。それは不変の世界である。そして実体は「一」である。仮に実体が「多」であるとするならば、ゼノンが指摘した通り、多の間には無限の「中間」があるしかないからである。
その「一」として不変の実体が、「痛み自体」や「赤自体」など原初的なものたちの融合体であり、「実体」である。その不可知な、一なる実体にはベルクソンが言うような質的多様性があるだろう。――人に知ることができるのはそこまでかもしれない。
これが無世界論である。
7 真実の行方
私は変化の矛盾を解消するために、独今論と無世界論という二つの存在論を検討してきた。どちらの世界も論理的に可能であるように思えるが、どちらが正しいかを確かめることは不可能かもしれない。人は世界の外部に立って世界のあり方を確かめることはできないからだ。
実体(宇宙)は自分の全体を映す鏡を持つことができない。実体が自らを描こうとするのは、鏡を持たない人が自画像を描こうとする行為に似ている。実体は自らを理解することができないのかもしれない。
しかし独今論と無世界論は、いずれも素朴な世界観から甚だしく逸脱した世界観である。素朴実在論と直観は放棄しがたい。独今論は悪魔の囁く時間論であり、無世界論は妖精の囁く時間論である。良識ある人ならどちらも受け入れないだろう。
改めて時間の実在論を再検討すべきでだろうか。これは天使の囁く時間論と言える。天使は次のように言う。――時間は実在しているのです。この世界はビッグバンという「神の一撃」によって始まったとしたら、ビッグバン以前には時間がない。だから時間の無限後退を考える必要はありません。あるいは永劫回帰のような循環型の世界を想定してもよいでしょう。循環型の世界では、世界内部にいる人は世界の「循環回数」を問うことに意味がありません。循環回数などは神のみぞ知るのです。したがって過去は存在したし、未来は存在するだろうし、現在もあなたのイメージする通り明晰に存在しているのです。時間の実在論は正しいのです。
天使の囁く時間論は人の直観を救済するものであるゆえに、多くの論者が受容している。ブロック宇宙を措定して世界における変化の実在を否定する永久主義者でさえ、人が経験する変化の感覚は肯定していたのだから、天使の囁く時間論を選択していると言えるだろう。これまで時間の非実在を主張してきた私とて、魅惑的な天使の囁きを拒絶し切るのは難しい。
ここで私が考え得る三つの時間論を並べてみよう。
天使の時間論: 時間は素朴なイメージで実在する(時間の実在論)
悪魔の時間論: この現在だけが実在する(独今論)
妖精の時間論: 私の経験は私が信じるような明晰なものではない(無世界論)
もちろん時間論は存在論と表裏の関係にあるので、上の三つはそれぞれ、天使の存在論、悪魔の存在論、妖精の存在論と言い換えてもよいだろう。
三つの時間論を論理的に考えるならば、明白な矛盾があるのが天使の時間論である。時間が実在するなら第2章と第3章で論じたように、形而上学的無限の帰結を回避できない。時間の実在論を前提とするならば、人の時間認識に関わらず時間は実在するのだから、ビッグバン以前に時間はなかったと考えても、ビッグバンが始まった時点で、「ビッグバン以前」が登場してしまう。そして循環宇宙の循環回数を人が「数える」に関わらず宇宙は循環しているのだから、循環回数は「決定」していなければならない。いずれも時間の長さの無限を認めることになる。そして「無限の実在」とは矛盾概念である。
※なお私は現象主義を前提に論じているのだが、仮に実在論を前提とするならば、ゼノンによる無限分割のパラドックスも生じることになる。これは第2章で論じたが、実在論では解決困難な難問である。
もちろん、ブロック宇宙こそが実体だとみなす永久主義を前提とするならば、時間の長さの無限を回避できるだろう。しかしこの立場でも意識経験における時間変化の感覚を認めるならば、意識の時間について同様の矛盾が生じることになる。
そしてもう一つ、天使の時間論では「変化」の矛盾が解消できない。変化とは無からの生成を認めることであり、それは「存在者が存在する」ことと「存在者が非‐存在する」ことが同一であるとする矛盾である。永久主義を前提として変化を説明する四次元主義の失敗は第4節で見た通りである。つまり現在主義を前提するにせよ、永久主義を前提するにせよ、天使の時間論は変化のパラドックスを棚上げしたままなのである。
天使の時間論は「変化」と「無限」という二つの矛盾を孕んでいる。人は矛盾した言葉を話したり矛盾した文を書いたりすることがあるが、世界に矛盾したものごとは存在できない。形而上学で重要なのは直観と整合させることでなく、論理と整合させることである。矛盾を孕む天使の時間論は却下するしかない。
全能の神でさえできないことが二つある。一つは矛盾したことである。もう一つは神自らが「しない」と決めたことである。その二つは同じことかもしれないが。
ここで昔読んだ印象深い漫画を紹介したい。残念ながら作品名は失念してしまったのだが、うろ憶えの内容は次のようなものである。――ある場所に幽霊が出るという噂があって、興味を抱いた登場人物たちが冒険に行く。その内一人は幽霊なんぞ絶対信じないという科学信仰の合理主義者である。そして夜、まさに幽霊が登場人物たちの前に出てくる。登場人物たちはパニックに陥る。しかしただ一人、合理主義者だけは幽霊を目にしても平然としている。「なぜ平気なのか?」と問われた合理主義者は答える「俺は自分の目より科学を信じる」。このセリフで他の人物たちはずっこける。――確かにこのシーンはギャグになっているのだが、しかし私は、合理主義者の態度の方が正しいのではないかと思った。全ての現象には合理的な理由がある、そう考えるならば、幽霊のようなものを目撃しても、それは錯覚かトリックであると考えるべきである。仮にそれが現在の科学では説明できない現象であり、本物の幽霊と認めるしかない状況に陥ったとしても、その幽霊の存在をも合理的に説明できる未知の科学法則がある、と考えるのが合理主義的態度なのだと思う。
百聞は一見にしかずという。しかし私の信念は逆であり、百見は一理にしかずである。件の漫画の作者は、合理主義を徹底するとギャグになるというメッセージを込めていたのかもしれない。実際に合理主義を徹底して変化の実在を否定したエレア派に対して、アリストテレスは上に引用したようにその合理性を認めながらも「狂気の沙汰」と言ったのだった。
しかし人類は、科学の発展によって幾度もそれまでの常識を転覆されてきたのではなかったか。太陽は地球を中心に回ると思っていたが実は地球が太陽を中心に回っていたのであった。空間は不動だと思っていたが実は伸びたり縮んだりするものであった。一つのものが離れた二箇所に同時にあることはできないと思っていたが素粒子にはそれができた。人の常識は当てにならない。ならば宇宙の真理が人の常識などという矮小な枠組みに入ると思うべきではない。
時間の実在を否定することは、とてつもなく非常識な主張である。私があえて非常識な主張をするのは相応にして十分な理由がある。時間には「変化」と「無限」という二つの矛盾があるからである。二つの矛盾を認めることは、非常識というより人知には不可能なのである。
天使の時間論を却下した結果、悪魔の時間論と妖精の時間論が残った。どちらかが正しいということになるかもしれないし、他に人知の及ばない時間論があり得るのかもしれない。しかし人知の及ばない時間論について人間が語ることには意味がないだろう。ここでは独今論と無世界論のどちらが存在論として無謬性が高いかを検討してみたい。
結論から言うと私には無世界論の方が正しいように思える。私が無世界論を選択する理由には一つの論理的な理由と、一つの直観的理由がある。
・無限論再び
論理的な理由とは「無限」の問題である。独今論は「時間」の問題だけを見るならば論理的に整合的な存在論である。しかし「空間」の問題はどうだろう。独今論の重要な前提は、現在経験されているクオリアの明晰性を肯定するということであった。これが全てのクオリアの明晰性を否定する無世界論との決定的な相違である。するとテーブルや道路のように空間という形式を持つクオリアが現前している場合、深刻な問題が現れるように思える。
ゼノンの「二分割」や「アキレスと亀」の私の解消法は、現象主義の立場から時間・空間の実在を否定し、現象(観念・クオリア)の実在のみを認めるならば、人に経験される現象は有限個なので無限分割を回避できる、というものだった。ところが空間的なものが現象だとしても、経験される通りに明晰に存在するとしたら、それは無限の部分を持つように思われるのである。
一メートルの幅があるテーブルの視覚像があるとしよう。その視覚像が私の信じる通りに明晰なものであるとするならば、私が計測する、しないに関わらず、テーブルの半分の五十センチの地点があると考えるしかない。そして一旦半分の地点を認めてしまえば、更にその半分、またその半分の地点の存在を認めるしかない。地点の数は無限であるしかない。つまりゼノンのパラドックスを完全に解消できないということである。
もちろん独今論の世界では「現在」だけが存在するのだから、「数える」ということに意味がないとも考えることはできる。しかし一メートルのテーブルの知覚像が「実在」するのならば、私が数える行為に関わらず知覚像の五十センチの地点もまた「実在」すると考えるしかないのではないか。つまりバークリーのように「存在=知覚」として、実在の場所を意識外部から意識内部へ移し変えたとしても、またカントのように空間が直観の形式だと考えても、ゼノンのパラドックスは悪霊のように取り憑いて振り払うことができないように思えるのである。もちろんこの問題は、俊足のアキレスが鈍足の亀に追いつけない、というような甚だしく反直観的な問題とは異なるかもしれない。しかし「無限の部分を持つもの」というのは明らかに矛盾した存在である。
次のような解消法を考えることができるかもしれない。――「一メートルのテーブル」というのは既に「大きさ」が表現されている。大きさとは知性で判断されるものではないか。たとえば象は蟻より遥かに大きいが、象の視覚像と蟻の視覚像は同じ大きさ――というより視覚像の「大きさ」ということには意味がない。視覚像は意識への単なる現れであり、視覚対象の大きさは知性による比較や計測によって判断されるものだ。つまり視覚像そのものは計測されなければ大きさがない全一的な「印象」である。大きさがないものの部分や地点は、「時間」を使用して知性によって分割しない限り存在しない。独今論ならばその分割を避けられるから、部分や地点は存在しない。
しかし、やはり次のようにも考えることができる。――四つの足があるテーブルの視覚像が明晰に存在するのならば、テーブルは「足」という部分を四つ持たなければならない。そしてひとたび部分の存在を認めてしまえば、その「部分の部分」を認めることになり、結局は無限分割を認めることになる。空間的なものが明晰に存在するということは、人が知性によってそれを個別の部分に分割する、しないに関わらず、部分となるものが存在していなければならないからである。
やはり独今論の世界では、空間の無限分割が回避できない可能性が強いように思われる。
ただし、独今論の立場からは次のような反論が考えられる。現在の明晰なクオリアが「音」や「痛み」のように非空間的なものなら無限分割は問題にならない、と。確かに現前するクオリアが非空間的なものであり、空間的なクオリアは「皮一枚の過去」の内に存在していて、それは不明瞭なクオリアだから無限分割を回避できるという考え方はできる。
しかし、この私は今現にパソコンのモニターという明晰な空間的クオリアを経験している。空間の無限分割を回避しようとするならば、現在に空間的なクオリアが現れていても、その明晰性を否定しなければならない。しかし、それでは無世界論と変わりがない。
あるいは、現在経験される空間的クオリアも「やがて消える」とし、次に非空間的クオリア、たとえば「痛み」が現れるとするなら、存在論的には「パソコンのモニターが消え、痛みが現れる」という二つの性質のみを持つクオリアが永久的にあるとみなせるので矛盾はない、と考えることができるかもしれない。しかしその考えは既に「今だけが存在する」という前提と矛盾しているように思われる。――この辺りに独今論のパラドキシカルな構造があると同時に、哲学的に興味深い問題が派生する。実際に、いくらパソコンのモニターを両手でしっかり掴んで「これは存在するのだ」と思っても、やがては消えていくだろう。また私が自分の人生を振り返り、あれやこれやの経験をしたのだから「過去」は実在したのだと確信しても、その確信ごと消えていく。
そもそも「消える」とは、一体どういうことだろう?
・ものごとが消えるとはどういうことか?
私が無世界論を選択する直観的な理由とは、「ものごとが消える」ということである。
私は「変化」とは何かについて考え続けてきたのだが、ここで変化について別の視点から考察してみたい。
哲学の歴史において、ものごとが消えるという事態を真剣に考究した哲学者は衝撃的なほどに少ない。一体、ものごとが消えるとはどういうことだろう? これはこれまで論じてきたように「無からは何も生じない」という論理によって、変化の実在を否定しようとする目的で問題提起しているのではない。ものごとが消えることは、現象学的な事実であることを一旦認めた上で、その事実が意味することは何かを問題にしているのである。
今、窓外には煌びやかな街の夜景が見えている。目を閉じればその夜景は消える。夜景の視覚像が「消える」ということはまるで魔法のようである。実在論を前提にしても夜景の視覚像が消えることの説明はできない。これは第三章で論じた。しかし仮に実在論が正しくても、夜景はいつかは消えるのである。世界に消えないものはない。「始まりがあるものには終わりがある」という格言通り、全ての物事は「時間」によってやがて消されていく。
現象主義を前提しようと、実在論を前提しようと、ものごとが消えるということは実は摩訶不思議なことではないか?
夢には不思議な点が二つある。一つは奇想天外な体験をすることである。もう一つは奇想天外な体験をしているにも関わらず、夢の私が不思議だと思わないことである。実はこの現実世界でも数々の奇想天外な体験をしているにも関わらず、私は不思議だと思えないのかも知れない。「全てのものごとは消えていく」――これは当然のことだと一般人は空気を吸うように受け入れているが、実は魔法のように奇想天外なことではないか。
「時間とは何か?」アウグスティヌスがこう問うて以来、数多の哲学者が数多の解答を試みてきた。その内いずれが正しいかはさて置き、「時間とは全てを消し去る究極の魔法である」と解答するのも、あながち的外れではないように思える。
消えるものは実体ではない。実体は消えないものである。――そんな素朴な思いがある。この思いはどこから来るのだろう。
「実体」という概念には「実体でないものが存在する」という含意がある。しかし実体でないのに「存在する」というのは語義矛盾であろう。錯覚論法で証明されたように、錯覚経験があったとしても、錯覚という意識経験は存在する。つまり実体の概念には素朴な心と物の二元論が前提としてあって、物が消えるのは不思議だが、心の内容が消えるのは不思議ではないとする億見が含まれている。これは実在論を前提とした
知覚因果説が正しいとする論点先取にすぎない。バークリーの以下の批判を想起すべきである。これは哲学者ならば一日一回読んで熟考するに値する、哲学史上最大級の問題提起である。
反対論者は、私の説が事物を瞬間ごとに消滅させては創造する不合理に陥ると攻撃する。しかしこの不合理をもって私は既存の哲学原理を深く攻撃できる。私が瞼を閉じれば周囲のあらゆる事物が無に帰着することは不合理と考えられる。しかしこれは哲学者が次のような場合に共通に承認するところではないか。
光と色彩は知覚される以上に少しでも長く存在しない感覚にほかならない〔……〕
もちろんバークリーの標的は実在論者である。しかしバークリーの観念論もまた、ものごとが消えるという摩訶不思議を何も解消していない。バークリーは心の外部にある物質的実在を想定しても、ものごとが消えることの不思議さは解消されないので、物質的実在を措定することの無意味さを主張したに留まっている。しかし実在の場所を心の外部から心の内部へと移し変えても、ものごとが消えることの摩訶不思議は何も変わらない。だから私は変化は矛盾だとしてその実在性を否定してきたのだが、ここでは変化のパラドックスを棚上げし、ものごとが消えることを現象学的な事実として、その意味するものを考えなければならない。
やはり現象主義の立場を取っても、消えるものは実体ではないだろう。実体が不滅でなければならないことは、これまで論じてきたように変化を否定する論理法則を適用できる。どのような種類のものであれ、「存在する存在者」は「非‐存在する存在者」に「なる」ことはできない。
確かに人の意識内においては、「ある」ものは「ない」ものになり、「ない」ものが「ある」ものになることによって、認識は成立する。しかし意識における「ない」とは、「ある」ものの一種ということになる。ベルクソンが「無」とは事物を否定する機能を持った一個の観念として「存在」しているとみなした所以である。――これらは認識論上の問題である。
存在論的には、矛盾したものは存在できない。「痛みがあったが、それが消えた」と言う場合、その言葉は矛盾していないが、その言葉の指示対象である「痛み」がほんとうに「存在する」ものであるなら、「非‐存在する」に「なる」ことはできない。「痛み」は実体ではない――しかしそう結論して終わるものではない。実体ではない先ほどの痛みとは何であるかが問題である。実体と属性、基体と性質、全体と部分、主語と述語という構図では変化を説明できないことは第三章で論じた通りである。では痛みが現れ、それが消えるとはどういうことだろう?
私は次のように結論せざるを得ない。消えるものは元から存在しないものである。消えたものは元から存在しなかったのである。
そんなわけはない。痛みを感じている最中に「この痛みは実はないのだ」と考えることはナンセンスだ、と思いたくなる。しかし、痛みは「ある」と思った次には「ない」になっている。時間論では「今」の捉えがたさが問題にされる。「今」は「ある」と言った瞬間「ない」になっている。痛みが五時間持続していようと同じことである。「痛みが五時間持続した」という信念ごと消えていく。「今」は無限小の瞬間であることはできない。一定の幅がなければならない。そしてどんな時間的幅があろうと、それが「時間的」である限りは消えるのである。一秒で消えるものも一億年で消えるものも本質的に変わりがない。
時間とは全てを消し去るものだ。魔法のようなものである。
実在論的には、「存在する」とは空間を占めるものである。人の五感はその空間を占めるものの表象であるとみなす。たとえば車の視覚像があるならば、その視覚的クオリアは空間を占める車の表象とみなし、車のエンジン音が聞こえたなら、その聴覚的クオリアは空間を占める車のエンジンから発せられた音波を表象したものとみなすのである。
しかし時間は、その空間を否定するものであり、したがって通常の意味での「存在」を否定するものなのだ。
しかし消えるものは元から存在しないものであると言っても、確かに痛みに該当する「何か」が消えていることは事実であるように思える。では先ほどの「痛み」とは何だったのだろう?
「知覚で知覚を知覚する」ことは原理的にできないのだった。これが人知の限界である。行き詰まりに呆然する私に、妖精がこう囁く。「痛みなんてなかったのよ」
私は妖精の囁きに強く誘惑されている。ただ「痛み」が全くなかったとは思わない。私がが痛みを感じているとき、実際は私が信じているような痛みは存在していない可能性を認めるべきなのである。「痛み」にせよ「赤」にせよ「愛」にせよ、人は自分の「ほんとうの経験」を捉えられていない可能性が強い。転んで足を捻挫して「痛い!」と叫んだとき、その「痛い!」の指示対象となるものは確かにあるのだけれど、それは自分が信じているようなあり方で存在しているのではないということである。無世界論の重要な前提は、現在経験されている「このクオリア」の明晰性を否定する、というものである。何であるにせよ現前するクオリアの明晰性を肯定してしまえば、それが消えて別のクオリアに「なる」ことは不可能であり、また他のクオリアと「相互浸透」していると考えることも不可能だからである。そして「痛み」にせよ「赤」にせよ、それらクオリアが人の「信念」の通りにあること――明晰性を否定するならば、それらは「変化」という矛盾と「時間(無限)」という矛盾を回避できるのである。そしてそれらは、消滅を蒙りながらも、何らかの意味において、その実在性を維持できる可能性が示されるのである。
ただその場合は「消滅」という表現は正しくないだろう。交差点の信号が「青」から「黄」へ、そして「赤」になるのを見た場合、「赤」が登場した時点において「青が消滅した」と考えるべきではなく、「〈青が消滅した〉という信念がある」と考えるしかないのである。そしてその「信念」もまた私が思っているような明晰なイメージで存在しているのではないということである。ほんとうに「ある」ものの内部の要素として、消滅したように見える青も痛みも、それらに対する信念も、ベルクソンの言う相互浸透のような形で、「ある」と考えるのである。これが無世界論によるクオリアの変化の説明となる。
痛みとは、私が思っているような明晰な存在者ではないことを認めるしかない。既述したが、空間的なものとは固定的で明晰なものであり、時間的なものとは動的で明晰ではないものである。人の意識内容が時間を本性とするならば、それは動的で捉えがたいものであり、明晰なものではないということになる。消えるものは明晰ではない。そして意識経験は「時間的」であるゆえに全て消えることが約束されている。ならば意識経験で明晰なものは何もないということになる。
今私が「痛み」を感じているとしても、「私は痛みを感じている」という「信念」を抜き取れば、残るものは「物自体」と類比的な「痛み自体」でしかないものだろう。もっとも、「痛み」や「経験」という言葉の意味とは元よりその信念のことなのだから、「私は痛みを感じている」という言葉と信念に間違いはないだろう。私は形而上学的に無世界論を選択したのだが、素朴実在論まで否定するわけではないのである。つまり「痛み」は私が信じているような明晰な存在者ではないものの、「痛みのような何か」が存在することは事実なのである。因果関係の実在性が否定されても「因果関係に見えるもの」が実在するように。私に痛みがあるとき、「私は痛みを感じている」という言葉と信念に間違いはないのである。
しかし形而上学的には、その言葉も信念もまた流れ消え去るものだ。言語もまた静的・空間的なイメージで存在するのではないと考えるしかない。つまり私が「痛い」と言っても「青」と言っても、その言葉もまた私が思っているような明晰な存在ではないということである。「今日痛みをほんとうに経験した」と日記帳に書いて金庫に保管しても無駄である。それらもまた消え去るものだ。私は実在論を否定して続けてきた。日記帳や金庫に対応した物質的実在というものが存在すれば、それは無限の部分を持つゆえに矛盾した存在である。したがって日記帳も金庫もバークリーの言う意味での知覚的存在(クオリア)である。――ところがそのクオリアは全て消え去ることが約束されている。
私は長らくクオリアこそが人の最も原初的な経験だと信じてきたのだが、ここにおいてその信念を放棄せざるを得なくなった。「青」にせよ「蛇」にせよ「痛み」にせよ、それらクオリアには「信念」や「判断」が含意されているのである。ジェイムズのように知性による判断以前の純粋経験を想定しようとしても同じことである。「意識は常に何ものかについての意識である」のだから、意識経験はみな何らかの判断を含んでいるのである。無世界論はその意識経験を根幹から懐疑する。
私は大森荘蔵の現象主義的な哲学を自らの哲学の出発点とした。その大森荘蔵はバークリーから強い影響を受けており、事実上のバークリー学徒であった。私は大森やバークリーと近い立場にあったのだが、ここで立場を変えざるを得なくなった。「存在するとは知覚されることである」――長らく信じてきたこのバークリーの標語を、私は放棄して次のように主張するしかない。
知覚は実在ではない
それぞれの知覚(クオリア)は私が信じている通りに明晰に存在しているならば、繰り返し論じた通り「変化」と「時間」の矛盾が帰結する。したがって感覚による判断は疑わしいとするエレア派の説を受け入れて、知覚の実在性を否定するしかない。
私は錯覚論法を根拠にして、夢も幻も現実の経験も「存在する」ということで貴賎が無いと考えた。今やその考えを修正するしかない。夢も幻も現実の経験も、私がイメージしているようには存在しない。全ての経験は夢幻に等しく、夢幻もまた夢幻の儚いイメージそのままに夢幻なのである。
現象主義や観念論とは心の外部にある世界の実在性を否定するもので、反実在論の最も極端な形態であると考えられている。しかし私はその現象主義や観念論に対しても、無世界論の立場から心の内部にある個別のクオリアたちの実在性を否定するのである。これは反実在論の極限であるだろう。
反実在論の方法を徹底的に遂行するならば無世界論に至るしかない。これが私の結論である。
こんな夢を見たことがある。雑誌をパラパラとめくっていると、ふと美しい風景写真が目に留まった。もう一度見ようと探したのだが、いくら雑誌をめくっても見つからない。本当に風景写真を見たのかわからなくなった。全てが消えてゆく世界では証拠もまた消えていって事実を確かめる術がない。シャボン玉のように儚くはじけるものも、太陽のように天文学的時間をかけて燃え尽きるものも、消えゆくものであるということは同じなのだ。この世界もまた消えていく。
消えるものは存在しないものである。消えたものは存在しなかったものである。私が過去に経験した様々なものごとは、私が信じているような明晰なあり方をしていなかったと考える他はない。
しかし以上の結論は、論理的整合性を保つために無理やり経験の現実を歪曲してしまったという感がある。そもそも個別的なクオリアの明晰性を否定するならば、それらクオリアが実は全く存在しなかったと考えることと変わりがなく、独今論と紙一重ではないだろうか? そんな強引な時間論を妄想するぐらいならば、いっそ独今論を選択してしまえ、という悪魔の囁きも聞こえる。
無世界論ではこの時空点も他の時空点も私がイメージしているような明晰なあり方では存在しない。しかしそれら時空点の存在を何らかの意味において認める。では具体的にどういう意味において時空点たちは存在しているのだろう? それこそが問題であり、明確な解が見出せなくても、何らかの示唆を見出せなければ、無世界論は独今論と本質的な差異がなく、独今論が主張する「現在のクオリアの明晰性」を否定しているだけだということになる。
この問題について私は、時間と空間が直観の形式だと考えたカント哲学に僅かな示唆を見出すことができるように感じている。
ここで第二章で用いた図4を再掲する。
図4では、アキレスの運動を赤い線で、亀の運動を青い線で表している。両者の運動は時間と空間という「形式」で表現できるということが重要である。アキレスがどの時点で、かつどの地点で亀に追いつくかは、両者の形式によって計算できる。
二つの線のどちらでもよいから、任意の点を線上の一つに置いて、自分がその点にいるものと考えよう。二つの線は時間と空間という形式を持つのだから、五分前に亀がどの地点にいたか、五分後にアキレスがどの地点にいるかは、両者の形式によってわかる。
無世界論では「アキレスが亀に追いつく」という「出来事」が何らかの意味において存在することは認める。もちろん、アキレスも亀も競争を始める前から生きていたのであり、競争が終わってからも生き続けるとみなす。つまり「アキレスの生涯」や「亀の生涯」も一つの出来事として時間と空間という形式を持ちながら、何らかの意味において存在しているとみなすことができる。それならば「全体」である世界そのものも一つの出来事として存在しているとみなすことができる。無世界論の世界像は妖精の世界のように不明瞭であるが、その世界は時間と空間という形式を性質として持っているのである。図4の二つの線上に任意の点を一つ置けば、そこからアキレスが亀に追いつく時点が存在論的に示唆されるように、他の時空点が、なんらかの意味において存在することが、時間と空間という形式の存在によって示唆されるのである。
もちろん時間も空間も私がイメージしているような明晰なイメージで存在しているのではない。物自体(実体)は時間と空間の内部にはなく、時間と空間は現象の形式だとするのがカント哲学であった。カント哲学は構成主義的で二元論的である。それを一元論的に解釈し直せば、現象そのものも物自体に含まれることになり、時間と空間は物自体の内部性質となる。したがって人の認識能力では物自体は全く不可知であり、人の言語では物自体を語ることができないことになる。ここで重要なのは、物自体は「語り得ない」のではなく、「語る」という行為自体が物自体から逸脱することなのである。
しかし、以上の論法には重大な欠点があるように思える。人が現実に認識しているのは「今・ここ」だけである。それが独今論が論理的に成り立つ理由でもある。しかし上の論法では全ての時空点を一挙に見渡す特権的な観察者が想定され、その観察者によって全ての時空点の存在が確認されたことを前提に語っているように思われるのである。したがって独今論の立場から上の論法に反論するのは容易いだろう。――人が経験しているのは「今・ここ」だけである。確かに時間と空間という「形式」は他の時空点の存在を示唆している。だがその示唆は必ずしも他の時空点の存在を保証しない。その示唆自体が「現在のクオリア」の性質として存在し、他には何もないと考えても何ら論理的不整合はない、と。
第5節でも論じた通り、現象主義の立場では「過去自体」は全くアクセス不可能なのであった。「昨日足が痛かった」という観念があっても、それは昨日の「足の痛み」という観念を表象しているとみなせず、昨日の足の痛みの存在を全く保証しない。バークリーもヒュームも「観念についての観念」という存在を措定することに無頓着だった。逆に観念連合というアイデアが孕む困難に敏感だったのが大森荘蔵で、大森は元の観念の不可知性を「過去自体」と言い表して、「立ち現れ」外部のものについては終ぞ語ることをしなかった。
しかし私は語らなければならない。
確かに、独今論の主張は説得的である。しかしその主張もまた「消える」ものだ。消えるものは消えることによって明晰性を失う。もちろん独今論は「消える」というクオリアのみが永久的に存在するのだと主張する。私が次々と新たな経験をしているつもりであっても、ラッセルの五分前世界創造説が示唆したように、私の過去の経験全ては二秒か三秒に圧縮されて不明瞭な形になり、その不明瞭なクオリアが現在の明晰なクオリアに「なる」というものこそが、永久的に「ある」ものだと考えれば不都合がない。
しかし私は次々と経験されるクオリアたちが「消える」ように思える。「この今」だけが存在するという時間論など信じられない。これは信仰の問題だけではない。独今論は空間の明晰性を認めるために、空間の部分が無限に実在することを認める可能性が濃厚なのであった。やはり論理的整合性は無世界論の方が高いだろう。
私の経験する現象たちは時間と空間という形式を持って存在する。その形式の延長線上に存在することが想定されるものたちは、独今論と異なり無世界論では、何らかの意味において存在しているとみなすことができる。そして「全体」である世界そのものも一つの出来事として存在しているとみなすことができる。
もちろん「消える」というならば「順序」があるのではないか、という素朴な批判は想定される。順序があるなら時間の実在を認めなければならないが、それは矛盾である。しか無世界論では個別の現象の明晰性を否定する。つまりB系列の線上に個別の現象が順序正しく並んでいるような図式は物自体を正確に描写したものではない。事態はむしろ逆であって、順序やB系列そのものが物自体の一つの性質として存在していると考えた方が妥当である。
なお次のような指摘も想定される。「消える」ことでクオリアたちの明晰性も順序も否定されるのなら、そのことによって「変化」と「時間」の矛盾は解消され、それらの実在を認められるのではないか、と。しかし変化と時間の実在は認められない。上に述べたようにB系列は或る意味で実在するのである。たとえるならB系列は実在の影である。影ならば矛盾してもよいと考えることはできない。たとえ影であっても矛盾した影など思考不可能であり、認められない。B系列上に並んだ出来事・クオリアは無限にあることはできない。有限でなければならない。私は第二章で「無限」を論考し次のように結論した。「無限に思える有限なものが永久にある」――この世界観は変わっていない。
更に次のような批判も想定されるだろう。「消える」ということが現象の認識の明晰性を否定するならば、人は一体何を認識しているのか、と。つまり私は今確かに何かを経験しているはずなのだが、「これ(経験?)」って何なのだ? という問題である。無世界論では何かを認識していることは肯定するが、その認識の明晰性を否定し、そして「知覚で知覚を知覚する」こと、認識のメタ認識ができないことを根拠にこの問題に人知の限界があると主張する。――このような説明は論理的整合性を保つための辻褄合わせをしているだけだ、と感じるのは当然であろう。現に、私は今パソコンのモニターを見ているように思われる。モニターは確かに「ある」ように思われる。無世界論は、モニターは私が思っているようには存在しないと言う。ならば、「これ」って何なのだろう? この問いを封じるのは不可能であるように思える。
しかし「一」なる実体を想定する無世界論の立場からすると、「これ」は「語りえない」というよりはむしろ、「語ってはならない」問題なのである。言語とは存在を分断・空間化して明晰化するものだからである。語ることは存在に対する裏切りであると言ってもよい。――とは言っても「これ」に対する疑問が消えるわけはないのだが。
ここで人が一体何を認識しているのかについて、随分先走るという感はあるが、解答を模索してみたい。私はかつてメルロ=ポンティの次の語り方に示唆を受けたことがある。
私が一定の時間と空間の中にいるのか、それとも私はどこにもいないのか、のいずれかだと述べる代わりに、むしろ私がこの瞬間この場所にいながらも、絶えず私は至るところにいるのだ、とどうして述べてはいけないのだろうか」
上のメルロ=ポンティの言葉の意味はともかく、語り方には惹かれるものがあった。「○○と考えてはいけない理由がない」――この論法は論理的可能性を示すものであると同時に、論理的不可能性を回避するものである。実在は、このような消極的語り方でしか示唆できないものなのかもしれない。
人は「全て」を一挙に認識していると考えてはいけない理由があるだろうか? 「今このクオリアしか認識していない」という反論があっても、今このクオリアはその明晰性とともに消えていくのだった。つまり個別のクオリアの明晰性が「消える」ということで否定され、他のクオリアとの境界も否定されるならば、「全てを一挙に認識するとはこういうことだ」と考えてはいけない理由がないように思えるのである。
たとえば一枚の絵を見たときの「印象」は静的でも動的でもない。「全体」を一挙に見るということも同じだと考えたいのである。認識されているように思われる個別の物事の明晰さを否定するのならば、真に認識しているものとは「全体」であると考えたいのである。「この痛み」は存在すると思っても消えていく。全体を認識するとは個別の物事が「消える」ということなのだ、と。
無世界論においては、性質が変化するのではない。変化が性質なのである。たとえば扇風機の羽根がゆっくり回転しているのを見れば、人はそれに変化を感じるだろう。羽根が位置を変えているのを見るのだから。しかし高速に回転しているのを見た場合、羽根の位置変化を見ることはできない。羽根の回転そのものが「一つの印象」として感じられるはずだ。これが「変化が性質である」ということの意味である。世界全体も「一つの印象」であるとみなすのが無世界論である。そしてその「一つの印象」を認識するとは、「こういうこと」、「これ」だと考えてはいけない理由がないように思えるのである。
前掲した図4の二つの線上に任意の点を一つ置けば、そこからアキレスが亀に追いつく時点が存在論的に示唆され、他の時空点もまた存在することが、時間と空間という形式によって示唆される。しかしその論法は全ての時空点を一挙に見渡す特権的な観察者が想定され、その観察者によって全ての時空点の存在が確認されたことを前提に語っているように思われる。人が現実に認識しているのは「今・ここ」だけなのである。――しかし「今・ここ」の明晰性が「消える」ということで否定されるならば、人が全ての時空点を一挙に見渡す特権的な観察者であると考えてはいけない理由がないように思えるのである(
無主体論的に表現すれば「全ての時空点を一挙に見渡すような〈印象〉のみが存在する」ということになる)。
ベルクソンによるメロディーの比喩を想起しよう。メロディーとは単なる個別の音の集合ではなく、それぞれの音が相互に浸透し合って有機的な一つの全体を形成するのだった。そのような部分に還元できない性質のものは無時間的な印象とでも言うしかないものだ。「痛み」や「赤」や「美しい」も同様に無時間的な印象としてあるように思える。無時間的なものだけが他の要素と「一つ」としてつながることができるのである。
ベルクソンによる「時間の空間化」批判はB系列だけでなくA系列にも当てはまる。トランプのカードを重ねて置く。上に「2」のカードがあれば他のカードは見えない。しかし「2」は「現在」と類比的でない。時間にはカードのような空間的明晰さがないからだ。B系列もA系列も物質の明確な「境界」も実在の性質なのであり、実在の方が明確な「境界」に区切られて、B系列やA系列として並べられるあり方をしているわけではないのだ。――このような論法で世界全体も「一つの印象」であり、その「一つの印象」を認識するとは、「こういうこと」だと考えてはいけない理由がないように思えるのである。
それにしても以上の論述は、途方もない形而上学的妄想であり、我ながら辻褄合わせの上に、更に強引な辻褄合わせを重ねているという印象がある。しかし矛盾したものは存在できないのだから、説明内容に明らかな矛盾がない限り、反直観的だという理由のみで退けるべきではないだろう。
上の説明で無世界論はかろうじて独今論との差別化に成功したように思える。他の存在論とも比較して、無世界論は甚だしく反直観的であるものの、無矛盾な存在論であることは認められて然るべきだろう。
私はアリストテレスが「狂気の沙汰」と言ったエレア派の哲学――無世界論を支持する。
私は狂っているのかもしれない。しかし形而上学では狂っていることなど大した問題ではない。形而上学には善も悪もなく、流行も廃りもなく、正気も狂気もない。単に正しいか間違ってるか不明かのいずれかでしかない。
かの名探偵シャーロック・ホームズはこう語っている。
完全にありえないことを除外したならば、残ったことは、いかにありそうにないことだとしても、それが事実に間違いないということだ
私には直観に基づいたアリストテレスの言葉より、論理に基づいたホームズの言葉の方が正しいように思える。
「矛盾」の語源である「どんな盾も突き通す矛で、どんな矛も防ぐ盾を突いたらどうなるのか?」という中国の故事を、遠い昔学校で習ったとき、生徒の一人が「宇宙が消滅する」と言ったことを私は憶えている。矛盾したものは論理的に存在できないのだから、もし世界に矛盾しているように見えるものが存在するのなら、その世界は実は存在していない(人の認識する世界像が間違っている)。つまり「宇宙が消滅する」と言った生徒は或る意味正しかったのである。
この世界には時間・空間・変化があるように思われるが、それらは矛盾している。だからこの世界は、実は存在していない。私が信じ、認識している通りの明晰なあり方では。――これが合理的な結論である。
ならば、改めて考えざるを得ない。何もかもが曖昧で明晰なものがない無世界論の世界で、ほんとうに、確実に「ある」と言えるものは何だろう?
・ほんとうに「ある」ものは何だろう?
無世界論という世界観では、私が過去に経験してきた多くのものごとや、現在経験しているものごとが、私が信じている通りに存在すること――明晰性が否定される。しかしそれら経験が全く「ない」とするわけではない。この妖精の囁く不明瞭な世界で、ほんとうに「ある」と言える、存在の確実性が保障されるものは何だろう?
論理法則や数学的真理はあるはずだ。同一律、矛盾律、排中律など論理学の基本法則は消えることがない。そもそも「論理法則が消える」と言うことは意味を成さない。これは無時間的な真理であるからだ。
では論理法則によって、ほんとうに「ある」と言えるものがどこまで探求できるのだろう。論理法則は適用できる対象がなければ意味をなさない。
一つ確実な存在があった。デカルトの「私」である。転んで足に「痛み」を感じたとしよう。その「痛み」も妖精の囁くように、私が信じているようなイメージでは存在しないかもしれない。しかしデカルトが方法的懐疑で論じたように、「懐疑する何か」の存在は懐疑することができない。これは無時間的な真理である。その懐疑する何かを「私」と定義するならば、「私」は存在する。
私の経験は全て消えていく。消えていくものは実体ではない。この世界もまた消えていく。全てが消えていく世界で残ったものは、「私」と論理法則のみである。この二種のものは悪魔や妖精が何と弄言しようと否定できない確実なものである。
では「私」と論理法則ほど確実ではないけれど、蓋然的に「ある」と言えるものは何だろう?
クオリアは人が信じているような明晰な存在者ではないにしても、何らかの意味において「ある」ことは確かである。そもそもデカルトの「私」も論理法則もクオリアから抽象されたものである。では、クオリアはどのような意味において「ある」のだろう? 私は転んで足を捻挫し、数日間に渡って激しい痛みに苦しみながら足を引きずっていたことがある。あのときの痛みが全く「ない」もので、痛みの「信念」のみがあったと考えることは難しい。やはりクオリアは何らかの意味において、そして人が具体的にイメージできない何らかの形において「ある」ものに違いない。そして信号機の「青」が消えて「黄」になる場合、「青が消えて黄になる」という「変化」や「順序」を含んだクオリアも何らかの意味においてあるはずだ。このようにして全ての変化の感覚を説明するしかないだろう。
もう一つ蓋然的に「ある」と言えるものは「意味」である。言葉の意味は普遍的に存在しているに違いない。これは円周率のような数学の概念も含んでいる。でなければ数学も論理学も哲学も文学も「学」として成り立たないからだ。「2たす3は5である」と言う場合、「2」や「たす」という意味が普遍的・無時間的に存在していなければ、数学は成立しない。プラトンが
イデア論を主張した理由は、「意味」それ自体が実在するとしたら、それは時間変化のパラドックスを回避できると考えたからかもしれない。「言葉」は時間の中にあっても「意味」は無時間的なものである。ヘラクレイトスの言うように、万物は確かに流転しているように感じられる。しかし万物が時間変化によって消滅するのなら、人の知識、特に普遍性の認識がなぜ成立するのかわからない。従ってプラトンは時間変化の外部にあって、人の認識を成立させる実体としてのイデアを想定したと解釈するのが妥当であるように思う。
無時間的なものだけが、時間変化による消滅を免れることができるということである。後の世に普遍論争を巻き起こしたイデア論の是非はともかく、プラトンの発想には何らかの真理があったように思われる。
ところで「クオリア」と「意味」は同じものとして扱うべきか、という問題があり得る。音楽を聴いたときの固有の印象、トロピカルな紺碧の海を見たときの固有の印象などは、意味という概念から大きくかけ離れているように思える。もっとも「意味」という概念自体が漠然としており、言語哲学では意味とは何であるかを巡って多くの議論があることは知られている。
ここでは意味とは何かという問題について詳述することはできないが、第一章でも紹介した
ジョン・サールの言葉に重要な示唆がある思うので再掲しておく。
もしあなたが二足す二は四に等しいと考える場合、そこに質的な感覚がないと考えるなら、それをフランス語やドイツ語で考えてみよう。たとえ、 2 + 2 = 4 という志向内容が英語の場合とドイツ語の場合とで同じだったとしても、「zwei und zwei sind vier」と考えることは英語で考えるのとはまったくちがう感じがする。
サールによれば、ドイツ語で「zwei und zwei sind vier」と考えることは、英語で考えるのとは全く異なる質感を持ち、かつ意味を持つということである。つまり意味はイデアのように超越的なものでなく、またクオリアと峻別できるものではなく、クオリアの内部性質として存在しているとみなすことができる。意味はクオリアのカテゴリーの一つとして還元可能だということになる。
とりあえずの結論として、ここでは確実に「ある」と言えるものを、コギトと論理法則、蓋然的に「ある」と言えるものを意味を含むクオリアとしておく。
そして全てのクオリアは論理法則の要請によって、人には理解不可能な形で融合し、「一」として存在しているに違いない。これが物自体というべきものになるだろう。
もちろん、その「一」としての物自体とは別の物自体もあるかもしれない。わかりやすく言うならば「私」と対置させられる「他我」である。「私」をミクロコスモスとするならば、マクロコスモスが想定できるということである。しかし仮に他我というものが実在するとしても、それは決してアクセスすることができない別の宇宙であるのだから、深く考究することに意味はないと私は考えている。
クオリアは蓋然的に「ある」と言えるものである。しかし他我の存在は蓋然的にさえ「ある」とは推定できない。せいぜい「あるかもしれない」と言える程度である。
私が「一」と言ったら風が吹いて窓がカタンと一回鳴る。それだけなら偶然だと思うだろう。しかし次に私が「二」と言ったらまた風が吹いて窓が二回鳴る。次に「四」と言ったらまた風が吹いて窓が四回鳴る。そんな「偶然」が千回続いたならば、私は「誰か」が風を起こしていると確信するだろう。ここで重要なのは「偶然」と「必然」の境界などないということである。他人に心があるとする根拠はつまる所、偶然とは思えない現象の秩序であって、それ以上のものはない。
私は他人と話をしたことはあるけれど、他人の心と話をしたことはない。
上のような独我論はカント哲学でも示唆されていたことである。世界が「私の表象」であるならば、その表象に他人の心があるなどと、どうして考えられるだろう。「全ての表象に『我思う』が伴い得る」のは確かだが、「他人という表象に『他人が思う』が伴っている」と考えるのは困難である。
ただし私はカントの言う経験的実在論は尊重しており、他人たちを心ない者として扱ったことはない。私はこれまでに多くの他人たちと接してきた。その他人たちに私の経験ではない別のクオリアが相関していても論理的な不整合があるというわけではない。実際に私は他人たちと会話するときは、常にその別のクオリアが相関している(他我が存在する)可能性を考慮している。「他我」という語の意味の実質とは、その「相関可能性」である他はない。
他人に心があるかも知れないならば、あるものとして他人たちと接するしかない。たとえば風の強い日に道路上を大きな袋が転がっているとしよう。袋は風に吹かれて転がっているのだろうけれど、ひょっとしたら中に子供が入っていて転がしているのかもしれない。だからほとんどの運転手は袋を轢かないように心がけて走るのである。
哲学史上の一難問である「他我問題」を、私は件のように自分のものではない別のクオリアの「相関可能性」として落着させたい。
8 私の死と世界の死
私は無世界論を選択し、前節で次のように結論した。全てが消えていく世界で確実に「ある」と言えるものは、デカルトが見出した「私」と論理法則のみである。そして蓋然的に「ある」と言えるものはクオリアである。そして、それらの融合体として「一」なる物自体を想定した。その「一」なる物自体は永久的に「ある」ということになる。物自体が「ある」ものならば、これまで論じてきたようにそれは「ない」ものに「なる」ことはないからだ。
ところがその結論と直観が相克する。素朴実在論的にはこの私(筆者)の死によって、この私は消滅するように思えるからである。もちろん無世界論的には、この私が消滅しても、前節で論じた通り「私」を含む物自体は消滅しない。しかしこの私の消滅とは、「この世界」が消滅することである。ここで深刻な問題が生じることになる。
この世界が消滅するならば、次にはどんな世界があるのだろう?
もちろん無世界論においては、この世界も私がイメージしているような明晰なあり方はしていないし、次の世界と言っても時間は実在しないのだから、存在論的に正確な意味で「次の」というわけではないだろう。しかし何らかの意味においてこの世界は消滅し、何らかの意味において次の世界があることは、物自体内部の性質としてあるはずであり、変化の実在を否定した場合に帰結する論理的な真理であるはずだ。
時速百キロメートルで走る電車が六分後にどの地点にいるか数学的に推測可能なように、私の死も(大雑把であるが)自然科学によって推測可能である。しかし「次の世界」は衝撃的なほどに全く推測できない。推測する材料がないのである。この問題には自然科学は全く役に立たない。ここに自然主義の限界が露呈する。この私の死とともにこの世界が消滅し、この世界の諸現象を統べる科学も死ぬからである。これは反実在論を徹底した場合に必然的に到達する結論である。
そして、ここにおいて第2節で論じた可能世界論が再登場することになる。現象主義の立場からすると、私が空を飛ぶ夢を見たなら、私が空を飛ぶ可能世界は存在したということになる。そして私がモンローと結婚する夢を見たなら、私がモンローと結婚する可能世界は存在したということになる。現象主義では夢の世界を「この現実」とは異なる世界として実現したと認めざるを得ないのだから、他の論理的にありうる可能世界も全て存在可能だと認めるしかない。
この私が消滅した後の次の世界は、論理的に可能な世界ならば、どんなものでもあり得る。なお、死後に「人生」があるなどと安易に想像することはできない。それは人生どころか「生」とすらみなすことができないものかもしれない。つまり私は、自分が死んだら別の人間に「生まれ変わる」などと俗なことを妄想しているのではないし、ウサギに生まれる変わるかもしれないなどと「輪廻」を説いているのでもない。私は幽霊や神や魂の存在は信じない。人が経験する諸々の現象は完全に物理法則に支配されている。物理法則の支配に収まらないのは、物理法則そのものを成立させる世界の原理なのである。
ウィトゲンシュタイン独我論のエッセンスは、「主体=ウィトゲンシュタイン」ではなく、「主体=世界」ということであった。これは「無主体論」と呼ばれる立場である。ただウィトゲンシュタインは実在論者であったので、暗に表象主義を前提しており、正確には「主体=表象世界」ということになる。しかし現象主義的な無主体論・独我論では表象主義を否定するので、真の意味で「主体=世界」である。したがって世界からこの私という人物が消えても主体としての世界は存在するということになる。
たとえば私が我を忘れて映画に没頭していたとする。この場合「世界」と「主体」は映画と一致する。そして映画の世界に私が登場しなくても映画を見ることができるように、この世界にこの私が登場していなくても、主体は世界を見ることが(論理的に)可能である。ただしその場合は「世界を見る」という表現は正確ではなく、単に視覚的クオリアや聴覚的クオリアがあるのみなのだから、「世界がある」という表現の方が適切だろう。これが現象主義的な独我論である。参考までに大森荘蔵は論文「無脳論の可能性」において、脳がなくても意識経験が論理的に可能であることを示唆している。これは現象一元論者であった大森からすると必然的な結論である。
もちろん実在論者ならば、自分の身体や脳、視神経がないのに物が見えるなどというのはナンセンスだと一蹴するだろう。しかし実在論が破綻していることはこれまでに論じてきた通りである。したがって私の目がなくても主体は物を見ることが論理的には可能であったはずだ。しかし「この世界(主体)」は、世界内に存在する特定の人物を開闢点として存在している。これは全く偶然なのである。あえて言うと「究極の問い」に回収されるべき問題である。世界には何もないのではなく何かがある。そして世界は「このように」ではなく、「別のように」存在することができたはずである。なのに世界は、端的にこのように特定の人物を開闢点として存在している。
永井均は、「〈私〉は永井均でなく他の誰かでもありえた」という言い方で自らの独我論的問題意識(独在論)を表明することがある。つまり世界の開闢点は永井均という人物なのであるが、別の人物から世界が開闢されていても不思議はないということである。しかし偶然にも「〈私〉=世界」は永井均という人物から開闢されている。その偶然性が永井の問題意識の底にあって、この独在論はウィトゲンシュタインの独我論と根を共有している。
この世界は開闢点としてこの私という人物が存在しているのだが、実はこの私が登場しなくても世界は存在することが論理的に可能である。ならば「次の世界」は固有の開闢点がなくても不思議ではないということである。そのような世界では「私は今何かを感じている」というような内省によって得られた自己意識は存在しないだろう。逆に次の世界は固有の開闢点となる人物がいて、その開闢点としての人物が地獄で百億年間拷問され続けるとしても何ら不思議はないことになる。次の世界は衝撃的なほどにわからない。上に述べたように「科学」さえ死んでしまう。このわからなさこそが、私にとっては死の恐怖の本質である。
「幸せ」のクオリアのみが永久的にある世界は形而上学的に可能であるはずだ。その世界はシンプルで節約の原理に適い、人にとっても理想的であるように思える。しかしこの世界はそうなっていない。この現実が示すのは、節約の原理や人の理想といったものが、所詮は人間固有の価値観に過ぎないということである。世界=物自体はそんな人の価値観など全くおかまいなく、ただあるようにあるだけである。
私の消滅によって、この世界が消滅することは確実である。しかし次の世界がこの世界と同じであることは論理的に可能である。つまり地球や太陽があり、日本やアメリカという国があり、そしてこの文章を書いている私とは異なる別の人物が世界の開闢点であっても不思議ではない。これは或る意味で輪廻転生の可能性を肯定するものである。念のため付言するが、これは実在世界と「魂」を前提した上で、魂が時を越えて同一世界の別の人物に宿るというイメージの輪廻転生とは全く異なるものである。むしろ世界が消滅し、新たな世界が誕生するのだが、その世界は以前の世界と極似している、といったイメージである。「主体=世界」が、開闢点・様相を変えながら存在し続ける「可能性」を肯定しているのである。
次の世界がこの世界と同じである――そんな可能性がどれだけあるかは全くわからない。しかし可能性は否定できない。ここではそれだけを確認できればよい。
ところでその可能性にこそ、この私の実存がある。
私は自らの哲学活動を公にしている。それは「私」のためである。この場合の「私」とは「この私」でなく、「主体=世界」としての「私」である。この私には、自らの哲学を公開することによって他の誰かが救済されるかもしれない、などという思いは露ほどにもない。既に述べた通り「他我」の存在は信じることが難しいものであり、せいぜい「あるかもしれない」というレベルのものである。
私の死によってこの世界は消滅する。しかし次の世界がこの世界と同じである可能性は否定できない。そしてその世界は固有の開闢点としての人物を有しているかもしれない。その開闢点の人物が、「次の私」ということになる。この私は次の私のために、こうして哲学を書き残している。
次の世界がこの世界と同じであり、次の私がこの私が書いた哲学を読む――そんな都合のいいことが果たしてあるのだろうか?
正直、私はそんなことが実現するとは自分でもほとんど信じていない。可能的な世界は真の意味で無限にあるからだ。しかしそのような可能性が論理的に否定できず、可能性が僅かでもあるのならば、私はこうして哲学を続けて、哲学を記録し公開を続けなければならないのである。「私」のために。
・カラシニコフの哲学
死の受容と克服は哲学と宗教にまたがる人類史上最大級の課題である。私はここで自らの哲学原理に基づいて一つの解決案を提出する。
ロシアの銃器設計者ミハイル・カラシニコフは、AK47(1947年式カラシニコフ突撃銃)を開発した。カラシニコフの銃器設計思想とは、構造が単純で壊れにくく、未熟な兵士でも扱い易く、どんな過酷な環境でも作動する、というものであった。AK47は1948年にソ連の制式自動小銃に採用された。その後ソ連の友好国でもライセンス生産され、第二次中東戦争、第三次中東戦争、ベトナム戦争等で大活躍することとなった。
AK47、AKM、AK74とカラシニコフが設計した AKシリーズの自動小銃は、驚異的な耐久力と信頼性によって戦場の兵士たちに愛用され、自動小銃の世界市場では競合する他の小銃を劇的に圧倒し、現在世界には約一億丁普及していると推定されている。AKは核兵器なみに世界の歴史を変えた。かつてはベトナム戦争や中南米やアフリカで用いられて植民地解放に貢献し、近年では中東やアフリカの民兵が用いて治安悪化の元凶となっている。AKは「小さな大量破壊兵器」とも呼ばれている。
AKにまつわるエピソードで、私の心を捉えた興味深いものがあった。ベトナム戦争やイラク戦争で、一部のアメリカ軍兵士が自国の小銃を捨てて、鹵獲した敵の AKを使っているという話である。私はそんなアメリカ軍兵士の気持ちがわかるような気がした。ベトナムやイラクの環境は苛酷であり、アメリカ軍の制式小銃である M16は弾詰まりが頻発したという。いざというとき弾が発射されないのは戦場では致命的である。しかし前述のカラシニコフの設計思想によって開発された AKは、M16と比較すると命中精度は劣るものの、泥に漬かっても砂にまみれても確実に作動し続けて、その信頼性は戦場の伝説になっていた。
戦場は命のやり取りをする場である。自分の命を預ける道具はいざというとき確実に作動するものでなければならない。自国製に拘らずに敵国の武器を選んだアメリカ兵の心境は共感できるものであった。
実は哲学でもカラシニコフの設計思想は通用するのではないか。構造が単純で壊れにくく、未熟な兵士でも扱い易く、どんな過酷な環境でも作動する――。
単純な構造の哲学は壊れない。デカルトのコギト命題がそうであった。いくら疑っても、疑う「何か」の存在は否定できない。これは構造が単純すぎて壊しようがない。このような単純な論理は誰にでも理解できて、そしてどんな環境(可能世界)でも通用する。
前述したように私の死と同時にこの世界は消える。そして次の世界は衝撃的なほどにわからない。科学でさえ死んでしまうのである。このわからなさこそが私にとっては死の恐怖の本質である。死とは、底が知れない頻闇の深淵に丸裸で飛び込むようなものである。身を護るものを何も持ち行くことができない。持ち行くことができるのは「知」一つである。
その知とは、カラシニコフが開発した AKのようにどんな環境でも確実に作動する単純堅牢なものでなくてはならない。
もしどんな魑魅魍魎が出没するかわからない未知の世界に、ただ一つの武器を持ち行くことが許されるとしたら、アメリカ軍の兵士でさえ AKを選ぶに違いない。
絶対確実な知識から全ての知識を基礎づけようとする「基礎づけ主義」は今や誰も信じていない。しかし絶対確実な知識から特定の問題についての真理を解明できるというタイプの基礎づけ主義はあり得るだろう。私は前節で疑うことが不可能な絶対確実な存在として、「私」と論理法則を挙げた。その二つは悪魔や妖精が何と弄言しようと否定できない確実なものである。
パルメニデスは「ある」と「ない」を峻別し、「ない」を否定することによって、「無からの生成」と「存在の無への転化」を否定した。それらはデカルトが方法的懐疑の末に到達した「いくら疑っても、疑っている何かが存在する」という真理と並べて、人知を支える三本柱とすべき真理であると私は考えている。
柱1: 無からは何も生じない
柱2: 存在は無になることがない
柱3: 「私」は存在する
「私」が「ある」ものなら、それは論理法則によって「ない」ものに「なる」ことはできない。人知を支える三つの真理だけは、衝撃的なほどにわからない「次の世界」でも通用するものである。この「知」だけが、底が知れない頻闇の深淵に持ち行くことができるものであり、確実に作動するものである。
時間は、経験的実在性を持つ。人の経験するものは全て時間という究極の魔法によって消し去られる。ただ「私」と論理法則のみが確実に生き残る。
宗教とは信じるものであり、信じることをやめれば神も仏も消えてしまう。しかし論理法則は信じるものではなく、疑うことが不可能なものである。論理法則は消えることがない。したがって論理法則を基に構築された哲学のみが信じるに値する。
私は論理学に詳しいわけではない。同一律、矛盾律、排中律といった基本的な論理法則のみを用いて自らの哲学を構築してきた。基本的な論理法則は AKのように構造が単純で壊れることがない。逆にハイテク兵器のような複雑な論理や理論を用いた哲学は、ベトナム戦争で米軍のハイテク兵器が故障を多発させてベトコンに敗れたことに暗示されるように、信頼できないと感じている。したがって私は複雑高等な非古典論理は学ぶつもりもない。AKのように単純堅牢な構造の哲学のみが、命を預けるに値する。カラシニコフの哲学には、哲学者も学ぶべきところがあるはずだ。
中島義道は大森荘蔵の独我論を解説する過程で以下のようなことを述べている。
以上の独我論にまつわる議論は「俗人」の耳には、グロテスクきわまりない机上の空論に響くかもしれませんが、それは「俗人」が日常言語的世界観にどっぷり漬かっていて、それに対して胡散臭さを感じないからです。言いかえれば、――これこそ「大森哲学」の底に流れる通奏低音なのですが――この世界に生み出されてあっという間に死んでいく、という人生の溜息の出るほどの不条理を感じないから、都合よく鈍感だからです。とはいえ、すべての人が哲学などしなくていいのですから、「俗人」は、その俗人的言語をまとったまま安らかに死んでいけばいいのです。
中島の言う「俗人」とは、ローティやクワインのような「基礎づけ」を批判しているプラグマティストも含まれているように私は思う。プラグマティズムやホーリズムといった哲学的方法がどれだけ社会の役に立っているか私は知らない。しかし社会の役に立つことだけが哲学の目的ではない。自らを救うための哲学も必要なのである。
実存は本質に先立つが、死に臨んで人の実存と本質は一致する。「人生の溜息の出るほどの不条理」に打ちのめされた経験のある者は、たとえ無謀とわかっていても、恥も外聞も忘れて宇宙の真理に挑まざるを得ない。哲学とは人生の不条理との闘いでもある。「俗人」は死に臨んでローティやクワインの本を棺桶に詰め込んで飾っておけばいいだろう。しかし私が死に臨んで持ち行くのは、自国製の小銃を捨てて AKを選んだアメリカ兵と動機を同じくして、単純堅牢な論理に基礎づけられた絶対に壊れない哲学である。
やがて死んでしまう人間にとって、救いとは何だろう?
それは希望である。人間にとって最も不幸なのは希望を完全に喪失することである。死の先に「ある」を見出すことができるなら、死は決して絶望の極限ではない。逆に死が絶対的な「ない」への変化と考えるならば、それは希望の完全な消失となる。しかし「ある」が「ない」に「なる」などというのは、素朴な人の臆見である。変化は実在の性質であって、実在そのものが変化するのではない。実在は端的に「ある」ものであり、ゆえに「ない」に「なる」ことはできない。もちろん「次の世界」はわからないし、地獄のような世界であっても不思議はない。しかし不安に暗澹とすることはない。その次の世界もまた「消える」のである。
死の恐怖は「ある」ことによって、実存の苦しみは「消える」ことによって、救いの可能性が認められるのである。
単純堅牢な論理に基づいた哲学のみが、死によってさえ潰えることのない希望を与えることができる。
蛇足になるかもしれないが、命の尊さと死の恐怖は表裏の関係にある点に配慮しておくべきかもしれない。自分の命を尊いと思うのは、その尊いものを失いたくないという思いと同じである。すると死の恐怖を克服するということは、命の尊さを克服するというパラドキシカルな構造を孕まざるを得ない。死の恐怖は完全に克服すべきものではないのだろう。宗教が死後の幸福を約束することによって、死を恐れぬ理想の戦士を作り上げてきた歴史的事実もある。道徳的には、多かれ少なかれ死の恐怖に慄くのがよい。
人は死に恐怖を感じているとき、同時に命の尊さを感じているのだ。
9 夢と現実と真実の狭間で
私は第一章より反実在論を選択し、それを現象主義の立場から徹底して、最終的にエレア派の哲学と同型の無世界論という哲学的極地に到達した。
しかし、正直に今の心境を述懐せざるを得ないのだが、私は自分が構築した形而上学を信じ切ることができない。無世界論はあまりにも反直観的である。いくら哲学で重要なのは直観でなく論理と整合させることだとわかっていても、人間性そのものである直観を焼却することなど不可能なことである。
形而上学的実在論と、時間の実在論は簡単に放棄できるものではない。
形而上学的実在論とそれを前提にした
物理主義に強く誘惑されるのは、特に病院に行ったときである。血液検査を受け、コレステロール、血糖、白血球、それに肝機能の指標となる AST、ALT、ALPなどの値を調べてもらうことがある。胃カメラを飲んで、自分の消化器官を自分で見たことがある。MRI(核磁気共鳴画像法)で脳をスキャンしてもらい、その写真を見たこともある。
現代医学は血液中の成分の僅かな変化や、消化器官の形状や色の変化、脳の血管の状態などを見て、病気や病気の因子をピンポイントで突き止めることができる。人体は複雑極まる。その人体の構造を全て理路整然と説明する圧倒的な医学・科学の成果には、反実在論や無世界論などという邪悪かつ荒唐無稽な哲学を折伏させてしまう天使の背光を感じざるを得ないのである。
時間の実在論に誘惑されるのは、数々の想い出があるからである。幼い頃見た大蛇の記憶。今も机上にある七歳のときもらった親友のキーホルダー。友人たちと遊び回った学生時代の狂騒。恋した女性を懸命に誘ってデートに成功したときの胸のときめき。青春時代を彩った懐かしの流行歌たち。今は亡き親族たちと過ごしたかけがえのない団欒のとき。――それらは整然と時間秩序を織り成すことによって私の人生を物語のように「一つのもの」として形づくっている。無世界論の主張は時間を破壊し、経験の明晰性を否定することによって私の人生そのものを霧消させてしまう。だからこそ時間の実在論はそう簡単に放棄できるものはない。時間の実在論に従えば私の想い出たちも、世界にあるものごとも全て上手く説明できるのである。天使の囁く時間論はあまりにも魅力的である。
形而上学的実在論と時間の実在論は対になって人の素朴な世界理解を成り立たせている。
ところで形而上学的実在論を前提に
心身問題を考究すると、必然的に物理主義に至ることは留意しておくべきである。実在論とは表象世界と実在世界を分ける一種の二元論であるからだ。実在論を前提にその二元性を解消するならば物的一元論を選択するしかないのである。これは第三章で解説した。物質的実在を認めながら、それに還元できない存在論的な「何か」があると認めるのは、極めて困難なことを明らかにしたのが現代心の哲学の最大の成果である。
物的一元論が正しいと仮定すれば、人の経験は全て合理的に説明できる。人に可能な経験は唯物論に統制されているように思える。カントの「経験的実在論」は「経験的唯物論」と言い換えても差し支えないように思える。時間、空間、量、因果などの形式がなければ人の認識は成立しない。それらは物理学の形式でもある。
カントがア・プリオリな総合判断の探求に腐心したのは、彼が観念論者だったからである。世界は観念に過ぎないのになぜ現象はこんなに秩序正しく生起するのか、という驚きがあったからだろう。その驚きはカントと立場を同じくしないとわからない。しかしカントの方法は成功していない。所詮数学は分析判断に過ぎず、物理学はア・ポステリオリな総合判断に過ぎないのである。カントはヒュームの懐疑を克服してはいない。論理的な問題として物理法則が突如変わる可能性が否定されているわけではないからだ。
電車が秒速 100メートルで走っているなら、2秒後には 200メートル先の地点にいる。これは時間と空間という「形式」によって必然であると思われるのだが、論理的には 3秒後に 500メートル先にいることが可能なのである。論理的可能性と物理的可能性は異なることだからだ。第二章でカントがニュートン力学を観念論の立場から説明し得たと考えたのは、我ながら拙速であった。可能世界論とカントの「ア・プリオリ」は問題性が重なっている。もしカントが現代の可能世界論や規則のパラドックスを知っていたならば、『純粋理性批判』の内容は大きく異なっていたかもしれない。
反実在論――観念論の世界では、物理法則が突然変わることは可能である。また局所的に物理学では説明できない物事が存在していても何ら不思議はない。
にも関わらずこの世界には物理学で説明できないことはただの一つも起きていないように思われる。これは一体どういうことだろう。これまでの章で論じてきたように、論理的に考えると物理主義は完全に間違っているはずなのに、経験的に考えると物理主義は完全に正しいように思われる。世界の事象は全て例外なく物理的に説明可能である。論理的に「例外」が禁じられているわけではないのに、なぜ一つも例外がないのだろう?
滑稽なことであるが、私は時々超能力で空を飛ぼうと試みることがある。身体がふわりと浮くように念じるのだが、現実世界では決して飛ぶことはできない。ただの一回でも飛ぶことができたなら、その時点で物理主義を完全に退けることができるのだが、この世界はそうはなっていないようだ。物質的実在を否定するならば、物理法則とはプログラムのようなものだと考えるしかない。しかしプログラムには必ずバグがあるはずなのだけれど、この世界にはバグらしきものが見当たらない。私は毎日どこかにバグはないかと探している。電車で隣にいる人の頭が、バグで突如カラスになることはあり得るはずなのに、この世界はそうはなっていないようだ。論理的に物理主義は間違っているのだから、いつ「例外」が生じても構わないはずなのに、私は飛ぶことができず、世界にバグはない。なぜ物理主義は経験的に正しいのだろう?
もちろん、反実在論では例外が生じることが「可能」であるということは、例外が生じることは「必然」であるということではないのだから、私の有限の経験に例外がなかったからといって、それは反実在論が偽であることの証明にはならない。しかし例外がない限り私は物理主義の強度を克服することが難しい。
例外がないということ――この問題はおそらく、部分と全体の存在論(メレオロジー)の領域に解答があると思われる。興味深いことに、メレオロジーの問題もゼノンのパラドックスから生まれたという。エレア派のように「一」が根源的な存在であって、他の全てはそれを分割した概念として存在していると考えれば、世界において物理的に説明できない「例外」がないことは当然であるはずだ。――と言っても、このように大雑把な一元論的世界の説明では、物理主義の強度を弱めることは難しい。さらに、物理的に説明できないものがないということは、前節で論じた死後の「可能世界」にも関係してくるようにも思える。死後にどのような世界があるかはわからないとしても、やはりその世界はこの世界と同じ物理法則に統制されているのではないかと思えるのである。もちろん論理的には思考可能なものならば、どのような世界もあり得るはずなのに――。物理主義の強度はこんな問題にも及んでくる。死は論理によって得られた信念と、経験によって得られた信念が衝突する機会となる。
経験世界は物理学に統制されており、世界にある何百何千億の事象のうちただの一つも例外がない。これは奇跡なのか必然なのか、それともウィトゲンシュタインが言うように「完全にどうでもいい」ことなのか。例外がないのは不思議なことだ、というのは所詮人間的価値観であり、世界はそんな人間固有の価値観など全くおかまいなしに、あるようにあるだけなのだろうか。
困惑を解消するために次のような想像をすることができる。――この世界は夢だった。目が覚めたら私は鳥人間だった。そして人間になっていた悪夢を思い出す。人間の私は空が飛べず、寿命は僅か百年弱で鳥人間の千億分の一程度。現実の世界では一億年に一回物理法則が変わっているのに、夢の世界では僅か数十年間同一の物理法則が持続しただけで、人間の私は物理主義に誘惑されてしまった。人間とは何て視野の狭い卑小な生き物なのだろう――。
「規則正しさ」なんて所詮は人間固有の価値観なのだ。
いずれにせよこの世界が「どのように」あるかについて例外がないということは、世界が「なぜ」あるかの解答ではないし、存在者たちが「なぜ」あるかの解答でもない。そして因果関係が実在するならば、それは矛盾であることは解消されない。物自体は時間、空間、量、因果によって成り立っているのではないのである。
物理主義は現象世界が「どのように」あるかについて完璧に説明できる。この世界は神秘的なほどに規則正しいあり方をしている。――しかし仮に「神秘的なほどに美しいもの」があったとしたなら、それは「神秘的なほどに規則正しいものがある」ということと神秘のレベルは同じなのだ。規則正しさのみを重んじて物理主義が真なる形而上学であることを認めることはできない。それはほんとうの神秘ではない。
真の神秘とは世界が「ある」ということなのだ。規則や様相の概念は人の意識にしか存在しない。世界はただ「ある」だけであり、人はただあるだけのものについて偶然だとか必然だとか、規則正しいとか不規則だとか言っている。
「リンゴの視覚像」のクオリアが一個だけある世界W1は思考可能である。私はそんな世界を大して不思議に思わない。しかし「リンゴの視覚像」に続けて、「目を閉じる→リンゴの視覚像が消える→目を開ける→リンゴの視覚像が現れる」というクオリアがある世界W2も思考可能であるが、私はつい視覚像の規則の原因となるものがあるはずだとW2の世界に「実在」というものを想定しまう。双方の世界は何ら本質的な差異がないのに。
「ジャ」という音のクオリアが一個だけある世界W3は思考可能である。私はそんな世界を大して不思議に思わない。しかしその音に多くの音がつらなってベートーベンの交響曲第五番となり、その曲だけが存在する世界W4も思考可能であるが、私はつい音楽とは誰かが作ったものだとW4の世界に「因果」というものを想定してしまう。双方の世界には何ら本質的な差異がないのに。
流れがあれば淀みがある。多くの人が活発に速く流れているところがあれば少しの人が鬱然と濃く淀んでいるところがある。世界はただそんなあり方をしている。
混沌があれば秩序がある。ものごとが時空上に雑然と転がっているところがあれば、ものごとが整然と幾何学的な秩序をかたちづくって並んでいるところもある。世界はただそんなあり方をしている。
世界はただあるだけなのに、私はこれまでの人生で実在や因果といった余剰物を世界の原因と措定して世界を理解した気になっていたが、それは大きな錯誤であった。複雑なものには単純なものより多くの説明が必要なのかもしれない。しかしその説明は世界が「ある」ことを説明していない。
――以上のように様々な思索をめぐらしても、まだ私は物理主義の強度を完全に克服することはできていない。
哲学では自分を説得するのは難しい。アウグスティヌスが『告白』で、「神は世界を創造する前に何をしていたのか」という問いに繰り返し反論しているのは、本人も不合理だと感じていたからに違いない。
今一度、反実在論と無世界論の立場から私は自分の説得を試みてみよう。
医学など自然科学の成果を反実在論の立場から整合的に説明することはできる。因果関係は実在しないが、「因果関係に見えるもの」は何らかの意味において存在しているのである。その「因果関係に見えるもの」こそが様相の開闢点としての端的な現実であり、それ以上原因を遡及することが不可能なものである。それは「究極の問い」の対象となるしかないものである。
そして私の想い出たちがどんなに明晰なものであるように思えても、それらは全て「消滅」する。消滅するということは、消滅した対象の明晰性を否定することであった。私のテーブルに歴然として存在するキーホルダーもやがては消滅してその明晰さを失う。たとえキーホルダーを銀行の貸金庫に保管しようとも、反実在論を前提とするならば、私の死によって世界も消滅するのだから、消滅を逸れるものは何もないのである。消滅するものは、元から(私がイメージする通りには)存在しなかったのである。これが無世界論である。
無世界論が示唆する世界は、わけがわからないあり方で存在している。
しかし
ウィトゲンシュタインが看破したように、世界がどのようにあるかということは、実は全くどうでもいいことなのである。神秘なのは世界が「ある」というそのことなのである。
こんな可能世界をイメージしてみよう。
W_Rome: 映画『ローマの休日』のDVDが一つだけある世界
W_Romeは形而上学的に可能な世界である。「W_Romeの世界があるということ」は端的な神秘としか表現しようがない。
しかしこの世界にいる常識的な人々は、W_Romeの世界などありえないように思うだろう。『ローマの休日』を作るには監督のウィリアム・ワイラー、出演者のオードリー・ヘプバーンやグレゴリー・ペックたちがいなければならない。また映画の撮影機材、そしてDVD再生機、そもそもローマ市や地球や太陽もあるはずだ、と常識的に考えたくなるだろう。
その常識と妥協して、W_Romeの世界にワイラー、ヘプバーン、ペックという人物たち、そして撮影機材やDVD再生機、ローマ市や地球や太陽を付け加えてみよう。ではそれらを付け加えたことで、「W_Romeの世界があるということ」という神秘は解消されただろうか? 解消されるわけはない。
ならばこうしてみよう。ヘプバーンの親、そのまた親、そして人類が進化していく歴史を付け加え、そしてビッグバン以来の宇宙の歴史までも付け加えてみよう。ではそのように夥しい要素を付け加えたことによって、「W_Romeの世界があるということ」という神秘は解消されただろうか? 解消されるわけはない。
逆に夥しい要素が加わったことで神秘の数が増えたと考えることもできる。最初はDVDだけが存在していたのに、ヘプバーンなどの人物たちや撮影機材なども加わったからだ。存在者が増えれば存在者の数だけ神秘も増えるのではないか。――これは因果系列が無限に実在することを認めたとしても同じことである。それでも「なぜ『ローマの休日』のDVDが作られるに至る無限の因果系列が存在するのか」と問うことができるからだ。したがって「究極の問い」は、無限後退やカントのアンチノミーとは本質的に異なる問題である。
W_Romeに因果関係として新たな要素を付け加えるということは、W_Romeの世界が「どのように存在するか」という「あり方」の変更をしただけであって、W_Romeという世界が「なぜ存在するか」という神秘を解消したことにはならない。科学はこの宇宙が存在する「根拠」を解明したわけではない。この宇宙の「存在の様態」「あり方」を解明したにすぎない。宇宙が「存在すること」に根拠はそもそもないのだから、解明することはできない。――ハイデガーの「存在論的差異」がいかに巨大な知的インパクトであったかと、今更ながら痺れるほどの感慨を得ざるを得ない。
W_Romeの世界もこの世界も、「存在すること」の神秘は同じレベルなのである。この世界には映画『ローマの休日』のDVDがある。そのDVDという存在者はヘプバーンなどの人物や映画の撮影機材を「様態」あるいは「属性」として有しているのであって、「原因」として有しているのではない。
したがってこの私の死によってこの世界と科学が死んで、次の「私」は別の科学が統べる別の世界にいると考えても、反実在論の立場からすると何ら不思議ではないのである。
ここに物理主義は葬り去られた。――はずであるにも関わらず、医学・科学の成果の恩恵を受けるたび、そして数々の想い出の時へと魂が惹かれるたび、私は物理主義へと強く誘惑されることになる。
「人間には理解できない未知の原理によって変化は実在します」という天使の囁きが、私には常に聞こえている。それを打ち消すように「未知の原理で1たす2が7になるなんて言うのはナンセンスよ」という妖精の囁きが聞こえる。「独今論を選択してしまえば余計なことを考えずにすむのだ」という悪魔の囁きも消えることがない。
現実性とは単に様相の一概念であるのみではなく、人の認識能力の限界を示すものでもある。人は神のように全ての時点と地点を平等に見渡すことはできない。人にとって現実化している時点と地点は「今ここ」だけである。人はその現実から他の全てを推測するしかないのであった。その現実とは、現前しているクオリアであった。しかし時間の内にあるそのクオリアは必ずしも明晰なものではなかった。「痛み」を感じながら、どんなに「この痛みの明証性は疑い得ない」と信じていても、その信念ごと消滅するのであった。消えていった現実はもはや現実ではなく夢であり、消えない夢はもはや夢ではなく現実である。
しかしその現実は矛盾している。論理的には現実を超えた真実が要請される。論理的な真実は現実を否定するものである。認識能力を制限するものとしての現実性に限界付けられながら、夢と現実と真実の狭間で、天使と悪魔と妖精に囁かれながら私は迷い続けなければならない。それが人の現実である。
にもかかわらず、再び同じ問題を提起し、解答を模索せざるをえない。人の思考の形式では到達できず、語ることは存在に対する裏切りだとわかっていても。無世界論に対する問いと解答は循環せざるを得ない。
私の人生が自分のイメージしている通りににはないのだとしたら、私の経験してきたものごとたち、そして「この経験」「これ」とは、一体何なのだろう。「これ」において一体何が起こっているのだろう。「これ」が私が信じてる通りには「ない」というなら、ほんとうに「ある」ものは、一体何なのだろう。明快な解答があってはいけないのだろうか?
「無限に思える有限なものが永久にある」という第二章で出した結論は変わらない。全ての要素は「一」なる全体の性質としてあるはずだ。しかし、その性質なるものが人には明晰には理解できないのである。ここが夢の世界であり、やがて覚めるとしても、そこもまた別の夢の世界かもしれない。その別の夢から覚めたとしても、やはりそこも夢の世界かもしれない――もしそんな(輪廻転生のような)ことが際限なく続いていくとしたら、「ほんとうの世界」や「ほんとうの自分」など、どこの世界のいつの自分にも定位できないということになる。それら夢体験の「全体」を想定して、その全体こそが「ほんとうにあるもの」なのだと言うことができるようにも思えるが、しかし少なくとも、神の視点から見たような仮想の「全体」なるものを、人の言葉で明快に語れるわけがない。またその全体が「ほんとうの自分」であるわけはない。自分が経験できないものが「ほんとうの自分」であるわけがないからだ。
私はかつてこんな漠然とした思いにかられていたことがある。哲学の探求をひたすら続けて、ついに宇宙の真理を発見したら、その瞬間華麗なるファンファーレとともに天空がぱっかり割れて、神と呼ぶに値する者がひょっこり顔を出し、「ゴールインおめでとう!」と言いながら世界の化けの皮を剥いでいき、真実の世界が明らかにされる――。今やそんな妄想は全く消えている。
人の経験はどれもこれも、子供がストローで吹くシャボン玉のようなものである。ひと息で銀河のように生まれる彩かな泡沫たちの世界。泡沫が映す虹は儚いけれど真実に見放された人には「これ」が全てなのだ。
夢が終わるとき夢の世界が消えるように、私の人生が終わるときこの世界も消えていく。
そう結論した私に、再び妖精が次のように囁く。――「これ」というのは存在しない。「これ」と言った瞬間に消えているでしょう。にもかかわらず、全ては「これ」にあるのよ。
ウィトゲンシュタインが主体は世界の限界だと言った境界線に沿って妖精は魔法の杖でくるりと世界を囲むように輪を描いて、その内にある何百億の銀河の群れや私の見たもの触れたもの聞いたもの得たもの築いたものすべて、さらに医者も科学者も技術者も彼らの理路整然とした説明も何もかもを、時間という究極の魔法で消し去ってしまう。ところが全てを消し去ったはずなのに、その輪の内にはいまだ何かがあり続ける。あるものはないものになることができないからだ。「これ」はある。
妖精は言う。「事態は残酷なほどに単純明快。変化は二つの矛盾があるのだから実在しない。無世界論は次のような論法で〈これ〉について説明できるのよ」
前提1: 変化は不可能であるゆえに、全経験は信念通りの明晰なあり方で存在してはいない
前提2: 「多」は不可能であるゆえに、全経験は融合した「一」の状態で存在している
結論 : 「これ」は実在の全体である
「ここにおいて夢と現実と真実と、現象と物自体は一つのものとして融合する。真理への道はここでお終い」
そう囁いた妖精もまた消えていく。
それでも「これ」はあるので、摩訶不思議に包まれた私は不可能を可能にしようと、可能世界に自らを映す鏡を思い描いて「これ」を語ろうと試みるだろう。世界は原因を持たずただあるだけなのだけれど、そのように自らを探求し尽くそうとするあり方で存在しているのだ。だからこそ哲学の道は真の意味で無限なのである。
伊佐敷隆弘『時間様相の形而上学』勁草書房 2010年
入不二基義『時間は実在するか』講談社現代新書 2002年
入不二基義『時間と絶対と相対と』勁草書房 2007年
入不二基義「無についての問い方・語り方」Heidegger-Forum Vol.6 2012年
入不二基義『あるようにあり、なるようになる 運命論の運命』
植村恒一郎『時間の本性』勁草書房 2002年
大森荘蔵『大森荘蔵著作集 第二巻 前期論文集II』岩波書店 1998年
大森荘蔵『物と心』東京大学出版会 1976年
大森荘蔵『流れとよどみ―哲学断章』産業図書 1981年
大森荘蔵『時間と自我』青土社 1992年
大森荘蔵『時間と存在』青土社 1994年
大森荘蔵『時は流れず』青土社 1996年
神山和好「水槽の中の脳型懐疑論を論駁する」科学基礎論研究 Vol.32 No.1 2004年
戸田山和久『知識の哲学』産業図書 2002年
永井均『〈子ども〉のための哲学』講談社現代新書 1996年
永井均『〈私〉の存在の比類なさ』勁草書房 1998年
永井均『存在と時間 哲学探究1 』文藝春秋 2016年
永井均 他『〈私〉の哲学を哲学する』講談社 2010年
野矢茂樹『同一性・変化・時間』哲学書房 2002年
中村秀吉『時間のパラドックス』中公新書 1980年
中島義道『「時間」を哲学する』講談社現代新書 1996年
中島義道『時間論』ちくま学芸書房 2002年
中島義道『生き生きとした過去――大森荘蔵の時間論、その批判的解読――』河出書房新社 2014年
松田毅「フッサールのメレオロジーに関する試論」神戸大学文学部紀要, 40: 1-31 2013年
松本仁『カラシニコフ Ⅰ Ⅱ』朝日新聞出版社 2008年
三浦要『パルメニデスにおける真理の探究』京都大学学術出版会 2011年
三浦俊彦『可能世界の哲学』NHKブックス 1997年
三浦俊彦 「
意識の超難問」の論理分析」『科学哲学 35-2』2002年
八木沢敬『神から可能世界へ 分析哲学入門・上級編』講談社選書メチエ 2014年
山川偉也『古代ギリシャの思想』講談社学術文庫 1993年
渡辺恒夫『人はなぜ夢を見るのか』化学同人 2010年
神崎繁、熊野純彦、鈴木泉 編集『西洋哲学史1』講談社 2011年
鈴木生郎・秋葉剛史・谷川卓・倉田剛 著『ワードマップ 現代形而上学』新曜社 2014年
アリストテレス『アリストテレス全集4─天体論・生成消滅論』岩波書店 1968年
ポール・デイヴィス『時間について』林一 訳 早川書房 1997年
マイケル・ダメット『真理という謎』藤田晋吾 訳 勁草書房 1986年
ブライアン・グリーン『宇宙を織りなすもの 上』青木薫 訳 草思社 2009年
モーリス・メルロ=ポンティ著 クロード・ルフォール編 中島盛夫 監訳『見えるものと見えざるもの』法政大学出版局 1994年
セオドア・サイダー『四次元主義の哲学―持続と時間の存在論』中山康雄 他 訳 春秋社 2007年
アール・コニー、セオドア・サイダー『形而上学レッスン』小山虎 訳 春秋社 2009年
『別冊日経サイエンス 時間とは何か?』 日本経済新聞出版社 2011年
最終更新:2016年05月20日 01:10