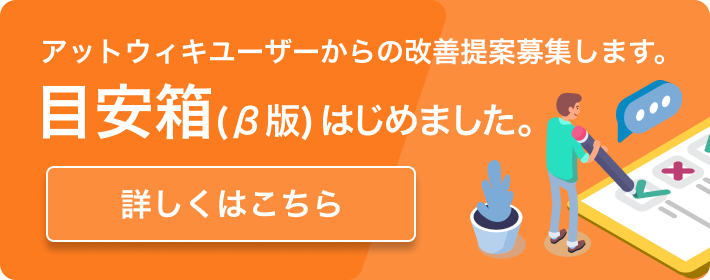形式化と文学
Seibun Satow
Oct, 27. 2009
Wir müssen wissen.
Wir warden wissen.
David Hilbert
第1章 うなぎをめぐる冒険
村上春樹は、柴田元幸東京大学教授の対談集『柴田元幸と9人の作家たち』の仲で、作品制作の過程について地祇のように述べている。
村上:だから僕はいつも、小説というのは三者協議じゃなくちゃいけないと言うのですよ。
柴田:三者?
村上:三者協議。僕は「うなぎ説」というのを持っているんです。僕という書き手がいて、読者がいますね。でもその二人でだけじゃ、小説というのは成立しないんですよ。そこにはうなぎが必要なんですよ。うなぎなるもの。
柴田:はあ。
村上:いや、べつにうなぎじゃなくてもいいんだけどね(笑)。たまたま僕の場合、うなぎなんです。なんでもいいんだけど、うなぎが好きだから。だから僕は、自分と読者との関係にうまくうなぎを呼び込んできて、僕とうなぎと読者で、3人で膝をつき合わせて、いろいろと話し合うわけですよ。そうすると、小説というものがうまく立ち上がってくるんです。…必要なんですよ、そういうのが。でもそういう発想がこれまでの既成の小説って、あんまりなかったような気がするな。みんな読者と作家とのあいだだけで、ある場合には批評家も入るかもしれないけど、やりとりが行われていて、それで煮詰まっちゃうんですよね。そうすると「お文学」になっちゃう。
でも三人いると、二人でわからなければ「じゃあ、ちょっとうなぎに訊いてみようか」ということになります。するとうなぎが答えてくれるんだけど、おかげで謎がよけいに深まったりする。そういう感じで小説書かないと、書いてても面白くないですよ(笑)インターネットなんかやっていると、読者から小説についての質問が来るわけです。村上さん、これはどういう意味ですかって。でも、そんなの、僕にだってよくわかんないから、わかりませんって言うしかないですよね。そんなのうなぎに訊いてくれよって(笑)。
呪術やジェドサイエンスにおいて、こうした関係はよく見られる。占い師=お客=水晶玉の三者で未来を協議する。占い師とお客だけではこれからのことは見当がつかない。そこで、水晶玉の出番となる。占い師は示され結果をお客に語る。なぜそうなのかは占い師にもわからない。水晶球が言っていることだからだ。この設定はドリフの「もしも」のコントでお馴染みである。お客がいかりや長介、占い師が他のメンバーという配役で、最後に「だめだこりゃ」となる。村上春樹は、いつもと同様、別に新鮮なことを語っているわけではない。聞いている側もこの程度の構造を即座に見抜けなければならない。
インタビューのこの部分だけでも、「ジュドサイエンスの楽園(Paradise of Pseudoscience)」を生み出し続ける村上春樹の言語感覚が理解できる。うなぎと言えば、われわれは町屋を思い起こす。それは間口を狭く、奥行きの深い短冊型の家屋で、「うなぎの寝床」とも呼ぶ。うまいこといったものだ。これは、江戸時代中期、間口の大きさによってかけられる税金が決められていたため、節税対策として生まれている。また、日本語には、主題優勢言語の特徴の一つでもあるのだが、主語と補語が一致しない「うなぎ文」(別名「こんにゃく文」)が見られる。「私はうなぎ」や「俺はこんにゃく」のように、「買う」や「選ぶ」、「とる」、「頼む」、「食べる」などの意味の動詞の代替として、コピュラ(英語で言うと、be動詞)を用いる場合がある。こうした構文を総称して「うなぎ文」と言う。その必然性はないけれども、「うなぎが好きだから」、それをそう名づけるとすれば、そこには村上春樹の自意識の優位性がある。
また、「お文学」というフレーズも同様である。「お」は敬語表現に属し、丁寧語と美化語に二別される。前者は「お肩」や「おビール」、後者は「お尻」や「お酒」がそれぞれにあたり、両者の区別は日記に記せるかどうかで判定されている。ただし、「お高くとまる」や「お偉方」のように、それをつけることで悪い意味になる場合もある。また、通常、「お」は和語、「ご」に看護に接頭される。「お寺」と言うが、「お寺院」とは使わない。もちろん、例外はある。最近急速に広まった「お受験」もその一つである。おそらく、この用法が定着した理由は、奇妙な使い方がそれにとりつかれた上昇志向の親たちのクレージーな雰囲気をうまく伝えているからだろう。しかし、「作家さん」という少々軽蔑雑じりの言い方がすでにある以上、「お文学」は社会的に共有される可能性は低い。独りよがりな言葉と言わざるを得ない。
そもそも、人は、一般的に、言葉を生み出すことができない。ある人が小説を「カキコキ」と独断的に呼ぶと決めて使ったところで、他者から相手にされず、共有もされない。
数は少ないが、言葉をつくり出せる才能の持ち主がいる。それには特異な雰囲気を持った世界を構築し、その得体の知れなさを聞いたこともないオノマトペによって表象させる。この奇妙ながら、その世界のリアリティを伝えていると、読者は共感し、自然に受けとめられる。オノマトペについての鋭敏なセンスがなければ、新たな言葉を生み出すことはできない。宮沢賢治や赤塚不二夫がそうした天才の好例である。「クラムボンはかぷかぷわらったよ」や「タリラリランのコニャニャチワ」は彼らの世界の気分を示している。オノマトペの達人がその世界を超えて創造した言葉を世間に浸透することができる。文学における新たな世界構築はオノマトペにかかわっている。
村上春樹の作品には、実際、無意味な言葉や数字が溢れている。彼が言葉なんて何でもいいと考えていることは確かだろう。しかし、引用したインタビューの中でも最も問題なのは、「べつにうなぎじゃなくてもいいんだけどね」という姿勢の作家が「謎がよけいに深まったりする」と主張している点である。と言うのも、言葉など何でもいいということと謎の深まりは相反するからである。それに気づいていないとすると、村上春樹は恣意的に小説を書いていることになる。
村上春樹は、彼の作中人物も含めて、しばしば意味なんてないと口にする。それは彼が子供に向き合ったことがないから言えることだろう。発達は人によって異なり、しかも早くなったり遅くなったりする。とりわけ子供の個体差は大人以上である。個別性が強い対象には、一般的対応では不十分であるので、解釈が必要である。言語的コミュニケーションもまだまだであることもあって、子供の行動には、相当突飛に思えても、大人が考えているよりもはるかに意味がある。子供に接するものは、その意味を読みとれなければならない。村上春樹は差異を見る気がない未熟なだけだ。
第2章 形式化
20世紀最大の数学者の一人ダフィット・ヒルベルト(David Hilbert)は、1891年、数学者と幾何学公理について議論した際に、「点、直線、平面の代わりに、椅子、テーブル、ジョッキを使っても幾何学ができるはずだ」と豪語している。それは「謎」を深めるためでは、もちろん、ない。論理を精緻化することが目的である。
ヒルベルトのこの意見は、厳密な学を目指そうとする数学の要請に基づいている。数学において、実は、「点、直線、平面」といった基本概念を明確に定義することは難しい。
ユークリッド原論では次のような曖昧な定義がいくつか見られる。
定義I-3
線の端は点である。
定義I-4
直線とは点がまっすぐに並んだ線である。
これらは「点」と「線」の関係を述べているだけであって、それぞれを定義しているわけではない。同様に、「端」や「まっすぐ」、「並んだ」も直観に依存しており、論理的な説明ではない。こういった語句を「無定義述語」と呼ぶ。
しかし、無定義述語は公理公準によって間接的に次のように定義されている。
公準1
任意の点から任意の点へ直線を引くことができる。
公理公準を満たせば、定義は必ずしも必須ではない。数学の目標は基本概念を定義することではなく、定理とその証明である。定義は外部、すなわち他者にとって必要な解説である。理論体系の内部から考えるのであれば、表現を改めて定義を公理に移動するか、もしくは省略するかでかまわない。公理が明確であれば、定義がなくても、数学の議論が進められる。ユークリッドの公理系も簡便さのための改訂や根本的な改良、批判的な変革を加えて、精緻化すればよい。
公準1は次のように言い換えられる。
公準1
相異なる任意の2つの点に対して、それらを通る直線を引くことができ、しかもその直線は1つである。
19世紀末、公理系の精緻化の流れが加速する。定義がなくてもかまわないほどの公理系の厳密性が確保されていないことに、多くの数学者たちが気づく。それには、非ユークリッド幾何学や集合論といった直観的には把握し難い新たな数学理論の登場が大きい。数学的な直観の認識の支配は無意識的である。数学者であっても、公理として明記されていないのに、直観的にそれを自然に納得してしまう。意識して直観を排して論理を厳密化しなければならない。
そうした試みの中で、最も有名なのがヒルベルトの『幾何学基礎論(Grundlagen der Geometrie)』(1899)である。これは、ゲッティンゲン大学において、1898年から99年にかけての冬学期に行った講義をまとめた小冊子で、数ヶ月もしないうちに、教科書として広く数学界で読まれている。この著作の成功はユークリッド幾何学を19世紀から20世紀へと向かうダイナミズムの中で捉え直すのではなく、それを公理主義によって解釈して見せたという点にある。ユークリッド以来の伝統を解体せず、その理論的完成を目指している。こうした保守的な姿勢の作品は、共通理解を多く踏まえているので、読者にとって受容しやすい。ヒルベルトは、そこで立ちどまるつもりがなく、集合論の基礎づけという壮大な企てに着手していく。この整備された集合論によって数学の体系全体が再構成され、現代数学が誕生する。
野崎教授は、『不完全性定理』において、数学者の仕事を「問題提起」・「体系化」・「精密化」の三つに大別している。第一の「問題提起」は、根本的な問いを示し、新たな学問や分野の誕生を促すことである。万物のアルケーを「水」と言ったタレスが挙げられる。第二の「体系化」は堆積した成果に整合性を持たせて集大成することである。その代表はユークリッドである。第三の「精密化」は各種の理論を逆説的論法を通じて批判的に考察し、厳密化することである。パラドックスで知られるゼノンがその典型である。ただ、生産性に乏しいいう欠点がある。ヒルベルトはこれら三つのすべてをやってのけた「数学界のスーパースター」と野崎教授は賞賛している。
ヒルベルトは公理公準を区別せず、理論の出発点をすべて公理とする。それは事実ではなく、あくまでも仮定である。その公理に立脚して、定理を有限回の作業を通じて証明する。そうした論証が厳密であれば、直観に引きずられてしまうような従来の数学の概念に代わって、「椅子、テーブル、ジョッキ」でも理解できるはずだ。
意味ある言葉は直観を誘発してしまうので、「椅子、テーブル、ジョッキ」と言わずに、点を「レレレのレ」、直線を「シェー」に先の公準1を置き換えてみよう。
公準1
相異なる任意の2つのレレレのレに対して、それらを通るシェーを引くことができ、しかもそのシェーは1つである。
まったく違和感がない。このまま赤塚マンガに使えそうだ。
もっとも、日常でも、新聞や雑誌、書籍を読んでいてわからない単語が出てきても、文脈から意味を推測し、内容を理解している。近年では、ワープロ・ソフトで文書を書く場面が多くなり、変換ミス等による、誤字脱字を目にすること増え、こうした推量の場面が多くなっている。
重要なのは公理系が厳密に与えられていることである。公理に基づき、それ以外の性質を使わないで、論証を進められる。そうであるなら、定義は希薄化するから、意味が問われなくなり、言葉は何だってかまわなくなる。公理を満たしていれば、どのような文字や記号、言葉を用いてもよい。数学的に形式化されていれば、論証は現論証の合理性・確実性を保障する。
形式化の考えに従えば、次のような一風変わった文も可能になる。
ケムンパスがタイホするウナギイヌはケムンパス
バカボンがタイホするウナギイヌはバカボン
ニャロメがタイホするウナギイヌはニャロメ
ウナギイヌがタイホするウナギイヌはウナギイヌ
一見したところで、何だかわけがわからないが、これらは自然数と乗法に関する次のような公理に基づいている。
(S1) すべてのp、q、rについて
p・(q・r)=(p・q)・r
(S2) あるuがすべてのpについて
u・p=p
このようなuを単位元と呼ぶ
(S3) すべてのp、qについて
p・q=q・p
この公理は非常に汎用性が高い。自然数のみならず、整数でも、有理数でも、実数でも、複素数でも用いられる。また、加算やより大きい数に使えるし、工夫すれば、最小公倍数などにも適用できる。そのため、この公理から数多くの定理を証明することが可能である。なお、自然数と乗法の場合、単位元を1と考えればよい。
直観にとらわれていると、謎めいているが、そんなものはない。先の文章がpを「ケムンパス」、qを「バカボン」、rを「ニャロメ」、uを「ウナギイヌ」、・を「がタイホする」、=を「は」に置き換えただけだということがすぐわかる。
もしお望みなら、すでに発見されている公理や定理、証明を援用し、任意の単語に入れ替えて、散文や詩を作ることも可能である。
野崎昭弘大妻大学名誉教授は、『不完全性定理』の中で、点を「ピン」、無限直線を「ポン」、「通る」を「パン」と代入して、交差する直線についての定理とその証明を次のように試している。
定理 ポンLはピンPをパンするが、ピンQをパンしていないとする。そしてPとQをパンする本がL´を考える。するとそのポンL´ともとのポンLとがどちらもパンしているピンはPだけで、それ以外の同じピンを両者ともにパンすることは決してない。
[証明] ポンL、L´が、P以外の同じピンRをパンしたと仮定しよう。するとポンLおよびL´は、どちらも相異なる2つのピンP、Rをパンすることになる。ところが相異なる2つのピンをパンするポンはただひとつである(♭)から、ポンL、L´は同一でなければならない。一方ポンLはピンQをパンするので、LとL´は同一ではありえない。だから最初の仮定は誤りで、ポンL、L´がP以外の同じピンをパンすることは決してない。[証明終]
まるでルイス・キャロルのようだが、とにかく証明はできている。言葉が何でもいいとは、こういう直観を排した論理の精緻性、すなわち形式化への意志である。その詩制を貫くのであれば、謎などという曖昧なものを排除せねばならない。謎があることはその公理系が直観に依存しているからであって、形式化が不徹底なだけである。
現代社会はこの形式化の恩恵を受けている。その一つがコンピュータである。形式的に定義された有限会の作業であれば、原理的には問題を解くことができる。コンピュータにとって言葉の意味はどうでもよい。
公理系をめぐる考えはさらに発展している。ヒルベルトは数学の基礎つけとして公理系を展開したが、構造主義以降、特定のモデルのみに当てはまるだけでなく、抽象的・一般的な理論体系を可能にする公理系が探求されるようになる。個々の公理が正しいかどうかは問われない。モデルの中で妥当であれば、それでよい。その外でのことはとやかく言わない。数学者の関心はいかなるモデルがあるかあるいはそのモデルがどれだけ生産的であるかに映る。
こうした現代化の進展は細分化・専門化・高度化を招き、ちょっとでも専門が違っただけで、その分野のことを理解できない。言葉なんて何でもいいのは、専門家集団内での論理の徹底追求のためであり、他者は排除される。同じ数学者でさえも、場合によっては、他者となる。その好例としてすでに引用した野崎教授の『不完全性定理』が挙げられる。教授はコンピュータ科学の基礎理論を専門とし、数学教育の分野でも活動もしている。その彼が数学史を辿りながら、クルト・ゲーデルの不完全定理の入門書として1996年に公表したのが同書である。執筆に当たっては、野崎教授は専門外であるので、小野寛晰北陸先端科学技術大学院大学教授と伊藤潤一岩手県立一関第二高校教諭に確認をしてもらっている。しかし、出版されると、それでもその分野の専門家から不備を見つけられている。林晋京都大学大学院教授が第3不完全性定理に関する誤解などを指摘している。また、円周率の桁数字に9が10個以上続けて表われるかどうかの判定を不可能と書いているが、金田康正東京大学大型計算機センター教授が実際にはすでに行われていると注意を受けている。野崎教授は正直にミスを認め、あとがきにそれらを記している。今日の学問はそれだけセクト化している。
野崎教授は、数学教育協議会の委員長も務めているように、専門外だからと言って、当て推量や思いこみで本を書くことなどしない。そんな手抜きは教育者としてあるまじき行為だ。しかも、複数の数学者に意見を尋ねている。そこまで慎重に執筆を進めても、不備が見つかってしまう。けれども、自分の専門分野に精通していても、初心者にそれwpいやエルとなると、彼らの誤って理解したり、つまずいたりする傾向を認識した上で、臨まなければならない。実際、野崎教授も、『数学的センス』の中で、『岩波数学事典第2版』の「群」の項目の一部を引用して、正確であるけれども、知っている人にしかわからない説明で、初心者向けには具体例による解説が不可欠だと主張している。事典や入門書には内部と外部の両方の認識を持つことが求められる。専門家はリテラシーを暗黙知として理解しているが、初心者にはそれを明示化して伝える必要がある。そのため、定義が重要となる。他者を相手にした場合、言葉など何でもよくはない。
第3章 作家の倫理
一方、形式化とは別の観点から村上春樹の本を読んでも、作品の出来以前に作家の倫理の点で疑問を持たざるを得ない。
『かえるくん、東京を救う』((2000)という短編小説がある。東京の地下に棲む大みみずくんが、阪神大震災に刺戟されて、地震を起こそうとしているのを知ったかえるくんが片桐さんと共に戦い、東京を救うという寓話である。ただし、夢の中の物語であろうと暗示されている。これは非常に評価が高く、川村湊法政大学教授を始めとする文芸批評家も好意的な評を書いているし、内田樹神戸女学院大学教授に至っては、彼の最高傑作とまで賞賛している。
しかし、この筋を聞いただけでも、この小説には不備があることがわかり、文学に値しないと言わざるを得ない。荒唐無稽だからではない。寓話にもなっていないからである。
自然をめぐる寓話は今の世界の意味づけを描く。「なぜ岩手山はそう呼ばれるか」とか「どうしてウサギの目は赤いのか」といった問いに寓話は答える。けれども、東京で地震を防いだという設定は寓話ではあり得ない。と言うのも、地震はこれからも引き続き起こるからだ。
言うまでもなく、日本全体ではまったくないわけではない。茨城県鹿嶋市の鹿島神宮と千葉県香取市の香取神宮にある武甕槌大神要石は、地震を鎮めているとされている。地震の原因である暴れる竜をこの石が抑えているために、地域にはその大きな災害がないという伝承がある。これを別にすれば、地震の原因は地下に棲む大なまずが暴れるためというのが古来からの主流とも言える伝承である。みみずはいわゆる益虫であるので、通常、日本では人間にとって害悪をもたらす対象として昔話の中で描かれることはない。なお、大みみずは、大ケラと並んで、神話上で中国を統一したとされる五帝の最初黄帝のシンボルである。彼が「土徳」とも呼ばれているように、大みみずは徳の比喩だ。それを抜きにしても次のような書き方が考えられる。
日本は世界でも有数の地震国である。人々は地震に苦しめられている。昔から地震を止めたという寓話をつくったところで、地震は現実にまた起こるから、人々は受け入れない。なぜ日本には地震が多いのかを説明する寓話ならあり得るだろう。また、主人公が地震の予兆を知って民衆や動物たちを救ったとするか、その人だけは備えていてそれを嘲っていた人々はひどい目にあうということも可能である。もちろん、逆に主人公に罰が当たるというケースもあり得る。いずれにせよ、あくまで人間は地震に対して受動的である。
日本が地震をつねに意識していることはレバー水栓からも明らかである。これは障害者や病人、高齢者等が使いやすいようにと普及したが、当初は上げ止めと下げ止めのイ二つの方式が並存している。しかし、阪神淡路大震災の際、上げ止めのレバーに物が落ちてきて水が流れ出る事例が報告され、以降、下げ止めに統一されていく。同様の理由からブレーカーも日本では下げ止めである。
『かえるくん、東京を救う』は、言及されているように、阪神大震災の後に書かれ、それを踏まえている。東海沖地震はいずれ訪れるとされ、大学・専門機関が研究を続け、国と地方自治体が共同で各種の対策を講じている。しかし、少なくとも一般の間では神戸が地震に襲われるなど想像もしていない。あの時以来、日本では、地震はどこでも起こり得るし、それに備えて、いかに被害を小さくするかが課題なのだと人々は知る。
にもかかわらず、村上春樹は主人公たちが元凶と戦って地震を食い止めるという寓話を書いてしまう。あまりにも脳天気だと言わざるを得ない。
自然現象を克服する寓話がないわけではない。宮沢賢治の『グスコーブドリの伝記』(1932)がそれに当たる。この物語の生まれた背景には、1931年の東北大飢饉がある。農村は極度の困窮に陥り、欠食児童や娘のみ売りなどが社会問題化している。この作品には、この悲惨な状況を改善できないものかという賢治の願いが込められている。
主人公ブドリは、自らを犠牲にして、火山を大噴火させて温室効果ガスを大気中に増加させ、地球温暖化によって冷害の再発を止める。これは原理的に間違っていない。地球温暖化は、今日では、人間生活に弊害があるという認識が広く浸透し、それを食い止めていこうというのが国際的なコンセンサスになっている。しかし、見逃してはならないことは、気候変動が問題となるはるか以前にそのメカニズムを正確に見出していた点である。おそらく世界の文学において、気候変動を扱った最も早い作品だろう。賢治の先見性には驚かされる。
地震はあくまでも記号であり、それにとわれずに、別の教訓を説く寓話として読むべきだという反論もあるだろう。事実、評価する論者はそうしている。
しかし、阪神大震災の後に、日本の作家が地震を口実にして書くとしたら、それは不謹慎経というものだ。スマトラ島の作家が津波を、ニューオリンズの作家がハリケーンを口実にして小説を書くことはあり得ない。それは彼らにとって固有の意味があるからだ。こんなこと少し深く考えれば、気がつくはずである。神戸在住の内田教授がこの小説を絶賛している姿に、彼の良識を疑わずにいられない。口実に用いる作家はそのことに実感がないだけである。
阪神大震災を経験した後でさえ、東京の地震をとりあげていることも村上治樹の想像力の貧困さを物語っている。それ以前、専門家の間ではともかく、関西では大地震が起こらないという一般的信念がはびこっている。次に大地震が生じるとしたら、東海地震の可能性が高く、また東海・南海・東南海連動型地震もありうるとして、国や自治体、研究機関も警戒し、膨大な予算と人員を当てている。そこ以外でも大地震の被害があったにもかかわらず、東海・南関東が一般の認識上の前景に現われ、他地域が後景に追いやられている。1923年の関東大震災に因み、池田勇人内閣は9月1日を「防災の日」に制定している。小松左京のベストセラー『日本沈没』も関東の地震を想定している。しかし、阪神大震災はその通念を揺るがす。日本には大地震が発生しない場所などない。作品において、もはや地震を関東に限定する必然性がない。このような認識の転換がなかったかのような小説を書く作家がいることも驚きだが、それを賞賛する文学研究者や読者が国内外に少なからずいることに吃驚する。はっきり言って、情けない。
阪神大震災を経験した後であれば、むしろ、作家たるもの地震を掘り下げた寓話を書くべきであろう。村上春樹は宮沢賢治を見習わなければならない。
全共闘運動の挫折の後に、ロマンティック・アイロニーを多用し、固有性を忌避する文学や音楽が数多く登場している。井上陽水の『傘がない』がその典型である。これは時代の要請で、失敗によって粉々になった自分自身の救済である。時代の固有性に対峙しているから、倫理性がある。村上春樹はその時流からデビューしている。
けれども、村上春樹は二作目以降も同じ姿勢で書き続ける。何のことはない、世界に対する自意識の優越性を確保することが作品の目的だったわけだ。村上春樹の散文は、ジャンル論で言うと、「ロマンス」に属する。これは円環構造を持ち、ある事件・出来事が終わるまでを描きるので、作者の願望を充足しやすいという特徴がある。固有性を奪えば、すべてを恣意的に扱うことができる。作品上に現われるものは口実にすぎない。
この物語で地震の原因を竜や大なまずにではなく、大みみずにしたのも、地震=なまずという固有性を避けるためだろう。歴史より作者の自意識が上に置きたいからだ。しかし、竜や大なまずにして物語を構築し。やっぱり伝説は本当だったという風にした方が読者に想像力を喚起させられる。人々の間で共有されているからだ。固有性への識は歴史の中に自分を位置づけいこうとすることである。歴史との連続と断続によってその作品の固有性が生まれる。固有性を無視するとしたら、それは自分を超歴史的存在と勘違いすることだ。加藤典洋早稲田大学教授は、『文学地図』において、大江健三郎と村上春樹の評価者が相反すると長々と書いている。大江健三郎は戦後文学の諸問題を作品内に取り入れるなど自分を文学史に位置づけながら、書いている。他方、村上春樹は自分を歴史の上に置く。だから。両者の評価が対立する。それだけのことだ。村上春樹は歴史とのコミュニケーションを拒否した作家なである。
村上春樹には、としかくこうした口実が多すぎる。最新作の『1Q84』にカルトを口実に使っている。けれども、日本はオウム真理教による殺人・テロ事件を経験している。そこでそういう小説を著すということは、ルワンダの作家が虐殺を、ニューヨークの作家が旅客機を使ったテロを口実に書くことと同じである。そんな無神経な小説家がいるなどとは思いもよらないが、村上春樹はそうする。
作家の倫理は固有性への繊細な配慮である。言葉はそれを記しただけでは一般的なものにすぎない。これは映像と比較すると、よく理解できる。
映像が映し出す光景は固有なものである。何の変哲もないスチール製の中古の事務机の写真だとして、それは机一般ではない。逆に、机一般を映すことは不可能である。他方、「机」と書き記した場合、映像と違って、そこに具体性や固有性はない。それはあくまで机一般である。机と言われても、他者であるから、どんなものかわからない。描写を通じて一般的なものを固有なものにするのが小説である。
言葉の性質上、固有性を表わすのが困難であるため、そこに文学の感動や楽しみが生まれる。思いつきや思い込みだけで独断的に書くと、他者がいないから、どうしても記述が一般的になってしまう。固有性への細やかな意識が作家には求められる。それは他者を気遣うことであり、作家の倫理である。村上春樹を読むと、こうした倫理性の重要性を逆に痛感させられる。
第4章 新たな文学モデルへ向けて
ルイス・キャロルは公理主義以前なので、数学の見方が現在とは違うが、言葉と意味の分離や論理性の追求が不可思議なことをもたらす逆説をファンタジーの中に描いている。曖昧さが不可解さ招くとは考えていない。安易に「謎」を口にする作家以上に、キャロルは悩ましい世界を提示している。現代数学を大胆に作品に導入する手法は今日においても有効である。
しかし、形式化の考えは文学にそれ以上の示唆を与えてくれる。登場してきた作品が新たなモデルを提供しているかどうかを判断できる点にある。表面的には奇抜だったり、突拍子もなかったり、騒々しかったりしていても、形式化してそのモデルを確認すると、旧態歴然たる代物であることもしばしばである。各誌の新人賞受賞作に目を通すと明らかだが、今の日本文学は文学モデルの構築に関して見るべき作品は少ない。村上春樹にしても、言葉なんて何でもいいのであれば、それを無視した形式化に耐えうるだけの文学モデルをつくり上げて然るべきである。先に触れた「問題提起」・「体系化」・「精密化」は文学者においても有効である。いずれかに貢献していれば、後に続くものが現われる。ギュスターヴ・フローベールやヘンリー・ジェイムズが形作った近代小説という文学モデルは、極めて汎用性が高い。どんなにつまらない人物であっても、いかに些細な出来事であっても、それを使えば、文学作品になりうる。また、かつて大江健三郎が提示した文学モデルは多くの追随者を生み出している。村上春樹もその一人である。けれども、彼の作品を形式化して考察すると、単純で、柄谷行人が『村上春樹の「風景」』で指摘しているように、昔ながらの「ロマンス」に収まってしまう。読者はいても、村上春樹の作品か後継者は生まれていない。それは作品のモデル性が貧弱だからである。古いモデルに恣意的なに言葉をはめこみ、それを「謎」と称し、読者も誉めそやす。「謎」などを言う前に、形式化を徹底化して、新たな文学モデルを生み出すべきだろう。
ひじょうに特殊な世界の性質しか反映していない公理系は、数学的に「悪い」公理系である──昔々、矢野健太郎先生が「これこれの公理系をみたす空間はただ1点から成る」ことを立証した論文について「そんな公理系に、どういう意味があるんでしょうねえ」と呆れておられたが、「ただ1点から成る」空間にしかあてはまらない公理系などは、ここでいう「悪い公理系」の代表的な例である。
(野崎昭弘『不完全性定理』)
〈了〉
参考文献
赤塚不二夫、『ニャロメのおもしろ数学教室』、角川文庫、1984年
池内了、『似非科学入門』、岩波新書、2008年
内田樹、『村上春樹にご用心』、アルテスパブリッシング、2007年
加藤典洋、『文学地図-大江と村上と二十年』、朝日選書、2008年
柄谷行人、『終焉をめぐって』、講談社学術文庫、1995年
川村湊、『村上春樹をどう読むか』、作品社、2006年
金田一秀穂、『気持ちにそぐう言葉たち』、清流出版、2009年
柴田元幸、『ナイン・インタビューズ 柴田元幸と9人の作家たち』、アルク、2004年
野崎昭弘、『不完全性定理』、利熊学芸文庫、2006年
野崎昭弘、『数学的センス』、利熊学芸文庫、2007年
宮沢賢治、『三田沢賢治全集8』、ちくま文庫、1986年
村上春樹、『神の子どもたちはみな踊る』、新潮文庫、2002年
村上春樹、『東京奇譚集』、新潮社、2005年
村上春樹、『1Q84』Book1・2、新潮社、2009年
森毅、『数学の歴史』、講談社学術文庫、1988年
森毅、『数学的思考』、講談社学術文庫、1991年
D・ヒルベルト、『幾何学基礎論』、中村孝四郎訳、ちくま学芸文庫、2006年
文化庁、『敬語の指針 平成19年2月2日文化審議会答申』
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/pdf/keigo_tousin.pdf
算円舎Web、『ユークリッド原論』
http://math.pisan-dub.jp/euclid/index.php