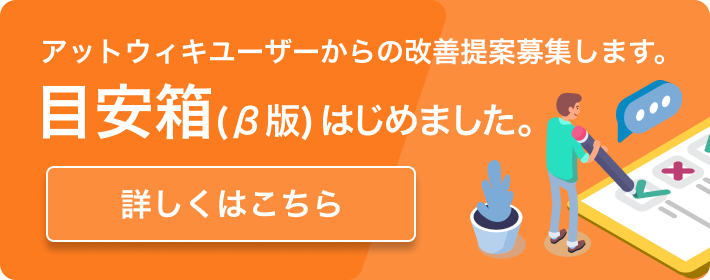今まで何度も歩いた、学校から家へ至る帰路。
今日だけで数えても、登校時に通っているので既に二回目だった。
それでも飽きた事は無い。何時も律と一緒に歩いてきたのだから。
今も、律は隣を歩いている。
二人の間で交わされているのは、他愛も無い話題だった。
学校でもプライベートでも、時間を共有する事が多い私達。
故に互いの得ている情報は近似し、話にサプライズは少ない。
けれど問題は無かった。
恋愛は損得勘定から繋がる機能的結合では無く、
感情から繋がる原始的結合なのだから。
つまり何を話すかよりも、誰と話すかが重要という事。
私達の進行方向からベビーカーを押して歩いてくる女性は、
結婚の際には所得や所属組織と言った機能的な物差しで配偶者を計ったかもしれない。
それを間違ったやり方だと言う心算は無いけれど、私は採用しない考え方だ。
律だから選ぶ、それだけのシンプルな選択だ。
律もその女性に視線が向いていた。
私と同じ事を考えてくれているのかまでは定かで無いが、
同じ対象に興味を示しているだけでも歓喜を感じる。
しかし、その女性との距離が縮まるにつれ、
律の興味が私とは違う対象へと向けられていた事を悟った。
律の視線は、ベビーカーの中の赤子へと向いていたのだ。
愛くるしいものを見た時に浮かべる、惚けた笑みを湛えながら。
その表情を私以外に向ける事は、あまり気分の良いものでは無い。
だから私は足早に通り過ぎて引き離したかったが、そうはいかなかった。
赤子の発する声に反応して、律は歩みを止めた。
その声が律に向けられている事は、赤子の視線が告げている。
擦れ違う際、視線が合ったのだろう。
「すみません」
律儀に頭を下げる女性に対して、律は鷹揚に応じた。
「いえいえ。可愛いお子さんですね」
「そんな……有難う」
子を褒められた女性の顔には、素直な笑みが浮かんでいた。
律を褒められたのなら、私は褒めた側に対して多少の警戒心は抱いてしまうだろう。
律を狙っているのではないか、と。
それが恋愛と家族愛の違いであり、”私は”この恋愛に満足している。
けれど──”律は”どうなのか?
律に連れる形で足を止めた私は、不安を抱えて状況を静観していた。
胸中に芽生えたこの不安は、先程抱いた嫉妬心とは明らかに違う。
赤子が惹起したものである事に違いが無いだけで。
律はしゃがみ込むと、赤子の目線に顔を合わせて幼い言葉で話しかけた。
その表情は、幸せそうだった。
瞳を蕩けさせ、笑みを浮かべて赤子と戯れる律。
そんな律を見るにつれて、私の不安は弥増してゆく。
「赤ちゃんと遊んでくれて、ありがとねー。
この子も喜んでるよ。
ほーら、きゃっきゃって」
女性は知り合いに話しかけるような砕けた口調で、律に話しかけていた。
彼女が年上である事を考慮しても、
初対面に対する態度としては些か礼を欠いているように思う。
だが律は気にしていない様子で、女性に言葉を返していた。
「いえー、とんでも無い。
こんな可愛い子と遊ばせてくれて、私も嬉しいですよ。
中々赤ちゃんと触れ合う機会無くって」
律の言葉の一つ一つに、私の心が締め付けられる。
今日だけで数えても、登校時に通っているので既に二回目だった。
それでも飽きた事は無い。何時も律と一緒に歩いてきたのだから。
今も、律は隣を歩いている。
二人の間で交わされているのは、他愛も無い話題だった。
学校でもプライベートでも、時間を共有する事が多い私達。
故に互いの得ている情報は近似し、話にサプライズは少ない。
けれど問題は無かった。
恋愛は損得勘定から繋がる機能的結合では無く、
感情から繋がる原始的結合なのだから。
つまり何を話すかよりも、誰と話すかが重要という事。
私達の進行方向からベビーカーを押して歩いてくる女性は、
結婚の際には所得や所属組織と言った機能的な物差しで配偶者を計ったかもしれない。
それを間違ったやり方だと言う心算は無いけれど、私は採用しない考え方だ。
律だから選ぶ、それだけのシンプルな選択だ。
律もその女性に視線が向いていた。
私と同じ事を考えてくれているのかまでは定かで無いが、
同じ対象に興味を示しているだけでも歓喜を感じる。
しかし、その女性との距離が縮まるにつれ、
律の興味が私とは違う対象へと向けられていた事を悟った。
律の視線は、ベビーカーの中の赤子へと向いていたのだ。
愛くるしいものを見た時に浮かべる、惚けた笑みを湛えながら。
その表情を私以外に向ける事は、あまり気分の良いものでは無い。
だから私は足早に通り過ぎて引き離したかったが、そうはいかなかった。
赤子の発する声に反応して、律は歩みを止めた。
その声が律に向けられている事は、赤子の視線が告げている。
擦れ違う際、視線が合ったのだろう。
「すみません」
律儀に頭を下げる女性に対して、律は鷹揚に応じた。
「いえいえ。可愛いお子さんですね」
「そんな……有難う」
子を褒められた女性の顔には、素直な笑みが浮かんでいた。
律を褒められたのなら、私は褒めた側に対して多少の警戒心は抱いてしまうだろう。
律を狙っているのではないか、と。
それが恋愛と家族愛の違いであり、”私は”この恋愛に満足している。
けれど──”律は”どうなのか?
律に連れる形で足を止めた私は、不安を抱えて状況を静観していた。
胸中に芽生えたこの不安は、先程抱いた嫉妬心とは明らかに違う。
赤子が惹起したものである事に違いが無いだけで。
律はしゃがみ込むと、赤子の目線に顔を合わせて幼い言葉で話しかけた。
その表情は、幸せそうだった。
瞳を蕩けさせ、笑みを浮かべて赤子と戯れる律。
そんな律を見るにつれて、私の不安は弥増してゆく。
「赤ちゃんと遊んでくれて、ありがとねー。
この子も喜んでるよ。
ほーら、きゃっきゃって」
女性は知り合いに話しかけるような砕けた口調で、律に話しかけていた。
彼女が年上である事を考慮しても、
初対面に対する態度としては些か礼を欠いているように思う。
だが律は気にしていない様子で、女性に言葉を返していた。
「いえー、とんでも無い。
こんな可愛い子と遊ばせてくれて、私も嬉しいですよ。
中々赤ちゃんと触れ合う機会無くって」
律の言葉の一つ一つに、私の心が締め付けられる。
「まー、幼児を狙った事件がラディカルに放映されてるからねー。
それで最近の母親は、結構警戒心が強くなってるって感じなのかな。
いや、そりゃ私だって人の事言えないけれど」
女性の言葉に、律がやや沈んだ声で返した。
「あ……じゃ、私も遠慮した方が良かったかな……」
「いえいえ。貴女はそんな風に見えないし。
赤ちゃん、好きなんでしょ?母性に満ちてるようにも見えるから」
単純に相手が女子高生だから、警戒心が緩んでいるだけなのだろう。
こんな短時間で律の正確な分析を為されたら、
長年連れ添っている恋人の私の立場が無い。
しかし、律は言葉通りに受け取ったらしかった。
「母性に満ちてる……って、褒め過ぎだしっ。
私、本当に母性あるように見えますか?
結構、ガサツみたいに学校では見られちゃうんですけど」
女性は力強く肯いていた。
「あるあるっ、ガサツだなんてとんでもない。繊細な女の子に見えるって。
きっと貴女なら、いいお母さんになれると思う、うん」
律は気恥ずかしそうな笑みを零した。
彼女の言葉は、きっと律に喜びを与えたのだろう。
反面、私は胸を締め付けられる思いだった。
「そんなぁ……やっぱ褒め過ぎだしっ。
でも、ありがとうございます。
けど……お母さんになるのって、大変ですよね。
私って怠ける系の子だし、務まるかなぁ、的な」
律は嬉しそうな笑みを浮かべつつ、謙遜の言葉を述べていた。
謙遜、だろうか。
最後に述べた言葉は、謙遜ではなく不安では無いのだろうか。
不安は未来に向けられる。
即ち、
その未来のライフプランに不安を抱く対象が含まれている事になる。
私は小刻みに頭を振って、その考えを無理矢理思考から追い出す。
大丈夫、謙遜してるだけだ──そう言い聞かせながら。
でも本当に────
──大丈夫?
「大丈夫っ」
太鼓判を押すような女性の声は、律に向けられている。
「赤ちゃんが生まれれば、母親としての自覚も出てくるはずだから。
それに確かに大変だけれど、赤ちゃんはそれを上回る幸せも授けてくれるから。
乗り越えられるよ。古い考えかもしれないけれど、いや、
私自身赤ちゃんが生まれるまでは古い考えだと思っていたけれどね。
女の幸せは赤ちゃんを産む事。
赤ちゃんが産まれて、初めてその言葉が真実だと思えたよ」
女性の言葉は、私を残酷なまでに苛んだ。
不安に続いて押し寄せる、絶望に似た憂鬱。
それらのネガティブな感情に嬲られて、
私はこの場に留まっている事さえ苦痛だった。
考えの新旧が問題なのでは無く、
幸福を一般化する事が問題なのだと彼女に言ってやりたかった。
一般化は時として、マイノリティに対するナイフになる。
そして最悪の場合、差別を正当化するスティグマにさえ至る。
それで最近の母親は、結構警戒心が強くなってるって感じなのかな。
いや、そりゃ私だって人の事言えないけれど」
女性の言葉に、律がやや沈んだ声で返した。
「あ……じゃ、私も遠慮した方が良かったかな……」
「いえいえ。貴女はそんな風に見えないし。
赤ちゃん、好きなんでしょ?母性に満ちてるようにも見えるから」
単純に相手が女子高生だから、警戒心が緩んでいるだけなのだろう。
こんな短時間で律の正確な分析を為されたら、
長年連れ添っている恋人の私の立場が無い。
しかし、律は言葉通りに受け取ったらしかった。
「母性に満ちてる……って、褒め過ぎだしっ。
私、本当に母性あるように見えますか?
結構、ガサツみたいに学校では見られちゃうんですけど」
女性は力強く肯いていた。
「あるあるっ、ガサツだなんてとんでもない。繊細な女の子に見えるって。
きっと貴女なら、いいお母さんになれると思う、うん」
律は気恥ずかしそうな笑みを零した。
彼女の言葉は、きっと律に喜びを与えたのだろう。
反面、私は胸を締め付けられる思いだった。
「そんなぁ……やっぱ褒め過ぎだしっ。
でも、ありがとうございます。
けど……お母さんになるのって、大変ですよね。
私って怠ける系の子だし、務まるかなぁ、的な」
律は嬉しそうな笑みを浮かべつつ、謙遜の言葉を述べていた。
謙遜、だろうか。
最後に述べた言葉は、謙遜ではなく不安では無いのだろうか。
不安は未来に向けられる。
即ち、
その未来のライフプランに不安を抱く対象が含まれている事になる。
私は小刻みに頭を振って、その考えを無理矢理思考から追い出す。
大丈夫、謙遜してるだけだ──そう言い聞かせながら。
でも本当に────
──大丈夫?
「大丈夫っ」
太鼓判を押すような女性の声は、律に向けられている。
「赤ちゃんが生まれれば、母親としての自覚も出てくるはずだから。
それに確かに大変だけれど、赤ちゃんはそれを上回る幸せも授けてくれるから。
乗り越えられるよ。古い考えかもしれないけれど、いや、
私自身赤ちゃんが生まれるまでは古い考えだと思っていたけれどね。
女の幸せは赤ちゃんを産む事。
赤ちゃんが産まれて、初めてその言葉が真実だと思えたよ」
女性の言葉は、私を残酷なまでに苛んだ。
不安に続いて押し寄せる、絶望に似た憂鬱。
それらのネガティブな感情に嬲られて、
私はこの場に留まっている事さえ苦痛だった。
考えの新旧が問題なのでは無く、
幸福を一般化する事が問題なのだと彼女に言ってやりたかった。
一般化は時として、マイノリティに対するナイフになる。
そして最悪の場合、差別を正当化するスティグマにさえ至る。
けれど言いはしない。
無用な争いを避けたいだけではなく、彼女に悪気が無い事など分かっていたから。
眼前の少女が性的マイノリティである可能性に思い至るなど、
過ぎた期待である事は分かりきっている。
それに彼女は言説の一般化はしても、押し付けてはいないのだ。
支持する事さえ不快な言説ではあるが、
押し付けていない以上はその一般化に正当な抗議を加える事は難しい。
私達は性的マイノリティであると、表明する勇気も当然無かった。
私達──私は性的マイノリティである自覚がある。
けれど、律は本当に”こちら側”だろうか。
その律は女性の言葉を受けて、
「女の幸せ……」
と復唱して赤子に視線を向けていた。
その表情は、相変わらず蕩けている。
それは女性の言葉に対して、肯定を示す仕草に他ならなかった。
──やはり律は──
「律っ」
限界だった。それ以上見ていられなかった。
だから私は叫ぶようにその名を呼び、注意をこちらに向けて帰るよう促す。
「何時までも足引き止めてたら悪いだろ?
そろそろ帰るぞ」
続いて女性に視線を向けて、言葉を放つ。
「すいません、律……連れがダラダラ話し込んじゃって。
そろそろ私達、帰りますね。お世話かけました」
一方的に帰宅を告げたにも関わらず、女性は機嫌を害した風は無かった。
「いーえー、とんでもない。
赤ちゃんと話してくれて、ありがとねー」
彼女は手を振った。
それに倣うように、ベビーカーの中の赤子も手を振る。
「いえ、こちらこそ。足引き止めてすいませんでしたー。
おーい、ママの言う事良く聞いて、いい子に育つんだぞー」
その言葉と共に、律も手を振り返していた。
私はそういった反応は一切返さず、律を急かす様に歩き始めた。
律もすぐに倣い、私の横に並んできた。
私が一方的に話を打ち切らせた事に不満を述べてくるかと思ったが、
律の口から放たれたのは別の言葉だった。
「いやー、可愛かったなー、赤ちゃん」
その話題は私の本意とするところでは無い。
少なくとも、今は。
「それはそうと、悪かったな。
話盛り上がってたのに、勝手に帰るとか決めちゃって」
「いや、私の方こそ悪かったよ。
澪と一緒なのに、何時までも話し込んじゃって。
待っててくれて、ありがと」
律は気分を害してはいなかった。
その事に胸を撫で下ろしはしたものの、心が平穏を回復したわけでは無かった。
植え付けられた不安は去らず、未だ私の心を蝕み続けているのだから。
多弁になる気分ではないが、
律に暗い胸中を気取られないよう敢えて私は話を振り続けた。
それは律の口から、
先程の赤子に纏わる話題が出る事を避ける意図もあったのだけれど。
律と話し合う決意は、既に固めてはいる。
この不安を抱えたまま律と交わっていける程、
私の精神は安定していない。
だがそれは、もっと閉鎖された空間で行いたかった。
人目に付く外で展開したい話題では無い。
無難な話を振り続け、家が近づいた段階で私は律を誘った。
「この後用事が無いなら、部屋に来てくれないか?」
「ん?いいよ」
律は特段の疑問を示さず、承諾してくれた。
無用な争いを避けたいだけではなく、彼女に悪気が無い事など分かっていたから。
眼前の少女が性的マイノリティである可能性に思い至るなど、
過ぎた期待である事は分かりきっている。
それに彼女は言説の一般化はしても、押し付けてはいないのだ。
支持する事さえ不快な言説ではあるが、
押し付けていない以上はその一般化に正当な抗議を加える事は難しい。
私達は性的マイノリティであると、表明する勇気も当然無かった。
私達──私は性的マイノリティである自覚がある。
けれど、律は本当に”こちら側”だろうか。
その律は女性の言葉を受けて、
「女の幸せ……」
と復唱して赤子に視線を向けていた。
その表情は、相変わらず蕩けている。
それは女性の言葉に対して、肯定を示す仕草に他ならなかった。
──やはり律は──
「律っ」
限界だった。それ以上見ていられなかった。
だから私は叫ぶようにその名を呼び、注意をこちらに向けて帰るよう促す。
「何時までも足引き止めてたら悪いだろ?
そろそろ帰るぞ」
続いて女性に視線を向けて、言葉を放つ。
「すいません、律……連れがダラダラ話し込んじゃって。
そろそろ私達、帰りますね。お世話かけました」
一方的に帰宅を告げたにも関わらず、女性は機嫌を害した風は無かった。
「いーえー、とんでもない。
赤ちゃんと話してくれて、ありがとねー」
彼女は手を振った。
それに倣うように、ベビーカーの中の赤子も手を振る。
「いえ、こちらこそ。足引き止めてすいませんでしたー。
おーい、ママの言う事良く聞いて、いい子に育つんだぞー」
その言葉と共に、律も手を振り返していた。
私はそういった反応は一切返さず、律を急かす様に歩き始めた。
律もすぐに倣い、私の横に並んできた。
私が一方的に話を打ち切らせた事に不満を述べてくるかと思ったが、
律の口から放たれたのは別の言葉だった。
「いやー、可愛かったなー、赤ちゃん」
その話題は私の本意とするところでは無い。
少なくとも、今は。
「それはそうと、悪かったな。
話盛り上がってたのに、勝手に帰るとか決めちゃって」
「いや、私の方こそ悪かったよ。
澪と一緒なのに、何時までも話し込んじゃって。
待っててくれて、ありがと」
律は気分を害してはいなかった。
その事に胸を撫で下ろしはしたものの、心が平穏を回復したわけでは無かった。
植え付けられた不安は去らず、未だ私の心を蝕み続けているのだから。
多弁になる気分ではないが、
律に暗い胸中を気取られないよう敢えて私は話を振り続けた。
それは律の口から、
先程の赤子に纏わる話題が出る事を避ける意図もあったのだけれど。
律と話し合う決意は、既に固めてはいる。
この不安を抱えたまま律と交わっていける程、
私の精神は安定していない。
だがそれは、もっと閉鎖された空間で行いたかった。
人目に付く外で展開したい話題では無い。
無難な話を振り続け、家が近づいた段階で私は律を誘った。
「この後用事が無いなら、部屋に来てくれないか?」
「ん?いいよ」
律は特段の疑問を示さず、承諾してくれた。
*
私は律を部屋に招き入れると、後ろから抱きすくめた。
正面を向いては、到底話せそうにも無かったから。
「み、澪っ?」
律は驚いたようだが、抵抗は示さなかった。
「赤ちゃん、そんなに可愛かったか?」
「まぁ、そりゃ、可愛かったけど……。
でも澪に対する感情とはベクトルが違うよ?」
そんな事は分かってる。これは嫉妬じゃない。
赤子の話ではあるけれど、嫉妬では無い。
「分かってるよ……。そういう話じゃなく、律も赤ちゃん欲しいか?
赤ちゃん、産みたいか?」
「澪?」
私の名を、訝しげな調子で律が呟いた。
答えは聞かなくても分かっている。
赤子と戯れていた時の律や、その母親と話していた時の律。
それらが答えを告げているのだ、
即ち私の放った問いへ向けた肯定を表しているのだ。
私は律の下腹部を擦りながら、謝罪の言葉を放つ。
「ごめんな、律。
私も女だから……律を孕ませてやる事はできない……。
律に赤ちゃんを授けてやる事は……できないんだ。
律も……赤ちゃんに幸せを感じているのなら、
私はそれを実現してやる事ができない……。
何で私、女なんかに生まれたんだろうな。
ホントに……ごめんな」
私が感じていた不安。
それは、律は恋愛よりも家族愛に惹かれるのでは無いかという事。
即ち、女同士では子供を埋めないからと、
何時かは律が私から離れてしまうのでは無いかという不安。
律の描く将来のビジョンに子供が含まれているのなら、
私ではその相方が務まらない事になるのだから。
「みぃおっ」
不安に苛まれていた私の耳に、律の可愛らしい声が届いた。
律は私の腕の拘束を解くと、振り向いて私と視線を合わせてきた。
「あのさ、確かに私達は女同士だから子供は産めないけど、
でも澪が居てくれれば私はそれでいいよ?
それで私、幸せだよ?」
律はそう言ってくれたが、私の不安が消失したわけでは無い。
「でも律は……子供が欲しいんだろ?
子供を産む事が幸せだって、そう考えてるんだろ?」
それは紛れも無い事実だろう。
勿論、私が律の観察を誤ったのならば話は別だ。
だが赤子や女性と話した時の律の表情や言葉から推量すれば、
私で無くとも同じ観察結果を導くだろう。
「確かに、子供は欲しい。
子供を産む事だって、私の幸せの一つだって考えてる」
ほら、律は現に肯定した。
けれども、律の話には続きがあった。
正面を向いては、到底話せそうにも無かったから。
「み、澪っ?」
律は驚いたようだが、抵抗は示さなかった。
「赤ちゃん、そんなに可愛かったか?」
「まぁ、そりゃ、可愛かったけど……。
でも澪に対する感情とはベクトルが違うよ?」
そんな事は分かってる。これは嫉妬じゃない。
赤子の話ではあるけれど、嫉妬では無い。
「分かってるよ……。そういう話じゃなく、律も赤ちゃん欲しいか?
赤ちゃん、産みたいか?」
「澪?」
私の名を、訝しげな調子で律が呟いた。
答えは聞かなくても分かっている。
赤子と戯れていた時の律や、その母親と話していた時の律。
それらが答えを告げているのだ、
即ち私の放った問いへ向けた肯定を表しているのだ。
私は律の下腹部を擦りながら、謝罪の言葉を放つ。
「ごめんな、律。
私も女だから……律を孕ませてやる事はできない……。
律に赤ちゃんを授けてやる事は……できないんだ。
律も……赤ちゃんに幸せを感じているのなら、
私はそれを実現してやる事ができない……。
何で私、女なんかに生まれたんだろうな。
ホントに……ごめんな」
私が感じていた不安。
それは、律は恋愛よりも家族愛に惹かれるのでは無いかという事。
即ち、女同士では子供を埋めないからと、
何時かは律が私から離れてしまうのでは無いかという不安。
律の描く将来のビジョンに子供が含まれているのなら、
私ではその相方が務まらない事になるのだから。
「みぃおっ」
不安に苛まれていた私の耳に、律の可愛らしい声が届いた。
律は私の腕の拘束を解くと、振り向いて私と視線を合わせてきた。
「あのさ、確かに私達は女同士だから子供は産めないけど、
でも澪が居てくれれば私はそれでいいよ?
それで私、幸せだよ?」
律はそう言ってくれたが、私の不安が消失したわけでは無い。
「でも律は……子供が欲しいんだろ?
子供を産む事が幸せだって、そう考えてるんだろ?」
それは紛れも無い事実だろう。
勿論、私が律の観察を誤ったのならば話は別だ。
だが赤子や女性と話した時の律の表情や言葉から推量すれば、
私で無くとも同じ観察結果を導くだろう。
「確かに、子供は欲しい。
子供を産む事だって、私の幸せの一つだって考えてる」
ほら、律は現に肯定した。
けれども、律の話には続きがあった。
「でもさ、それはあくまで幸せや望みの一つというだけであって。
澪が居てくれる方が、私にとっては幸せだから。
ほら、望む幸せ、何でもかんでも手に入れられる訳じゃないだろ?
相反する二つの幸せのどちらかを選ぶなんて、往々にしてあるよ。
そして私はその選択において、澪を選んだ」
「律は……本当にそれでいいのか?
私でいいのか?子供だとか結婚だとか、そちらに幸せ求めなくていいのか?」
律に拒まれても、どうせ私はそれを受け入れられないだろう。
それでも敢えて質問してしまうのは、
きっと胸中巣食う不安に決着を付けたいからだろう。
「いーよ。澪でいいんじゃなくて、澪がいい。
それに私、きっと幸福な方だよ?いや、トップクラスに幸せだよ。
私はね、自分が思い描く幸福像のうち、一番上位にある幸福を手にしてるんだから。
つまり、澪。澪と愛を分かち合う事こそ、私にとって一番の幸せなんだ。
結婚して子供を産む幸福を得たとしても、
それは澪を手に入れる幸福に比べれば弱いよ」
全部手に入れられないのなら、最上位の幸福を選ぶ。
律の展開するその論理は、確かに納得がいくものだった。
私は胸中の不安が晴れていく事を実感した。
「それにさ、子供産めないなら埋めないで、そう悪い事だらけでもないよ?
女は子供を産むと母に進化して、配偶者よりも子を愛してしまうらしい。
勿論一概に皆そうだとは言わないけど、そのリスクの存在は確かだ。
でもそもそも子供が産めないなら、私はそうならずにずっと女のまま、
死ぬまで澪を愛し続ける事ができるんだ」
律は悪戯っぽく笑いながら付け足していた。
私の心から不安は消え去り、幸福が芽生えていた。
律からずっと愛される幸福、それこそ私が欲しかったもの。
それこそが、私の胸中から不安を消し去ってくれるものだった。
律は説得力のある言葉で、愛の永続に蓋然性を与えてくれていた。
「ありがとな、律」
私は律を抱き寄せて、胸に収めた。
「みぃお、さっき女に生まれた事を悔しがってたけど、その必要無いよ?
だって、澪の大きい胸、抱かれてると安心するし。いい匂いするし。
ここは私の大好きな場所。
だから、言うよ?」
律は胸に顔を埋めたまま、上目の視線で私を捉えて言う。
「女に生まれてくれて、ありがとっ」
私は微笑みを返して、強く強く律を胸に押し付けた。
澪が居てくれる方が、私にとっては幸せだから。
ほら、望む幸せ、何でもかんでも手に入れられる訳じゃないだろ?
相反する二つの幸せのどちらかを選ぶなんて、往々にしてあるよ。
そして私はその選択において、澪を選んだ」
「律は……本当にそれでいいのか?
私でいいのか?子供だとか結婚だとか、そちらに幸せ求めなくていいのか?」
律に拒まれても、どうせ私はそれを受け入れられないだろう。
それでも敢えて質問してしまうのは、
きっと胸中巣食う不安に決着を付けたいからだろう。
「いーよ。澪でいいんじゃなくて、澪がいい。
それに私、きっと幸福な方だよ?いや、トップクラスに幸せだよ。
私はね、自分が思い描く幸福像のうち、一番上位にある幸福を手にしてるんだから。
つまり、澪。澪と愛を分かち合う事こそ、私にとって一番の幸せなんだ。
結婚して子供を産む幸福を得たとしても、
それは澪を手に入れる幸福に比べれば弱いよ」
全部手に入れられないのなら、最上位の幸福を選ぶ。
律の展開するその論理は、確かに納得がいくものだった。
私は胸中の不安が晴れていく事を実感した。
「それにさ、子供産めないなら埋めないで、そう悪い事だらけでもないよ?
女は子供を産むと母に進化して、配偶者よりも子を愛してしまうらしい。
勿論一概に皆そうだとは言わないけど、そのリスクの存在は確かだ。
でもそもそも子供が産めないなら、私はそうならずにずっと女のまま、
死ぬまで澪を愛し続ける事ができるんだ」
律は悪戯っぽく笑いながら付け足していた。
私の心から不安は消え去り、幸福が芽生えていた。
律からずっと愛される幸福、それこそ私が欲しかったもの。
それこそが、私の胸中から不安を消し去ってくれるものだった。
律は説得力のある言葉で、愛の永続に蓋然性を与えてくれていた。
「ありがとな、律」
私は律を抱き寄せて、胸に収めた。
「みぃお、さっき女に生まれた事を悔しがってたけど、その必要無いよ?
だって、澪の大きい胸、抱かれてると安心するし。いい匂いするし。
ここは私の大好きな場所。
だから、言うよ?」
律は胸に顔を埋めたまま、上目の視線で私を捉えて言う。
「女に生まれてくれて、ありがとっ」
私は微笑みを返して、強く強く律を胸に押し付けた。
<FIN>